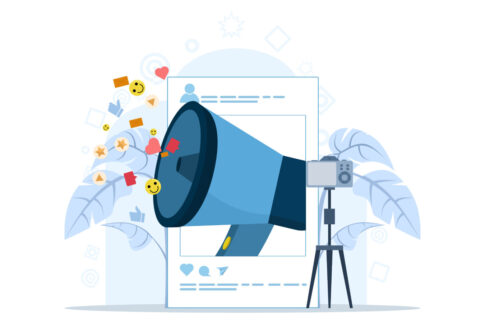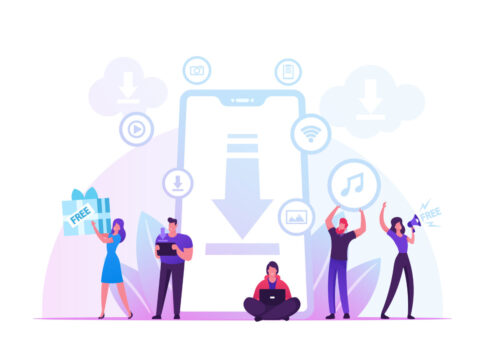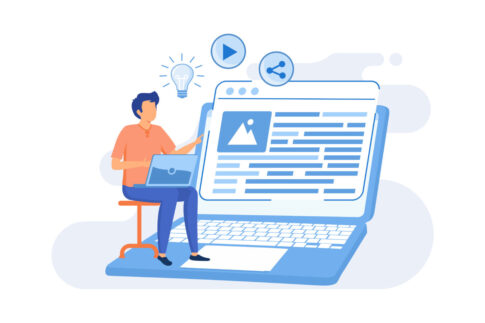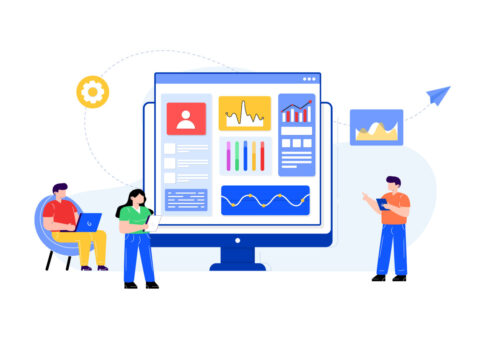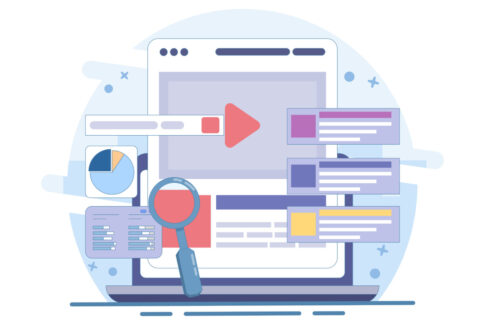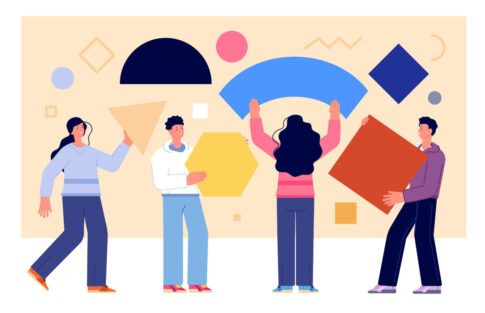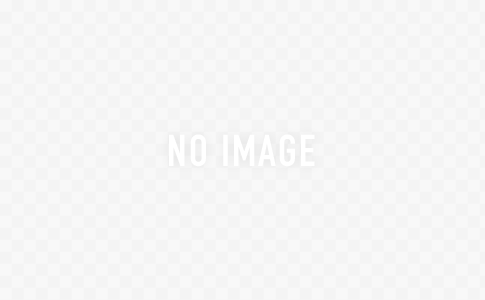アメブロで複数アカウントは作れる?本記事では、可否と前提条件を公式情報の要点に沿って整理し、作成5手順・切替方法・メール管理・運用設計・AmebaPickの注意点まで初心者向けに解説していきます。テーマ分けで読者を迷わせず、収益化とブランド強化につなげる実践の型がわかります。
複数アカウントの可否と前提条件
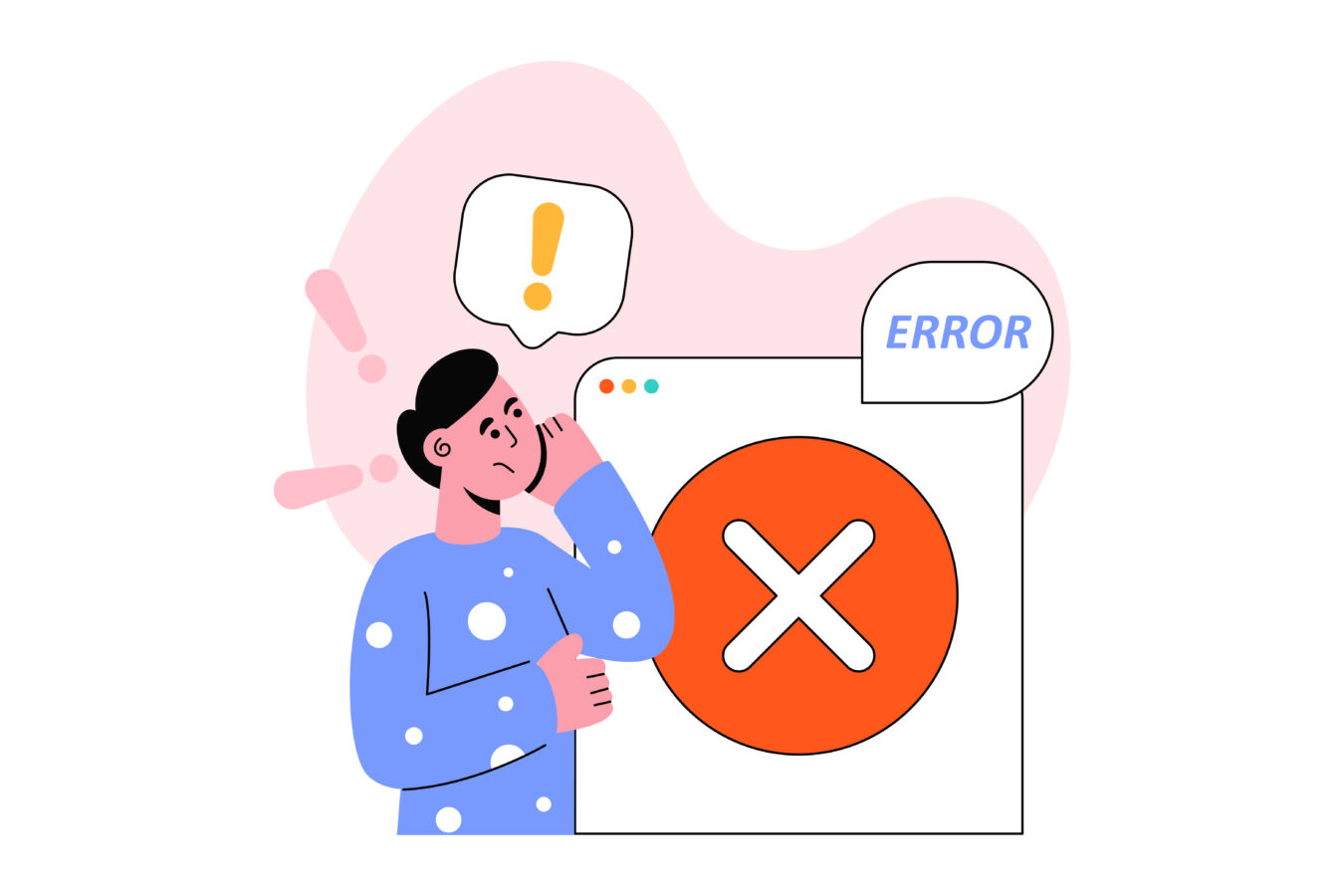
アメブロは〈1人で複数アカウントを運用すること自体〉は可能です。新しく運用したいテーマごとにアメーバIDを追加登録すれば、個人用・ビジネス用・ジャンル別などに分けて管理できます。
一方で、同一のメールアドレスでは複数登録ができない仕様のため、アカウントごとに異なるメールを用意するのが前提です。
また、複数アカウントの使い分けが許容されていても、なりすまし・スパム・同一内容の大量投稿など、利用規約で禁止される使い方は厳禁です。
特に収益化機能(AmebaPickやドットマネー)には固有のルールがあり、複数口座の所持や不正利用は報酬取り消し・停止の対象となり得ます。
まずは「可能な範囲」と「禁止される行為」を切り分け、目的に合わせて安全に設計することが大切です。
【ポイントの整理】
- 複数アカウント自体は可→各IDを個別に登録
- 同一メールでの複数登録は不可→用途別にメール準備
- 規約違反(自演・スパム・不正受益)はNG→報酬取消リスク
- OK:テーマ別にIDを分け、読者も分けて運用
- NG:同一内容の量産、なりすまし、報酬目的の不正
| 区分 | 前提・補足 |
|---|---|
| 作成可否 | 新規アメーバIDを登録すれば複数運用は可能 |
| メール要件 | 同一メールは不可。IDごとに別メールを用意 |
| 規約面 | 禁止行為(不正・スパム等)はアカウント処分の対象 |
| 収益化 | AmebaPickやドットマネーは1ID/1口座が原則 |
公式ヘルプの要点と注意事項
公式ヘルプでは、1人が複数のブログ(アカウント)を持つことは可能と示されています。実装面では、追加で運用したい数だけ新規のアメーバIDを登録すればよく、ID単位でブログと設定が分離されるため、テーマやターゲットの切り分けがしやすくなります。
注意点は、同一メールアドレスで複数登録はできない仕様であること、ならびにアメーバの利用規約で禁止される使い方(なりすまし・誹謗中傷・スパム投稿・同一内容の濫用など)に該当しない運用を守ることです。
とくに複数アカウントで相互に過度な誘導を行ったり、同一内容を反復して露出を水増しするような行為は、検索面の評価低下だけでなく、プラットフォーム上の措置対象になり得ます。
運用開始前に「目的・対象読者・投稿ルール(何を、どこで、どの頻度で)」をアカウントごとに決め、プロフィール・説明文・カテゴリもテーマに合わせて設定しておくと、混同や投稿ミスを防げます。
【公式ヘルプの読み取り方】
- 可否の結論→複数運用は可能
- 運用条件→IDを個別登録・設定を分ける
- 守るべき線引き→規約違反に当たらない使い方
- 同一内容の再投稿を複数IDで繰り返す行為
- 第三者を装うレビュー・自作自演的な導線づくり
同一メール不可と準備方法
複数アカウントを作る際は、IDごとに〈異なるメールアドレス〉が必要です。まず、用途別(例:個人・事業・ジャンル別)にメールを用意し、受信箱の混在を避けるために、それぞれでフィルタやラベルを設定して管理性を高めます。
登録後は、復旧用メール・電話番号・2段階認証などのセキュリティ設定を、各IDで必ず有効化しておきましょう。
実務面では、ログイン情報の取り違えが最も多いトラブルです。パスワードマネージャーで「アカウント名(用途)→ID→メール→バックアップ手段」を紐づけると、切替時の入力ミスを減らせます。
さらに、プロフィール画像・ヘッダー・説明文・投稿テンプレートをアカウントごとに差別化しておくと、投稿画面で「どのIDで書いているか」を視覚的に判断でき、誤投稿の防止に役立ちます。
【準備チェック】
- 用途別にメールを取得→受信整理(ラベル/フィルタ)
- 2段階認証・復旧情報の設定→紛失時の備え
- パスワードマネージャーでID情報を一元管理
- 各IDでヘッダー/アイコンを変え、見た目で判別
- 下書きテンプレに「想定読者・NG例」を明記
AmebaPickの1ID1口座原則
収益化機能を使う場合は、一般のアカウント運用と別に、AmebaPickとドットマネーのルールを理解しておく必要があります。AmebaPickは〈AmebaID1つにつき1アカウント〉が原則です。
無断で複数のPickアカウントを登録したり、複数のドットマネー口座を併用する行為は、禁止事項に該当するおそれがあり、報酬の取り消しや利用停止などのリスクがあります。
ドットマネーも「1個人につき1登録」が基本で、複数口座の所持は統合・削除対応が求められます。
安全に収益化するには、Pickの登録IDとドットマネー口座を1対1で整合させ、家族名義や複数口座での受け取り、自己発注の疑いを招く運用などを避けることが重要です。
運営ポリシーとして「広告表記のルール」「レビュー方針(提供有無の明示)」「問い合わせ先」を各IDで整えておくと、審査や万一の確認にもスムーズに対応できます。
【運用ルールの要点】
- Pick=AmebaIDと1対1で登録・連携
- ドットマネー=1個人1口座。複数所持は統合・削除
- 不正の疑いを招く行為(自演/水増し/名義貸し)は避ける
- 複数IDの報酬を1つの口座に集約
- 家族・他人名義での受取や名義貸し運用
新規アカウント作成の基本手順

複数のテーマで発信したい場合は、新しいアメーバIDを追加して運用を分けます。基本の流れはシンプルですが、事前準備と入力ミス防止のコツを押さえるとスムーズです。
まず既存IDから確実にログアウトし、用途別に用意した〈別メールアドレス〉を使って登録します。作成直後はプロフィールやヘッダー画像も仮設定で構いません。
最初に「何を誰に届けるか」を1行で言語化し、説明文とカテゴリを合わせると迷いが減ります。なお端末やブラウザのプロファイルを分けると、切替時の誤投稿を防ぎやすくなります。
例として「美容レビュー用」と「料理レシピ用」でIDを分けると、読者も動線も明確になります。最後に、認証メールの受信・ID命名・パスワード設定・復旧情報の登録まで一気に終えると、後戻りが少なく安全です。
【手順の全体像】
- 既存IDからログアウト→ブラウザのシークレット/別プロファイルを起動
- トップページの「新規会員登録」→用途別に準備したメールを入力
- 認証コードを受信→時間内に入力して本人確認を完了
- アメーバIDを命名→テーマが伝わる短いIDにする
- 強固なパスワードを設定→パスワードマネージャーに保存
- プロフィール・カテゴリ・復旧情報(電話/予備メール)を設定
- 別メール+別プロファイルで環境を分離
- 説明文は「対象読者→提供価値→投稿頻度」を1行で記載
| 準備項目 | 要点 |
|---|---|
| メール | 用途別に新規取得→受信フォルダをラベルで整理 |
| 端末/ブラウザ | プロファイル分離→ログイン先を視覚で判別 |
| プロフィール | 仮画像と説明文でテーマを先に明示→後で詳細化 |
ログアウトから新規登録まで
最初に既存アカウントから確実にログアウトします。次に、シークレットウィンドウや別ユーザープロファイルを使って新規登録画面を開くと、クッキーの混在を避けられます。
登録では有効なメールアドレスを入力し、届いた認証メールの案内に従って手続きを進めます。迷惑メール振り分け対策として、事前に差出人ドメインを受信許可にしておくと安心です。
登録途中でブラウザを閉じると認証が失敗する場合があるため、認証メール受信→コード入力→基本情報の流れは中断せずに完了させます。
登録直後はブログタイトルや説明文を仮でも良いので入れておき、カテゴリもテーマに合うものを一旦選びます。
ログイン状態の保持は、メインと新規が入れ替わらないよう「この端末で保持するか」を使い分けると安全です。
【登録時のチェック】
- ログアウト→新規ウィンドウ→登録の順で環境を分離
- 認証メールは受信許可を事前設定→迷惑フォルダも確認
- 基本情報入力は中断せず一気に完了→エラーを回避
| つまずきポイント | 回避策 |
|---|---|
| 既存ログインが残る | 必ずログアウト→シークレット/別プロファイルで登録 |
| 認証メール未着 | 受信許可・迷惑フォルダ・数分待機→再送信を実施 |
| 入力中断で失敗 | 認証→コード入力→基本情報まで一気に完了 |
認証コードとID命名の型
認証コードは有効時間が限られるため、メール受信後すぐに入力します。届かない場合は、受信許可設定や迷惑メールフォルダ、メールアドレスのタイプミスを確認し、必要ならコードの再送を行います。
次に決めるアメーバIDは、短く覚えやすく、テーマが伝わる名前が基本です。英数字と一部の記号は使えますが、極端に長い並びや紛らわしい表記は避けます。
将来の拡張性を考え、テーマ名+差別化要素(例:beauty_lab、cooknote、kids_craft)のように、発信領域と世界観が想像できる構成にすると、プロフィールやURLを見た読者が迷いません。
また、類似IDが既に使われている場合に備え、候補を複数用意しておくと登録が止まりにくくなります。
【ID命名のヒント】
- 短い・覚えやすい・テーマが伝わる
- 被りに備えた候補を3つ以上用意
- 将来の拡張に耐える語(例:coffee_review→cafereview)
- 数字羅列や過剰な記号で読みにくいID
- 商標や著名人を連想させる紛らわしい表記
| 目的 | 良い例と意図 |
|---|---|
| 美容レビュー | beauty_lab → 美容×検証の世界観が伝わる |
| 料理レシピ | cooknote → レシピ帳の連想で覚えやすい |
| 子育て工作 | kids_craft → 読者像と内容が即時に伝わる |
強固なパスワード設定のコツ
複数アカウント運用では、パスワードの強度と管理が安全性を左右します。推奨は12文字以上で、英大文字・小文字・数字・記号を混在させ、辞書にある単語や使い回しは避けます。
各IDごとに異なるパスワードを設定し、パスワードマネージャーに保存しておくと、誤入力や再利用のリスクを下げられます。
復旧用メールと電話番号も設定し、2段階認証が利用できる場合は必ず有効化します。投稿端末が複数あるなら、端末ごとにログイン保持の有無を分け、共有端末では必ずログアウトします。
さらに、定期的な見直し(例:重要IDは半年ごと)をルール化すると、長期運用でも安全性を維持できます。
【安全運用のチェック】
- 12文字以上+4要素(英大小・数字・記号)を混在
- IDごとに異なるパスワード→マネージャーで保管
- 復旧情報と2段階認証を設定→紛失・乗っ取り対策
- 主要IDのパスワードを今すぐ更新→保存を確認
- 共有端末は自動ログインを無効化→都度ログイン
メールアドレス管理と運用設計

複数アカウント運用の土台は、メールアドレスの整理と「誰が・どのIDで・どの目的に使うか」の設計です。
IDごとに別メールを用意し、受信ルールと命名規則を決めておくと、登録通知・認証コード・問い合わせ対応が混在せず、作業の抜け漏れを防げます。
加えて、復旧用メールや電話番号、2段階認証の設定までを最初のセットアップで一気に完了させることが安全です。
運用開始後は、フィルタとラベル、転送や自動振り分けを活用し、重要通知を見逃さない仕組みを作ります。
投稿や審査の連絡は時間差で来ることがあるため、メールの確認時間帯も決めておくと、対応スピードが安定します。
最後に、メール・ID・パスワード・復旧情報をパスワードマネージャーに一元化し、端末別のログイン状態を定期点検すると、長期運用でもミスが起きにくくなります。
【運用設計の要点】
- IDごとに別メール→通知の混在回避
- 復旧情報と2段階認証→初期設定で完了
- フィルタ・ラベル→重要通知を見逃さない導線
- 命名ルール(用途_ジャンル@…)と受信ラベル
- 重要通知の転送先と確認時間帯
| 用途 | 命名・運用の例 |
|---|---|
| 個人日記 | personal_blog@… → ラベル「個人」/通知は自分のみ |
| 美容レビュー | beauty_blog@… → ラベル「案件/レビュー」/下書き共有なし |
| 料理レシピ | cooking_blog@… → ラベル「レシピ」/画像受信は自動フォルダ |
用途別メール取得とラベル整理
新規IDごとに別メールを取得し、用途が一目で分かる名前にします。受信箱は「登録・認証」「問い合わせ」「コメント通知」などのラベルで分け、通知系は重要マークや自動振り分けを設定します。
複数人で関わる場合でも、ログイン共有は避け、必要な通知のみをチーム用の受信先へ転送すると安全に連携できます。
Gmailなどではエイリアス(+タグ)を使った仕分けも有効で、登録・審査・請求などのトピック別にフィルタを作ると、重要メールの見落としが減ります。
画像や添付の多いジャンルでは、容量対策として古い大型添付を定期整理するルール化が有効です。
最終的には「用途別メール→ラベル→フィルタ→確認時間帯→アーカイブ」の流れを定型化し、誰が見ても同じ手順で処理できるようにしておくと、急なトラブル時にも対応がブレません。
【整理のコツ】
- 用途が分かる名前→迷子にならないメール運用
- ラベルとフィルタ→登録/審査/問い合わせを自動仕分け
- チーム連携は転送で最小限共有→ログイン共有は避ける
- 通知が一つの受信箱に集中→重要メールが埋もれる
- 添付の肥大化→容量不足で認証メールが受信不能
回復用メール・電話の設定
復旧情報は、登録直後に必ず設定します。復旧用メールはメインとは別の信頼できるアドレスを紐づけ、電話番号も本人が確実に受け取れる回線を登録します。
2段階認証を有効にしておくと、乗っ取りや不正ログインの抑止になります。バックアップコードが提供される場合は、安全な場所に保管し、端末紛失時の最終手段として活用できるようにします。
複数IDを運用するなら、各IDの〈復旧用メール/電話〉を一覧で見える化しておくことが重要です。さらに、端末変更や番号変更のタイミングで復旧情報の更新が漏れやすいため、更新チェックを「端末買い替え時」や「電話番号変更時」のチェックリストに入れておくと安心です。
復旧情報の整備は、実際にトラブルが起きた際の復旧時間を大幅に短縮し、投稿停止のリスクを抑えます。
【推奨設定】
- 復旧用メール=メインと別系統の信頼アドレス
- 電話番号=本人受信可能な回線+2段階認証を有効化
- バックアップコード=オフライン保管で緊急時に備える
紛失時の確認と復旧手順
ログインできなくなった場合は、まず原因の切り分けから始めます。パスワード誤り、2段階認証の受信不可、認証メール未着、端末紛失など、どこで止まっているかを特定します。
次に、登録メールで「パスワード再設定」を実施し、迷惑メールやプロモーションタブも確認します。2段階認証で詰まる場合は、バックアップコードを使用し、ない場合は復旧用メール・電話で本人確認のフローへ進みます。
端末を紛失したときは、まず他端末からログイン履歴を確認し、見慣れない端末のセッションをすべて無効化します。
パスワードの即時変更と、復旧情報(電話/メール)の見直しを同時に行い、関連するアメブロIDのパスワードも個別に更新します。
最後に、パスワードマネージャーの記録と実際の設定が一致しているかを照合し、同じ事故が起きないように「原因→対策→担当」を簡単に記録しておくと、再発防止につながります。
【復旧フロー】
- 原因特定→パスワード再設定→迷惑メール確認→再送
- 2段階認証で停止→バックアップコード→復旧用連絡へ
- 端末紛失→セッション無効化→全IDのパスワード更新
- 登録メールにアクセス可能か→受信許可/容量を確認
- バックアップコードの所在→保管場所をチームと共有
アプリ・PC切替と並行運用の基本

複数アカウントを安全に並行運用するには、PCとスマホで「環境を分ける」ことが基礎になります。PCはブラウザのプロファイル機能でIDごとに閲覧履歴・Cookie・拡張機能を分離し、プロファイル名やテーマ色を変えて一目で判別できるようにします。
スマホは、アプリアカウントを切り替える運用が基本のため、通知の混同を避けるルール(いつ・どのIDで受け取るか)を決めます。
さらに、各IDの下書きテンプレ・プロフィール画像・固定フレーズを差別化しておくと、投稿画面で誤ログインに気づきやすくなります。
画像・動画の保管先もID別のフォルダを作り、ファイル名の先頭にIDを入れると検索が速くなります。
最後に、投稿前の確認フロー(URLのID確認→プレビュー→リンク点検→予約設定)を定型化し、誰が見ても同じ手順で実行できるようにしておくと、ヒューマンエラーを大きく減らせます。
【並行運用の柱】
- PC=プロファイル分離/スマホ=切替ルールの明確化
- ID別テンプレ・素材・フォルダで視覚判別と検索効率化
- 公開前チェックを定型化→ミスを未然にブロック
- PC:ID別プロファイル+専用ブックマークバー
- スマホ:通知と下書きの時間帯をIDごとに固定
| 項目 | 実務ポイント |
|---|---|
| 環境分離 | Cookie・履歴・拡張機能をIDごとに分離し誤投稿を防止 |
| 素材管理 | フォルダ名・ファイル名の先頭にIDを付け検索性を確保 |
| 確認フロー | 公開前にURLのID→プレビュー→リンク→予約を順に確認 |
ブラウザプロファイル分離運用
PCでは、ブラウザのプロファイル機能を使ってアカウントごとの作業環境を分けるのが効果的です。プロファイルを「beauty用」「recipe用」のように用途名で作成し、アイコンとテーマ色を変えるだけで、今どのIDで作業中かを視覚的に判断できます。
保存パスワード・拡張機能・ブックマークもプロファイル単位で独立するため、ログインの取り違えや自動入力ミスが減ります。
さらに、各プロファイルのスタートページを該当ブログのダッシュボードに設定し、ブックマークバーには「新規投稿」「画像管理」「アクセス解析」など頻出ページを並べておくと動線が短くなります。
シークレットウィンドウは一時的な確認に有効ですが、恒常運用はプロファイル分離のほうが再現性と安定性に優れます。
拡張機能は最低限に絞り、クリップボード履歴や自動置換ツールはID誤適用を招かないように、プロファイル別の設定にしておくと安心です。
【設定のコツ】
- プロファイル名・色・アイコンで即判別できる設計
- スタートページ=各IDのダッシュボードに固定
- 拡張機能は最小限→プロファイル単位でON/OFF管理
| 課題 | 対策 |
|---|---|
| 自動入力の誤適用 | 保存先をプロファイルごとに分離→使い回しを禁止 |
| 作業画面の混同 | 色・アイコン・ブックマーク命名で視覚区別を強化 |
| 確認漏れ | プレビューとURLのID確認をブックマークレット化 |
アプリのログイン切替の基本
スマホアプリは、基本的に一度に1つのIDでログインして運用します。切替の際は必ず現在のIDを把握し、必要に応じてログアウト→別IDでログインの順に進めます。
自動ログインを有効にしている端末では、誤投稿の原因になるため、複数IDを扱う端末は自動ログインをオフにし、毎回のログイン確認をルール化すると安全です。
通知はアプリにログイン中のIDに紐づくため、通知を受けたいIDを時間帯で決める、あるいは端末ごとに担当IDを固定するなど、整理された運用にします。
画像・メモの共有は、クラウドフォルダをID別に用意し、スマホの共有シートから該当フォルダへ直送できるようにしておくと、取り違えが起きにくくなります。
切替直後はプロフィールアイコンとブログURLのIDを必ず確認し、投稿画面に進む前に「どのIDで書いているか」を声に出してチェックするなど、儀式化した動作も人為ミスの抑止に有効です。
【切替時の注意】
- 自動ログインは複数ID端末ではオフ→毎回確認
- 通知はログイン中のIDに紐づく→時間帯または端末で整理
- 素材はID別フォルダへ直送→共有シートの行き先を固定
- 自動ログインのまま誤IDで投稿→自動ログインを無効化
- 通知に釣られて誤IDの編集画面へ→URLのIDを先に確認
投稿ミス防止のチェック項目
公開直前の「数十秒の確認」で、多くの事故は防げます。まず、編集画面のURLにあるIDが狙いのアカウントと一致しているかを確認します。
次に、プレビューでプロフィール名・アイコン・ヘッダーが想定どおりかを見て、本文の固定フレーズ(ID専用の署名や注意書き)が正しく表示されるかをチェックします。
リンクはURL・アンカーテキスト・遷移先の3点を確認し、アフィリエイト表記やPR表記が必要な場合はテンプレートの抜けがないかを見ます。
予約投稿では日時・タイムゾーン・再通知の設定を再確認し、同時刻に別IDの予約がないかもカレンダーで重複チェックします。
最後に、公開後の動作確認として、別端末で記事を開き、キャッシュに依存しない状態で表示崩れやリンク切れがないかを見ると安心です。
【公開前チェックリスト】
- URLのID→プロフィール表示→固定フレーズの順に確認
- リンク先・アンカー・表記(PR/広告)の3点確認
- 予約時間・重複・通知の整合性を最終チェック
- URLでID一致を確認→プレビューで見た目を確認
- リンク・画像・表記を点検→誤字脱字を最終確認
- 予約or即時公開を選択→公開後に別端末で動作確認
- 各IDに固有の固定フレーズと署名を設定
- 公開前チェックを1枚のシートにまとめ、毎回実施
| チェック | 方法 |
|---|---|
| ID一致 | 編集画面URLとプロフィール名・アイコンで二重確認 |
| 表記・リンク | PR表記・アンカー整合性・リンク先の実到達を確認 |
| 予約整合 | 時刻・タイムゾーン・他IDの予約重複をカレンダーで確認 |
AmebaPick運用と規約遵守の要点

AmebaPickはアメブロ公式のアフィリエイト機能で、Ameba利用規約とAmebaPick利用規約、関連ガイドラインに従って運用します。
基本の前提として〈AmebaID1つにつきAmebaPickは1アカウント〉で、無断の複数登録や複数のドットマネー口座登録はNGです。違反があると、記事削除・報酬取消・機能停止などの措置が取られることがあります。
広告表示は読者にわかるように行う必要があり、AmebaPick利用時は記事にPR表示が自動付与されます。
あわせて、薬機法・景表法などに抵触する表現、根拠のないNo.1表記、権利侵害、広告主が定める掲載条件違反などは避けましょう。
まずは「ID・口座の1対1」「PR表示」「表現の適法性」「広告主条件の確認」という4点を運用の土台にすると安全です。
- IDとAmebaPickは1対1、ドットマネーも1個人1口座で統一
- PR表示は自動付与→記事の見出し・本文でも誤認を招かない表現に
- 薬機法・景表法・権利侵害のNGを事前に洗い出し
- 各案件の「報酬条件・注意事項」を必ず確認
| 確認項目 | 要点とヒント |
|---|---|
| ID・口座 | AmebaID=Pick1アカウント/ドットマネーは1個人1登録。統一管理で誤連携を防止。 |
| 表記 | PR表示は自動。誇大広告や根拠なしNo.1、医薬的効能の断定は避ける。 |
| 案件条件 | 成果条件・禁止キーワード・媒体条件を案件詳細で必ず確認する。 |
禁止事項と報酬取消リスク
禁止事項に該当すると、記事削除や報酬取消、機能停止などの対応が行われます。代表例は次のとおりです。
①法律に反する効果・効能の記載(化粧品・健康食品等での医薬的断定、浸透の過度表現など)②広告主ごとの掲載条件違反(禁止キーワードでの出稿、条件外の誘導)③モラル・ルール違反(虚偽情報、根拠のないランキングやNo.1表記)④権利侵害(画像や文章の無断利用)などです。
さらに、AmebaPickの登録運用では「AmebaID1つに対し1アカウント」「複数ドットマネー口座の登録禁止」が明記されており、これらに抵触する運用は避ける必要があります。
処分は事前通知なく行われる場合があり、判断理由は原則開示されません。日常運用では、案件詳細の「報酬条件・注意事項」を読み、記事公開前にNG表現チェックとリンク先条件の再確認を徹底しましょう。
- 法律系NG→薬機法・景表法に触れる断定表現は避ける
- 広告主条件→「成果判定期間」「禁止ワード」などを厳守
- 運用規則→IDは1対1、ドットマネー口座の複数利用は不可
- 「飲むだけで痩せる」など医学的断定の記載
- 根拠なしのNo.1・最安・売上日本一の表現
- 第三者の写真・ロゴを無断転載しての紹介
広告表記とレビュー基準
AmebaPickを使う記事には、読者に広告であることが伝わるようPR表示が自動で付きます。加えて、本文・見出し・レビューの書き方でも誤認を招かない配慮が必要です。
効果を断定する表現は避け、使用感は具体的事実(使い方、質感、サイズ感、計測データ等)に基づいて書くと安全です。
医薬的効能の暗示や、「肌の奥まで」など科学的裏づけのない表現はNG。ランキングやNo.1を名乗る場合は、出典・調査主体・調査日を明示します。
写真や図は自作・自撮りが原則で、他者素材は利用許諾とクレジットを確認しましょう。広告主が案件個別に設ける「掲載可否条件/リスティングNGキーワード」も遵守が必要です。
最後に、レビュー記事の締めにPR表記の再確認と、リンク先条件(成果の起点・判定期間など)の整合をチェックして公開すると安心です。
- PR表示は自動→本文でも誤認防止の言い回しを徹底
- レビューは事実ベース→断定表現・誇大表現は避ける
- 案件条件→掲載要件・NGワード・成果条件を事前確認
- 出典・根拠・比較条件を明記(ランキング・No.1表記時)
- 画像は自作・自撮りを基本に、他者素材は許諾と表示
問い合わせとヘルプ活用先
不明点があるときは、まずAmebaPickのFAQ(ヘルプ)で「投稿ルール」「報酬条件」「おまかせ広告」などのページを検索し、該当するガイドを確認します。
解決しない場合は、Amebaのお問い合わせ窓口から「Ameba Pick」を選んで送信します(必要に応じてログインして本人確認のうえやり取り)。
報酬まわりや口座連携の疑問は、ドットマネーのヘルプ内「アカウント」「エラー」セクションが早道です。
複数口座を作ってしまった場合は統合・削除の案内があり、同一交換先の重複登録はエラーになります。
運用を安定させるには、問い合わせ履歴と設定変更の記録をIDごとに残し、同じ質問はFAQの該当URLをチーム内ナレッジに貼って再発防止します。
| 窓口 | 用途と見つけ方 |
|---|---|
| AmebaPickヘルプ | 投稿ルール・報酬・機能のFAQ。検索→該当ガイドへ。 |
| お問い合わせ | ヘルプで解決しない個別相談。サービス名で「Ameba Pick」を選択。 |
| ドットマネー | 口座・交換エラー・複数口座の統合/削除の案内を確認。 |
まとめ
アメブロの複数アカウントは、目的別に分けて運用すれば効果的。まずは可否と規約を確認し、異なるメールで作成→ID/パスを安全管理→切替と投稿ミス防止を徹底。
AmebaPickは1ID1口座などのルールに留意。今日できるのは、用途別のメール取得とコンテンツ計画づくりです。