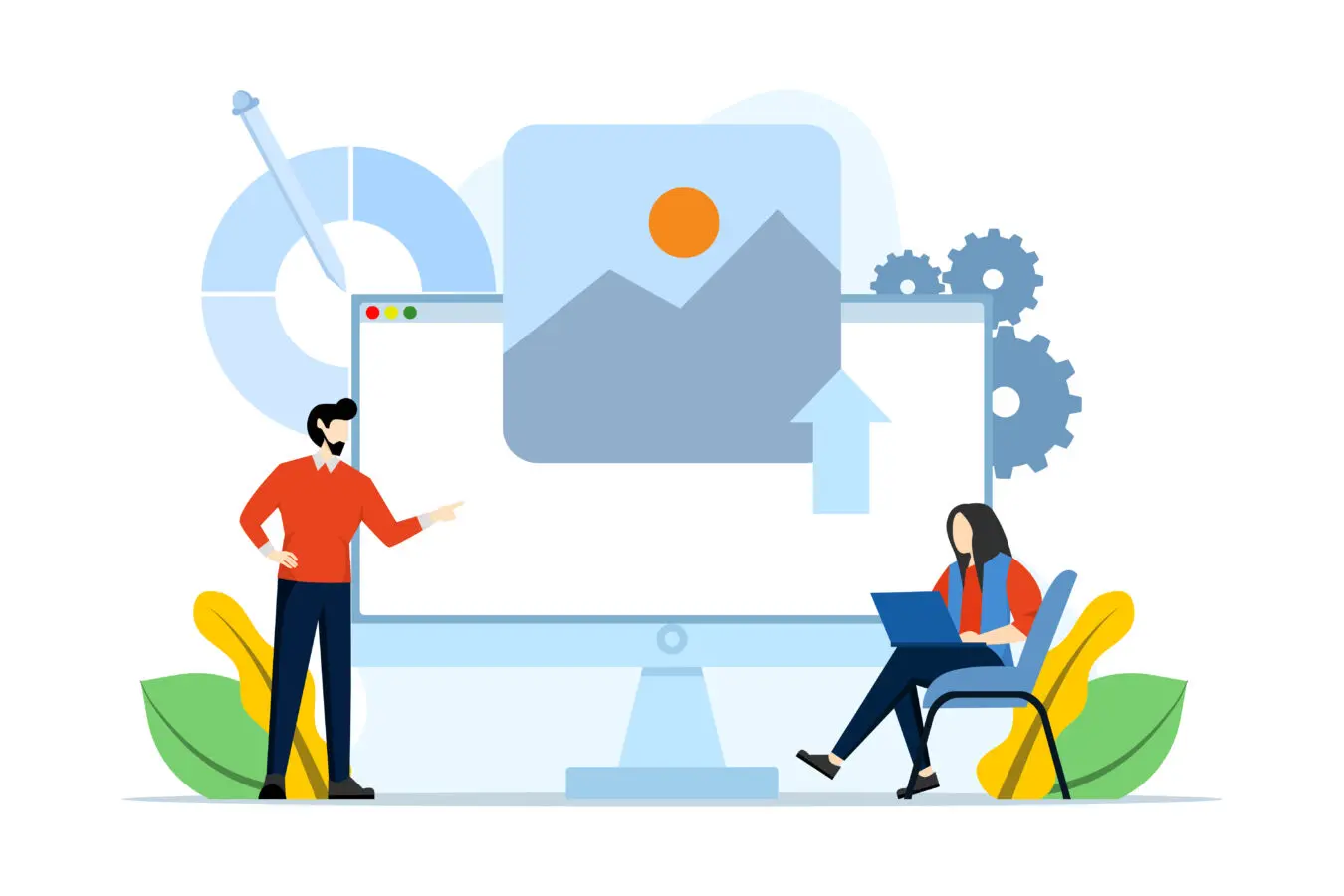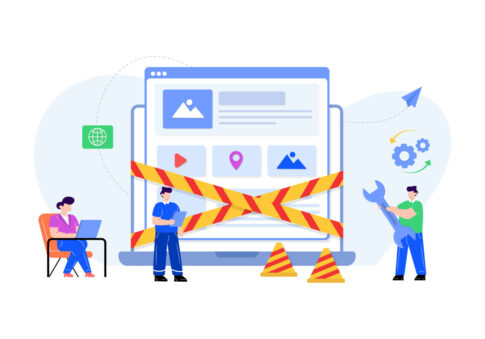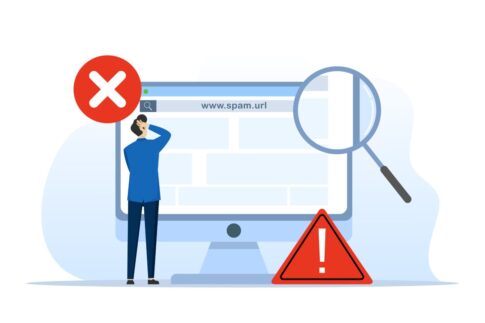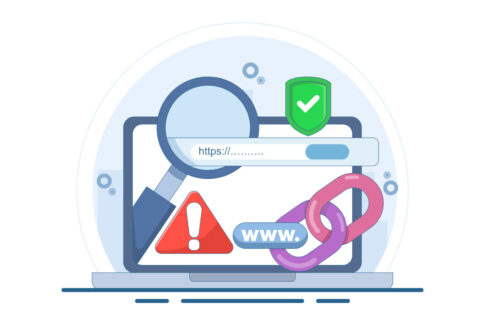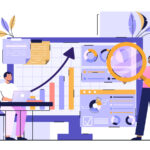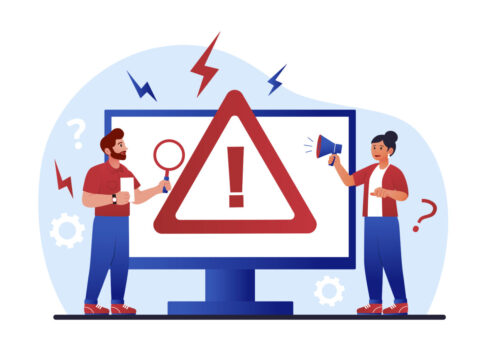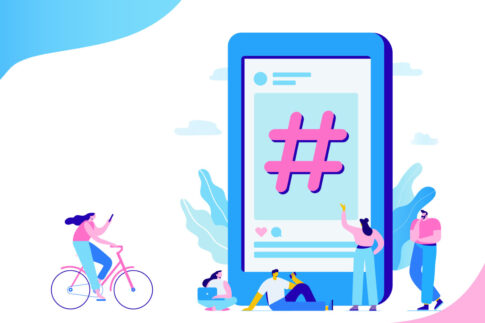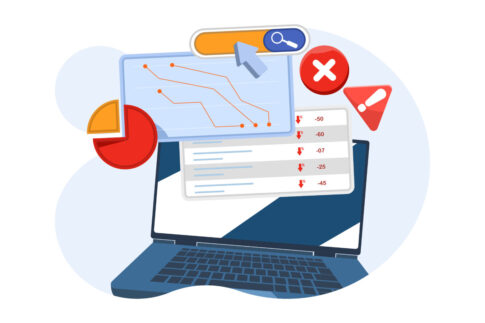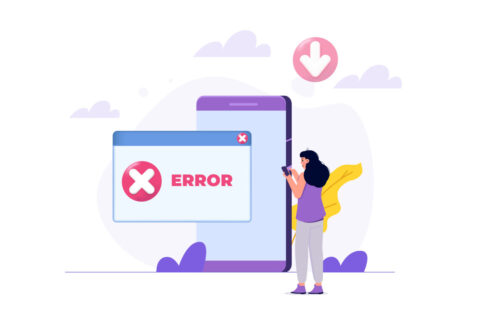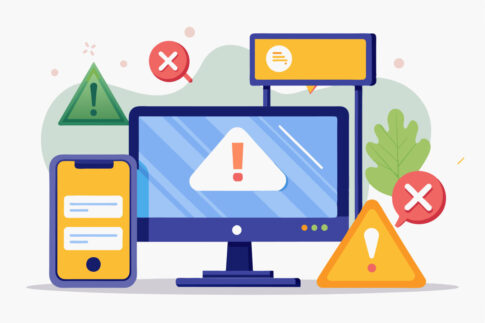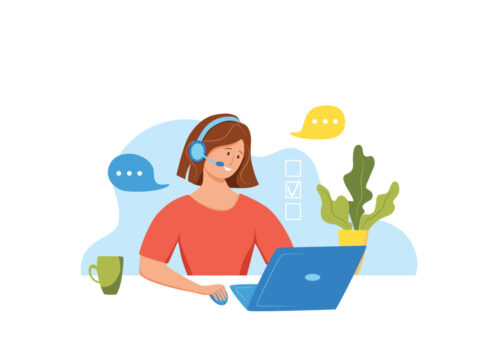アメブロでテーマを整理しようとしたのに「編集できない」「画面が開かない」「削除できない」と困っていませんか。原因は、編集できる場所の勘違いから、アプリとブラウザの仕様差、反映遅れや一時的な不具合までさまざまです。
本記事では、テーマ編集を開ける場所と条件を整理したうえで、症状別に原因を切り分け、保存できない・並び替えが反映されない・削除できない場合の対処手順まで、初心者でも迷わない順番で解説していきます。
目次
テーマ編集できる場所と条件

アメブロの「テーマ編集」は、記事を分類するための“テーマ一覧”を追加・並び替え・削除する管理機能です。
まず押さえたいのは、読者として見ている閲覧画面からは編集できず、ログインした「ブログ管理」側でのみ操作できる点です。
また、同じ「テーマ」という言葉でも、デザインの見た目を変える“デザインテーマ”とは別物なので、探す場所を間違えると「編集できない」と感じやすくなります。
さらに、削除には条件があり、対象テーマに記事が1件以上あると削除できません。ここでの“記事”には下書きが含まれるため、表示上は0件でも削除できないケースが出ます。
- 閲覧画面ではなく「ブログ管理」から操作する
- 編集したいブログのアカウントでログインしている
- アプリなら「ブログ管理→設定・管理→テーマ」から開く
- 削除は、対象テーマに記事(下書き含む)が残っているとできない
アプリでテーマ編集を開く手順
アプリで「テーマ編集できない」ときは、最初に“今いる画面がブログ管理かどうか”を確認すると解決が早いです。
タイムラインや記事一覧を見ている状態だと、テーマの編集メニューは出てきません。アプリの「ブログ管理」から設定・管理へ進み、「テーマ」を開くと、テーマ名の追加や並び順の編集ができます。
並び順は0〜100の範囲で設定する仕様のため、数字が未入力だったり同じ数字が重複していたりすると、並びが意図どおりにならないと感じることがあります。
操作後に反映されない場合は、保存できていないか、回線が不安定で処理が完了していないケースもあるため、保存完了まで画面を閉じないのがコツです。
- アプリ下部などのメニューから「ブログ管理」を開く
- 「設定・管理」へ進む
- 「テーマ」をタップしてテーマ編集画面を開く
- 追加する場合は「テーマ名」と「順番(0〜100)」を入力して追加する
- 編集後は保存まで完了させ、表示が変わったかブログ側で確認する
PC・スマホブラウザで編集する手順
PCでは、テーマ編集は「テーマ編集の画面」から行います。ブラウザの場合、閲覧ページと管理ページが見た目で区別しづらく、ログインしていても“閲覧側の自分のブログ”を開いているだけだと編集にたどり着けないことがあります。
迷ったら、管理メニュー内に「設定・管理」や「テーマ編集」といった管理項目が出ているかで判断すると確実です。
なお、テーマの削除は、対象テーマに記事が残っていると実行できないため、削除が目的なら先に記事側のテーマ付与を外す必要があります。
| 手順 | やること |
|---|---|
| 1 | ブラウザでアメブロにログインし、「ブログ管理」を開きます |
| 2 | 管理メニューの「設定・管理」から「テーマ編集」へ進みます |
| 3 | テーマ名の追加、順番(0〜100)の設定、不要テーマの削除操作を行います |
| 4 | 保存まで完了させ、ブログ表示側で反映を確認します |
閲覧画面と管理画面の違い
「テーマ編集できない」の多くは、閲覧画面で探し続けてしまうことが原因です。閲覧画面は読者が見るページと同じ扱いで、記事を読む・テーマ一覧で絞り込むことはできても、テーマの追加や並び替え、削除といった編集機能は出ません。
一方、管理画面はログイン状態でブログを“運営する側”のメニューが表示され、テーマ編集を含む設定がまとまっています。見分けるコツは、画面内に「ブログ管理」「設定・管理」など運営者向けの導線があるかどうかです。
ここを切り分けられると、次に「表示されない」「保存できない」といった不具合の切り分けにも進みやすくなります。
- 自分のブログを開いていても「閲覧画面」だと編集メニューは出ません
- 「テーマ(記事分類)」と「デザインテーマ(見た目)」は別機能です
- ログイン中でも、別アカウント・別ブログだと編集対象が違うことがあります
症状別:テーマ編集できない原因を切り分け
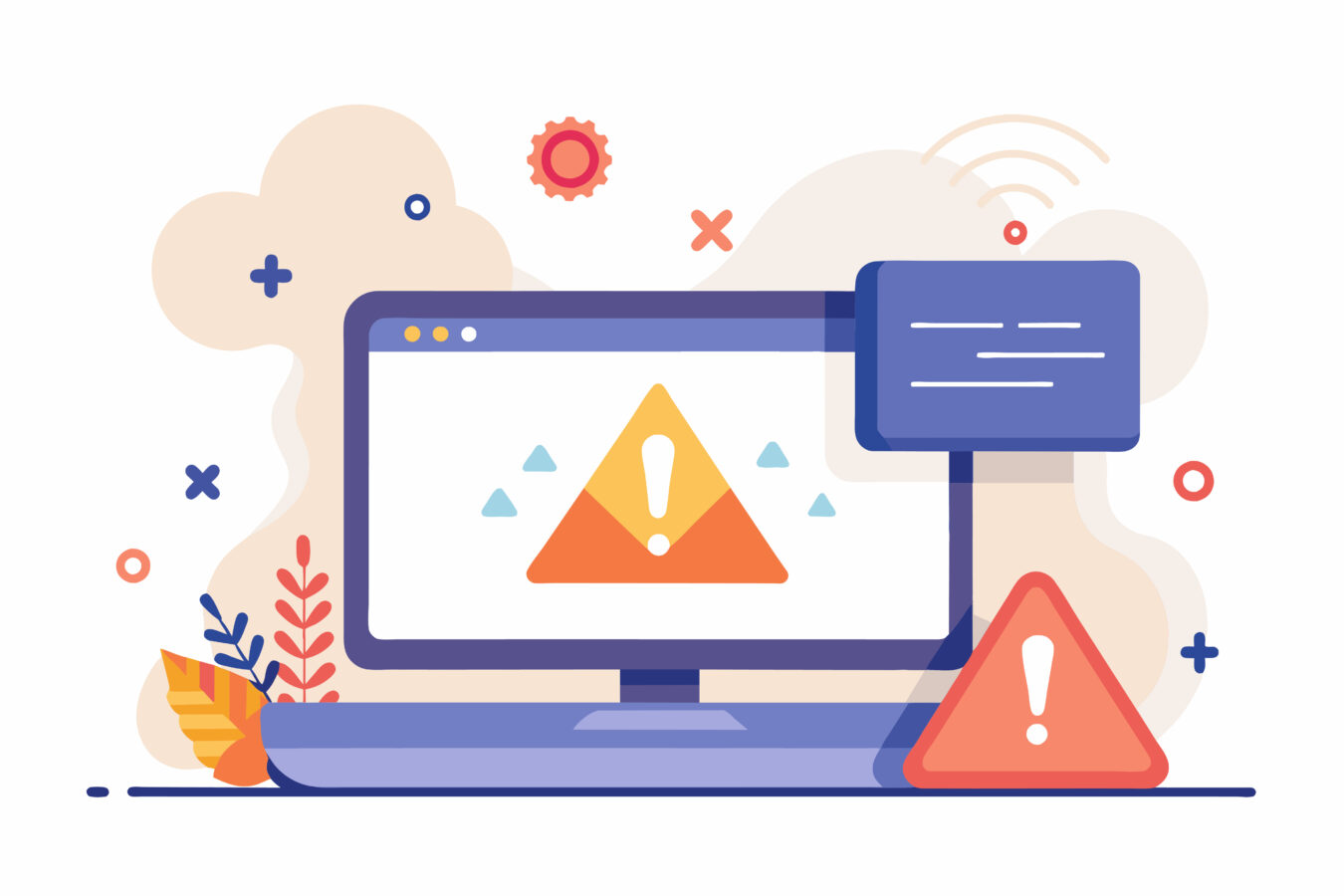
「テーマ編集できない」と言っても、実際の症状は大きく3つに分かれます。1つ目は編集画面そのものが開かない・ボタンが押せない。2つ目はテーマを追加・変更しても保存できない。3つ目は並び順を変えたのに反映されない、です。
ここを切り分けずに対処すると、キャッシュ削除や再インストールなど遠回りをしがちです。まずは自分の症状を1つに絞り、次に「基本チェック→環境別対処」の順で試すと短時間で解決しやすくなります。
特にアメブロは、アプリ版とブラウザ版で操作導線が違い、ログイン先の取り違えも起きやすいので、症状の前に「どの端末・どの環境で・どの画面を操作したか」をメモしておくと切り分けがスムーズです。
- 症状を3つのどれかに分類する(開かない/保存できない/反映されない)
- アプリとブラウザで同じ操作を試し、再現するか確認する
- 編集対象のブログでログインしているか確認する
編集画面が表示されない・押せない
編集画面が開かない場合は、まず「管理画面に入れていない」「そもそもテーマ編集の入口が違う」などの操作ミスが多いです。
次に多いのが、アプリの動作不安定や回線の一時的な不調、ブラウザの拡張機能による表示崩れです。
特にスマホで“画面が押せない”症状は、広告ブロックやコンテンツブロック系の設定が影響することがあります。
また、ログイン中でも別アカウントの状態だと、編集したいブログの管理メニューにたどり着けず、結果として「編集が出ない」になります。
切り分けは、同じアカウントで別環境(アプリ→ブラウザ、または逆)に切り替え、入口が出るかを確認するのが早いです。
【表示されない・押せない時のチェックリスト】
- 今の画面が「ブログ管理」か(閲覧画面ではないか)
- 編集したいブログのアカウントでログインしているか
- アプリの「ブログ管理→設定・管理→テーマ」から開いているか
- ブラウザはシークレット等で開くと同じ症状か
- 回線を変えると改善するか(Wi-Fi↔モバイル)
- 閲覧画面で操作していて編集メニューが存在しない
- 別アカウントでログインしている
- 一時的な通信不良やアプリの不安定な状態
- ブラウザ拡張機能やコンテンツブロックの影響
追加・変更が保存できない
保存できない場合は、「保存ボタンを押したつもりでも通信が切れて処理が完了していない」「入力ルールに合っていない」「同じ内容で更新になっていない」などが考えられます。
テーマ名が長すぎる、空欄がある、並び順の数値が未入力といった“入力の不備”があると、保存が進まないケースがあります。
また、保存後すぐに画面を閉じたり、別画面へ移動したりすると、処理が途中で止まって反映されないことがあります。
対策としては、入力を最小限にして保存できるか試し、保存完了まで待つ、別環境で同じ操作を試す、の順に進めるのが効率的です。
- テーマ名が空欄になっていないか、余計な空白がないか確認する
- 並び順(0〜100)を入力し、重複していないか確認する
- 保存を押したら、完了するまで画面を閉じずに待つ
- 同じ操作をブラウザ版でも試して、保存できるか確認する
- 改善しない場合は再ログインやアプリ再起動を行う
- まずは新規テーマを1つだけ追加して保存できるか試します
- 入力は短いテーマ名+順番入力に絞ると切り分けが早いです
- 保存後はブログ表示側でテーマ一覧を開いて確認します
並び順が反映されない
並び順が反映されないときは、原因が「設定そのもの」か「表示の見え方」かで対処が変わります。
まず、並び順は数字で管理されるため、同じ数字が複数テーマに設定されていると意図どおりにならないことがあります。
また、並び順を変えた直後はアプリ表示が古い情報を持っていて、更新されるまで時間がかかるケースもあります。
さらに、どこで並びを確認しているかも重要で、管理画面では並びが変わっているのに、閲覧画面のテーマ一覧が更新されていない場合があります。
切り分けは、管理画面で数字が保存されているかを確認し、次に別環境(別ブラウザや別端末)でテーマ一覧を見て同じ並びになるかを確認すると確実です。
| 確認ポイント | 対処の目安 |
|---|---|
| 数値の重複 | 同じ順番が複数ある場合は、重複をなくして保存し直します |
| 保存の成否 | 管理画面で並び順の数値が残っているか確認します |
| 表示の更新 | アプリ再起動、ブラウザ更新、別端末で確認して差を切り分けます |
| 確認場所 | 管理画面と閲覧画面の両方で並びを確認し、差を把握します |
- 並び順の数字が重複している
- 保存前に画面を閉じてしまい、変更が残っていない
- アプリ側の表示が更新されておらず古い並びが出ている
テーマが削除できないときの典型パターン

テーマ編集で特に詰まりやすいのが「削除できない」です。多くの場合、削除ボタンが出ないのではなく、削除しようとしても完了しない、または削除対象として扱われない状態になっています。
基本ルールとして、テーマはそのテーマに紐づく記事が残っていると削除できません。ここで注意したいのは、表示上の「記事数」と実態がズレるケースがあることです。
代表例が下書きや予約投稿が残っているパターンで、公開記事が0件でも削除できない原因になります。
また、テーマ側ではなく記事側の設定が残っていると、削除条件を満たせません。まずは「そのテーマがどの記事に付いているのか」を洗い出し、外したうえで削除する流れにすると、迷わず解決できます。
- 対象テーマに紐づく記事がないか(下書き・予約含む)
- 記事側でテーマが外れているか
- 別環境(アプリ/ブラウザ)でも削除できないか
記事数0でも下書きが残っている
「記事数0なのに削除できない」場合、まず疑うべきは下書きや予約投稿です。テーマ一覧の表示が“公開記事だけ”を数えているように見える場面があり、管理上は下書き・予約が残っているため削除できない、というズレが起きます。
特に、過去にテーマを作って下書きを書いたまま放置していると、本人の記憶から抜けていて原因に気づきにくいです。
対処は、該当テーマが設定されている下書き・予約投稿を探し、その記事からテーマを外すか、下書きを削除することです。
検索やフィルタでテーマを絞れる場合は活用し、難しい場合は最近の下書きから順に確認すると見落としが減ります。
【下書き残りを疑うチェックリスト】
- 下書き一覧に該当テーマが付いた記事がないか
- 予約投稿一覧に該当テーマが付いた記事がないか
- 過去に試し書きした下書きが残っていないか
- 同じテーマ名を複数作っていないか
- 公開記事は0件でも、下書きや予約にテーマが残っていることがあります
- テーマ名を変えたつもりでも、別テーマとして残っていることがあります
- 投稿画面の自動入力で、意図せず同じテーマが付くケースがあります
削除できないテーマがあるケース
削除できないと感じるケースには、実際に削除条件を満たしていないだけでなく、操作環境によって削除メニューが見えにくい場合もあります。
たとえば、アプリだと削除ボタンが画面下部にあり気づきにくい、ブラウザだと表示領域の関係でボタンが押せない、など“UIの問題”が起こることがあります。
また、編集対象のブログではなく別ブログを見ている、別アカウントでログインしている、といった取り違えでも削除できません。
さらに、仕様変更や一時的な不具合の影響で削除操作が進まないケースもあるため、同じ操作をブラウザ版でも試して再現するかどうかを確認すると、原因が絞れます。
| 状況 | 対処の目安 |
|---|---|
| 削除ボタンが見つからない | 画面をスクロールし、管理画面のテーマ編集内に削除操作があるか確認します |
| 押しても反応しない | 回線を変える、再ログインする、別ブラウザで操作してみます |
| 削除できない表示が出る | 下書き・予約を含め、紐づく記事が残っていないか確認します |
| 環境差が疑わしい | アプリとブラウザで同じ操作を試し、再現するか切り分けます |
- まず条件(記事が残っていないか)を確認します
- 次に環境(アプリ/ブラウザ)を変えて同じ症状か確認します
- 最後にログイン先と編集対象ブログの取り違えがないか確認します
記事側でテーマを外す手順
テーマ削除の最短ルートは、「テーマ編集画面で削除を連打する」ではなく、記事側からテーマ付与を外して条件を満たすことです。
該当テーマが付いている記事を見つけ、記事編集画面でテーマを別のものに変更するか、未設定にします。
下書きや予約投稿も同様に、編集画面でテーマを外す必要があります。すべて外せたら、テーマ編集画面に戻って削除を実行します。
作業が多い場合は、よく使うテーマだけ残し、使っていないテーマをまとめて整理すると、以後の運用も楽になります。
- 削除したいテーマ名をメモし、同名テーマがないか確認します
- 公開記事の編集画面を開き、該当テーマが付いていれば外します
- 下書き・予約投稿も同様に編集画面を開き、テーマを外します
- テーマ一覧に戻り、削除操作ができるか確認します
- 削除後、テーマ一覧や記事表示で意図した状態か確認します
- 下書きフォルダに残った過去の試し書き
- 予約投稿に付いたテーマ
- 新規投稿画面で前回テーマが自動入力されたままの下書き
基本チェック:環境別の直し方
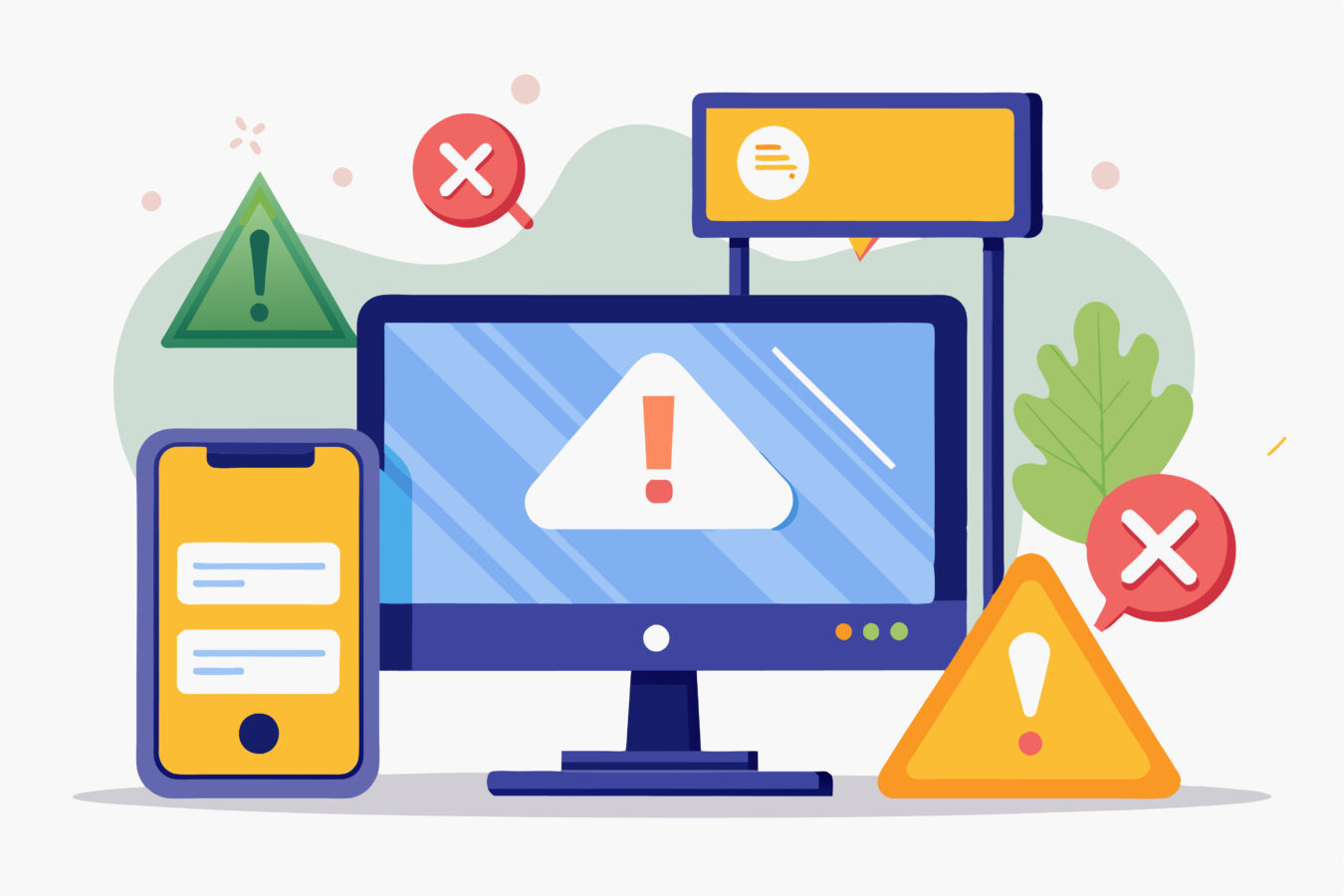
テーマ編集がうまく動かないときは、原因が「設定や操作の問題」ではなく、端末やアプリ、ブラウザの環境差で起きていることもあります。特にアメブロはアプリとブラウザで表示や操作導線が異なり、同じことをしたつもりでも結果が変わるケースがあります。
ここでは、不具合系の基本である「環境を変えて再現するか」を軸に、最短で直すためのチェックをまとめます。
大切なのは、いきなりアプリを消す・端末を初期化するような強い対処に走らず、まず“負荷の低い手順”から試して原因を絞ることです。原因が絞れれば、同じ失敗を繰り返さずに済み、問い合わせ時も状況説明が簡単になります。
- アプリ→ブラウザへ切り替えて同じ操作を試す
- 軽い対処(更新・再ログイン)→重い対処(キャッシュ削除)へ進める
- 回線と端末を変えて再現するかで原因を絞る
アプリ版とブラウザ版の違いを確認
まず試してほしいのは、アプリでダメならブラウザ、ブラウザでダメならアプリという“入口の切り替え”です。
テーマ編集は管理画面で行う点は共通ですが、表示の仕方やボタン位置、反映のタイミングに差が出ることがあります。
たとえばアプリでは操作はできたのに表示が更新されず「反映されない」と感じる、逆にブラウザではボタンが押しにくい、などのケースが起こり得ます。
切り分けは「同じアカウントで」「同じテーマを」「同じ操作で」試し、結果が変わるかを見るのがコツです。
結果が変わるなら環境差の可能性が高く、片方で編集できるなら、その環境を“当面の回避策”として使いながら、安定した環境を探すのが現実的です。
| 比較軸 | 確認すること |
|---|---|
| 入口 | アプリのブログ管理か、ブラウザのブログ管理か |
| 操作 | 編集画面が開くか、保存が完了するか、削除できるか |
| 反映 | 管理画面の表示と、閲覧画面のテーマ一覧の表示が一致するか |
| 回避策 | 片方でできるなら、その環境で一旦作業を完了させる |
- アプリは表示更新が遅れて古い並びが残るケースがあります
- ブラウザは拡張機能や広告ブロックでボタンが押せない場合があります
- 同じ操作でも保存完了までの待ち時間に差が出ることがあります
キャッシュ削除・再ログイン・再起動
テーマ編集の不具合は、ログイン状態の不整合やキャッシュの影響で起きることがあります。まずは軽い対処として、ページの更新やアプリの再起動、ログアウト→ログインを試します。
これで改善しない場合に、アプリのキャッシュ削除やブラウザのキャッシュ削除へ進めると安全です。
いきなりアプリ再インストールをすると、ログイン情報や通知設定の再確認が必要になり手間が増えるため、段階的に進めるのが効率的です。
また、保存できない・反映されない症状は、操作直後に画面を閉じてしまうことでも起きるため、保存処理が完了したことを確認してから戻るのがポイントです。
- 画面を更新し、同じ操作で再現するか確認する
- アプリを完全に閉じて再起動し、もう一度テーマ編集を開く
- ログアウト→ログインし直して、編集対象ブログが正しいか確認する
- 改善しない場合はキャッシュ削除を行い、再度操作する
- 保存後はすぐ閉じず、表示が変わるまで待ってから確認する
- アカウントとパスワードの再確認(再ログインに備える)
- 編集したいテーマ名と現在の順番のメモ(戻しやすくする)
- 反映確認に使う端末やブラウザを決めておく
端末・回線・拡張機能の影響
押せない、表示されない、保存できないといった症状は、端末や回線の状態、ブラウザの拡張機能が原因になることがあります。
特にブラウザでは、広告ブロックやスクリプト制限、コンテンツブロックが管理画面の動作に影響するケースがあります。
スマホでも、通信が不安定だと保存処理の途中で止まり、結果として「保存できない」「反映されない」になりやすいです。
切り分けは、回線を切り替える、別端末で試す、拡張機能を一時的に無効にして試す、の順で負荷の低いものから進めます。
ここで別環境では正常に動くなら、アメブロ側の仕様というより、環境由来の可能性が高いと判断できます。
【環境要因を切り分けるチェック】
- Wi-Fiとモバイル通信を切り替えて再現するか確認する
- 別端末(PC/スマホ)で同じ操作を試す
- ブラウザはシークレットで開いて再現するか確認する
- 広告ブロックなど拡張機能を一時停止して試す
- 通信が重い時間帯を避けて再操作する
- 別端末では同じ操作が問題なくできる
- シークレットでは動くが通常ウィンドウでは動かない
- 回線を変えると保存や表示が安定する
解決しない場合の確認先と問い合わせ準備

ここまでの切り分けと基本チェックを試しても直らない場合は、アカウントや端末の問題ではなく、サービス側の不具合や仕様変更の影響を疑う段階です。
このとき重要なのは、同じ操作を繰り返して消耗しないことと、問い合わせで一度で状況が伝わる形に整理しておくことです。
特に「編集画面が開かない」「保存できない」「削除できない」などは、再現条件が分からないと確認に時間がかかります。
先に公式案内を確認し、同様の障害が出ていないかを把握したうえで、問い合わせに必要な情報をまとめるとスムーズです。
さらに、急ぎでテーマを整理したい場合は、別環境での編集を“暫定回避策”として使うと、運用を止めずに済みます。
- 公式案内で障害や仕様変更がないか確認する
- 再現条件をまとめてから問い合わせる
- 急ぎなら別環境で編集して作業を完了させる
障害情報と公式案内の確認
不具合が疑われるときは、まず公式の「お知らせ」やヘルプで、障害やメンテナンス情報、仕様変更の案内が出ていないか確認します。
これを先に行う理由は、個別の設定ミスではなくサービス全体の問題だった場合、端末側の対処を続けても解決しないからです。また、テーマ編集は管理機能の一部なので、管理画面周辺で障害が出ていると影響を受けることがあります。
公式案内が出ている場合は、案内されている手順や回避策が優先になります。案内が見つからない場合でも、同じ症状が出ていないかを確認することで、問い合わせ時の説明が整理しやすくなります。
| 確認先 | 見るポイント |
|---|---|
| 公式お知らせ | 障害・メンテナンス・不具合修正の告知がないか |
| 公式ヘルプ | テーマ編集の仕様、削除条件、編集手順の変更がないか |
| アプリ更新情報 | 最新版への更新で改善する不具合が含まれていないか |
- 公式案内がある場合は、その内容が最優先です
- お知らせとヘルプは掲載場所が異なるため両方見ます
- アプリ更新が滞っていると、既知の不具合が残ることがあります
問い合わせ前にまとめる情報
問い合わせは、情報が揃っているほど回答が早くなります。特にテーマ編集は、どの画面で何をしようとして、どこで止まったかが重要です。
初心者がつまずきやすいのは「押せない」「できない」とだけ伝えてしまい、確認に時間がかかることです。
そこで、症状を一文で言える形にし、端末情報、アプリかブラウザか、再現手順、エラー表示の有無をセットでまとめます。
スクリーンショットが用意できるなら、個人情報が写っていないかを確認したうえで添付すると状況が伝わりやすくなります。
【問い合わせ前にまとめる情報】
- 症状:開かない/押せない/保存できない/反映されない/削除できない のどれか
- 発生場所:アプリかブラウザか、ブログ管理のどの画面か
- 端末情報:機種名、OS、ブラウザ名、アプリのバージョン
- 再現手順:どこを開き、何を入力し、どのボタンを押したか
- エラー:表示文言、表示されたタイミング、スクリーンショットの有無
- アプリのブログ管理→設定・管理→テーマを開くと画面が真っ白になる
- テーマ名を追加して保存を押すが、保存後に一覧に反映されない
- 順番を変更して保存したが、閲覧画面のテーマ並びが変わらない
回避策として別環境で編集する方法
急ぎでテーマを整えたい場合は、原因の特定を待たずに、編集できる環境で作業を完了させるのが現実的です。
具体的には、アプリで不具合が出るならブラウザ版で操作し、ブラウザで押せないならアプリで操作する、といった切り替えが有効です。また、ブラウザ版はシークレットで開くと拡張機能の影響を受けにくく、操作できるケースがあります。
端末が複数あるなら、別端末でログインして操作するのも手です。回避策で作業を終えた後は、反映が正しく出ているかを閲覧画面で確認し、必要なら後日あらためて原因切り分けや問い合わせを行う流れにすると、運用を止めずに済みます。
- アプリで不具合なら、ブラウザでブログ管理を開いて同じ操作を試す
- ブラウザで不具合なら、アプリのブログ管理からテーマ編集を試す
- ブラウザはシークレットで開き、拡張機能の影響を避ける
- 回線を切り替え、保存や反映が安定するか確認する
- 編集後は閲覧画面でテーマ一覧を確認し、意図した並びかチェックする
- 編集対象のアカウントとブログが正しいか毎回確認します
- 保存完了前に画面を閉じると反映されないことがあります
- 同じ順番の重複など設定ミスがあると、環境を変えても直りません
まとめ
アメブロでテーマ編集できないときは、まず編集場所が正しいかを確認し、アプリ版とブラウザ版で同じ操作ができるか試すのが近道です。
次に、表示されない・保存できない・並び順が反映されないなど症状別に原因を切り分け、キャッシュ削除や再ログイン、別端末での再現確認で環境要因を潰しましょう。
削除できない場合は、下書きや記事側のテーマ付与が残っていないかも確認します。それでも解決しなければ、公式案内を確認し、状況を整理して問い合わせへ進むとスムーズです。