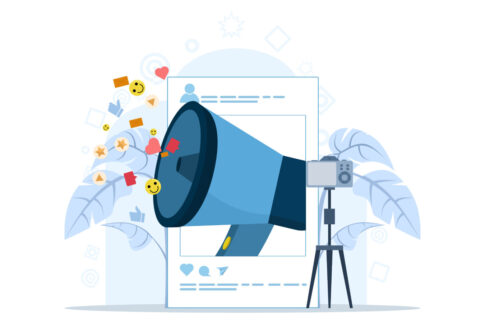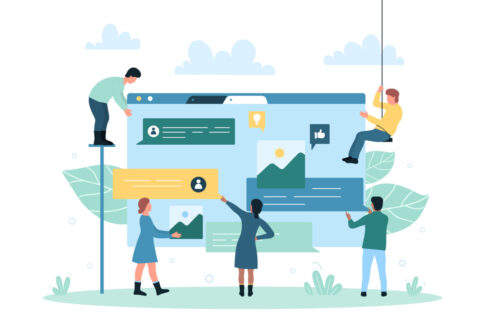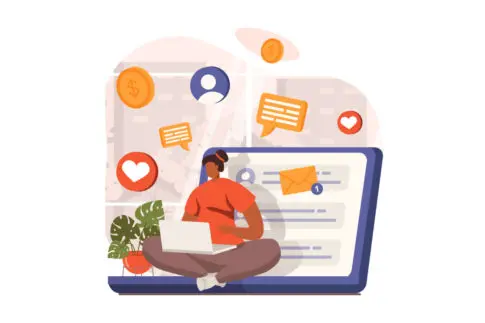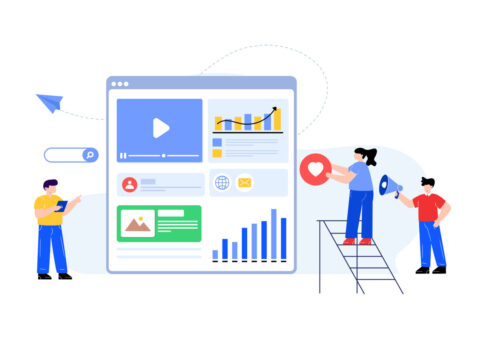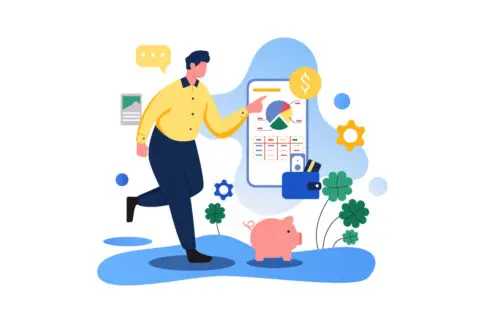アメブロのAmebaPick審査期間がどれくらいか不安な方向けに、申請から承認通知までの流れ、期間の目安と数え方(営業日)、早い/遅いケースの違い、遅延時の確認・問い合わせ、提携審査との違い、期間短縮のコツまでを整理して解説していきます。この記事だけで迷わず準備できます。
目次
AmebaPick審査期間の目安と数え方

AmebaPickの審査期間は、公式の案内で「基本情報入力後、審査のため2〜3営業日」と明記されています。営業日表記のため、土日祝日を挟むと実際の待ち時間は延びやすい点に注意しましょう。
一方で、ヘルプには「ブログの審査は申請後最大10分、混雑時は2〜3日かかる場合あり」との記載もあります。
これは審査対象や混雑状況により所要時間が振れることを示すもので、実務上は「2〜3営業日」を上限の目安にしつつ、早ければ短時間で完了するケースもある、と理解しておくと安心です。
承認連絡はメールまたはプッシュ通知で届くため、迷惑メール振り分けや通知設定もあわせて確認しておくと取りこぼしを防げます。
| 公式目安 | 補足ポイント |
|---|---|
| 2〜3営業日 | 土日祝を除く換算。混雑や確認事項により前後あり |
| 最大10分の案内も | 状況次第で短時間完了のケースあり。通知設定は事前確認 |
- 登録メールの受信可否(迷惑メール・フィルタ)
- アプリの通知ON・端末のプッシュ許可
- 申請情報の入力漏れ・誤記の有無
申請から通知までの流れと確認手順
申請フローはシンプルです。まず、Amebaに登録済みのメールで認証し、届いたURL(有効期限あり)から基本情報を正確に入力して申請します。
入力後は審査に入ります(目安2〜3営業日)。承認されると、AmebaPickの利用が可能になり、通知はメールまたはプッシュで届きます。
申請時にエラーや不備があると審査に入れない、あるいは追加確認が必要になる場合があるため、氏名・住所・連絡先などの基礎情報、利用規約への同意状況をあらかじめ整えておくのが安全です。
オフィシャルブロガーは別途確認が入る旨の注記があるため、同区分の方は通常より時間がかかる前提で計画しましょう。
通知待ちの間は、メール受信設定とアプリ通知をONにし、申請メールのURL有効期限(24時間内アクセス)を過ぎていないかも確認しておくと安心です。
- 登録メールの認証→案内URLから基本情報入力(期限内アクセス)
- 審査待機(目安2〜3営業日)→メール/プッシュで結果受信
- 承認後にAmebaPickの利用開始(商品検索→Pick作成)
早いケース・遅いケースの違い
早いケースは、申請情報が正確で、ブログの基本要件に問題がなく、審査の混雑が少ないときに起きやすいです。ヘルプにある「最大10分」の記載は、このような条件がそろった場合の短時間完了の一例と捉えられます。
反対に、遅いケースは、申請情報の不備・入力漏れ、登録メールの未認証、オフィシャルブログ特有の追加確認、審査の混雑(年末年始や大型連休明けなど)で起こりやすく、結果として「2〜3営業日」を超えて実日数で待つこともあります。
通知に気づかないだけで完了見逃しになる例もあるため、メールの迷惑振り分け、フィルタ、モバイルの通知許可は必ず事前に整えておきましょう。
万一、案内されている目安を大きく超えた場合は、ヘルプページ経由の問い合わせフォームから申請状況を確認するのが確実です。
営業日カウントと週末・祝日の扱いの基本
公式案内は「2〜3営業日」と示しています。営業日は一般に土日祝日を含まない平日を指すため、金曜に申請すると翌週扱いになり、実日数では待機が長く感じられます。
大型連休・年末年始の前後は審査件数が増えやすく、ヘルプにも「混雑時は2〜3日程度かかる場合あり」との記載があるため、余裕をもった申請日程にすると安心です。
実務上は、営業日カウントを前提に「最短=即日〜翌営業日、通常=2〜3営業日、混雑・追加確認あり=それ以上」と見込み、通知設定と受信環境を整えたうえで待機するのがおすすめです。
迷った場合は、公式の「始め方」ページとヘルプの記載を併読し、想定外に遅いときは問い合わせ窓口から状況確認を行いましょう。
審査が遅い時のチェックと対処手順

AmebaPickの審査は、公式ヘルプで「申請後から最大10分程度(混雑時は2〜3日)」と案内されています。
基本情報入力後の目安として「2〜3営業日」の記載もあるため、まずは10分〜数時間の範囲で通知有無を確認しつつ、混雑時は数日待つ想定で準備すると安心です。
まずは「本当に遅延なのか」を切り分けるために、申請日を営業日換算で数え直し、週末・祝日を含めていないかを確認します。
そのうえで、受信環境(メール・アプリ通知)の点検、申請内容の再確認、ブログ側の基本設定(プロフィール・カテゴリ・公開設定など)の整合性を順に見直すと、原因に当たりやすくなります。
問い合わせは最後の手段にせず、事前に確認した事実やスクリーンショットを整理してから行うと、やり取りが1回で済みやすいです。
以下の表は、遅延時に効果が高い見直し観点をまとめたものです。
| 観点 | 確認内容 | ねらい |
|---|---|---|
| 受信環境 | 迷惑メール・フィルタ・アプリ通知のON/OFF | 承認通知・追加確認の見落とし防止 |
| 申請情報 | 氏名・住所・連絡先・生年月日・電話番号などの基本情報/誤記 | 審査の差し戻し防止・再入力の回避 |
| ブログ整合 | プロフィール・カテゴリ・記事テーマの一貫性 | 審査基準との適合性を明確化 |
- 営業日換算で再カウント→週末・祝日を除外
- メール・通知設定を点検→テスト送受信で確認
- 申請内容とブログ基本設定の齟齬を修正
メール認証・受信設定の再確認
審査が遅いと感じたとき、通知の見落としが原因というケースは少なくありません。まず、登録メールアドレスが現在も利用可能であるかを確かめ、受信ボックス・迷惑メール・プロモーション等の分類も横断して検索します。
検索キーワードは「Ameba」「AmebaPick」「申請」「審査」「承認」などが有効です。独自フィルタや転送設定を使っている場合は、転送先で迷惑判定されていないかも確認します。
スマホ側は、アプリの通知をON、端末側のプッシュ通知もON、バッテリー節約や集中モードで通知が抑制されていないかを点検します。
加えて、申請時に使ったメールアドレスとアメブロのアカウント情報が一致しているかも重要です。不一致があると、本人確認の追加連絡が必要になることがあります。
最後に、テストとして自分宛にメールを送る、別アドレスからの受信を試すなど、環境起因の問題を切り分けましょう。
【受信環境の見直しポイント】
- 迷惑メール・プロモーション振り分けの解除
- 独自フィルタ・転送設定の一時停止で動作確認
- アプリ通知・端末プッシュのONと権限付与
数日経過時の問い合わせ方法と必要情報
営業日換算で所定の目安を超えている、または追加確認の連絡が来ない場合は、公式ヘルプの「お問い合わせ」から状況確認を行います。問い合わせ前に、事実関係を簡潔にまとめておくとスムーズです。
具体的には、申請日(営業日換算の経過日数)、登録メールアドレス、ブログURL(またはブログID)、発生している事象(通知未着・エラー表示の有無)、試した対処(受信設定の見直し等)を時系列で整理します。
スクリーンショットを添付できる場合は、申請完了画面や設定画面、メール受信ボックスの検索結果画面など、状況を客観的に示す画像を準備すると、担当側のトラブルシュートが早まります。
問い合わせ送信後は、同内容の再送を短時間で重ねないことも大切です。重複チケットは確認の手間を増やし、かえって対応が遅れる原因になります。
返信を待つ間は、受信環境の点検を維持しつつ、申請情報の整合やブログの基本整備を進めておくと、追加連絡に即応できます。
- 申請日・経過営業日数・登録メールの明記
- ブログURL・発生事象・試した対処の整理
- 関連スクリーンショットの用意(任意)
基本情報不備・規約違反の見直しポイント
審査の停滞は、入力不備やブログ側のポリシー不適合が原因のこともあります。まず、氏名・住所・連絡先などの基本情報が正しく入力されているか、略称や旧住所が残っていないかを確認します。
銀行情報等の受取設定が必要な場合は、名義・口座種別の表記ゆれにも注意しましょう。
ブログ側では、プロフィールの内容とカテゴリが記事テーマと一致しているか、公開範囲が限定になっていないか、画像・引用・商標の扱いがガイドラインに沿っているかを点検します。
特に、無断転載や出典不明素材の使用、誇大・断定的な表現、年齢制限のある内容、薬機・景表などの法令に抵触し得る表現は避けるべきです。
レビュー記事では、体験に基づく記述と客観情報を分け、根拠のない効能断定や比較の誤解を招く見出しを修正します。
整備後は、代表的な記事の見出しと導入文を読み替え、誰に何をどのように伝えるブログかが一読で伝わる状態に整えましょう。
- 入力不備(氏名や住所の表記ゆれ・連絡先の誤記)
- 無断転載・出典不明画像の使用や過度な断定表現
- プロフィール・カテゴリと記事テーマの不一致
審査前に整えるブログ設定の要点

AmebaPickの審査は、申請情報だけでなくブログの「土台」が整っているかも見られます。まずは、プロフィール・カテゴリ・記事テーマの一致、公開設定やナビゲーションの分かりやすさ、画像・リンクの基本マナーなど、読む前の印象を決める要素を整備しましょう。
とくに初回訪問の読者は、プロフィールと最新記事、固定表示の案内(自己紹介・目次・お問い合わせ)を見て全体像を判断します。
ここに一貫性があれば、記事の評価も上がりやすくなります。内部リンクは無理に増やすより、関連記事への導線を本文の上部・中盤・末尾に各1つ置く程度が読みやすいです。
画像は縦横サイズを揃え、代替テキストを入れて内容が伝わるようにします。加えて、プライバシーポリシーや問い合わせ導線はフッターなどから一発で辿れるようにし、広告表記やレビューの開示も簡潔に添えておくと信頼性が高まります。
| 設定項目 | 確認観点(審査前チェック) |
|---|---|
| プロフィール | 誰が・何を・誰向けに書くかを一文で明示。顔写真orロゴ、発信テーマ、得意分野を簡潔に |
| カテゴリ | 主軸テーマと一致。雑記は減らし、レビュー/比較/Q&Aなど機能別の並びに整理 |
| 固定ページ | お問い合わせ・プライバシーポリシー・運営者情報を設置。フッターやサイドに常設 |
| 内部リンク | 上部・中盤・末尾に関連1リンクずつ→回遊導線を過剰にしない |
| 画像・表記 | 画像サイズを統一、代替テキストを付与。提供・PR・体験の別を明示 |
- 主軸テーマの明示(プロフィール・カテゴリ・見出しの語彙を統一)
- 信頼の基本(問い合わせ・ポリシー・自己紹介の整備)
- 読みやすさ(画像サイズ統一・過剰リンク回避・要点先出し)
プロフィール・カテゴリの整合と記載
プロフィールはブログの名刺です。最初の2〜3行で「自分は何者か」「誰のどんな悩みを解決するのか」「このブログで得られること」を一文ずつ示すと伝わります。肩書きは専門用語を避け、読者の言葉に置き換えると親しみやすくなります。
アイコンは顔写真または統一デザインのロゴを使い、ヘッダーやサイドの紹介文と内容を合わせます。カテゴリは「主軸テーマ→機能別(レビュー/比較/使い方/Q&A)」で階層を浅く保つと回遊がスムーズです。
雑記的な話題は主軸に寄せた切り口に修正し、適合しないものは別カテゴリか別媒体へ分離します。さらに、各カテゴリのトップに「このカテゴリで解決できること」を短いリードで置くと、初見でも迷いません。
プロフィール末尾にはお問い合わせ・ポリシー・自己紹介の深掘り記事へのリンクを配置して、信頼導線を用意しましょう。
【整合のための確認ポイント】
- プロフィールの一文要約=カテゴリ名・記事見出しの語彙と一致
- カテゴリは機能別で重複を排除→同テーマ記事を束ねる
- 自己紹介・お問い合わせ・ポリシーへの導線を明示
- 誰向け:◯◯の初心者向けに
- 提供価値:レビュー・比較・使い方で選び方を解説
- 実績・根拠:体験+データで公平に紹介
記事品質とテーマ一貫性の整え方
記事品質は「読みやすさ×必要十分な情報×一貫した視点」で決まります。まず、導入文で読者の悩みと結論の要点を先出しし、本文は見出しごとに1トピックを完結させます。
レビューは「基本情報→使い方→良い点→気になる点→向き不向き→結論」の並びにすると比較しやすいです。比較記事は3点までに絞り、価格・サイズ・特徴を表で示すと理解が早まります。
写真はビフォー→使用中→アフターの順で最小3枚を基準に、同じ比率で揃えるとモバイルでも崩れにくいです。
文章は主観と客観を分け、体験は「私はこう感じた」、事実は「仕様では◯◯」と書き分けます。内部リンクは結論直後と中盤に1つずつ配置し、関連記事→収益記事へ自然に誘導します。
最後に、カテゴリの主軸から外れる記事はタイトルと導入の切り口を調整し、ブログ全体で「誰に何を提供するのか」がブレないようにします。
| 要素 | 実装のコツ | 効果 |
|---|---|---|
| 導入文 | 悩み→結論→読むメリットを一文ずつ先出し | 直帰低下・本文の理解が速い |
| レビュー構成 | 基本情報→使い方→良い点/気になる点→結論 | 信頼性向上・購入判断がしやすい |
| 比較表 | 3製品・3指標(価格/サイズ/特徴)で簡潔に | 視認性向上・迷いの解消 |
| 写真 | 同一比率・最小3枚・代替テキストを付与 | モバイル最適化・検索流入の補助 |
- 導入が長く結論が後回し→結論先出しに修正
- 主観だけ・数値根拠なし→仕様・価格・比較を併記
- 内部リンク過多→上部・中盤・末尾の計3つに整理
提携審査の目安とAmebaPickとの違い
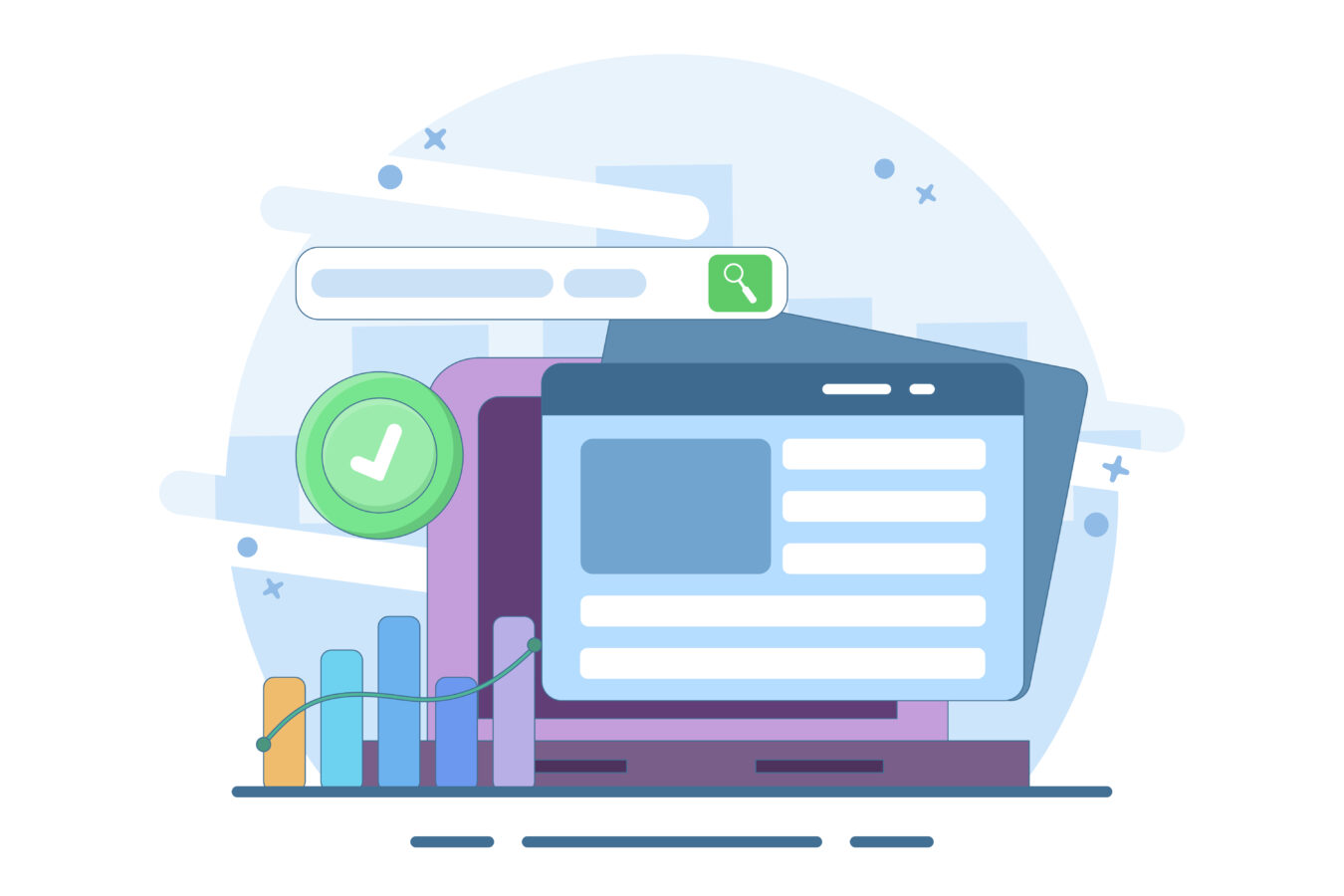
AmebaPickの「利用審査」は、プラットフォームを使えるかどうかを確認する一次審査です。
一方、本稿でいう「提携審査」は、個別のショップや案件ごとに露出可否・利用条件・素材の取り扱いをチェックする二次審査を指します。
つまり、AmebaPickの承認=すべての案件が自由に使える、ではありません。案件によっては即時に使えるものもあれば、手動確認が必要なもの、取り扱い領域(医薬・美容、金融、酒類など)ゆえに表現や年齢・地域の制限が厳しいものもあります。
運用上は、①ブログの主軸テーマと案件の相性、②表現規定(効能断定や誤認誘導の禁止)、③素材・画像・商標の扱い、④年齢・地域・媒体別の制限、を常に突き合わせてから着手すると安全です。
提携審査は「案件の看板を一緒に背負う行為」と捉え、読者に誤解を与えない説明と開示(PR・提供・体験の別)が整っていることを前提に、案件選定→導線設計→レビュー品質の順で準備を進めましょう。
| 審査の層 | 目的・見る点 | 運用の着眼点 |
|---|---|---|
| 利用審査(AmebaPick) | 媒体利用の可否/基本情報の妥当性 | プロフィール・カテゴリ整合、公開設定、受信環境の整備 |
| 提携審査(案件別) | 案件ポリシー適合/表現規定の順守 | テーマ適合、表現の客観性、素材・開示のルール徹底 |
- 利用審査=入口、提携審査=案件ごとの入口
- 案件ごとに条件・禁止事項・開示ルールを再確認
- 主軸テーマと読者像に合う案件を優先して選定
案件ごとの提携完了目安の確認方法
提携完了までの目安は案件ごとに異なります。即時に提携できるタイプもあれば、担当による手動確認が入るタイプもあります。
まずは案件詳細の「利用条件」「成果対象」「禁止事項」「素材の使い方」を読み、審査の有無や判定のタイミングが示されていないかを確認します。
次に、管理画面の提携状況(例:申請前/申請中/承認/不可 などの表示)がどこで確認できるかを把握し、ステータスの更新間隔を数日単位で観察します。
想定より遅いと感じたら、申請内容(サイトURL・カテゴリ・紹介予定ページ)が案件の期待と一致しているか、レビュー予定の表現が規定に抵触していないかを再点検し、必要に応じて申請文や紹介計画の補足を用意しておくと、追加の確認依頼に即応できます。
即時提携タイプでも、初回掲載時はルールに沿ったPR表記や比較基準の明示が求められることが多いため、記事側の体裁を先に整えておくと全体の進行がスムーズです。
- 案件詳細で審査有無/即時可否を確認
- 管理画面の提携ステータスと更新箇所を特定
- 想定超過時は申請内容と記事側の体裁を再点検
| タイプ | 特徴と運用のコツ |
|---|---|
| 即時提携 | 申請後すぐ利用可。初回からPR表記・比較基準・画像権利の整備を厳守→記事テンプレで漏れ防止 |
| 手動審査 | ブログのテーマ・表現・掲載面を確認。申請時に紹介方針を簡潔に添えると齟齬が減る |
否認時の見直しと再申請の基本
否認は「相性が悪い」のサインです。やみくもな再申請より、理由の仮説を立てて修正→再申請の順で進めると通過率が上がります。
まず、案件の禁止事項と表現規定を読み直し、効能・効果の断定、価格・比較の誤認誘導、医療・美容・金融などでの過度な宣伝的表現がないかを点検します。
次に、ブログ側の整備です。プロフィール・カテゴリ・関連記事の並びが案件テーマと一致しているか、PR・提供・体験の開示が記事上部に明確か、画像・商標の出典と権利表記が適切かを見直します。
記事は「主観(体験)」と「客観(仕様・データ)」を分け、デメリットも併記してバランスを取ると、案件の品質要件に合致しやすくなります。
修正後は、代表記事のBefore/Afterを示し、どこを直したかを一文で説明してから再申請すると齟齬が減ります。
再申請のタイミングは短期連投を避け、一定期間の運用と記事改善の実績を積んでからのほうが、判断材料が増えて受け入れられやすい傾向があります。
- 効能断定・比較の誤認誘導・過度な煽り表現
- PR表記・素材権利の不備(出典・商標・画像)
- ブログ主軸と案件テーマの不一致(読者像のズレ)
| 課題 | 見直す箇所 | 修正のコツ |
|---|---|---|
| 表現の過剰 | 見出し・導入・ボタン文言 | 客観語に置換/根拠の有無を明示/デメリット併記 |
| 開示不足 | 記事上部のPR明記・画像キャプション | 提供・体験・比較基準を先出し→誤認防止 |
| テーマ不一致 | プロフィール・カテゴリ・関連記事網 | 主軸テーマへ寄せる/不一致記事は別媒体に分離 |
- 禁止事項と表現規定の再読→該当箇所を修正
- 代表記事のBefore/Afterを準備→修正点を一文で説明
- 短期連投を避け、改善実績を添えて申請
審査期間短縮のための運用法

AmebaPickの審査は「営業日」で進むため、実際の待機時間を短く体感するには、申請の質とタイミングを整えることが近道です。まず、審査前の一週間でブログの土台を整えます。
プロフィール・カテゴリ・主要記事の一貫性をそろえ、レビューや比較など“審査後すぐ使う記事”の雛形も用意しておくと、追加確認が来ても即応できます。
申請タイミングは、週末直前より平日早い時間に行うと、営業日換算での待機ロスを抑えやすいです。
受信体制も重要で、登録メールの迷惑振り分け解除、アプリ通知の許可、端末の省電力や集中モードの除外設定を事前に整えます。
記事側は、画像サイズや見出しの語彙、内部リンクの置き方を統一して「誰に何を提供するブログか」を冒頭で明示します。
PR表記・出典表記・問い合わせ導線など信頼の基本がそろっていれば、追加質問が減りやすく、結果的に審査全体のリードタイムを短縮できます。
| 施策 | 実装のポイント | 期待できる効果 |
|---|---|---|
| 土台整備 | プロフィール・カテゴリ・固定ページを統一 | 追加確認の抑制→審査往復の短縮 |
| 記事準備 | レビュー/比較の雛形と画像を事前作成 | 修正依頼に即応→承認後の立ち上がり加速 |
| 申請時刻 | 平日昼間に申請→営業日換算で有利 | 実日数の待機を圧縮 |
| 通知環境 | 迷惑解除・通知許可・省電力除外 | 承認連絡の見逃し防止 |
申請前チェックリストとミス予防
審査の遅延は、入力不備や整合性の欠落が原因で起こりやすいです。申請前に、登録情報とブログの表示内容がズレていないかを必ず突き合わせます。
氏名・住所・連絡先の表記ゆれ、旧情報の残存、ブログURLや公開設定の誤りは、差し戻しの典型です。プロフィールは「誰向け」「何を提供」「得られる価値」を一文ずつ明示し、カテゴリは主軸テーマに沿って機能別に整理します。
記事は、導入で結論を先出し→本文で根拠→最後に行動導線という型にそろえると、審査側にも意図が伝わりやすくなります。画像は同一比率で統一し、代替テキストを付けます。
引用や比較では出典・条件・評価軸を明示し、過度な断定は避けましょう。申請の直前にテスト公開と表示確認を行い、リンク切れや表示崩れ、PR表記の欠落がないかを最終チェックします。
- 登録情報とブログ表示の一致(氏名・連絡先・URL)
- プロフィール・カテゴリ・主要記事の一貫性
- PR表記/出典表記/問い合わせ導線の有無
- 画像比率統一・代替テキスト付与・リンク切れなし
- 通知設定の確認(メール迷惑解除・アプリ許可)
通知見逃し防止の設定と管理のコツ
承認メールや追加確認の見逃しは、審査全体の時間を無駄にします。まず、登録メールの受信ボックスで送信元や件名のキーワードをフォルダ振り分けし、重要度を高く設定します。
迷惑メール・プロモーション分類を解除し、独自フィルタや転送の影響も点検します。スマホはアプリ通知を許可し、端末の通知・サウンド・バッジを有効化、集中モードや省電力の対象外に設定します。
通知が来たら即時に対応できるよう、申請日と対応履歴をメモに残し、追加提出が必要なファイル(プロフィール文、記事キャプチャ、出典一覧など)はクラウドにまとめておきます。
複数アドレスを持つ場合は、受信用に一つへ集約し、テスト送受信で実際に届くかを確認すると安心です。問い合わせ後の再送は短時間に重ねず、受信環境を保ったまま返信待ち→既読確認→次アクションの順で管理しましょう。
- 迷惑振り分け放置→受信許可とフォルダ振り分けで回避
- 通知OFF・省電力対象→アプリ通知ONと除外設定で回避
- 複数アドレスの混在→受信アドレスを一つに統一
まとめ
審査は「流れの把握→基本情報の整備→メール受信設定→ブログの一貫性確認→必要時の問い合わせ」の順で整えると迷いません。
期間は営業日で数え、週末・祝日を考慮します。提携審査は別枠と捉え、記事品質と導線を磨きつつ、チェックリストでミスを予防し、通知の見逃しを減らすことが承認への近道です。