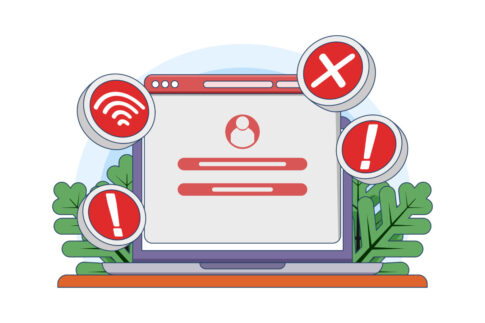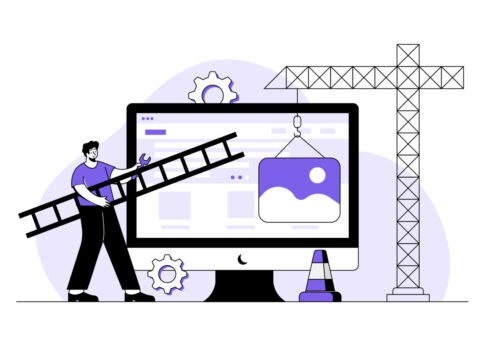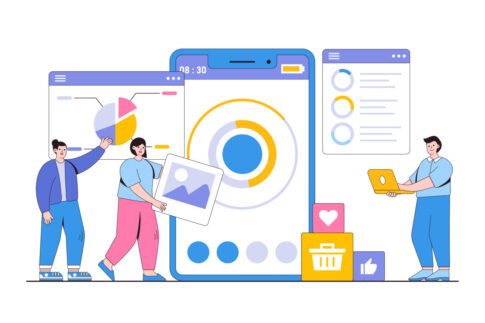AmebaPickで収益化を始めたい方向けに、仕組みと始め方、対応ストアと報酬の流れ、審査準備、稼げる記事テーマと商品選定、リンク配置とSNS再利用、規約の注意点、ドットマネー受取までを実践手順で解説していきます。今日から安全に始める型がわかります。
目次
AmebaPickの仕組みと始め方

AmebaPickは、Amebaブログ内で商品リンクを作成・掲載し、読者の購入(または所定の成果地点)に応じて報酬が発生する公式アフィリエイト機能です。
ブログと管理画面が一体化しているため、記事編集画面から商品検索→リンク生成→掲載までがスムーズに行えます。報酬の受け取りは2通りです。
楽天市場のアイテムは楽天アフィリエイトで受け取り、楽天市場“以外”はドットマネーが付与されます。ドットマネーは付与から“6か月以内”に交換が必要です(期限経過で失効)。始め方はシンプルです。
Amebaブログの基本設定(プロフィール・ジャンル・固定ページ)を整え、管理画面からAmebaPickの利用申請→承認後に「商品を探す」からリンクを作成します。
リンクはテキスト・カード・ボタン等を選べ、記事の文脈に合わせた配置が可能です。成果を積み上げるには、ターゲットと記事テーマを先に決め、レビュー型・比較型・チェックリスト型など記事フォーマットを固定化すると運用が安定します。
| 要素 | 内容・確認ポイント |
|---|---|
| 報酬付与 | 成果承認後にドットマネー付与→管理画面で残高・交換手続き |
| リンク形式 | テキスト/カード/ボタンなど。記事の導線と視認性で使い分け |
| 掲載位置 | 本文の結論付近/比較表の直後/レビュー要点の直下などに集約 |
| コンプライアンス | 利用規約・ガイドラインを順守。誤認表現・権利侵害を回避 |
【スタート手順(概略)】
- プロフィールと固定ページを整備→提供価値・問い合わせ導線を明記
- 記事フォーマットを決定→テーマに合う商品タイプを想定
- AmebaPick申請→承認後に商品検索・リンク生成→テスト掲載
- 記事内の主CTAは1つに統一→リンクの乱立を避ける
- サムネと冒頭三行に「誰に→何が→どう良くなる」
- リンク先の体験を確認(スマホで可読性・カート導線)
対応ストア一覧と報酬発生の流れ理解
AmebaPickは、提携済みストアの商品を紹介して成果を計測します。代表的な大型EC(例:楽天市場、Amazon など)に対応し、管理画面の「対応ストア一覧」から最新の取扱状況・リンク種別・成果条件を確認できます(取扱や条件は変更される場合があるため、都度の確認が前提です)。
成果は「読者がリンクをクリック→対象ストアへ遷移→所定の行動(購入など)→承認→ドットマネー付与」という流れで計上されます。
自己購入や虚偽レビュー、過度な誇大表示は規約違反となる可能性があるため、レビューは事実ベースで、比較は評価軸を明確に示します。
リンクは記事1本につき目的を1つに絞り、クリック導線を分散させないことが収益最大化につながります。
| 項目 | 概要 | 確認ポイント |
|---|---|---|
| 対応ストア | 大型EC等に対応(最新は管理画面で確認) | 取扱の有無・成果条件・掲載可否の更新を定期チェック |
| 成果地点 | 購入などストアごとの条件で承認 | カート導線・対象外カテゴリの有無を事前把握 |
| リンク種別 | テキスト/カード/ボタン/画像リンク等 | スマホ表示で可読性・押しやすさ・回遊を確認 |
【成果を取りこぼさない要点】
- レビュー要点→結論→リンクの順に並べ、クリック動機を明確化
- リンクは1つに集約→関連記事と競合させない
- ストア条件の変更に備え、定期的にリンク先の挙動を点検
- 自己購入や誤認を誘う表現
- 景品表示法・薬機法に触れる断定的表現
- 画像・文章の権利侵害(引用は出典と範囲を明記)
申請手順と審査準備のチェック
申請はAmebaブログの管理画面から行い、承認後にリンク作成が可能になります。審査通過を安定させるには、ブログ自体の基本整備が重要です。
まず、プロフィールに提供価値・運営者情報・問い合わせ導線を明記し、固定ページ「初めての方へ」「方針/免責」「よくある質問」を用意します。
記事はオリジナル性のある内容を複数本公開し、誤認を招く表現やセンシティブなテーマの取り扱いに注意します。
画像は権利関係を整理し、引用は出典を明確にします。審査後も規約やガイドラインは更新されることがあるため、定期的に管理画面を確認し運用をアップデートします。
| チェック項目 | 基準・整備ポイント |
|---|---|
| プロフィール | 「誰に→何を→どう良くなる」を1行で明示。連絡先・導線を設置 |
| 固定ページ | 初めての方へ/方針・免責/FAQで不安を事前解消 |
| 記事品質 | 独自の体験・比較・写真等でオリジナリティを担保 |
| 表現と権利 | 誇大・断定を避け、画像/引用は出典・許諾を確認 |
【申請前の最終確認】
- 記事内の主CTAと言い回しを統一(リンクは1つに集約)
- スマホ表示で可読性・押しやすさ・回遊を実機チェック
- ガイドライン更新を管理画面で確認→表現・導線を微修正
- 最初の3本は「結論→手順→比較/事例→リンク」の同一フォーマットで作成
- 保存数・プロフィール遷移・クリック率を週次で可視化
稼ぐ設計|記事テーマと商品選定

AmebaPickで収益を伸ばす起点は、記事テーマと商品選定を「読者の検索意図」と「購入までの距離」で設計することです。まず、読者が何を解決したいのか(悩み語)を言い切り、記事テーマを1つに絞ります。
次に、そのテーマに最も適合する商品を〈価格帯・在庫/配送・レビュー件数・サイズ/カラー展開・再現性〉の観点で選びます。
記事は意図に合わせて、やり方(ハウツー)、比較(選び方)、体験(レビュー)のどれかに特化するとクリックと購入がぶれません。
導線は本文の小結→リンクの並びを固定化し、リンクは1本に集約して迷いをなくします。季節性やトレンド商品は賞味期限が短いので、定番と組み合わせて在庫切れリスクを回避します。
最後に、掲載後24時間はクリック率・保存数・プロフィール遷移を見て、タイトルと言い回しだけを小さく改善すると、再現性のある伸び方になります。
| 意図/段階 | 記事テーマ例 | 商品選定の基準 |
|---|---|---|
| やり方 | 「◯分でできる〜の始め方」「失敗しない手順」 | 初心者向け・必要道具が少ない・到着後すぐ使える |
| 比較 | 「AとBどっち」「選び方の軸と向き不向き」 | 価格/サイズ/機能が明確に差別化・公式情報が確認可能 |
| 体験 | 「1週間使って分かったこと」「用途別の使い分け」 | 写真/動画が用意できる・日常で再現しやすい使用例が豊富 |
【運用フロー】
- 悩み語を1つ決める→記事テーマを1本化
- 商品候補を3つに絞る→在庫/配送/レビューを確認
- 本文の小結→リンク1本→CTAの順で固定化
- 読者の使用シーンに合うか(自宅/職場/外出先)
- サイズ・色・価格が比較しやすいか
- 在庫と配送目安が安定しているか
ターゲット像と購買動機の整理
ターゲット像は、アクセス解析やコメントの「読者の口ぐせ」を材料に具体化します。年齢や性別といった属性より、いつ・どこで・どんな場面で困っているか(使用シーン)を先に決めると、商品要件が一気に明確になります。
購買動機は〈問題回避(失敗したくない)〉〈効率化(時短/省手間)〉〈快適/自己表現(見た目・体験)〉の3軸で整理し、本文冒頭で動機に直結するベネフィットを提示します。
反対に、購入を迷わせる理由(価格・サイズ不安・設置/設定の手間)は、本文の中盤で先回りして解消します。ターゲット像は1記事1タイプに絞り、導入文と見出しの言い回しを合わせると、クリック後の離脱が下がります。
【把握しておく情報】
- 閲覧端末と時間帯→画像サイズ/文章量の最適化
- 想定予算→代替案(上/中/下の価格帯)を1つだけ提示
- 使用シーン→「朝の支度」「仕事帰り」などで再現例を作成
| ターゲット | 主な動機 | 不安/障壁と対処 |
|---|---|---|
| 在宅ワーカー | 時短・省スペース | 設置の手間→写真で手順化/必要工具を冒頭で明記 |
| 子育て層 | 安全・耐久・洗いやすさ | 素材と洗い方→公式情報への導線と自分の写真 |
| 美容関心層 | 見た目・持続性 | 誇大表現回避→使用条件/頻度を具体化して期待調整 |
- 問題回避:失敗例→回避手順→リンク
- 効率化:時間短縮の数値→必要道具ゼロ→リンク
- 快適/表現:Before/After写真→使用感の一言→リンク
レビュー構成と使用例の作り方
レビューは「読み手がそのまま再現できる」ことが最重要です。構成は〈結論→使用環境→写真/動画→良い点→気になる点→向き/不向き→リンク〉の順に固定し、主観だけでなく条件(部屋の明るさ/身長/使用頻度/肌質など)を明示します。
写真は1枚目で全体、2枚目で重要ディテール、3枚目でサイズ感を示し、本文の直後にリンクを1つだけ置きます。良い点はベネフィット(できること)で語り、気になる点は代替案や回避策とセットで短く添えます。
体験の「前提」が違うと誤解を生みやすいため、使用前の状態と比較基準を書いて期待値を調整します。最後に、購入後の初回設定や保管のコツを1行入れると、保存と再訪が増えます。
| 要素 | 書き方のコツ |
|---|---|
| 結論/総評 | 誰におすすめ→理由を1文で。数字や所要時間を添える |
| 使用環境 | 前提条件を明示(頻度/場所/体格/肌質など) |
| 良い点/気になる点 | ベネフィットで要約→懸念は回避策とセットで簡潔に |
| 写真/動画 | 全体→部分→サイズ感の順。矢印(→)で視線誘導 |
| リンク/CTA | 小結の直後に1つだけ。ボタン文言は行動形に統一 |
【使用例テンプレ(置き換えて作成)】
- 状況:◯◯のために△△で使用(週◯回/◯分)
- 結果:◯◯が◯%短縮/◯個分のスペース確保
- コツ:最初に◯◯すると失敗しにくい/保管は◯◯が便利
- 効果を断定する表現(個人差・使用条件を明記して調整)
- リンクの乱立(1本に集約してクリックを分散させない)
- 引用・画像の出典不明(出典/撮影者を明記)
クリック率を高める導線設計

AmebaPickのクリック率は、記事内の「視線が止まる位置」にリンクを集約できるかで大きく変わります。
基本は〈結論→小結→リンク→補足〉の順で、読了前でも意思決定できる配置にすることです。タイトル・サムネ・冒頭三行・見出しで使う語を統一し、本文でも同じ言い回しを繰り返すと、期待とのズレが減りクリックが安定します。
スマホ閲覧が中心なので、リンクは指が届きやすい幅と行間を確保し、1記事の主目的に対してリンクは1本に絞ります(関連記事や他CTAと競合させないのがコツです)。
さらに、比較表やチェックリストの直後は「判断の直後」で反応が高いため、ここにボタン形式のリンクを置くと効果的です。
下表のように、記事内の各ポイントに役割を与え、テキストかボタンかを使い分けると、クリック→回遊→購入の流れが途切れません。
| 配置箇所 | 狙い | 実装のコツ |
|---|---|---|
| 冒頭小結の直後 | 早期意思決定 | 要約→1本のリンク→補足の順。過剰な説明は後段へ |
| 比較表・チェックリスト直後 | 判断直後の後押し | 評価軸の再掲→ボタン1つだけ→文言は行動形 |
| 結論セクション末尾 | 読了直後の背中押し | ベネフィットの再提示→リンク→FAQ1行で不安解消 |
【確認ポイント】
- 主目的に対するリンクは1本に集約→競合リンクを置かない
- リンク前に小結でベネフィットを1文提示→動機を可視化
- スマホでタップしやすい行間と余白→誤タップを防止
リンク配置とボタン文言の最適化
リンクは「読者が次に知りたいこと」が解決された直後に置くと押されやすくなります。
冒頭では要約とベネフィットの後にテキストリンクを、本文中は比較表・チェックリストの直後にボタンリンクを、結論ではFAQの一言(サイズ/配送/返品の不安解消)を添えてからリンクを置くと、心理的な引っかかりを減らせます。
文言は「名詞+動詞」で行動を具体化し、リンク先で得られる体験を明確にします(例:◯◯を詳しく見る/最安値を見る など)。
また、リンクの色・形状・位置は全記事で統一すると、常連読者が迷いません。テキストリンクは本文に馴染ませ、ボタンは1記事1回までに抑え、他のCTAと競合させないのが基本です。
計測は「クリック率→到達率→完了率」の順で、影響が大きい箇所(比較直後か結論か)から改善しましょう。
【配置の型】
- 冒頭:要約1文→テキストリンク1本→本文へ
- 中盤:比較表/チェックリスト→ボタン1つ→補足2〜3行
- 末尾:結論→FAQ1行→テキストリンクで再提示
- ベネフィット型:◯分で分かる詳細を見る/失敗しない選び方を見る
- 行動型:在庫と価格を確認する/レビュー写真をもっと見る
- 安心型:返品条件を確認して購入する/サイズ表を見て選ぶ
| 要素 | 注意点 |
|---|---|
| アンカーテキスト | 「こちら」ではなく具体語で。クリック後の体験を想像できる語に |
| ボタン配置 | 1記事1回・主目的に限定。関連記事リンクと同段に置かない |
| 余白/行間 | 上下16px以上を目安→誤タップを防ぎ離脱を抑制 |
SNS連携と再利用投稿の型
公開直後の24時間は、XとInstagramで「同じ主題・同じ語彙・1つのリンク」で再提示すると、取りこぼしが減ります。
Xは一文要約→要点箇条書き→スレッドで補足、Instagramはリール(30〜45秒で手順抜粋)・ストーリー(Q&A/投票)・フィード(図解1枚)に役割を分け、いずれもリンクは記事内の該当h3へ統一します。
投稿は朝/昼/夜で角度を変えて再投下し、保存数・プロフィール遷移・リンククリックを週次で確認。
固定ポスト(X)とハイライト(IG)には「導入記事+連載まとめ」を置き、プロフィールリンクは常に最新の関連記事または本記事に差し替えます。文言は記事タイトルと同じ悩み語を使い、クリック後の違和感をなくします。
| 時間帯 | 狙い | フォーマット例 |
|---|---|---|
| 朝 | 発見と習慣化 | X一文要約+要点2つ/IGストーリーで「今日の結論」 |
| 昼 | 再想起と比較 | Xチェックリスト画像/IGフィード図解→保存促進 |
| 夜 | 熟読と行動 | X事例スレッド/IGリール→該当h3へ1リンク |
- リンクを複数置く(クリックが分散して完了率が低下)
- 記事と異なる語彙(クリック後に期待外れ感が生まれる)
- 同文言の連投(アルゴリズムと読者双方で飽きが来る)
規約遵守とNG行為の回避

AmebaPickで安定して成果を出すには、集客設計と同じくらい「規約・法令に沿った運用」の仕組み化が重要です。まず、記事内の広告要素(AmebaPickリンク・PR表記・価格情報)と編集コンテンツを整理し、読者が誤解しない配置と表現を徹底します。
Amebaでは他社アフィリエイトの利用は“禁止”です。AmebaPick以外のアフィリエイトリンクは使用できません(例外:楽天ROOM/一部ポイント紹介リンク)。
画像やレビューは出典・撮影者・検証条件(使用頻度・環境・肌質など)を明示し、誇大な断定や最新価格の断定記載は避けます。
法令面では、薬機法(効能効果の断定不可・医薬品的な表現に注意)と景品表示法(有利誤認/優良誤認・二重価格の要件)への配慮が必須。
定期的に「表現・価格・リンク」の棚卸しを行い、更新やキャンペーン終了に合わせて文言を見直しましょう。
| 領域 | 避けたいNG | 安全な運用のコツ |
|---|---|---|
| リンク | 外部ASPと混在・クリックを誘導する過度な煽り | AmebaPickリンクのみ/1記事1リンクに集約・文脈に沿った配置 |
| 表現 | 「絶対」「完全」「副作用なし」など断定 | 条件・根拠・個人差を併記し、体験は再現条件を明示 |
| 価格 | 恒常的でない「通常価格」との比較 | 取得日を記載/公式価格へ導線/曖昧な最安表現を避ける |
- リンク・価格・PRの棚卸し→期限切れ/在庫切れを差し替え
- 薬機法/景表法レッドフラグの再点検→言い換え・条件明示
外部ASP併用禁止と表現ガイド
AmebaではAmebaPick“以外”のアフィリエイト利用自体が禁止です。併用の可否ではなく、他社ASPリンクは使用不可(投稿時エラーの対象)と理解してください。
混在は読者体験の分断や規約違反リスクにつながり、最悪の場合は記事削除やアカウント停止の可能性もあります。編集面では、広告と編集を明確に分け、PR表記(広告・アフィリエイトを示す表示)を見やすい位置に置きます。
リンクのアンカーテキストは「こちら」ではなく、クリック後に得られる体験が分かる具体語(例:サイズ表を見る/返品条件を確認)を使用。
比較記事では評価軸(価格/サイズ/用途/耐久など)を冒頭で宣言し、結論→根拠→リンクの順で配置すると誤認を防げます。
画像は出典と加工の有無を明記し、口コミ引用は範囲を限定しつつ出典を付け、体験談は条件(年齢・頻度・使用環境)を書き添えて期待値を調整します。
| 項目 | NG表現/配置 | 推奨の言い換え/配置 |
|---|---|---|
| 断定語 | 「最安値確定」「必ず痩せる」 | 「◯月◯日時点の価格」「◯◯の条件で◯人中◯人に効果感」 |
| リンク | 本文に複数ボタンを乱立 | 小結→1リンク→補足の型。関連記事と同段に置かない |
| PR表示 | スクロールしないと見えない位置 | 冒頭とリンク直前に明示(例:本記事は広告を含みます) |
- 本記事のアフィリエイトはAmebaPickのみか
- PR表記は冒頭/リンク直前で視認できるか
- 比較の評価軸と結論が対応しているか
薬機法・景表法の注意ポイント
美容・健康領域の紹介では、とくに薬機法と景品表示法に注意が必要です。薬機法では、医薬品等でない商品に医薬品的な効能効果(治療・予防・診断など)を断定的に記すことは不可。
サプリや化粧品の表現は「保湿をサポート」「肌にうるおいを与える」のように、承認範囲・一般的効能の語感に抑えます。
体験談を述べる場合も、個人差・使用条件・期間・併用の有無を明記し、誤認を防ぎます。景表法では「優良誤認(著しい性能表示)」「有利誤認(価格・割引が恒常的でないのに通常価格表示)」が論点です。
二重価格は「比較対象の実体(販売実績/期間)」が要件になるため、曖昧な通常価格と比較しないこと。No.1・日本初などの主張は根拠(調査主体・方法・期間・対象)を記事内に明示できない場合は使用を避けましょう。
| 法律/論点 | ありがちなNG | 安全な書き方 |
|---|---|---|
| 薬機法 | 「治る」「効く」「副作用なし」 | 使用条件を明記し、機能表現に限定(例:◯◯成分で肌を保湿) |
| 景表法 | 恒常的でない通常価格との比較/根拠なきNo.1 | 取得日と条件を併記/比較は仕様・機能の客観項目で |
| 表示全般 | ビフォーアフターのみで断定 | 撮影条件・期間・再現プロセスを併記/個人差を明示 |
- 効能効果の断定を避け、機能・使用感ベースに修正
- 価格・No.1等の主張に根拠の出典・日付を付与
- 体験談の条件(期間/頻度/併用)を本文に明記
報酬受け取り|ドットマネー活用

AmebaPickの成果は、承認後にドットマネー残高として付与され、管理画面から各種交換先へ手続きできます。大切なのは「失効させない運用」と「必要なタイミングに間に合う運用」です。
まずは、記事制作と同じくらい受け取り運用を仕組み化しましょう。交換先ごとに手続きフローや所要日数、手数料・本人確認の要否が異なるため、月初に残高と有効期限を確認→月中に交換→月末に最終チェック、のように固定のルーティンを作ると安心です。
交換直前にはスマホ実機でリンク先やアカウント情報を再確認し、名義・口座・ポイントIDの入力ミスを防止します。
以下の表で「何を・どこで・いつ」確認するかを可視化し、漏れなく運用してください。
| 確認項目 | 確認場所 | ポイント |
|---|---|---|
| 残高/明細 | ドットマネー管理画面 | 付与日・ステータス(承認/保留)を確認 |
| 有効期限 | 残高・明細の表示欄 | 期限切れが近い明細を優先して交換 |
| 交換先条件 | 交換先一覧/各説明ページ | 本人確認・最小交換額・手数料・処理日数の有無 |
| 名義・口座等 | プロフィール/銀行情報登録 | 名義一致・桁数・記号形式のチェック |
【運用のコツ】
- 月次の「残高・期限チェック→交換→最終確認」を固定化
- 銀行・ギフト・ポイントの3系統で予備の交換先を用意
- 交換申請後はステータスが反映されるまで履歴を保管
- 期限の近い明細から交換→期限アラートをカレンダー登録
- 名義・口座・ポイントIDの一致確認→スクリーンショット保存
- 交換先の条件変更を月初に確認→急な仕様変更へ備える
交換先一覧と有効期限の基本
ドットマネーは、銀行振込・主要デジタルギフト券・各種ポイント/電子マネーなど複数カテゴリに交換できます。
交換先は時期・キャンペーン等で入れ替わることがあるため、「交換先一覧」ページで最新のラインナップと条件(最小交換額/手数料/処理日数/本人確認の要否)を毎回必ず確認してください。
有効期限は明細や残高の表示欄で確認でき、期限管理は「明細単位」での把握が安全です。貯めてから一括交換する場合でも、期限が先に来る明細が混在しやすいので、先入先出し(古い順に交換)を基本にします。
キャンペーンやレート変更はメリットが大きい一方、終了日や条件に注意が必要です。交換を急ぐと誤入力が起きやすいため、手続き前に必ず入力項目を声出し確認(口座種別/名義/ID)→スクショ保存まで行いましょう。
【交換先カテゴリ(例)】
- 銀行振込(現金化)
- 主要EC等のデジタルギフト券
- 国内主要ポイント/電子マネー系
【有効期限の管理手順】
- 管理画面で「明細の期限」を確認→期限が近い順に並べ替え
- 先入先出しで交換→交換後は履歴とスクショを1か所に保管
- 月初に期限アラートを設定→月中で交換→月末に未処理ゼロを確認
- 交換先ごとに最小交換額・手数料・処理日数が異なる
- キャンペーンの適用条件(対象期間・対象交換先)を必ず確認
- 期限表記は明細と残高で表示形式が異なる場合がある
振込スケジュールと管理方法
振込や交換の処理日数は交換先によって差があります。必要な資金の入金タイミングに間に合うよう、「いつ・どこへ・いくら」交換するかを月初に決め、期日から逆算して申請しましょう。
スプレッドシートやタスク管理に「残高/期限/交換先/申請日/処理予定/完了」を列で持ち、毎週更新すると抜け漏れが防げます。
本人確認が必要な交換先は、初回のみ審査に時間がかかる場合があるため、早めに手続きしておくと安心です。交換完了後は、受取口座の入金確認・ギフト残高/ポイント反映の確認までをワンセットにして記録します。
| タスク | 頻度/タイミング | 管理のコツ |
|---|---|---|
| 残高・期限チェック | 月初+週次 | 期限順に並べ、古い明細から処理 |
| 交換申請 | 月中(余裕を持って) | 必要情報をテンプレ化→誤入力防止 |
| 入金/付与確認 | 申請後〜反映まで | 履歴とスクショを保存→差異はサポートへ |
【運用テンプレ(置き換えて使用)】
- 月初:明細期限を確認→期限が近い順に交換先を決定
- 月中:交換申請→処理予定日をメモ→受取確認
- 月末:未処理ゼロを確認→翌月の目標残高を設定
- 同名義・同口座で統一→名義不一致の差し戻しを防止
- 申請前に通信環境を安定化→重複申請を回避
- 反映遅延があれば履歴・スクショを添えて問い合わせ
まとめ
本記事では、AmebaPickの仕組み→審査→商品選定→導線設計→規約→報酬受取を一連で整理しました。
まずはプロフィール整備と審査準備→1テーマ1商品でレビュー作成→リンクは1つに統一→SNSで再利用。ドットマネーの期限も忘れず管理しましょう。