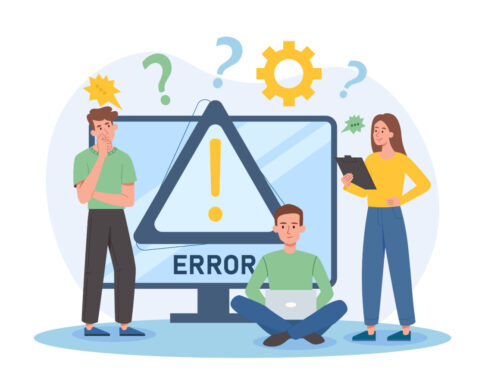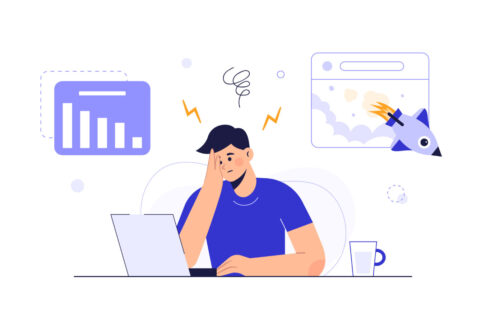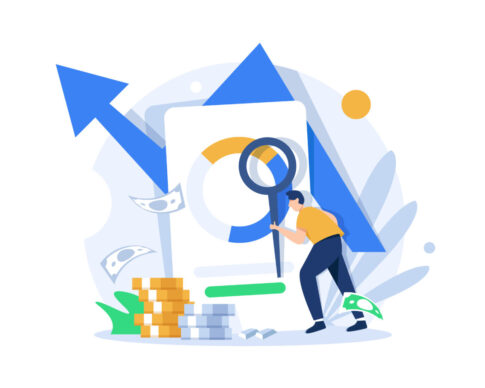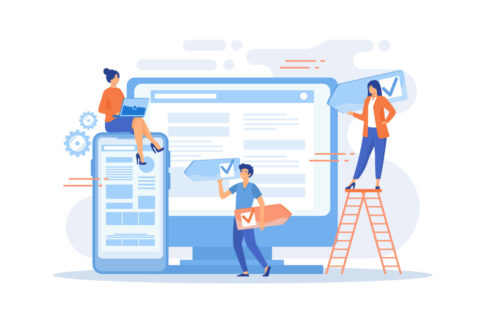アメブロのアクセス数は「記事別」で見ると原因と改善点が明確になります。本記事は、指標の意味、期間比較、タイトルと導線の見直し、リライト優先度、流入別分析までを12チェックで整理。初心者でも迷わず実践できる手順で、PVの伸び悩みを最短で解消します。
目次
記事別アクセスの基礎

アメブロの成果を見るときは、まず「記事別」で数字を切り分けるのが近道です。全体PVだけでは、どの見出し・どの導線・どのテーマが読まれているかが分かりにくいためです。
記事別の画面では、各記事の閲覧数(アクセス数)の推移を同じ土俵で比べられ、公開直後の初速と数日後の伸び方、再訪で読まれ続ける“息の長さ”まで把握できます。
重要なのは、同じ記事でも更新当日の速報値と翌日以降の確定値で差が出ること、アプリ閲覧とブラウザ閲覧で体感が異なること、内部(アメブロ内)と外部(検索・SNSなど)で読まれ方が変わることです。
これらを踏まえ、記事の役割(入門/比較/体験談など)を決めてから評価すると、単なるPV競争にならず改善点が見つかります。
下表の観点を“基礎の型”として固定しておくと、毎週の点検が楽になります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 見る単位 | 記事別の閲覧数・公開後の日数・直近/過去の比較をそろえる |
| 数字の性質 | 速報→確定で微差が出る前提。内部/外部・アプリ/ブラウザの差も把握 |
| 記事の役割 | 入門・比較・体験談・お知らせなど役割を先に定義して評価 |
主要指標の意味と定義の把握
指標の意味をそろえると、議論がぶれません。記事別アクセスでは、①閲覧数(その記事が開かれた回数)②公開から◯日間の合計(初速を見る)③直近◯日の移動平均(短期の傾向)④上位記事との乖離(相対評価)という4つの軸で見ると判断が速くなります。
加えて、内部リンク経由の閲覧と外部流入の閲覧は役割が異なります。内部で伸びる記事は回遊の“ハブ”、外部で伸びる記事は“入口”として機能します。数値は「同曜日比較」「公開後同日比較(公開1日目どうし)」のように基準をそろえて確認します。
タイトル・アイキャッチ・冒頭本文を変更した場合は、変更日をメモし前後の差分で効果を見ます。以下のポイントを押さえると、数字の解釈ミスを減らせます。
- 閲覧数は“記事ごとの読まれ方”を示す→全体PVとは分けて評価
- 初速(公開後◯日)と継続(30日/90日)で役割を分けて把握
- 内部と外部の比率を確認→ハブ記事か入口記事かを判定
- 比較は同条件で実施→同曜日・公開後同日・同カテゴリで整合
- 編集や画像差替の実施日を記録→前後の差分で効果を判断
集計期間と比較軸の決め方
期間と比較軸が曖昧だと、改善が空振りします。公開直後の効果を見たいときは「公開当日〜3日間」をひとまとまりに、検索から評価されるかを見るときは「30日〜90日」を基準にします。
季節要因や曜日差の影響を避けるため、同曜日比較(例:先週火曜の同時間帯)や、公開後同日比較(公開2日目どうし)を使います。
テーマや記事タイプが違うものを横並びにしないのも大切です。入門ガイドと体験談、お知らせと比較記事は役割が違うため、同じ“仲間内”で比べます。
計測ログは週次で固定のフォーマットに書き出し、増減の理由を一言メモに残すと、次の手当てが明確になります。
| 比較軸 | ねらい | 使いどころ |
|---|---|---|
| 公開後同日 | 初速の純粋比較 | タイトル/冒頭/サムネ変更の効果検証 |
| 同曜日同時間 | 曜日・時間帯の偏り除去 | 夜間/朝など時間帯戦略の是非判断 |
| 30〜90日 | 検索・外部からの定着 | 長期で読まれる記事の発見と強化 |
記事タイプ別の違いのチェック
同じPVでも、記事タイプで「効き方」は変わります。入門・用語集は検索からの入口になりやすく、比較・おすすめは内部回遊を増やし、体験談は滞在と信頼を高め、告知系は短期間での到達が重要です。タイプによって評価指標を変えることで、誤ったリライトを防げます。
たとえば、入門は30日後の外部流入を重視、比較は記事末の内部リンククリック、体験談はスクロール深度や後続の記事到達、告知は公開当日の到達率とクリック、という具合です。
以下のチェックをひな形に、記事を“役割で採点”すると、次の一手が明確になります。
- 入門・用語集→30〜90日の外部流入・検索での継続
- 比較・おすすめ→記事末の内部リンク到達・回遊の増加
- 体験談→滞在時間・スクロール深度・関連記事への遷移
- 告知・お知らせ→当日の到達率・クリック率・既読率
可視化と原因特定の戦略

記事別の数字を“見える化→原因仮説→是正”の流れで回すと、改善が速く進みます。まずは同期間・同条件で数字をそろえ、上位・下位の記事を並べて差分を観察します。
つぎに、タイトルと検索意図の一致、本文の読み始め(冒頭文)での離脱、記事内の導線(内部リンクやボタン)の到達を順に点検します。
最後に、仮説に紐づく修正(タイトルの言い換え、冒頭の要約追記、リンク位置の再配置)を実施し、変更日を記録して前後比較で効果を判断します。
ここで重要なのは、単発のPVに一喜一憂せず、同曜日・公開後同日・30〜90日の視点を切り替えて“育つ記事”を見極める姿勢です。以下の手順を定型化すると、毎週の確認が短時間で終わり、次の一手が迷いません。
- 同条件で抽出→上位/下位の差分を観察(期間・曜日を統一)
- タイトルと意図の一致→クエリ想定と見出しの整合を確認
- 冒頭文とサムネ→読み始めの離脱兆候を点検
- 導線の到達→本文中/末の内部リンク到達を確認
- 修正→記録→前後比較→再配信の順で検証
タイトルと検索意図の一致チェック
検索は「知りたい(Know)」「比べたい(Compare)」「申し込みたい(Do)」の三段階に分けて考えると整います。タイトルが意図とズレていると、クリック後の期待落差で離脱が増えます。
たとえば“Know”の問いに“Do”を強要する文言(今すぐ◯◯)を乗せると読み始めで離脱しやすく、“Compare”の比較軸が曖昧だと滞在が伸びません。
タイトルは“主要キーワード+読者が得たい結果”を基本形にし、h2・h3見出しと同じ語彙を使って整合させます。迷ったら、検索しそうな一文を仮で書き、その質問に“正面から答える”言い換えをタイトルへ反映します。記事末の結論とタイトルの約束が一致しているかも重要です。
下表を使って、記事タイプごとの調整ポイントを確認しましょう。
| 意図 | タイトルの調整ポイント | 見出し・本文での確認 |
|---|---|---|
| Know(知りたい) | 「とは/基本/仕組み」など理解語を入れる。煽りや断定を避ける | 冒頭で結論→要点→詳細の順。用語の定義を最初に明記 |
| Compare(比べたい) | 比較軸(価格/機能/対象)を明示。数字や表を予告 | h3で比較軸を列挙→表で並べる→用途別の向き不向きを整理 |
| Do(申し込みたい) | 「手順/始め方/注意点」を併記。過度なCTAは控えめに | 手順は見出しで段階化。注意点とFAQを同ページに置く |
タイトル変更は効果が出るまでラグがある場合があります。変更日を記録し、公開後同日比較(例:変更前/後の2日目どうし)で公平に評価しましょう。
内部リンクと導線の改善基準
導線の目的は「次に読むべき1本へ、迷わず誘導する」ことです。記事の役割(入口/ハブ/成約前)に応じて、本文中・中盤・記事末の3地点にリンクを配置し、同一リンクの過剰な重複は避けます。
アンカーテキストは「名詞+効果」(例:◯◯の始め方|3つのコツ)の形にしてクリックの意図を明確化。関連記事だけでなく、カテゴリー上位や“まとめ記事”へも橋をかけると、回遊が安定します。
スマホではファーストビュー直下に1リンクを置き、長文の場合は中盤に“要点ボックス→関連リンク”の流れを作ると離脱を抑えられます。以下の要点を守ると、導線改修の優先順位が決まります。
- 3地点配置→本文冒頭/中盤/記事末に1本ずつ、役割に合わせて出し分け
- アンカーは具体化→「名詞+効果」でクリック後の期待値を一致
- “横”と“上”の導線→関連記事(横)とまとめ/カテゴリ(上)を両立
- 重複を避ける→同一リンクの連打は1ページ2回までを目安に調整
- 計測前提→変更日を記録し、到達率の前後比較で効果を判断
冒頭文とサムネの離脱防止の注意点
冒頭文とサムネは“第一印象”を左右する最重要ポイントです。冒頭は「結論→読む価値→概要」の順で3〜5行にまとめ、専門語は言い換えます。
サムネは記事テーマが一目で分かる言葉を短く入れ、本文のトーンと統一。人物やアイコンの向き・余白・コントラストが弱いと、一覧で埋もれがちです。
読み始めの段落に“空行+小見出し”を置くと視線が流れやすく、回遊リンクはスクロール後の“最初の折り返し”付近に入れるとクリック率が安定します。
- 冒頭=結論→読む価値→概要の順。専門語は言い換え
- サムネ=短い訴求+高コントラスト。本文のトーンと統一
- 一覧での可読性→余白と文字サイズ。過剰な装飾は避ける
- 折り返し地点に関連リンク→読み始め直後の離脱を抑制
サムネと冒頭は“ペア”で改善します。タイトルだけを差し替えても効果が薄いことが多いため、同日にセットで更新し、公開後同日比較で短期の初速、30日比較で中期の伸びを確認しましょう。
伸びる記事の改善と運用

「伸ばす=偶然のヒットを量産する仕組み化」です。上位記事の“何が効いたか”を要素に分解し、同じ型を他記事へ移植します。
具体的には、タイトルと言い回し、冒頭3〜5行の要約、見出し語と検索意図の一致、本文中の内部リンク位置、図表や箇条書きの有無、更新日・追記履歴の明示などを共通テンプレにします。
さらに、役割(入口/ハブ/告知)ごとに評価軸を分け、入口は外部流入と30〜90日の継続、ハブは記事末の内部リンク到達、告知は当日の到達率を重視します。
運用では、上位10本の“型”を毎月棚卸しし、下位〜中位へ横展開。微修正→再配信→前後比較→残す/戻すを素早く回すと、安定した底上げが可能です。
| 改善対象 | 狙い・測り方 |
|---|---|
| タイトル/冒頭 | 検索意図との一致で初速改善。公開後同日比較でクリック/到達を確認 |
| 見出し/本文構成 | 「結論→根拠→事例→次行動」へ整流化。スクロール深度・到達率を計測 |
| 内部リンク | ハブ化で回遊増。本文中/末の到達率を前後比較 |
| 図表・箇条書き | 理解負荷の軽減。滞在・離脱の変化で効果を確認 |
| 更新・再配信 | 新鮮度シグナルの付与。更新日明示と再配信後の初速を確認 |
上位記事の共通点と要素の把握
上位記事は“偶然に強い”のではなく、要素がそろっています。まず、タイトルは主要キーワード+読者の目的語(例:見方/比較/始め方)が入り、クリック後の冒頭で約束をすぐ果たします。
見出しは検索意図に沿って段階化され、本文の結論→根拠→具体例→次の行動の流れが崩れていません。
本文中に1回、記事末に1回の内部リンクが置かれ、関連やまとめ記事へ自然に誘導。図や表、短い箇条書きが適所に入り、スクロールの“息継ぎ”を作っています。
さらに、更新日・追記履歴が明示され、情報鮮度への不安を減らしています。これらをチェックリスト化し、上位10本で共通する“型”を抽出して他記事へ横展開します。
- タイトル=主要KW+目的語→冒頭で約束を即回収
- 見出し=意図順(知る→比べる→行動)で段階化
- 内部リンク=本文中1/末1→次に読む1本へ確実に誘導
- 図表・箇条書き=理解負荷を軽減し離脱を抑制
- 更新日・追記履歴=鮮度の明示で信頼を担保
リライト優先度の判定基準
リライトは「伸びしろの大きい順」に着手します。高PVの微減より、中位圏(掲載順位や内部到達が惜しい)を押し上げるほうが全体効率は高くなります。
具体的には、①公開後30〜90日で外部流入が鈍化した入口記事、②記事末の内部リンク到達が低いハブ候補、③タイトルクリックは高いが冒頭到達が低い“期待落差”記事、④検索需要の季節ピークに近いテーマ、を優先します。
作業は“軽→中→重”の三層に分け、軽は見出し・冒頭・内部リンク差替、中は章構成と図表追加、重はテーマ再定義まで踏み込みます。判定は毎週の一覧で行い、担当と期限をセットにして滞留を防ぎます。
- 中位圏の押上げ>下位の新規作成>上位の維持(影響度順)
- 入口:30〜90日の外部流入が鈍化→タイトル/冒頭/FAQ追記
- ハブ:記事末到達が低い→本文中リンク追加・アンカー具体化
- 期待落差:クリック高・到達低→冒頭3〜5行の要約を再設計
更新タイミングと再配信の運用
更新は“いつ何を直すか”を決めてから行います。まず、曜日・時間帯の傾向に合わせ、初速を取りやすい枠(例:読者が多い時間帯)で軽リライトを実施。
見出し・冒頭・内部リンクの3点セットを同日に更新し、公開後同日比較で初速を評価します。検索の定着を狙う中〜重リライトは、月1回の棚卸しでテーマの穴や競合差分を補強。
再配信は、更新直後/季節の需要期/関連記事公開とセット、の3パターンで回し、プロフィールや固定記事、SNSでも同一の訴求を短く繰り返します。再配信のたびに“どの導線から来たか”を記録し、効果の高い導線へ資源を寄せます。
- 軽リライト(週次)→見出し/冒頭/内部リンクを同日更新
- 中〜重リライト(月次)→章構成・図表・事例を追加
- 再配信(更新直後/需要期/関連公開時)→導線別の効果を記録
- 評価→公開後同日・同曜日・30〜90日で三段階チェック
更新と再配信は“セット運用”が基本です。直したら必ず露出を作り、数字は前後比較で判定。効果が出た型はテンプレに昇格し、次の候補へ横展開していきます。
流入と読者行動の分析

記事別の数字を深掘りする際は、「どこから来たか(リンク元)」「どの端末で読まれたか(デバイス)」「いつ読まれたか(時間帯・曜日)」「誰が読んだかの傾向(新規/常連)」の4軸で切り分けると、原因と打ち手が具体化します。
同じPVでも、検索流入は“入口記事の強化”が効き、アメブロ内流入は“内部リンクの再設計”、SNS流入は“サムネ・冒頭の改善”が効きやすいなど、対処が変わるためです。
さらに、スマホ中心かPC比率が高いかで、見出しの長さ・表の可読性・ボタン位置の最適解も変化します。最後に、新規と常連の比率を追うと、集客と再訪のバランスが見えます。
下表を分析メモの“ひな形”にして、毎週同じ型で記録すると改善が進みます。
| 分析軸 | 見る目的 | 主な打ち手 |
|---|---|---|
| リンク元 | 入口/ハブの役割判定 | 検索=タイトル・FAQ追記/内=内部リンク/SNS=冒頭・サムネ |
| デバイス | 表示最適化と離脱抑制 | スマホ=見出し短縮・ボタン大型化/PC=表・図で深掘り |
| 時間帯・曜日 | 初速と再配信の最適化 | 同曜日比較で掲載枠を決定/反応の薄い時間は再配信で補強 |
| 新規/常連 | 集客と再訪の比率調整 | 新規=入口強化/常連=連載・関連記事の導線強化 |
リンク元とデバイス別の比較
まず、記事別の数字をリンク元(アメブロ内・検索・SNS・外部サイトなど)で区分し、各ルートの役割を決めます。
検索が多い記事は“入口”としてタイトル・見出し語の整合とFAQ追記が効きやすく、アメブロ内からの比率が高い記事は“ハブ”として本文中と記事末の内部リンク位置を再設計すると回遊が伸びます。
SNS流入が多い記事は、一覧での可読性(サムネ文字のコントラスト・短い訴求)と冒頭3〜5行の約束回収が鍵です。
次に、デバイス別(スマホ・PC・アプリなど)の到達率を比較します。スマホ優位なら段落短め・見出しは20字前後・ボタンは親指で押しやすい位置に。
PC比率が高いなら、表・図・箇条書きで深い説明を加えます。異常値(急な増減)は、当日の再配信・外部からの紹介・画像差し替え・内部リンク変更など“出来事”と照合して原因仮説を立てましょう。
- 検索比率↑=入口強化:タイトル言い換え/FAQ追記/結論を冒頭へ
- 内リンク比率↑=ハブ強化:本文中1・末1の導線/アンカーは具体化
- SNS比率↑=第一印象強化:サムネの短い訴求+冒頭で約束を即回収
- スマホ優位=可読性最優先:見出し短縮・余白・ボタン固定で離脱抑制
- PC比率↑=深掘り重視:表・図を追加し“保存したくなる”情報量に
時間帯と曜日の傾向の把握
時間帯・曜日の傾向は、初速を左右します。まず、同曜日比較(例:先週火曜の同時間帯)で“いつ露出させると読まれるか”を見極めます。
朝は通勤前後のスマホ閲覧、昼は休憩中の流し読み、夜は腰を据えた閲覧になりやすく、記事タイプごとに相性が異なります。
公式の提供画面で日別の動きを確認し、可能なら時間帯の傾向を見られる画面(例:スマホで利用できる場合など)も併用して、投稿・再配信の枠を決めます。
時間帯別の詳細が得られない環境では、投稿時刻を2〜3パターンに分けてテストし、公開後同日比較で初速を評価すると確実です。
季節・イベント・競合の更新が重なるとブレるため、1回の結果に引きずられず“数週間単位”で判断します。
- 同曜日・同時間で比較→季節要因や偏りを除去
- タイプ別に最適枠→入門は朝夕/体験談は夜など仮説を検証
- 時間帯データが乏しい時→時刻テスト→公開後同日比較で評価
- 再配信の固定枠→数字が良い時間に“型”として定着
新規読者と常連読者の違いのチェック
新規と常連の比率が分かると、集客と再訪のバランス調整ができます。新規は“入口強化”が効き、タイトル・冒頭・FAQ・用語解説が刺さります。
常連は“次の一歩”が重要で、連載・事例・深掘り記事への導線、プロフィールや固定記事からのシリーズ一覧が効きます。
簡易的な判定でも、初見が多い記事は検索・外部比率が高く、滞在は短め、スクロールは浅くなりがち。
常連が多い記事は内部からの到達が高く、記事末リンクの到達率が高くなります。以下の手順で“違い”を可視化し、打ち手を分けましょう。
- 入口判定:リンク元比率で新規寄り(検索・外部)/常連寄り(内)を分類
- 行動差の確認:滞在・スクロール・記事末到達で深さを比較
- 新規向け改善:タイトルの言い換え/冒頭の要約/FAQ・用語の追記
- 常連向け改善:連載リンク/まとめ記事/関連記事ブロックを強化
- 再評価:公開後同日・同曜日・30〜90日の三段階で効果を確認
新規比率が高いのに再訪が伸びない場合は、記事末の導線を“1本に絞る”だけでも到達が改善します。
常連比率が高いのに伸び悩む場合は、入口記事に戻ってキーワードとタイトルの整合から整え直しましょう。
まとめ
まず「指標の定義→期間比較→タイトル/導線→上位共通点→リライト→流入別差」の順で点検し、毎週同じ基準で更新します。
実践は①記事別トップ10を抽出②見出し・冒頭を微修正③内部リンクを3本追加④翌週の変化を確認。小さな改善の積み重ねが、安定したアクセス増につながります。