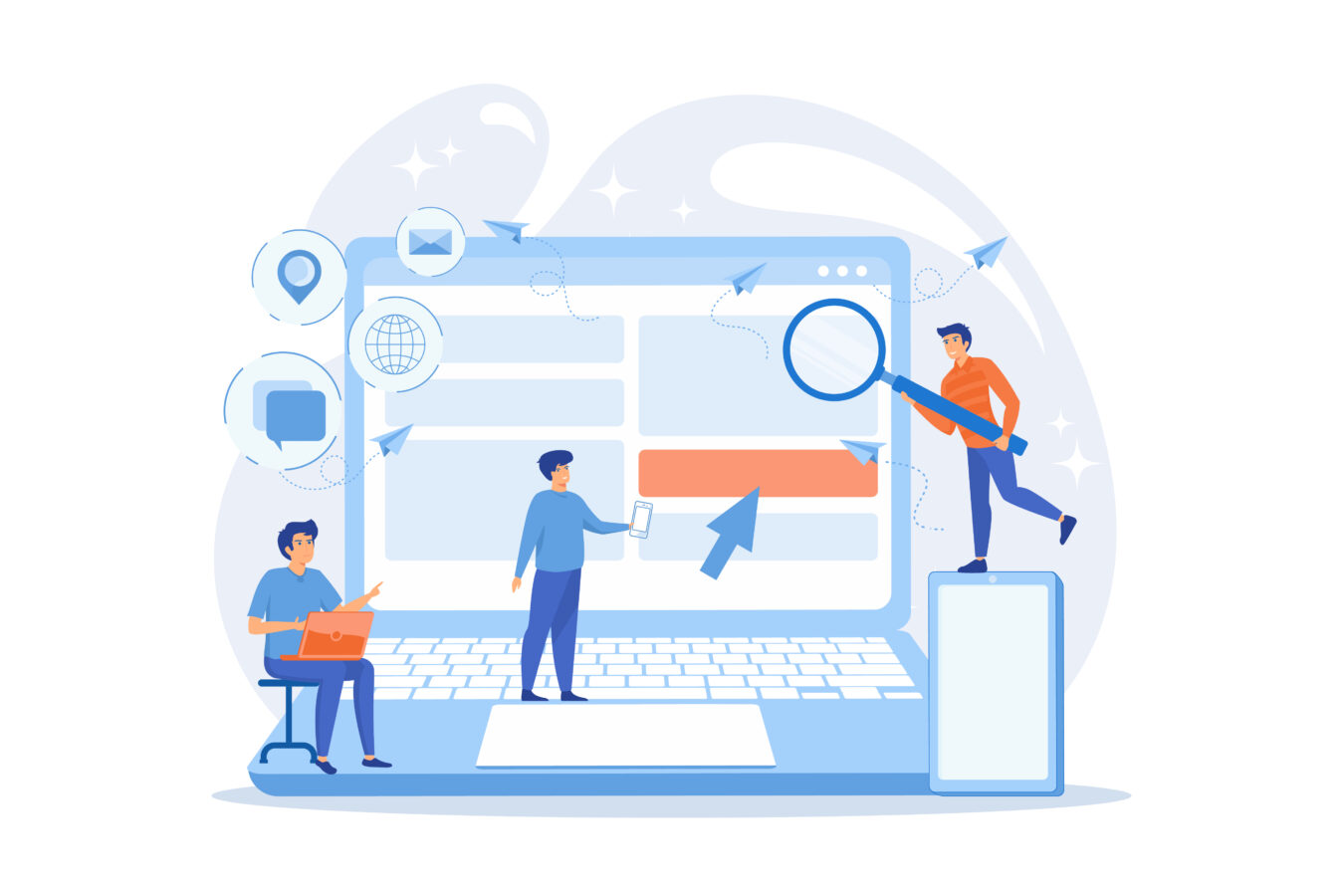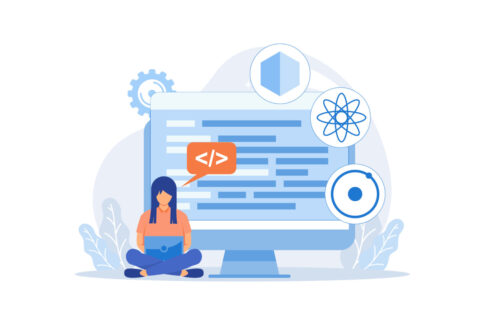「集客を丸投げしたいけど、本当に任せて大丈夫?」——本記事では、丸投げの範囲と責任分担、費用相場と契約形態、業者選びの基準、進め方とKPI運用、禁止行為とリスク管理を実務目線で整理。
任せる部分と社内で握る部分を明確化し、ムダ費用やトラブルを避けながら成果につなげる判断軸を提供します。
目次
丸投げの範囲と責任分担

「集客を丸投げ」は、外部に任せる“作業”と自社で握る“意思決定・資産管理”を分けて設計すると安全です。
まず、任せられる領域を洗い出します。例として、広告運用・クリエイティブ制作・記事制作・LP改善・計測設定・レポート作成などは委託可能です。
一方で、事業目標・KPI・予算配分の最終決定、ブランド方針、アカウント権限や請求情報の管理は社内が保持します。
次に、責任の所在をRACI(Responsible/Accountable/Consulted/Informed)で文章化し、タスクごとに誰が実務を担い、誰が最終責任を負い、誰に相談・共有するかを明確にします。
これを契約書と運用設計書(スコープ表・KPI表・権限一覧)に落とし込むと、期待の齟齬や「やっているつもり」の空回りを避けられます。
最後に、成果の判定基準(例:CVR・CPA・ROAS・自然検索CVなど)とレポート頻度・定例の目的を揃え、週次で“数字→原因→次の打ち手”を決める流れを固定化します。
- 委託=実務中心、社内=方針・最終判断・資産管理を保持
- RACIで役割を文書化→契約と運用設計書に反映
- 評価指標・頻度・承認フローを事前合意→運用の迷いを排除
| 領域 | 丸投げしやすい業務 | 社内で保持すべき項目 |
|---|---|---|
| 広告 | 入札・配信設計・クリエイティブ差し替え・日次最適化 | 月次予算上限・KPI閾値・請求/決済権限 |
| SEO/コンテンツ | 構成案・記事制作・内部リンク整備・リライト | ブランド表現・NGワード・最終公開権限 |
| 計測/レポート | タグ実装・イベント設定・週次レポート作成 | 指標定義・アカウント所有権・データ共有範囲 |
対応業務の例とRACI整理
RACIは「誰が手を動かすか(R)」「誰が最終責任か(A)」「誰に相談するか(C)」「誰へ共有するか(I)」を一行で示せる実務ツールです。
丸投げの誤解を避けるため、主要タスクごとにRACIを事前に確定します。例えば「ショッピング広告のフィード修正」は、代理店がR、事業責任者がA、在庫担当がC、経理とCSがIという具合です。
「LPのABテスト」なら、代理店がR、マーケ責任者がA、デザイナー/開発がC、営業/CSがIです。
承認が滞りやすいタスク(タグ実装・フォーム変更・価格表記)にはSLA(承認期限)を設け、遅延時の暫定措置も決めておくと運用が止まりません。RACIは一度作って終わりではなく、四半期ごとに見直し、担当変更や体制変更を反映します。
- タスクは“成果物ベース”で定義→「LP第1ビュー文言差し替え」など具体化
- Aは必ず1名→責任の所在を曖昧にしない
- SLAと代替フローを明記→承認遅延でも前進できる運用へ
| タスク | R(実行)/A(最終) | C(相談)/I(共有) |
|---|---|---|
| フィード修正 | R:代理店|A:事業責任者 | C:在庫・MD|I:経理・CS |
| LP ABテスト | R:代理店|A:マーケ責任者 | C:デザイン・開発|I:営業 |
| タグ/イベント | R:代理店|A:データ責任者 | C:開発・法務|I:全関係者 |
- 【よくある失敗】「誰が最終承認か不明」→Aを複数にしない
- 【手順の型】タスク定義→RACI割当→SLA設定→承認経路→成果物格納先→振り返り
社内体制と窓口の一本化
丸投げで成果を出すには、社内の“受け皿”を作ることが不可欠です。窓口(オーナー)を1名に定め、承認・優先順位付け・他部署調整をその人に集約します。
オーナーは、週次の定例で「数字→洞察→次アクション」を即決し、SLAに沿って承認します。問い合わせや依頼はチケットで一元管理し、経緯と決定事項を残します。
アカウント権限は“原則自社所有”で、代理店は運用権限に限定します。請求やドメイン、計測ツールの所有権が外部にあると、解約時に資産ごと失うリスクがあります。
情報共有は、ダッシュボードの共通化(定義と算出式を明記)と、週次のレポートテンプレで標準化します。
法務・情報セキュリティ・経理とは、データ共有範囲と秘密保持、個人情報の取扱いを事前に合意しておくと、スピードとコンプライアンスを両立できます。
- 窓口が複数→承認が二転三転し施策が遅延
- 権限を外部に移譲→解約時に資産が回収できない
- 数値定義が部署ごとにバラバラ→議論が噛み合わない
| 領域 | 一本化のポイント | 実装のヒント |
|---|---|---|
| 承認 | オーナー1名に集約→SLAで期限管理 | チケット運用・優先度タグ・週次レビュー |
| 権限 | 自社所有を原則→外部は運用権のみ | アカウント台帳・権限一覧・定期棚卸し |
| 可視化 | 定義統一ダッシュボード | 用語集・算出式をヘッダーに記載→解釈のズレを防止 |
- 【初期セット】窓口任命→権限棚卸し→RACI/スコープ表→定例アジェンダ→ダッシュボード共有
- 【運用の型】週次:実績/学び/次の一手→月次:方針・予算見直し→四半期:RACI更新
費用相場と契約形態

集客を外部へ委託するときの費用は、契約形態と業務範囲で大きく変わります。一般的には、戦略設計や体制整備などの初期費用と、運用・改善を行う月額費用の二本立てです。
加えて、広告費や制作物(LP・バナー・記事)にかかる実費は月額とは別に発生します。
契約形態は、固定報酬(リテーナー)、成果報酬、ハイブリッド(固定+成果)のいずれかが中心で、固定は計画性が高く品質を維持しやすい、成果報酬は短期の費用対効果を測りやすいがスコープが狭くなりがち、ハイブリッドは双方のバランスを取りやすい、という特徴があります。
いずれの場合も、対応業務の範囲(戦略・広告運用・SEO・計測・制作・レポート)と、成果指標(CV・CVR・CPA・ROASなど)の定義、承認フローを事前に文章化しておくと、見積の比較と運用の安定に直結します。
- 月額=人月×難易度×範囲、広告費・制作費は別建てで可視化
- 契約形態は固定・成果・ハイブリッドを比較→自社の目的と整合
- スコープ表・KPI表・承認フローを見積段階で明文化
| 契約形態 | 向いているケース | 注意点 |
|---|---|---|
| 固定報酬 | 継続改善・複合施策(SEO×広告×制作) | 成果の線引きをKPIで合意/稼働の見える化を定例で担保 |
| 成果報酬 | 短期KPIが明確(資料DL・新規購入など) | 指標の定義と計測方法を厳密化/スコープが狭くなりやすい |
| ハイブリッド | 基盤運用+成果インセンティブを両立 | 固定:成果の配分比率を明記/重複成果の扱いを規定 |
月額・初期費用の目安整理
初期費用は、現状診断・KPI設計・計測環境整備・基盤制作(テンプレLPやレポート基盤)に充てられることが多いです。
規模が小さく範囲が限定的な場合は小さめ、チャネル横断で土台から整える場合は中〜大きめになります。
月額費用は、担当者の稼働(人月)と、扱うチャネル数・改善サイクルの速度で決まります。たとえば、広告のみの運用と、SEO・広告・制作・計測を横断する運用では必要な体制が異なり、費用にも差が出ます。
広告費や制作物(記事・LP・バナー)は別枠で見積り、月次の実費と運用費を分けて管理すると、費用対効果の評価が明確になります。
重要なのは絶対額よりも「何にどれだけ投下し、どの指標をどれだけ動かすのか」を可視化することです。初期は小さく始め、学びが得られた領域に配分を寄せると、無駄を抑えながら伸ばせます。
- 初期:診断・KPI・タグ設計・LPテンプレ→最短で運用開始
- 月額:運用・改善・定例・レポート→学びを次月に反映
- 別枠:広告費・制作費→実費として透明化
| 費用区分 | 主な内容と見積りの見方 |
|---|---|
| 初期費用 | 現状診断、KPI・ダッシュボード設計、タグ・イベント整備、LP/広告テンプレ作成 |
| 月額費用 | 運用(入札・配信・SEOリライト)、ABテスト、週次定例、月次レポート |
| 実費(別枠) | 媒体広告費、記事/LP/バナー制作費、ツール利用料(計測・分析) |
- 見積比較のコツ:同じスコープ・同じKPIで横並び比較→範囲差による見かけの安さに注意
- 運用開始後:週次で学び→翌月の配分を調整→費用対効果を継続改善
固定報酬と成果報酬の違い
固定報酬は、毎月の稼働と品質を安定させやすく、複数チャネルを横断して基盤を整えたい場合に向きます。
優先順位の付け替えや、施策の前倒し・後倒しといった柔軟な運用がしやすい点も利点です。一方で、成果へのインセンティブを明確にしたい場合は、成果報酬またはハイブリッドが検討候補になります。
成果報酬では、対象指標(新規購入、資料DL、見積依頼など)とカウント方法、重複やキャンセルの扱い、帰属期間(何日以内を成果とみなすか)を明記します。
検索意図が薄い流入や、外部要因で変動しやすい指標のみで設計すると、短期的な獲得に偏りやすく、ブランドやLTVに寄与する施策が後回しになるリスクがあります。
ハイブリッドは、基盤運用を固定で担保しつつ、成果に応じて追加報酬を支払う方式で、双方のバランスを取りやすい選択肢です。
どの形でも、KPI定義と計測ルール、運用での優先順位を契約に落とし込むことが、後のトラブル防止につながります。
- 指標の定義が曖昧→重複/キャンセルの扱いで認識差が発生
- 成果偏重→長期的な資産施策(SEO・改善基盤)が後回しに
- 帰属期間の未定義→SNS・指名検索などの寄与が見えない
| 方式 | メリット | デメリット/対策 |
|---|---|---|
| 固定報酬 | 計画性・品質担保・横断運用に強い | 短期成果の緊張感が薄れやすい→四半期のKPIレビューで是正 |
| 成果報酬 | 費用対効果を把握しやすい | スコープが狭くなりがち→測定対象外の施策は別枠で合意 |
| ハイブリッド | 基盤と成果の両立・柔軟 | 配分ルールが複雑→算式と事例を契約に明記 |
- 合意の型:KPI定義→計測仕様→帰属期間→重複/キャンセル→レポート方法→支払条件を契約付帯に記載
- 運用の型:月次でKPI/費用をレビュー→四半期で方式や配分を再評価
業者選びの基準と確認

業者選びで重要なのは「成果に直結する評価軸」を事前に定義し、客観的な材料で比較することです。
まず、提供範囲(広告運用・SEO・制作・計測・CRM連携など)と、自社の目的(新規獲得強化か、購入率向上か、LTV最大化か)を突き合わせます。
次に、実績・事例・体制・運用プロセス・計測の設計力・コンプライアンスの6点を基準化し、一次情報で確認します。
提案書の“良さそう”な表現より、実運用の仕組み(週次の意思決定、ABテストの設問設計、ダッシュボード定義、権限管理、データ保全)まで明文化されているかが肝心です。
見積はスコープ(やること)とアウトカム(どう数値が動く想定か)の両方で比較し、稼働時間の多寡だけで判断しないことがポイントです。
打合せでは、過去案件の失敗例とリカバリー手順、承認が滞った際の代替案、計測不整合時の切り分け手順まで具体的に聞くと、現場対応力が見極めやすくなります。
- 実績(再現性)
- 事例(前後の数値と期間)
- 体制(専任・代替・SLA)
- プロセス(週次運用・ABテスト)
- 計測(定義・タグ運用・ダッシュボード)
- 法務・情報管理(NDA・個人情報・権限)
| 観点 | 確認ポイント | 判断のヒント |
|---|---|---|
| 目的整合 | 自社KPIと提案の関係が明文化 | 「何をどれだけ動かすか」を数式で提示できるか |
| 再現性 | 複数事例の“前後比較”が提示 | 業界・客単価が近い案件の学びを転用できるか |
| 体制 | 専任/バックアップ・SLA・連絡経路 | 担当交代時の引継ぎ手順が文書化されているか |
| 計測 | タグ・イベント命名・二重計測対策 | 定義表とダッシュボードの雛形があるか |
実績・事例・体制の見極め
実績の見極めでは、単なるロゴ掲載や「◯◯%改善」といった抽象表現ではなく、期間・母数・前提条件・副作用まで開示されているかを重視します。
例えば「広告CPA30%改善」の事例なら、配信前の入札/除外設計、LP側の同時改善点、季節要因の有無、予算規模、到達率やスクロールなどの中間指標の動きまで確認します。
SEOの事例では、対象KW群、内部リンクの塊化、リライトの差分、構造化やFAQ追加の影響など、具体的な施策単位の因果を問いましょう。
体制は、専任の有無、代替担当のスキル、SLA(返信・承認・リリースの期限)、緊急時の連絡経路をヒアリングし、属人化リスクを評価します。
さらに、週次定例の進め方(数字→洞察→次アクションの順)、ABテストの計画(テスト仮説→評価指標→停止条件)、ダッシュボードの定義表(指標の算出式と取得元)が用意されているかを確認すると、日々の運用品質を事前に見通せます。
- 期間・母数・前提(季節・在庫・価格)
- KPIの前後と中間指標の推移
- “やめた施策”と学び(負けパターンの開示)
| 領域 | 聞くべき内容 | 評価ポイント |
|---|---|---|
| 広告 | 入札/除外とLP改善の連携 | 創意工夫と標準運用のバランス |
| SEO | リライト差分・内部リンク・構造化 | 検索意図の解像度と塊化の設計力 |
| 体制 | 専任/バックアップ・SLA・緊急連絡 | 属人化回避と継続性の担保 |
- 良い業者のサイン:失敗事例や撤退判断を率直に共有→学びをテンプレ化
- 注意サイン:成果数値のみ強調→施策や前提の開示が乏しい
見積内訳とスコープ確認
見積は「稼働の内訳」と「成果に結び付く設計」の両面でチェックします。まず、スコープ(やること・やらないこと)を行単位で明確化し、例外や前提条件(ツール費・撮影費・翻訳・サーバ設定など)も列挙します。
次に、固定費と変動費(広告費・制作物)を分離し、月次でどのKPIをどれだけ動かす計画かを数値で提示してもらいます。
レポート作成や定例、ABテスト、タグ実装、デザイン/コーディング、CMS反映、検収工数など、見落としがちな部分を含めて比較すると、後からの追加費を防げます。
契約前の最終確認では、帰属(アカウント・タグ・原稿・データ)、承認フローとSLA、解約時のデータ引渡し、同時進行の他社施策との干渉ルールまで合意すると安全です。
評価は「価格の安さ」ではなく「スコープ整合×成果仮説×運用品質」で行うと、長期的な費用対効果が安定します。
- “一式”表記→後請求の温床→作業単位で分解を依頼
- 帰属の曖昧さ→解約時の資産喪失→所有権を契約に明記
- 計測未整備→成果の判定不能→タグ・定義表を初期範囲に含める
| 項目 | 確認内容 | 合意のヒント |
|---|---|---|
| スコープ | 実施/非実施・例外・前提が明確 | 作業一覧と成果物の格納先を明文化 |
| 費用 | 固定/変動・実費の区分・支払条件 | 広告費は別建て・制作は見積別紙で透明化 |
| 計測 | 指標定義・命名規則・二重計測対策 | 定義表・ダッシュボード雛形を添付 |
| 権限/帰属 | アカウント・タグ・原稿・データの所有 | 自社所有を原則・運用権のみ付与 |
- 実務の進め方:スコープ表→KPI表→権限一覧→SLA→レポート雛形の順で雛形を提示→3社で横並び比較
- 運用開始後:週次で内訳と学びを公開→翌月配分へ反映→見積前提との差分を都度更新
進め方とKPI・レポート

外部へ集客を委託する進め方は、「目標→計測→実行→振り返り→次の一手」を週次で回す仕組み化が要です。
まず、事業のKGI(売上・新規購入数・商談数など)から逆算して、チャネル別KPI(LP到達率・CVR・CPA・ROAS・自然検索CVなど)を定義します。
次に、イベント計測(スクロール・CTAクリック・フォーム開始/完了)を実装し、命名規則を統一します。権限は“自社所有・運用は外部”を原則に、アカウント台帳と承認フローを明文化します。
レポートは「数値→洞察→アクション」で1ページに集約し、異常検知(急なCVR低下・エラー増)には即応ルールを設定します。
成果判定は短期(週・月)と中期(四半期)で分け、前提差(在庫・価格・季節)も併記して誤解を防ぎます。
最後に、学びをテンプレ化して横展開(勝ちLP構成・勝ち見出し・勝ち入札戦略)すると、担当が替わっても成果が継続します。
- KGI→KPI→イベント定義を先に合意
- アカウントは自社所有→運用権のみ付与
- レポートは「数値・原因・次手」を1ページ化
| 層 | 目的 | 代表指標と実務 |
|---|---|---|
| 事業(KGI) | 売上・新規獲得の最大化 | 売上/粗利・新規購入・商談数/月次で方針を見直し |
| チャネル(KPI) | 到達・CV・効率の改善 | CVR・CPA・ROAS・自然CV/週次で配分を最適化 |
| 行動(イベント) | 詰まりの特定と解消 | スクロール・CTA・フォーム開始/完了/UIを機動修正 |
目標設定と計測・権限設計
目標設定は「誰に・何を・どれだけ・いつまでに」を数式で置くと運用が安定します。
例として、KGI「新規購入+◯◯件」をKPIに分解(自然検索CV+広告CV+SNS送客CV)し、さらに中間指標(LP到達率・フォーム開始率・カート復帰率)へ落とし込みます。
計測は、媒体タグと計測ツールの二重計測や同意管理の状態を確認し、イベント命名(evt_scroll_75、btn_lp_cta、form_start、form_submitなど)を共通化します。
権限は、所有(アカウント・ドメイン・タグ・GTM・計測ツール・広告アカウント)と運用権(編集・公開・請求)を分離し、台帳に記録します。解約や担当交代時の引継ぎ(エクスポート・権限剥奪・秘密保持)も事前に手順化します。
週次のレポートでは、KPIの到達状況に加え、前提(在庫・価格・クリエイティブ差し替え・システム変更)を記録し、振れの理由を可視化すると、意思決定のスピードが上がります。
- イベント未整備→改善ポイントが特定できない
- 所有権が外部→解約時に資産回収が困難
- 定義不一致→数値の解釈が部署でズレる
| 領域 | 設計のチェック項目 |
|---|---|
| 目標 | KGI→KPI→イベントの分解/目標値と期限/前提の明文化 |
| 計測 | タグ実装・命名規則・二重計測対策・同意管理の設定 |
| 権限 | 所有と運用の分離/台帳・SLA・引継ぎ手順の整備 |
- 実務の型:KGIとKPIを1枚に図示→イベント名と発火条件を併記→関係者で合意
- 異常時の型:検知→切り分け(媒体/LP/タグ)→暫定措置→恒久対応を時系列で記録
定例MTGと改善サイクル
定例MTGは「報告会」ではなく「意思決定の場」にします。アジェンダは固定化し、最初にKPIサマリー(計画比/前週比)を共有、次に洞察(何が効いたか・なぜか・再現性はあるか)を短く整理します。
その上で、翌週のアクション(ABテスト・入札/除外見直し・LPの文言/FAQ位置変更・記事のリライト・フィード修正)を3〜5件に絞って決めます。各アクションには仮説・期待指標・担当・期限を付与し、チケットで管理します。
月次では、学びのテンプレ化(勝ちクリエイティブ・勝ちLP構成・勝ち入札)と配分の見直し(在庫・粗利・季節要因を反映)を実施します。
四半期では、KGI達成度の評価とRACI/権限の更新、契約条件やKPIの再設計を行います。会議時間は短く、事前資料は1枚に集約すると、意思決定のスピードが落ちません。
- 数値5分→洞察10分→次の一手10分→決定事項の確認5分
- アクションは3〜5件に限定→担当・期限・期待指標を明記
- 学びはテンプレ化→別案件・別LPへ横展開
| 区分 | 目的 | アウトプット |
|---|---|---|
| 週次 | 短期最適化と素早い検証 | KPIサマリー・優先アクション・チケット更新 |
| 月次 | 学びの定着と配分調整 | 勝ちパターン集・予算/入札/在庫連携の見直し |
| 四半期 | 戦略と体制の更新 | 目標再設定・RACI/権限更新・契約/指標の再設計 |
- 会議運用のコツ:事前に「決めたいこと」を明記→議論が脱線しない
- 可視化のコツ:ダッシュボードのヘッダーに用語と算出式→解釈のズレを防止
禁止行為とリスク管理

外部に集客を委託する際は、成果を急ぐあまりに規約違反や不正確な運用が紛れ込みやすくなります。
短期の数字を追うほど、検索エンジンや広告媒体のポリシーに反する“近道”が提案される可能性があるためです。
まず重要なのは、委託範囲の中に「やってはいけないこと」を明文化し、契約と運用ドキュメントで共有することです。
検索領域では、隠しテキスト・リンクスパム・自動生成の低品質ページの量産などが典型です。広告領域では、誤認を招く表現、禁止カテゴリの訴求、トラッキング回避の実装などが該当します。
さらに、アカウントや計測ツールの“所有権”が外部に渡ると、解約時に資産を回収できないリスクが高まります。
運用を安全に進めるには、ブラック手法の線引き、契約条項での罰則と是正手順、アカウント権限の設計、データのバックアップと引渡しのルール作りをセットで行うことが有効です。
週次レポートの末尾に「遵守チェックリスト」を差し込み、逸脱の早期発見→是正までの流れを固定化すると、現場の一次防御線として機能します。
- 禁止行為を契約と運用設計書に明記→線引きを共有
- アカウントは自社所有→運用権のみ外部付与
- 遵守チェックを週次テンプレに組込み→早期発見と是正
| 領域 | 主なリスク | 予防と対策 |
|---|---|---|
| SEO | リンク購入・自作自演・隠し要素 | リンク方針の明文化・出典と監修体制・品質レビューの義務化 |
| 広告 | 誤認訴求・禁止カテゴリ・不正トラッキング | クリエイティブ審査フロー・媒体ポリシー表の共有・監査ログ |
| 計測 | 二重カウント・無断タグ・同意違反 | 命名規則の統一・台帳管理・同意管理と権限棚卸し |
ブラック手法と契約条項
ブラック手法は「短期の数値を作るために、媒体や検索エンジンのルールを逸脱する行為」です。
SEOでは、購入リンクの大量投下、生成ツールでの低品質記事の量産、無関係サイトへの過剰な寄稿、隠しテキスト・リダイレクト乱用などが典型です。
広告では、誤解を招く価格表示、比較優位の“盛り”表現、禁止カテゴリのすり抜け、リマーケティングの過配信や同意回避が問題になります。
契約段階で、これらの禁止行為を列挙し、違反時の通知→是正→損害負担の順序を条項化しておくと、グレー提案の抑止になります。
さらに、“成果”の定義を正しく整備し、虚偽や水増しを防ぐ検収ルール(データ出所・集計式・重複/キャンセルの扱い)を取り決めます。
週次の遵守チェックでは、リンク獲得経路、制作フロー、広告の審査差し戻し履歴、計測の差異ログを確認し、逸脱の兆候(急な指標ジャンプ、不自然な流入源、同一IPのレビュー集中など)を検知します。
法務・情報セキュリティとも連携し、秘密保持・個人情報取り扱い・サブ委託の再委託制限まで網をかけると安心です。
- 禁止行為の具体列挙(SEO/広告/計測)と違反時の是正・解除条項
- 成果定義・検収方法(データ出所・算式・重複/キャンセル規定)
- 再委託条件・秘密保持・個人情報・監査権限(ログ提出義務)
| 分類 | 想定される問題 | 条項/運用での対処 |
|---|---|---|
| SEO | リンク購入・低品質量産 | リンク方針と出所開示義務・品質基準と監修プロセスの明文化 |
| 広告 | 誤認表現・禁止領域 | クリエイティブ審査フロー・媒体ポリシー遵守条項・差戻し時の是正SLA |
| 数値 | 水増し・二重カウント | 計測定義表・第三者計測との照合・監査ログの保管 |
- 運用の実例:審査差戻しが連続→根本原因(表現/カテゴリ/ランディング)をテンプレに落とし込み再発防止
- 観察ポイント:流入源の急増・CTRやCVRの異常値→施策の出所と整合性を確認
アカウント権限と資産保全
資産保全の要は「所有と運用の分離」です。広告・計測・CMS・EC・解析などのアカウントは、原則として自社がオーナー権限を持ち、外部には運用権(編集・投稿・配信)だけを付与します。
権限の付与/剥奪は台帳で管理し、解約や担当交代時の即時剥奪とログ保全を手順化します。
タグ管理(GTM等)や解析ツールのプロパティ、イベント定義、ダッシュボード、LPや記事の原稿・画像・構成データは“資産”として定義し、引渡し方法(データ形式・期限・無償/有償)を契約に明記します。
バックアップは、テンプレ・計測定義・RACI・権限一覧・レポート雛形を定期エクスポートし、社内の共有ストレージに時系列保管します。
二要素認証・SSOの利用、パスワードの共有禁止、休眠権限の定期棚卸しも重要です。万一、媒体停止やタグ誤実装が起きた場合は、切替手順(代替LP・バックアップタグ・リカバリ用プロパティ)を用意しておくと、売上影響を最小化できます。
- オーナー=自社、運用=外部の原則→台帳で可視化
- 引渡し:タグ/イベント/原稿/画像/テンプレの形式と期限を契約化
- バックアップ:月次のエクスポート→共有ストレージで世代管理
| 資産 | 保全ポイント | 運用のヒント |
|---|---|---|
| アカウント | 自社オーナー・二要素・SSO | 権限棚卸し・解約時の即時剥奪 |
| 計測/タグ | 命名規則・定義表・監査ログ | バックアップコンテナ・代替計測の切替手順 |
| 制作物 | 原稿・画像・LP・テンプレの引渡し | 格納先と版管理・利用条件の明記 |
- 初期セットの型:権限一覧→アカウント台帳→計測定義→バックアップ計画→引渡し条項の確認
- 運用の型:週次で遵守チェック→月次で資産棚卸し→四半期で権限見直し
まとめ
丸投げで成果を出す鍵は、役割の線引きと数値管理です。対応業務と責任者をRACIで明確化し、費用相場・契約条件を可視化。
実績・体制・見積内訳で業者を比較し、KPI・権限・定例運用で改善を継続します。最後に、禁止手法と権限管理を契約で担保。
まずは「スコープ表」「KPI表」「権限一覧」を作成し、候補3社で比較検討を進めてください。