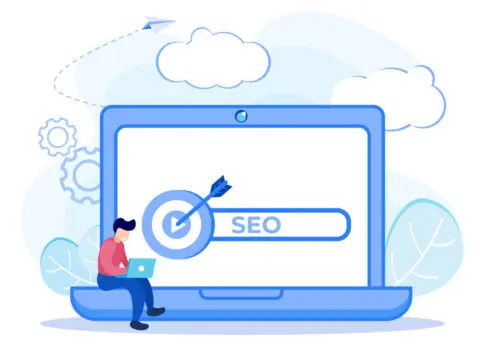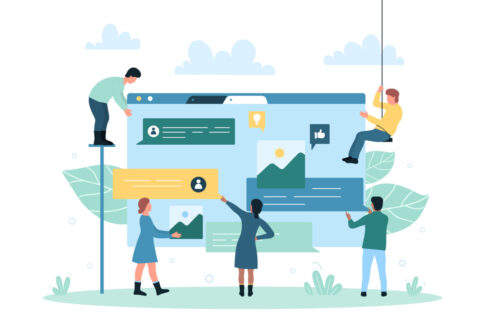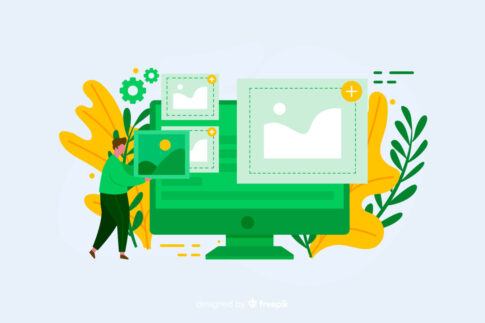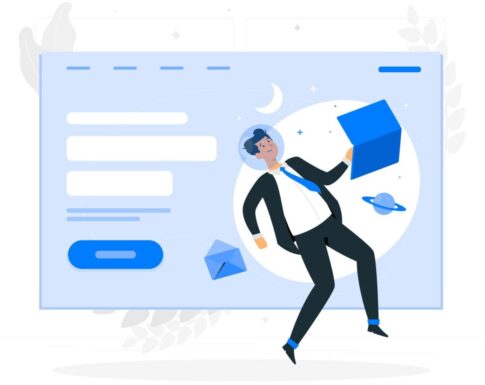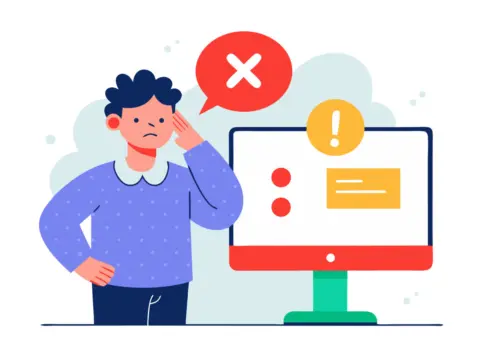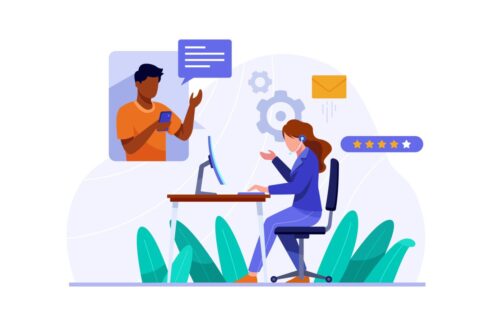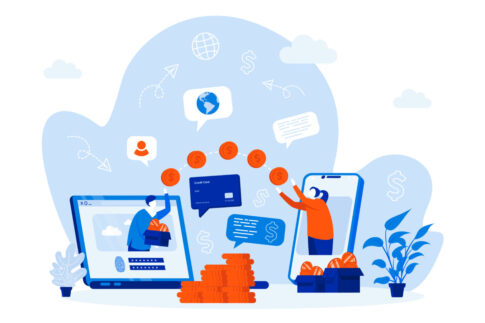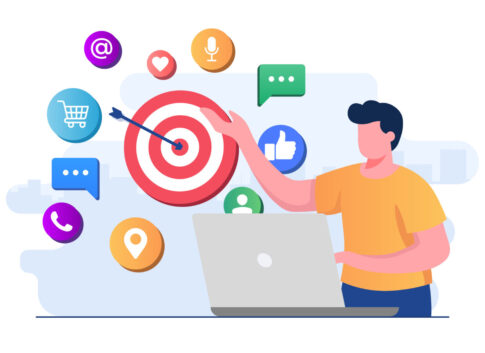アメブロの「リンク」を正しく使えば、回遊率とクリック率が上がり、集客と検索評価の底上げにつながります。本記事では、内部/外部リンクの基本、リンクカードの使い分け、最適な配置とアンカーテキストのコツ、スマホ・PCでの挿入手順、nofollow確認までを実務の型で解説していきます。
アメブロのリンク基本と活用メリット

アメブロのリンクは「内部リンク(自分のアメブロ内の他記事)」「外部リンク(自社サイトやSNSなど別サイト)」「表示形式(リンクカード/テキスト)」の組み合わせで考えると整理しやすいです。
内部リンクは関連記事へ自然に誘導でき、読者が次の記事へ迷わず移動できるため回遊率の向上に直結します。
外部リンクは公式情報や自社LP、SNSなどへ橋渡しする役割があり、コンテンツの信頼性補強や導線の拡張に有効です。
表示形式は、カードが視認性とクリックのしやすさ、テキストが文章の流れを保ちながら文中に溶け込む点が強みです。
リンク設計の基本は「読者が次に知りたいことへ最短で案内する」ことです。見出し直下や段落の切れ目など、読者の視線が止まる位置に要点リンクを置くと、クリック率は上がりやすくなります。
反対に、過剰なリンクは読みづらさや離脱につながるため、1ブロックに詰め込みすぎないことが大切です。
用途別の使いどころを下表でイメージし、記事の目的に合わせて最小のリンクで最大の導線を作りましょう。
| 種類 | 主な目的 | 使いどころ |
|---|---|---|
| 内部リンク | 関連記事へ誘導→回遊・滞在時間の向上 | 見出し直下/まとめ前/用語説明の直後 |
| 外部リンク | 根拠提示・SNS導線・LP誘導 | 事実や用語の出典提示/CTA周辺 |
| リンクカード | 視認性向上・クリック促進 | 導入部・重要見出し直下・最後のCTA前 |
| テキストリンク | 文脈の中で自然に補足 | 段落中の要点語句・補助解説の直前 |
- 読者の次の疑問→最短導線で案内する
- 見出し直下や段落の切れ目に要点リンク
- 1ブロックのリンク過多を避け読みやすさ維持
内部リンクと外部リンクの違い整理
内部リンクは、同一ブログ内の記事同士を結び、カテゴリやテーマ単位で深掘りを可能にします。読者は興味のあるテーマを連続して読み進めやすくなり、結果として滞在時間やスクロール率が伸びやすくなります。
設計のコツは、上位の解説記事→個別の詳細記事→実践ノウハウの順に矢印でたどれる階層を作ることです。
例えば「アメブロのリンク基本」から「リンクカードの使い方」「アンカーテキストの作り方」へ進み、最後に「チェックリスト」へ導くと、読者は迷わず学習を完了できます。
外部リンクは、読者の疑問に対する根拠・定義・最新情報へ橋渡しする役割です。自社サイトやLPへ誘導する場合は、文脈上の理由を明確にし、クリック先で得られる具体的価値(例:テンプレートDL、料金表、申し込み可)を近接文で示すと、違和感のない導線になります。
外部の参考情報を示すときは、本文の主旨が外部頼みにならないよう、要点は本文で完結させたうえで「詳細は外部参照」という順番にしましょう。
【内部と外部の設計ポイント】
- 内部=深掘り導線の整備→学習体験を連続化
- 外部=根拠・最新情報・CTA導線→目的に直結
- 本文で要点を完結→リンクは補助として配置
- 内部リンクの往復で同ページを行き来→迷子化
- 外部リンクの連打→離脱増・戻りが発生しやすい
- リンク先の更新停止・404→信頼低下につながる
リンクカードとテキストの使い分け
リンクカードは、URLをカード状に可視化し、タイトルやサムネイルが表示されるため、視認性が高くクリックを促しやすい形式です。特に導入部や重要見出し直下で「この記事の要点をさらに深める先」を提示するのに向いています。
一方、テキストリンクは文章の流れを崩さずに情報を補う用途に最適で、段落内のキーワードから自然に遷移させたいときに効果を発揮します。
使い分けの基準は「目立たせたいか/文のリズムを優先するか」です。カードは目立つ反面、連発すると表示が重くなり冗長に見えます。
1記事あたりのカードは要所に絞り、同テーマのリンクを塊で配置するより、読者の視線が止まる位置に分散して置くとクリックが分散して取りこぼしを減らせます。
テキストリンクはアンカー文字列が肝心です。「こちら」よりも「内部リンクの作り方」など内容が分かる語にすると、意図が伝わりクリック率が上がります。
【使い分けの基準】
- 強調・視認性重視→リンクカードを要所に配置
- 文脈の自然さ重視→テキストリンクで補助
- アンカーは内容が分かる語にして曖昧語を回避
| 形式 | メリット | 注意点 |
|---|---|---|
| リンクカード | 視認性が高くクリックを促しやすい | 連発で冗長化・表示負荷→要所に限定 |
| テキストリンク | 文中に溶け込み読みやすさを保てる | 曖昧なアンカーはクリックが伸びにくい |
クリック率と回遊率の向上効果
クリック率と回遊率は、リンクの「位置」「文脈」「アンカー文字列」で大きく変わります。まず位置は、導入部・重要見出し直下・まとめ前など、読者が次の行動を考えやすい箇所が効果的です。
文脈は、読者が今まさに抱えている疑問に続く答えを示すことが鍵で、「用語定義→詳しい解説へ」「事例→ノウハウへ」「悩み→解決策へ」のように、矢印で進行方向が想像できる並べ方にすると、クリックは自然に増えます。
アンカーは具体性が重要で、「こちら」ではなく「内部リンク設計の型」「リンクカードの配置例」のように、クリック後の価値が分かる表現にしましょう。
改善は小さくテストするのが近道です。同じ内容でも、導入部と見出し直下でクリック率が変わることはよくあります。まず要点リンクを3か所に置き、1〜2週間ほど反応を見て、反応の薄い箇所を差し替えます。
カード→テキスト、長いアンカー→短い要点語、リンクの直前に一文で期待値を添える(例:→図解で手順を確認)など、微調整だけでも効果が動きます。
【改善の打ち手】
- 導入部・重要見出し直下・まとめ前に要点リンク
- アンカーは「何が得られるか」を具体化
- 反応の薄い箇所は形式・位置・文言を小さくABテスト
- 読者の次の疑問を想定→矢印で導く並べ方
- 1画面内に“迷わないリンク”を1〜2本だけ置く
- カードとテキストを混在させ単調さを回避
内部リンク設計と導線最適化の型

内部リンク設計は「読者が次に知りたいことへ最短で到達できる状態」を作ることが目的です。
まず、サイト内の役割を〈ハブ(まとめ・入口)〉〈詳細(解説・事例)〉〈行動(申込・問い合わせ)〉に分け、各ページからどこへ進むのが自然かを明確にします。
さらに、見出し直下や段落の切れ目など視線が止まりやすい位置にリンクを配置し、アンカー(リンクの文字列)は内容が想像できる具体語にします。
重要ページは全体のハブとして被リンクならぬ“被内部リンク”を集め、検索エンジンと読者の双方に「中心ページ」であることを示します。
過剰なリンクは読みにくさと迷いを生むため、1画面内のリンクは用途の異なる1〜2本に抑え、残りは本文中で文脈に沿って補完します。
最後に、クリックデータや滞在時間を定期的に見直し、反応の薄い箇所は位置・形式・アンカーを小さく差し替えて最適化します。
| ページ種別 | 主な役割 | 内部リンクの型 |
|---|---|---|
| トップ/カテゴリ | 全体の案内・入口 | 主要テーマのハブへ集中的に送客→詳細記事へ分岐 |
| まとめ/比較 | 意思決定の支援 | 個別解説・事例・Q&Aへ下流導線→最終的にCTAへ |
| 個別解説 | 深掘り・用語整理 | 関連解説・手順記事・チェックリストへ双方向リンク |
| CTA/LP | 問い合わせ・登録 | 前段の不安点へ戻る導線を最小限にし離脱を抑制 |
- 役割分担(入口→深掘り→行動)で導線を設計
- 見出し直下・段落の切れ目に要点リンクを配置
- 重要ページへ内部リンクを集中し中心性を明確化
重要ページへの内部リンク集中
重要ページは、検索流入とコンバージョンを支える“軸”です。サイト内の関連記事から一貫してリンクを集めると、読者は迷わず中心情報へ到達でき、評価の分散も防げます。
設計の出発点は、中心に据えるページの選定です。例えば「アメブロのリンク活用ガイド」をハブにし、周辺の「リンクカードの使い方」「アンカー作成」「配置パターン例」などから常にハブへ戻れる双方向リンクを張ります。
カテゴリページやまとめ記事からもハブへ送客すると、上下左右に矢印が通ったネットワークになり、回遊の起点が明確になります。
内部リンクの集中は量より質が重要です。関連性の低いページから無理に集めるより、テーマ軸が近く読者の次の疑問に答えるページから張る方がクリックと満足度が伸びます。
リンクの位置は、見出し直下や要約ボックスの直後など、注意が向きやすい箇所を優先します。アンカーは「こちら」ではなく「内部リンク設計の型」など内容を具体化し、同一ページ内で同じアンカーを乱発しないようにします。
最後に、重要ページからは逆向きに“次の一歩”(事例・チェックリスト・CTA)へ送るリンクを用意し、滞在→行動への連鎖を作ります。
- ハブページを決め、関連解説から一貫して送客
- 見出し直下・要約直後にリンク→発見性を最大化
- アンカーは内容が分かる具体語→同一表現の乱用回避
- 関係の薄い記事から機械的に大量リンク→関連性の低下
- フッターのみの一括列挙→読者が認識しづらい
- 同一アンカーの多用→クリックが分散・測定しづらい
アンカーテキスト最適化ルール
アンカーテキストはクリックの“理由”そのものです。読む前に内容が理解でき、クリック後に得られる価値が想像できる表現にすると、回遊と滞在が伸びます。
基本は簡潔・具体・一貫性です。文脈と一致した名詞句を使い、8〜20文字程度で要点をまとめると読みやすくなります。
主語のない「こちら」「詳しく」ではなく、「リンクカードの配置例」「内部リンク設計チェックリスト」のように中身を明示します。
キーワードの詰め込みは不自然になりやすいので、文意を損なわない程度に1回で十分です。アンカーの近くに短い期待値文(例:→図解で手順を確認)を添えるとクリック理由が強化されます。
同じページ内でアンカー表現を変えすぎると学習効果が働かず、逆にすべて同じにすると視認性が落ちます。重要導線は表現を固定し、補助導線は軽い表現で差別化するなど、階層に応じて書き分けます。
スマホでは行間が詰まるため、長すぎるアンカーや絵文字の多用は避け、改行前後の空白で押しやすさを確保します。
リンク直前直後の語彙は曖昧さを避け、アンカー自体を要点語にすることで、読み手の負荷を下げられます。
| NG表現 | 改善例(意図が伝わるアンカー) |
|---|---|
| こちら | 内部リンク設計の型(図解) |
| 詳しく見る | リンクカードの作り方と配置例 |
| 参考 | アンカーテキストの書き方チェック |
- 簡潔・具体・一貫性→8〜20文字を目安に設計
- 期待値の一言を添えてクリック理由を明確化
- 重要導線は表現を固定→補助は軽く差別化
導線マップ作成と配置優先度
導線マップは、読者が入口から目的達成まで進む経路を図にしたものです。まず、想定読者ごとに“最終行動”(例:お問い合わせ・プロフィール遷移・フォロー)を定め、そこに至る情報の順序を決めます。
次に、入口ページ(検索流入しやすい解説)→比較/まとめ→実践/チェックリスト→CTAという段階を並べ、各段階で読者が抱える疑問を1つずつ解消するページを割り当てます。
ページごとに「入れるリンク」と「受けるリンク」を整理し、役割が重複していないかを点検します。
最後に、スマホの1画面内で過不足なく発見できるかを基準に、見出し直下や要約直後、まとめ前に優先リンクを配置し、残りは本文中の文脈で補完します。
- 最終行動を定義→到達までの段階(入口→比較→実践→CTA)を設定
- 各段階の疑問を洗い出し→対応する記事を割り当て
- ページごとの「入れる/受ける」リンクを1〜3本に整理
- 見出し直下・要約直後・まとめ前に優先リンクを配置
- 見出し直下(H2直後の要点リンク)
- 導入部の要約ボックス直後
- まとめ直前の“次の一歩”リンク
- 段落中の補助テキストリンク
- カードの連発で表示が重い→要所に限定し軽量化
- 同一ページ間の往復リンク→迷子化に注意
- 計測なしの貼り替え→ABテストで小さく検証
リンクカード活用と配置の最適解
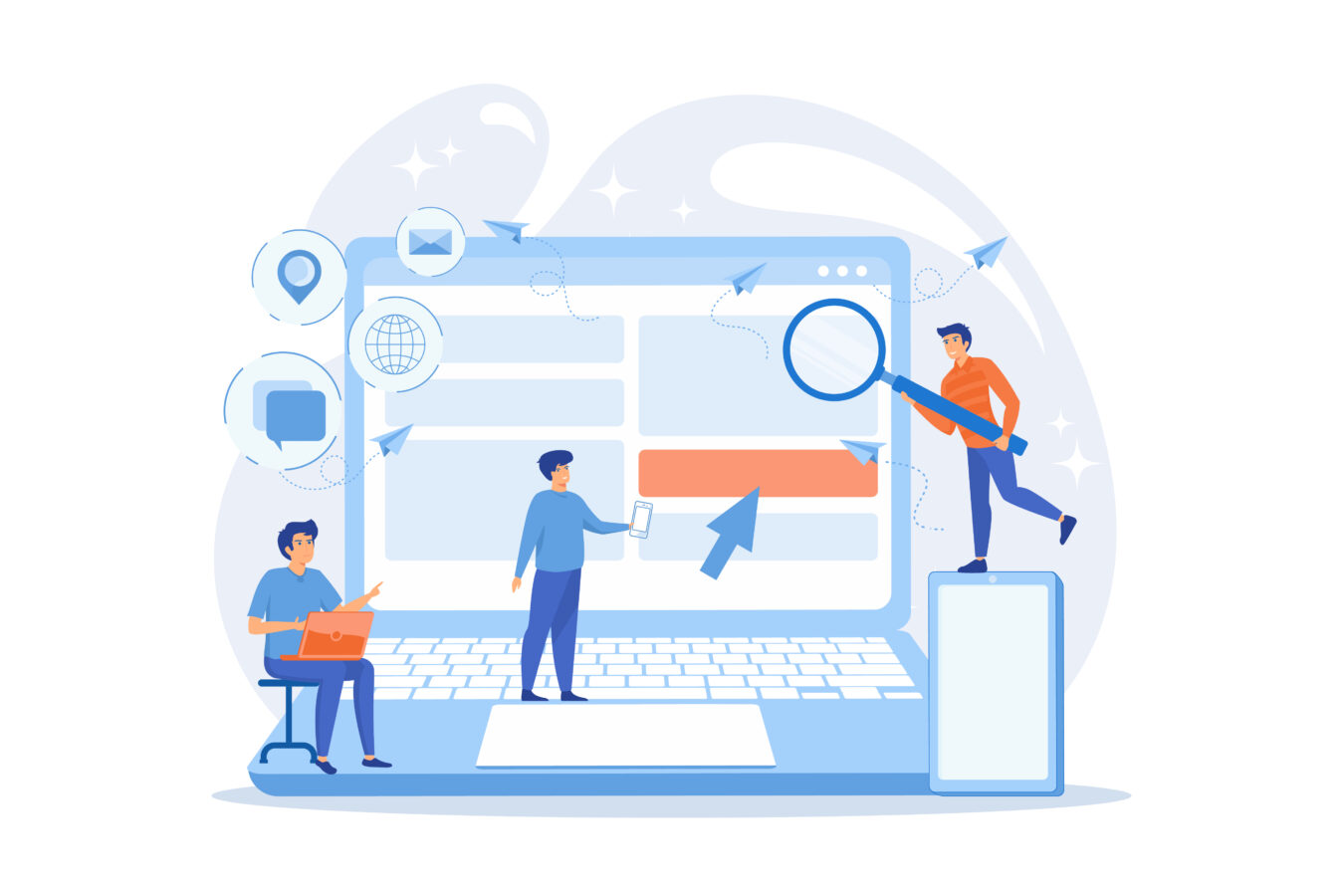
リンクカードは、URLを視覚的にまとめて見出し・タイトル・画像を一枚で提示できるため、読者の注意を集めやすく、クリックのきっかけを作りやすい形式です。
テキストリンクよりも存在感があり、導入部や重要見出し直下など「次に進む判断」をする瞬間に置くと効果が出やすくなります。
一方で、カードを連続して並べると画面が重く感じられ、読み進めづらくなります。したがって、カードは要所のみ、テキストリンクは文中の補足導線として併用するのが最適解です。
配置の基本は「目的ページへ最短で案内する」ことです。記事の意図が伝わる短い前置き(例:→図解で手順を確認)を添えてからカードを置くと、クリック理由が明確になり迷いが減ります。
スマホ閲覧を前提に、1画面内にカードは1枚程度、同テーマのカードは間隔をあけて挿入します。まとめ前には「次の一歩(チェックリスト・事例・申込導線など)」のカードを置き、読後の行動を後押ししましょう。
- 導入部:全体像や結論へ→理解の土台を提示
- 重要見出し直下:深掘りガイドや図解へ→学習を継続
- まとめ直前:チェックリストや事例へ→行動を具体化
カード化に適したURLの基準
カードにするURLは「内容が一目で伝わるページ」を選ぶのが基本です。タイトルが明快で、ページの主題が絞られており、代表画像が用意されていると、カードの視認性が高まりクリックを後押しします。
ログイン必須や閲覧制限のあるページ、リダイレクトが多いURL、内容が薄いランディングページはカードにしても期待値と実体がずれて離脱を招きやすいため避けます。トラッキング用の長いクエリは可能なら短縮し、URLは極力シンプルに保ちます。
また、カードは「リンク先の価値が瞬時に理解できるか」が基準です。比較表、手順の図解、テンプレート配布、公式情報など、読者の作業を具体的に前進させるページはカード向きです。
逆に、雑多な情報の寄せ集めや画像のないテキスト中心ページは、文脈内のテキストリンクの方が読まれやすい傾向があります。
【基準チェック】
- タイトルが主題を明確化→曖昧語を避け一読で理解
- 内容がページ内で完結→クリック直後に価値を提示
- 閲覧制限・過剰リダイレクト・不安定URLを回避
| URLタイプ | カード適性 | ポイント |
|---|---|---|
| 図解/チェックリスト | 高い | 視覚要素がカードと相性◎→導入や見出し直下に最適 |
| 比較/まとめ記事 | 中〜高 | 結論・選び方を先に示すとクリック率が上がる |
| 申込/ダウンロード | 中 | 近接文で得られる特典を明記→期待値と実体を一致 |
| ログイン必須/動的ページ | 低い | カードからの離脱を誘発→テキストリンクで補助 |
見出し直下と導入部の活用例
導入部は「この先で何が得られるか」を短く示し、直後にカードで全体像や結論へ案内すると、読者は安心して読み進められます。
例えば、リンク活用の記事なら導入の3〜4行目に「全体ガイド」カードを置き、本文では詳細を追う構成にします。
見出し直下では、そのセクションの核心に直結する深掘り先(図解・チェックリスト・事例)をカードで提示します。読者は見出しで期待した回答にすぐ到達でき、不要なスクロールを減らせます。
カードの直前には、クリックの理由を一文で補強します。例として「→配置例を図で確認」「→チェックリストで抜け漏れ防止」など、期待値を明示する表現が有効です。
カードは同じ画面に複数並べず、テキストリンクと交互に配置してリズムを作ります。まとめ前には「次の一歩」を示すカードを1枚だけ置き、読み終わりの意思決定(比較、申込、事例確認など)を後押しします。
【活用例】
- 導入部:全体ガイドのカード→記事全体の地図を提示
- H2直下:その章の図解/手順カード→理解を加速
- まとめ前:チェックリストカード→行動へ自然に接続
カード数目安と表示速度対策
カードは強い訴求を持つ一方で、連発すると読みづらさや体感速度の低下につながります。目安は1記事あたり3〜5枚、1画面内1枚、1つのH2につき最大1枚です。
連続配置は避け、カードの前後に短い説明文を挟んで情報の塊を小分けにします。画像が多い章ではカードを控え、テキストリンク中心で軽量化します。
スマホでの閲覧を基準に、通信環境が弱い状況でもストレスがないかを確認し、反応が鈍い箇所はカード→テキストへ置き換えるなど小さく調整します。
速度対策は、カードの“置き場所”で改善できます。特にファーストビューに重い要素を集中させず、本文のリズムに合わせて分散します。
カードの直後に長大な画像や表を重ねない、同一テーマのカードを1段落おきに離す、といった配慮だけでも体感は変わります。
効果測定では、クリック率と離脱率の両面で見て、表示が遅い章から順に枚数や位置を見直します。
- カードの連打→画面が重く単調化→要所に限定し間隔を確保
- ファーストビューに要素詰め込み→上部は1枚だけに抑制
- 期待値不一致(タイトルと中身のズレ)→近接文で価値を明示
SEOに効く外部リンクと出典表記

外部リンクは、読者に一次情報や補足データを提示して理解を深める役割があります。記事内で根拠を明示できると内容の信頼性が高まり、読後の満足度や再訪率の向上につながります。
ポイントは「関連性」と「期待値の一致」です。本文の主張とリンク先の内容が密接に結び付いていること、クリック直後に読者が求める情報へ到達できることが重要です。
配置は、主張を行った直後・定義や数値を提示した直後・結論の根拠を示す段で用いると自然です。アンカーテキストは「こちら」ではなく、内容が分かる名詞句(例:用語定義、機能仕様、料金表 など)にすると、クリック理由が明確になります。
また、同じテーマで複数の信頼できる一次情報がある場合は、最小限に厳選します。リンク先がログイン必須・不安定・過度な広告だと、読者体験が損なわれがちです。
リンクの前後には短い前置き(→根拠となる公式情報を確認 など)を添えると、期待値のズレを避けられます。
最後に、外部リンクは“本文の代替”ではなく“補強”として使い、本文だけで主旨が理解できる構成を保つことが大切です。
- 本文の主張直後に根拠リンク→期待値の一致を重視
- アンカーは名詞句で具体化→クリック理由を明確に
- 本文だけで要点は完結→リンクは補強として配置
関連性重視の外部リンク選定
外部リンクは「読者の疑問に直接答える一次情報」を最優先に選びます。定義・仕様・手順は公式ヘルプや公的機関、数値や統計は公表データ、料金や機能はサービス公式のページが適しています。
記事の文脈と離れた権威サイトへのリンクは、いくら有名でも“関連性の弱さ”からクリック後の満足度が下がることがあります。
逆に、規約・手順・フォームなど“次の行動に直結するページ”は、少ないリンクでも強い効果を発揮します。
【選定基準】
- 本文の主張と1対1で対応する一次情報かどうか
- クリック直後に目的の情報へ到達できる導線か
- 更新日・発表主体・責任の所在が明確か
【避けたい例】
- まとめ的で範囲が広すぎ、主張を裏づけないページ
- 広告過多・ポップアップ過多で読みにくいページ
- ログイン必須・リダイレクト多段で到達性が低いページ
アンカーテキストは「用語定義」「機能仕様」「申込手順」のように、クリック後に得られる内容を具体化します。
近接文で「→定義の原典」「→申込の公式手順」など一言補うと、期待値のズレを防げます。配置は主張や数字の直後が自然で、1段落に1本までを目安にすると読みやすさを保てます。
信頼できる出典表記と記載例
出典表記は「何の根拠を、どの主体が、いつ公表したか」を読者に伝えるための署名です。本文の近くに簡潔に示し、必要なら表や脚注で整理します。
発表主体(公式/公的/学術など)と更新日の明記が重要で、リンク切れや情報の陳腐化を防ぐために定期点検もしましょう。
以下は、情報種別ごとの推奨リンク先と記載の例です。
| 情報種別 | 推奨一次情報 | 記載例(文中表記の一例) |
|---|---|---|
| 定義/仕様 | サービス公式ヘルプ/公的ガイド | 出典:〇〇公式ヘルプ「リンク機能の仕様」 |
| 料金/機能 | 公式料金ページ/お知らせ | 出典:〇〇公式「料金・機能一覧」 |
| 統計/数値 | 公的統計/公式レポート | 出典:〇〇統計「年次データ」 |
| 法令/制度 | 官公庁サイト/法令データ | 出典:〇〇庁「告示・手引」 |
【文中の書き方の目安】
- 主張の直後に簡潔な出典名→リンクを付与
- 表・図の下に「出典:発表主体+ページ名」
- 更新日が重要な内容は「最終更新:YYYY/MM/DD」も追記
出典名はページタイトルをそのまま使うと、リンク先で同じ名称が確認できて便利です。長いタイトルは要点のみ抜粋し、本文の読みやすさを優先します。
- 発表主体は誰か→公式/公的/学術を優先
- 更新日は明記されているか→陳腐化の有無を確認
- 本文の主張と出典の内容が1対1で対応しているか
nofollow確認と貼り方の注意
外部リンクの評価伝達は、リンクの属性(rel)や設置場所に左右されます。プラットフォームやテーマによっては、ユーザー投稿内のリンクに rel=”nofollow” や rel=”ugc” 等が自動付与される場合があります。
仕様は提供側で変更されることがあるため、毎回「自分のページで実際にどう出力されているか」を確認するのが確実です。確認はブラウザの検証ツールやページソースで a タグを直接見る方法が最も簡単です。
【確認手順】
- 記事をプレビュー/公開→該当リンク上で右クリック→検証を選択
- a タグの rel 属性(nofollow/ugc/noreferrer/noopener など)を確認
- target・リダイレクト有無(短縮URL/計測リンク)も併せて点検
【貼り方のポイント】
- 広告・紹介・申込誘導などは「広告/PR」である旨を本文で明確化
- 短縮URLや多段リダイレクトは避け、到達性と透明性を確保
- 同一段落に外部リンクを詰め込みすぎず、1段落1本を目安に配置
属性の有無にかかわらず、外部リンクは“読者の利便性”を最優先に設計します。アンカーは内容が分かる具体語にし、リンク直前には「→根拠となる公式情報」など一言を添えて期待値を合わせてください。
表示速度や可読性の観点から、連続配置を避けて文脈に沿って分散させると、クリック率と読了率の両立がしやすくなります。
- 「こちら」など曖昧なアンカー→内容が分かる名詞句に修正
- ログイン必須や不安定URLへの誘導→到達性の高い一次情報へ差し替え
- 外部リンクの連打→主張直後の最小本数に限定し文脈で補強
スマホ・PC別のリンク挿入手順と注意点

スマホとPCでは操作手順や確認ポイントが少し異なりますが、基本は「読者が次に知りたい場所へ迷わず進める導線づくり」です。スマホは移動中の編集に向き、直感的に貼り付けやすい一方で、誤タップや改行位置のズレが起こりやすいです。
PCは見出し構造や段落のバランスを俯瞰でき、リンクカードとテキストリンクの配置最適化に向いています。まずは「挿入→表示確認→微調整」を1セットにし、記事全体のリズムを崩さない範囲で要所にリンクを置きます。
特にファーストビューは重くせず、導入の3〜4行目、H2直下、まとめ前など発見されやすい位置に限定すると、クリック率と読了率の両立がしやすくなります。
貼り付け後はリンク先の到達性、アンカーの具体性、nofollow等の属性、スマホ幅での折返しを合わせて点検しましょう。
| デバイス | 主な操作場所 | 向いている作業 |
|---|---|---|
| スマホ | アプリ編集画面(鎖アイコンのリンク機能) | 素早い貼付・その場の修正・カードの要所挿入 |
| PC | エディタ(可視編集/HTML編集) | 構成の俯瞰、リンクの位置最適化、表・画像との整合 |
- 要所に限定して配置→1画面に1本目安
- 貼付直後にスマホ幅で折返しと押しやすさ確認
- リンク先の到達性と期待値一致を必ず点検
スマホアプリでのリンク挿入手順
スマホでは、まず編集画面でリンクにしたい語句を選択し、鎖アイコンをタップします。ポップアップにURLを貼り付け、表示用のテキストを入力して確定します。
リンクカードを使う場合は、URLをそのまま貼るだけでカード化されることがありますが、前後に短い前置き文(例:→図解で手順を確認)を添えるとクリック理由が明確になり、誘導が自然になります。
挿入後はプレビューで表示を確認し、改行の位置、カードと本文の間隔、指で押しやすい行間になっているかをチェックします。
誤タップを防ぐため、連続するリンクの間には1行分の空白や短文を挟み、同一段落に外部リンクを詰め込まないことが大切です。
テキストリンクは「こちら」ではなく内容が分かる名詞句にし、長すぎれば10〜20文字程度に短縮します。カードが重く感じる場合は、同テーマの2枚目以降をテキストリンクへ置き換え、体感速度を優先しましょう。
- カードの連続で重い→同画面1枚に制限し間隔を確保
- 誤タップ多発→リンク間に空白や短い説明を挟む
- アンカーが曖昧→「内部リンク設計の型」など具体語へ修正
PC編集画面とHTML編集の基本
PCでは、可視編集でリンクボタンからURLと表示テキストを設定し、段落のまとまりに合わせて位置を調整します。
H2直下は強い導線になるため、章の核心へ直結するリンクを1本だけ置き、本文中は関連説明の直後にテキストリンクで補完するのが読みやすい配置です。
リンクカードは目立つ反面、画像・表と重なると視線が散りやすいので、カード→本文→テキストリンクの順でリズムを作ると自然です。
HTML編集を使う場合は、意図しない改行や連続スペースがアンカーを分断しないか、余計な追従要素(スクリプト付き短縮URLなど)が混ざっていないかを確認します。
公開前に、同一ページで同じアンカーを乱用していないか、内部リンクの往復で迷子導線になっていないかも合わせて見直してください。
| 編集モード | 利点 | 注意点 |
|---|---|---|
| 可視編集 | 直感操作で素早い挿入・配置確認が容易 | 細かな余白や改行のズレに気づきにくい |
| HTML編集 | 細部の調整・不要要素の除去・属性の点検に有効 | 誤った編集で表示崩れ→公開前プレビュー必須 |
リンク先確認とアンカー見直し
リンクは挿入して終わりではなく、「期待どおりに開くか」「何が得られるか伝わるか」を確認して完成です。
まずプレビューで、スマホ幅・PC幅の両方を確認し、404やリダイレクト多段、ログイン必須など到達性の問題がないかを点検します。
次に、アンカーを読み返し、クリック後の価値が一読で分かる名詞句か、長すぎず短すぎないか、直前に短い期待値文(例:→チェックリストで抜け漏れ防止)があるかを確認します。
外部リンクは本文の主張を補強する位置に限定し、同一段落に複数並べないことで読みやすさを守れます。内部リンクは重要ページへ集中しつつ、戻り導線を最小限にして迷子を防ぎます。
最後に、公開後1〜2週間はクリック位置を小さく入れ替え、カード↔テキスト、アンカーの言い換え、見出し直下の有無などをABテストで微調整しましょう。
- 到達性:https/リダイレクト/ログイン要否を確認
- 具体性:アンカーは内容が分かる名詞句に統一
- 配置:H2直下・導入・まとめ前の要所に限定
まとめ
内部/外部リンクとリンクカードを使い分け、関連性の高い導線を要所に配置できれば、回遊率と検索評価は着実に伸びます。
まず重要ページを洗い出し、見出し直下にカード1〜3個、本文中に具体的なアンカーで内部リンクを追加。挿入後はスマホ・PCで表示確認し、URL・nofollow・OGPの不具合も点検しましょう。