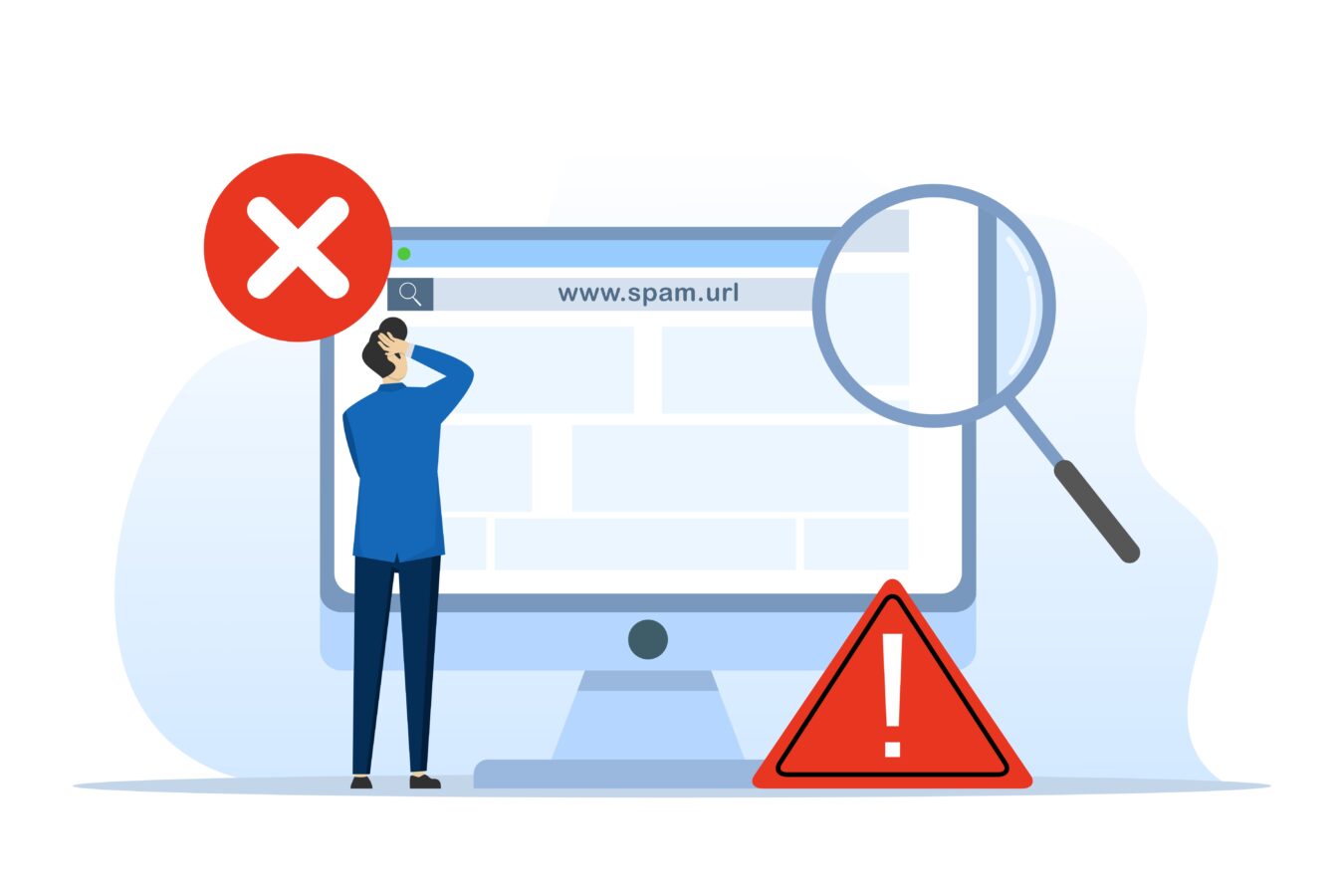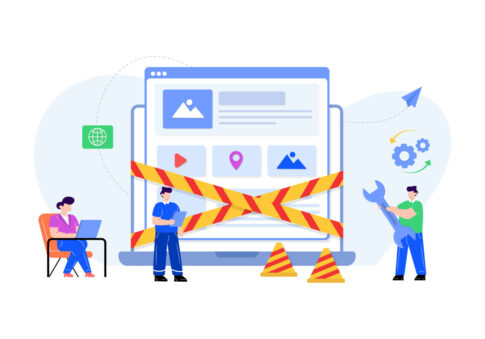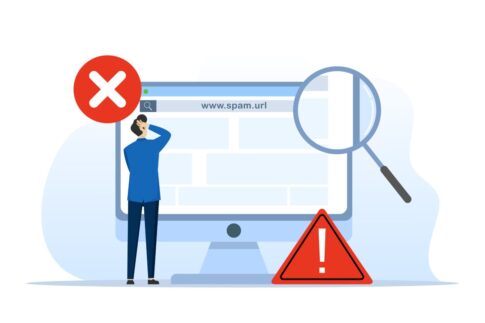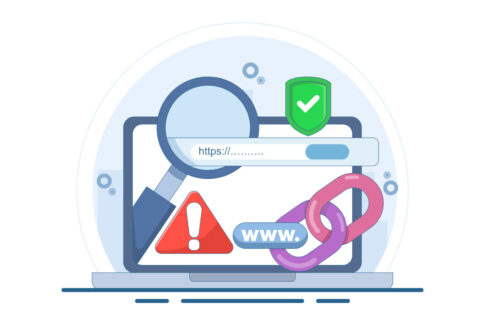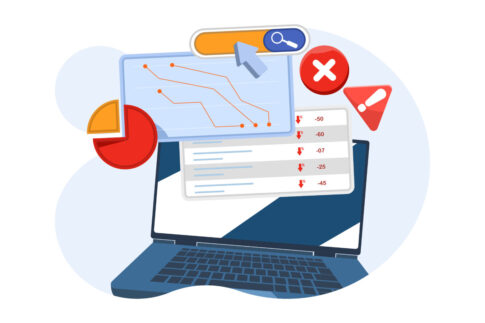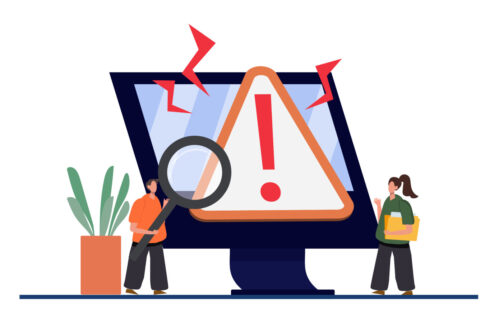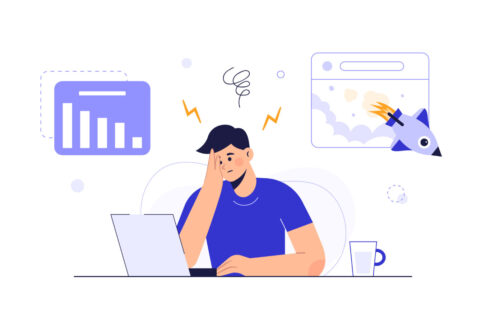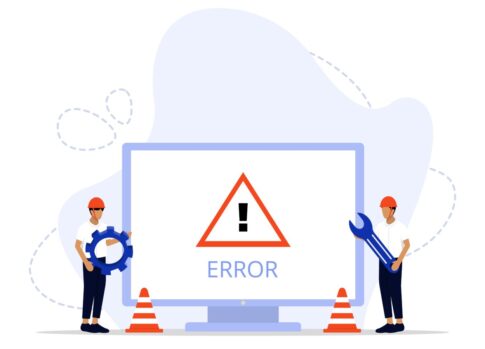アメブロでコメントを消そうとしても、削除ボタンが出ない・押しても反映されない・そもそもコメントが見当たらないなど、焦る場面があります。
原因は「自分のブログについたコメントか」「他ブログにつけたコメントか」で対処が大きく変わり、設定や表示の違いが絡むこともあります。この記事では、削除できる範囲の確認から、アプリ/PCの削除手順、削除できない原因のチェック、迷惑コメントの予防策、解決しない場合の問い合わせ準備までを5手順で解説していきます。
削除できるコメントの種類

アメブロのコメントは、どこに付いているかで削除できる人が変わります。いちばん多い勘違いは「他ブログに自分が付けたコメント」を自分で消そうとして、削除ボタンが見当たらないケースです。
結論として、自分のブログに付いたコメントはブログ管理者として削除できますが、他ブログに付けたコメントは原則として自分では削除や修正ができません。さらに、コメントそのものを消せても、履歴や通知の一部は削除できないことがあります。
まずは対象を切り分けて、削除できる場所とできない場所を押さえるのが最短ルートです。承認制を使っている場合は、コメントが公開済なのか承認待ちなのかでも見え方が変わるため、削除先の画面を間違えないようにします。
| 対象 | 削除できる人 | よくある誤解 |
|---|---|---|
| 自分のブログについたコメント | 自分 ブログ管理者として削除可能 | 記事画面で探して消そうとして見つからない コメント管理で削除します |
| 他ブログにつけた自分のコメント | 相手 ブログ管理者のみ削除や修正が可能 | 自分の操作で消せると思い込みやすい 削除希望は相手へ連絡します |
| 承認待ちのコメント | ブログ管理者が承認か削除を判断 | 表示されないのは不具合ではなく承認待ちのケースがあります |
| コメントした記事の履歴や一部の通知 | 原則として消せないことが多い | コメントを消せば履歴も消えると思いがち 別管理のため残る場合があります |
自分のブログについたコメントは削除できる
自分のブログに付いたコメントは、ブログ管理者としてコメント管理から削除できます。記事のコメント欄から直接探すより、コメント管理で月別に確認しながら処理するほうが確実です。
承認制を設定している場合は、公開済のコメントだけでなく承認待ちのコメントも別画面で確認でき、そこで削除や承認の操作を行います。
削除すると元に戻せないため、迷惑行為の証拠として残したい場合は先に画面保存をしておくと安心です。
また、同じ相手や同種の迷惑コメントが続く場合は、削除だけで終わらせず、コメント受付設定や拒否設定など次の対策もセットで考えると再発を抑えやすくなります。
削除ボタンが見当たらないときは、記事画面ではなくコメント管理を開けているか、対象月が合っているか、承認待ち側に切り替える必要がないかを先に確認してください。
- 対象月を合わせてコメント管理で探す
- 承認制なら承認待ち側も確認する
- 削除後は元に戻せないため必要なら画面保存する
他ブログにつけたコメントは自分で消せない場合
他の人のブログに自分が付けたコメントは、原則として自分では削除や修正ができません。削除ボタンが出ないのは不具合ではなく仕様のケースが多いです。
消したい場合は、相手のブログ管理者に削除を依頼する流れになります。さらに、相手が承認制の場合は、あなたのコメントが公開されずに承認待ちのままになったり、管理者の判断で非表示や削除になったりすることもあります。
投稿者の希望で表示状態を操作できるものではないため、まずは現状を落ち着いて整理し、必要な連絡だけを行うのが安全です。
依頼するときは、相手の負担を増やさないように、どの記事のどのコメントかが分かる情報を添え、短く丁寧に伝えるのが基本です。
【削除依頼までの進め方】
- 該当記事を開き、自分のコメントが表示されているか確認する
- 承認制の可能性を想定し、表示されない場合は即断しない
- 削除が必要なら相手のブログ管理者へ連絡手段を選ぶ
- 記事タイトルや投稿日時など特定できる情報を添えて削除を依頼する
- 返答がない場合は追加投稿を控え、状況が悪化しない運用に切り替える
履歴や通知など消せない範囲を整理
コメントが削除できないと感じる原因の一部は、コメントそのものではなく履歴や通知の表示にあります。
たとえばコメントした記事の履歴は、コメントを削除したかどうかとは別に管理され、履歴自体は削除できない扱いです。PCではホームのコメントした記事から確認でき、アプリでもブログ管理の一覧で確認できる形です。
履歴は直近の一定期間と件数だけが表示される仕組みのため、時間が経つと見えなくなることはありますが、手動で消す操作はできません。
また、コメントを削除した直後でも、端末側の表示更新のタイミングや通信状態によっては、しばらく古い表示が残るケースがあります。
その場合は再読み込みやアプリの再起動で表示が切り替わることがあります。消せない範囲を先に理解しておくと、削除操作そのものを間違えているのか、表示の問題なのかを切り分けやすくなります。
- コメントした記事の履歴は削除できない扱い
- 相手ブログのコメントは投稿者が削除や修正できない
- 削除直後は表示更新の都合で見え方が遅れて変わる場合がある
コメント管理から削除する手順
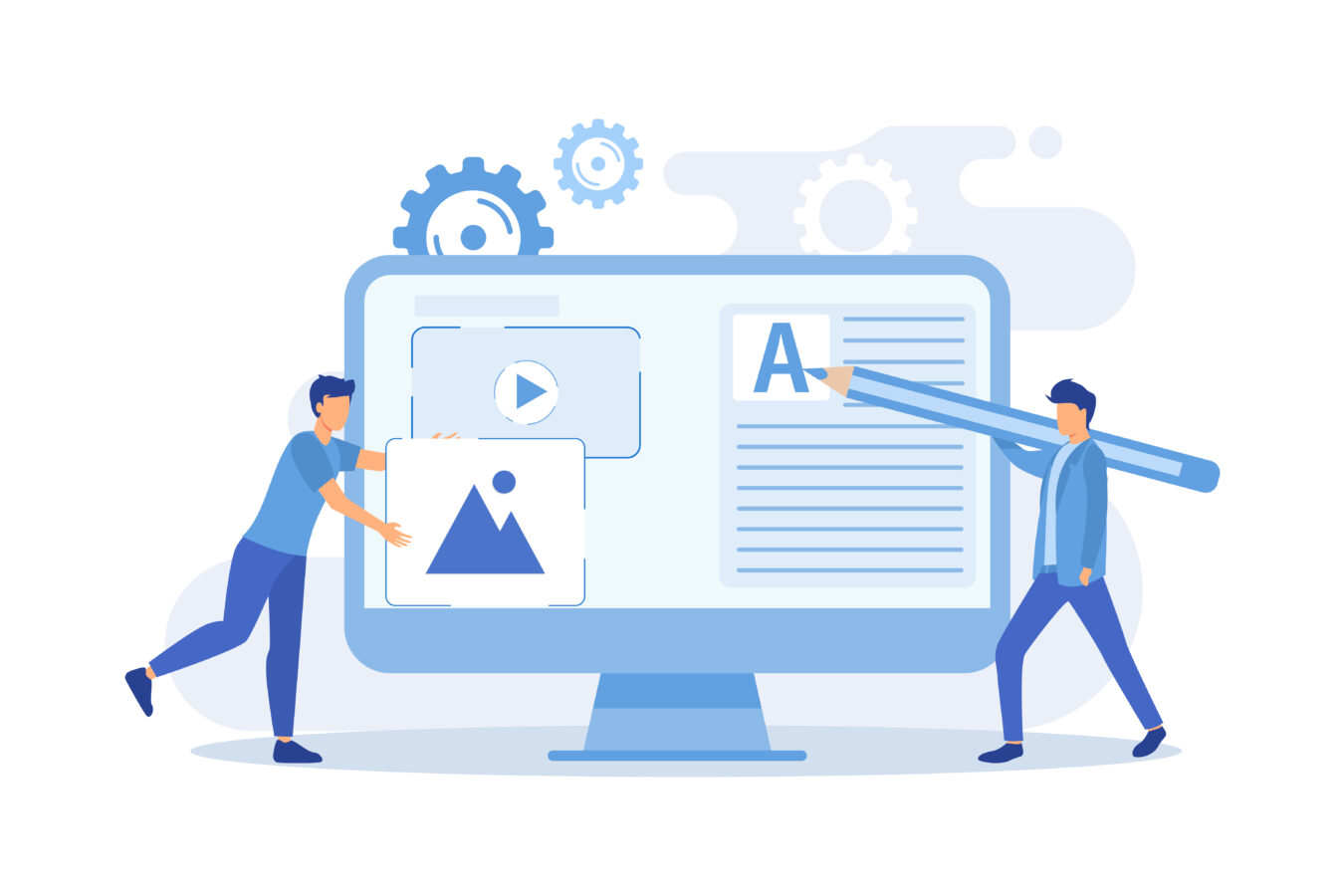
自分のブログについたコメントを削除する場合は、記事本文の画面で探すより「コメント管理」から処理するのが確実です。
コメントは記事ごとに分散しているため、どの記事に付いたか分からない状態だと、記事を探し回っても見つからないことがあります。
コメント管理なら一覧で確認でき、対象コメントを見つけたら削除へ進めます。削除操作はアプリとPCブラウザで画面の場所や表示が少し違うため、まずは利用環境を決めて手順どおりに進めるのが近道です。
また、承認制を使っている場合は「公開済」と「承認待ち」で表示が分かれ、探す場所を間違えると「削除できない」「見当たらない」と感じやすくなります。
さらに、月別や期間で絞り込みできる表示があると、古いコメントを探すときに便利です。削除前に必要なら画面保存を行い、削除後は記事側の表示やコメント数が更新されているかまで確認すると、操作ミスを防げます。
- 削除対象が「自分のブログについたコメント」か再確認する
- 公開済か承認待ちかを想定して、探す画面を決める
- 必要なら画面保存してから削除する
アプリで削除する基本手順
アプリで削除する場合は、まずブログ管理側のコメント一覧に入り、削除したいコメントを選んで操作します。
初心者がつまずくのは、記事のコメント欄に表示されるコメントを直接タップしても管理メニューが出ない、または削除項目が見当たらない点です。
アプリは「管理」からコメントを扱う前提のため、コメント管理画面に到達できているかが最初の分かれ目になります。
削除対象が古い場合は、一覧をスクロールして探すより、月別や期間の切替が使える表示を活用したほうが早いです。
削除後に「消えていない」と感じる場合は、表示の更新が追いついていないだけのこともあるため、再読み込みやアプリの再起動で確認します。
承認制の場合は、承認待ち側の一覧に残っていて公開されていないこともあるので、公開済と承認待ちの両方を確認してから判断します。
【アプリで削除する手順】
- アメブロアプリを開き、ブログ管理のメニューへ進む
- コメント管理の一覧を開き、削除したいコメントを探す
- 対象コメントの操作メニューから削除を選び、確認が出たら実行する
- 承認制の場合は承認待ち側にも切り替えて同様に確認する
- 削除後に記事側も開き、表示が更新されているか確認する
PCブラウザで削除する基本手順
PCブラウザでは、管理画面のコメント一覧から削除する流れが基本です。
PCは画面が広く、コメントの日時や投稿者などの情報を見ながら処理しやすい反面、ログイン状態が切れていて操作できないケースや、別アカウントでログインしていて削除権限がないケースが起きやすい点に注意します。
削除ボタンが出ないときは、まず自分のブログの管理画面を開けているか、対象が自分のブログへのコメントかを確認します。
PCではブラウザ拡張や広告ブロック機能の影響でボタンが反応しにくいことがあるため、反応が悪い場合は別ブラウザで試すのも切り分けとして有効です。
削除操作を行ったら、同じ画面を再読み込みして一覧から消えているか確認し、必要なら実際の記事ページも開いてコメント欄の表示を確認します。
| 確認ポイント | 内容 |
|---|---|
| ログインと権限 | 別アカウントでログインしていると削除できません。管理画面に入れるアカウントか確認します。 |
| 対象の場所 | 他ブログのコメントは削除できません。自分のブログのコメント管理を開けているか確認します。 |
| 操作反応 | ボタンが反応しない場合は再読み込み、別ブラウザ、拡張機能の影響を切り分けます。 |
月別表示と承認待ち切替で探すコツ
「削除できない」と感じる場面の多くは、実際には削除対象を見つけられていないことが原因です。
特にコメントが多いブログでは、一覧のスクロールだけで探すのは現実的ではありません。そこで有効なのが、月別や期間の絞り込みと、公開済と承認待ちの切替です。
承認制を使っている場合、コメントが公開されていないため記事側に見当たらず、承認待ち一覧にだけ存在するケースがあります。
この場合は、記事を探すのではなく承認待ち側で削除します。また、投稿日時が分かるなら、該当月に絞って探すと一気に見つけやすくなります。
投稿者名や本文の一部が分かる場合も、一覧上で目視しやすくなるため、削除作業前に「いつ頃」「どの記事」「どんな内容」かを思い出すこと自体が時短になります。
見つけた後は、同じ投稿者からの連投がないかも合わせて確認し、必要なら承認制や拒否設定へつなげると再発防止になります。
- 記事側ではなくコメント管理の一覧で探す
- 承認制なら公開済と承認待ちを切り替えて確認する
- 投稿月に絞ってスクロール量を減らす
- 投稿日時や文面の一部を手がかりに目視しやすくする
削除できない原因チェックリスト

コメントが削除できないときは、いきなり不具合と決めつけず「何が起きているか」を分けて確認すると解決が早いです。
多いのは、対象が自分のブログではなく他ブログへのコメントだった、別アカウントでログインしていた、承認待ち側に入っていて記事側に表示されていなかった、というパターンです。
次に、削除ボタンが出ない・押しても反映されない・コメント自体が見つからない、のどれなのかでチェック項目が変わります。
基本は、原因切り分け→基本チェック→環境別対処→問い合わせ準備の順で進めます。まずはログイン状態と権限、次にコメントの所在、最後にアプリとブラウザなど環境差を確認する流れにすると、迷いなく対処できます。
| 症状 | まず疑うポイント |
|---|---|
| 削除ボタンが出ない | 他ブログのコメント、別アカウント、管理画面ではなく記事画面を見ている、承認待ち側の切替漏れ |
| 削除しても消えない | 表示更新の遅れ、通信不安定、アプリやブラウザの状態、同じコメントを別画面で見ている |
| コメントが見つからない | 月や期間が違う、承認待ちにある、記事の表示が限定公開になっている、コメント受付設定の影響 |
ログイン状態と権限の確認ポイント
削除できない原因として最初に確認したいのは、ログイン状態と権限です。アメブロは複数アカウントを使い分けている人も多く、いつの間にか別アカウントに切り替わっていて、管理者として操作できないケースがあります。
削除ボタンが出ないときは、まず「自分のブログの管理画面」を開いているか、そこに入れるアカウントでログインしているかを確認します。
また、削除できるのは自分のブログに付いたコメントだけで、他ブログに付けた自分のコメントは原則として自分では削除できません。
ここが混ざると、どれだけ手順を試しても改善しません。加えて、端末やアプリのログイン情報が古くなっていると、操作の途中でログインが切れていたり、ボタンが反応しなかったりする場合があります。
その場合は、一度ログアウトしてログインし直す、別ブラウザでログインし直すなど、認証をリセットする対処が有効です。
- 削除したいコメントは自分のブログについたものか
- 管理画面に入れているアカウントでログインしているか
- ログイン切れやアカウント切替が起きていないか
コメントが見当たらない時の確認順
コメントが見当たらない場合は、探す場所を間違えている可能性が高いです。記事のコメント欄だけを見ていると、承認待ちのコメントや削除済みのコメントは表示されず、存在しないように見えます。
まずはコメント管理の一覧で探し、次に公開済と承認待ちを切り替えます。次に、古いコメントであれば月別や期間の表示を合わせ、該当月へ絞って探します。投稿者名や本文の一部、投稿時期が分かるなら、それを手がかりに一覧から見つけやすくなります。
また、コメント受付の設定によっては、特定条件のコメントが受付されず、相手側には投稿できたように見えても実際には反映されないケースがあると言われています。
そうした場合でも、公式案内がある設定項目が優先されるため、コメント受付の状態や承認制の設定を確認し、どの状態で止まっているかを整理します。
最後に、表示の更新の遅れもあり得るため、再読み込みやアプリの再起動で表示が変わるかを確認します。
【見当たらない時の確認順】
- 記事画面ではなくコメント管理の一覧を開く
- 公開済と承認待ちを切り替えて探す
- 月別や期間を合わせて該当月に絞る
- 投稿者名、本文の一部、投稿時期で目視しやすくする
- 再読み込みやアプリ再起動で表示更新を確認する
アプリ・ブラウザ差の不具合対処
削除ボタンが反応しない、削除後に一覧から消えないなどの症状は、アプリとブラウザ、端末や通信環境の差で起きることがあります。
まず基本チェックとして、通信が安定しているか、端末の空き容量が極端に少なくないか、アプリが最新版かを確認します。
そのうえで、環境を切り替えて同じ操作を試すと原因が絞れます。例えば、アプリでうまくいかないならPCブラウザで削除を試す、スマホのブラウザで試す、別ブラウザに切り替える、といった順です。
ブラウザ側でボタンが反応しにくい場合は、再読み込み、キャッシュの影響を減らすための再ログイン、拡張機能や広告ブロックの影響を切り分けるのが有効です。
削除が実行されたかどうかは、削除直後の画面だけで判断せず、コメント管理の一覧を再読み込みし、可能なら該当記事も開いてコメント欄を確認します。
それでも改善しない場合は、どの環境で再現するかをメモし、問い合わせ時に伝えられるよう整理しておくとスムーズです。
- 再読み込み→アプリ再起動→ログインし直し
- アプリで不可ならブラウザで試す ブラウザで不可なら別ブラウザ
- 同じアカウントで別端末でも再現するか確認する
- 削除後は一覧と記事側の両方で反映を確認する
迷惑コメントの予防と再発防止

迷惑コメントは、削除して終わりにすると同じ相手や同じ種類の投稿が繰り返されやすいです。再発を減らすには、コメント欄の「入口」を調整し、投稿しづらい状態を作るのが効果的です。
アメブロのコメント機能は、運用スタイルに合わせて承認制にする、会員のみ許可する、記事ごとに受付を制御するなど段階的に対策できます。
ポイントは、厳しくしすぎて普通の読者とのコミュニケーションまで止めないことです。まずは承認制や会員のみなど、影響範囲が分かりやすい設定から始め、状況に応じて拒否設定や画像認証などの強めの対策を組み合わせます。
また、内容が悪質な場合は、ブログ内の設定だけで抱えず、通報や迷惑申請などの公式の手続きに切り替えることも重要です。ここでは、初心者が迷いやすい設定の違いと使い分け、判断ラインを整理します。
- 削除だけでなくコメント受付の設定を見直す
- 影響の小さい対策から段階的に強める
- 悪質な場合は通報や迷惑申請へ切り替える
承認制・会員のみ・記事ごとの拒否設定
迷惑コメント対策でまず検討しやすいのが、承認制や会員のみなど投稿条件を変える方法です。承認制は、コメントが投稿されても即時公開されず、管理者が確認してから表示させる仕組みです。
これにより、迷惑コメントが公開されて他の読者の目に触れるリスクを下げられます。一方で、承認作業が増えるため、更新頻度やコメント数が多いブログでは負担が出ることがあります。
会員のみは、誰でも書ける状態よりもハードルが上がるため、外部からの無差別投稿を減らしやすいです。ただし、アメブロ会員以外の読者がコメントできなくなるため、読者層によっては交流が減る可能性があります。
さらに、記事ごとにコメント受付を制御できる場合は、迷惑コメントが集まりやすい記事だけを閉じる、告知記事だけ一時的に閉じるといった運用ができます。
まずは「どの記事で」「どんな迷惑コメントが」起きているかを整理し、影響が少ない設定から適用するのが現実的です。
| 対策 | 効果 | 注意点 |
|---|---|---|
| 承認制 | 迷惑コメントを公開前に止めやすく、内容を確認してから表示できます | 承認作業が増えるため、運用負担が上がる場合があります |
| 会員のみ | 無差別投稿が減りやすく、荒らし対策として扱いやすいです | 会員以外がコメントできず、交流が減る可能性があります |
| 記事ごとの受付制御 | 迷惑コメントが集まりやすい記事だけ対策でき、影響範囲を絞れます | 閉じた理由が伝わらないと読者が戸惑うため、必要なら短い案内を添えます |
画像認証や拒否設定の使い分け
承認制や会員のみでも収まらない場合は、投稿の手間を増やす画像認証や、特定の相手を受け付けない拒否設定を検討します。
画像認証は、自動投稿のような機械的な投稿を減らす目的で使われることが多く、コメント投稿時に追加の操作が必要になります。
その分、通常の読者にも手間がかかるため、いきなり常時オンにするより、迷惑コメントが増えた期間だけ強めるなど、運用で調整すると影響を抑えられます。
拒否設定は、特定の相手からのコメントを受け付けない、または表示させない目的で利用されますが、相手が名前や手段を変えてくると完全には防げないケースもあります。
いずれも万能ではないため、単体で解決を狙うより、承認制で公開を止めつつ、画像認証で自動投稿を減らし、必要に応じて拒否設定で個別に対処する、といった組み合わせが現実的です。
設定を変えたら、読者側の見え方も変わるので、実際にコメントを投稿するテストをして、想定どおりに動いているかを確認します。
【強めの対策を入れる順番の目安】
- 承認制にして公開前に止める
- 無差別投稿が多いなら画像認証を追加する
- 特定の相手が繰り返すなら拒否設定を検討する
- 迷惑コメントが落ち着いたら設定を段階的に戻す
- 設定変更後はテスト投稿で読者側の体験を確認する
通報や迷惑申請の判断ライン
迷惑コメントの中には、単なる宣伝や不快な内容を超えて、脅しや個人情報の書き込みなど、放置すべきでないものがあります。
そうした場合は、削除や設定変更だけで抱えず、公式の通報や迷惑申請などの手段を検討します。判断ラインは「読者や自分に実害が出る可能性があるか」「繰り返し性が高いか」「規約やマナーの範囲を明らかに超えているか」で整理すると迷いにくいです。
特に個人情報が含まれる場合は、拡散を防ぐためにも迅速に非表示や削除を行い、必要なら証拠として画面保存をした上で手続きを進めるのが安全です。
また、相手との直接のやり取りで状況が悪化することもあるため、反論や言い返しを優先せず、淡々と削除・設定・通報の順で対応します。
通報や申請を行う際は、どの記事のどのコメントか、何が問題かを客観的に整理しておくとスムーズです。
- 個人情報や連絡先などが書き込まれている
- 脅しや誹謗中傷など精神的・実務的な被害が想定される
- 同じ相手が設定を変えても繰り返し投稿してくる
- 宣伝や誘導がしつこく、読者体験を大きく損ねている
解決しない時の問い合わせ準備

ここまでの手順を試してもコメントが削除できない場合は、原因が「権限や画面の見間違い」ではなく、表示や操作の不具合、またはアカウント固有の状態にある可能性が出てきます。
この段階では、やみくもに同じ操作を繰り返すより、問い合わせに備えて情報を整理したほうが早く解決しやすいです。
問い合わせで重要なのは、困っている現象を第三者が再現できる形にすることです。削除できないコメントがどこにあり、何をしたらどうなったのか、どの環境で起きるのかが伝われば、案内も具体的になります。
また、悪質コメントが絡む場合は、問い合わせ前に一時的な防止策を入れて被害を広げない配慮も必要です。ここでは、発生条件の整理→画面証跡の準備→暫定対応の順で、初心者でも迷わない形にまとめます。
- 現象を言葉で説明できるように整理する
- 再現手順と環境差をメモして切り分ける
- 被害が続く場合は受付設定を一時的に強める
発生条件と再現手順をメモする
問い合わせに備えるメモは、難しく考えず「いつ、どこで、何をしたら、どうなったか」を順番に書くだけで十分です。
特にコメント削除は、記事画面とコメント管理、公開済と承認待ち、アプリとブラウザなど分岐が多く、操作の場所が違うだけで結果が変わります。そのため、再現手順は画面の入口から書き、どのボタンを押したかまで具体的に残します。
例えば「コメント管理の一覧で対象コメントを開く→削除を押す→確認でOK→一覧に残る」など、手順が追える形にします。
加えて、他の環境では起きないかを簡単に試しておくと、原因が絞れます。アプリで起きるならブラウザでも同じか、PCではどうか、別端末ではどうかのように、環境差を記録します。
コメントが「見当たらない」場合も、公開済と承認待ちを切り替えたか、月別表示を変えたかなど、探し方の経路が重要情報になります。
【メモに入れる項目】
- 対象コメントの場所 どの記事か 公開済か承認待ちか
- 症状の種類 削除ボタンがない 押しても消えない 見つからない など
- 再現手順 画面の入口から操作の流れを順番に
- 試したこと 再読み込み ログインし直し 別環境での確認
- いつから起きるか 急に起きたか前からか
端末情報と画面証跡のそろえ方
問い合わせでは、端末やアプリの環境情報があると案内が早くなります。特にアメブロはアプリ版とブラウザ版で画面構成が違うため、「アプリで起きているのか」「PCブラウザで起きているのか」が分かるだけでも切り分けが進みます。
端末情報としては、スマホの機種、OSの種類、アメブロアプリのバージョン、利用ブラウザの種類が基本です。
画面証跡は、削除できないコメントが表示されている画面、削除ボタンが出ない画面、エラー表示が出る画面など、問題が分かる箇所をスクリーンショットで残します。
スクリーンショットは、個人情報や第三者の情報が含まれる場合があるため、提出が必要な範囲だけに絞り、必要に応じて見せたくない部分は伏せる考え方も大切です。
ただし、伏せすぎると状況が伝わらないこともあるので、操作箇所やメニュー名が分かる範囲は残します。動画で残すと伝わりやすいケースもありますが、まずは静止画で十分です。
| 用意する情報 | 具体例 |
|---|---|
| 利用環境 | スマホ機種 OS アプリ版かブラウザ版か ブラウザ種類 |
| 発生画面 | コメント管理一覧 対象コメント表示 削除ボタン周辺 エラー表示 |
| 対象の特定情報 | 該当記事の日時やタイトル コメントの投稿日時など分かる範囲 |
| 試した対処 | 再読み込み 再ログイン アプリ再起動 別端末や別ブラウザでの結果 |
暫定対応 コメント受付の一時停止も検討
解決まで時間がかかりそうな場合や、迷惑コメントが連投されている状況では、暫定対応としてコメント受付を一時的に止める判断も有効です。
削除できない状態のまま放置すると、読者の目に触れて信用を落としたり、対応に追われたりする負担が増えます。
承認制に切り替える、会員のみへ変更する、対象記事だけコメントを閉じるなど、影響の範囲を見ながら一時的に強めると被害を抑えられます。
大切なのは、いきなり全面停止にせず、まずは承認制や対象記事限定での停止など、最小の影響で止められる方法から試すことです。
また、読者との交流が目的のブログでは、コメント欄を閉じることで不安に感じる人もいるため、必要に応じて「現在コメント受付を制限しています」など短い案内を添えると誤解が減ります。
状況が落ち着いたら、段階的に設定を戻していく運用にすると、コミュニケーションを完全に失わずに済みます。
- まず承認制で公開前に止める 運用負担は増えるが影響は調整しやすい
- 特定記事だけコメント受付を止めて影響範囲を絞る
- 悪質な連投が続くなら会員のみや拒否設定も検討する
- 落ち着いたら設定を段階的に戻し、再発するか観察する
まとめ
コメントが削除できない時は、まず「自分のブログについたコメント」か「他ブログにつけたコメント」かを切り分けるのが最短です。
次にコメント管理から削除手順を実行し、表示されない場合は月別表示や承認待ちの切替で探します。それでも無理なら、ログイン状態・権限・アプリ/ブラウザ差など原因チェックを進めましょう。
迷惑コメントは承認制や拒否設定で予防し、改善しない場合は発生条件・端末情報・画面を整理して問い合わせに備えるとスムーズです。