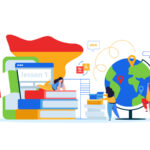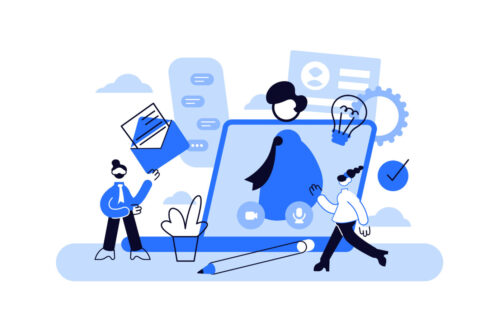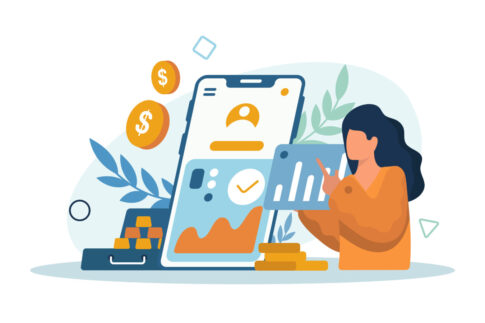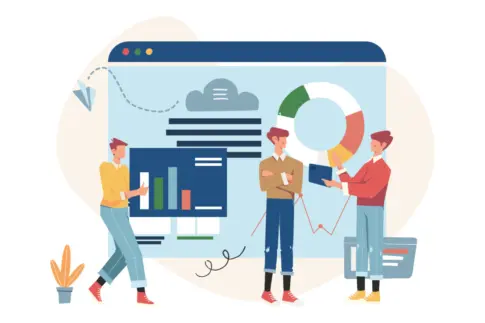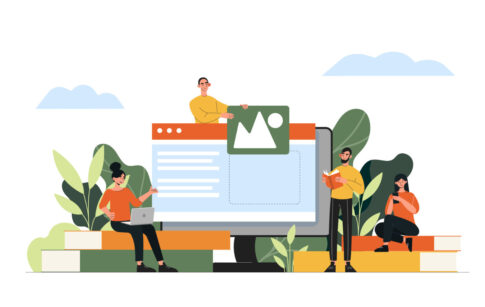公務員でもブログで副収入は可能ですが、地方公務員法の兼業規定と住民税通知のリスクを知らずに広告を貼ると発覚の危険大。
本記事では許可不要でできる情報発信・Ameba Pick活用法、稼ぎ方5選、バレない税務処理までを実例で解説。読むだけで安全ラインを見極め、アメブロ収益を着実に積み上げる方法がわかります。
目次
公務員がアメブロで収益化できる?

結論から言えば、収益化自体は可能ですが「事前に職務専念義務・信用失墜行為の禁止・兼業規定をクリアできるか」が成否を分けます。
アメブロ運営は在宅・業務外で行えるため職務専念義務に抵触しにくい半面、広告収入やアフィリエイト報酬が発生すると地方公務員法第38条が定める兼業に該当する可能性が高まります。
そこで重要なのが〈営利企業への従事許可〉を必要としない“成果報酬型ではない活動”を選択し、広告表示を控えた情報発信や電子書籍販売など、役所への届け出不要で運営できる形へ落とし込むことです。
実際には「年間数万円の講演料」や「自作ハンドメイド販売」程度なら黙認される事例もありますが、グレーゾーンのまま続けると人事課への通報や住民税通知で発覚するリスクを抱えます。よって収益モデルの選定、税務処理の方法、匿名運営の徹底が、公務員ブロガーにとっての3本柱となります。
地方公務員法と兼業許可のポイント
地方公務員法第38条は「報酬を得て営利企業の役員や従業員になること」を原則禁止し、同条第1項第2号で「報酬を得て事業を営むこと」も制限しています。
ブログ広告収入は“報酬を得る事業”に該当するため、本来は自治体の人事委員会または任命権者から兼業許可を取る必要があります。
ただし同法には「職務遂行に支障がない」「公務の信頼を失墜しない」場合に許可を与えられる裁量余地があり、近年は副業解禁の流れから許可事例が徐々に増加中です。
【許可申請の流れ】
- 所属長に口頭相談→申請書類のフォーマットを受領
- ブログ概要・収益見込額・執筆時間帯を記載
- 人事課で審査(1〜2か月)
- 許可証交付後に広告開始
| 審査項目 | チェック内容 |
|---|---|
| 職務専念義務 | 執筆が勤務時間外か |
| 信用失墜行為 | 誹謗中傷・政治活動がないか |
| 利害衝突 | 担当業務と無関係なテーマか |
- 趣味・特技のノウハウ共有
- 地域観光レポート(職務外)
- 教育・育児など公的イメージと親和性の高い内容
- 自部署の内部情報を扱う
- 政治的主張を含む記事
- 公務と競合する有料サービスの宣伝
副業判定ラインとブログ収入のグレーゾーン
副業かどうかの判定基準は「報酬の有無」「反復継続性」「営利性」の3点です。たとえば無料ブログに広告を貼らず趣味記事を書くだけなら報酬が発生しないため兼業に当たりません。
しかしGoogle AdSenseやAmeba Pickを設置するとクリック数や売上に応じた報酬を得る“営利行為”となり、兼業許可が必要になります。
【副業判定フローチャート】
- 報酬が0円→兼業外 → 記事投稿OK
- 報酬見込みあり→営利性チェック
- 反復継続性あり→兼業許可必須
| 収入形態 | 兼業許可の要否 | グレー度 |
|---|---|---|
| 広告クリック報酬 | 要許可 | 高 |
| 講演料 | ケース判定 | 中 |
| 印税・電子書籍 | 要許可 | 中 |
| 寄付ボタン | 要許可 | 高 |
【実例で見るグレーゾーン】
- 毎月広告表示→反復継続あり→許可対象
- 職員研修で得たスキル記事→広告なし→趣味と判断され許可不要
- 休日に書籍化し印税10万円→単発収入でも営利性が高く許可必要
- 広告開始前に試算表を作り人事課へ相談
- 匿名+顔出しNGで個人特定を防ぐ
- 収益が伸びる前に確定申告と住民税“普通徴収”に切替
- 住民税の特別徴収で副収入がバレる
- 銀行口座へ広告報酬が振込まれる証跡が残る
- 兼業許可なしで懲戒処分リスク
グレーゾーンを避けるには、まず副業判定ラインを超えないモデルで試運転し、収入が増え始めたら速やかに兼業許可を取得するのが安全策です。
次章では許可不要で始められる稼ぎ方5選を紹介し、公務員でもリスク低く収益を得る方法を具体的に解説します。
公務員でも許可不要でできる稼ぎ方5選

兼業許可を取らずに始められる方法の共通点は「報酬の発生源が自治体外の営利企業ではなく、記事から直接お金を受け取らない」ことです。
ここでは〈1〉講演・セミナー依頼を生む情報発信、〈2〉自作テンプレート・ノウハウ資料の無償公開→後日有料販売、〈3〉電子書籍のロイヤリティ受取(紙書籍印税同様に許可不要判定が多い)、〈4〉ふるさと納税返礼品レビューで地域からPR謝礼を受けるケース、〈5〉自治体外の学術雑誌への寄稿料獲得──の5つを取り上げます。
いずれもブログ記事そのものには広告を付けず、成果報酬型にしないことで「営利企業従事」に該当しにくいのがポイントです。
| 方法 | 許可不要になりやすい理由 | 収益化ステップ |
|---|---|---|
| 講演依頼 | 自治体・学校など公共性が高い | 専門記事→プロフィール公開→依頼フォーム設置 |
| 電子書籍 | 「著作権収入」は紙書籍印税同様の扱い | 連載記事を再編集→Kindle出版 |
| 資料販売 | 一次情報+自作物は営利企業への従事に当たらず | 無料配布→高機能版をnoteで有料 |
| 寄稿料 | 学術・業界誌は職務関連性が低い | 専門コラム掲載→定期連載化 |
| 地域PR謝礼 | 観光協会など非営利団体からの謝礼 | 地域レポ記事→招待取材→謝礼 |
- 広告タグを貼らず成果報酬型にしない
- 自治体・公共団体と連携し社会貢献性を示す
- 金銭授受は1件ごとに領収書を残し透明性を担保
- 職務と関連が深いテーマは「利害相反」と判断される場合あり
- 年間20万円超なら確定申告と住民税普通徴収を必ず実施
- ブログ内で民間企業のPR記事を書くと営利従事扱いになる恐れ
広告表示しない情報発信で講演依頼を得る
公務員が最も安全に収入を得やすいのが「専門知識を無料公開→講演・研修依頼を受ける」モデルです。ブログにはバナー広告を一切貼らず、経験談・統計データ・行政施策の背景など公共性の高い情報を発信します。
記事末尾に〈プロフィール〉と〈お問い合わせフォーム〉を設置しておくと、自治体や学校、NPOから講演オファーが届く確率が上がります。講演料は自治体同士の謝金規程に準じて1〜3万円程度が相場で、単発・事業外収入として認められるケースがほとんどです。
【講演依頼を生みやすい記事構成】
- 冒頭:課題提起(例「地域防災で○○が課題です」)
- 本文:現場で得た実例+数値データ
- まとめ:読者が実践できるアクション3つ
- CTA:講演・研修依頼はこちら→フォーム
| チェック項目 | 推奨設定 | リスク回避 |
|---|---|---|
| プロフィール | 部署名ではなく「地方自治体職員」と表記 | 勤務先特定を避ける |
| 謝金受取 | 自治体振込:公務員向け講師謝金科目 | 人事課事前相談で不安を解消 |
| 公開資料 | 統計は出典明記・守秘情報を削除 | 情報漏えい防止 |
- 広告表示ゼロで兼業リスクが低い
- 専門性アピールで昇進面談でもプラス材料
- 1時間講演でブログ広告数ヶ月分の収益が得られる
- 職務中撮影の写真を無断掲載しない
- 同僚や住民が特定できる個人情報を記載しない
- 年間講演収入が20万円超→確定申告必須
アメブロ公式アフィリエイトAmeba Pickの注意点
Ameba Pickは記事内に楽天・Amazon商品を簡単に貼れる公式アフィリエイト機能ですが、公務員が利用する場合は「報酬が成果報酬型広告である」ため兼業許可が必要になるのが最大の落とし穴です。
クリックや購入額に応じて運営から直接報酬が支払われる仕組みは、地方公務員法上の「営利企業への従事」に該当しやすく、黙って使うと処分リスクが高まります。
【利用前に確認すべき3ポイント】
- 人事課に「アフィリエイト報酬=広告料」と説明し兼業許可申請
- 年間予想収益を低め(1万円未満)に見積もり、まずは試用許可を得る
- 広告ラベル(PR)を自動表示→ステルスマーケティング防止
| リスク要素 | 具体的な問題 | 回避策 |
|---|---|---|
| 成果報酬 | 月3万円超で営利性が高いと判断 | 月上限を設定し売上超過前に広告停止 |
| 広告審査 | コンプライアンス違反商品リンク | 医薬品・成人向け・ギャンブル商材を避ける |
| 税務 | 特別徴収で副収入が自治体に通知 | 確定申告で住民税を普通徴収へ切替 |
- レビュー記事は自費購入品に限定→広告色を薄める
- 月収が増えたら許可範囲を超えないうちに法人化や家族名義へ移行
- 売上データを月次で人事課へ報告し透明性を確保
- 許可なしで広告貼り付け→収益振込→住民税で発覚
- 知人のショップ商品を大量紹介→利害関係を疑われる
- 広告ラベルを削除してステマ判定→信用失墜行為
Ameba Pickを使う場合は、まず兼業許可を正式に取得し、収益が想定外に伸びる前に報酬管理と税務処理を整えることが不可欠です。許可不要のモデルと組み合わせてリスクを分散すると、安全な副収入ポートフォリオを構築できます。
収益化ステップ:準備→記事執筆→集客→マネタイズ
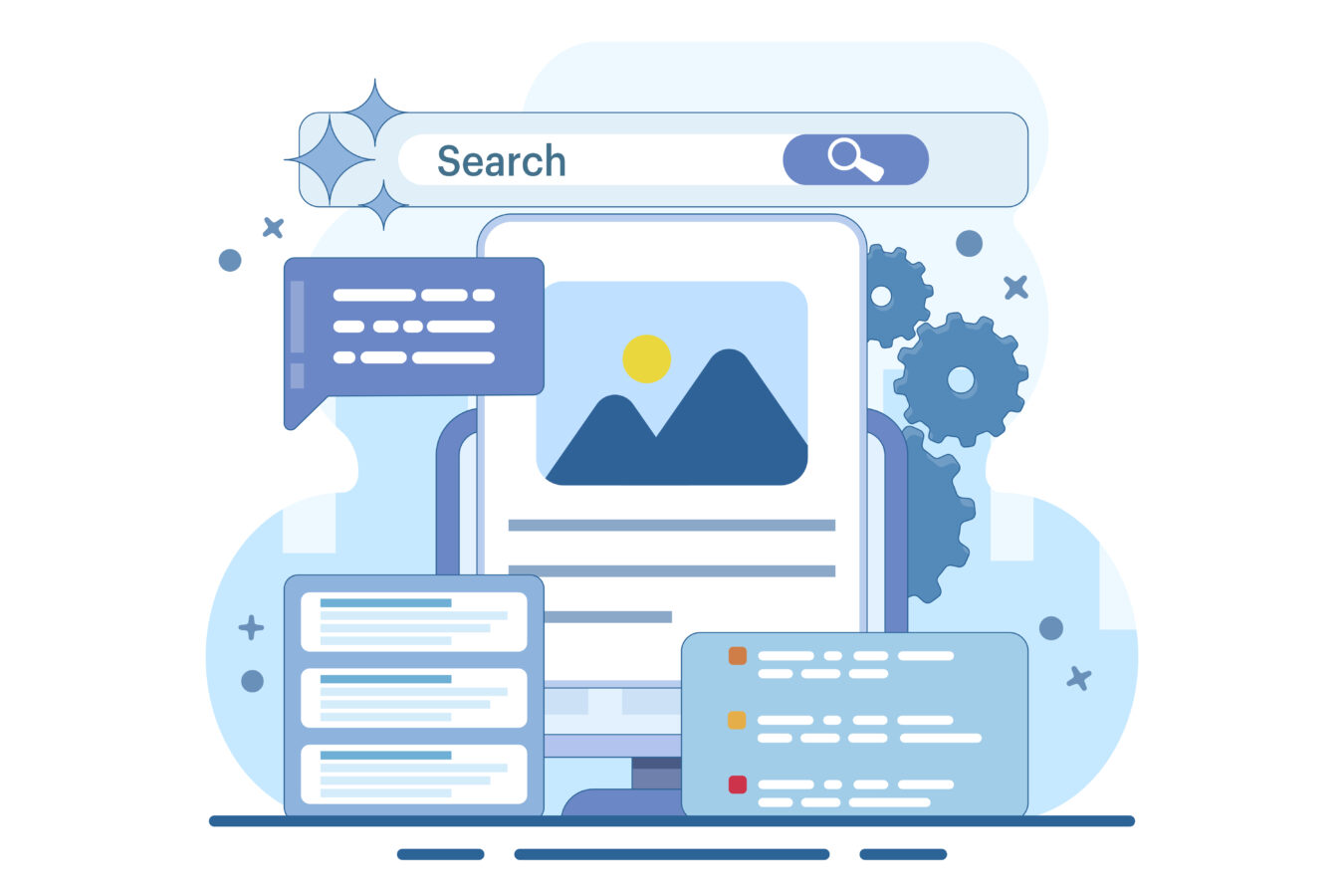
公務員がアメブロで安全に稼ぐには「副業リスクの棚卸し→ニッチテーマ決定→検索流入を狙う記事量産→マネタイズ設計→会計・税務処理」の5段階で進めると失敗がありません。
準備段階では兼業許可の要否を判断し、許可不要モデル(講演・寄稿・電子書籍など)と許可取得必須モデル(広告・アフィリエイト)を組み合わせてポートフォリオを作成します。
記事執筆では検索ボリューム1,000以下のロングテールを狙った“ニッチ戦略”が王道。週1本ペースで3か月続けるとGoogleの再評価が入り、月間PVが緩やかに上昇します。
集客期にはSNSと内部リンクを活用し、記事同士をクラスター化。最後に講演・資料販売・広告など複数導線を設置してマネタイズを開始します。
こうして得た報酬は住民税普通徴収に切替え、年間20万円超なら青色申告承認申請書を提出し65万円控除を受けると税負担を最小化できます。
| フェーズ | 主なタスク | 重要KPI |
|---|---|---|
| 準備 | リスク分析・テーマ決定 | 副業許可の有無 |
| 記事執筆 | ロングテール記事量産 | 週1本更新×12週 |
| 集客 | SNS連携・内部リンク | 月PV3,000 |
| マネタイズ | 講演・Ameba Pickなど導入 | 月収1万円突破 |
| 会計・税務 | 普通徴収・青色申告 | 税率15%以下維持 |
- 兼業許可はPVが伸びる前に申請し時間を確保
- テーマ記事30本でクラスター完成→次テーマへ横展開
- 税務はクラウド会計を早期導入し手間を最小化
ニッチテーマ選びとキーワードリサーチ法
公務員ブロガーが勝ちやすいのは「専門知識×読者ニーズ」が重なるニッチ分野です。たとえば〈公共施設管理の裏側〉〈地域おこし成功事例〉〈災害対策マニュアル〉など、民間ライターが書きにくいテーマは競合が少なく、上位表示までの期間も短縮できます。
【リサーチの具体手順】
- Googleキーワードプランナーでメインワードを検索
- ボリューム100〜1,000の候補をCSVでDL
- 「とは」「方法」「チェックリスト」など行動キーワードをフィルタ
- 競合タイトルをSERPで確認→同テーマが3本以下なら狙い目
- 30候補をTrelloやNotionに整理し投稿計画を作成
| 選定基準 | 目安数値 | 理由 |
|---|---|---|
| 検索ボリューム | 100〜1,000 | 流入と競合のバランス |
| 競合数 | トップ10中公式サイト2本以下 | 個人でも上位化しやすい |
| CPC | 50円以上 | 広告単価が高く収益性◎ |
- 1記事1キーワード主義で内部リンク強化
- 同じ悩みを角度違いで解決する“横展開”戦略
- 自治体公開資料を引用し一次情報の信頼度UP
- 職務上の内部情報→守秘義務違反リスク
- 政治的主張中心→信用失墜行為で懲戒の恐れ
- 検索ゼロの個人日記→集客が伸びない
広告換金前にやるべき会計・税務管理
収益が発生したら「住民税通知でバレない」対策と節税準備を同時に進めます。まずGoogle AdSenseやAmeba Pickの報酬が確定した時点でクラウド会計ソフト(freee・マネーフォワード)に取引登録を開始。事業所得として経費を計上することで課税所得を圧縮できます。
【税務チェックリスト】
- 確定申告区分:雑所得→事業所得へ早めに移行
- 住民税:確定申告書第二表で“自分で納付=普通徴収”を選択
- 青色申告:承認申請書を3月15日までに提出→65万円控除
- 納税資金:収益の30%を別口座にプール
| 項目 | 手続き | 提出時期 |
|---|---|---|
| 開業届 | 屋号なしでOK | 収益化から1か月以内 |
| 青色申告承認 | e-Taxまたは税務署窓口 | 3/15(新規は開業2か月以内) |
| 普通徴収選択 | 確定申告第二表に◯印 | 確定申告提出時 |
- 取材交通費・書籍代・クラウド会計月額
- パソコン減価償却(10万円以上)
- サーバー・ドメイン・画像素材
- 普通徴収を選ばず特別徴収→給与課へ副収入通知
- 銀行口座を給与振込と同一にし経理混在
- 税理士に依頼せず期限後申告→無申告加算税
換金前に会計・税務の土台を固めれば、収益が拡大しても慌てることなくスムーズに申告できます。安全ラインをキープしつつ、本業に支障のない副収入を着実に育てていきましょう。
バレないためのリスク管理とトラブル回避策

公務員が副収入を得る際に最も警戒すべきは「身バレ」と「税務バレ」の二 大リスクです。身バレは読者や同僚からの突き合わせで個人が特定され、SNS拡散や職場通報に発展するケース。
税務バレは住民税の特別徴収ルートから人事課に副収入が知られるケースで、いずれも懲戒処分や信頼失墜につながります。
ここでは、匿名運営を徹底するプロフィール設定、税金手続きで情報が流出しないルート確保、収益と経費の記録を透明化しておく3段階のリスク管理フレームを提示します。さ
らにコメント対応や情報開示請求への備えなど、実際に起こりやすいトラブル事例と回避テクニックも紹介し、公務員ブロガーが安心して長期運営できる環境づくりをサポートします。
- 匿名運営でプロフィールを最小公開
- 税務は普通徴収+開業届で分離処理
- 収益レポートを月次保存し不正疑惑を防止
実名・勤務先を特定されないプロフィール設定
プロフィールから個人情報が露見すると読者→SNS→勤務先という経路で拡散リスクが発生します。最小限に抑えるべき情報は「本名」「自治体名」「担当部署」「顔写真」の4項目です。
ニックネームは業務と無関係の趣味・ペット名などを用い、アイコンはフリー素材・イラストACなどのオリジナルイラストを採用しましょう。
【匿名プロフィール作成フロー】
- ニックネームを決定(例:CityCat)
- フリーイラストをCanvaで丸抜きしアイコン化
- 自己紹介は「地方自治体職員」と幅広い表現に留める
- 勤務年数・部署をぼかし「公共サービスに従事」の一文
- お問い合わせフォームはGmail+匿名SNSリンクのみ
| プロフィール項目 | 安全な書き方 | NG例 |
|---|---|---|
| 肩書き | 「地方自治体職員」 | 「◯◯市役所 建設課」 |
| 写真 | イラスト・後ろ姿 | 顔写真・職員証 |
| 経歴 | 「公共インフラ計画に従事」 | 「道路整備係 10年」 |
- 住んでいる県名は書かず地方区分で表記
- 記事内の写真はExif情報を削除
- SNS連携時は投稿時間帯をランダム化
- 勤務先サイトと同じ文章をコピペ→検索で一致
- SNSで「今日議会でした」とリアルタイム投稿
- 顔を隠したつもりでも背景に庁舎が写り込み
住民税通知で発覚しないための税金手続き
副収入が20 万円を超えた場合は確定申告が必須ですが、その際に「住民税を特別徴収(給与天引き)」にすると自治体の給与担当へ副収入額が通知され、身バレの引き金となります。これを避けるには「普通徴収」を選択して自分で納付する形に切り替えます。
【普通徴収へ切替える手順】
- 確定申告書第二表「住民税に関する事項」へ移動
- 『給与・公的年金以外の所得にかかる住民税の徴収方法』で「自分で納付」に○を付ける
- e-Tax提出後も申告控えをPDF保存→人事課へ提出を求められた際に説明資料として提示できる
- 6〜7 月に自治体から届く住民税納付書で自宅近くの金融機関かコンビニで納付
| 手続き | 必要書類 | 提出期限 |
|---|---|---|
| 確定申告 | 青色申告決算書・申告書B | 毎年3月15日 |
| 普通徴収選択 | 申告書第二表のみ | 確定申告時 |
| 青色承認 | 開業届・承認申請書 | 開業2ヶ月以内 |
- 副業用の銀行口座を分け入出金を一本化
- クラウド会計で月次損益を自動集計し証跡を残す
- 納税資金を収益の30%プール→納付漏れ防止
- 税務署へ行かずe-Taxだけで済ませ領収証書を保存しない
- 普通徴収に○をつけ忘れ特別徴収で自動通知
- 報酬支払調書が勤務先に届きダブルチェックで発覚
プロフィールの匿名性と税金手続きを適切に行えば、公務員でも安心してアメブロ収益化に取り組めます。最後に、これまで解説したステップを念入りにチェックし、リスクを抑えた副業ライフを実現しましょう。
まとめ
公務員がアメブロで稼ぐ鍵は「兼業許可ラインの把握→許可不要のマネタイズ→税務・個人情報管理」の3工程です。
広告表示より講演・電子書籍など“成果報酬型”を選び、住民税を普通徴収に変更すれば発覚リスクを最小化できます。本記事の手順を参考に、規定を守りつつ副収入を安全に育てていきましょう。