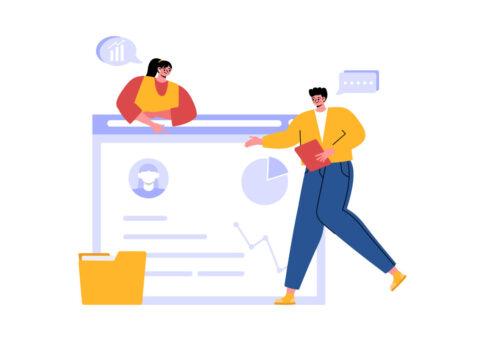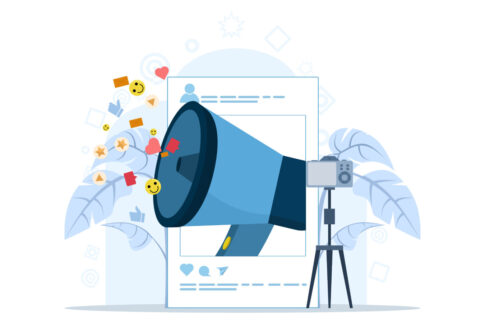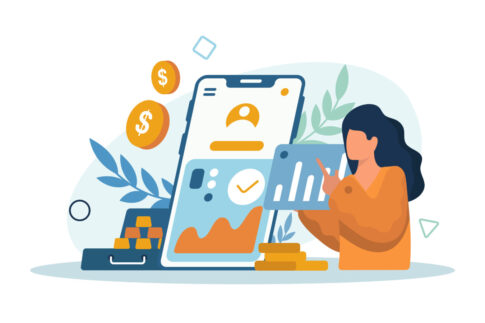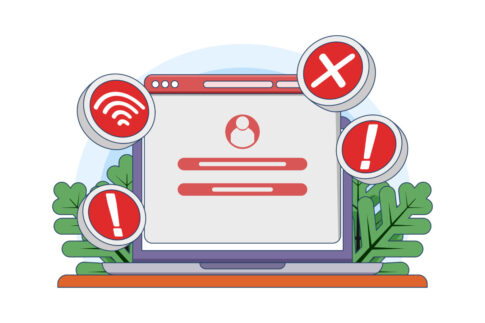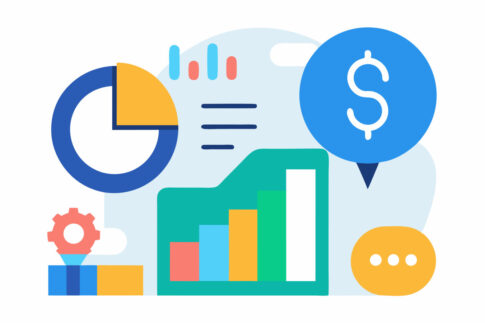アメブロで収益化する第一歩はAmebaPickの審査通過です。本記事では「審査基準の全体像→申請前の禁止事項→通過率を上げる運用→不承認時の見直し→審査後の注意点」を、落ちないための必須10項目としてやさしく解説していきます。実例ベースのチェック観点をご紹介していきます。
目次
AmebaPick審査基準

AmebaPickの審査は、ブログが「安全で信頼でき、読者に役立つ情報を継続的に提供しているか」を多面的に確認するプロセスです。
具体的には、運営実態(プロフィールや連絡手段が整っているか)、コンテンツ品質(独自性・正確性・網羅性)、ポリシー適合(規約・ガイドライン・表記ルールの順守)、表示面の健全性(広告過多や外部タグの負荷がないか)、技術面(リンクが正常に動作し、読み込みに支障がないか)といった観点で見られます。
とくにAmeba内のアフィリエイト機能であるAmebaPickは、読者の利便性と透明性が重視されます。記事の主役は「情報・体験・解決策」であり、広告やリンクはそれを補助する立ち位置にとどめるのが基本です。
以下の表で、代表的な審査観点と確認ポイントを整理しました。これらを満たしたうえで、更新頻度や内部導線(関連記事・目次・カテゴリ)を整えると、読みやすさと信頼性が高まり、審査でもプラスに働きます。
| 観点 | 見るポイント | 整備のヒント |
|---|---|---|
| 運営実態 | プロフィール/問い合わせ/方針の明確さ | 自己紹介・連絡先・運営方針を固定ページ化 |
| 品質 | 独自性・正確性・読者課題の解決度 | 一次情報/体験/比較表で価値を明示 |
| 適合 | 規約/ガイドライン/表記ルール順守 | PR/広告の明示・引用出典の明記 |
| 表示 | 広告過多・外部タグの過負荷の有無 | 広告は必要最小限・配置は本文を邪魔しない |
| 技術 | リンク/画像の動作と可読性 | リンク切れ/画像最適化/目次導線の整備 |
- プロフィール・問い合わせ・ポリシーページの整備
- PR/広告の開示と紛らわしくない表現
- 独自性の高い記事を定期更新→内部リンクで回遊を設計
参加要件と対象ブログの整理
まずは「参加できる状態」にブログを整えることが前提です。ブログ自体が公開設定で、通常の閲覧・投稿が問題なく行えること、Amebaの利用規約や各種ガイドラインに反しない運用であることが大枠の要件です。
あわせて、運営者情報が曖昧なブログは信頼性が下がるため、プロフィール(運営者名/活動内容/得意分野)を充実させ、問い合わせ手段(フォームやメール)を明示しておきます。
プライバシーポリシーや免責の整備も、広告やアフィリエイトを扱うブログでは実質的に必須と考え、固定ページとして常時アクセスできるようにしましょう。
対象ブログのテーマは一貫性が重要です。美容なら美容、育児なら育児といった主軸を定め、カテゴリやタグ設計も主軸に沿って整理します。雑記型でも「読者が何を得られるか」が明確であれば問題ありません。
記事は独自の体験・写真・検証を交え、他サイトの焼き直しにならないようにします。リンクは、AmebaPickの導入を前提に「本文の文脈に自然に溶け込む導線」で配置し、ボタン連打や誘導文の過剰強調は避けます。
最後に、モバイル閲覧を基準にレイアウトを確認し、フォントサイズ・行間・画像幅を整えると、離脱を防ぎやすく審査印象も良くなります。
- 公開設定・基本機能が正常→下書きでテスト投稿
- プロフィール/問い合わせ/ポリシーを固定ページ化
- 主軸テーマとカテゴリ体系を統一→回遊導線を設計
コンテンツ品質とポリシー適合
コンテンツは「独自性」「正確性」「読者メリット」を核に設計します。商品の紹介なら、仕様の引用元や比較条件を明示し、メリットだけでなく注意点も併記して読者の判断材料を増やします。
口コミの転記だけに頼らず、自身の使用感や撮影画像、検証手順など一次的な要素を入れると、独自性が自然に高まります。
表現面では、誤解を招く断定・過度な誇張・根拠不明の数値は避け、引用は最小限・出典を明確にします。
ポリシー適合の観点では、禁止領域(誹謗中傷/違法行為助長/成人向け/差別的表現など)は当然NGです。
アフィリエイト表記は読者に明確に伝わる位置と書き方で行い、本文と広告の境界が曖昧にならないよう工夫します。広告やリンクが本文より目立つ配置、折り込みすぎのボタン、スクロール阻害のポップアップは、可読性と信頼性を損ないます。
技術面では、リンク切れ・画像404・遅延読込の不具合を放置しないこと、スマホでの表示を優先して見出し階層と段落を整えることが大切です。
仕上げとして、内部リンクで関連情報へ誘導しつつ、外部リンクは権威性のある参照に限定し、記事末尾には読者の次の行動(関連記事・カテゴリ・問い合わせ)を自然に提示します。
- 無断転載や過度な引用→独自要素や出典明記で回避
- 誤解を招く断定・過剰な煽り→根拠提示か表現の中立化
- 広告過多や強引な誘導→本文を主役に、広告は補助へ
申請前チェック|禁止事項の把握

AmebaPickの申請前に最優先で確認したいのは「規約・ガイドラインに抵触しないこと」と「読者が誤解しない表示」です。
ここでいう禁止事項は、法令や一般ルールに反する表現だけでなく、著作権・商標・肖像・プライバシーの侵害、過度な誇大表示、医療・美容・投資などでの根拠不十分な断定、アダルト/暴力的内容、差別的表現、危険行為の助長などを含みます。
画像や引用の扱い、レビューの書き方、広告の見せ方は小さな見落としで不適合になりやすい領域です。
実務では「素材の権利確認→表現の中立化→広告と本文の区別→連絡・ポリシー整備」の順に点検すると抜け漏れを抑えられます。とくにAmebaPickのリンクは本文の補助にとどめ、誘導文が過度に先行しないようにします。
最後に、未成年を含む第三者情報や個人が特定できる記載は掲載前に削除・匿名化し、問い合わせ先・プライバシーポリシーを固定ページで示すと信頼性が高まります。
| リスク領域 | 申請前に見るポイント |
|---|---|
| 権利侵害 | 画像・ロゴ・地図・歌詞・引用の出典と利用条件を確認→許可/ライセンスの有無を明確化 |
| 不適切表現 | 根拠が曖昧な断定(最安・必ず・劇的など)を中立表現へ修正→数値は出典付き |
| 広告表示 | 本文と広告の境界を明示→リンク付近や冒頭に広告/PRの表記を付し誤認防止 |
| 個人情報 | 顔・氏名・連絡先・位置情報の扱いを最小化→同意のない公開は回避 |
- 素材の出所と利用条件をメモ化→後から証跡参照可に
- 断定・煽りを事実ベースに修正→比較条件も明記
- 広告/PRの表記を記事冒頭またはリンク近くに明示
権利侵害・不適切表現の洗い出し
権利と表現のチェックは、AmebaPick審査でつまずきやすい箇所です。まず画像・図版は「自作/購入素材/提供素材/引用」のいずれかを明確化し、購入や提供素材は利用範囲(商用可・改変可・クレジット要否)を再確認します。
企業ロゴや商品画像は、提供元の素材ガイドラインに従い、二次配布や改変禁止の条項がないかを見ます。地図・スクリーンショットはサービスごとの利用条件が異なるため、クレジットや埋め込み方法を守るのが安全です。
引用は必要最小限にとどめ、出典(サイト名/ページ名など)を明示し、本文の主従関係を保ちます。レビューや体験談では、効果の断定や誤認を招く比較を避け、再現性のない表現は「個人の感想」等で中立化します。
医療・美容・健康・金融などのセンシティブ領域は、根拠のない数値・保証・結果の断定を避け、出典のある統計や公式情報を優先します。
第三者の顔・氏名・連絡先の掲載は事前同意がなければ避け、未成年の情報はぼかし・匿名化を徹底します。
最終確認として、タイトル・見出し・アイキャッチの三点を横並びで見て、過度な煽りや誤認の余地がないかをチェックします。
| 項目 | チェック観点(例) |
|---|---|
| 画像・図版 | 商用可/改変可/クレジット要否、ロゴ使用可否、スクショの条件、地図の帰属表示 |
| 引用・転載 | 必要最小限・主従関係・出典明記・改変なし |
| 表現 | 最安/必ず/確実/劇的等の断定を中立化→比較条件・根拠・数値の出所を明示 |
| 個人情報 | 顔/氏名/位置情報/連絡先の公開可否→匿名化・同意の確認 |
- 他社LPやECの商品画像を無断流用→提供素材以外は避ける
- 統計やグラフの再掲載→出典と引用条件を確認
- 体験談の断定表現→個人差の明示と事実ベースへ修正
広告バランスとリンク表記
AmebaPickのリンクは「本文の理解を助ける補助」として配置するのが基本です。記事冒頭やリンク周辺で広告/PR等の表記を明示し、本文より広告が目立つ構成は避けます。
折りたたみの直前直後にボタンを多段配置すると誤クリックを誘発するため、本文の流れに合わせた最小数に絞りましょう。
価格や在庫の記載は変動しやすいので、日付や条件を併記して誤認を防ぎます。ランキング・比較記事では、選定基準(評価軸)を本文内に短く示し、広告枠が順位を左右しないことを明確化します。
計測タグやバナーを多重に入れると読み込みが遅くなり離脱を招くため、主要計測は一本化し、装飾は軽量に保ちます。
リンクテキストは「商品名+用途」など内容が推測できる文言にし、クリック後の体験を想像できるようにします。
外部リンクは安全性と遷移先の有効性を定期点検し、切れたリンクは速やかに差し替えます。アフィリエイトの存在を隠す表現や、公式と誤認させる文言(公式最安・唯一無二保証など)は避け、レビューではメリットと注意点をセットで提示すると信頼が高まります。
| 配置ルール | 実践ポイント | 期待できる効果 |
|---|---|---|
| 本文優先 | 情報→理解→判断の流れを妨げない位置に最小数配置 | 可読性向上・離脱低下・審査での印象改善 |
| 識別可能 | 広告/PR等を冒頭やリンク近くに明示→誤認を防止 | 透明性の担保・苦情/否認リスクの低減 |
| 軽量表示 | 計測は主軸のみ、重いウィジェットは削減 | 読み込み改善・回遊率向上 |
- 広告/PRの明示→リンク近くか冒頭でわかるように
- ボタン連打の多段配置を回避→本文の流れを優先
- 価格・在庫は変動前提→日時や条件を添えて誤認防止
通過率を上げる運用ポイント
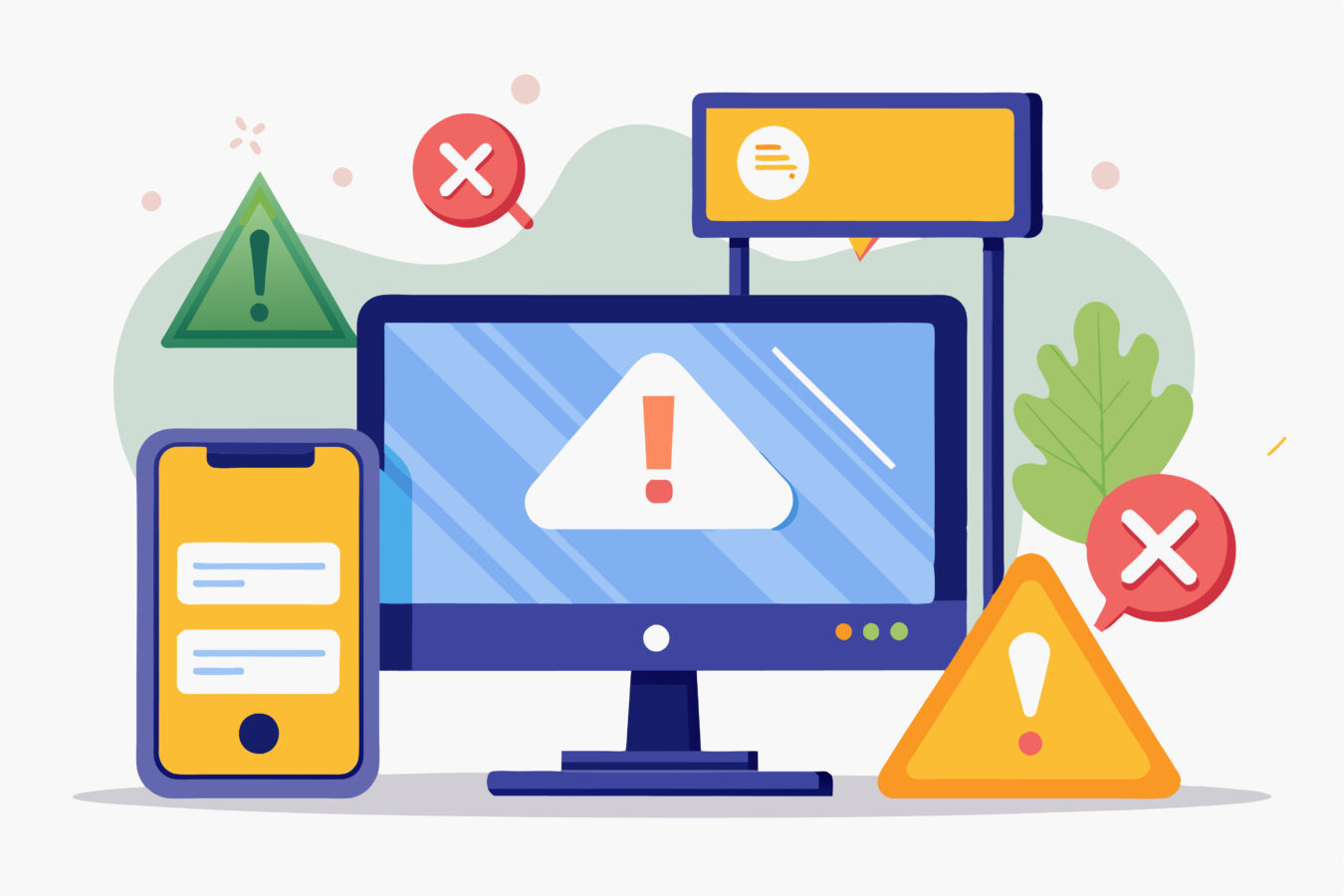
AmebaPickの審査は、単発の“良い記事”よりも「安定した運用=読者に価値が届く仕組み」を重視します。通過率を上げる近道は、テーマの一貫性を軸に、価値が伝わる見せ方と回遊しやすい導線を整えることです。
まず、主軸テーマを決めたうえで記事群を計画し、各記事に役割(入門・比較・体験・Q&A・レビュー)を持たせます。
次に、記事内で何が分かるのかを冒頭で明示し、根拠や注意点を添えて“誤解のない情報提供”を徹底します。
最後に、関連記事への内部リンクや目次、カテゴリ整理で読み進めやすくし、広告は本文の理解を助ける範囲に抑えます。
下表を参考に、審査前に運用の土台を整えておくと、読みやすさ・信頼性・透明性が同時に高まり、審査印象が安定します。
| 項目 | 改善アクション | 審査での見え方 |
|---|---|---|
| テーマ設計 | 主軸を決めて記事群を計画→入門/比較/体験を配置 | 一貫性があり読者価値が伝わる |
| 本文構成 | 冒頭に結論/目的→根拠→注意点→行動の順で整理 | 誤解が少なく透明性が高い |
| 内部導線 | 関連記事・目次・カテゴリで回遊を最適化 | 読みやすく離脱が少ない |
| 広告配置 | 本文の補助に限定→PR表記を明確化 | 可読性と信頼性が担保 |
- 主軸テーマと記事役割の棚卸→不足パートを補完
- 各記事の冒頭で読者メリットを明示→誤認を防止
- 内部リンクと目次で回遊を設計→広告は最小限
テーマ一貫性と読者価値の可視化
審査で評価されやすいのは「何について、誰に、どんな価値を届けるか」が即座に伝わるブログです。まず主軸テーマを一つ定め、そこから派生するサブテーマを記事群として組み立てます。
たとえば「敏感肌のスキンケア」を主軸にするなら、入門(基本の選び方)→比較(成分別の違い)→体験(使用レビュー)→Q&A(よくある悩み)→注意点(パッチテスト等)と役割を分け、各記事を相互に内部リンクで結びます。
本文では冒頭で「この記事で分かること」を短文で示し、結論→根拠→注意点→行動の順に並べると、読者にとって価値が可視化されます。
レビューでは良い点だけでなく“合わなかった点”も併記し、再現性の低い表現は避けます。画像は実物写真や比較表を用いて事実ベースで補足し、価格や在庫など変動要素は日付や条件を添えて誤解を防ぎます。
最後に、次に読むべき関連記事(入門→比較→体験…)を自然な流れで提示すれば、回遊が生まれやすく、審査でも「読者中心の設計」と評価されます。
【可視化の方法】
- 冒頭に「この記事で分かること」→期待値を整える
- 結論/根拠/注意点/行動の順で読みやすく整理
- 関連記事の導線を本文内に自然に配置→回遊を促進
- 雑記化で主軸が不明→カテゴリ名と記事役割を再定義
- 良い点のみ強調→注意点も併記して中立性を担保
- 画像が大きすぎて遅い→掲載幅に合わせて軽量化
更新頻度・内部導線の最適化
更新頻度は“多ければ良い”ではなく“継続して価値を更新できているか”が重要です。週の投稿本数を無理なく続けられる水準に設定し、未成熟な記事を急ぎ量産するよりも、既存記事の追記・比較表の刷新・最新情報の反映で質を底上げします。
内部導線は「読者が次に迷わない」ことが目的です。目次で内容を俯瞰できるようにし、本文末には「関連する次の記事」を2〜3本に厳選して配置。
カテゴリは広すぎる名称を避け、主軸テーマに沿って階層を整理します。レビュー記事→比較記事→入門記事の順に往復できるリンク網を作ると、学習の流れが途切れません。
広告やAmebaPickのリンクは本文の理解を助ける位置に最小限配置し、PR表記を明確にして誤認を防ぎます。表示が重いパーツは下部へ移し、テキストの読み始めを阻害しない構成にすると、体感速度と回遊が同時に改善します。
| 施策 | 実践ポイント | 期待できる効果 |
|---|---|---|
| 更新頻度 | 無理のない週次計画→新規とリライトを半々に配分 | 品質の平準化・継続性の担保 |
| 内部リンク | 入門↔比較↔体験の三方向に往復導線を設置 | 回遊増・読了率向上 |
| 目次とカテゴリ | 見出しを整理→カテゴリは主軸に沿って再編 | 迷いの減少・検索意図への整合 |
| 広告最適化 | 本文の補助に限定→PR明示→重いウィジェット削減 | 可読性と信頼性の維持 |
- 新規1本+リライト1本→品質と鮮度を両立
- 公開後に内部リンク/関連記事/目次を必ず点検
- リンク切れ・表示崩れを週次でチェック→修正を即反映
不承認時の見直しと再申請

AmebaPickの審査で不承認になった場合は、原因を感情的に捉えず「仮説→検証→再提出」の流れで客観的に整えることが近道です。
まず、直近の申請内容とブログの状態を時点固定します。具体的には、申請時のトップ/代表記事/プロフィール/ポリシー/広告配置/リンク表記のスクリーンショットやURLを控え、いつ・何を・どう直したかを履歴化します。
次に、読者目線で「主役がコンテンツか、広告か」「根拠と注意点が併記されているか」「表現が誤認を招かないか」を点検します。
技術面では、リンク切れ・画像404・表示崩れ・読み込み遅延がないかを別端末/別ブラウザでも確認します。
最後に、改善の優先順位を「規約適合→可読性→価値の可視化→導線設計→広告最適化」の順に並べ、過度に一度で全変更を行わず、小さく直して結果を測ると、再申請時に整合性の取れた説明ができます。
| 領域 | 見直し観点 | 再申請前の整備例 |
|---|---|---|
| 規約適合 | 禁止表現・権利・開示表記の妥当性 | PR表記の明確化、引用出典の明記、煽り文の中立化 |
| 可読性 | 結論→根拠→注意点→行動の順 | 冒頭に「この記事で分かること」を追加 |
| 価値可視化 | 読者メリットが即時に伝わるか | 比較表・実体験・注意事項をセットで提示 |
| 導線 | 内部リンク・目次・カテゴリの整理 | 入門↔比較↔体験へ往復リンクを設置 |
| 広告 | 本文より目立たない配置・点数 | リンク最小化、重いウィジェットの削減 |
- 時点固定(申請時の状態を保存)→差分が説明できる準備
- 規約適合を最優先に是正→PR/引用/表現を整える
- 読者価値と導線を強化→小さく直して動作確認
否認理由の仮説化と改善ログ
否認理由が明示されない場合でも、原因は「表現・権利・広告・品質・技術」のいずれかに集約されます。
そこで、各領域で「考えられる理由」を仮説化し、対応と検証結果をログ化します。仮説は主観ではなく、ページの客観的事実(配置、文言、画像の重さ、リンクの到達など)に基づいて立てるのがポイントです。
改善は一度に多数ではなく、インパクトの大きい順に小刻みに行い、変更ごとにスクリーンショット・変更理由・期待効果・確認結果を短文で残します。
こうして作った改善ログは、再申請時の補足説明(どの点をどう改善したか)の根拠になりますし、次回以降のテンプレートにもなります。
下の表は、よくある症状から仮説と対処を結びつけた例です。自サイトの実測(表示速度、クリック到達、スクロール深度)と合わせて検証すると、再現性のある改善が進みます。
| 症状 | 仮説(例) | 対処とログ化の要点 |
|---|---|---|
| 広告が目立つ | 本文より上位/多段ボタンで誤クリック誘発 | 配置を本文後半へ移動→PR表記追記→変更前後のレイアウト保存 |
| 信頼性が弱い | 根拠や注意点の不足・引用不明 | 出典明記・比較条件追記→記事冒頭に要点追加→差分を記録 |
| 表示の重さ | 大判画像・外部タグ過多 | 画像圧縮・ウィジェット削減→速度再計測→数値と日時を記録 |
| リンク不整合 | 切れリンク・遷移先のミスマッチ | 最新URLへ更新→全体クロール→修正一覧を作成 |
- 変更点:〇〇を△△へ移動/修正
- 目的:読者の誤認防止/可読性向上/速度改善
- 検証:別端末・別ブラウザ・再読込で再現性確認
チェックリスト運用と再提出準備
再申請前は、属人作業を排し「必ず同じ順序で確認できる」チェックリストに落とし込みます。
項目は、規約適合(禁止/権利/PR表記)→コンテンツ(結論/根拠/注意点/行動)→導線(目次/内部リンク/カテゴリ)→広告(点数/位置/読み込み)→技術(リンク/画像/速度/モバイル表示)の5群に分けると漏れが減ります。
あわせて、再申請に添える説明文の下書きも用意し、「どの箇所を」「どの方針で」「どう改善し」「どう確認したか」を一段落で簡潔にまとめます。
提出前の最終確認は、非ログイン状態・シークレットウィンドウ・別端末で行い、キャッシュ影響を排除します。
重い変更(テーマ/大規模レイアウト)は事前にテストページで検証し、問題がなければ本番へ段階反映します。
以下のチェック表を印刷または固定ページに置いて運用すると、次回以降の再現性が上がります。
| チェック項目 | 確認内容(例) |
|---|---|
| PR/開示 | 広告/PRの明示がリンク近くや冒頭で視認可能 |
| 表現 | 断定/煽りの中立化、注意点・条件の併記 |
| 構成 | 冒頭に「わかること」、結論→根拠→行動の順序 |
| 導線 | 関連記事2〜3本への往復リンク、目次の整合 |
| 技術 | リンク切れ/画像404なし、表示速度とモバイル表示の確認 |
- 非ログイン・別端末で最終表示確認→キャッシュ影響を排除
- 改善ログとスクショを添付準備→差分を簡潔に説明
- 提出直後は更新を控え、審査対象の状態を固定
審査後の注意点と違反回避

AmebaPickの審査を通過した後は「運用の継続性」と「コンプライアンスの平常化」が重要です。合格直後は表示や導線が整っていても、記事追加・季節施策・テンプレ改修のたびに広告バランスや表記が崩れがちです。
まず、PR/広告の明示位置、リンク文言、比較基準、引用・画像の出所などを“固定ルール”として文書化し、全記事で同じ順序で点検します。
次に、編集(内容の中立性)と収益(掲載可否)の役割を分け、編集基準→収益基準→法規・規約基準の順でレビューを回すと判断がぶれにくくなります。
さらに、リンク切れ・画像404・表示遅延は苦情や誤認につながるため、週次の機械チェックと月次の手動点検を併用しましょう。
指摘や問い合わせが来た場合に備え、修正フロー(受領→一次判定→改稿→再確認→完了記録)を決め、履歴を残すと再発防止に役立ちます。
| 領域 | 継続運用の要点 | 違反リスクを下げる運用 |
|---|---|---|
| 表示・表記 | PR/広告の位置と文言をテンプレ化 | 記事冒頭+リンク近くに明示→毎回同じ表現で統一 |
| 編集品質 | 結論→根拠→注意点→行動の順に統一 | メリットと注意点を必ず併記→誇張表現は中立化 |
| 技術 | リンク/画像/速度の定期点検 | 切れリンク即修正→画像軽量化→重いウィジェット削減 |
- 新規公開前にPR表記・比較基準・出典の3点を確認
- 週次でリンク/画像の自動チェック→差分を修正
- 改修は小分け→変更理由と結果を簡潔に記録
ステマ規制対応と開示表記の徹底
審査後に最も崩れやすいのが開示表記です。対価(紹介料・提供品・割引等)や関係性がある紹介は、読者が“広告・利害関係の有無”を一目で判断できる位置に明確に示します。
基本は「記事冒頭での総括表示」+「リンクやボタン付近の個別表示」の二段構えです。文言は短く具体的にし、本文より広告が目立つ装飾は避けます。
比較・ランキングでは、選定基準(評価軸)を本文内で簡潔に記し、広告の有無が順位に影響しない構造を保ちます。
レビューは実体験や検証条件を明示し、効果の断定や再現性の低い表現は中立化します。価格・在庫・キャンペーンは変動するため、確認日や適用条件を添えて誤認リスクを下げます。
SNS埋め込みや外部計測の追加で表示が重くなると離脱が増え、表記の視認性も落ちるため、軽量化と表示位置の見直しを同時に行うと効果的です。
| 場面 | OKの考え方 | NG/注意の例 |
|---|---|---|
| 記事冒頭 | 本記事には広告/アフィリエイトを含む旨を明示 | 末尾だけに小さく記載→読了前に伝わらない |
| リンク付近 | リンク近傍にPR表記→識別可能なテキスト | ボタンのみ強調→広告である旨が読み取れない |
| 比較/ランキング | 評価軸を提示→広告の有無と順位は切り離す | 根拠不明の1位表記→広告有無を伏せる |
- 本記事にはアフィリエイト広告を含みます。購入前に条件をご確認ください。
- リンク先は外部サイトです。価格・在庫は掲載時点から変動する場合があります。
- 提供品を含むレビューは、その旨を各該当箇所に明示します。
プライバシー・問い合わせ体制整備
収益化ブログは、読者からの問い合わせや権利関連の要望に継続的に対応する体制が不可欠です。
まず、固定ページでプライバシーポリシーを公開し、取得する情報(問い合わせフォーム・アクセス解析等)、利用目的、第三者提供の有無、保存期間、問い合わせ窓口、開示・訂正・削除の手続を明確にします。
未成年の読者や画像・レビューに関与する第三者の同意、肖像・著作物の取扱いも方針として記載します。
問い合わせはフォームとメールの両方を用意し、受付→一次返信→事実確認→対応→完了連絡→記録の流れを定型化。個人情報は必要最小限のみ受領し、完了後は所定期間で削除します。
権利侵害の申出(画像の削除依頼・誤記訂正など)は優先度を上げ、事実関係を確認のうえ迅速に是正します。トラブル再発を防ぐため、依頼内容と対応結果を月次レビューし、テンプレやチェックリストを更新しましょう。
| 項目 | 必須要素 | 運用のコツ |
|---|---|---|
| プライバシーポリシー | 取得情報・目的・保存期間・問い合わせ先 | 固定ページ化→フッター/プロフィールから常時導線 |
| 問い合わせ対応 | 受付→一次返信→是正→記録の標準手順 | 目標返信時間を設定→テンプレ文で迅速化 |
| 権利対応 | 削除/訂正の基準・証跡の扱い | 申出フォームを分離→証憑の提示方法を明記 |
- 窓口不明→ポリシーと問い合わせ導線を全ページから到達可能に
- 返信遅延→一次自動応答+目標返信時間の明示
- 個人情報の過収集→必須項目を最小限にして保存期間を短縮
まとめ
AmebaPick審査は、基準の理解→禁止事項の把握→運用の最適化→否認時の改善→審査後の遵守の順で整えると通過に近づきます。
本文の10項目をチェックリスト化し、不安な箇所は修正→再確認→提出へ。読者価値を最優先に、広告は控えめで自然に配置しましょう。