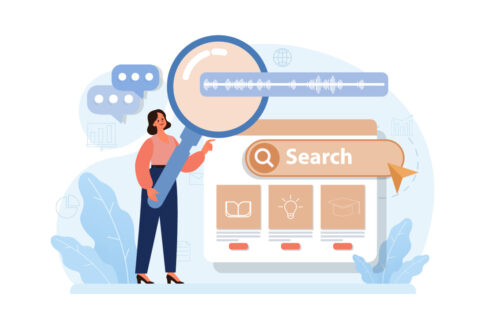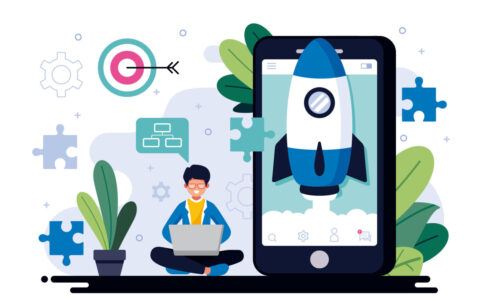アメブロ記事のURL、毎回どこで確認していますか? 本記事では、記事URLを「管理トップ」「記事一覧」「記事ページ」の3通りで素早く取得する方法を解説していきます。
さらに、取得したURLをX・Instagramで拡散してクリック率を高める告知文テンプレ、短縮URLとUTMの使い分け、リンク切れを防ぐ運用チェックリストもご紹介します。URL運用を整えるだけで、集客と管理の手間が大きく減ります。
アメブロ記事URLの基礎と仕組み

アメブロ記事のURLは「どのブログの、どの記事か」を指し示す“住所”です。URLを正しく把握しておくと、SNS告知・内部リンク・外部サイトへの掲載・アクセス解析が格段にやりやすくなります。
基本的に、アメブロの公開記事URLは〈ドメイン〉+〈ブログID〉+〈記事ID〉の3要素で構成され、タイトルを変更してもURLは変わりません(記事を削除して再投稿すれば新URLになります)。
また、アメブロの画面遷移で付与されるパラメータ(例:?frm=… など)は“どこから来たか”を表す補助情報で、共有時は外しても記事に到達できます。
共有・保存・チラシやメールマガジンに載せる場合は、できるだけ“すっきりしたURL”を使うのが安全です。
スマホアプリ内の「共有」から取得したリンクがアプリ用のスキームになることがありますが、ブラウザで記事を開き、上部アドレス欄のURLをコピーすれば汎用的に使えます。
URLを管理しやすくするため、代表記事・問い合わせ・プロフィールなど“よく使うリンク”はメモアプリや短縮URLでテンプレ化しておくと、更新直後の告知が数分で完了します。
| 要素 | 意味・ポイント |
|---|---|
| ドメイン | アメブロの配信元。共有時は https の正味のURLを用いると安全 |
| ブログID | あなたのブログを特定する識別子(プロフィールURLにも共通) |
| 記事ID | 各記事固有の番号。タイトル変更では変化しない |
| パラメータ | ?以降の補助情報。共有時は外して“正味のURL”にすると安心 |
- 共有は“余計なパラメータなし”のURLで統一
- アプリではなくブラウザのアドレス欄からコピー
- 例:SNS告知・プロフィール・他サイトに貼るURLは1本に統一→クリック率と計測が安定します
URL把握の利点とアクセス効果
URLを把握して素早く共有できると、アクセスの“落とし穴”を避けられます。正しいURLを即時に掲出できれば、読者はワンタップで記事に到達し、離脱が減ります。
さらに、内部リンク・外部リンク・SNSのどこに“入口”を置くかが明確になり、回遊率や再訪率の底上げにつながります。
実務では、公開直後30分の告知にURL統一を徹底するだけで、公開直後UU(ユニークユーザー)や記事末CTAのクリック率が上がるケースが多いです。
ブックマーク・メルマガ・外部プロフィールにも同一URLを載せれば“どこから来ても同じ記事に着地”でき、迷いを減らせます。
| 設置場所 | アクセス効果を高めるコツ |
|---|---|
| SNS(X/Instagram) | 先頭30字で価値を宣言+記事URL1本のみ。画像はテンプレ化で視認性アップ |
| サイドバー/プロフィール | 代表記事URLを固定。入口は“1画面1リンク”で分散を避ける |
| 記事本文(内部リンク) | 中腹に関連1本、末尾は主目的1本(代表記事/フォロー/まとめ) |
| 外部サイト・名刺 | 短縮URLで見た目を整えつつ、クリック先が分かる表記を添える |
- 直近3本の“共有用URL”をメモに保存(SNS告知をテンプレ化)
- プロフィールとサイドバーのリンクを代表記事1本に整理
- URLの統一は“見つけやすさ=クリック率”に直結します。まずは告知時のパラメータ削除から始めましょう
公開・下書きで異なるURL仕様
公開状態と下書き状態では、URLの扱いが変わります。公開記事は誰でもアクセスできる“共有可能URL”が確定しますが、下書き(予約含む)はログイン中の本人だけが確認できるプレビューURLで、第三者に共有しても閲覧できません。
つまり、SNSに貼る・メルマガに載せるなど“外部公開”は、必ず公開後のURLで行う必要があります。
予約投稿の段階では、公開時刻をまたいでからもう一度記事を開き、ブラウザのアドレス欄から最終URLをコピーしましょう。
タイトル変更や本文修正で公開URLが変わることは通常ありませんが、記事削除→再投稿では新しいURLになります。
アプリの共有メニューがアプリ専用リンクを返す場合は、ブラウザで記事を開き直すのが安全です。
| 状態 | URLの扱い・注意点 |
|---|---|
| 公開 | 共有可能。パラメータを外した“正味のURL”で統一 |
| 下書き/予約 | 本人のみ閲覧可。外部共有不可。公開後に改めてURLを取得 |
| タイトル変更 | 基本は同URLのまま。計測リンクは継続利用可 |
| 削除→再投稿 | 新URLになる。外部の貼替えが必要 |
- 予約投稿は“公開後にURL再取得”をルール化
- 削除/再投稿時は差し替え表を作成し、SNS・サイドバー・過去記事を一括更新
- 公開可否の最終確認は“ログアウトまたは別ブラウザ”で。見えていれば共有準備は完了です
URLの確認・取得方法を3通りで解説

アメブロ記事のURLは「管理トップ」「記事一覧」「記事ページ(実際に開く)」の3ルートで安全に取得できます。どの方法も難しくありませんが、用途に応じて最適解が異なります。
作業の原則は、①公開状態のURLを使う、②余計なパラメータ(?以降)は外す、③同じURLを使い回して計測と管理を安定させる、の3点です。
SNS告知のスピードを重視するなら記事ページで即コピー、複数リンクをまとめたいなら記事一覧、公開状態の最終チェックと同時に進めたいなら管理トップが相性良いです。
以下に、各ルートの手順と注意点をまとめます。
| ルート | 向いている用途 |
|---|---|
| 管理トップ→ブログ→該当記事 | 公開状態の確認と同時にコピー。誤リンク防止 |
| 記事一覧(編集・削除)→右クリック | 複数記事のURLをすばやく集約。内部リンク整理 |
| 記事を開く→アドレス欄からコピー | 最短でSNS告知/メールで共有。スマホ/PC共通 |
- 公開済みか(予約/下書きは不可)
- パラメータ削除(?以降を外す)
- トップではなく“記事URL”になっているか
- 代表記事・プロフィール・問い合わせなど“定番URL”はメモアプリや短縮URLでテンプレ化しておくと、更新直後の告知が数分で完了します
管理トップ経由で安全にコピー
管理トップ経由は、公開状態を確認しながら誤リンクを防ぎたいときに最適です。ログイン後、画面の「管理トップ」または「ブログ管理」を開き、「ブログ」→公開ページへ移動。
最新記事や目的の記事をクリックし、ブラウザのアドレス欄からURLをコピーします。公開直後のレイアウト崩れや画像表示、誤字脱字の最終チェックも同時にできるため、SNS告知前の“品質確認+URL取得”として定番にしましょう。
| 手順 | ポイント |
|---|---|
| 管理トップ→ブログ | あなたの公開ページへ遷移。全体の見え方を確認 |
| 該当記事を開く | タイトル・画像・リンクの表示を確認 |
| URLをコピー | ?以降のパラメータを外して保存・共有 |
- 予約投稿は公開後に再取得(プレビューURLは共有不可)
- 別タブや別ブログのURLを誤ってコピーしないよう、タイトルバーで確認
- このルートを習慣化すると、「品質確認→告知」の流れが1タスクで完了します
記事一覧から素早くアドレス取得
「記事の編集・削除」画面にある記事一覧は、複数URLをまとめて確保したいときの時短ルートです。
管理トップから「記事の編集・削除」を開き、一覧のタイトルまたは“公開ページを見る”リンクを右クリック→「リンクのアドレスをコピー」。
必要なURLをメモアプリやスプレッドシートに貼り付け、SNS告知や内部リンク整理に使います。テーマ別まとめやキャンペーン特集など、複数記事を一括で紹介する際に便利です。
| 活用シーン | 具体例 |
|---|---|
| 特集・まとめ作成 | 関連5〜10本のURLを一気に収集→まとめ記事へ貼付 |
| SNS告知 | 連投用にURLをストック→メモから貼り付け |
| 内部リンク整理 | 古い記事のリライト時に対象URLを一覧で管理 |
- コピーしたURLは「タイトル/URL」の2列で表にする
- 短縮URLとUTMは後から付与。原本URLは必ず保存
- スマホは右クリックが使えないため、PCでの収集→スマホと同期(メモ/クラウド)が効率的です
記事を開き上部アドレスをコピー
最も汎用的で迷いの少ない方法が、記事ページを開いてブラウザ上部のURLをコピーする手順です。PC・スマホ共通で使え、公開直後のスピード告知に向きます。
手順はシンプルで、該当記事を開く→アドレス欄をタップ/クリック→コピー。スマホアプリでURLが表示されない場合は、ブラウザ(Safari/Chrome)で記事を開き直してコピーします。
| チェックポイント | 確認内容 |
|---|---|
| 公開状態 | 非公開/下書きでは共有不可。公開後に再取得 |
| URLの体裁 | ?以降のパラメータを外して“正味のURL”へ |
| リンク先 | トップURLでなく記事URLになっているか |
- アドレスバーが隠れるUIでは、上方向へ軽くスクロールして表示→長押しでコピー
- 「共有」→「リンクをコピー」でも可。短縮URL利用時は遷移先を明記
- 記事URLを取得したら、X/Instagramの告知テンプレに即貼り付け→公開直後UUを底上げしましょう
SNS拡散でクリック率を底上げ

SNS拡散で成果が分かれる最大の理由は「投稿の型」と「導線の明確さ」です。アメブロへの送客は、投稿文の先頭で価値を言い切り(30字目安)、本文はメリットを2点だけ提示、リンクは1本に統一するのが基本です。
さらに、X(旧Twitter)はテキスト主導、Instagramはビジュアル主導と役割が異なるため、同じ内容でも表現を最適化します。
投稿の目的は1つに絞り(クリック/保存/フォローのいずれか)、KPIもそれに合わせて設定すると改善が速く進みます。
運用は「固定の投稿枠(曜日×時間)を2〜3つ決める→4週間継続→先頭30字/画像テキストだけ小さくABテスト」というリズムが鉄板です。
UTMパラメータ(?utm_source=x など)で流入源を記録し、アメブロ側では「外部流入UU」「代表記事CTR」「記事末CTR」を週次でノート化。数字が弱い場所だけをピンポイントで直すと、投稿本数を増やさずにクリック率を底上げできます。
| 媒体 | 投稿の目的 | 見るKPI |
|---|---|---|
| X | 記事クリック(速報・タイムライン勝負) | インプレッション→リンククリック率、公開30分のUU |
| 保存→プロフィール遷移(後追い読了を狙う) | 保存数、プロフィール遷移率、リンククリック | |
| アメブロ | 代表記事→フォロー/記事末CTA | 外部流入UU、代表記事CTR、記事末CTR |
- 投稿の先頭30字=「対象×結果×所要」を固定文に(例:初心者向け|5分で◯◯の手順)
- リンクは代表記事1本に統一(UTM付き)、投稿枠は2つの時間帯に固定
- 画像テンプレを1枚作成(色・フォント・ロゴを統一)
- 1投稿に複数リンク→クリック分散で成果が見えない
- 長文の説明→冒頭で価値が伝わらずスクロールで離脱
- 計測は週1回で十分です。同条件(曜日・時間)で比較し、先頭30字→画像テキスト→投稿時間の順に小さく調整しましょう
X・Instagram告知文の型を統一
告知文を毎回ゼロから考えると質が安定せず、作業も長引きます。
Xは「先頭30字で価値宣言→本文2行でメリット→#タグ3〜5個→URL1本」、Instagramは「1枚目に結論画像→2〜3枚目で要点・図解→最終スライドで行動案内(プロフィールのURLから読む)」という“型”を決めてしまいましょう。
先頭の価値宣言は「誰に」「何が」「どれくらいで」までを短文で言い切ると、一覧での視認性が上がります。メリット2点は箇条書き風に簡潔に(例:失敗回避/無料テンプレあり)。
ハッシュタグは一般語+テーマ語を混在させ、毎回1つだけ入れ替えて反応を見ると勝ちタグが見つかります。頻度は、Xは更新直後+日中の再掲1回、Instagramは1投稿+ストーリーズ1回程度が無難です。
どちらも1投稿1目的(クリックor保存)を徹底し、両方を同時に狙わない方が成果が読みやすくなります。
| 要素 | X テンプレ | Instagram テンプレ |
|---|---|---|
| 冒頭(先頭30字) | 忙しい人向け|5分で◯◯改善の手順 | 画像1枚目に大きく結論(数字/結果語) |
| 本文 | ・得られること1 ・得られること2 | 2〜3枚目でチェックリスト/Before→After |
| 行動案内 | 記事はこちら→(URL1本のみ) | 最終スライド:プロフィールのURLから読む→ |
| ハッシュタグ | #アメブロ #初心者 #テーマ語 など3〜5個 | #テーマ語 #読者の悩み語 など3〜5個 |
- 先頭30字で「対象×結果×所要」を明記
- 本文はメリット2点のみ(冗長にしない)
- リンクは1本、短縮URLなら遷移先を明記
- 先頭30字:数字あり/なし
- 画像テキスト:結果語(◯倍/◯分)vs 悩み語(時間がない/続かない)
- KPIはX=リンククリック率、Instagram=保存数・プロフィール遷移率。週次で記録し、勝ちパターンをテンプレへ反映します
視認性を高めるアイキャッチ設計
スマホのタイムラインで「一瞬で伝わる」ことがクリック率を左右します。画像は少色(メイン1+補助1)、高コントラスト、太めのフォント、余白多めが基本です。文字は大きく、短く、センターブロックで配置。
背景は無地か薄いテクスチャにして、人物写真や細かい模様の上に細字テキストを重ねるのは避けます。構図は「結論(大)→補足(小)」の二段で、数字や結果語(◯分/◯倍/3ステップ)を前面に。
Instagramは1:1または縦長、Xは横長でも文字が読めるサイズを意識し、シリーズものは色・レイアウト・アイコンを固定して認知を積み上げます。
サムネは1記事1枚で十分ですが、Instagramの2〜3枚目にチェックリストや比較表を入れると“保存価値”が上がり、後追いクリックにつながります。
| 設計項目 | ベストプラクティス | 避けたい例 |
|---|---|---|
| 色 | メイン1色+補助1色。背景は明るめ、文字は濃色 | 多色使い、背景と文字のコントラスト不足 |
| 文字 | 短く大きく(7〜10語程度)。太字/行間広め | 長文、細字、詰まりすぎ |
| 構図 | 結論(大)+補足(小)の二段、余白多め | 要素過多で情報が散る、余白がない |
| 統一感 | シリーズは色・フォント・アイコン固定 | 毎回テイストが違い認知が育たない |
- 数字・結果語を1つ入れる(例:5分/3ステップ/PV2倍)
- 余白を増やし、文字の周りに“息継ぎ”を作る
- スマホで実寸表示→文字が一瞬で読めるか
- 先頭30字と画像のメッセージが一致しているか
- サムネ×先頭30字の一致はクリック後の満足度にも直結します。メッセージの整合を最優先に整えてから投稿しましょう
リンク管理と計測を強化するコツ

URLを“貼る→終わり”では、どこから来て、どこで離脱したのかが分かりません。リンク管理と計測をセットにすると、少ない投稿本数でも効果を最大化できます。
基本は〈原本URLの一本化〉〈短縮URLの整備〉〈UTMで流入源を識別〉〈週次の数字記録〉の4点です。
まず、アメブロ内の代表記事・お問い合わせ・プロフィールなど“定番URL”は原本を1本に固定し、どこに貼っても同じページへ着地するようにします。
次に、SNSや紙媒体では短縮URLを使って見た目を整え、UTMパラメータで「媒体・投稿タイプ・キャンペーン名」を付与。
アメブロ側では「外部流入UU」「代表記事CTR」「記事末CTR」を週次で記録し、弱い箇所だけテキスト・位置・色を小さく改善しましょう。
リンク管理表(タイトル/原本URL/短縮URL/UTM/設置場所/更新日)を作ると、差し替え・棚卸しが一気に楽になります。
| 管理項目 | 記録内容(例) |
|---|---|
| 原本URL | 代表記事・まとめ・問い合わせなど、常に使うリンクの“正”を1本定義 |
| 短縮URL | 媒体別に作成(x/ig/mail)。見た目とクリック集計を兼用 |
| UTM | utm_source=x / utm_medium=social / utm_campaign=weekly など |
| 設置場所 | プロフィール/サイドバー/記事末/固定ツイート/IGプロフィールなど |
| 更新日 | 差し替えやキャンペーン切り替えの日付を記録 |
- 同曜日・同時刻に「外部流入UU/代表記事CTR/記事末CTR」を記録
- 低い指標のリンクだけ文言→位置→色の順で小改善
- “原本URLの一本化→媒体別短縮URL→UTM付与”の順に整えると、管理と検証が漏れなく回ります
短縮URLとUTMパラメータの使い分け
短縮URLは「見た目」と「クリック集計」を、UTMパラメータは「流入の識別」を担います。用途が違うので、両方を併用しましょう。
まず原本URLにUTMを付け、「どこから・どの投稿で」来たかを表現(例:?utm_source=x&utm_medium=social&utm_campaign=2309_weekly)。
次に、そのUTM付きURLを短縮サービスで短くし、SNSや紙媒体に貼ります。これで見た目を保ちながら、クリック→アメブロ側での行動(代表記事CTR、記事末CTR)まで一貫して追えます。
短縮URLは媒体別(x/ig/mail/line)に分け、キャンペーン期間が終わったらアーカイブして再利用。
メールや名刺など“URLの文字が目立つ”媒体では短縮を、ウェブ内のバナーやテキストリンクではUTMのみ(短縮なし)でも十分です。
| 場面 | 短縮URL | UTM |
|---|---|---|
| X/Instagram告知 | ◯(見た目とクリック集計) | ◯(source/medium/campaignを必ず付与) |
| ブログ内テキスト/バナー | △(不要なことが多い) | ◯(流入識別用に有効) |
| 紙/名刺/チラシ | ◯(読みやすさ重視) | △(手入力が前提のため省略も可) |
- utm_source=媒体(x/ig/mail)
- utm_medium=配信種別(social/cpc/newsletter)
- utm_campaign=企画名+年月(weekly_2025_03 など)
- 短縮URLだけでUTMなし(流入源が判別できない)
- UTMを毎回バラバラに命名(比較不能)
- UTM付き原本→媒体別に短縮、という順序を固定しておけば、後からでも効果検証が容易になります
リンク切れ対策と変更時のリダイレクト案
リンク切れは信用と機会損失の両方を傷つけます。対策は〈差し替え表〉〈一括点検〉〈柔らかいリダイレクト〉の3段。
まず、URL変更(記事削除→再投稿、まとめの差し替え、タイトル変更に伴う構成変更など)が発生したら、旧→新の対応表を作り、サイドバー/プロフィール/固定投稿/関連記事のリンクを一気に更新します。
次に、月1回は「代表記事→関連記事→記事末」の主要導線をクリックテストし、404や外部のリンク切れがないか確認。
アメブロでは細かな301リダイレクト設定が難しいため、旧記事を残せる場合は“冒頭に新URL案内”を設置し、本文冒頭と末尾に目立つ導線を置く“疑似リダイレクト”が有効です。
削除が避けられないときは、上位のまとめ記事やカテゴリーへのリンクを置いて迷子を防ぎます。
| 状況 | 推奨アクション | チェック |
|---|---|---|
| 記事削除→再投稿 | 旧記事の冒頭に新URLを明示/関連記事・SNSの差し替え | 旧→新のCTR、404発生の有無 |
| まとめ差し替え | サイドバー・プロフィール・固定投稿を同日更新 | 代表記事→まとめのCTR |
| 外部リンク切れ | 代替商品・代替資料への差し替え/注意書きの追記 | クリック後直帰率の改善 |
- 主要導線のクリックテスト(代表→関連→記事末)
- 差し替え表の更新(旧→新URL、更新日を記録)
- URL変更とテーマ変更を同日に実施→原因不明の崩れ
- SNS・サイドバーの差し替え漏れ→旧リンクが残存
- “疑似リダイレクト”を置くと、検索やブックマークからの迷子を減らせます。案内文は冒頭に太字で配置しましょう
運用上の注意点とよくある質問

アメブロ記事URLの運用は「正しいURLを素早く共有する」だけでなく、リンク切れや計測漏れを未然に防ぎ、読者が迷わない導線を保つことが大切です。
特に、予約投稿後のURL取り違え、パラメータ付きURLの乱用、トップURLへの誤リンク、SNS側の再掲時に短縮URLだけ差し替えて原本URLがバラける――といった細かなミスが積み重なると、クリック率や回遊率が大きく下がります。
そこで、作業のたびに確認する“最低限の型”を決めておくと安心です。以下のチェックとQ&Aを活用し、日次の告知から月次の棚卸しまで、ミスの再発を防ぎましょう。
| 場面 | 注意点・対策 |
|---|---|
| 予約投稿直後 | 公開後に記事を開いて“正味のURL”(?以降なし)を再取得。プレビューURLは共有不可 |
| SNS告知 | 1投稿1リンク。先頭30字で価値を宣言。短縮URLは媒体別に分け、UTM付き原本を保管 |
| 内部リンク整理 | 記事末は主目的1本(代表記事/登録/まとめ)。横並びリンクはCTR分散 |
| 差し替え | 旧→新URLの差し替え表を作り、サイドバー/プロフィール/固定投稿/関連記事を同日更新 |
- 公開状態か/トップではなく記事URLか
- パラメータ削除済みか(?以降なし)
- URLは“1記事1本”で統一するほど、計測と運用が楽になります
ありがちなミスと防止チェック
URL運用で起こりがちなミスは、〈プレビューURLの誤共有〉〈トップURLの誤貼付〉〈パラメータ乱用〉〈短縮URLだけ差し替え〉の4つに大別できます。
プレビューURLは公開前の本人確認用で、第三者は閲覧できません。予約投稿の直後は、必ず公開後のページを開き直してブラウザ上部からコピーしましょう。
トップURLの誤貼付は、SNSからの直帰増加の典型例です。コピー前に「記事タイトルが表示されているタブか」を確認し、スマホでは“共有→リンクをコピー”ではなくアドレスバーからコピーを推奨します。
パラメータは?以降の補助情報です。SNSやメルマガで余計なパラメータが付いたURLを回すと、媒体ごとにURLがバラつき計測が混乱します。
計測は短縮URLの集計またはUTMに一本化し、共有は“正味のURL”に統一します。短縮URLのみ差し替えるミスも頻発します。原本URLが変更された場合、必ず短縮側のリンク先も更新しましょう。
| ミス | 起きやすい場面 | 防止策 |
|---|---|---|
| プレビュー共有 | 予約投稿/公開直後 | 公開後に再取得。ログアウトor別ブラウザで閲覧確認 |
| トップURL貼付 | 慌てて告知 | コピー前に記事タイトルのタブか確認。スマホはアドレスバーから |
| パラメータ乱用 | SNSからコピペ | ?以降を削除して共有。計測はUTM/短縮で統一 |
| 短縮URL差し替え漏れ | 再投稿・URL更新時 | 原本→短縮の順で更新。リンク管理表を運用 |
- 旧→新の差し替え表を作成→主要導線を一括置換
- 旧記事の冒頭と末尾に新URLを掲出(疑似リダイレクト)
- リンク管理は“表にする”だけで再発率が下がります。タイトル/原本URL/短縮URL/設置場所/更新日を記録しましょう
スマホ・PC操作の違いと代替策
スマホ運用では「右クリックができない」「アプリはURLが見えにくい」といった制約があります。代替策は、〈ブラウザで開いてアドレスバーからコピー〉〈リンク長押しで“リンクをコピー/共有”〉〈PCでURLを一括収集→クラウドメモと同期〉の3つ。
とくにアプリ閲覧中は共有リンクがアプリ専用スキームになることがあり、ブラウザ(Safari/Chrome)で記事を開き直すのが安全です。
PCでは記事一覧の右クリックでURLを素早く収集できる一方、タブが増えるほど取り違えが起きやすいので、コピー前に“記事タイトルのタブか”を常にチェックしましょう。
通知や省電力の影響でスマホに届いたURLを見逃すこともあります。iOS/Androidの通知設定でSNSとメールの通知を許可し、バッテリー最適化から対象アプリを除外しておくと、URLの受け渡しがスムーズです。
URLの貼り付けは、スマホではクリップボード履歴アプリ、PCではスニペットツール(定型文)を活用すると時短になります。
| 環境 | おすすめ操作 | 注意点 |
|---|---|---|
| スマホ(アプリ) | 共有→リンクをコピー/ブラウザで開き直す | アプリ専用リンクの可能性。最終はブラウザで確認 |
| スマホ(ブラウザ) | アドレスバー長押し→コピー | パラメータ削除、トップURL誤コピーに注意 |
| PC | 記事一覧で右クリック→リンクアドレスをコピー | タブ取り違え防止。コピー前にページタイトル確認 |
- スマホしか使えない週は“ブラウザ版”を基本に運用
- 定番URLはメモ/短縮でテンプレ化→ワンタップ貼付
- どの環境でも“正味のURLで1本化”が最優先です。操作に迷ったら、ブラウザで記事を開いて上部からコピーに戻りましょう
まとめ
要点は、①取得ルートを3通り持ち状況に応じて使い分け②SNS告知は先頭30字で価値宣言+1リンクに統一③短縮URLは見た目を整え、UTMで流入源を計測④リンク切れと変更時の差し替え表でリスク管理。
まずは直近記事のURLを取得→X/Instagramでテンプレ告知→UTMで成果を記録、の順で回し、週次でクリック率と外部流入を確認しましょう。