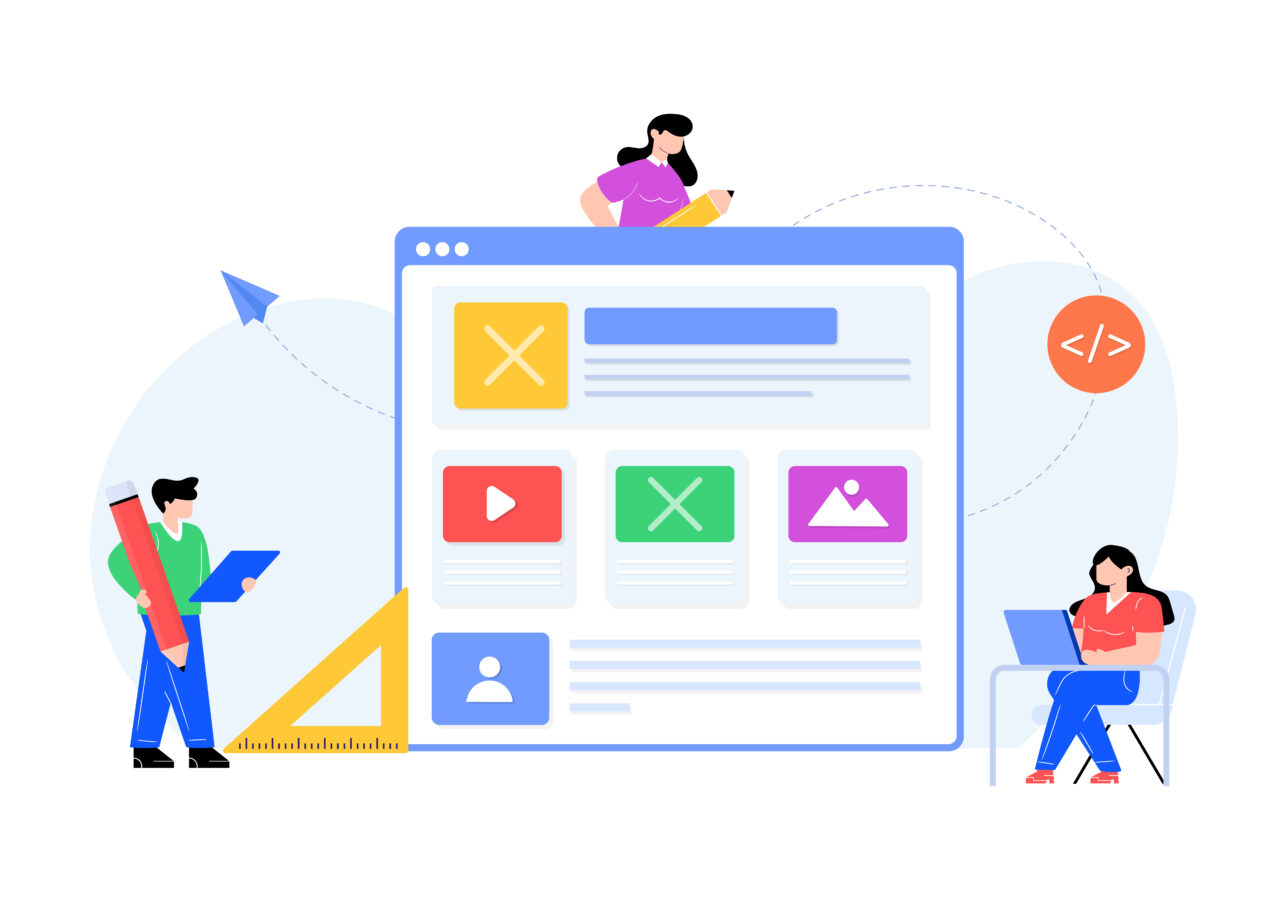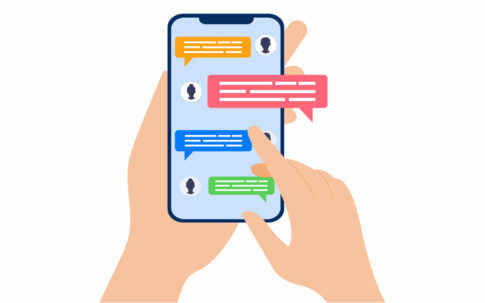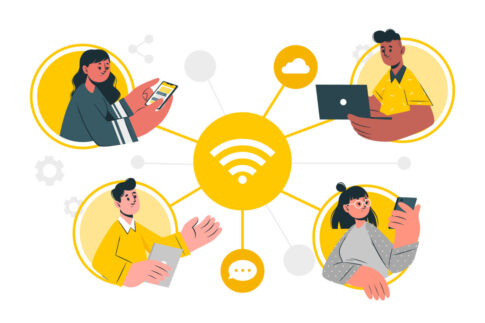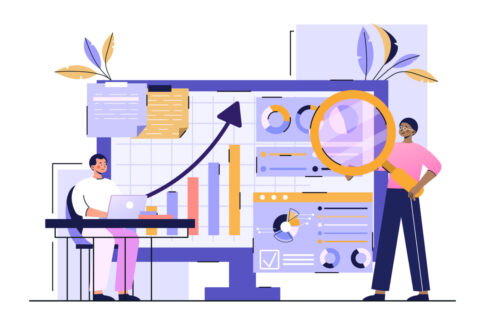アメブロの新機能とSNS導線の使い方を、設定5手順・活用10例でやさしく解説します。プロフィールや記事下のボタン配置、リンクカード、ヘッダー/フッターの最適化で再訪と成約率を底上げ。クリック計測と週次改善の回し方まで、初心者でも迷わず実装できる実践ガイドです。
目次
アメブロ新機能の概要と導線活用メリット
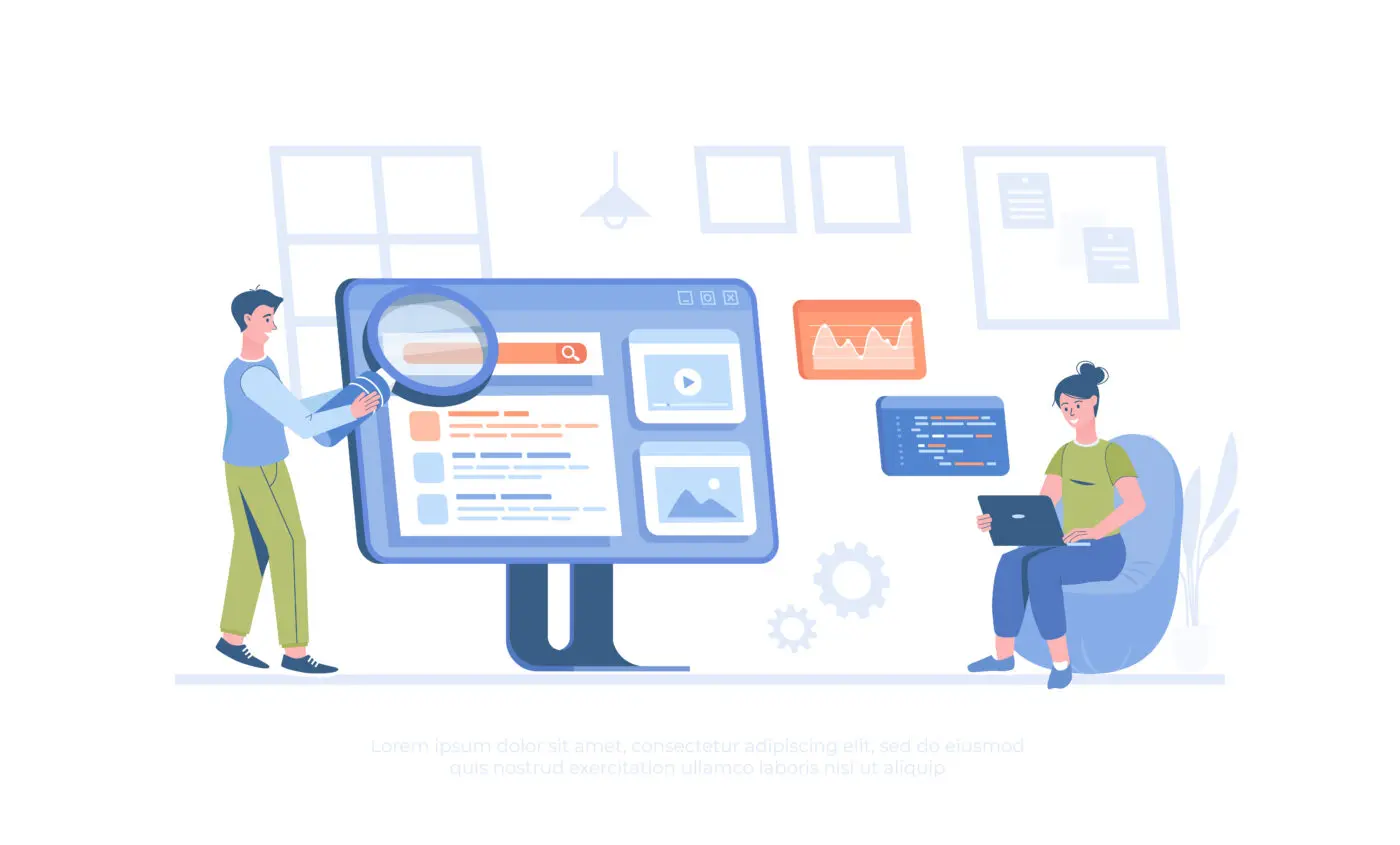
アメブロで読者をSNSへ案内する導線は、プロフィール・記事下・ヘッダー/フッター・サイドバーなど複数の表示箇所に置けるよう整ってきました。
SNSボタンや外部リンクの表示を整えると、ブログで興味を持った読者が、X・Instagram・YouTubeへ自然に移動し、最新情報に触れやすくなります。
結果として、フォロー増→再訪増→指名検索増という良い循環が生まれやすく、告知や販売、予約といった「行動」につながる接点が増えます。
まずはプロフィールに主要SNSを明記し、記事下には「続きはSNSで」や「最新事例をSNSで確認」といった一言とリンクを配置します。
ヘッダーやフッターには常時見える案内を置き、サイドバーや自己紹介には、キャンペーンや固定コンテンツへのリンクをセットします。
計測のために、SNS別にリンク名を分けておくと、どこからのクリックが多いかを把握でき、配置や文言の見直しが進めやすくなります。
| 配置箇所 | ねらい | 文言・活用例 |
|---|---|---|
| プロフィール | 常時表示で信頼と導線を明示 | 「公式Instagram」「最新事例はX」など明確な表記 |
| 記事下 | 読み終わりの次アクションを提示 | 「続報→X」「図解まとめ→Instagramハイライト」 |
| ヘッダー/フッター | 全ページ共通の案内で迷いを減らす | SNSアイコン+短い説明を横並びで配置 |
- フォロー増→再訪増で安定的なアクセス基盤を形成
- 最新情報・短報はSNS、深い解説はブログと役割分担が明確
SNSボタン追加と外部リンク強化機能
SNS導線づくりの起点は、プロフィールと記事周りのリンク整備です。プロフィールには、X・Instagram・YouTubeなど主要SNSの公式アカウントを明記し、アイコンまたはテキストで分かりやすく並べます。
記事下には、読者が次に取る行動が想像できる短い案内(例:「最新企画はXで更新」「ビフォー→アフター写真はInstagram」)とリンクを配置します。
ヘッダー/フッターには常時見えるアイコンを置き、色や大きさで「押しやすさ」を確保します。
外部リンクは、同じ表記(アカウント名・URL)で統一し、記事ごとにリンク先を変える場合は、ラベル(例:「記事下_X」「記事下_Inst」)を分けておくと、どの導線が効いたかを後で判断しやすくなります。
【整備の手順(例)】
- プロフィール編集→主要SNSのアカウントURLを追記→保存
- 記事テンプレートの末尾に、SNS案内の短文+リンクを設置
- ヘッダー/フッターにSNSアイコンを横並びで追加
- リンク名(ラベル)をSNS別に分けて、後の比較に備える
例:レビュー系記事なら「未公開写真→Instagram」、速報系記事なら「続報→X」で導線の役割を分けると、読者が迷わず行動できます。
- リンクが多すぎると逆に迷います。主要SNSは3つ程度に絞ると効果的です。
- アイコンのみは意味が伝わりにくい場面があります。短い補足文をそばに置くとクリック率が安定します。
固定表示・リンクカード活用と注意点
キャンペーンや代表コンテンツを長く見せたい場合は、固定的に見える場所(自己紹介やサイドバーなど)に案内を置きます。
URLを貼るとカード状のプレビュー(リンクカード)になる場合は、サムネイルとタイトルで内容が一目で分かるため、クリックのきっかけが生まれます。
カード表示にならない環境もあるため、テキストの補足(例:「◯◯の全まとめ」)を併記すると安心です。
記事本文では、冒頭・中盤・末尾のいずれかに「関連まとめ」への案内を1回ずつ入れると、読み流しによる機会損失を減らせます。固定表示と記事内リンクの両方を使うことで、初見の読者にも再訪の読者にも届きやすくなります。
【活用と注意のポイント】
- 固定で見せる情報は厳選→「代表事例」「最新キャンペーン」「お問い合わせ」などに限定
- リンクカードが生成されない場合に備え、短い説明文を必ず添える
- 画像は明るく文字は少なめ→スマホでも判別しやすい表現に
| 手法 | 期待できる効果 | 注意点 |
|---|---|---|
| 固定表示 | 全ページで訴求を継続。回遊と再訪を促進 | 更新を忘れると情報が古く見える→月1で見直し |
| リンクカード | 視覚的に分かりやすくクリックを誘発 | 生成不可の環境あり→テキスト補足を併記 |
- 季節企画や新商品の案内を固定→記事更新時も効果が途切れない
- 代表記事のまとめを固定→初見の読者が最短で価値に到達
導線強化で再訪・成約率を底上げの狙い
SNS導線の目的は、単にフォロワーを増やすことではなく、「関心を維持する接点」を育てることです。ブログで深い解説に触れた読者を、SNSで短報・最新情報・写真・動画に触れさせることで、思い出してもらう回数が増えます。
再訪が増えると、比較検討中の読者が「もう一歩」進みやすくなり、問い合わせや購入、予約といった行動につながりやすくなります。
配置のコツは、記事の冒頭・見出し直下・末尾のいずれかに、次の行き先を一行で案内することです。
文言は「押すと何が起きるか」を明確にし、SNSごとに役割を分けます(例:X→速報、Instagram→写真事例、YouTube→使い方動画)。そのうえで、アクセス解析のリンク元やクリック状況を見ながら、位置と文言を毎週少しずつ調整します。
【導線文言の作り方】
- 役割の明示:「最新の入荷情報→X」「施工事例の写真→Instagram」
- 不安の解消:「キャンセル規定と価格→こちら」「所要時間と流れ→こちら」
- 読み終わりの背中押し:「続きは写真で確認→Instagram」「動画で詳しく→YouTube」
- 同一ページにリンクを詰め込みすぎると逆効果。主要導線は3つまでに絞る
- 更新のないSNSへ誘導し続けると離脱増。休止時はリンクを一時的に外す
SNS導線の設定手順と表示位置の最適化

SNSへの導線は、まず〈プロフィール〉〈記事下〉〈常時表示エリア(ヘッダー・フッターやサイドバー)〉の三か所を整えると効果が安定します。
読者は「読み終わった直後」と「サイト共通の見える場所」で次の行き先を決めるため、この二つの動線が弱いと、せっかくの興味が途切れやすくなります。
最初は、プロフィールに公式アカウントへのリンクを明記し、記事下にはXとInstagramのボタン(またはテキストリンク)を1文の案内とセットで設置します。
さらに、ヘッダー・フッターにアイコン+短文の案内を置き、全ページで同じ導線を維持します。導線文言は「押すと何が分かるか」を具体化(例:最新情報→X、ビフォー→アフター写真→Instagram)し、リンク名をSNS別に分けておくと、クリック計測の比較がしやすくなります。
| 表示位置 | ねらい | 最初の一手 |
|---|---|---|
| プロフィール | 常時表示で公式案内と信頼を提示 | SNSリンクを明記→「何が見られるか」を一言で追記 |
| 記事下 | 読み終わりの次アクションを後押し | 1文の案内+X/Instagramリンクを固定で挿入 |
| ヘッダー・フッター | 全ページ共通の導線で迷いを防止 | アイコン+短文を横並び配置→3つまでに厳選 |
【はじめの手順】
- プロフィール編集→主要SNSのURLを登録→説明文に役割を追記
- 記事テンプレートの末尾に案内文+リンクを追加して保存
- ヘッダー・フッター(またはサイドバー)にアイコンと短文を配置
- 導線は少数精鋭(最大3つ)→迷いを作らない
- 文言は「押すと得られる内容」を具体化→クリック率が安定
プロフィールでSNSボタンを設定する
プロフィールは、初見の読者が「この人(この企業)はどこで最新情報を出しているか」を確認する場所です。
X・Instagram・YouTubeなど主要SNSのURLを登録し、アイコンだけでなくテキストでも「何が見られるか」を明記します。(例:「X|入荷・速報」「Instagram|事例写真」「YouTube|使い方動画」。)
自己紹介文には、ブログとの役割分担(深い解説はブログ、速報はX、写真はInstagram)を一文で追記し、導線の意図を読者に伝えます。
プロフィール画像・ヘッダー画像は、SNSアイコンやアカウント名と整合させると、認知が一度でつながります。リンク名(ラベル)は「prof_X」「prof_Inst」のようにSNS別で分けておくと、後でクリック比較がしやすく、表示位置の見直しに活用できます。
【チェック項目】
- SNSリンクのURLが正しいか(httpsの有無・表記ゆれの解消)
- 各SNSの役割が一言で分かるか(例:速報・事例・動画)
- プロフィール画像・説明文とSNSのトーンが一致しているか
- リンク名をSNS別に分けて保存しているか(計測のため)
- アイコンだけで案内がない→補足文を添えるとクリック率が上がる
- リンクが多すぎて視認性低下→主要3つに絞り、残りは記事下で案内
記事下にX・Instagramリンク表示
読者が行動を決めやすいのは「読み終わり」の瞬間です。記事の末尾に、1文の案内とX・Instagramへのリンクを固定で入れておくと、自然に次の行き先が決まります。
案内文は、記事の内容に合った役割で書き分けます。レビューや事例記事なら「未公開写真はInstagram」、速報系なら「続報はXで配信」、ノウハウ記事なら「図解の要点をXで再掲」のように、押した後の利点が一目で分かる表現にします。
リンク配置は「1文+2ボタン(またはテキストリンク)」を基本にし、色や余白で押しやすさを確保します。毎回手で入れるのが大変な場合は、記事テンプレートやよく使うフレーズに登録しておくと抜け漏れを防げます。
リンク名は「post_X」「post_Inst」のように記事下専用で分け、プロフィール導線との効果差を比較しましょう。
【文言サンプル】
- 最新の入荷とお知らせ→Xで配信中
- ビフォー→アフター写真をまとめて見る→Instagram
- 本記事の図解まとめ→Xの固定ポストで復習
- ボタンは2つまで→3つ以上は迷いを生むためサイドバーで補完
- 案内文は15〜20文字前後→スマホの折り返しを避ける
ヘッダー・フッターへの導線配置の工夫
ヘッダー・フッターは、全ページで共通に表示されるため、読者がどのページにいてもSNSへ移動できます。スマホではヘッダーの表示領域が限られるため、アイコンだけでなく短いテキスト(例:「速報→X」「事例→Inst」)を添えて意味を明確にします。
フッターは縦に要素を並べられるので、アイコン+説明文+リンクを横並びのブロックにして、タップ幅を十分に確保します。
サイドバーが使えるレイアウトなら、固定ウィジェットとして同じ内容を設置し、スクロール中にも導線が目に入るようにします。
運用上は、季節企画やキャンペーンの案内を月1で見直し、更新のないSNSがある場合は一時的にリンクを外すと、空振りによる離脱を防げます。
| 配置 | 強み | 運用のコツ |
|---|---|---|
| ヘッダー | 最上部で視認性が高い。初見の導線に有効 | アイコン+短文で意味を明示。3つまでに厳選 |
| フッター | 全ページで共通。タップ幅を確保しやすい | ブロック化して誤タップ防止。月1で文言を更新 |
| サイドバー | スクロール中も視界に入りやすい | 固定ウィジェットを設置。X固定ポストやInstハイライトを案内 |
- 全エリアに同じ導線を重複配置→クリックが分散して検証が難しくなる
- 更新の止まったSNSへ誘導→一時的に外してブログ内回遊を優先
例:ヘッダーに「速報→X・事例→Inst」、記事下に「本記事の続き→X固定ポスト」、フッターに「まとめ→固定記事」の流れを組むと、初見・再訪どちらにも迷いの少ない導線になります。
プロフィール・記事下のリンク設計と文言

プロフィールと記事下は、読者が「次にどこへ行くか」を決める重要ポイントです。設計の出発点は、各SNSの役割分担を決めることです。
たとえば「X→速報・お知らせ」「Instagram→事例・ビフォー→アフター」「YouTube→使い方解説」のように、見に行く理由が一目で分かる配置にします。
プロフィールでは、SNSアイコンだけでなく短い説明文を添えるとクリックの迷いが減ります。記事下では、本文の内容に合わせて1文の案内+リンクを固定で入れ、読了直後の関心を逃しません。
ボタンやリンクの文言は「押した後に何が見られるか」を具体的に表現し、長すぎない短文で統一します。
テキストリンクの場合は、リンク直前の文章に「写真で確認」「動画で解説」など行動の見出しを入れると、スマホでも意図が伝わりやすくなります。
| 表示位置 | 役割 | 文言サンプル |
|---|---|---|
| プロフィール | 常時の案内と信頼の提示 | 「速報→X」「事例写真→Instagram」「使い方→YouTube」 |
| 記事下 | 読了直後の背中押し | 「未公開写真をInstagramで見る」「続報はXで配信」 |
【設計の流れ】
- 各SNSの役割を決める→プロフィールに短文で明示
- 記事テンプレート末尾に1文+リンクを固定化
- リンクの並び順は重要度順に統一→迷いを防ぐ
- 導線は少数精鋭(最大3つ)→押す場所を明確化
- 文言は「押すと得られる中身」を短く具体化
ボタン文言と押した後の見え方の最適化
ボタン文言は、クリック前の不安を解く短い説明です。「お問い合わせ」「SNSへ」など抽象的な表現より、「最新入荷をXで確認」「事例写真をInstagramで見る」のように、得られる情報を具体化すると押されやすくなります。
押した後の見え方も大切です。SNS先では、プロフィールや固定投稿の先頭に「何が見られるアカウントか」を一行で示し、記事とのつながりを保ちます。
サムネイルやヘッダー画像は、ブログのトーンと揃えると安心感が生まれます。スマホではボタンの幅と余白が重要です。指で押しやすいサイズを確保し、上下に適度な余白を入れて誤タップを防ぎます。
| 目的 | よくある表現 | 改善した表現 |
|---|---|---|
| 速報へ誘導 | 「Xはこちら」 | 「最新のお知らせ→Xで配信」 |
| 事例へ誘導 | 「Instagramへ」 | 「ビフォー→アフター写真をInstagramで見る」 |
| 動画解説へ | 「YouTube」 | 「手順を動画で解説→YouTube」 |
【最適化のチェック】
- 文言は12〜18文字前後に収め、要点だけにする
- 押した先の固定ポスト・ハイライト・再生リストを整えておく
- 記事内の言い回しとボタン文言を合わせ、違和感をなくす
- 抽象的なCTA→具体的な中身に置き換える(何が分かるかを明示)
- リンク先が雑然→固定投稿やハイライトで導線の入口を整備
固定記事・自己紹介での案内文の作成と配置
固定記事と自己紹介は、初見の読者に「どこから見れば良いか」を伝えるハブです。最初に、ブログの価値とSNSの役割を一文で整理し、代表コンテンツとSNS導線を同じページにまとめます。
固定記事では、上部に「まず読むべき3本」、続いて「速報・写真・動画」の順にSNSへの案内を置くと、迷いが減ります。
自己紹介は、プロフィールの延長として、活動内容とSNS更新の頻度、発信する内容を短く書き、同じ順番でリンクを並べます。
季節の企画やキャンペーンは、固定記事の上部に入れ替えで掲載し、終了後は速やかに差し替えます。更新フローを月1回の点検に組み込むと、古い情報による離脱を防げます。
| 配置 | 書く内容 | 文言サンプル |
|---|---|---|
| 固定記事 | 代表記事+SNS導線のまとめ | 「速報→X」「事例写真→Instagram」「手順動画→YouTube」 |
| 自己紹介 | 活動内容・更新頻度・案内 | 「最新情報はX、事例はInstagram、解説はYouTubeで発信」 |
【作成のコツ】
- 見出し直下に一行の要約→その後に導線ブロックを配置
- リンクは重要度順に固定→毎回の並び替えは避ける
- 画像は明るく文字少なめ→スマホで判読できるサイズに
- 月1回の点検日を決め、固定記事と自己紹介を同時に更新
- 終了した企画や古い案内はすぐ差し替え→信頼低下を防止
リンクカード活用とクリック促進の工夫
リンクカードは、URLを貼るだけでサムネイルとタイトルが表示され、内容が直感的に伝わる手段です。画像とタイトルで「何が分かるか」を一目で示せるため、テキストのみよりクリックされやすくなります。
カード表示にならない環境もあるため、同じ行に短い補足文(例:「事例を写真でまとめました」「動画で流れを確認」)を添えると取りこぼしを防げます。
カードは連続で並べすぎると視認性が落ちるため、1画面に2つまでを目安にします。
記事内では、本文の流れを邪魔しない位置(冒頭後・中盤の区切り・末尾)に1回ずつ配置し、文脈と合うカードだけを残します。クリックの伸びは、サムネイルの明るさと文字の少なさ、タイトルの具体性で大きく変わります。
| 要素 | 工夫ポイント | 例 |
|---|---|---|
| サムネイル | 明るい色・被写体を中央に・文字少なめ | ビフォー→アフターは左右分割の写真 |
| タイトル | 読者の得る結果を具体化 | 「入荷速報を毎朝更新」「事例20枚を写真で解説」 |
| 補足文 | カード前後に一言で中身を説明 | 「図解と手順をまとめました」 |
【配置と検証のコツ】
- 1画面2カードまで→過密を避けて押しやすく
- 同じURLを複数回貼らない→最も効果的な位置だけに集約
- カードが出ない環境に備え、テキスト補足を必ず併記
- カードの連続表示は離脱の原因→間に本文や小見出しを挟む
- 古い画像や曖昧なタイトルはクリック率を下げる→月1で見直し
記事とSNSの相互送客と活用事例の紹介

ブログ記事は「詳しい説明と信頼づくり」、SNSは「短い更新と気づきの回数」を増やす役割を持ちます。両者をつなぐと、読者が迷わず次の行動に進み、再訪と問い合わせのチャンスが増えます。流れの作り方はシンプルです。
記事の冒頭・見出し直下・末尾に1行の案内を置き、X→速報、Instagram→写真事例、YouTube→操作動画のように役割を分けます。
SNS側では、プロフィールリンクや固定投稿・ハイライトに「どのテーマのどのまとめへ戻るか」を明記し、最新記事や比較ページに誘導します。
さらに、週1回の振り返り投稿で「今週の要点→関連記事へ」の復習導線を作ると、思い出す回数が増え、自然検索や指名検索にも良い影響が出ます。下表は検討段階ごとの主役チャネルと導線例です。
| 読者の段階 | 主に使うチャネル | 導線の置き方・文言例 |
|---|---|---|
| 発見・関心 | SNSの短い投稿/記事の導入 | 「詳しくは◯◯のまとめへ」「写真で流れを見る→Inst」 |
| 比較・検討 | 記事本文(表・事例)/固定投稿 | 「料金・違いを表で確認→記事」「決め手の事例→Inst」 |
| 行動・申込み | 記事末尾/プロフィールリンク | 「空き状況→こちら」「無料相談→フォーム」 |
【相互送客の設計ポイント】
- 記事=答えと根拠、SNS=要点と最新の様子→役割を明示
- 案内は1行で具体化→「未公開写真→Inst」「続報→X」
- SNS側の固定投稿・ハイライトに「戻るリンク」を常設
- まずは1テーマで循環を構築→記事3本とSNS投稿3本でセット運用
- 週次でクリックと再訪を記録→文言と位置を少しずつ調整
記事からSNSへ自然に誘導する流れの設計
読者が最も動きやすいのは「読み始め」と「読み終わり」です。冒頭では要点のすぐ下に「写真で流れを見る→Instagram」「速報はXで更新」など1行の案内を置き、本文中は区切りの良い段落後に事例写真や短い動画へ誘導します。
末尾では、その記事に合うSNSの役割をもう一度だけ提示し、ボタンは2つまでに絞ります。
案内文は「押したあと何が見えるか」を具体化し、12〜18文字前後で読みやすくします。毎回の入力が手間なら、記事テンプレートに「案内1行+X/Instリンク」を組み込むと抜け漏れを防げます。
【設計の流れ】
- 冒頭:要点直下に1行の案内を配置(例:未公開写真→Inst)
- 本文:区切りで事例・図解へ誘導(例:図解の拡大→Inst)
- 末尾:次の行き先を再提示(例:続報→X固定ポスト)
【文言サンプル】
- 「ビフォー→アフター写真をまとめて見る→Instagram」
- 「最新のお知らせと入荷情報→Xで配信中」
- 「手順を短い動画で確認→YouTube」
- 例:レビュー記事では冒頭に「全写真→Inst」、本文中で「使用感の動画→YouTube」、末尾で「価格変動の続報→X」の順に置くと、読者の関心の流れと導線が一致し、自然な移動が生まれます。
SNSからブログへ戻す導線と復習導線
SNS側では「どこへ戻るか」をはっきり示すのがコツです。プロフィールリンクは「リンクまとめ」や固定ページに向け、上部に「まず読むべき3本」「比較表」「最新記事」へのリンクを並べます。
Xは固定ポストを「要点→記事リンク」に、Instagramはハイライトを「テーマ別の戻り口(事例/Q&A/キャンペーン)」に整理すると、迷いが減ります。
週1回の「今週の要点」投稿で、要点3つ→関連記事リンクの復習導線を作ると、再訪と指名検索がじわじわ伸びます。
| SNS機能 | 置く内容 | 戻すリンクの例 |
|---|---|---|
| プロフィール | リンクまとめ(まず読む3本/比較/最新) | 「初めての方へ→総まとめ」「料金の比較→記事」 |
| 固定投稿 | 要点3つ+記事リンク | 「失敗しない選び方→解説記事」「事例20枚→ギャラリー」 |
| ハイライト | テーマ別の入口(事例/Q&A/キャンペーン) | 「事例→記事の詳細」「Q&A→長文解説」 |
- 更新が止まったテーマは一時的に非表示→古い案内は離脱の原因
- 同じ記事へのリンクを投稿内で乱発しない→固定投稿に集約
例:毎週金曜に「今週の要点を3つ」→それぞれの関連記事へ戻す投稿を行うと、復習導線が整い、翌週の検索・再訪の底上げにつながります。
事例投稿・ハイライトで信頼構築の工夫
読者が安心して行動できるかは、実例の見せ方で大きく変わります。事例投稿は「前→施策→後」を同じ粒度で示し、写真には一言の結論を添えます。
数値は「件数・割合・期間」をセットで簡潔に。ハイライトは、初見でも流れが分かるよう「入口→比較→決め手→よくある質問→戻るリンク」の順に並べ、最後に関連記事へ戻す導線を入れます。
コメントには早めに返信し、質問が多い内容はQ&Aのスライドに追加。キャンペーンは終了日を明記し、終わったらすぐ差し替えます。
【見せ方のチェック】
- 写真は明るく、比較は同じ角度・同じ距離で
- 結論は1行で先に提示→本文で根拠と手順
- ハイライトは5〜7枚で完結→最後に「詳しく→記事」
| 要素 | 工夫ポイント | 文言・例 |
|---|---|---|
| 事例投稿 | 前→施策→後を同条件で比較 | 「送信率1.5%→2.4%、ボタン文言の変更で改善」 |
| Q&A | 質問は短文、回答は箇条書き | 「料金は?→◯◯円〜/所要時間→◯分」 |
| 戻りリンク | ハイライト末尾に常設 | 「詳しい手順→ブログの解説へ」 |
- 月1回の見直しで古い事例を更新→最新の写真と数値に差し替え
- 批判的な声にも誠実に対応→改善策と期限を一言で提示
例:フォーム改善の事例をInstagramで「前→後→要点→戻りリンク」の4枚で見せ、最後に「詳しい理由は解説記事へ」。このセットをテーマごとに作ると、記事とSNSの往復が自然に増えます。
導線計測と改善サイクルの運用設計と定着

SNS導線の効果を安定して伸ばすには、「計測の仕組み→週次の見直し→小さな修正」を回し続けることが大切です。最初に、表示位置ごとにリンク名(ラベル)を分けます。
例として〈プロフィール=prof_x/prof_inst、記事下=post_x/post_inst、ヘッダー=head_x〉のように統一しておくと、どの導線が押されたかを後から比べられます。
あわせて、URLの末尾に簡単な識別子(例:?from=post_x)のような目印を付けると、アクセス解析や短縮URLのクリック数と結びつけやすくなります。
数字は増やしすぎず、〈クリック数・再訪率・問い合わせ等の完了数〉の三つに絞ると、次の一手が決めやすくなります。
週に一度、上位ページだけを対象に、導線の位置と文言を振り返り、良かった配置を横展開。月に一度、ヘッダーや固定記事の案内を見直せば、古い情報による離脱も防げます。
| 対象 | 計測の置き方 | 見る数字・判断 |
|---|---|---|
| プロフィール | リンク名をSNS別に分ける(prof_x 等) | クリック数が少なければ説明文を追加→翌週再計測 |
| 記事下 | 1文+X/Instリンクをテンプレ化 | 押されない場合は文言を具体化→「未公開写真→Inst」 |
| ヘッダー/フッター | アイコン+短文の横並び→3つまで | 分散が大きければ1箇所に集約→翌週比較 |
- リンク名の統一→場所ごとに必ず分ける
- 数字は三つに固定→クリック・再訪・完了
- 週次で1箇所だけ直す→翌週に効果確認
クリック計測と流入元の見える化の設定
クリック計測は「どこに置いた導線が効いたか」を知るための土台です。はじめに、表示位置×SNSごとにリンク名(ラベル)を分けます。
例:prof_x(プロフィール→X)、post_inst(記事下→Instagram)、head_x(ヘッダー→X)。同じURLでもラベルが違えば、どの場所から押されたかを区別できます。
さらに、URLの末尾に簡単な識別子を付けておくと(例:…/instagram?from=post_inst)、アクセス解析や短縮URLの管理画面で集計しやすくなります。
短縮URLを使う場合は、SNS別・場所別に作成し、名前に「post」「prof」などの接頭辞を付けると、一覧で迷いません。
計測を始めたら、毎週同じ曜日に〈クリック数・再訪の割合・問い合わせ等の完了〉を記録し、3週分だけを見比べます。
増減の理由は「文言変更」「位置変更」「画像差し替え」のどれかに絞ってメモしておくと、次の改善が決めやすくなります。
【設定の手順】
- リンク名のルールを決める(例:prof_x/post_x/head_x)
- URL末尾に識別子を付ける(例:?from=post_x)
- SNS別・場所別に短縮URLを作成→名前で判別可能に
- 週1回、同じ指標で記録→3週単位で良否を判断
| 場所 | ラベル例 | 識別子例 |
|---|---|---|
| プロフィール | prof_x/prof_inst | ?from=prof_x/?from=prof_inst |
| 記事下 | post_x/post_inst | ?from=post_x/?from=post_inst |
| ヘッダー | head_x | ?from=head_x |
- 同じラベルを複数箇所で使わない→比較ができなくなる
- 指標を増やしすぎない→三つに固定して継続を優先
週次レビューと改善タスクの定着の回し方
改善は「小さく早く」が続けるコツです。週に一度、15〜20分だけ時間を取り、先週の実施内容と数字を1枚にまとめます。
見るのは〈クリック数・再訪率・完了数〉の三つだけ。増えていれば「何が効いたか」を言葉で残し、減っていれば「どこを直すか」を1つだけ決めます。
タスクは30〜60分で終わる単位に分割し、担当・期限・判定線(例:クリック率+0.3pt)をセットにします。
翌週は、同じ曜日・同じ指標でビフォー→アフターを確認。良かった配置や文言は、同じ型をほかのページにも横展開します。月末には、ヘッダー/固定記事の案内文も見直して、古い情報の放置を防ぎます。
【レビューの進め方】
- 先週の実施メモを確認→導線の位置・文言・画像の変更点を把握
- 三つの指標を記録→上位ページだけに絞って可視化
- 次の一手を1つ決定→担当・期限・判定線を付与
| 確認項目 | 見る場所 | 次の動き |
|---|---|---|
| クリック数 | 短縮URL/アクセス解析 | 文言を具体化→翌週比較 |
| 再訪率 | 解析のユーザー指標 | 固定投稿・ハイライトで復習導線を追加 |
| 完了数 | 問い合わせ・予約の記録 | 記事末尾のボタン位置を調整→離脱を減らす |
- 会議は15分上限→1つだけ直す→翌週に結果を見る
- メモは「やったこと→数字→次の一手」を1行で統一
A/B比較と勝ちパターンの横展開の手順
A/B比較は「1回に1要素だけ」を守ると効果が読み取りやすくなります。まず、改善したい指標と判定線を決めます(例:記事下のXリンクのクリック率+0.3pt)。
次に、変更する要素を1つに絞ります。文言(例:「Xはこちら」→「最新のお知らせ→X」)、位置(本文直後→末尾)、見た目(ボタン→テキスト)など、どれか1つだけを変えます。
1週間運用して、同じ曜日の並びで比較。勝ちが出たら、同じ条件のページに横展開します。
いきなり全ページに広げず、まずは同カテゴリの3〜5ページで再確認し、効果が安定していれば全体へ広げます。負けた案はメモを残し、次の候補を試します。
【A/Bの進め方】
- 目的・判定線を決める(例:+0.3ptで合格)
- 変える要素を1つに限定(文言/位置/見た目)
- 1週間比較→勝ちを同カテゴリへ展開
| テスト要素 | 案A | 案B |
|---|---|---|
| 文言 | 「Xはこちら」 | 「最新のお知らせ→Xで配信」 |
| 位置 | 本文中の区切り後 | 記事末尾の直前 |
| 見た目 | テキストリンク | ボタン+短い補足文 |
- 一度に複数変更→原因が特定できない(1要素だけに絞る)
- 判定線なし→続行/停止の判断が曖昧(数値目標を先に設定)
例:レビュー記事で「文言のみ」変更し、合格したら同じレビュー系の記事に横展開→安定したらヘッダーや固定記事の案内文にも反映、という順で拡張すると、効果の再現性が高まります。
まとめ
本記事は、SNSボタンの設定→表示位置の最適化→文言設計→相互送客→計測と改善を一気通貫で整理しました。
まずはプロフィールと記事下の導線を整備し、固定記事とリンクカードで案内を強化。最後にクリック計測を仕込み、週次レビューで勝ちパターンを横展開して成果を安定化させましょう。