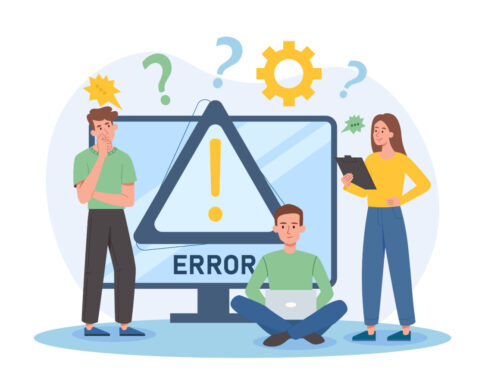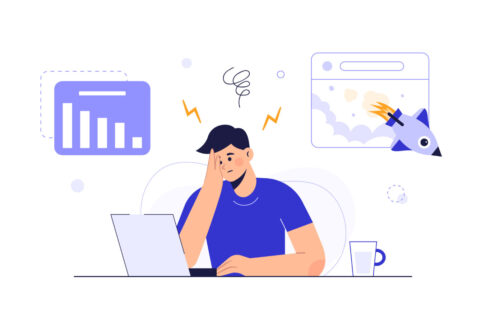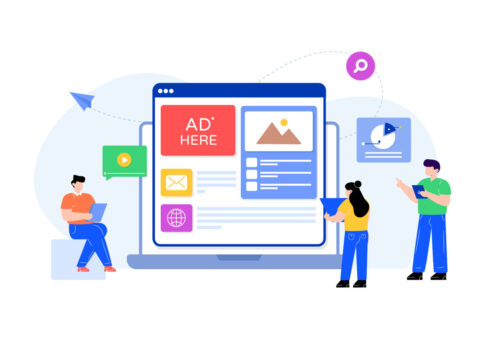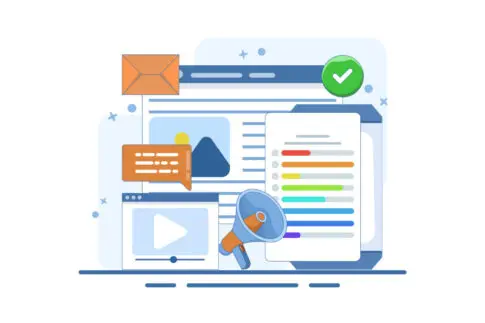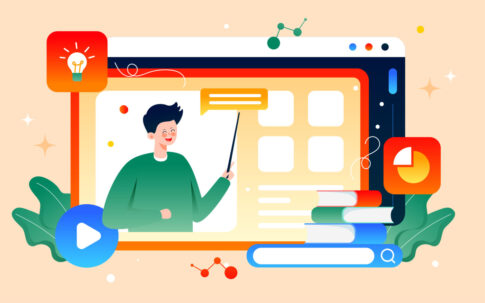「アメブロのアクセス数に自分は含まれる?」に、一次情報と実測で答えます。PV/訪問者の違い、公式リニューアル後の除外方針、混在しやすい場面の見分け方、GA4のIP・ボット除外、判定の記録テンプレまでを整理。今日から“正しい数値”で運用を始められます。
仕組みと一次情報の基礎

アメブロのアクセス数を正しく読むには、用語と計測の前提をそろえることが出発点です。
基本は、ページが開かれるたびに加算される「PV」と、人(ブラウザ)単位での「訪問者(ユニーク)」の違いを理解し、管理画面で表示される「今日」「昨日」「リアルタイム」の粒度の差を押さえます。
公式の案内では、本人アクセスやクローラーを可能な限り除外する方針が説明されており、ログイン状態・端末識別・既知ボットの判定等でノイズ低減が図られます。
ただし、未ログインや新しい端末・共有Wi-Fiなど例外では混在が残り得るため、一次情報(ヘルプ・お知らせ)に沿った前提と、現場の検証を組み合わせて読む姿勢が欠かせません。
以下の表で要点をそろえ、以降の判定・除外・運用につなげます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| PV | ページ表示ごとに加算。記事再読・画像クリック等でも増える可能性 |
| 訪問者 | 人(ブラウザ)単位の概数。日付境界や端末差で変動に注意 |
| 今日/昨日 | 締め時刻や集計遅延の影響を受ける。前日比は移動平均で判断 |
| リアルタイム | 速報値。後で確定値と差が出る前提で傾向把握に使う |
| 本人除外 | ログイン・端末識別で除外強化。未ログインや新端末では混在余地 |
| ボット除外 | 既知クローラーをフィルタ。新種や急増時は取りこぼしに留意 |
PV・訪問者と今日/昨日/リアルタイムの把握
数字を見誤らないためには、「どの数値を、何の判断に使うか」を先に決めます。PVは見られた量、訪問者は来た人の概数という役割分担です。
運用では、前日比や週次比較だけに頼らず、移動平均と曜日比較を組み合わせてブレを均します。リアルタイムは「今、流入が動いているか」を掴むための速報で、確定値と差が出る前提で使います。
業種別に見ると、飲食は「今夜の空席告知→PVスパイク→予約導線まで届いたか」、治療院は「初診記事の訪問者増→所要時間・持ち物ページへの回遊」、ECは「商品PV増→カート到達率」のように、次の動作とセットで評価します。
以下の手順で確認すると、早合点を避けられます。
- PVは記事別の増減→見出し/サムネ/導入の影響を切り分ける
- 訪問者は曜日×デバイスで比較→端末入替や未ログイン影響を把握
- 今日/昨日は集計遅延を想定→週次の移動平均も同時に確認
- リアルタイムは流入源を即確認→SNSスパイクや外部掲出を特定
公式リニューアル情報と除外強化の確認
公式のヘルプやお知らせでは、アクセス解析のリニューアルにより「本人アクセスや既知クローラーを可能な限り除外する」旨が示されています。
実務では、この方針を「完全除外ではなく、例外時は混在し得る」という前提で解釈するのが安全です。
具体的には、ログイン状態・端末やブラウザの識別・既知ボットの判定でノイズを削減しつつ、未ログイン・新端末・共有Wi-Fi・Cookie削除など“本人判定が途切れる”場面では混在が起きやすいと捉えます。
また、既知ボットのリスト更新にはタイムラグがあり、新顔のクローラーは一時的に混入する可能性があります。
運用側は、公式の意図(除外強化)に沿いながら、例外時の検証ルールを持つことで数字のブレを素早く説明できます。
- 「除外=ゼロ」ではない→未ログイン/新端末では混在余地
- リアルタイムと確定値の差→遅延・フィルタ処理の影響を想定
- 既知ボットの更新遅延→短期的なスパイクは外部要因を併記
- 本人除外は状態依存→ログイン維持と同一端末確認を徹底
ヘルプ記述の相違点と注意点の把握
ヘルプの文言は方針や概念の説明が中心で、現場の“例外事象”を網羅していないことがあります。
たとえば「本人アクセスは除外されます」という表現でも、未ログインや初見端末、共有Wi-Fi、ブラウザ変更、Cookie削除直後などは判定が外れやすく、数値に混ざる余地が残ります。
さらに、アプリ閲覧とブラウザ閲覧で参照情報が異なる、日付境界や集計締めに伴う“昨日/今日”のズレ、端末の省電力・通信不安定時にイベントが欠損する、といった実務の揺らぎも存在します。
一次情報の趣旨を尊重しつつ、下表のように「表現→実務解釈→現場の注意」に落とし込むと、チーム内の判断がそろいます。
| ヘルプの表現 | 実務での解釈 | 現場の注意 |
|---|---|---|
| 本人アクセスは除外 | 状態依存で機能。未ログイン/新端末では混在余地 | 検証は同一端末・ログイン維持で実施→例外はメモ |
| クローラーは除外 | 既知ボット中心。新種や急増時は取りこぼし | スパイク時は流入国・UAを確認→短期は移動平均で評価 |
| 今日/昨日の数値 | 締め時刻・処理遅延で確定と差が出る | 週次/同曜日比較を併用→単日判断を避ける |
| PVと訪問者 | 量(PV)と人(訪問)の指標は役割が違う | 目標は混同しない→CTA到達とセットで評価 |
この前提を共有しておくと、急な増減や端末入替時のブレも落ち着いて説明でき、誤ったリライトや施策の空振りを避けられます。
自分アクセス混在の判定
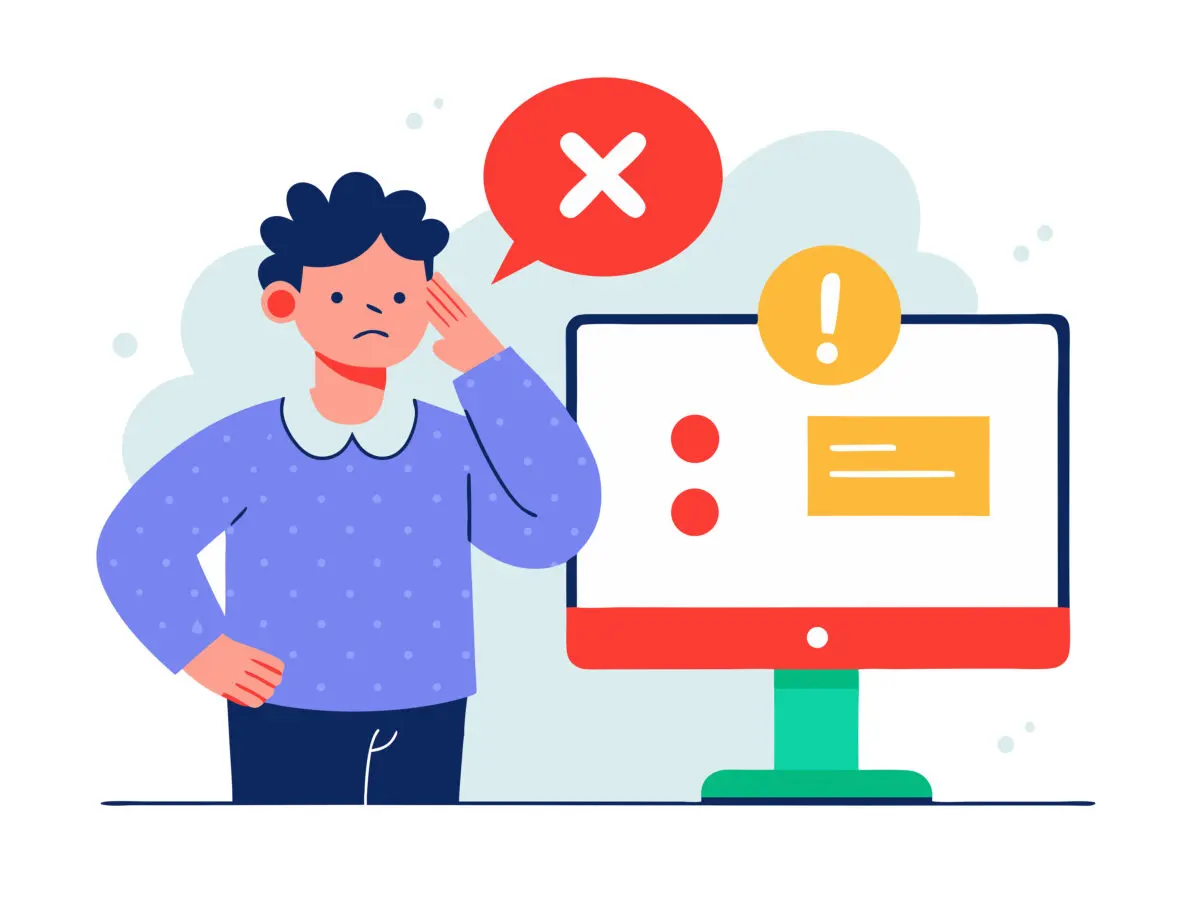
自分の閲覧が混在しているかは、「状態(ログイン/未ログイン)×端末(普段/新端末)×回線(自宅/共有/モバイル)」の三要素で概ね推測できます。
まず前提として、ログインかつ普段の端末・自宅回線での閲覧は除外されやすい一方、未ログインや新端末、共有Wi-Fiでは混在の余地が残ります。判定は感覚ではなく、同一条件での再現テストと、時間帯・リンク元・デバイス指標の突き合わせで行います。
飲食なら「今夜の空席記事」、治療院なら「初診案内」、ECなら「送料/返品ページ」など、動きが読みやすい1本を指標記事に選び、短時間で意図的にアクセスして“差”を見ます。
数値は日次のブレが出やすいため、移動平均と同曜日比較で評価し、差分が継続再現するかを確認すると誤判定を避けられます。
- 判定の基本:状態×端末×回線の三要素で混在リスクを推測
- 検証の基本:同一条件・短時間でテスト→差分が再現するかを見る
- 比較の基本:時間帯/リンク元/デバイス指標を突き合わせ
- 評価の基本:単日ではなく移動平均+同曜日比較で安定判定
ログイン/端末/回線別のチェック
混在の有無は、ログイン状態・端末の既知/未知・回線の性質で大きく変わります。
ログイン+普段端末+自宅回線は最も安全で、編集プレビューや本文確認でも混在は起きにくい傾向です。
未ログインやCookie削除直後、新端末、ブラウザ変更直後、共有Wi-Fi(職場/カフェ/ホテル等)、VPN経由では判定情報が薄くなり、新規訪問として扱われやすくなります。
業種別の検証は、飲食=ランチ前後の指標記事、治療院=夕方〜夜の初診記事、EC=新着/価格改定ページなど、トラフィックが読める時間帯に合わせると差が見えやすいです。
以下のルールを起点に、例外が出た場合はその状態を記録し、次回以降の評価基準に加えましょう。
- ログイン+普段端末+自宅回線:混在リスク 低
- ログイン+新端末 or ブラウザ変更直後:混在リスク 中
- 未ログイン+共有Wi-Fi/VPN/モバイル回線:混在リスク 高
- Cookie削除/端末リセット直後:混在リスク 高(最初の数アクセス)
上記はあくまで目安です。実務では「状態の組合せ」を必ずメモし、同条件での再現性を確認してから結論づけると、誤った判断を避けられます。
時間帯・リンク元・デバイスでの見分け方
自分アクセス混在は、時間帯・リンク元・デバイスの3指標で切り分けると特定しやすくなります。まず時間帯は、検証した短時間(例:19:05〜19:15)に狙ってアクセスし、その直後〜数時間後の確定値に同刻の増分が載っているかを確認します。
リンク元は「その他」「ブックマーク」「不明」が急増していないか、外部SNSや検索の増分と整合しているかを見ます。
デバイスはPC/スマホ/タブレット別、アプリ/ブラウザ別の偏りで判定します。飲食であればピークの直前、治療院は退勤後、ECは夜間帯の比較が効きます。
次の表をチェックリスト代わりに活用してください。
| 項目 | 見分け方 | 補足 |
|---|---|---|
| 時間帯 | 検証10分枠の増分がそのまま載るか | 単発より再現性重視。翌日も同条件で再試行 |
| リンク元 | 「その他/直接」増分が検証回数に近いか | SNS/検索が動いていない時刻で行うと判定しやすい |
| デバイス | 普段使わない端末側にだけ増分が集中 | アプリ/ブラウザの違いも併記して比較 |
| 位置/回線 | 共有Wi-Fi使用時のみ増える | 場所/SSIDを記録。VPN有無も明記 |
| 確定差 | 速報(リアルタイム)と確定値の乖離 | 処理遅延を考慮し2〜3時間後に再確認 |
3指標のうち2つ以上で一致が取れた場合は「混在の可能性高」と判断し、次のh3の手順で確証度を上げます。
検証手順と記録テンプレの導入
検証は「短時間・同条件・再現性」を守るだけで精度が上がります。まず指標記事を1本選び、検証窓(10分)を決め、状態(ログイン/未ログイン、端末、回線、ブラウザ/アプリ)を固定します。
検証窓内に規定回数アクセスし、アメブロと外部解析(例:GA4の自分IP除外をON)を翌日同時刻に比較。
差分が検証回数に近いときは混在の疑いが強まります。業種別に「読まれやすい時間」を窓にすると判定しやすい一方で、外部流入のノイズが増えるので、初回は深夜など静かな時間帯も有効です。
- 指標記事と検証窓を決定→状態(ログイン/端末/回線)を固定
- 窓内で所定回数アクセス→アクセス方法を統一(例:ブックマークのみ)
- 翌日、アメブロと外部解析の同時間帯を比較→差分を計測
- 条件を1つだけ変えて再試行(未ログイン→ログイン 等)→再現性を確認
- 記録をテンプレに保存→次回の基準に反映
【記録テンプレ(例)】
・日時/検証窓:__/__〜__ ・記事:__ ・回数:__
・状態:ログイン(有/無)・端末:__・回線:__・ブラウザ/アプリ:__
・アメブロ増分:__ ・外部解析増分:__ ・差分:__
・リンク元内訳(その他/直接/SNS/検索):__
・所感/次回変更点:__
- 重要ポイント:同条件で差分が再現するかを最優先で確認
- 重要ポイント:変更は一度に1要素のみ→因果を特定
- 重要ポイント:記録テンプレを運用して、チーム間の判断基準を統一
このプロセスを週次で1〜2回回すだけでも、「いつ・どんな条件で混在が起きるか」を早期に把握でき、集計や施策判断の誤差を最小化できます。
除外と併用ツールの実務

自分アクセスやクローラーを極力排して「実際の読者だけ」を捉えるには、アメブロ標準の解析で分かること・分からないことを切り分けたうえで、外部ツールを組み合わせて不足を補う運用が有効です。
基本線は、①アメブロ解析で日々の傾向と記事別の相対比較を行う、②GA4(Google アナリティクス)で自分のIP除外・既知ボット除外を有効化し、時間帯やデバイスの詳細を精査、③サーチコンソールで検索クエリと掲載順位の変化を把握、の三層構えです。
とくに「昨日と今日の差」や短期スパイクはノイズの影響を受けやすいため、同曜日比較と移動平均で均しつつ、入口別(検索/SNS/直接/その他)に分けて評価します。
下表の役割を共有しておくと、チーム内の判断がぶれません。
| ツール | 主な役割 |
|---|---|
| アメブロ解析 | 記事別PV・リンク元・時間帯の傾向確認(除外は“可能な限り”の前提) |
| GA4 | IP除外・ボット除外・デバイス/回線の詳細・ファネル到達の把握 |
| サーチコンソール | 検索クエリ・掲載順位・表示/クリックの変化を確認し、タイトル/見出しへ反映 |
アメブロ解析の項目と限界の把握
アメブロ解析は日常運用に十分な粒度を持ちますが、「本人除外やボット除外は完全ではない」点を前提に読みます。見るべき基本は〈記事別PV・リンク元(検索/SNS/その他)・時間帯・デバイス〉です。
記事別PVは見出し・導入・サムネの効き目を確認する土台、リンク元は入口のバランスを把握する指標、時間帯は更新/再掲のタイミング設計、デバイスはスマホ前提の可読性チェックに直結します。
一方で、IP単位の厳密な本人除外、既知以外のボット判定、検索クエリの特定などは不得手です。
飲食なら「ランチ直前のスパイクがSNSか本人か」、治療院なら「退勤後の初診記事の増分が実読かボットか」、ECなら「セール告知の直後スパイクが購入に届いたか」を切り分ける必要があり、ここは外部ツールと突き合わせて補完します。
- 重要ポイント:記事別PVは相対比較で評価→単日の上下に振り回されない
- 重要ポイント:「その他」増分は本人/共有Wi-Fiの混在を疑い、翌日も同時刻で再確認
- 重要ポイント:時間帯は同曜日比較と移動平均で均す→短期スパイクはメモ化
- 重要ポイント:検索クエリは別途サーチコンソールで特定→タイトル/見出しへ反映
GA4連携とIP除外/ボット除外の導入
GA4は「自分アクセスと既知ボットを外して、残った実利用を精査する」ための中核です。まずプロパティを作成して計測IDをアメブロに設定し、以降は“除外と分解”を優先します。
IP除外(固定回線・職場回線・主要モバイル回線を登録)により本人アクセスを最小化し、既知ボット除外を有効化して巡回ノイズを抑えます。
次に、デバイス/回線(モバイル/PC・Wi-Fi/セルラー)とチャネル(Organic/SNS/Direct/Referral)で到達を分解し、ファネル的に〈表示→記事到達→回遊→CV到達〉の落ちどころを特定します。
飲食は「アクセス急増=席予約到達か」を、治療院は「初診記事→所要/持ち物ページ→予約到達か」を、ECは「商品閲覧→カート到達か」を確認し、弱点へ施策を集中させます。
- 計測IDを設定→リアルタイムで到達確認(導入ミスを先に排除)
- IP除外を登録(自宅/職場/主要モバイル)→本人アクセスの混入を削減
- ボット除外を有効化→既知クローラーの影響を最小化
- チャネル/デバイス別に分解→どの入口で離脱が大きいかを特定
- 目標到達(予約/購入/問い合わせ)に最短の導線を検証→文言/配置を小さく改善
- 補足:短期比較は偶然誤差が出やすい→同曜日×4週移動平均で判断精度を上げる
サーチコンソール併用とクエリ確認の基準
サーチコンソールは「どんな言葉で見つかり、どのページが評価されているか」を示す一次データです。運用の起点は〈表示回数・クリック率・平均掲載順位〉の三点を、ページ×クエリで見ること。
タイトル/説明文/見出しに入れた重要語が実際のクエリと噛み合っているかを確認し、乖離があれば表現を近づけます。
飲食なら「店名+ランチ/予約/席/地名」、治療院なら「部位+痛み+地域/初診/所要」、ECなら「商品名+型番/送料/返品」など“判断語”を優先し、クリック率が低い語はタイトルの先頭側に近づける、説明文に判断材料(所要/価格/納期)を一行足す、といった小さな修正で改善を重ねます。
下表の基準を使うと、迷わずリライト方針を決められます。
| 状況 | 見る指標/切り口 | リライトの方針 |
|---|---|---|
| 表示多×CTR低 | クエリとタイトル語の一致度/先頭位置 | 重要語を先頭側へ、説明文に判断語(所要/価格/納期)を追加 |
| 表示少×順位高 | 関連語の網羅/内部リンクの導線 | 同系記事から内部リンクを追加→小見出しに関連語を自然に含める |
| 順位低×CTRも低 | 競合タイトルの語感/ニーズ適合 | 意図のズレを修正(入門/比較/手順)、事例や数字を足して再評価 |
サーチコンソールのクエリは“読者が使った言葉”そのものです。見出し直下の要点一行や本文の言い回しをクエリに寄せるだけでも、クリック率と滞在の両方がじわりと改善します。
変動時の読み解きと運用

アクセスが大きく動いた時は、まず「実読の増減」か「ノイズ(自分/ボット/一時的拡散)」かを切り分けます。
単日に一喜一憂せず、同曜日比較と移動平均でならしながら、入口別(検索/SNS/直接/その他)とデバイス別の整合を見ます。
飲食なら「SNS告知後のランチ記事でPV急増→予約ページ到達率が伴っているか」、治療院なら「退勤後の初診記事でPV増→所要/持ち物ページの閲覧と問い合わせが増えているか」、ECなら「セール告知後に商品PV増→カート到達が伸びているか」を確認します。
数字が跳ねた直後ほど思い込みが強くなるため、検証用のメモ(時間帯・端末・回線・リンク元)を残しておくと、原因の見落としを避けられます。
- 入口別の増分を確認(検索/SNS/直接/その他)→どこで動いたか把握
- デバイスと地域の偏り→海外や特定端末に偏っていないか
- 指標ページの到達→予約/問い合わせ/カートの動きと整合するか
- 自分/関係者の閲覧の有無→端末・回線・ログイン状態をメモ
PV急増/急減の原因切り分けの比較
急増と急減は、見るべき指標が少し異なります。急増は「入口の広がり」と「深部到達の有無」を対で確認、急減は「入口の縮小」と「表示の不具合/更新間隔」を優先確認します。
下表を使えば、短時間で当たりを付けられます。飲食の急増でSNSが原因なら予約ページ到達率も一緒に伸びるのが自然です。
伸びないならタイトル釣り・読み飛ばし・ボット混入の可能性。治療院の急減で検索が落ちたなら、同キーワード群の表示回数低下と更新間隔の空きが重なっていないかを見ます。ECはセールの終了直後に急減が起きやすく、価格訴求が弱まっただけのケースが多いです。
| 現象 | まず確認する指標 | 判断の目安/次の一手 |
|---|---|---|
| 急増(短時間) | 入口別増分(SNS/直接/その他)と指標ページ到達 | 到達が伴う→実読増。伴わない→釣り/ボット/自分混入→見出し・リンク元点検 |
| 急増(1日〜) | 検索の表示回数/CTR、関連記事の回遊 | 表示回数↑CTR横ばい→タイトル要改善。CTR↑→見出し表現をテンプレ化 |
| 急減(短時間) | 表示速度/画像エラー/リンク切れ | 不具合があれば即修正→再計測。なければ更新間隔とSNS告知の有無を確認 |
| 急減(数日〜) | 検索表示回数/順位、更新状況 | 表示回数↓→需要/季節要因。順位↓→タイトル/見出しをクエリに寄せて小リライト |
いいね/コメント整合で実数判断の改善
PVだけでは実読か判定しづらい時は、アメブロ特有の反応指標(いいね/コメント/読者登録)の整合を見ます。
実読が増えたなら、少なくともどれか一つは上向きます。飲食なら「空席記事のPV急増+予約案内記事へのコメント質問が増える」、治療院なら「初診記事PV↑+“持ち物/所要”への質問が増える」、ECなら「商品PV↑+サイズ/納期への質問が増える」といった一致が目安です。
反応が横ばいのままPVだけ跳ねた時は、SNSでの“見たけど読んでいない”拡散や、その他/直接の増分=自分/関係者の閲覧の可能性を疑います。
次の観点で短く点検し、タイトル・導入・CTAの整合を合わせると、反応率が持ち直しやすくなります。
- 反応の位置:本文前半の結論に近い箇所で反応があるか(早離脱対策)
- 質問の質:価格/所要/場所など“判断語”への質問が増えているか
- 導線の一貫性:本文の言い方=CTA=着地先H1が一致しているか
- 記事タイプ:ノウハウ記事は保存/ブクマ、告知記事はクリック/予約を主指標にする
週次レポートとAB改善サイクルのチェック
変動に強い運用は、週次の“同じ型”で作れます。レポートは〈表示→クリック→深度(スクロール/滞在)→到達(予約/問い合わせ/カート)〉を入口別に1枚化し、最大の落ちどころを一つだけ選定。
改善はA/Bで一要素(見出し語の順序、数字の有無、ファーストビューの一行、ボタン文言/色)に限定し、同曜日×同時間帯で最低1週間比較します。
勝ち案はテンプレへ昇格、負け案は表現を微修正して入替席で再挑戦。飲食は告知時間帯と席情報の出し方、治療院は初診“所要/持ち物/刺激目安”の一行、ECは価格/送料/納期の近接配置など“判断行”を毎週見直すと、反応率がじわりと改善します。
- 同時に多要素を変更→因果不明に。変更は一要素に限定
- 短期の当たりで採択→偶然の可能性。同曜日×4週で裏取り
- PV中心の評価→行動未確認。到達(予約/問い合わせ/カート)で判定
- 報告だけで未実施→次週の“実施担当と期限”をレポートに明記
この小さな改善サイクルを続けるだけで、スパイクや凹みに振り回されず、安定して「実読」を伸ばせます。数字は“責めるため”ではなく“次の一歩を決めるため”に使い、同じ型で淡々と積み上げていきましょう。
まとめ
要点は、①仕様を一次情報で確認②ログイン・端末・回線で混在を判定③GA4のIP/ボット除外とサチコで補完④週次で差分を見て小さく改善、の4つです。
まずは除外設定とチェックリストを導入し、同一条件で計測→差分だけ直す運用に切り替えましょう。