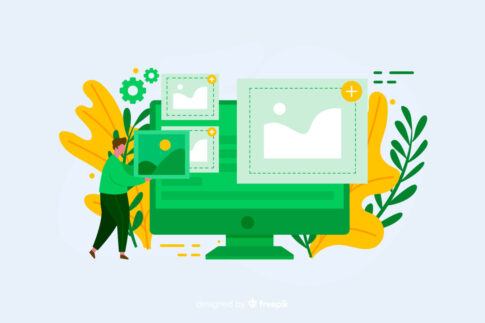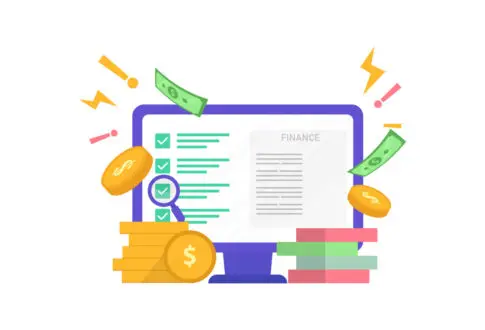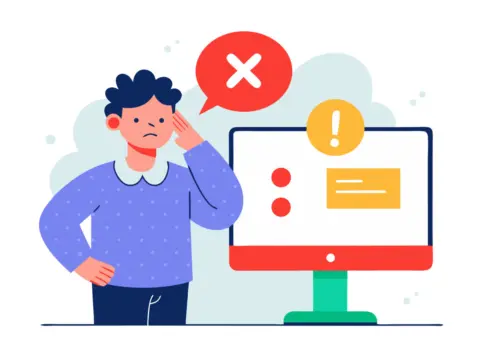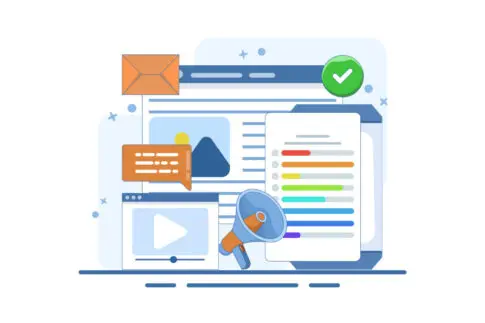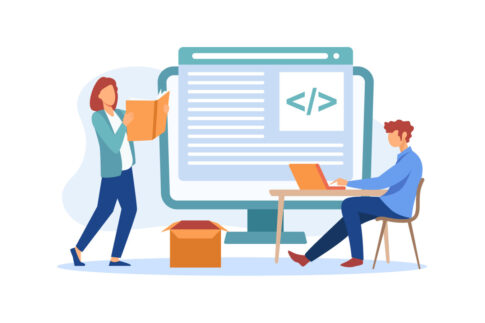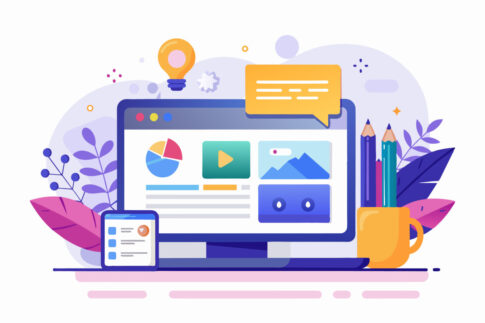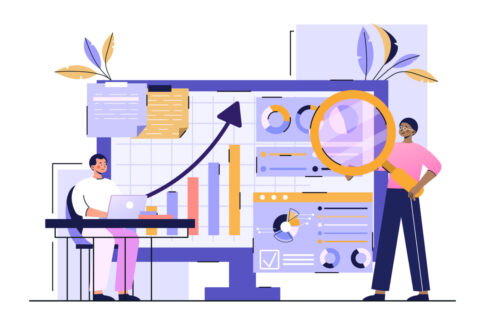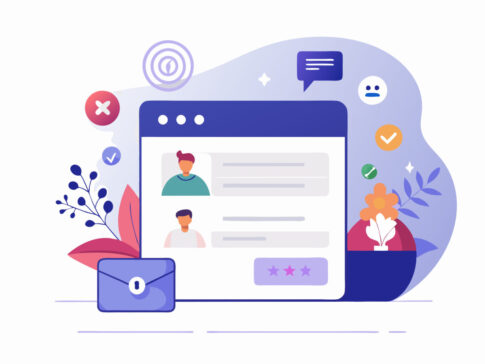アメブロの「囲み枠」は、要点を目立たせて読みやすさと回遊を高める強力な装飾です。本記事では、囲み枠のメリット3つと基本効果、効果が出る配色・線幅・余白、見出し直下/まとめ前の最適配置、使い方テンプレと応用(CTA・内部リンク)、表示崩れを防ぐ注意点までを実例ベースで解説していきます。
目次
囲み枠のメリットと基本効果

囲み枠は「目立たせる」「分ける」「動かす(行動させる)」の3作用で記事の体験を底上げします。まず視認性の面では、地の文と見た目を切り替えることで重要情報を一瞬で認識でき、スクロール中の取りこぼしを防げます。
次に情報設計の面では、関連項目をひとかたまりにまとめることで文脈迷子を減らし、長文でも読みやすさを維持できます。
最後に行動の面では、CTA(次にしてほしい行動)を囲みで強調し、内部リンクのクリックやお問い合わせ導線へ自然に誘導できます。
実務では「見出し直下に要点」「本文中盤に補足・注意」「まとめ前にCTA」を基本の3定位置として使い分けると効果が安定します。
強調過多は逆効果になりやすいため、1画面あたり1つを目安に、色・線幅・余白を控えめに整えるのがコツです。まずは既存記事の“読者が迷いそうな箇所”から、囲み枠で道標を置くイメージで導入しましょう。
| 目的 | 典型の配置 | 効果確認の指標 |
|---|---|---|
| 視認性 | h2直下で要点・結論をひと言 | 冒頭離脱の低下、スクロール率の改善 |
| 情報整理 | 本文中盤で補足・注意・用語を整理 | 滞在の体感向上、読み戻りの減少 |
| 行動喚起 | まとめ前でCTAと関連リンク | 内部リンクCTR・問い合わせ遷移の上昇 |
- 見出し直下→結論・要点の簡潔提示
- 本文中盤→補足/注意/チェックの整理
- まとめ前→次の一歩(CTA・関連ガイド)
視認性アップと要点の強調
視認性を高める囲み枠は、装飾ではなく“読み手のナビゲーション”です。最優先は可読性で、彩度の高すぎる色や太すぎるボーダーは避け、本文と十分なコントラストを確保しながらも主張しすぎない設計にします。
おすすめは「背景:ごく薄い色」「線幅:1〜2px」「角丸:4〜8px」「内側余白:上下12〜16px/左右16〜24px」。見出し直下では、本文を読む前に“何が分かるか”をひと言で宣言し、3行以内で収めるとスクロールを阻害しません。
目立たせたい単語は太字よりも「改行+短文」で視線を止める方がスマホでは効果的です。加えて、小さなアイコン(例:チェック・ビックリ)を先頭に添えると、意味の想起が速くなります。
実例として、料金や期限など“数値情報”は囲み枠にまとめると誤読を防げます。逆に、本文全体を囲む“なんでも枠”は視覚疲労を生むため避けましょう。
強調対象は1枠1テーマに絞り、複数テーマを並べる場合は枠同士の間に十分な余白を確保します。
| 項目 | 設定の目安(スマホ前提) |
|---|---|
| 背景色 | 本文より+5〜10%の明度差(薄グレー/薄ベージュなど) |
| 線幅/角丸 | 1〜2px/4〜8pxで控えめに、情報の主役は内容に |
| 余白 | 上下12〜16px/左右16〜24px→窮屈さを解消 |
- 色の主張が強すぎ→薄色+細線へ調整
- 1枠に情報を詰め込み→短文3行以内+箇条書きで簡潔化
- 連続配置で“全部重要”化→1画面1枠を目安に間隔を空ける
情報整理で読みやすさ向上
読みやすさは「意味のまとまり」を視覚で示せるかに左右されます。囲み枠は、用語解説・注意事項・手順サマリー・関連リンクの束ねに適しています。
まず本文の流れを壊さない位置(段落の切れ目)に置き、同系情報をひとまとめにします。3要素までなら本文中で箇条書き、4要素以上なら表の方が視線移動が楽です。
長文化しやすい“注意点”は、本文では要旨だけ述べ、枠内で「やる・やらない・例外」の3点に整理すると迷いが減ります。
また、章の途中で論点が変わる“橋渡し”にも枠は有効です。たとえば「ここまでの要点→次章で何を解説するか」を短く示すと、読者はペースを保てます。
リンクを枠に含める場合は、1枠1リンクに絞り、アンカーは内容が分かる語にします(例:→内部リンク設計の型)。
最後に、同じ種類の枠はスタイルを統一し、読者に“これは注意枠だ”“これはポイント枠だ”と学習させるとスクロールが楽になります。
- 用語・定義→最初の登場段落の直後
- 注意・禁止事項→該当手順の直前(実行前に可視化)
- 要点サマリー→章末の橋渡しとして次章を示す
| 用途 | 配置の目安 | 中身の作り方 |
|---|---|---|
| 用語解説 | 初出直後 | 1行定義+例を1つ→冗長な背景説明は本文側へ |
| 注意事項 | 作業直前 | やる/やらない/例外の3分割で判断を速く |
| 手順まとめ | 章末 | 箇条書き3〜5点→詳細は本文へ戻す導線を1本 |
CTA強調で回遊率を底上げ
CTAの役割は“次の一歩”を迷わせず提示することです。囲み枠でCTAを強調する際は、①何が得られるか(ベネフィット)②何をするか(行動)③どこへ行くか(リンク先)を短文で並べます。
文言は「名詞+効果」→「動詞」の順にすると視線の滑りが良く、例として「内部リンク設計の型|5分で図解を確認→チェックリストを見る」のように書くとクリック理由が明確になります。
配置は“まとめ前”が基本で、記事の理解が深まった直後に提示すると遷移率が上がります。複数CTAは競合するため、主要CTAは1つに絞り、補助はテキストリンクで控えめに添えましょう。
また、内部リンクの行き先はハブ記事(総合ガイド)やチェックリストなど“受け皿”にすると回遊が安定します。外部リンクCTAは一次情報や公式ヘルプなど、読者の疑問解消に直結する先へ。
計測は、枠内リンクのCTR、遷移先での滞在の体感、戻り率を見て、文言や配置を小さくABテストします。アイコンや矢印(→)は視線誘導に効きますが、過度な装飾は逆効果です。
| CTA種類 | 最適配置 | 文言の型(例) |
|---|---|---|
| 内部ガイド | まとめ前/章末 | 「◯◯の手順|図解5分→チェックリストを見る」 |
| 問い合わせ | 比較・意思決定直後 | 「無料相談|要点だけ確認→問い合わせフォームへ」 |
| 一次情報 | 主張直後 | 「定義の原典→公式ヘルプを確認」 |
- 行動が曖昧→動詞を具体化(登録する/図解を見る)
- 訴求が多すぎ→主要CTAを1つに、補助はテキストで
- リンク先が弱い→ハブ/公式/図解など“受け皿”へ差し替え
デザインと配置の最適解

囲み枠は「読みやすさを保ちながら要点と行動を際立たせる」ための道具です。最適解は、派手さよりも“控えめで一貫した設計”と“迷いを減らす配置”にあります。
色は本文と十分なコントラストを保ちつつ薄めに、線は細めに、余白は広めにして窮屈さを避けます。
配置は視線の流れに沿って、〈見出し直下=要点宣言〉→〈本文中盤=補足/注意〉→〈まとめ前=CTA〉の3定位置を基本にします。
多用は逆効果のため、1画面1枠・1枠1テーマを徹底し、同種の枠はスタイルを統一して「これは注意」「これはポイント」と一目で分かる状態を作ります。
最後に、見出しや表・画像との干渉を避けるため、前後に短い導入文を挟み、リンクは1枠につき1本に絞ると可読性とクリック率の両立が可能です。
| 観点 | 設計の基本 | ねらい |
|---|---|---|
| 色/線 | 薄色背景+1〜2pxの細線 | 主張しすぎず中身で惹きつける |
| 余白 | 上下12〜16px/左右16〜24px | 窮屈さ解消→読みやすさ維持 |
| 配置 | 見出し直下・本文中盤・まとめ前 | 視線の流れに沿って誘導 |
- 1枠1テーマ・1画面1枠で過剰強調を防ぐ
- 同種の枠は色と線を統一→学習効果で迷いを減らす
- 前後に短文を挟み、画像や表と干渉しない配置にする
色・線幅・余白の選び方
色・線・余白は可読性を決める最重要要素です。色は本文より明度を5〜10%上げた薄色(薄グレー/薄ベージュ等)を基本にし、警告や注意だけは彩度をわずかに上げます。線幅は1〜2px、角丸は4〜8pxで控えめにまとめると、スマホでも“囲みすぎ感”が出ません。
余白は上下12〜16px・左右16〜24pxを目安に広く取り、行間を詰めないことで圧迫感を回避します。背景色と文字色のコントラストは十分に確保しつつ、原色や蛍光色は避けると長文でも疲れにくくなります。
見出しと同系色を選ぶと統一感が出る一方、枠が主役化しやすいので、要点語は太字より“短文+改行”で止めるのがスマホ向きです。アイコンは意味が即時に伝わるもの(チェック/注意)を小さく添え、過度な絵文字は避けます。
最後に、リンクを入れる枠は未訪問/訪問時の色差が分かるようにし、指で押しやすい行間を確保しましょう。
| 項目 | 推奨の目安 | 理由/効果 |
|---|---|---|
| 背景色 | 本文より明度+5〜10%(薄色) | 主張しすぎず要点だけ浮かせる |
| 線幅/角丸 | 1〜2px/4〜8px | 情報が主役・装飾は脇役に徹する |
| 余白 | 上下12〜16px/左右16〜24px | 圧迫感回避→可読性とタップ性の両立 |
- 濃色+太線で主張過多→薄色+細線へ調整
- 余白不足で窮屈→上下左右の内側余白を拡張
- リンク密集→1枠1リンク+指で押せる行間にする
見出し直下とまとめ前の配置
配置は効果を左右します。見出し直下は“その章で得られること”を3行以内で宣言する場所で、読者の期待値を合わせて離脱を防ぎます。本文中盤は補足・注意・用語解説を短文化して置くと、流れを崩さず理解を支援できます。
まとめ前はCTA(次の一歩)に最適で、内部ガイドやチェックリスト、問い合わせの導線を1つだけ提示するとクリックが集中します。
いずれも枠の前後に短い導入文を挟み、画像・表・広告と連続しないよう“呼吸”を確保するのがコツです。
スマホでは1画面の要素数が限られるため、枠→短文→本文のリズムを守ると読みやすさとCTRが両立します。
枠内リンクのアンカーは「名詞+効果」→「動詞」の順(例:内部リンク設計|図解5分→チェック)で、クリック後の価値が一目で伝わるようにしましょう。
| 位置 | 目的/入れる内容 | 運用ポイント |
|---|---|---|
| 見出し直下 | 要点宣言・ベネフィット提示 | 3行以内/リンクは入れても1本 |
| 本文中盤 | 補足・注意・用語の簡潔整理 | 段落の切れ目/同系情報を束ねる |
| まとめ前 | CTA・次の一歩の提示 | 主要CTAは1つ/受け皿はハブやチェック |
- h2直下で“何が分かるか”を先出し
- 中盤で補足・注意を短文化して誘導
- 最後にCTA枠→内部ガイドや申込へ誘導
多用を避ける適量の目安
囲み枠は“量”で品質が決まります。多用すると「全部重要」に見えて逆効果になり、読了率とクリック率が落ちます。目安は〈1画面1枠・1枠1テーマ〉で、同じ画面に2枠を並べないこと。
記事全体では、1500〜2000字で3枠前後、3000字で4〜5枠が上限の目安です(用途が重ならない場合のみ)。同種の枠は章ごとに最大1つに抑え、注意枠が連続する場合は1つを本文内の箇条書きへ置き換えます。
計測は、枠の有無によるスクロール率・内部リンクCTR・滞在の体感を比較し、効果が薄い箇所は削除またはテキスト化して軽量化します。
枠を残す基準は「枠がないと誤読や迷子が増えるかどうか」。疑わしいものは思い切って外し、情報を本文の短文+箇条書きで再配置すると、視線の迷いが減ります。
| 記事ボリューム | 適量の目安 | 分配の例 |
|---|---|---|
| 〜2000字 | 2〜3枠 | h2直下/中盤/まとめ前に各1 |
| 2000〜3000字 | 3〜4枠 | 要点・補足×2・CTA |
| 3000字超 | 4〜5枠 | 章が増える分だけ中盤枠を追加 |
- “全部重要”化→1画面1枠・1枠1リンクに統一
- 同種枠の連続→片方は本文の箇条書きへ置換
- CTR低下→文言を短文化/位置を見出し直下かまとめ前へ移動
使い方テンプレと実例

囲み枠を“毎回ゼロから作る”のは非効率です。よく使う場面ごとにテンプレを用意しておけば、迷わず早く整った記事に仕上げられます。
ここでは、①注意書き・ポイント提示、②リストや表の整理、③画像・リンクとの組み合わせ、の3カテゴリでそのまま流用できる型と実例をまとめます。
基本は〈1枠1テーマ〉と〈見出し直下/中盤/まとめ前〉の3定位置。文面は短く、3行以内+箇条書きで“パッと見で意味が通る”設計にします。
色は薄色、線は細め、余白は広めを徹底し、本文とのコントラストを保ちながら主張しすぎないことがコツです。
最後に、各枠に入れるリンクは1本までに絞り、押した後に得られる価値を近接文でひと言添えるとクリック理由が明確になります。
| 用途 | 推奨配置・頻度 | 文面の骨子 |
|---|---|---|
| 注意/ポイント | 該当手順の直前・章の冒頭/各章1回 | 要点1行+根拠1行+例1行(最大3行) |
| リスト/表の整理 | 中盤の段落の切れ目/記事あたり1〜2回 | 見出し1行+箇条書き3〜5点、または2列表 |
| 画像/リンク連動 | 見出し直下(図解)、まとめ前(CTA) | ベネフィット1行+行動1行+リンク1本 |
- 注意書き枠:やる/やらない/例外の簡潔セット
- チェックリスト枠:3〜5項で抜け漏れ防止
- CTA枠:ベネフィット→行動→リンクの順
注意書き・ポイント提示の型
注意枠は“誤解や手戻りを防ぐ”ための最短ルートです。長文化すると肝心の注意が埋もれるため、結論→理由→例(または代替)を各1行で示すのが安全です。
章冒頭なら「この章で守るべき線引き」、手順直前なら「実行前に確認すべき条件」を置き、読者の行動前に視線を止めます。色は薄い警告色(薄オレンジ/薄黄色)にして、本文に溶け込みつつ注意の意味が伝わるようにします。
下記テンプレは、そのまま文言だけ差し替えて使えます。
| 用途 | タイトル例 | 文面テンプレ |
|---|---|---|
| 手順前の注意 | 投稿前に必ず確認 | 結論:◯◯を公開前に点検してください。理由:××のため表示崩れが起きやすくなります。例:画像は長辺1200px目安に統一。 |
| 規約/ルールの線引き | やってよいこと・NGの線引き | やる:◯◯/やらない:△△/例外:□□(状況Aのみ可)。不明点は→◯◯の詳細ガイド。 |
| ポイント提示 | 今日のポイント3つ | 要点:①◯◯ ②△△ ③□□。詳しい理由は本文中の「◯◯」章で解説。 |
- 結論→理由→例(代替)の順に3行で完結
- 動詞は具体化(確認する/統一する/差し替える)
- リンクは1本だけ→近接文で“何が分かるか”を明記
- 長文で要点が埋もれる→3行までに圧縮
- 色が強すぎて本文が負ける→薄色+細線へ調整
- 注意を連発→片方は本文の箇条書きに置換
リストや表を包む整理術
情報量が多い章は、枠で“ひとかたまりに見せる”と理解が速くなります。チェックリストは3〜5項まで、用語や違いの比較は2列または3列の表を枠で包むと、視線が散らずに読み進められます。
テーブルはスマホ前提で、2列は左25%/右75%、3列は左20%/中40%/右40%を目安にすると折り返しが安定します。
枠のタイトルは“目的語+対象”で短く(例:投稿前チェック、画像サイズの目安)。箇条書きは1行1意味にし、動詞から始めると行動につながりやすいです。
| ケース | 枠タイトル | 構成テンプレ |
|---|---|---|
| 投稿前チェック | 公開前チェックリスト | 箇条書き3〜5点(タイトル・画像サイズ・リンク到達性・プレビュー・予約時刻) |
| 用語/違いの整理 | ◯◯と△△の違い | 2列表で定義/使いどころ/注意点を並置 |
| 比較/選び方 | おすすめの選び方 | 3列表で“基準/◯◯が向く人/△△が向く人” |
【枠で包む実例(チェックリスト)】
- タイトルを20〜25文字で明確化(例:投稿前チェックリスト)
- 行動動詞で始める(画像を圧縮する/リンクを1本に絞る)
- 終わった項目は絵文字や記号で自分向けにチェック
- 2列は25/75、3列は20/40/40で見やすく
- 1セルは1情報→改行を入れて“塊”を小さく
- 表の直前直後に短文を挟み、流れを保つ
- セル内の長文→要点語+改行で2行に分割
- 項目が5つ超→章を分けるか、不要な列を削る
- リンクを複数詰める→1枠1リンクに統一
画像・リンクとの組み合わせ
画像やリンクは、囲み枠と組み合わせると“理解の速さ”と“次の一歩”が同時に高まります。図解や完成イメージは見出し直下の薄色枠で、キャプションを「何が分かるか」中心に短文で添えます。
リンクはまとめ前のCTA枠でベネフィット→行動→リンク1本の順。画像とリンクを同じ枠に入れる場合は、上:画像、下:1行説明→リンクの縦並びがスマホで読みやすいです。
外部埋め込みの重さが心配なときは、静止画+テキストリンクへ置き換えると表示が安定します。
| パターン | 構成 | 使いどころ/注意 |
|---|---|---|
| 図解+説明 | 画像→1行説明→補足1行 | 見出し直下。画像は長辺1200px目安、余白広め |
| 画像+CTA | 画像→ベネフィット1行→リンク | まとめ前。主要CTAは1つに絞る |
| テキスト+リンク | 要点1行→リンク1本 | 中盤の補足。外部は一次情報中心に |
- 画像は“説明が要る1枚”だけを厳選→類似は間引く
- リンクは1枠1本→アンカーは内容が分かる語に
- 画像下にベネフィット1行→クリック理由を明確化
- 重い埋め込み→静止画+テキストリンクへ置換
- タップ密集→行間と余白を広げ、指で押せる間隔に
- 折り返し崩れ→プレビューでスマホ幅を必ず確認
集客に効く応用テクニック

囲み枠は「読む→理解する→行動する」の各段階で役割が変わります。まず冒頭〜序盤では、見出し直下の薄色枠で“この記事で得られること”を3行以内で宣言し、離脱を抑えます。
中盤では、関連小テーマを1枠1テーマで整理し、迷いを減らすことでスクロールの勢いを保ちます。終盤では、まとめ前のCTA枠で“次の一歩(内部ガイド・比較・問い合わせ)”を1つだけ提示し、回遊と成約への導線を固定します。
さらに、枠のスタイルを記事横断で統一すると、読者は「注意枠」「ポイント枠」「CTA枠」を見た瞬間に意味を理解できるため、クリックの判断が早まります。
最後に、各枠に入れるリンクは1本まで、アンカーは“名詞+効果→動詞”の順に短文化し、近接文でクリック後の価値を一言添えると、自然な遷移が生まれます。
| 段階 | 枠の目的/置きどころ | 中身の作り方(要点) |
|---|---|---|
| 冒頭 | 見出し直下で価値宣言 | ベネフィットを3行以内/リンクは入れても1本 |
| 中盤 | 補足・注意・用語の整理 | 1枠1テーマ/箇条書き3〜5点/同系情報を束ねる |
| 終盤 | CTAで“次の一歩”を提示 | 主要CTAは1つ/受け皿はハブ・比較・チェック |
- 1画面1枠・1枠1リンクで選択肢を絞る
- 色/線/余白を統一し、意味で識別できるようにする
- 近接文で“クリック後に得られること”を一言で提示
内部リンク導線の設計方法
内部リンクは「受け皿(ハブ)→深掘り(詳細)→実践(チェック/比較)」の三層で設計すると、囲み枠との相性が最も良くなります。
まずサイト内で“必ず読ませたい”ハブ記事を1〜3本決め、各記事の見出し直下に薄色のポイント枠を置いて、ハブへ戻る導線を固定します。
次に中盤の補足枠では、今読んでいる章に直結する詳細記事だけを1本だけ提示(「◯◯の図解→5分で確認」など)。
そしてまとめ前のCTA枠で、読後の行動に最短で到達する受け皿(チェックリスト・比較・問い合わせ)へ丁寧に誘導します。
重要なのは“広く”より“深く”。関連記事を並べるよりも、読者の次の疑問に1対1で答えるリンクに絞ると、CTRと満足度が同時に伸びます。
| 役割 | リンク先の種類 | 枠の置き場所/文言例 |
|---|---|---|
| ハブ | 総合ガイド/目次 | 見出し直下|「全体像→図解で把握」 |
| 詳細 | 個別解説/事例 | 中盤補足|「◯◯の手順→画像つきで確認」 |
| 実践 | チェック/比較/問い合わせ | まとめ前CTA|「抜け漏れ防止→チェックを見る」 |
- リンク乱立→各枠1本に統一、目的が重複する先は削除
- 文言が曖昧→「名詞+効果→動詞」に短文化
- 受け皿が弱い→ハブ/比較/チェックなど“使える先”へ差し替え
CTAボックス文言の作り方
CTA枠の文言は「ベネフィット→証拠/安心→行動」の3点で組み立てます。まず“読むとどう良くなるか”を短く提示(例:回遊率が上がる/誤設定を防ぐ)。
次に“根拠や安心材料”を一言(図解あり/テンプレ付き/3分で読める)。最後に“具体的な行動”を動詞で明示し、リンクは1本だけ添えます。
数字や時間を入れると期待値が揃い、クリックの迷いが減ります。文量は2〜3行が目安。行頭に小さなアイコンや「→」を置くと視線が走りやすくなります。
| 要素 | 作り方 | 例文 |
|---|---|---|
| ベネフィット | 成果や解決を具体化(数/時間) | 「5分で配置の最適解が分かる」 |
| 証拠/安心 | 図解/テンプレ/チェックの提示 | 「図解+チェックリスト付き」 |
| 行動 | 動詞で明確化/1リンクのみ | 「→配置チェックを今すぐ見る」 |
- 学習系:「3分で要点だけ→図解を見る」
- 比較系:「最短で選べる→比較表を開く」
- 相談系:「迷ったら→無料相談フォームへ」
計測と改善の簡易チェック
囲み枠の効果検証は“軽く・早く・1点ずつ”が原則です。公開直後〜1時間は初動を、当日〜翌日は回遊を観察します。見るべきは〈枠内リンクCTR〉〈見出し直下枠後のスクロール率の体感〉〈まとめ前CTAからの遷移〉の3点。
数が取りにくいときでも、クリックの反応やコメント内容、滞在の手触りで仮説を立て、次の記事で1点だけ変更(位置/文言/リンク先)を試します。
改善の順序は、①見出し直下の価値宣言を短文化、②中盤の補足枠は内容を1テーマに絞る、③CTA枠は文言に数字と動詞を入れ、リンクは1本に削る——が鉄板です。
| 項目 | 確認タイミング | 次の一手 |
|---|---|---|
| 初動(閲覧) | 公開後1時間 | 価値宣言を3行→2行へ短縮/要点語を先頭へ |
| 回遊(内部CTR) | 当日〜翌日 | 中盤枠のリンク先を“直結の詳細”に差し替え |
| 成約(CTA遷移) | 翌日 | CTA文言に数字/時間/動詞を追加し1本化 |
- 変更を一度に多発→必ず1点だけ変えて因果を明確に
- リンクが多すぎ→各枠1本/主要CTA1つに整理
- 位置が悪い→見出し直下かまとめ前へ移す
まとめ
囲み枠は「視認性アップ」「情報整理」「CTA強調」の3点で成果に直結します。
色・線幅・余白は控えめに整え、配置は見出し直下とまとめ前を基本に、使いすぎを避けて適量運用。テンプレ化→計測→微調整の循環を回せば、記事の読みやすさと回遊率を継続的に伸ばせます。