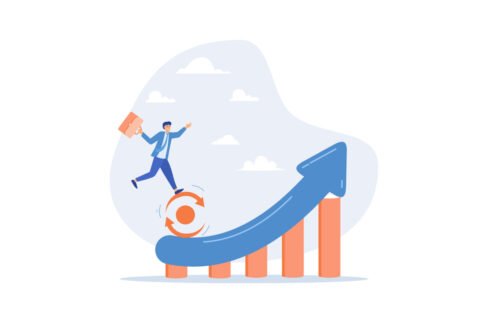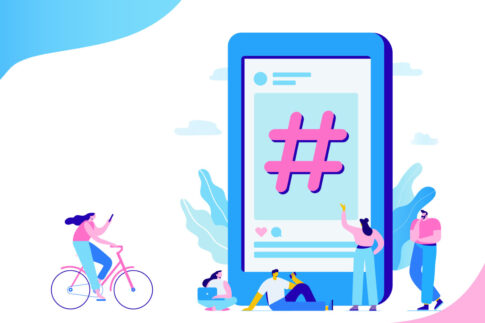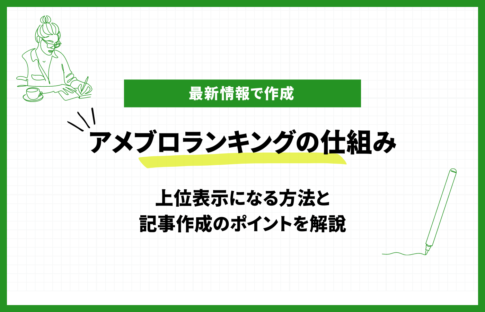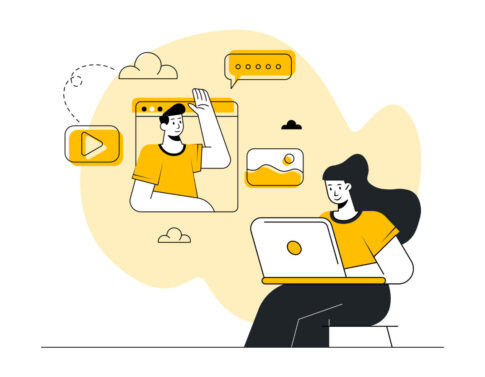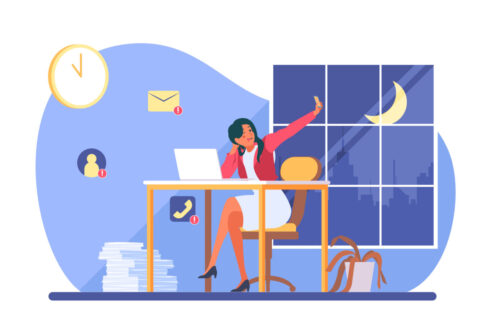アメブロのアクセスは“内部リンク設計”で伸ばせます。本記事では〈基本と目的〉〈設置場所と導線〉〈リンクカード/テキストの使い分け〉〈カテゴリー別導線〉〈計測・改善〉の5手順を、初心者にも分かりやすく解説していきます。回遊率と滞在時間を高め、成約につなげる実践ポイントをご紹介します。
アメブロ内部リンクの基本と目的
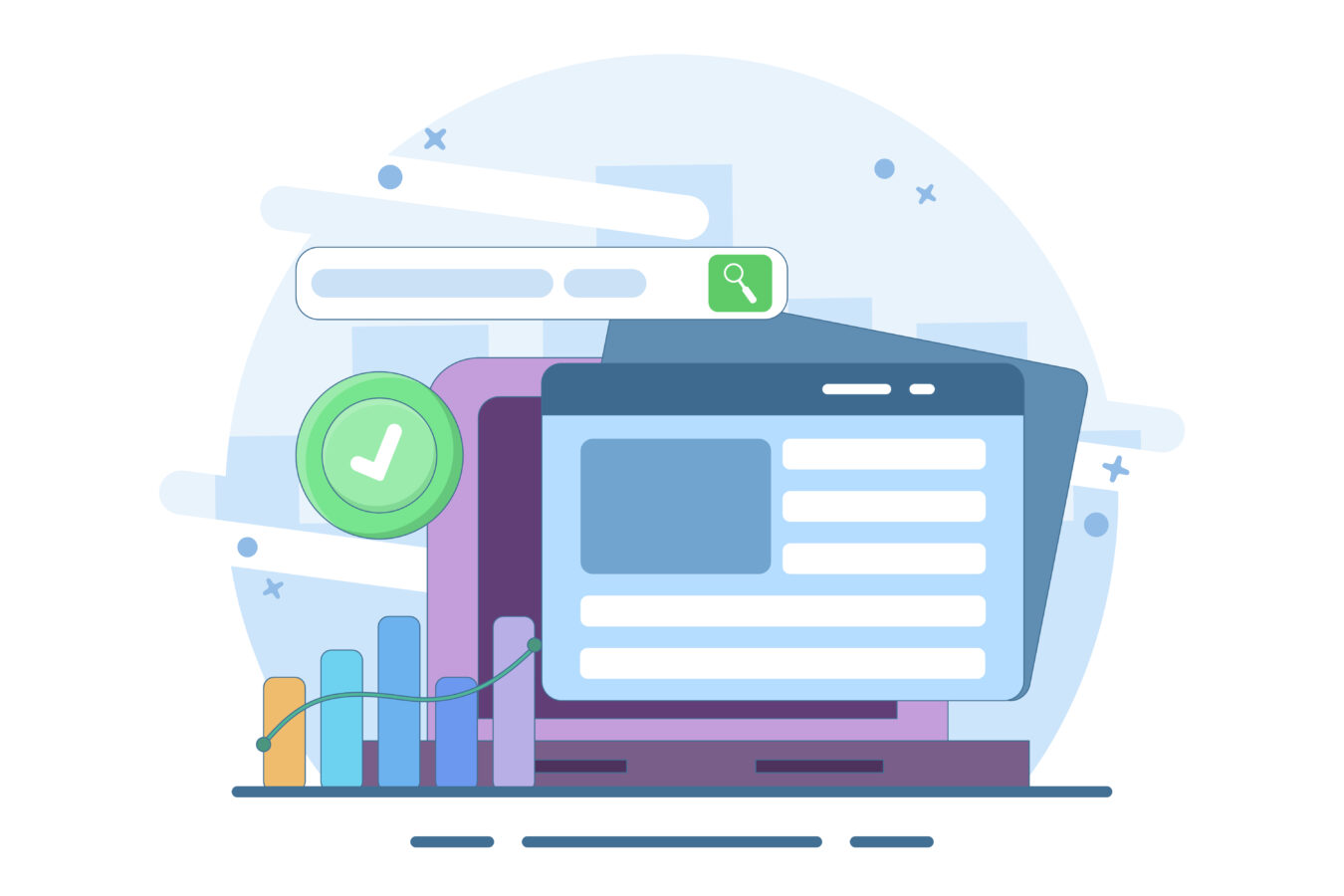
内部リンクとは、同じブログ内の別記事・固定ページへ読者を案内するリンクのことです。目的は大きく分けて、読者の回遊を高めること、検索エンジンに記事同士の関係性を伝えること、そして収益記事やコンバージョン記事へ迷いなく導くことの三点です。
たとえば「スキンケア入門」を読んだ人が、本文の流れに沿って「クレンジングの選び方→化粧水の使い方→クリームの比較」に進めるようリンクを配置すると、滞在時間が自然に伸び、満足度も上がります。
アメブロはスマホ比率が高いため、文中リンクは短い文章で前後の文脈を整え、押しやすい位置に置くのが基本です。
まずは主要カテゴリごとに“起点記事”を決め、その記事から関連の深い学習順に内部リンクでルートを作ると、初めての読者でも迷いにくくなります。
| 目的 | 具体的な効果 |
|---|---|
| 回遊 | 関連記事へ自然誘導→ページ/セッション増→離脱抑制 |
| 検索 | 記事同士の関連性を明示→重要記事に評価を集中 |
| 収益 | ノウハウ記事→比較記事→レビュー記事へ段階導線 |
- 起点記事→解説記事→比較/レビューの順でルート化
- リンク前に「読む理由」を一文で提示→クリックの納得感を高める
- 優先カテゴリと起点記事
- 学習順のリンク階層(入口→深掘り→収益)
- スマホ優先の設置位置(段落頭・結論直後)
SEOとユーザー回遊の基礎
内部リンクは、読者の「次に読みたい」を先回りして提示するナビゲーションであり、同時に検索エンジンへ構造を伝えるシグナルでもあります。
アンカーテキスト(リンクの文言)は短く具体的にし、「こちら」ではなく「化粧水の選び方」など内容が想像できる表現にします。階層は浅くシンプルに保ち、重要記事へは複数の入口を用意すると到達率が上がります。
直帰が多い記事には本文中の前半にも内部リンクを置き、読了前の離脱を防ぎます。計測では、クリック率・ページ/セッション・滞在時間を定点観測し、リンク位置変更や文言差し替えで改善します。
- アンカーは具体名で内容を示す→読者も検索エンジンも理解しやすい
- 直帰が高い記事は本文前半にも内部リンク→早期離脱を回避
- 重要記事へ複数の入口→カテゴリトップ、人気記事、本文中
- 同じ段落に無関係なリンクを多量設置→読者が迷う
- 「こちら」など中身が不明なアンカーの多用→クリックされにくい
- 本文とリンク先の不一致→否定的な体験で離脱増
内部リンクの種類と役割
アメブロで主に使うのは「リンクカード」と「テキストリンク」です。リンクカードはサムネイルとタイトルが並ぶため視認性が高く、特集や推したい記事の訴求に向きます。
テキストリンクは文中に自然に溶け込み、読者の理解が深まった直後に“次の一歩”を提示できます。
加えて、プロフィール・サイドバー・フッターの固定導線や、カテゴリ(テーマ)一覧・月別アーカイブも内部導線として機能します。役割が異なるため、強調したい箇所はカード、理解補助はテキスト、と使い分けるのが基本です。
| 種類 | 役割 | 使いどころ |
|---|---|---|
| リンクカード | 視覚訴求・クリック誘発 | 導入直後/まとめ直前の強調、特集・収益記事 |
| テキストリンク | 文脈内の理解補助 | 用語解説直後、手順の次の段階、比較の根拠提示 |
| 固定導線 | 入口の一貫性担保 | プロフィール/サイドバー/フッターの常設リンク |
| テーマ/月別 | 網羅的な回遊 | 「もっと読む」動機が強い読者向けの一覧導線 |
- カードは「今読んでほしい一本」を明確に提示
- テキストは短く具体的なアンカーで文脈を崩さない
- 強調=カード/理解補助=テキストの原則
- 一画面にカードは1つ程度→過剰強調を避ける
クリック誘導と読みやすさ設計
クリックは「文脈→リンク→得られる価値」の順で生まれます。まず段落の冒頭で読者の疑問を一文で提示し、すぐ後ろに答えへつながる内部リンクを置きます。
アンカーテキストは名詞中心で短く、リンク直前にベネフィット(何が分かるか)を添えると、押す理由が明確になります。
スマホでの可読性を最優先し、リンクは指が届きやすい位置に配置、連続リンクは避け、段落間に余白を確保します。
本文末だけでなく、重要な根拠や結論の直後にも一つ置くと、理解が深い瞬間に次記事へ進んでもらえます。
- 段落の主旨を最初に一文で提示→疑問を明確化
- 直後に関連リンク→「読む理由」を短く添える
- 結論直後にも再提示→理解のピークで遷移を促す
- アンカー例→「化粧水の選び方」「乾燥肌向け成分表」
- 配置例→導入直後/解説直後/まとめ前の三点
- 「こちら」「詳しく」だけの曖昧アンカー
- 一文にリンクを複数挿入→誤タップ増
- 本文と無関係な誘導→離脱と不信感につながる
設置場所と導線設計の実践テンプレ

内部リンクの「どこに置くか」は、回遊と読了率に直結します。基本は〈記事冒頭→本文途中→末尾〉の三点配置で、読者の関心が高まるタイミングに合わせて導線を用意します。
冒頭では“この記事で得られること”に直結する一本を、途中では解説の直後に理解を深める関連記事を、末尾では次に読むべき“本命記事(比較・まとめ・収益記事)”を提示します。
スマホ閲覧が多いアメブロでは、押しやすい位置と短いアンカーテキストが鍵です。また、記事ごとに「起点→深掘り→収益」の役割を決めてリンクを張ると、ブログ全体で学習順がそろい、読者が迷いにくくなります。
下表を目安に、まずは直帰の高い記事から配置を整え、クリックとページ/セッションを定点観測して改善を回しましょう。
| 配置 | 狙い | 実践のコツ |
|---|---|---|
| 冒頭 | 読者の疑問に即応→離脱抑制 | 導入直後に1本だけ提示→アンカーは「〜の基本」など具体名 |
| 途中 | 理解直後の遷移→回遊拡張 | 用語解説の直後に関連リンク→1段落1リンクを目安 |
| 末尾 | 次の行動を明確化 | 本命記事を1〜2本に厳選→カードで視覚的に強調 |
- 三点配置(冒頭・途中・末尾)を必ず用意
- アンカーは短く具体的→「こちら」は避ける
- 1画面にカードは1つ程度→過剰強調を防ぐ
- 直帰率の高い記事を抽出→三点配置を先行整備
- クリック率・ページ/セッションを毎週チェック→位置と文言を差し替え
- 成果記事への導線は末尾でカード強調→文中はテキストで自然誘導
記事冒頭・途中・末尾の配置
冒頭・途中・末尾は読者心理が異なります。冒頭は「探していた答えに出会えるか」を見極める瞬間なので、導入直後に“解決の核心”へつながる内部リンクを一本だけ提示します。
例えば「アメブロ 内部リンク とは?」の記事なら、冒頭で「内部リンクの基本と効果」を示す基礎記事へ。途中は理解が深まる局面です。
用語解説の直後や手順の区切りで「用語集」「チェックリスト」「比較記事」へ進めると、自然に回遊が伸びます。末尾は次アクションの決定フェーズ。比較・まとめ・収益記事など“読者が今知りたい最終回答”へ導きます。
【配置のポイント】
- 冒頭→導入直後に1本だけ。ベネフィットを前置きして「読む理由」を明確化
- 途中→1段落1リンクを目安。解説直後に“理解を補強する”関連記事へ
- 末尾→本命記事を1〜2本に厳選。リンクカードで視覚的に強調
また、同一段落に複数リンクを詰め込むと誤タップが増え、可読性が下がります。スマホ優先で行間を確保し、リンクの前後は短文で区切ると押しやすくなります。
シリーズ記事では、冒頭に「前回」「次回」をテキストで、末尾に「まとめ・比較」をカードで、という“役割分担”が有効です。
週次でクリックとページ/セッションを確認し、冒頭リンクは文言、途中リンクは位置、末尾リンクはカード/テキストの形式を入れ替えてABテストを回しましょう。
結果が出やすいのは、導入直後の一文とアンカーテキストの具体化(例:「こちら」→「内部リンクの基本」)です。
別タブ設定と離脱防止の基本
内部リンクは“新しいタブで開く”設定を活用すると、元の記事を残しつつ回遊を広げられます。特に長文記事や比較検討が必要な読者には効果的で、読み戻りが容易になり滞在時間が伸びます。
一方で、すべてを別タブにすると端末上でタブが増え過ぎ、かえって混乱を招くこともあります。基本は、本文中の参考リンクや用語解説は別タブ、同一ストーリーで必ず読ませたい“次章的リンク”は同タブ、と使い分けます。
モバイルではOSやブラウザの挙動により別タブが新しいウィンドウになる場合があるため、公開前プレビューで実機確認を行いましょう。
- 別タブ推奨→用語集・参考・外部引用・比較表
- 同タブ推奨→ストーリー上の次記事・シリーズの続き
- 実機確認→iOS/Androidの標準ブラウザで動作をチェック
- 全リンクを別タブ→タブが乱立し迷子になる
- 戻る導線が無い→パンくず/関連記事が不足
- 外部リンクの過多→ブログ外で滞在が終わる
テスト運用では、同一記事で「途中リンクは別タブ/同タブ」を週替わりで試し、ページ/セッションと直帰率を比較します。
外部サイトへ飛ばすリンクは必ず内部リンクの直後に置き、先に自サイト内の次行動を提示してから外部へ誘導すると、離脱の影響を抑えられます。末尾では「次に読む」候補を2本以内に絞り、ボタン風テキストかカードで明快に示すと効果的です。
画像周りとボタン体裁の整え方
画像の近くは注目が集まりやすく、内部リンクの“押しどころ”になります。画像直下に短文+テキストリンクを置くと、視線の流れが途切れずクリックが生まれます。
リンクカードは画像と競合しやすいので、一画面にカードは1つまでに抑え、他はテキストで自然に誘導します。
ボタン体裁は、アメブロの装飾機能(太字・行間・記号)を使い、周囲に十分な余白を取り、タップ領域を広げるのがコツです。アンカーは名詞中心で短く、前後にベネフィットを一文添えて“押す理由”を明示します。
| 要素 | 配置のコツ | 文言の作り方 |
|---|---|---|
| 画像直下 | 短文→リンクの順で配置→上下に余白 | 「内部リンクの基本を3分で確認」など価値を先に提示 |
| ボタン風テキスト | 太字・前後に空行→1画面1つを目安 | 「比較表を見る」「設置テンプレをダウンロード」 |
| リンクカード | まとめ前で1つだけ強調→他はテキスト | タイトルをそのまま表示して内容が分かる形に |
【体裁チェック】
- 画像の直下に“次の一歩”を必ず用意→視線が流れるうちに誘導
- 一文は30〜40文字程度で改行→モバイルで読みやすく
- アンカーは名詞中心で7〜12文字→誤タップ防止に間隔を確保
- 結論直後の画像→直下に「根拠記事」への短いリンク
- カードの直前に一言ベネフィット→クリック理由を言語化
- ボタン風テキストは記事内1回→乱用せず目立たせる
画像自体をリンクにする場合は、同時に代替テキストも整えて可読性を担保します。装飾は“強調のための節度”が大切で、過度なアイコンや連続カードは逆効果です。
週次でクリックヒート(クリックの多い位置)を観察し、画像直下リンクの文言と位置を微調整していきましょう。
リンクカードとテキストの使い分け

アメブロの内部リンクは「リンクカード」と「テキストリンク」を使い分けることで、読者の視線誘導とクリック動機を両立できます。
リンクカードはサムネイルとタイトルで内容を瞬時に伝えられるため、強調したい記事や次の一手(比較・まとめ・収益記事)へ導く場面に向いています。
一方、テキストリンクは文脈の流れを崩さずに自然な遷移を作れるため、用語解説の直後や結論の直後など“理解が深まった瞬間”で効果を発揮します。
まずは記事構成上の役割を「起点→深掘り→比較→収益」に分け、起点・比較・収益にはカード、深掘りにはテキストを基本線に設計すると、過度な装飾を避けながら回遊を伸ばせます。
スマホ閲覧を想定し、一画面のカードは1つ程度に抑え、他は短いアンカーのテキストで補うと誤タップや読みづらさを防げます。
| 形式 | 得意な役割 | 配置の目安 |
|---|---|---|
| リンクカード | 視覚的強調・注目記事の提示 | 導入直後/まとめ直前/CTA手前に1つ |
| テキストリンク | 文脈内の理解補助・細やかな誘導 | 用語解説後/結論直後/手順の区切り |
- 強調したい一本→カード、理解を後押し→テキスト
- カードは一画面1つまで→他は短いアンカーで補助
リンクカードの活用場面と効果
リンクカードは、視覚で内容を把握できるため「今読んでほしい記事」を明確に示すのに適しています。特集・比較・ランキング・まとめ・体験談など、クリック後の満足度が高い“主役級”の導線に置くと効果的です。
設置場所は、導入直後(読者の期待を固める)、本文の山場直後(理解が高まった瞬間に提示)、まとめ直前(次の一歩を提示)のいずれかに厳選します。
複数のカードを連続すると視線が分散するため、一画面1つまでとし、他の関連はテキストで補助しましょう。
カード直前にはベネフィットを短文で添えるとクリック動機が明確になります(例:〈比較表で最短ルートを確認できます〉)。
- 推したい記事に集中→カードは“主役”限定で使用
- カード直前に一言ベネフィット→クリック理由を言語化
- カードは改行と余白で囲む→誤タップと読みづらさを回避
| 場面 | 狙い | 実践のコツ |
|---|---|---|
| 導入直後 | 「読む価値」を即提示 | 特集/まとめへ1つだけ提示→他は本文で後追い |
| 山場直後 | 理解のピークで遷移 | 根拠→すぐ比較・事例へ。前置きは1文で簡潔に |
| まとめ直前 | 次アクションを明確化 | 比較/収益記事へ誘導→カード+テキストで二段提示 |
- 連続カードの多用→視線が散り主役が不明確
- 本文と無関係なカード→離脱・不信感の原因
テキストリンクの文中設置術
テキストリンクは、文脈のリズムを保ったまま“次に読む理由”を提示できるのが強みです。基本は「主旨提示→説明→リンク→補足」の順で、リンク直前に読者の得られる価値を短文で示します(例:〈用語の定義は以下で詳しく解説〉)。
同一段落に複数リンクを詰め込むと誤タップと読みにくさを招くため、1段落1リンクを目安にします。
用語解説の直後、チェックリストの直後、結論の直後など“理解が進む瞬間”に置くとクリックされやすく、導入・途中・末尾の三点に散らすと回遊が安定します。
スマホ前提で、リンクの前後には余白を作り、アンカーは名詞中心で短く具体的にすると、読みやすさと押しやすさが両立します。
| 設置位置 | 相性の良い内容 | 文例(リンク直前の一言) |
|---|---|---|
| 用語解説後 | 基礎/用語集/入門記事 | 「定義の一覧は下記で確認できます」 |
| 手順の区切り | チェックリスト/テンプレ | 「実践用の手順テンプレはこちら」 |
| 結論直後 | 比較・事例・収益記事 | 「具体例と比較は次の記事で解説しています」 |
- 1段落1リンクを目安→誤タップと迷いを防ぐ
- リンク直前に価値を一言→クリックの理由を明確化
- 導入・途中・末尾の三点配置→回遊の安定化
- 画像直下に短文+リンク→視線の流れで押されやすい
- 外部リンクは内部リンクの後に配置→離脱を抑制
アンカーテキスト作成基準の基本
アンカーテキストは「何が得られるか」を端的に示すのが基本です。「こちら」「詳しく」は避け、内容やメリットが想像できる名詞中心の短文にします。文字数は7〜12文字程度が目安で、スマホでも読み切れる長さにすると誤タップが減ります。
記事の意図に合わせ、〈入門/基礎/手順/比較/事例/チェックリスト〉などのラベル語を活用すると、読者は次の行動を選びやすくなります。
アンカーは文脈と一致させ、リンク先のタイトルと大きく乖離させないことも信頼性の点で重要です。
計測では、クリック率だけでなく遷移先の滞在と回遊も見て、文言の粒度(抽象→具体)や語尾(名詞止め→説明付き)をABで検証します。
- 名詞中心・短く具体→「内部リンクの基本」「比較表を見る」
- ラベル語の活用→入門/基礎/手順/比較/事例/一覧
- 文脈一致→直前の説明と同じ語をアンカーに採用
- 「こちら」「詳しくはこちら」→具体語へ置換(例:内部リンクの基礎)
- 長い説明文そのまま→7〜12文字へ要約
- 本文と無関係な語→直前のキーワードをアンカーに再利用
- 現状アンカーを洗い出し→曖昧語を具体語へ差し替え
- トップ5記事でABテスト→クリックと回遊で評価
- 勝ちパターンを他記事へ横展開→表記を統一
カテゴリー別の内部導線

アメブロの「テーマ(カテゴリ)」は、読者が迷わず必要な情報へ進むための“案内板”です。まずは各テーマに「起点記事(入門)」を1つ決め、そこから「深掘り(解説・事例)→比較(まとめ)→収益(レビュー・申込導線)」へ進む矢印を、内部リンクで一本のルートとして設計します。
記事個別で最適化するのではなく、テーマ単位で起点と終点を固定すると、ブログ全体の回遊が安定します。
横断リンクは便利ですが、テーマをまたぐ導線は関連性の高いものに限定し、基本は同テーマ内で完結させると迷いが減ります。
カテゴリトップに「まず読む」「次に読む」「最後に読む」の3本を常設し、各記事の冒頭・本文中・末尾に同じ順序のリンクを繰り返すと、初見の読者でも進むべき道が直感的に分かります。
| テーマ役割 | 導線の核 | 配置の例 |
|---|---|---|
| 入門 | 基本概念と全体像 | 冒頭に「まず読む」を固定→本文中に用語集→末尾で深掘り |
| 深掘り | 手順・事例・注意点 | 用語解説直後にチェックリスト→結論直後に比較へ |
| 比較・まとめ | 選び方と分岐 | 章末で各ケースへ分岐→末尾は収益記事をカードで提示 |
- 起点→深掘り→比較→収益の順を全記事で統一
- カテゴリトップに3本導線を常設→各記事でも同順で繰り返す
シリーズ記事の相互リンク設計
シリーズ構成は、読者の学習順を自然に積み上げられる強力な型です。各回の冒頭に「前回」「今回のゴール」「次回」をテキストリンクで明記し、末尾では「次回」「総まとめ」をカードで強調します。
記事タイトルだけでは連続性が伝わりにくいため、本文冒頭でシリーズ全体の目次を短く置き、現在地を示すと離脱が減ります。
途中の章では、用語や手順の節目に“復習リンク”を差し込み、理解が進む瞬間に次の回へ進めるのがポイントです。公開順が前後した場合も、各回の末尾に最新の順序で並べ替えたリンク集を置いて整合性を保ちます。
- 冒頭→「前回/今回のゴール/次回」を明示
- 本文中→用語・手順の節目に復習リンクを1つだけ
- 末尾→「次回」「総まとめ」をカードで強調(1画面1枚)
- 回ごとに導線表現がバラバラ→読者が現在地を見失う
- 連続カードの多用→主役が不明確になりクリック低下
人気記事・関連記事の連携
「人気記事(アクセス上位)」や「関連記事」は、読者の“今知りたい”に最短で応える補助導線です。
自動掲載に頼り切るとテーマ外の記事が混ざることがあるため、カテゴリごとに手動でリンク集を用意し、季節性や更新日を定期点検すると精度が上がります。
関連記事は、本文の文脈に沿う短いテキストリンクを基本にして、まとめ前だけカードで強調します。
人気記事は入門・比較のような“入口・判断”系を上位に保ち、収益記事だけを前面に出さない方が回遊が安定します。クリック後の滞在や離脱も併せて見て、古い情報や重複テーマは差し替えましょう。
- 関連記事→本文中は短いテキスト、まとめ前のみカード
- 人気記事→入門・比較を上位に、収益は混在させて自然誘導
- 月次点検→季節性・重複・鮮度で入れ替え
| チェック項目 | 見直しの観点 |
|---|---|
| クリック率 | 文言が抽象的→具体語へ置換(例:「こちら」→「内部リンク入門」) |
| 滞在時間 | ミスマッチの可能性→リンク先の導入を読者像に合わせる |
| 直帰率 | 古い・重複テーマ→最新記事へ差し替え |
テーマ一覧・月別リンクの整理
「テーマ一覧(カテゴリリスト)」と「月別リンク(アーカイブ)」は、探索型の読者に有効です。テーマ一覧は各カテゴリの起点記事へ必ずつなげ、説明文を一行添えて“どんな悩みが解決するか”を明確にします。
月別リンクは時系列の追跡に便利ですが、情報の鮮度差が出やすいため、古い入門記事には冒頭に最新まとめへのリンクを置き、最短で現行の情報へ導くと親切です。
どちらの一覧にも“まず読む/次に読む/最後に読む”の3本を再掲し、入口の一貫性を保つと迷いが激減します。
- 各テーマは起点記事へ直結→一行で解決内容を明記
- 月別は古い記事の冒頭に最新まとめへ誘導
- 一覧の各ブロックに「まず→次→最後」の3本導線を再掲
- 見出しの語尾は名詞止め→一覧での視認性が上がる
- 一画面にカードは1枚→他はテキストで軽量化
- 四半期ごとに一覧を棚卸し→断捨離と差し替えで鮮度維持
計測・改善と失敗対策の運用手順

内部リンクは「設置して終わり」ではなく、数値で確認→原因を仮説化→小さく改善、の循環が大切です。
まずは週次で対象記事を決め、リンクのクリック数とクリック率、ページ/セッション、直帰率・離脱率を同じ期間・同じ流入で比較します。
次に、どの位置・どの文言・どの形式(カード/テキスト)が効いているかを切り分け、1回の改善では変数を一つだけ動かします。
スマホ比率が高い前提で、誤タップが起きていないか、スクロールの浅い帯でリンクが埋もれていないかも確認します。
改善後は、勝ちパターンのみをテンプレ化して他記事へ横展開し、負けパターンは記録して再発を防ぎます。記事の性質(入門/比較/収益)ごとに目標指標を変えると、無理のない改善が進みます。
| 指標 | 見るポイントと初動 |
|---|---|
| リンクCTR | 低い→アンカーが抽象的。具体語へ差し替え、前後にベネフィットを一文追加 |
| ページ/セッション | 伸びない→途中リンクが少ない。解説直後に1本追加して導線を短縮 |
| 直帰率 | 高い→冒頭リンクを強化。導入直後に“答え”へつながる1本を配置 |
| 離脱率 | 高い→末尾の本命リンクを厳選。カード1つ+補助テキストに整理 |
- 対象記事を決めて基準期間の数値を記録
- 変数を一つだけ変更(位置/文言/形式)
- 同期間で比較→勝ちパターンをテンプレ化
クリックと回遊率の測定ポイント
測定の目的は「どのリンクが、どの読者に、どの位置で効いているか」を把握することです。最初に、導入直後・本文途中・まとめ前の三点を基準位置としてクリック数とクリック率を把握します。
次に、ページ/セッションと滞在時間を併せて見て、クリック後に読了されているかを確認します。クリックだけ増えて滞在が伸びない場合、リンク先の導入が読者像とズレている可能性があります。
スクロールが浅い帯にリンクが集中していると押されにくいので、視線のたまり場(画像直下・見出し直後)へ移動させると改善が出やすいです。
外部リンクは内部リンクの直後に置き、先に自ブログ内の「次の一歩」を提示してから外へ出すと回遊が安定します。
- 位置別のCTR→導入/途中/末尾で最適位置を判定
- 遷移先の滞在→クリック後に読まれているか
- 出口の把握→離脱ページで導線の漏れを特定
| 症状 | 初期アクション |
|---|---|
| CTRが低い | アンカーを具体語に変更→前後に「得られること」を一文追加 |
| ページ/セッションが伸びない | 本文途中の“理解直後”に1リンク追加→導線を短縮 |
| 滞在が短い | リンク先の導入を読者像に合わせて書き換え |
リンク過多・不一致の見分け方
リンク過多は、読者の迷いと誤タップを招きます。兆候は、同一段落に複数リンク、1画面にカードが2枚以上、本文テーマと無関係な誘導が散見される、などです。
不一致は、アンカーの表現とリンク先の内容がずれ、クリック後に「求めていた情報ではない」と感じさせる状態です。
対策はシンプルで、1段落1リンク、1画面1カード、アンカーは名詞中心で短く具体、の三原則を徹底します。
直帰が高い記事では、冒頭リンクのアンカーを本文のキーワードと一致させ、リンク先タイトルとも整合させると誤解が減ります。
シリーズ物は「前回/次回/総まとめ」の三点だけを固定し、その他は文中の補助リンクに留めると過密を避けられます。
- 1段落に2本以上のリンク→整理対象
- カードが連続して表示→1枚に削減
- アンカーとリンク先のタイトルが乖離→語を揃える
| 問題 | よくある原因 | 是正のコツ |
|---|---|---|
| 誤タップ増 | 連続リンク・余白不足 | リンク間に空行→周囲を短文で区切る |
| 離脱増 | 無関係な誘導・外部リンクの前置き | 内部リンク→外部リンクの順に並べ替え |
| 信頼低下 | アンカー誇張・内容不一致 | 名詞止めで具体→内容と語を一致 |
A/Bテストと差し替え運用の型
A/Bテストは、小さな変更で確実に学びを得るための型です。テスト前に仮説を一文で明文化し、変更点は一つに絞ります(例:アンカー「こちら」→「内部リンクの基本」)。
期間と評価指標(クリック率・ページ/セッション・遷移先の滞在)を事前に決め、同じ曜日と流入条件で比較します。勝ちが出たら即テンプレ化し、同系の記事へ横展開。
負けは「やらないリスト」に残し、再実装を防ぎます。差し替えは“在庫管理”の発想が有効で、月次でリンクの棚卸し→古い・重複・不一致を除去→新規記事を編入、の順に回します。
季節記事は期初に入替を前倒しするとムダが減ります。
- 仮説を一文化→「〇〇の方がCTRが上がる」
- 変数を一つ→位置/文言/形式のいずれか
- 評価指標を固定→CTR・ページ/セッション・滞在
- 勝ちをテンプレ化→同系記事へ横展開
| テスト項目 | 狙い | 負けた時の撤退基準 |
|---|---|---|
| アンカー文言 | 抽象→具体でCTR改善 | CTR±1pt未満なら現状維持、別位置テストへ |
| 設置位置 | 導入/途中/末尾の最適帯を特定 | 滞在短縮が出たら元位置へ戻す |
| 形式(カード/テキスト) | 視覚強調と可読性のバランス | 連続カードでスクロール率低下→テキストへ戻す |
- 対象記事の数値を記録→仮説と変更点を一文で定義
- 1変更のみで2週間比較→曜日と流入を合わせる
- 勝ちをテンプレへ反映→月次棚卸しで全体に展開
まとめ
内部リンクは、読者を次の記事へ迷いなく導く設計です。まずは記事冒頭・本文中・末尾に関連リンクを1つずつ配置し、別タブ設定と明快なアンカーテキストを徹底します。
リンク過多は避け、クリックと回遊率を定点観測→差し替えで改善。今日から3記事を相互リンク化して運用を始めましょう。