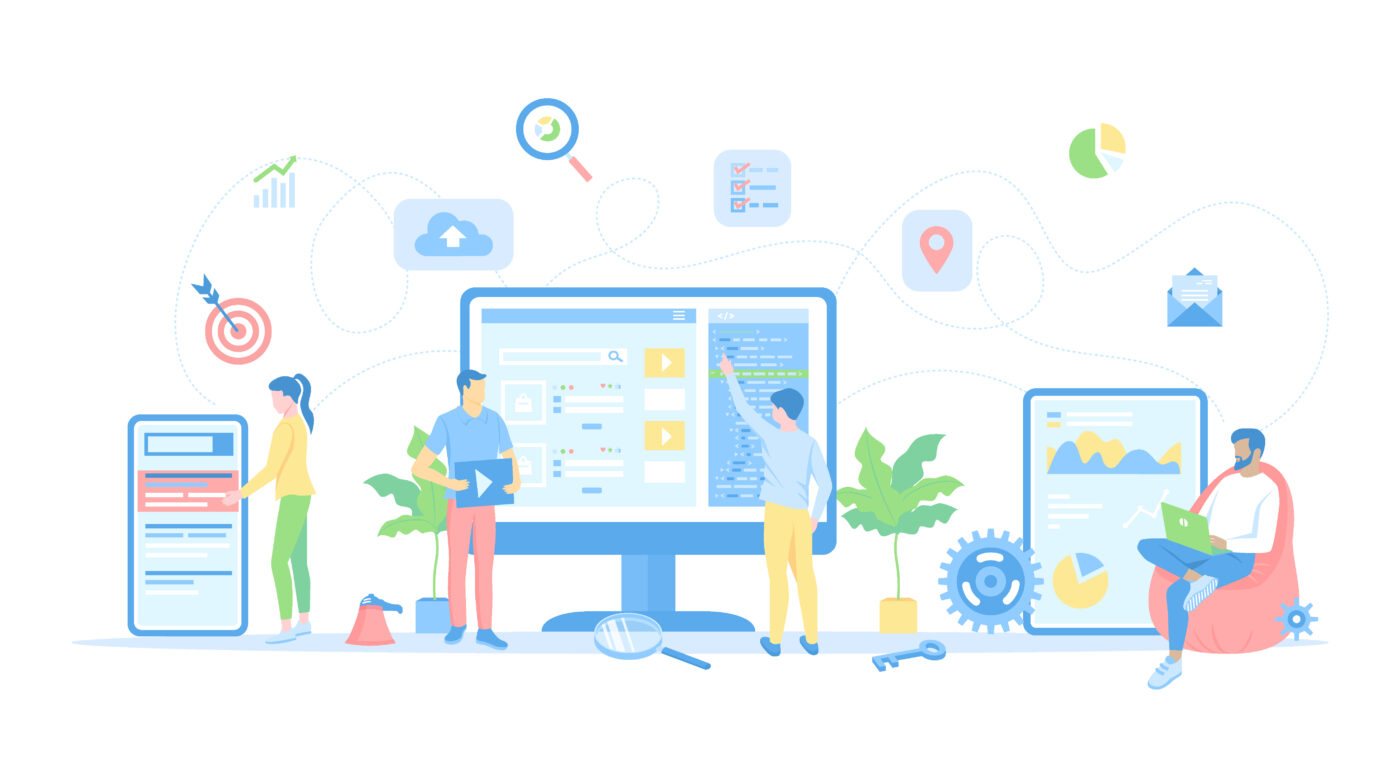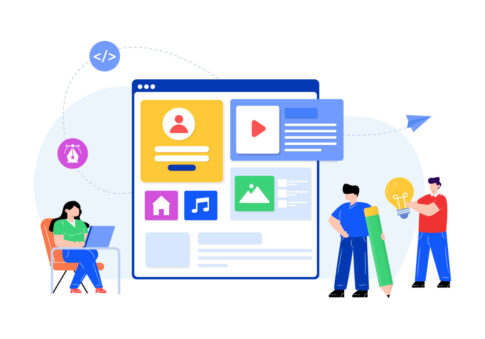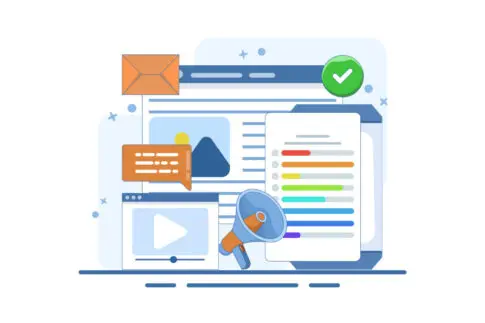アメブロ公式の「検索パフォーマンス」機能を使えば、クリック数・表示数・CTR・平均順位の4指標を一目で把握でき、記事ごとの強みと弱点が明確になります。
本記事ではPC・アプリ双方の確認手順から、データを活かしたタイトル最適化・リライト方法までを解説。数値に基づいて検索流入を大幅に伸ばしたい方は必読です。
目次
検索パフォーマンス機能とは?概要とメリット

検索パフォーマンス機能は、アメブロ公式アクセス解析に追加された専用モジュールで、記事単位・ブログ全体の検索経由パフォーマンスを可視化できるダッシュボードです。
クリック数・表示数・CTR(クリック率)・平均順位という4指標を日別/期間比較で確認できるため、どの記事が検索結果で目立ち、どこで読者が離脱しているかを一目で把握できます。
従来のPVだけでは判断しにくかった「検索経由の質」まで測定できる点が大きなメリットです。また、指標は自動で集計されるため外部ツールを導入する必要がなく、初心者でもログイン直後に確認できます。
検索パフォーマンスで閲覧できるデータは過去30日分のみで、期間は「7日」「30日」などの固定プリセットから切替える方式です。さらに、指標の変化をクリックすると該当記事がリスト化されるため、改善すべき記事をすぐ抽出でき、検索流入を狙ったPDCAサイクルが高速化します。
4つの指標(クリック数・表示数・CTR・平均順位)
検索パフォーマンス機能では、Googleサーチコンソールと同様に4指標を自動で計算し、グラフと数値で表示します。各指標の意味と活用ポイントは次のとおりです。
| 指標 | 概要と活用ポイント |
|---|---|
| クリック数 | 検索結果から実際に記事がクリックされた回数。増減を見ることでタイトル改善の成果を測定できる。 |
| 表示数 | 検索結果に記事タイトルが表示された回数。検索キーワードと記事の関連性を示す。 |
| CTR | クリック数÷表示数×100。表示はされるが読まれない記事を発見し、タイトルやアイキャッチの改善指標に活用。 |
| 平均順位 | 検索結果における平均掲載順位。検索上位を目指すリライト対象を選定しやすい。 |
【指標改善の基本ステップ】
- 平均順位が10位以内→CTRを上げるため数字やベネフィットをタイトルに追加
- 平均順位が20位以下→キーワード再選定と内部リンク強化で検索エンジン評価を向上
- 検索ボリュームが少ない記事はCTRよりクリック数を重視→ニッチキーワード攻略
- 表示数が多いのにCTRが低い記事を優先リライト→短期間で流入増を狙える
記事一覧はスクロールで制限なく表示され、比較件数の公式上限は公表されていません(実装時点で数十件単位を閲覧可能)。クリック率が急落した場合はタイトル改変の影響や競合記事の増加を想定し、キーワード配置や共起語を見直すと効果が出やすいです。
モジュール表示条件とデータ更新サイクル
検索パフォーマンスモジュールは、ブログが検索経由で一定数の表示データを取得して初めてダッシュボードに表示されます。
具体的には「過去30日で検索表示数が一定基準(非公開)を超えること」が前提条件とされており、新規ブログや投稿直後の記事ではモジュールが表示されないことがあります。
表示が確認できない場合は、まず公開記事数と検索表示回数を増やすことが先決です。データは1日1回自動更新されますが、公式ヘルプでは具体的な反映時刻を公開していません(最大48時間程度の遅延が発生する場合あり)。
急激な表示回数増減がある場合でも、最大48時間の遅延が公式に許容されているため、数値反映が遅い=不具合とは限りません。
- 十分な表示数が無い新規記事は「表示するデータがありません」と表示
- データ更新は1日1回、最新値は前日分まで
- Googleサーチコンソール連携設定を行うと集計精度が向上
- 記事が「公開」設定か確認(下書き・限定公開は集計不可)
- 投稿直後の場合→48時間待っても反映しなければ公式ヘルプで障害情報を確認
データ更新タイミングを把握しておくと、リライト施策の効果測定を無駄なく行えます。
たとえば月曜にタイトルを修正した場合、翌水曜以降の数値で初動をチェックし、CTRが改善していなければ再度見出しやメタディスクリプションを調整するといったサイクルを組むと、効率的に検索流入を増やせます。
使い方|PC版・アプリ版での確認手順

検索パフォーマンスモジュールは、PCブラウザとスマホアプリの両方で同じ4指標を確認できますが、画面レイアウトと操作動線が異なります。
まずPCでは「アクセス解析」ダッシュボードの左メニューにある「検索パフォーマンス」をクリックすると、日別グラフと記事別一覧が同一画面に表示されます。
一方アプリでは、画面下部の「分析」タブ→「検索パフォーマンス」の順にタップし、指標を切り替えながら確認します。いずれも過去7日・30日・90日など期間プリセットで比較できます。
更新タイミングは毎日午後に前日分が反映されるため、リライト後は翌々日に初期反応をチェックすると変化を逃しません。また、データが蓄積されるとグラフエリアに「期間比較」ボタンが表示され、クリック数とCTRの伸び率が色分けされるので、改善箇所の優先度がひと目で分かります。
PCブラウザアクセス解析での確認ステップ
PCブラウザは画面が広いため、一覧性と詳細性を両立した確認が可能です。操作フローは以下のとおりです。
- アメブロにログイン→ダッシュボード左メニュー「アクセス解析」をクリック
- 「検索パフォーマンス」を選択→自動で過去7日分のサマリーが表示
- 期間プルダウンで「30日」「90日」を選択し、トレンドを把握
- グラフ下の「記事別」タブ→PV順から「クリック数順」「表示数順」へ切替
- 気になる記事タイトルをクリック→日別詳細グラフとキーワード一覧を確認
アプリ版アクセス解析での確認ステップ
スマホアプリは移動中でも素早く指標をチェックできる点が強みです。最新版(iOS19.16.0/Android26.5.0 以降)にアップデートしたうえで、以下の手順を行います。
- アプリ起動→画面下部「分析」をタップ
- 上部タブから「検索パフォーマンス」を選択
- デフォルト表示の7日グラフを左右スワイプ→クリック数・CTR・平均順位を切替
- グラフ下の「記事別」をタップ→検索指標で並び替え
- 記事タイトルをタップ→「キーワード詳細」ボタンで検索クエリごとのクリック率を確認
- プッシュ通知を「アクセス解析更新」に設定→毎日データ反映を即確認
- 気になる記事を長押し→「リライト」ショートカットで直接編集画面に遷移
アプリでは横向き表示に切り替えるとグラフが拡大し、タップした箇所の日付と指標値がポップアップで表示されるため、細かな増減も追跡しやすくなります。
また、共有アイコンからグラフを画像として保存し、チームチャットで進捗を共有する使い方も便利です。指標を確認したら、その場でタイトル修正→公開ボタンという短いサイクルでPDCAを回せるため、作業効率が大幅に向上します。
Search Console連携のすすめ
アメブロの検索パフォーマンスは単体で十分実用的ですが、Google Search Console(以下GSC)と連携するとデータの精度と分析幅が一段と広がります。
GSCはサイト所有権を確認することで、検索クエリやインデックス状況を詳細に取得でき、アメブロ側の表示数と突き合わせることでキーワードロスを発見しやすくなります。連携手順とメリットは次のとおりです。
| ステップ | 手順概要 | 得られるメリット |
|---|---|---|
| ①所有権確認 | GSCで「URLプレフィックス」を選択→ブログURLを入力→HTMLタグを取得 | アメブロの「Google Search Console 設定」にタグを貼付→即時認証 |
| ②データ取得 | GSCの「検索パフォーマンス」→クエリ・ページを閲覧 | 表示回数が多い未クリッククエリを特定→新規記事テーマに活用 |
| ③比較分析 | アメブロとGSCのクリック数を比較 | データ乖離が大きい記事を抽出→インデックス障害やタイトルミスマッチを検証 |
- アメブロのHTTPS化が完了していない旧URLは別プロパティとして登録する
- GSCに反映されるデータには最大48時間のタイムラグがある
連携後は、アメブロ側で「Search Console データ連携ON」に設定すると、検索パフォーマンスモジュール内にGSC由来の矢印アイコンが出現し、クリックでGSCページへ直接遷移できます。
これにより、平均掲載順位が急落したキーワードのインデックス状況や、カバレッジエラーの有無を即座に確認できるため、問題解決スピードが向上します。
GSCで得たクエリを記事タイトルやH2タグに反映し、アメブロ側の検索パフォーマンスで改善を確認する──このダブルトラッキング体制が、検索流入増加を最短化する鍵です。
データを活かす改善アクション

検索パフォーマンスで得た4指標を活用すれば、リライトや内部リンクの優先順位が明確になり、効率良く検索流入を伸ばせます。まずクリック数とCTRが高い記事は読者ニーズに合致しているため、関連コンテンツへの導線を追加して回遊を強化しましょう。
一方、表示数が多いのにCTRが低い記事はタイトル改善で即効性が期待できます。平均順位が20位前後の記事は、キーワード再配置や内部リンク強化で1ページ目へ押し上げやすいポジションです。データ確認→改善案決定→実装→効果測定というサイクルを月1回以上回すと、ブログ全体の検索流入が底上げされます。
キーワード分析でタイトル・見出しを最適化
検索パフォーマンスの「記事別」一覧では、タイトルをクリックすると検索クエリごとのクリック数とCTRが表示されます。ここで上位クエリとタイトル内キーワードが一致しているかを確認し、ズレがあれば見出しやメタディスクリプションを修正しましょう。
【タイトル改善のステップ】
- 検索クエリ上位5語を抽出し、主要キーワードを左寄せ配置
- 数字・期間・ベネフィットを組み合わせ、CTRを向上
- 全角32〜35文字以内に収め、モバイル検索での省略を防止
| 指標状況 | 最適化方針 |
|---|---|
| 表示数多・CTR低 | キーワードを前半に移動+具体性を追加 |
| 平均順位低 | 共起語をH2・H3に追加し関連性を強化 |
- H2にメインキーワード、H3にサブキーワードを配置
- 読者の次の疑問を先回りして用語を設定→離脱率低下
また、クリック数は多いが平均順位が伸び悩む記事は、タイトルを変えずにH2・H3へキーワードを追加するだけで順位が改善するケースがあります。必ず公開後1週間の数値を再確認し、CTRが上がったかをチェックしましょう。
リライトと内部リンクで検索順位を強化
平均順位が15〜30位に滞留している記事は、本文の深度不足や内部リンクの弱さが原因であることが多いです。検索パフォーマンスで該当記事を抽出し、以下の流れでリライトとリンク強化を行います。
【リライト実施フロー】
- 想定読者の検索意図を再確認し、導入文に結論を先出し
- 不足している見出しを追加し、コンテンツ網羅性を向上
- 公式FAQやプレスリリースなど一次情報へ引用リンクを設置
- 関連キーワード記事へ内部リンクを張り巡らせ回遊率を上げる
- アンカーテキストにキーワード+ベネフィットを含める
- 1記事につき3〜5本を目安にリンク設置→過剰リンクを防止
- リンク先の冒頭に結論を記載し直帰率を低減
内部リンクを張る際は、ドメイン内で検索順位が高いハブ記事から順位が低いサブ記事へリンクを流すと、ドメインパワーの分散を防げます。
また、検索パフォーマンスで平均順位が1ページ目に入った記事には、アフィリエイト記事やコンバージョンページへのリンクを追加し、検索流入を収益へ結び付ける導線を整えておくと効果的です。
リライト後は「30日比較グラフ」でクリック数と平均順位の変化を確認し、CTRが5%以上改善した記事を成功パターンとしてノウハウ化すると、他記事への水平展開がスムーズに行えます。
運用ポイント|効果測定とトラブル対策
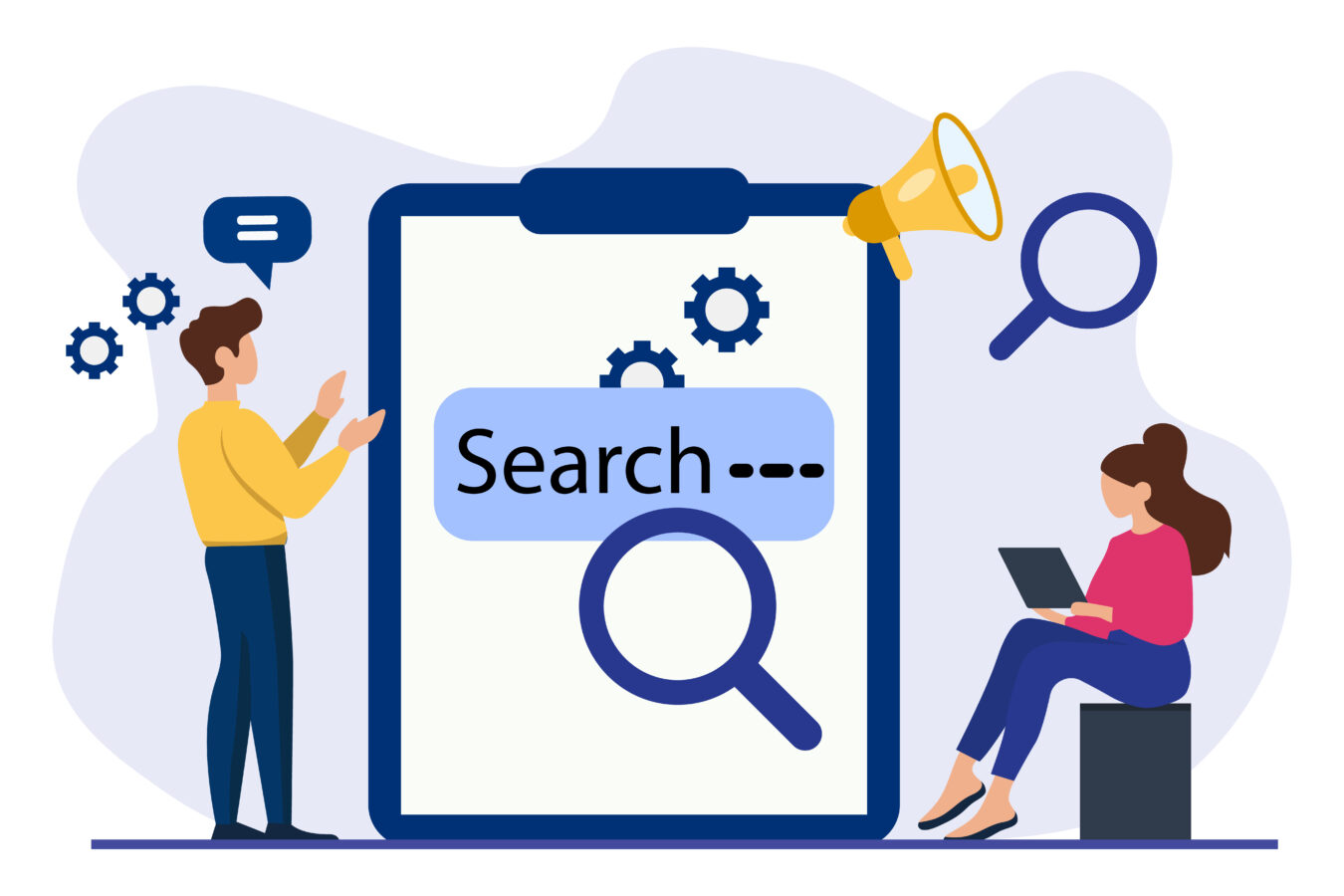
検索パフォーマンスは指標を眺めるだけでは成果につながりません。もっとも重要なのは、グラフ比較で仮説を立て、改善を実行し、再度データで検証するPDCAサイクルを回すことです。
アメブロのモジュールには「30日間」「7日間」の期間プリセットがあり、クリック数・表示数・CTR・平均順位をワンタップで切り替えられます。
長期グラフで全体トレンドを把握し、短期グラフで施策の初動を確認することで、リライトや内部リンク追加が奏功したかを日次で追跡できます。
さらに、データが反映されない・指標が急落するトラブル時にも、公式ヘルプの更新サイクルや遅延許容時間を理解していれば慌てず対処可能です。ここでは「30日・7日比較グラフを活用したPDCA手順」と「データ反映トラブルの確認術」を具体例とともに解説します。
30日・7日比較グラフでPDCAを回す
30日グラフはリライト施策の効果や季節要因を俯瞰するのに最適で、7日グラフは施策直後の微細な変化を捉えるのに向いています。
まずは30日間のクリック数を基準線としてトレンドを掴み、「急増・急減した日」と「平均順位が変動した日」をチェックします。その後、7日間比較で短期的な上昇・下降の原因を探ると、PDCAの優先度が明確になります。
| 期間比較 | 活用シーン |
|---|---|
| 30日間 | 大幅リライトや内部リンク追加など中長期施策の評価 |
| 7日間 | タイトル変更・画像差し替えなど即効施策の効果測定 |
【PDCAサイクル実践手順】
- Plan:30日グラフで低CTR記事を抽出→改善キーワードを決定
- Do:タイトル先頭に主要キーワード+数字を追加→公開
- Check:7日グラフでクリック数とCTRを毎日確認→改善率10%を合格ラインに設定
- Action:合格なら他記事に横展開、未達ならH2・H3に共起語を追加し再検証
- 平均順位が10位以内→タイトル改善でCTR強化
- 表示数急増&クリック数横ばい→アイキャッチと冒頭文を検証
たとえばタイトル改修後にCTRが「7日比較で+5%、30日比較で+2%」なら施策は成功と言えます。逆にクリック数が伸びても平均順位が下がった場合は、キーワード詰め込み過ぎや競合増加が考えられるため、本文の自然さや内部リンク構造を見直しましょう。
定例のデータ取得日は週1回に固定し、スプレッドシートで指標と施策を紐付けて記録すると、次の改善案がすぐ浮かびます。
データ反映遅延・未表示時の確認術
検索パフォーマンスは毎日午後に前日分が反映される仕様ですが、最大48時間の遅延が公式で許容されています。反映が遅いからといってすぐ不具合を疑うのではなく、まず以下のチェックリストを確認しましょう。
- 記事公開から48時間経過しているか
- 公開範囲が「公開」になっているか(下書き・限定は集計不可)
- アプリ・PCとも最新版か
- Search Console側でインデックスエラーが出ていないか
また、指標が突然ゼロになる場合は「URL変更」「リダイレクト設定ミス」「noindex付与」が原因のことがあります。
Search Consoleのカバレッジレポートで該当URLのステータスを確認し、エラー表示なら修正しましょう。内部リンクの貼り替え忘れによる重複URLも順位低下の要因なので、リライト時は必ず旧URLへの301リダイレクト設定を維持してください。
| 症状 | 主な原因 | 対処法 |
|---|---|---|
| 指標がゼロ | noindexタグ誤設定 | HTML編集でnoindexを削除→再公開 |
| 平均順位急落 | URL変更・リダイレクト忘れ | 旧URL→新URLへ301設定→Search Consoleで再クロール依頼 |
| CTR急落 | 競合増加・タイトル改悪 | キーワード再配置+数字・ベネフィット追加 |
最後に、データ確認とトラブル対応は「毎週月曜の午前」「毎月1日の朝」と定例化すると漏れがありません。更新遅延を踏まえて2日前までのデータで判断し、急変動があった場合のみ個別に当日データをモニタリングすると、過剰対応を防ぎつつ精度高く改善を進められます。
まとめ
検索パフォーマンスは、検索流入改善の羅針盤となる公式分析ツールです。4指標を定期チェックし、キーワード調整→内部リンク最適化→結果検証のPDCAを回せば、検索順位とCTRを継続的に強化できます。まずは記事別データを確認し、上位表示を狙うキーワードからタイトルを再設計してみましょう。