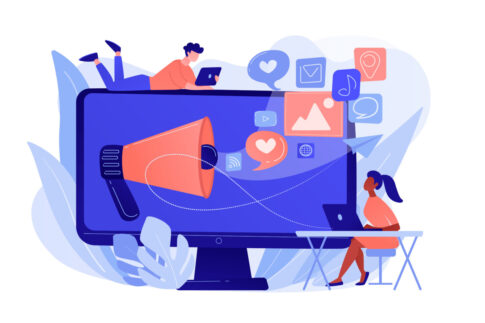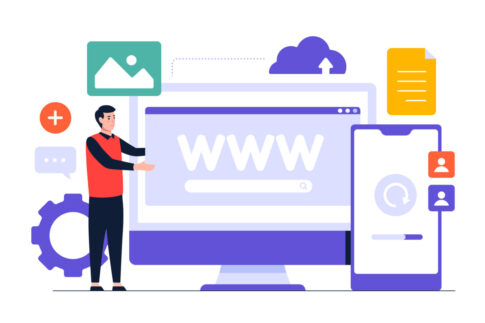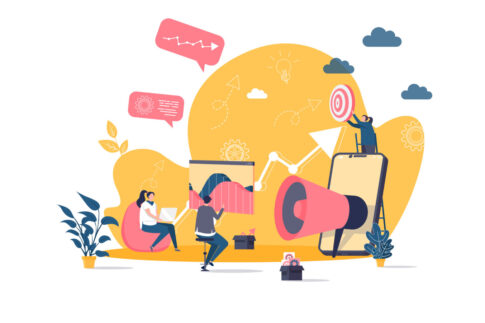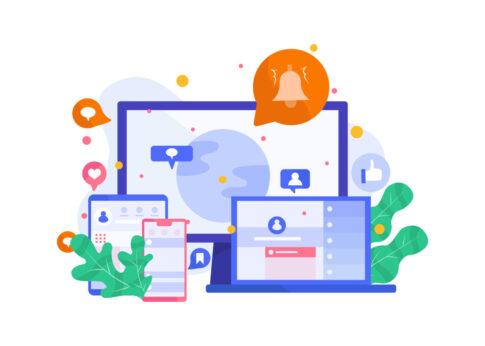ブログ集客を動画で底上げする実践ガイドです。7つの動画型、最初の三秒の見せ方、プロフィールとリンク集とUTMの設計、着地ページの要点・証拠・FAQ配置、数字の見方(セッション/CV/CVR)までを簡潔に整理。読了後は、今日作る1本と導線、週次で直すポイントが明確になります。
目次
「何の悩み」に動画で答えるかを決める

最初に決めるのは「誰の、どんな悩みを、どの動画で解決し、どのページに案内するか」です。ここが曖昧だと、再生は伸びてもブログに来ない、来ても行動しないというムダが生まれます。
基本方針は一つの動画につき一つの悩み、一つの着地、一つの行動です。動画では冒頭で結論を言い切り、本文は要点を一つだけ示し、最後に次の一歩を提示します。
着地先の記事は、見出し直下に結論と要点を置き、本文末に関連記事と本命の行動ボタンを用意します。プロフィールのリンク集は、代表記事、該当カテゴリの起点、本命の行動の順に並べると迷いが減ります。
下の表を使って「悩み→動画の型→着地→行動」をあらかじめ対応づけておくと、一貫した導線が作れます。
| 読者の悩み | 合う動画の型 | 着地と行動の例 |
|---|---|---|
| 全体像を知りたい | Q&A型で結論と要点を一つ | 入門記事に誘導/チェックリストを受け取る |
| どれを選ぶべきか | 比較基準型で判断軸を提示 | 比較記事に誘導/資料請求や相談を申し込む |
| すぐ実行したい | 一つの手順だけを実演 | 手順記事に誘導/テンプレートをダウンロード |
- 誰のどの悩みかを一文で定義する
- 動画の型と着地ページをセットで選ぶ
- 行動は一つに絞り、ボタン文言を結果が分かる表現にする
検索意図とKPIを整理する
動画と記事を連携させるには、検索意図と指標を同じ土台で管理することが重要です。検索意図は入門、比較、手順の三つに分け、各段階で必要な情報と行動をそろえます。
入門は不安の解消と基本理解、比較は判断材料の提示と用途別の提案、手順は今日から動ける具体的なステップです。
KPIは最大三つに絞り、到達(セッション)、成果数(CV)、成約率(CVR)を基本にします。週次では同じ曜日と時間に数字を確認し、弱い一箇所だけを改善します。
たとえばセッションが少ないならリンク名とタイトルの具体化、CVが少ないならボタンの位置と文言、CVRが低いなら着地の冒頭に要点、証拠、FAQを引き上げるといった具合です。
下の表に、意図別の制作ポイントと見るべき指標をまとめました。
| 検索意図 | 制作の要点 | 主なKPIと最初の打ち手 |
|---|---|---|
| 入門 | 結論を先に示し、要点を三つ以内で提示 | セッション/タイトルとリンク名を具体化し入口を増やす |
| 比較 | 判断基準を二つ程度に絞り用途別の向きを示す | CV/ボタン近くに表と事例を配置し判断を後押し |
| 手順 | 一つの手順だけ実演し注意点を一つ添える | CVR/着地の冒頭に要点、証拠、FAQを近接配置 |
- セッションが少ないのに成約率を先に直そうとする
- 一度に複数箇所を変更して因果関係が分からなくなる
収益モデルとCTAを決める
収益モデルと行動ボタンは、検索意図と読者の段階に合わせて選びます。アフィリエイトは手順や比較と相性が良く、公式サイトに進む前に注意点や条件を簡潔に示すと承認率が安定します。
資料請求や相談などのB2Bリード獲得は比較と事例が軸になり、費用感や導入ステップを質問と並べて表示すると問い合わせの質が上がります。
自社商品やデジタル商品の販売は手順と組み合わせ、テンプレートの配布やサンプル閲覧を先に体験してもらうと完了率が伸びます。
CTAの文言は「行動後に何が手に入るか」を短く明記し、上部、中部、末尾の三箇所に役割を持たせます。下の表を参考に、モデルごとに最初の設計を決めてください。
| 収益モデル | 合う場面 | CTA文言の例 |
|---|---|---|
| アフィリエイト | 手順の実演や比較の直後 | 特典付きの公式ページを確認する |
| 資料請求・相談 | 比較基準と事例を見せた後 | 料金と導入ステップを確認する |
| 自社商品・デジタル商品 | 手順の完了と同時に提示 | テンプレートを無料で受け取る |
- 一つの動画に一つの行動を設定し文言は結果を示している
- リンク名と着地ページの見出しが同じ表現でそろっている
ブログ送客に強い動画の型7選

動画からブログへ人を送る目的は、視聴の勢いを保ったまま「次にすべき行動」をはっきり示すことです。ここで紹介する七つの型は、入門・比較・手順という検索意図に対応しつつ、短時間で価値提供と導線提示ができる構成です。
どの型でも共通するのは、最初の数秒で結論を一文で示すこと、要点を一つに絞ること、最後に行動を具体名で言うこと、そしてプロフィールのリンク名と着地ページの見出しを同じ表現にそろえることです。
企画時は、一つの動画に一つの着地、一つの行動だけを紐づけると迷いが減ります。表に型ごとの狙いと相性の良い着地をまとめました。これを基準に企画を並べると、短期間でも安定した送客ループが作れます。
| 型 | 狙い | 相性の良い着地と行動 |
|---|---|---|
| Q&A | 疑問を一つだけ解消 | 入門記事に誘導/チェックリストを受け取る |
| 比較基準 | 選び方を素早く提示 | 比較記事に誘導/資料請求や相談を申し込む |
| 一つの手順 | 今すぐ実行を後押し | 手順記事に誘導/テンプレートを受け取る |
| 改善前後 | 直し方の効果を体感 | 事例記事に誘導/同じ改善を試す |
| FAQまとめ | 不安の一括解消 | 代表記事に誘導/詳細ガイドを読む |
| 事例短編 | 成果の再現点を学ぶ | 事例詳細へ誘導/相談や見積もりへ進む |
| 要点切り抜き | 長尺の核心を迅速に共有 | 該当セクションへ誘導/資料の要点版を読む |
- 冒頭の一文と着地ページの冒頭文が同じ主張になっている
- リンク名が内容名になっている
Q&Aで結論から答える
Q&A型は、視聴者の疑問を一つだけ選び、結論を最初に言い切る構成です。短い時間で安心感を与えやすく、入門意図の流入に向いています。
作り方は、画面の最初に質問と結論を同時に出し、その後に理由を一行、例を一つ、最後に次の行動を具体名で示します。質問はコメント欄や検索クエリから拾うと反応が安定します。
説明は冗長にせず、数字や固有名を使って曖昧さを減らします。着地は入門記事が基本で、冒頭に用語最小の全体マップ、末尾にチェックリストと代表記事の導線を置くと定着します。
| 要素 | 画面に出す内容 | 着地で補う内容 |
|---|---|---|
| 結論 | 一文で答えを提示 | 背景と前提を短く整理 |
| 理由 | 根拠を一行 | 図や表で理解を深める |
| 例 | 具体例を一つ | 別パターンの例を追加 |
| 行動 | チェックリストを受け取る | 代表記事と関連三本の導線 |
- 質問が抽象的で結論がぼやける
- 行動が具体名で示されず離脱が増える
比較基準を示して選び方を明確にする
比較基準型は、選択肢の多さで迷っている人に向け、判断の軸を二つほどに絞って提示する構成です。動画では結論を先に出し、その結論に至る基準を短く二点、用途別の向き不向きを一言ずつ。
表や細かい条件は動画では出さず、着地記事の比較表にまとめます。こうすると視聴は軽く、判断は着地で深まります。CTAは資料請求や相談、または各公式への遷移が中心です。
| 構成 | 動画で伝える要点 | 記事で深掘りする点 |
|---|---|---|
| 結論 | 用途別のおすすめを一言 | 推薦理由の詳細と注意点 |
| 基準 | 二つに絞って提示 | 採点表や加点理由 |
| 用途別 | 向く人を一言で示す | ケース別の選び方 |
一つの手順だけを短く見せる
一つの手順型は、今日から動ける小さな行動を提示します。ゴールを先に宣言し、やることを一つだけ実演、注意点を一つ添えて完了です。
動画の尺は短めでも十分で、複数手順がある場合は一本ずつ分割してシリーズ化します。着地は手順記事で、冒頭に結論と全体の流れ、本文で各ステップの詳細、末尾にテンプレートの受け取りや公式への案内を置きます。
実演では、手元や画面のアップを入れ、字幕は動作と同じ言葉にし、遅延を避けてテンポを保ちます。
| 構成 | 動画の内容 | 記事の役割 |
|---|---|---|
| ゴール | 完成イメージを先に示す | 効果の目安や成功条件を提示 |
| 手順一つ | 動作を実演 | 画像付きで詳細手順を説明 |
| 注意点 | 失敗しやすい点を一言 | 代替方法やチェックリスト |
改善前後の違いを具体的に示す
改善前後型は、失敗例から始め、直し方を一言で示し、改善後の結果を見せる流れです。視聴者が自分の状況に重ねやすく、行動の動機づけが強まります。数字やスクリーンショットを使い、前後の差が一目で分かる画作りにします。直し方は一つだけ示し、詳しくは記事で解説とするのがコツです。着地には、直し方の手順と補助資料、同じパターンの事例リンクをまとめておくと、再現性が高まります。
| 場面 | 動画で見せる内容 | 記事で補足する内容 |
|---|---|---|
| 前 | 問題の状態を短く提示 | 原因の切り分け手順 |
| 直し方 | 一言で解決策を示す | 手順の詳細と代替案 |
| 後 | 改善した状態を提示 | 数値の解説と次の一手 |
- 同じ構図で前後を並べて差を強調する
- 前と後は同じ指標で示す
- 直し方は一つに絞る
よくある質問をまとめて答える
FAQまとめ型は、同じテーマの短い質問を三つほど並べ、それぞれ一言で答え、詳しくはブログで確認してもらう構成です。疑問を一括で解消できるため、保存や再訪につながります。
質問はコメント欄や検索クエリから抽出し、重複は統合します。着地には、質問別の詳細、関連手順、代表記事の導線をまとめます。
動画はテンポ良く切り替え、字幕を短い問いと答えの対で表示すると理解が速くなります。
| 要素 | 動画での表現 | 記事での展開 |
|---|---|---|
| 質問 | 短い疑問文を表示 | 背景や前提を丁寧に補足 |
| 答え | 結論を一言で表示 | 根拠や例を追加 |
| 導線 | 詳しくは該当記事へ | 関連記事三本と代表記事のリンク |
- 長い説明でテンポが失われる
- 質問は三つ以内にする
- 一つの問いに一つの答えに限定する
短い事例で成果と学びを伝える
事例短編型は、背景、取り組み、結果、学びの四点を短文で示し、再現ポイントだけを強調します。信頼性や納得感が高く、専門性の印象を作りやすい型です。
動画では数値やビジュアルを使い、学びを箇条書きで二点ほどに絞ります。着地には、施策の詳細、使った資料、関連テンプレートをまとめ、同じ条件で試す手順を用意します。視聴者が自分の環境に当てはめやすいよう、前提条件や期間を明記します。
| 項目 | 動画で伝える内容 | 記事で深掘りする内容 |
|---|---|---|
| 背景 | 開始時の状態を一行 | 制約や対象の詳細 |
| 取り組み | 実施したことを短く | 手順や設定の具体 |
| 結果 | 数値や変化を明示 | 集計方法と解釈 |
| 学び | 再現できる要点を二つ | 他ケースへの応用 |
- 数値の出典や計測条件を記事側に明示する
- 前提と期間を明記する
- 学びは再現可能な表現にする
長尺の要点だけを分かりやすく切り出す
要点切り抜き型は、ウェビナーや長編記事の核心だけを短く共有し、興味を持った人を該当セクションへ案内します。
長尺のすべてを要約しようとせず、たった一つの重要な学びに絞るのが成功のコツです。動画では、要点を一文で提示し、裏づけの図解を一枚だけ見せ、続きは指定セクションへ誘導します。
着地は該当セクションの見出し直下に要点を再掲し、関連リンクと行動ボタンを近接配置します。これにより、視聴から読書への移行が滑らかになり、読了率も上がります。
| 素材 | 切り出す内容 | 着地の整備 |
|---|---|---|
| 長編記事 | 核心の一段落 | 該当見出し下に要点を再掲 |
| ウェビナー | 重要スライド一枚 | 画像と文字起こしを添える |
| 資料 | 結論ページのみ | 関連リンクと行動ボタンを近接 |
- 動画の要点と着地の要点が同じ表現になっている
- 行動ボタンの文言が結果を示している
- 要点は一つだけにする
- 続きは該当セクションへ誘導する
短く分かりやすい作り方と編集に統一する

動画を量産しながら品質を保つには、毎回ゼロから考えず「短く分かりやすい」型に統一することが近道です。基本は三部構成です。
冒頭で結論を先出しし、本文は要点を一つに絞って簡潔に伝え、最後に行動(CTA)を具体名で示します。尺は15〜30秒、縦9:16、音量は声がBGMよりも常に前にある状態をキープします。
画面テキストは大きく、1画面1メッセージを原則とし、被写体に重ならない位置に配置します。さらに、撮影・編集・公開の一連をテンプレ化すると、少人数でも継続できます。
たとえば「台本テンプレ(結論→理由→例→行動)」「撮影チェック(明るさ・背景・マイク)」「編集プリセット(字幕サイズ・余白・カラー)」を共通化し、サムネとカバー文、説明文の書き方も統一します。
下表を参考に、最小の設定を決めましょう。
| 要素 | 統一のポイント | 実装例 |
|---|---|---|
| 尺と画面 | 15〜30秒・縦9:16・1画面1メッセージ | 0–3秒で結論、10–25秒で要点、最後にCTA |
| テキスト | 大きめの可読サイズ・高コントラスト | 白字+影、行長は8〜12語、中央〜上配置 |
| 音と明るさ | 声>BGM・顔または手元が明るい | マイク使用、自然光+補助ライト |
| 導線 | リンク名=着地見出しと同文 | 導線テンプレを受け取る/比較表を見る |
【運用の流れ】
- 台本テンプレに沿って一気に3本分を書き出す
- 同一セッティングでまとめ撮りし、編集プリセットを当てる
- 説明文・カバー・リンク名は共通書式で仕上げる
- 冒頭の一文と着地の冒頭文が同じ主張になっている
- CTAの文言が結果を示している(例:チェックリストを受け取る)
最初の三秒で結論を示す構成にする
視聴が継続するかは最初の三秒で決まります。ここで「誰に」「何が分かるか」「得られる結果」を一文で提示し、画面テキストでも同じ内容を大きく表示します。
入門なら全体像の地図、比較なら用途別の結論、手順なら完成イメージを先に置きます。映像は顔出し・手元・画面キャプチャのいずれかを選び、被写体が中心に入る構図でブレを抑えます。
本文では要点を一つだけ、理由は一行、例は一つに限定し、余白を恐れずテンポを保ちます。最後に行動を具体名で告げ、固定コメントやピン留めで同じ文を再掲します。
下のタイムラインを基準に、台本と撮影をそろえましょう。
| 秒数 | 目的 | 実装のヒント |
|---|---|---|
| 0–3秒 | 結論と対象を即提示 | ブロガー向け/CVが上がる導線の型 を大きく表示 |
| 3–10秒 | 要点の提示 | 要点は1つ、数字や固有名で曖昧さを削る |
| 10–25秒 | 例または注意点 | 一例だけ見せ、詳細はブログで深掘り |
| 25–30秒 | 行動の指示 | プロフィールのリンクから導線テンプレを受け取る |
- 入門:ブログ集客の導線を15秒で地図化します
- 比較:この2基準で動画ツールを選べます
- 手順:CVが上がるボタン位置を一つだけ直します
字幕と説明文を検索語に合わせ読みやすくする
発見され、理解され、行動につながる字幕と説明文には共通の作法があります。字幕は「無音でも内容が分かる」「検索語と一致する」「短く読み切れる」が基本です。
行長は8〜12語、漢字とひらがなの比率は読みやすさを優先し、背景とのコントラストを高くします。
説明文は一文目に対象と価値、二文目に次の行動を置きます。検索語は自然な文章で一度だけ入れ、乱用は避けます。
ハッシュタグは広い語1〜2、具体語2〜3の少数精鋭に絞り、カバーの文字は冒頭テロップと同じ文にします。リンク名・説明文・着地見出しは同じ表現でそろえると、クリック後の落差が減り、CVRが安定します。
| 要素 | 目的 | 書き方の例 |
|---|---|---|
| 字幕 | 無音でも理解・検索語一致 | ブログ集客の導線を3手順で整理 |
| 説明文 | 価値の要約と行動の指示 | ブロガー向け。動画で導線の型を解説。続きはリンクからテンプレを入手 |
| タグ | 発見面の拡張 | #ブログ集客 #動画活用 #導線設計 |
| カバー | 一覧での認知 | 15秒で分かる導線の型 |
- 対象+価値:ブロガー向け。動画でブログ集客の導線を短く整理
- 行動の指示:リンク集から導線テンプレを受け取る
記事への組み込みと導線を最適化する

動画からの流入を成果に変えるには、記事の中で「見つける・理解する・行動する」の順番が迷わず進む設計が欠かせません。
おすすめは、冒頭の上部に動画または要点を置き、すぐ下で本文の結論を一文で提示し、続いて理由と具体例を短く示す構成です。
本文の各段落末には自然文のアンカーリンクを置き、関連セクションや代表記事へ誘導します。ボタン名やリンク名は必ず内容名で表記し、リンク先の見出しと同じ文にそろえると、クリック後の期待外れが起きにくくなります。
計測のために、動画から来る主要リンクにはUTMを付与し、リンク集上位の三件は常に最新の導線へ更新します。下の表は、記事内の代表的な配置と目的、最初に行うべき実装の例です。
| 配置 | 目的 | 実装の例 |
|---|---|---|
| 冒頭上部 | 価値を即時に伝える | 要点を一文で表示、動画または要点図を併記 |
| 本文中 | 理解と回遊を促進 | 段落末に自然文アンカーで関連見出しへ誘導 |
| 本文下部 | 決断を後押し | 関連記事三本と代表記事、行動ボタンを近接配置 |
【公開前チェック】
- 冒頭の一文と動画の冒頭テロップが同じ主張になっている
- リンク名と着地見出しの表現が一致している
- 冒頭に要点と動画を配置
- 段落末の自然文アンカーを設定
- 末尾に関連記事三本と行動ボタンを固定
プロフィールとリンク集とUTMを整理する
プロフィールは動画視聴直後の「次の一歩」を示す場所です。肩書と提供価値を一文で示し、リンク集は三から五件に絞ります。並びは代表記事、カテゴリ起点、本命の行動の順が基本で、季節の企画や最新記事は入れ替え枠にします。
各リンクにはUTMを設定し、命名を統一します。リンク名は必ず内容名で書き、到達後の見出しと同じ表現にそろえると、クリック後の離脱が減ります。下の表を基準に、リンク管理と命名を整理してください。
| 項目 | 設定の要点 | 記載例 |
|---|---|---|
| プロフィール文 | 誰向けと得られる価値を一文で表記 | ブロガー向け。成果につながる導線テンプレを配布 |
| リンク名 | 内容名で具体的に記載 | 導線テンプレを受け取る、比較表を見る |
| 並び順 | 代表記事、カテゴリ起点、本命の行動の順 | 記事導線の基本、入門まとめ、資料請求 |
| UTM | 小文字統一、要素を固定 | source=tiktok、medium=social、campaign=blog_video、content=howto |
【必須チェック】
- 上位三件のリンクにUTMが正しく設定されている
- リンク名と着地見出しが同文で統一されている
- リンクが多すぎて迷う構成
- 抽象的なリンク名や「こちら」の表記
着地ページを要点と証拠とFAQで整える
着地で行うべきことは、価値を一目で伝え、疑問を素早く解消し、行動を明確に示すことです。最上部には「誰に」「何が」「どう良いか」を一文で掲示し、その直下に証拠を並べます。
証拠はレビュー、実績、比較表、提供者情報など、判断材料として機能する要素です。次にFAQを配置し、価格、期間、返金、サポート、申込み後の流れといった不安の大きい項目から順に記載します。
行動ボタンは上部、中部、末尾に一つずつ役割分担で設置し、ボタン近くに事例やFAQを置くと迷いが減ります。変動がある条件には更新日の明記も忘れずに。
下の表は、要素ごとの具体項目と配置のコツです。
| 要素 | 具体項目 | 配置のコツ |
|---|---|---|
| 要点 | 対象、価値、到達点を一文で提示 | 最上部に大きく表示、動画冒頭の文と同じ表現に統一 |
| 証拠 | 実績、レビュー、比較表、提供者情報 | 要点のすぐ下に近接配置、図解で視認性を確保 |
| FAQ | 価格、期間、返金、サポート、申込み後の流れ | 問い合わせの多い順に並べ替え、折返し前に一項目以上を表示 |
| 行動 | 文言、位置、近接要素の整備 | 上部は最短導線、中部は後押し、末尾は決断支援 |
【週次の改善手順】
- 冒頭の一文を見直し、対象と価値と到達点を明確にする
- 証拠を一つ追加し、ボタンの近くに配置する
- FAQを一問増やし、強い不安から先に解消する
- 行動ボタンを乱立させず、目標は一つに絞る
- 価格や条件には更新日を併記し、記事とLPで表記をそろえる
配信と拡散と計測を同じ手順で回す

動画×ブログの成果は、思いつきで作るより「毎回同じ手順」で回した方が伸びやすいです。おすすめは、作る→出す→話す→直すの四工程を週次で固定すること。
作るでは企画テンプレと台本フォーマットを使い、出すでは同じ曜日・時間に公開して認知のリズムを作ります。
話すではコメント返信・固定表示・ライブで“今の疑問”を拾い、直すではGA4とGSCの数字から弱い一箇所だけを改善します。運用を小さくしないと継続できないため、撮影はまとめ撮り、字幕・説明文・カバー文はテンプレ差し替え、リンク名は内容名に統一。
さらに、リンクにはUTMを付けてtiktokやXなど流入源ごとに分解できるようにしておきます。下表の「工程×目的×最初のアウトプット」をチームで共有すると、少人数でも迷わず回せます。
| 工程 | 目的 | 最初のアウトプット |
|---|---|---|
| 作る | 迷わず量を確保 | 台本テンプレと撮影チェックリスト |
| 出す | 想起と到達の安定化 | 投稿カレンダーと固定表示の定型文 |
| 話す | 再訪と回遊の創出 | Q&A化するコメントの収集メモ |
| 直す | 因果を掴んで改善 | 週次レポートと1点改善の記録 |
- 同じ曜日・時間に公開して比較可能にする
- 変更は位置・文言・近接要素のどれか1点に限定
- リンク名=着地見出し=動画冒頭文を同じ表現にそろえる
投稿カレンダーと固定表示とライブで継続する
継続のコツは「決めた枠を守る」ことです。少人数なら週3本が無理なく続く目安。月・水・金の昼休みと夜間に固定し、4週分の同枠データを横並びで比較します。
企画は入門・比較・手順・Q&Aをローテーションし、シリーズ名を付けて追いやすくします。固定表示は要点+導線を一行で書き、コメント返信は24時間以内を目標に、次の行動を明記(例:詳しい表はリンク集の比較記事)します。
ライブは週1回・15〜30分で、冒頭にアジェンダ→Q&A→まとめ→リンク案内の順に進行。録画は短尺に切り出して再投稿し、固定コメントで関連記事へ送客します。
計測は、リンク集上位3件にUTMを必ず付けて流入源を分けます。これだけで「どの枠・どの切り口・どの導線が効いたか」を毎週確認できます。
| 曜日 | 時間帯の例 | 企画ローテ例 |
|---|---|---|
| 月 | 12:00/20:00 | 入門まとめ(全体像→代表記事) |
| 水 | 12:30/21:00 | 比較の基準提示(詳細は表で) |
| 金 | 13:00/20:30 | 手順を一つ実演(テンプレDL) |
- ネタ切れ→コメントと検索キーワードから質問を収集してQ&A化
- 投稿が途切れる→まとめ撮りと説明文テンプレで前倒し
セッションとCVとCVRをGA4とGSCで確認する
数字は「到達→行動→成約」の順に見ます。到達はセッション、行動はCTAクリックやスクロール、成約はCVとCVRです。
まずGA4でutm_sourceが動画媒体のセグメントを作り、ランディングページ別にセッションとCVを確認。弱ければリンク名を内容名に変更し、上位リンクの並びを代表記事→カテゴリ起点→本命CTAに固定します。
次にCTAの位置と文言を見直し、結果提示型に変更(例:料金と導入ステップを確認)。最後にCVRはLPの冒頭を要点→証拠→FAQに並べ替え、フォーム必須項目を最小化します。
GSCではページ単位で表示・CTR・掲載順位を見て、タイトル先頭の具体化と言い換え語の調整を行います。毎週同じ曜日・時間で数字を取り、改善は1点に絞ると因果がつかめます。
| 段階 | 見る指標と場所 | 最初の打ち手 |
|---|---|---|
| 到達 | GA4のセッション/GSCの表示・CTR | リンク名の具体化と上位3件の入替、タイトル先頭の明確化 |
| 行動 | GA4のCTAクリック・スクロール | CTAを見える位置へ移動、文言を結果提示型に変更 |
| 成約 | GA4のCV・CVR | LP冒頭を要点→証拠→FAQに再構成、フォーム摩擦を低減 |
- セッション不足→リンク名・並び・タイトル先頭を具体化
- CV不足→CTA位置と文言、近接要素に事例とFAQを追加
- CVR不足→LP冒頭の順番を再配置、フォーム必須を最小化
まとめ
要点は、誰のどの悩みに答えるかを先に決め、短尺動画→リンク集→該当記事→CTA→計測を同じ順序で回すことです。
動画は結論先出し、リンク名は内容名で具体化、着地は要点・証拠・FAQを上部に配置。数値はセッション→CV→CVRの順で確認し、位置・文言・近接要素のどれか1点だけを週次で改善しましょう。