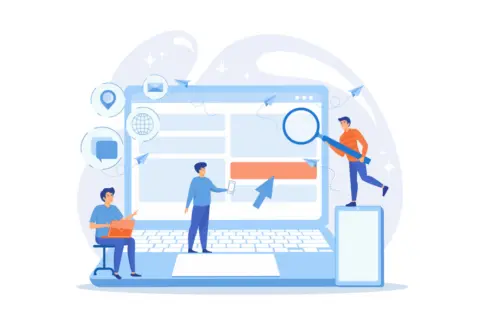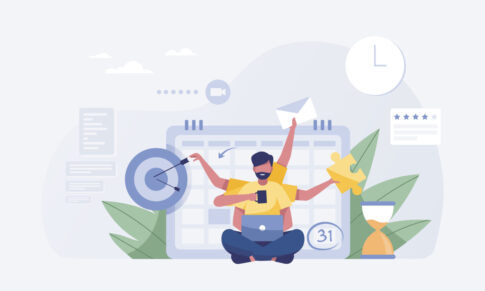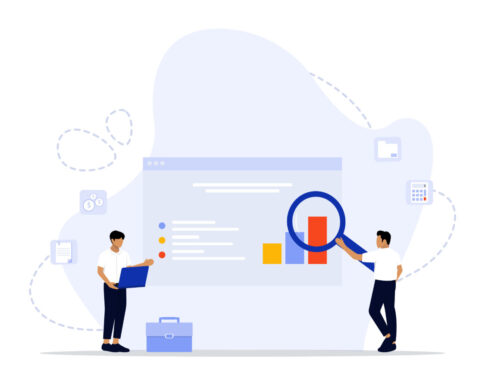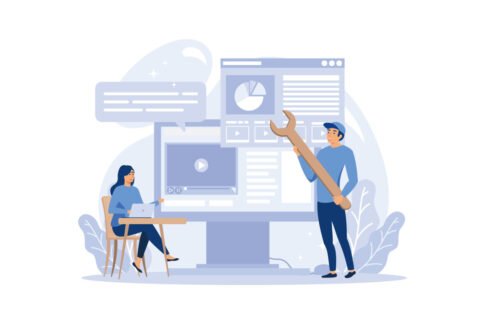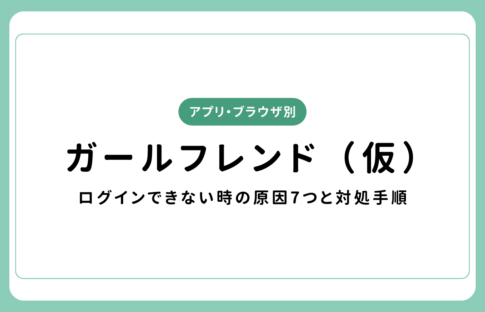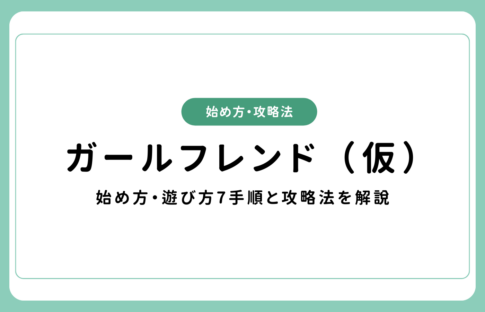ブログ集客コンサルは「何を頼めば良いか」「費用対効果は出るのか」で迷いがちです。
本記事は、役割と提供範囲、費用の目安、失敗しない選び方、契約〜実行の流れ、内製と併用して効果を最大化する方法までを整理。チェックリストとROI試算の考え方で、納得して発注・運用できます。
ブログ集客コンサルの役割と提供範囲

ブログ集客コンサルは「戦略を作る」「実装を回す」「数値で改善する」の三領域を一気通貫で支援します。
単にアドバイスを出すだけではなく、現状診断から優先度付け、キーワード方針とサイト構造の再設計、記事制作体制の整備、内部リンクとCTAの導線設計、GA4やSearch Consoleを使った計測とレポーティングまでを、再現可能な手順に落とし込みます。
自社のリソースやスキルに応じて、内製と外部をどう分担するかも重要です。例えば「戦略はコンサル、制作は内製」「方針は内製、計測設計と改善会だけ外部」など、役割を明確にすると費用対効果が安定します。
下表は、提供範囲とアウトプットの目安です。
| 領域 | 主なアウトプット | 成功指標の例 |
|---|---|---|
| 戦略 | 現状診断、キーワード計画、サイト構造案、四半期ロードマップ | 対象キーワードの網羅率、重複意図の解消数、公開計画の遵守率 |
| 実装 | 記事テンプレ、編集ガイド、内部リンク設計、CTA配置案 | 記事到達数、内部リンククリック率、CTAクリック率 |
| 改善 | ダッシュボード、月次レポート、リライト計画、ABテスト設計 | CTR向上、滞在と深度の改善、LP直CVR、獲得単価の低下 |
- 記事は出せているが検索流入とCVが伸び悩んでいる
- 社内でKPIや優先順位が決まらず、着手順の判断に時間がかかる
戦略設計とキーワード計画とサイト構造の設計
戦略設計では、まず現状を「集客・回遊・転換」の三層で分解し、阻害要因を特定します。次に、キーワードを目的別と段階別に整理し、重複意図を統合したうえで、狙う面を決めます。
サイト構造は、ハブ記事とスポーク記事の二層で計画し、パンくずとカテゴリを簡潔に保ちます。これにより、検索エンジンにも読者にも意図が伝わりやすくなり、回遊が自然に生まれます。
実務では、週単位で「新規公開」「追記・差分更新」「統合・リダイレクト」を配分し、四半期ごとにテーマの穴を棚卸しします。戦略は一度決めて終わりではありません。
Search Consoleのクエリ変化やSERPの形式変化を見ながら、見出しの型や記事タイプ(比較・手順・事例)の比率を微調整していきます。
| 項目 | 設計のポイント | アウトプット例 |
|---|---|---|
| 現状診断 | 表示・CTR・滞在・離脱・CTA・LPを分解 | 三層のボトルネック表、優先度リスト |
| KW計画 | 目的別と段階別で拡張し重複意図を統合 | 面のカバレッジ表、優先順位マップ |
| 構造設計 | ハブとスポーク、パンくず、カテゴリの簡素化 | サイトマップ、内部リンクの指針 |
【運用のヒント】
- 重複意図は統合して評価を集中、上位URLを正規化する
- ハブは用語と評価軸、スポークは具体的手順や比較に特化する
記事制作と内部リンクと導線設計の実行支援
制作支援の中心は「テンプレ化」と「品質基準の明文化」です。記事テンプレには、導入の要約、結論、根拠、手順、事例、注意、次の一歩の順序を固定し、見出し語は検索意図の質問に一対一で答える表現にします。
編集ガイドには、引用ルール、図表の作り方、撮影やスクリーンショットの基準、禁止表現をまとめます。内部リンクは、ハブからスポークへ、スポーク同士も横連携し、アンカーテキストは「その先で得られる内容」を具体化します。
CTAは上部・本文中・末尾で役割分担し、LPの見出しと同じ言葉と同じ根拠を近接表示します。これにより、クリック後の不安が減り、CTA率とLP直CVRが安定します。
制作の速度を保つために、週次で「下書き→校閲→公開→差分更新」のスプリントを回し、Search ConsoleのクエリやGA4の深度データに合わせて、見出しと図表、内部リンクの差し替えを継続します。
| 領域 | 実務のコツ | 確認項目 |
|---|---|---|
| テンプレ | 結論前倒し、章ごとに到達基準を明記 | 導入要約と図の再掲、重複表現の削減 |
| 内部リンク | ハブ↔スポークの双方向と横連携 | 孤立ページの有無、具体的アンカー |
| CTA | 動詞と結果の文言、事例直後の配置 | 記事とLPで同語・同数値、フォームの最小化 |
- 導入で結論と価値が言い切れている
- 内部リンクがハブとスポークで往復できる
計測と改善とレポートの運用設計
計測設計では、UTM命名とGA4イベント名を先に固定し、誰が見ても同じ意味で読める状態にします。
基礎のダッシュボードには、検索からクリックまでの前段(表示、CTR、平均掲載順位)と、記事内の読了指標(エンゲージメント率、スクロール深度)、行動指標(CTA率、LP到達率、LP直CVR、フォーム離脱率)を並べます。
週次の改善会では「最も落ちている一段」を選び、翌週に一要素だけ変更して同条件で再計測します。
月次レポートでは、四半期KPIに対する進捗、勝ちパターンのテンプレ化、今後の穴埋めテーマを示します。レポートは“報告”で終わらせず、直後のリライトやABテストの指示書とセットにすることで、会議後すぐ実行へ移れます。
| 段階 | 見る指標 | 主な打ち手 |
|---|---|---|
| 検索→クリック | 表示、CTR、平均掲載順位 | タイトル前半の具体化、導入要約の改善、適切な構造化 |
| 読了→行動 | エンゲージメント率、深度、離脱位置 | 結論の前倒し、図表追加、内部リンクの再配置 |
| 行動→完了 | CTA率、LP到達率、直CVR、離脱率 | CTA文言と配置のAB、LPの言葉合わせ、フォーム短縮 |
- 数値だけ並ぶレポート→次の一手が決まる指示書を同梱
- 同時に多要素を変更→一要素ずつの検証に絞る
効果と費用の目安を整理

ブログ集客コンサルの「効果」は、集客(表示・クリック)、回遊(滞在・深度・内部リンク)、転換(CTA・LP到達・完了)の三層に分けると設計しやすいです。
ここで大切なのは、金額だけで判断しないことです。費用は「どの層に、どのアウトプットを、どれだけの頻度で提供するか」によって価値が決まります。
例えば、戦略ドキュメントとサイト構造の再設計は“初速のてこ”、記事テンプレと内部リンク網は“再現性のてこ”、計測ダッシュボードと月次改善会は“継続改善のてこ”です。
費用対効果を見誤らないために、下表のように「段階→主KPI→想定アウトプット→レビュー頻度」を一枚にまとめ、四半期ごとに見直します。これだけで、投下資源のズレや“報告だけのレポート”を防げます。
| 段階 | 主KPI | 想定アウトプット/レビュー |
|---|---|---|
| 集客 | 表示・CTR・平均掲載順位 | KW計画・タイトル/導入差し替え・週次レビュー |
| 回遊 | エンゲージメント率・スクロール深度 | 見出し/図表の再構成・内部リンク最適化・隔週レビュー |
| 転換 | CTA率・LP到達率・直CVR | CTA文言/配置のAB・LP言葉合わせ・月次レビュー |
- 四半期KPI(例:LP直CVR)を1つだけ掲げ、他は従属指標として扱う
- UTM命名とGA4イベント名を固定し、誰が見ても同じ意味で読める状態にする
成果指標の設計と達成基準の考え方
成果指標は「上流→中流→下流」を連結して設定します。上流は表示・CTRのような“見つけられ度”、中流は滞在・深度・内部リンククリックのような“読み進め度”、下流はCTA率・LP到達率・直CVRのような“行動度”です。
各指標はSMART(具体・計測・達成可能・関連・期限)で置き、基準は〈現状値→ベースライン(維持)→ストレッチ(改善)〉の三段で持ちます。
例えば、CTRは「タイトル前半の具体性」「導入の要約」が主なレバー、深度は「結論の前倒し」「図表の前出し」、CTA率は「動詞+結果の文言」「事例直後の配置」がレバーです。
指標を単独で追うと空回りするので、必ず“対”で見ます(例:CTR↑と深度→、深度→とCTA↑)。下表は、代表指標の意味と設計ポイントです。
| 指標 | 意味 | 設計ポイント |
|---|---|---|
| CTR | 検索結果で選ばれる強さ | クエリの語を前半へ、数値や対象を明示、導入で“読む価値”を言い切る |
| 深度/滞在 | 読み進められる度合い | 結論→理由→手順→事例→注意の順、図表を前出し、段落を短く |
| CTA率 | 記事が行動に結びつく度合い | 動詞+結果のCTA、事例直後に配置、LP見出しと同語/同数字 |
| 直CVR | LPの最終転換力 | メッセージ統一、フォーム最小化、速度(LCP/CLS/INP) |
【基準づくりのコツ】
- 四半期で“下流1指標”を最重要にし、上流/中流は支援指標に置く
- 改善は1要素ずつ検証(タイトル前半か、図表位置か、CTA文言か)
料金形態と相場の考え方と費用配分
料金は「形態」と「含まれる範囲」で見ます。形態は概ね、月額顧問(伴走型)、プロジェクト(期間・成果物定義型)、スポット/時間(単発課題解決型)、成果連動やハイブリッド(固定+成功報酬)に分類できます。
重要なのは、費用が何に使われ、どんなアウトプットで返ってくるかを明確にすることです。例えば、伴走型は“継続改善と内製化”に強く、プロジェクト型は“立ち上げの初速”に強い、スポットは“詰まっている一箇所”に効きます。
相場は業務範囲・工数・体制で変動するため、金額の妥当性より「戦略/実装/計測の三点が揃うか」「レビュー頻度が合うか」を先に見極めます。費用配分は、総予算を100としたときの“比率”で検討すると判断がぶれません。
| 形態 | 向いている状況 | 注意点 |
|---|---|---|
| 月額顧問 | 継続改善・内製化の伴走が欲しい | 範囲が曖昧だと負荷が拡散。KPIとレビュー頻度を明記 |
| プロジェクト | 短期で立ち上げや再設計をしたい | 成果物の定義と検収基準を先に合意 |
| スポット/時間 | 詰まりの解消やレビューだけ欲しい | 議題とゴールを明確化、実行者の役割分担を確認 |
| ハイブリッド | 固定+成果でリスクと成果を分けたい | 成功の定義と計測方法を先に設計 |
- 戦略/構造:20(初期2か月で集中的に実施)
- 制作/内部リンク:50(継続の主戦力。内製と外注を半々に)
- 計測/改善:30(ダッシュボード整備+月次改善会)
投資回収の試算と判断基準の作り方
投資判断は「数式」でシンプルにします。まず、平均LTV(1件あたりの売上/粗利の目安)を置き、必要CV数=目標売上÷LTV で算出します。次に、必要セッション=必要CV数÷(記事内CTA率×LP到達率×直CVR)で概算します。
これで「必要な流入量」と「どのレバーを動かすべきか」が見えます。例えば、LTVが同じなら、直CVRを上げる方がセッションを増やすより費用対効果が高いケースが多いです。
試算は“静的”ではなく“更新可能”であることが重要です。四半期ごとに実績値で置き換え、ストレッチ値とベースライン値の二本を持ちます。下表のテンプレに、現在値を差し込んで使ってください。
| 項目 | 算出式 | 入力/例 |
|---|---|---|
| 必要CV数 | 目標売上÷LTV | 例:1,000,000÷50,000=20 |
| 必要セッション | 必要CV数÷(CTA率×LP到達率×直CVR) | 例:20÷(0.10×0.60×0.20)=1,667 |
| 差分インパクト | 各率の+1ptで減るセッション | 例:直CVR+1pt→必要セッション約8%減 |
【判断基準づくりの手順】
- 四半期KPIを1つ決め、他は従属指標にする
- 必要セッションの分解から、最も効くレバー(CVRか深度かCTRか)を選ぶ
- 一要素ずつABテスト→翌月の試算に反映し、投資継続の可否を決める
コンサルの選び方とチェックポイント

「誰に頼むか」で成果と投資効率は大きく変わります。ブログ集客コンサルを選ぶときは、①再現性のある実績が一次情報で示されているか、②支援範囲(戦略・実装・計測)が過不足なく設計されているか、③体制とコミュニケーション(頻度・SLA・窓口)が明確か、④契約前にリスクと想定外のコストを洗い出せているか、の4点で評価します。
単発の成功談や抽象的な表現だけでは判断できません。施策前後の数値、改善サイクル、現場で使ったドキュメント(テンプレやチェックリスト)の提示がない場合は、再現性が乏しい可能性があります。
面談では、あなたの既存記事や計測環境を前提に「最初の90日で何をし、四半期で何を測るか」を具体語で語れるかを確認しましょう。下表を使うと、候補の比較がスムーズです。
| 評価軸 | 見るべき情報 | 確認のしかた |
|---|---|---|
| 実績の実在性 | 前後数値・使用テンプレ・担当範囲 | 匿名でもよいので数値スクショ・ドキュメント見本を依頼 |
| 支援範囲 | 戦略/実装/計測のカバーと優先度 | 90日計画・四半期KPI・週次レビューの進め方 |
| 体制 | 担当者スキル・代替要員・SLA | 窓口/稼働時間/レス期限・緊急時の連絡手順 |
| 契約条件 | 成果物・検収基準・中途解約 | 合意書に文面で明記、口頭合意を残さない |
- 最初の90日でやること→あなたのサイト前提で「3つ」だけ挙げてもらう
- 提示できる一次情報→数値スクショまたは資料見本の有無
実績と一次情報の提示と再現性の確認
実績確認で重要なのは「一次情報」と「再現性」です。まず、施策前後の数値(表示・CTR・深度・CTA率・直CVRなど)を、期間と定義付きで提示できるかを確かめます。
匿名でもかまわないため、Search ConsoleやGA4のスクリーンショット、LP改善前後の差分、ABテストの設計書と結果など、一次情報が1点でも出ることが信頼の土台です。次に、成果が特定条件に依存していないかを確認します。
たとえば大型予算の広告併用やブランド力による例外を、他案件へ横展開できる根拠(テンプレや手順)で説明できるかを見ます。
再現性の指標は、テンプレ・チェックリスト・内製移管の実績があるかどうかです。面談では、あなたのサイトの1記事を題材に「タイトル前半」「導入要約」「内部リンク」の3点をどう直すか、具体案を出してもらい、その場で実装手順と計測方法まで話せるかを確認します。
【確認ポイント】
- 施策前後の数値に「期間・対象・定義」が付いている
- テンプレ/チェックリスト/ダッシュボードの見本がある
- 他業種・他規模での再現例と横展開の手順が説明できる
| 項目 | 妥当な提示例 | 注意すべき例 |
|---|---|---|
| 数値 | 「3か月で直CVR 1.2→2.1%(記事20本/LP1種)」 | 「数倍になった」などの抽象表現だけ |
| 根拠 | AB設計書・前後スクショ・採点基準 | 図表だけで定義が不明、前提条件の非開示 |
| 再現性 | テンプレとSOP、内製移管の実績 | 属人的ノウハウで手順化がされていない |
- 「匿名で構いませんので、施策前後の指標と期間・定義を添えた資料を1点ご提示ください」
- 「記事テンプレまたは編集ガイドのサンプルを1ページ拝見できますか」
支援範囲と体制とコミュニケーションの評価
よいコンサルでも「支援範囲」と「体制」が合わなければ成果は出にくいです。まず、戦略(KW計画・構造設計)/実装(記事テンプレ・内部リンク・CTA配置)/計測(UTM・GA4ダッシュボード・改善会)の3点が揃っているかを確認します。
片寄りがある場合は、社内や別パートナーで補えるかも合わせて検討します。体制では、担当者の経験(BtoB/BtoC・コンテンツ量・CMS経験)、代替要員の有無、窓口の一元化、SLA(質問への返信・差し替えの所要時間)を明文化してもらいましょう。
コミュニケーションは、週次の定例・チケット運用・指示書のフォーマット(Googleドキュメント等)を固定し、会議が“報告会”で終わらない仕組みを作ることが重要です。
定例では「最も落ちている段階を1つ選ぶ→一要素だけ変更→翌週に同条件で再計測」というループを回せるかが評価軸になります。
【運用の型】
- 週次:ダッシュボード確認→一要素変更→実装チケット発行
- 月次:成果レビュー→テンプレ改訂→四半期KPIの進捗共有
| 項目 | 合格ライン | 要注意サイン |
|---|---|---|
| 支援範囲 | 戦略/実装/計測の三点が揃う | 戦略のみ・レポートのみ・制作のみの片寄り |
| 体制 | 担当スキルと代替要員、SLAの明記 | 担当が不在時のバックアップ不明、返信期限が曖昧 |
| 定例運用 | 一要素AB→翌週再計測を継続 | 毎回テーマが変わる、宿題が残り続ける |
- 返信SLA(例:24時間以内)、差し替えSLA(例:当日中/翌営業日)
- 定例の目的と成果物(例:AB案・指示書・改訂テンプレ)
契約前の確認事項とリスクの洗い出し
契約前に「成功の定義」と「失敗時の手順」を文面で揃えておくと、想定外のコストや遅延を防げます。まず、成果物と検収基準(例:キーワード計画の粒度、サイト構造案の形式、テンプレの項目、ダッシュボードの指標)を仕様書に落とし込みます。
期間・役割分担・中途解約・著作権/二次利用・秘密保持・制作物の帰属、そして広告やツール費など外部費用の負担者も明記します。
リスクは、①成果が出ない、②担当変更や稼働不足、③計測やデータの不整合、④法規やプラットフォーム規約の不遵守、の4系統で洗い出し、対策をセットで合意しておきます。
たとえば成果が出ない場合は「四半期でKPI再設計・テーマ差し替え」、担当不在時は「代替要員/返金規定」、計測不整合時は「定義表の再発行」、規約面では「PR明示・著作権のガイド適用」といった具合です。
【契約前チェックリスト】
- 成果物/検収基準/納期/役割分担が文書で定義されている
- KPI・計測定義・UTM命名が共有されている
- 中途解約・担当交代・不履行時の手当が条項にある
- 著作権・PR明示・秘密保持の取り決めがある
| リスク | 想定される事象 | 合意しておく対策 |
|---|---|---|
| 成果不足 | KPI未達成・流入停滞 | 四半期でテーマ/手段の再設計、優先順位の入替 |
| 体制 | 担当交代・稼働不足 | 代替要員/補償、稼働時間ログ、定例の維持 |
| 計測 | 定義の不一致・データ欠損 | 定義表とUTM命名を固定、ダッシュボードの再構築 |
| 規約/法令 | PR不明確・著作権違反 | 表記ガイド適用、監修/法務レビューの導入 |
- 「本契約における成果物はA・B・Cとし、検収は公開または納品をもって完了とする」
- 「四半期KPI未達の場合、優先テーマを合意の上で差し替える」
契約から実行までの進め方
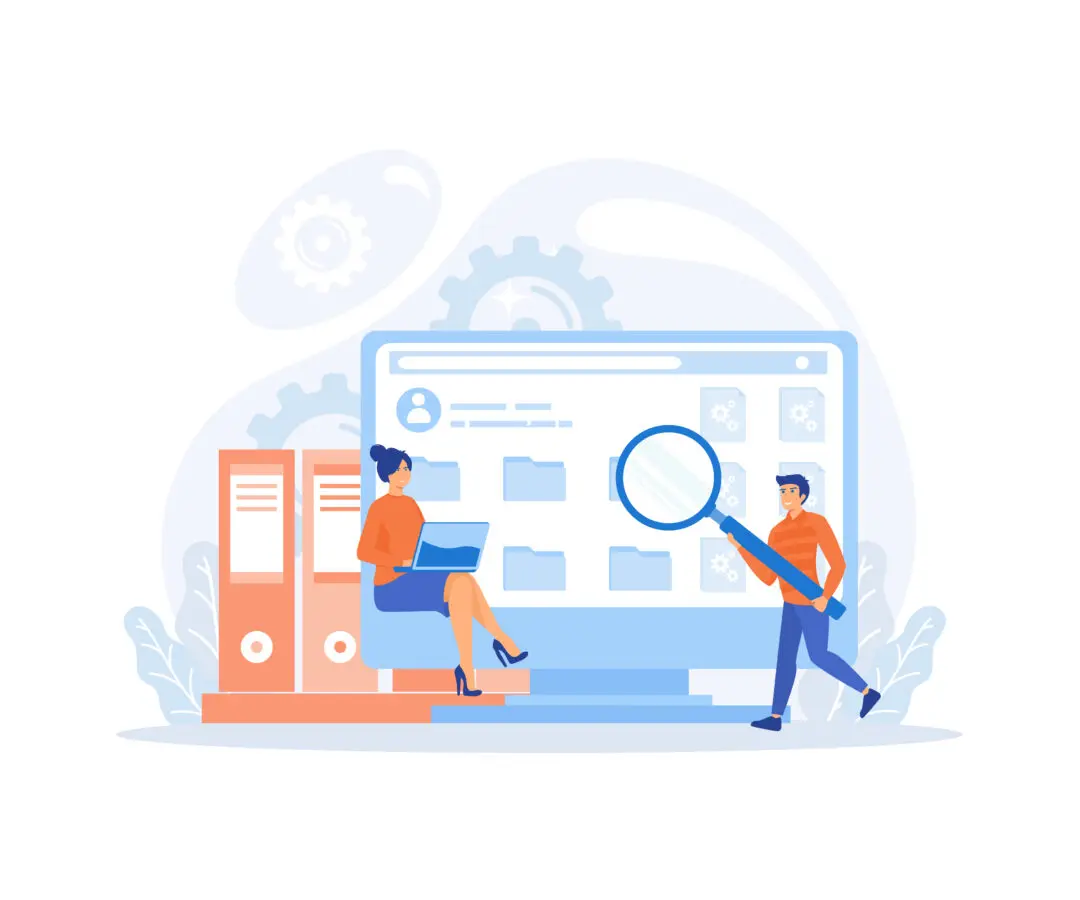
コンサル契約は「合意→診断→設計→実装→改善→共有」の順で、誰が何をいつまでに行うかを明文化すると成果が安定します。
まずキックオフで目的・KPI・体制・SLA(返信/差し替えの目安)を合意し、必要なアクセス権(Search Console・GA4・CMS)とデータ定義をそろえます。次に、現状診断の結果をもとに四半期のロードマップを作成し、バックログ(新規/追記/統合/AB)に落とし込みます。
運用は週次のスプリントで「最も落ちている一段」を一要素だけ改善し、翌週に同条件で再計測。月次は成果レビューとテンプレ改訂、四半期はKPIの見直しと優先テーマの差し替えを行います。
成果はダッシュボードと指示書(リライト指示・AB案)で共有し、ナレッジ(記事テンプレ・内部リンク指針・CTA文言集)に吸い上げます。
最終的には内製化に備え、手順書・チェックリスト・診断スクリプトを標準化して、担当が入れ替わっても同じ品質で回せる状態を作ります。
| フェーズ | 主なアウトプット | 責任/期限の例 |
|---|---|---|
| 合意/準備 | KPI・SLA・権限・データ定義 | 両者でRACI作成、1週以内 |
| 診断/設計 | 現状診断、KW計画、構造案、Q計画 | コンサル主導、2〜3週 |
| 実装 | 記事テンプレ、内部リンク、CTA、AB設計 | 内製/外部で分担、週次 |
| 改善/共有 | ダッシュボード、月次レポ、指示書 | 月次、四半期で見直し |
- 最も落ちている一段を一要素だけ改善→翌週に再計測
- 成果物はテンプレ化し、次の案件に横展開できる形に残す
現状診断と戦略設計と優先順位の決定
着手前の診断は「集客・回遊・転換」の三層で分けて行います。Search Consoleの表示/CTR/クエリ、GA4の深度/離脱/イベント、CMSの発行履歴やカテゴリ構成を集約し、重複意図や孤立ページ、内部リンクの断線、CTAとLPのメッセージ不一致を洗い出します。
次に、キーワードを目的(HowTo/比較/事例)×段階(学習/比較/決定)×対象で拡張し、重複は統合、欠けは補完の方針に整理。サイト構造はハブ(全体像・評価軸)とスポーク(手順・比較・事例)で再設計し、パンくず・カテゴリを簡潔に保ちます。
優先順位は「インパクト×工数」の行列で決めます。たとえば、CTR低迷はタイトル前半と導入要約で短期に改善、深度は結論前倒しと図表の前出し、CTAは文言を動詞+結果にし事例直後へ配置、LPは見出しの言葉合わせとフォーム最小化が効きます。
診断結果は四半期ロードマップ(新規/追記/統合/ABの比率)と、週次スプリントのバックログに落とし込み、誰がいつ何をするかをRACIで固定します。
| 診断項目 | 見るデータ | 初期アクション |
|---|---|---|
| 集客 | 表示・CTR・平均掲載順位 | タイトル前半の具体化、導入要約の再構成 |
| 回遊 | 深度・離脱位置・内部リンククリック | 結論前倒し、図表追加、アンカーの具体化 |
| 転換 | CTA率・LP到達率・直CVR | 事例直後にCTA、LP見出しの言葉合わせ、フォーム最小化 |
- 四半期KPIを1つに絞る(例:LP直CVR)
- 最短で効くレバーから着手(CTR→深度→CTA→LPの順で点検)
四半期計画と月次改善のサイクル設計
四半期計画は「テーマ×アウトプット×レビュー頻度」を決め、月次と週次の運用に落とします。四半期の前半は構造とテンプレの整備(ハブ/スポーク、編集ガイド、内部リンク指針、CTA配置ルール)に投資し、中盤からは記事量産ではなく“差分更新と統合”で評価を集中。
月次は成果レビューとテンプレ改訂、ABの勝ち要素をルールへ反映します。週次はスプリントで「最も落ちている一段」を一要素だけ変更し、翌週に同条件で再計測。
役割はRACIで固定し、SLA(質問/差し替えの対応時間)も明記します。ダッシュボードは前段(表示・CTR)、中段(深度・離脱)、下段(CTA・LP直CVR)を横並びにし、会議が報告で終わらないよう、同時に「指示書(リライト/AB案)」を発行して実装へ接続します。
| サイクル | 目的 | 主な作業 |
|---|---|---|
| 週次 | 一点集中の改善 | 指標確認→一要素変更→翌週再計測 |
| 月次 | 勝ち型のテンプレ化 | レポ共有→テンプレ改訂→優先テーマの更新 |
| 四半期 | KPIと構造の見直し | ロードマップ更新、穴埋めテーマの決定 |
【運用のヒント】
- 新規/追記/統合/ABの比率を月初に決め、突発案件でも崩さない
- ABは一度に一要素だけ(タイトル前半・図表位置・CTA文言など)
成果共有とナレッジ化と内製化の支援
成果を継続させるには、「見える化→標準化→移管」の順で仕組みに落とし込みます。まず、ダッシュボードと月次レポートで成果と学びを見える化し、勝ち要素(タイトルの型、導入要約、図表の位置、CTA文言/配置、LPの言葉合わせ)をテンプレートに反映します。
次に、制作の手順書(記事テンプレ、編集ガイド、内部リンク指針、ABの設計手順)、計測の手順書(UTM命名、GA4イベント定義、ダッシュボード更新)を標準化。
最後に、内製化に向けて研修と伴走(レビュー、制作代行の段階的縮小)を行い、チェックリストで品質を担保します。
共有資産は「誰でも検索できる場所」に保管し、更新履歴と担当を残すことで、担当交代時の学習コストを抑えます。
| 共有資産 | 内容 | 更新頻度 |
|---|---|---|
| 記事テンプレ/編集ガイド | 構成・表記・引用・図表の基準 | 月次(AB勝ち要素を反映) |
| 内部リンク/CTA指針 | ハブ↔スポーク、アンカー語彙、配置ルール | 月次(深度/CTA率を見て改訂) |
| 計測定義/ダッシュボード | UTM・イベント名・指標の定義 | 四半期(KPI変更時に更新) |
- テンプレと手順書が最新版で、変更履歴と担当が残っている
- 定例の進め方(週次/月次/四半期)とSLAがドキュメント化されている
まとめ
結論:コンサルは「戦略設計・実行支援・計測改善」を代替し、内製と併用すると成果が伸びます。実績と一次情報の提示、再現性、支援範囲とSLA、計測設計を事前確認。
まず小さく検証し、四半期計画と月次改善で勝ち型をテンプレ化→段階的に内製へ移管する流れが安全です。