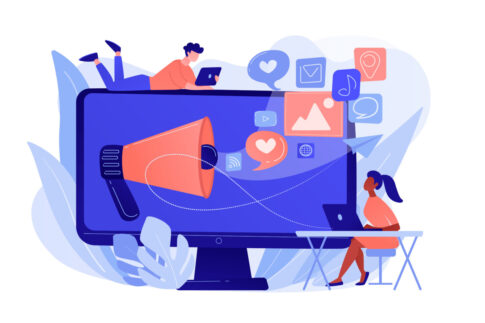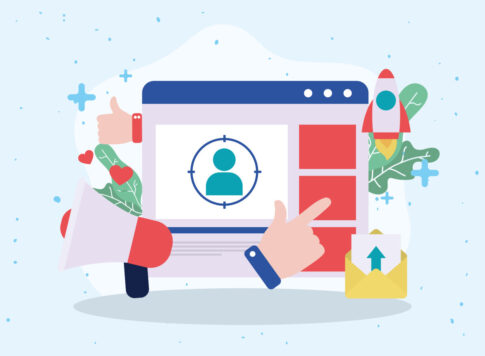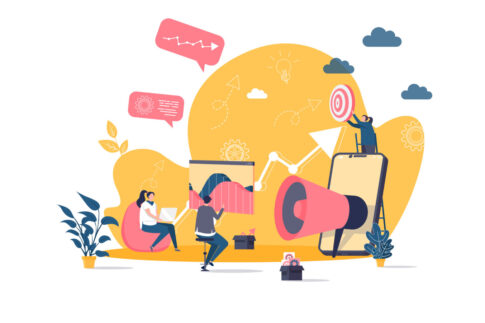ブログ集客は100記事で何が変わる?本記事は、初心者が遠回りせず成果に近づくための「準備と設計」「記事配分(集客・収益・ハブ)」「内部リンク」「書き方テンプレ」「効果の見方と改善」をやさしく整理。今日から迷わず実行できるポイントをまとめます。
100記事で起きる変化と到達目安

100記事まで積み上げると、書くたびにバラバラだった記事が「集客記事→比較やレビュー→申し込みや問い合わせ」に自然につながる導線へと整い、検索意図の理解と見出し設計の精度が上がります。
公開本数が増えることで、検索の表示回数やクリックの推移、上位に入った記事の共通点など、判断に足るデータも蓄積されます。
ここで大切なのは、数値そのものの“大小”ではなく「どの記事タイプが入口になり、どの内部リンクが読者を次の行動へ導いているか」を把握することです。
100記事はゴールではなく、構造化と改善の起点です。到達目安はジャンルや競合状況で大きく変わるため、無理に一律の数値目標を置かず、入口記事の増加、回遊の深まり、申し込みや問い合わせへの導線の整備といった“動きの質”を見ます。
下表の観点で現在地を確認し、次の一手を明確にしましょう。
| 到達指標 | 見方 | 次の行動 |
|---|---|---|
| 上位に入った記事 | どの切り口が検索意図に最も合致したか | 同系統の派生テーマを追加→クラスター化 |
| 入口になった記事 | 最初に読まれる記事の傾向と導線の有無 | ハブ記事へ誘導文を追加→回遊を強化 |
| 内部リンクの通り道 | 関連記事への移動が発生しているか | 比較表や関連記事枠を最適配置→直して再計測 |
| 行動のきっかけ | ボタンやリンクのクリックがどこで起きるか | 訴求文と遷移先の整合を点検→文言と位置を調整 |
- 一律の数値より「入口→回遊→行動」の流れを重視
- 勝ち筋の切り口を横展開→同クエリ群で面を作る
- 更新と追記で最新状態を維持→信頼と再訪を獲得
得られることと強み
100記事までの過程で得られる一番の資産は、再現性のある「書き方の型」と、読者の反応から逆算した「サイト構造の仮説」です。
まず、情報収集→見出し→本文→比較表→CTAという流れが定着し、執筆スピードと品質が安定します。次に、検索の表示やクリックの推移から、入口になりやすいテーマや見出しの言い回しが見えてきます。
さらに、内部リンクの置き方を揃えることで、関連記事に自然に移動する“通り道”ができ、単発アクセスが積み上がりに変わります。
レビューや比較に実測・写真・価格などの一次情報を重ねるほど説得力が増し、記事間の信頼が相互に強化されます。外部環境の変化があっても、型と構造があると素早く追記・差し替えができ、記事群全体の鮮度を保てます。
【得られることの要点】
- 書き方の型が定着→品質とスピードが安定
- 入口記事の傾向が判明→同系統を横展開
- 内部リンクの導線が整う→回遊と滞在が伸びる
- 一次情報が蓄積→比較表やレビューの信頼が高まる
伸びない理由と直し方
伸び悩みの多くは、検索意図とのズレ、同じ狙い語の重複、見出しと本文の不一致、内部リンクの不足、遷移先ページとのミスマッチに集約されます。
たとえば「始め方」なのに比較が中心、「比較」なのに判断軸が曖昧、といったズレはクリック後の離脱を招きます。記事同士が同じ語を狙って競合すると評価が分散し、どれも中途半端になります。
さらに、CTA文言と遷移先の表示内容が食い違うとクリックはあっても行動につながりません。まずは原因を切り分け、表のように兆候から直す順番を決めると効果的です。
| 原因 | 兆候 | 直し方 |
|---|---|---|
| 意図のズレ | 表示はあるのにクリックや滞在が伸びない | 見出しを意図に合わせて再設計→要点を冒頭で明示 |
| 重複と分散 | 似た記事が複数あり双方が上がらない | 統合して一本化→代表記事に内部リンクを集中 |
| 本文の弱さ | 比較軸が曖昧・一次情報が少ない | 価格・所要時間・写真を追加→表で可視化 |
| 導線ミスマッチ | クリックはあるが行動に至らない | CTA文言を見直し→遷移先の条件と整合 |
- タイトルと見出しの約束を守る→ズレは即離脱につながる
- 内部リンクは文脈の直後に置く→次に読む理由を示す
目標の決め方と続ける仕組み
続けるコツは、背伸びした数値ではなく「行動が明確で毎週回せる目標」を置くことです。たとえば、週のはじめにテーマと見出しを決め、必要な写真や実測を先に集めてから執筆に入ると迷いが減ります。
目標は〈公開本数〉〈上位に入った記事の追加や追記〉〈内部リンクの付け替え〉〈行動につながるクリックの改善〉の4点を基本に、無理のない範囲で固定します。
確認は、検索の表示とクリック、読まれた時間、ボタンのクリックの三つを見れば十分です。感覚で判断せず、先に決めた型で改善点を一つずつ潰すことで、積み上げが結果に変わります。
【続ける仕組みの例】
- 週の冒頭にテーマと見出しを決める→迷いを減らす
- 写真・実測を先に用意→本文に客観情報を入れやすい
- 公開と同時に内部リンクを配置→回遊を設計
- 翌週は一つの改善だけに集中→効果を見極めやすい
- 数値は参考、行動を固定→毎週回すことを最優先
- 入口になった記事を軸に横展開→面で強化
- 更新・追記のルールを決めて鮮度を維持
100記事作成の準備と設計

「100記事で成果を出す」ための土台は、書き始める前の準備と設計です。ここでやることは難しくありません。誰に何を届けるかを決め、どの記事を入口にし、どの記事で判断を後押しし、どこで行動につなげるかを地図にするだけです。
最初に読者像と検索意図を整理し、続いて記事タイプの配分(集客・収益・ハブ)を決めます。最後に、記事同士を結ぶ内部リンクとカテゴリ構成を作り、公開後に迷わず回遊できる導線を用意します。
これらは一度で完璧にする必要はありません。公開と同時に仮説を動かし、反応を見ながら少しずつ整えていけば大丈夫です。下の手順と表を参考に、あなたのサイトに合わせて無理なく着手しましょう。
【設計の流れ】
- 読者像と検索意図を定義→困りごと・利用シーン・予算感を言語化
- 記事タイプの配分を決定→入口と決定の役割を切り分け
- ハブ記事を設置→関連ページを束ねる起点を作成
- 内部リンクのルール化→文脈直後に同一表記でリンク
- 公開→反応を見て追記と差し替え→設計を微調整
| 目的 | 記事タイプの例 | 測り方と次の行動 |
|---|---|---|
| 入口を増やす | 基礎解説・始め方・用語集 | 表示とクリックの推移→ハブへ誘導文を強化 |
| 判断を後押し | 比較・ランキング・チェックリスト | 滞在と回遊→CTA前の要約を最適化 |
| 行動につなげる | レビュー・体験記・事例 | ボタンクリック→文言と遷移先の整合を点検 |
- 誰に向けるか→読者の状況・制約・目的
- 入口と決定の役割分担→記事タイプの配分
- リンクの通り道→ハブ→比較→レビューの順
読者ターゲットとキーワード
読者ターゲットは細かい人物像より「状況」で切ると、キーワードが自然に決まります。たとえば、時間がない人は時短や最短ルート、予算が限られる人は安さやコスパ、初めての人は始め方やチェックリストを探します。
まずはシード語(中心語)を決め、関連語を洗い出し、検索結果の上位を観察して意図(概要・比較・レビュー・Q&A)を分類します。
抽象語ばかりを狙うより、読者の条件を掛け合わせた具体語を混ぜると、早い段階で「読まれる」実感が得やすくなります。
たとえば「ブログ 集客 始め方」「内部リンク 作り方」「レビュー 書き方」のように、目的や作業を含む語を優先します。
| 読者の状態 | キーワード例 | 本文の要点 |
|---|---|---|
| これから始めたい | ブログ 集客 始め方/記事 構成 例 | 結論→手順→必要物→注意点→次の一手の順で提示 |
| 比較して選びたい | 内部リンク 方法 比較/記事 配分 例 | 比較軸を固定→向く人・向かない人を同列で記載 |
| 実際の使い勝手が知りたい | レビュー 書き方 例/テンプレ 作り方 | 写真・実測・所要時間を明記→再現性を担保 |
| 今すぐ解決したい | 表示 伸びない 直し方/クリック 増やす 方法 | 先に結論→原因→手順→再発防止→関連Q&A |
- 抽象語の乱発→「始め方」「作り方」など行動語を混ぜる
- 同じ語を複数記事で競合→一本に統合して強くする
- 検索結果の意図とズレた見出し→冒頭で意図に合わせて再設計
【作業の手順】
- シード語を決める→関連語と近い語をリスト化
- 上位ページの見出しを観察→意図を分類して不足を見つける
- 具体語(条件・用途)を追加→記事タイトルと見出しに反映
記事配分|集客 収益 ハブ
記事配分は、100記事を「集客記事」「収益記事」「ハブ記事」に役割分担する考え方です。集客記事は検索の入口になりやすい基礎・始め方・Q&A。収益記事は比較・ランキング・レビューで判断を後押しし、行動へつなげます。
ハブ記事はテーマ全体の案内役で、関連ページを束ねて回遊の基点を作ります。配分はジャンルやサイトの強みによって変わりますが、入口を増やしつつ決定記事へ橋渡しできるよう、入口を多め、決定を厚め、ハブは各カテゴリに1本以上を基本にすると組み立てやすいです。
重要なのは、各タイプの本文が役割に合っていること、そして記事同士が明確にリンクしていることです。
| タイプ | 内容の例 | 導線の置き方 |
|---|---|---|
| 集客 | 始め方・基本・Q&A・チェックリスト | 本文中の要点直後にハブへ→「次に読む」で提示 |
| 収益 | 比較・ランキング・レビュー・事例 | 表の直後にCTA→遷移先と文言の整合を取る |
| ハブ | 総合ガイド・用語集・カテゴリ案内 | 各小テーマへ深掘りリンク→戻り導線も用意 |
- 集客:全体の約半分→入口を広げる
- 収益:全体の約三〜四割→判断を後押し
- ハブ:各カテゴリに1本以上→回遊の基点
【実装のポイント】
- 集客→ハブ→収益の順に読みやすい動線を固定
- 比較は軸を統一→価格・機能・向き不向き
- レビューは写真・実測・所要時間で再現性を確保
内部リンクとカテゴリ構成
内部リンクは、読者の迷いを減らし、記事同士の力を束ねる最重要要素です。カテゴリは広げすぎず、上位は少数精鋭にします。
各カテゴリに必ずハブ記事を置き、そこから基礎→比較→レビュー→Q&Aの順で回遊できる通り道を作ります。リンクは本文の文脈が立ち上がった直後に設置し、同じ語は同じURLへ統一します。
パンくずや関連記事枠も共通ルールで固定すると、スマホでも迷いにくくなります。リンク文言は「名詞だけ」ではなく、行動が分かる短い文を使うとクリックが増えます。また、公開後にリンク切れや重複記事が出てきたら、統合や差し替えで道を整備しましょう。
| 位置 | 目的 | 文言例 |
|---|---|---|
| 冒頭 | 次の読むべき道を提示 | はじめに→「最短で始める手順はこちら」 |
| 本文中 | 文脈の直後で深掘り | 「比較表で違いを確認する→◯◯の比較」 |
| 末尾 | 判断と行動の後押し | 「検討中の方はレビューで実測を確認」 |
- カテゴリを増やしすぎる→上位は少数、下位で整理
- リンク文言が曖昧→行動が分かる短文にする
- 戻り導線がない→ハブに戻るリンクを常設
【整備の手順】
- カテゴリを少数に整理→各カテゴリのハブ記事を作成
- ハブ→基礎→比較→レビュー→Q&Aの順にリンクを設置
- 四半期ごとにリンク切れと重複記事を棚卸し→統合・差し替え
早く成果を出す記事の作り方

短期間で成果を出すには、書きながら迷わない「ひな形」を最初に決めることが近道です。結論を先に示し、理由→手順→具体例→次の一手の順で並べると、読者は最短で要点に到達できます。
さらに、見出しごとに「写真や表で可視化する要素」を決めておくと、本文の説得力が上がります。タイトルは検索意図に直結する行動語を含め、導入では対象読者と到達点を一文で宣言。
本文では一次情報(自分で撮った写真・実測値・所要時間)を最小単位で差し込み、最後に比較やレビュー、Q&Aへ内部リンクで誘導します。
公開後は、表示とクリック、回遊、ボタンの押下の3点だけを確認し、次に直す場所を一つに絞るとスピードが落ちません。
| 要素 | 目的 | 具体例 |
|---|---|---|
| タイトル | 検索意図の明示 | ブログ集客 始め方→最短ステップを解説 |
| 導入 | 対象と到達点の宣言 | 「初心者向け。この記事で内部リンクの作り方が分かる」 |
| 本文 | 再現性の担保 | 写真・所要時間・費用・チェックリストを併記 |
| 締め | 次の行動の提示 | 比較記事へ→レビューへ→問い合わせへ |
【作業の手順】
- 見出し案を作り、各見出しで提示するデータを先に決める
- 結論→理由→手順→具体例→次の一手の順で本文を書く
- 公開と同時に内部リンクとボタンを設置→翌週に一か所だけ改善
- 写真と数値を先に集める→本文が短時間で書ける
- 一記事一目的→比較は比較、レビューはレビューに徹する
- 改善点は毎週一つ→効果が見え、継続しやすい
情報収集の型と見出し設計
情報収集は「一次情報→公式→権威ある解説→上位ブログ」の順で確認し、見出しは検索意図に合わせて設計します。
最初にシード語を決め、関連語と近い語を洗い出し、上位ページのH2/H3を観察して意図を分類。足りない視点(注意点・費用・所要時間・代替案)を補う形で見出しを並べ替えます。
導入では「誰が何を得られるか」を一文で宣言し、各見出しに写真や表で示す要素を対応付けます。文章だけで説明せず、判断材料は図表で可視化すると、読み飛ばしされにくくなります。最後に「次に読むべき1本」を明示し、回遊を設計します。
| 検索意図 | 見出しに入れる要素 | 図表の例 |
|---|---|---|
| 概要・始め方 | 結論・準備物・手順・注意点・次の一手 | 手順フロー・チェックリスト・所要時間表 |
| 比較 | 比較軸・用途別の最適・向く人と向かない人 | 比較表・価格と特徴のマトリクス |
| レビュー | 使用条件・良い点・気になる点・代替案 | ビフォー→アフター・実測値の表 |
| Q&A | 結論・原因・手順・再発防止・関連FAQ | 原因別対処の対応表 |
【調査の手順】
- 一次情報と公式を確認→数字・条件・注意事項を控える
- 上位の見出しを分類→不足視点を洗い出し、見出しに追加
- 各見出しに「何を可視化するか」を割り当て→写真や表を準備
- 抽象的な見出し→行動語と具体名詞を入れて意図を明確化
- 本文と見出しの不一致→冒頭で要点を先に提示して整合
- 出典不明の数字→一次情報と確認日を明記
比較とレビューの型
比較は「同じ軸で並べること」、レビューは「使用条件を明記すること」が基本です。比較では価格・機能・サポート・向き不向きなどの軸を固定し、用途別の最適解を冒頭に提示。
本文は表で違いを可視化し、写真は同条件で撮影します。レビューは使用期間・頻度・環境・比較対象を先に示し、良い点と気になる点を分けて書き、最後に代替案と「向く人・向かない人」を対で提示します。
どちらも断定は避け、読者が自分事として判断できる材料を並べることが大切です。
| 記事タイプ | 必須要素 | 並べる順番 |
|---|---|---|
| 比較 | 比較軸・用途別の最適・向く人と向かない人 | 結論→比較表→短評→注意点→導線 |
| レビュー | 使用条件・写真・実測値・良い点・気になる点・代替案 | 基本情報→使用条件→検証→良い点→気になる点→代替案 |
【レビューで示すポイント】
- 写真は全体→手元→ビフォー→アフターの順で統一
- 数値は所要時間・サイズ・費用など再現に必要なもの
- 代替案は価格帯や用途が近いものを一つ以上
- 比較→同条件の写真・同じ指標の表
- レビュー→使用条件・実測値・撮影条件を明記
CTAと遷移先の整合
読者が迷わず次の行動に進むには、CTAの文言・位置・周辺説明と、遷移先ページの内容が一致していることが重要です。
文言は動詞+ベネフィットで簡潔にし、ボタン直前に「できること・所要時間・注意点」を短く要約。遷移先では価格や条件、申込みの手順が本文の説明と矛盾しないようにします。
配置はファーストビューと本文中、末尾の三か所が基本ですが、本文中は関連表やレビューの直後など「読者が判断した瞬間」に置くと自然です。
公開後はクリックだけでなく、その先の行動が発生しているかを見て、文言や位置を調整します。
| 設置位置 | 意図 | 文言例 |
|---|---|---|
| ファーストビュー | 目的の確認と最短導線 | 最短で始める手順を見る→今すぐチェック |
| 本文中 | 判断直後の後押し | 違いを表で確認→比較の決定版へ |
| 末尾 | 行動の最終案内 | 実測レビューを見る→写真と数値を確認 |
【整合チェックの手順】
- ボタン前の要約に「できること・時間・注意点」を入れる
- 遷移先の価格や条件と本文の記載を突き合わせる
- クリック後の離脱箇所を確認→文言と位置を調整
- 「無料」「最短」など強い語は条件を明記→期待値を合わせる
- ボタンは名詞でなく動詞+ベネフィット→行動が分かる
- 同一語は同一URLへ→読者の迷いをなくす
効果の見方と改善

成果を早く実感するには、感覚ではなく「見方の順番」と「直し方の型」を固定することが近道です。まずは検索の入り口である表示とクリックの動きをつかみ、次に本文の読みやすさと回遊(内部リンクの踏まれ方)を点検、最後にボタンや問い合わせにつながる導線を確認します。
この順番で見ると、直すべき箇所が自然に決まり、手戻りが減ります。重要なのは、すべてを一度に直そうとしないことです。
週ごとに一か所だけ改善して計測→次の一手、という小さなサイクルを回すと、100記事に到達する前から手応えが出ます。下の表は、よくある詰まりポイントと次の行動の例です。
| 指標 | 見方 | 次の行動 |
|---|---|---|
| 表示とクリック | 上位表示なのにCTRが低いか | タイトルと言い回しを意図に合わせて改稿→要約を導入に追加 |
| エンゲージメント時間 | 同ジャンルと比べ短いか | 導入で結論を先出し→図表と写真で要点を可視化 |
| 内部リンク | 関連記事への移動が起きているか | 文脈直後にリンク設置→リンク文言を行動文に変更 |
| ボタンクリック | クリック後に離脱が多いか | 文言と遷移先の条件をそろえる→注意点を直前に要約 |
- 入口の記事は増えているか→表示とクリックの変化
- 読まれる型が定着しているか→時間と回遊の変化
- 行動につながるか→クリック後の到達率
検索の表示とクリックの増やし方
検索の入り口を強くするには、検索意図に合う言い回しと、答えが素早く見つかる構成が必要です。タイトルは行動語と具体語を入れ、導入で「誰が何を得られるか」を一文で宣言します。
本文は見出しごとに要点を先に置き、本文中の最初の一段落で結論→理由→次の一手の順に並べます。
上位ページの見出しを観察し、足りない視点(費用・所要時間・代替案・注意点)を補うと、クリック率が改善しやすくなります。
画像は代替テキストを簡潔に付与し、図表に見出しとキャプションを入れて検索結果との整合を高めます。似た狙い語で記事が分散している場合は統合して一本化し、強い一本に内部リンクを集中させましょう。
| 症状 | 原因の仮説 | 改善アクション |
|---|---|---|
| 表示はあるがCTRが低い | 意図とタイトルがずれている | 行動語と具体語を追加→導入に要約と到達点を追記 |
| 1位群でも伸び切らない | 不足視点で比較され負けている | 費用・時間・代替案・注意点を見出しに追加 |
| 似た記事が競合 | 語句重複で評価が分散 | 統合して代表記事へ→旧URLは導線強化 |
- 釣り気味の表現は避ける→本文と約束が合わないと離脱と否認の原因
- タイトル変更は導入と見出しもセットで再設計→整合を担保
読まれる文章と回遊の伸ばし方
読了と回遊は、文章の見やすさと「次に進む理由」の明確さで決まります。段落は短くし、各見出しの冒頭で要点を一文にまとめます。
写真は全体→手元→ビフォー→アフターの順で並べ、図表には判断に直結する比較軸(価格・時間・向き不向き)を揃えて表示します。
内部リンクは文脈が立ち上がった直後に置き、名詞だけでなく行動が分かる短文にするとクリックが増えます。関連記事枠やパンくずは共通ルールで固定し、スマホのタップ導線を最優先に設計しましょう。
回遊を伸ばすコツは、シリーズ化と戻り導線です。ハブ→基礎→比較→レビュー→Q&Aへ行き来できる道を整えておくと、単発のアクセスが積み上がりへ変わります。
| 位置 | 施策 | 狙い |
|---|---|---|
| 導入直後 | 要約と対象読者・到達点を一文で提示 | 読み進めるべき理由を最初に示す |
| 本文中 | 表と写真で比較・手順を可視化→直後に内部リンク | 理解→次の深掘りへの移動を自然に誘発 |
| 末尾 | 要点の再掲と関連記事の順路を提示 | 迷いをなくし、継続的な回遊を促す |
【整え方の手順】
- 各見出しの冒頭に要点の一文を追加
- 判断材料は表と写真で可視化→文だけにしない
- 内部リンクは行動が分かる文に変更→クリック後の戻り導線も設置
- リンク先で迷わないか→ハブと戻り導線を常設
- 同一語は同一URLへ→表記ゆれをなくす
申し込みや問い合わせにつなげる導線
行動につなげる鍵は、ボタンの前後で「何ができるか・どれくらい時間がかかるか・注意点は何か」を短く示し、遷移先の内容と完全にそろえることです。
文言は動詞+ベネフィットで簡潔にし、本文中は判断の直後(比較表のすぐ下やレビューの結論直後)に配置します。
遷移先では価格や条件、申し込み手順の表示が本文の説明と一致しているかを必ず確認します。
また、問い合わせに至らない場合は、代替の小さな行動(資料を見る・チェックリストを使う)を用意すると心理的なハードルが下がります。クリック率だけでなく、その先の到達率まで見て、文言・位置・導入文の三点を調整しましょう。
| 要素 | 見るポイント | 改善アクション |
|---|---|---|
| ボタン文言 | 行動と得られることが伝わるか | 動詞+ベネフィットに変更→例「比較表を見る」「写真と数値を確認」 |
| 設置位置 | 判断直後にあるか | 比較表直下・レビュー結論直後・冒頭の確認用に配置 |
| 遷移先整合 | 価格・条件・手順が一致しているか | 本文の注意点をボタン直前で要約→期待値を合わせる |
| 小さな行動 | 段階的に進める導線があるか | チェックリスト・資料・保存導線を用意→後日の再訪を促進 |
- 「無料」「最短」など強い語は条件と注意書きをセットで表示
- クリック後の離脱が多い場合→遷移先の最初の見出しを本文の表現に寄せる
【整合チェックの手順】
- ボタン前の要約に「できること・時間・注意点」を追加
- 遷移先の価格や条件と本文の記載を突き合わせる
- 到達率の低い位置を上げる→位置と文言をテスト
100記事達成後の次の一手
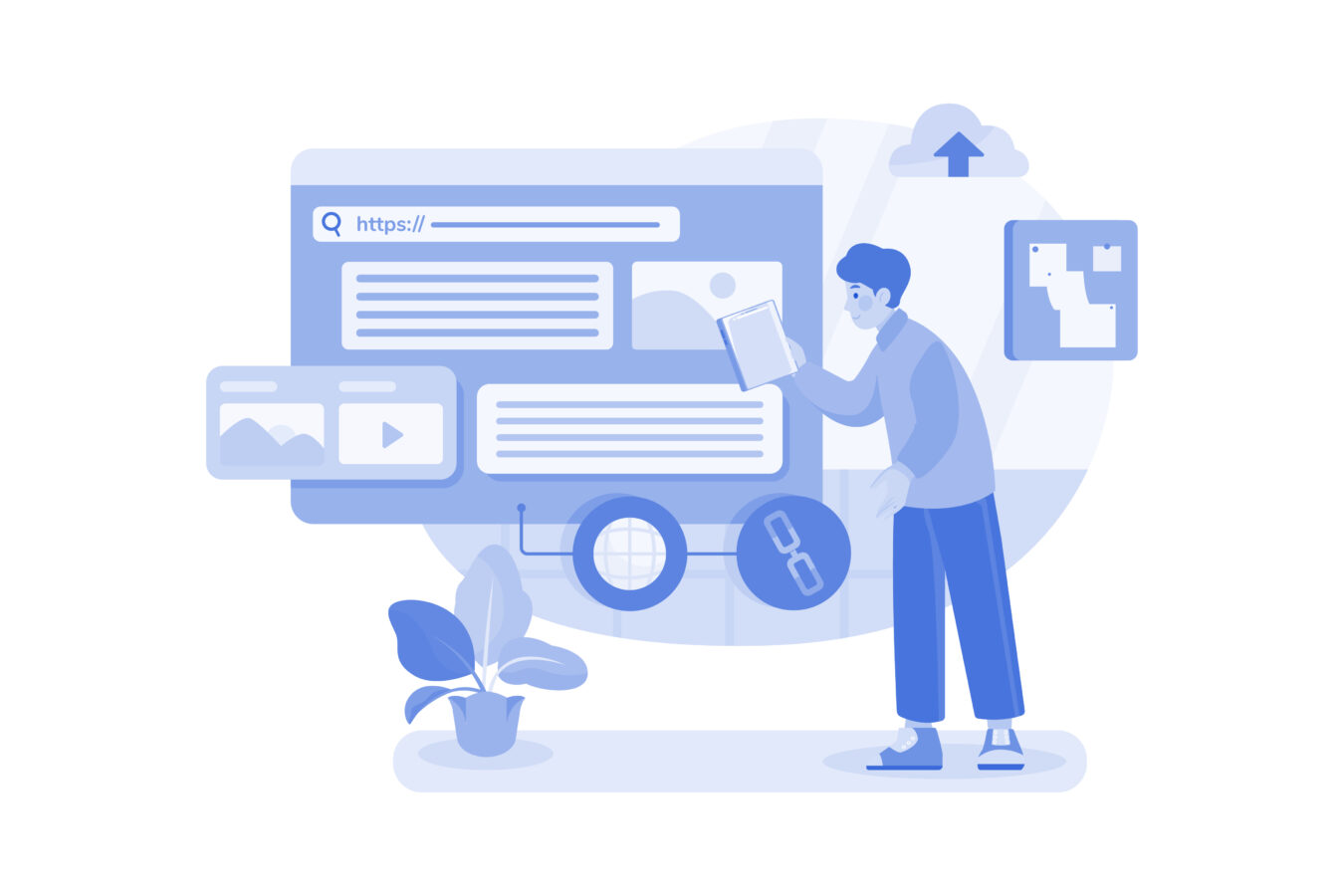
100記事に到達したあとは「数を増やす」よりも「勝ち筋を強くする」段階に入ります。ここでやることは、伸びているテーマを面で広げる、読まれていない記事を直す(または統合する)、次に書くテーマをデータから選ぶ、の三点です。
感覚ではなく、検索の表示とクリック、本文の読まれ方、内部リンクの踏まれ方、ボタンの到達率という“動き”で判断します。
特に入口になった記事と、その直後に読まれる記事の組み合わせは、今後のサイト設計のヒントになります。カテゴリごとにハブ記事を起点に回遊を確認し、道筋が弱い箇所は「要点の再掲→比較やレビューへの導線→戻り導線」を整備しましょう。
下表を使って、状況→見るポイント→次の行動の順で淡々と改善すると、100→150→200記事と伸ばす過程でもブレずに積み上がります。
| 状況 | 見るポイント | 次の行動 |
|---|---|---|
| 特定テーマが伸びた | 入口記事→次に読まれる記事の組み合わせ | 横展開で派生記事を追加→ハブと内部リンクを強化 |
| 読まれない記事が多い | 表示はあるか/CTR・滞在・回遊のどこで詰まるか | リライトか統合を選択→代表記事に力を集中 |
| 行動につながらない | ボタン前の要約・文言・遷移先の一致 | 整合を点検→文言と位置を調整、代替行動も用意 |
- 横展開を毎月追加→勝ち筋を面で強化
- 統合・リライトを定期実施→評価の分散を防止
- 導線の整合チェック→クリック後の到達率まで確認
伸びたテーマの横展開
横展開は、伸びた切り口を「用途・対象・条件」で細分化し、同じ型で量産することです。たとえば「内部リンク 作り方」の記事が入口になっているなら、「WordPressの具体手順」「小規模サイト向けの通り道設計」「比較記事へのつなぎ方」など、読者の作業単位で広げます。
写真や表の見せ方、CTAの位置、戻り導線を共通化すると、記事間の移動が滑らかになります。作る順番は、入口→判断→行動の直列を意識すると迷いません。
【横展開の型】
- 用途別→個人ブログ向け/企業サイト向け/EC向け
- 対象別→初心者向け/少人数運用向け/更新頻度が少ない方向け
- 条件別→予算ひかえめ/時短重視/画像多めの構成
| 伸びた切り口 | 派生テーマ | リンク先の設計 |
|---|---|---|
| 始め方ガイド | 準備物リスト/注意点/よくある失敗 | ハブ→比較→レビューへ順路を固定 |
| 比較記事 | 用途別の最適解/向く人・向かない人 | 個別レビュー直下にCTA→戻り導線も設置 |
| レビュー | 使用条件違いの再検証/代替案の詳解 | 比較の決定版へ回帰→シリーズで再訪を促す |
- 同じ語で記事を量産しない→代表記事に内部リンクを集中
- 写真・表のフォーマットを統一→読者の学習コストを下げる
読まれない記事のリライトと統合
読まれない記事は「直す」「まとめる」「役割を変える」の三択です。まず、表示はあるのにCTRが低い→タイトルと導入の意図ずれ。表示は少ない→狙い語の競合や重複。
滞在が短い→要点が後ろ・図表不足。回遊が弱い→リンクの位置と文言が曖昧、と切り分けます。重複して評価を奪い合っている場合は統合し、代表記事に一本化します。
統合時は、弱い記事の要点・写真・実測値を代表記事へ取り込み、元記事には注記を付けて読者を迷わせないようにします。
役割転換の例として、検索で伸びない記事を内部リンク用の「用語集」「Q&A」に作り替え、回遊の通り道として活用する方法も有効です。
【棚卸しの手順】
- 表示・CTR・滞在・回遊を一覧化→詰まり箇所を特定
- 重複を洗い出し→代表記事を決め、統合設計を作成
- 統合後に見出しを再設計→表と写真で判断材料を補強
| 症状 | 原因の見立て | 対応 |
|---|---|---|
| CTRが低い | タイトル・導入が意図とずれ | 行動語と具体語を追加→導入で到達点を宣言 |
| 滞在が短い | 要点が後ろ/図表不足 | 冒頭に要点→比較表・写真を追加 |
| 回遊が弱い | リンク位置と文言が曖昧 | 文脈直後に設置→行動が伝わる文に変更 |
| 評価の分散 | 似た記事が競合 | 統合して一本化→代表記事へ内部リンクを集中 |
- 入口ポテンシャルが高いページから→表示があるのにCTRが低い
- 比較・レビューなど“決定記事”は厚く→数値と写真で補強
次に書くテーマの選び方
次のテーマは「勝ち筋の近縁」「不足している検索意図」「読者の行動を前に進める題材」から選ぶと外しにくいです。
入口になった記事のクエリと見出しを見返し、読者が次に知りたくなる具体的な条件(費用・時間・対象・用途)を洗い出します。
抽象語だけでなく、作業や目的の言葉(始め方・作り方・比較・レビュー・直し方)を組み合わせるのがコツです。
季節性やイベントの需要があるジャンルは、事前に準備して公開→更新で追うと効率的です。記事の役割(入口・判断・行動)を明確にし、内部リンクの通り道に沿って配置すれば、単発ではなく面で効果が出ます。
【選定のチェックポイント】
- 伸びた記事の“すぐ隣”を狙う→用途・対象・条件で細分化
- 不足意図を補う→概要・比較・レビュー・Q&Aの穴を埋める
- 行動に近い題材を優先→比較表の続編やレビューの深掘り
| 目的 | テーマの例 | 配置と導線 |
|---|---|---|
| 入口拡大 | 最短手順/チェックリスト/よくある失敗 | ハブ直下に配置→比較へ誘導 |
| 判断支援 | 用途別の最適/向く人・向かない人 | レビューへ直結→戻り導線で往復可能に |
| 行動促進 | 実測レビュー/導入手順の詳解 | CTA直前に配置→注意点を要約して整合 |
- 抽象語の乱発→行動語と具体条件を必ず混ぜる
- 同じ語で量産→代表記事に集約し、周辺で面を作る
まとめ
100記事の要は、狙う読者とキーワードを決め、集客・収益・ハブを配分して内部リンクで束ねることです。
情報収集→比較→レビューの型で書き、CTAと遷移先の整合を徹底。表示とクリックを見直してリライト・統合を回す。伸びたテーマは横展開し、次の一手へつなげましょう。