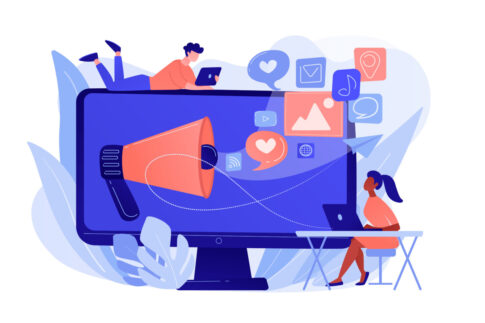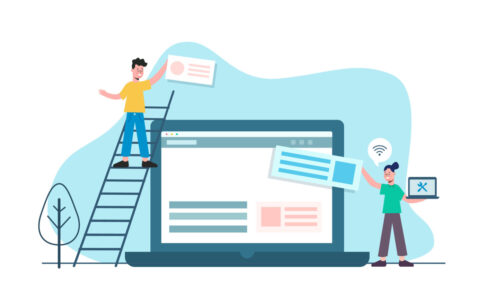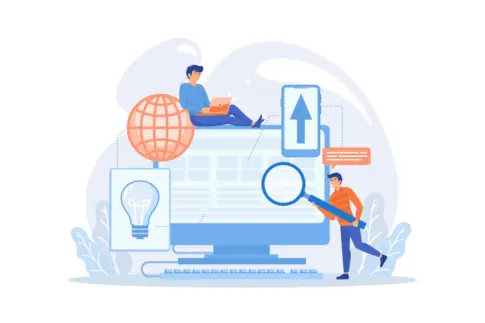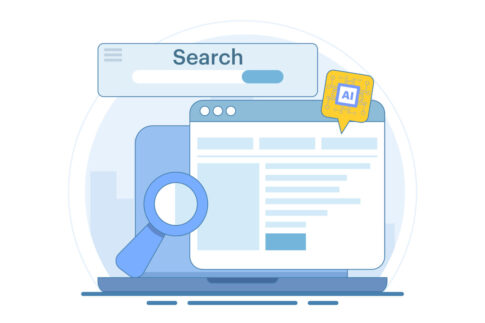「ブログ集客は誰が見るのか?」は感覚ではなくデータで判定できます。
本記事はGA4とサーチコンソールを活用し、来路・検索意図・属性・行動を5ステップで特定する方法を解説。内部リンクとCTAの最適化までつなげ、少人数でも狙う読者に届きCVへ進む導線づくりを支援します。
目次
結論|ブログ集客は誰が見るかをデータで定義
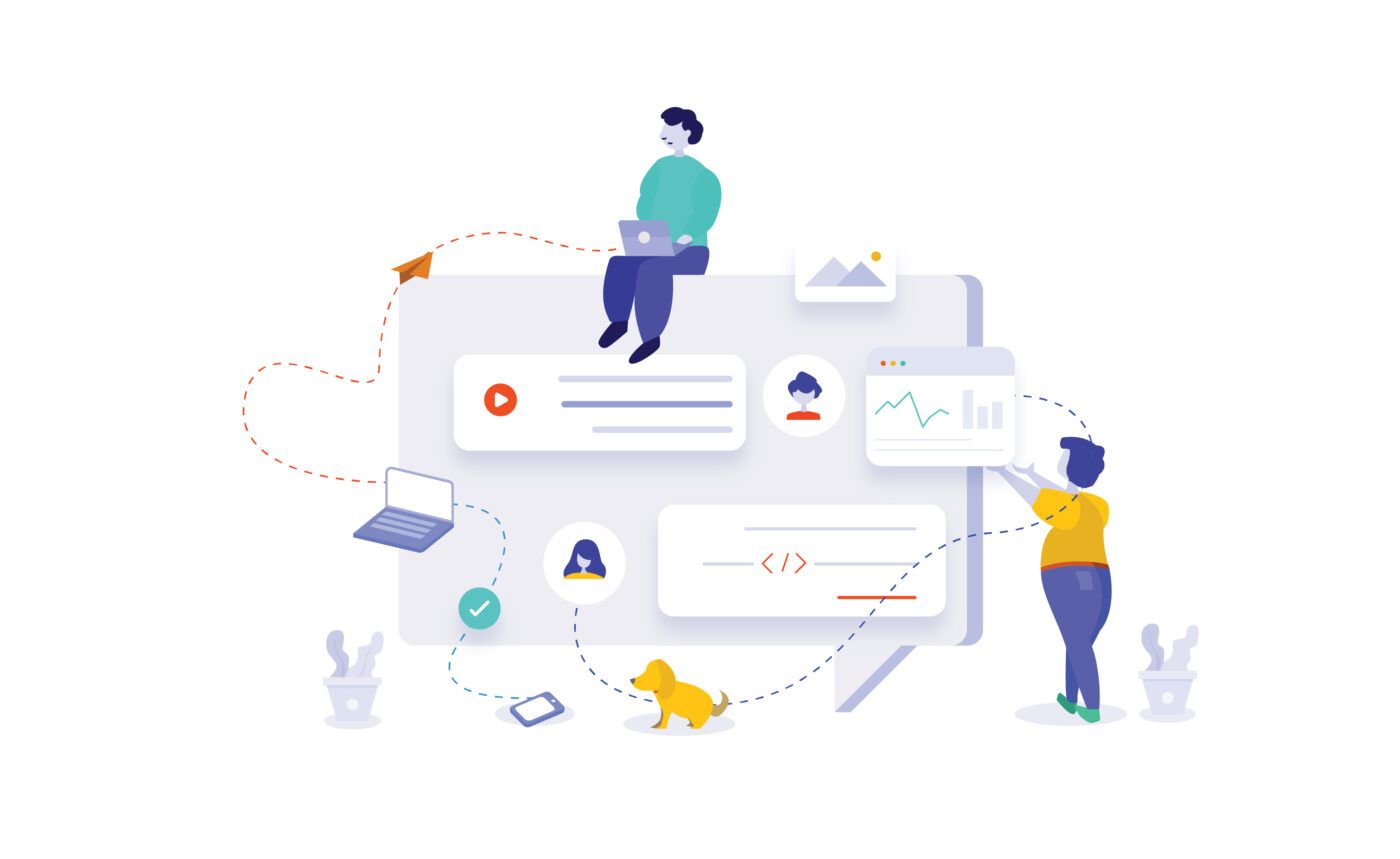
「誰が見るか」は勘ではなく、計測データで定義できます。出発点は、流入経路と検索意図を特定し、読者が次に進む導線を可視化することです。
具体的には、GA4でチャネル別の流入と行動を把握し、サーチコンソールで検索クエリとランディングページの対応を確認します。
さらに、UTMでキャンペーンやSNSの投稿別成果を切り分けると、施策ごとの効果が明確になります。解像度を上げるために、地域やデバイス、興味関心といった属性でセグメントを分け、回遊や離脱のポイントを比較しましょう。
重要なのは、数値を集めるだけでなく、読者の用件に沿って記事タイプとCTAを調整することです。比較を求める読者には比較表と料金ページへの導線、初学者には基礎ガイドとチェックリスト、導入直前の読者には事例と問い合わせを提示する、といった形で設計します。
【確認すべき指標】
- チャネル別の流入とエンゲージメント→どこから来てどこで離脱するか
- 検索クエリとLPの対応→何を探して来ているか
- 内部リンクとCTAの到達→次の一歩へ進めているか
| 知りたいこと | 見るデータと判断の観点 |
|---|---|
| 来路 | 参照元・メディア・キャンペーン→流入の増減と質を比較 |
| 用件 | 検索クエリとLP→見出しと本文が意図に合っているか |
| 導線 | 次ページ遷移とCTAクリック→最短経路で案内できているか |
- データで読者像を定義→記事タイプとCTAを合わせる。
- 新規と既存の役割を分担→入口記事とハブ記事で回遊を作る。
- 改善は小さく速く→タイトル・見出し・導線を優先して調整。
ゴールとKPIを設定|CVと回遊で評価軸を揃える
成果を正しく測るには、目的と評価軸を最初に揃えることが欠かせません。購入や問い合わせといった最終ゴールだけを見ると、学習段階の読者が多いブログでは判断を誤りやすくなります。
ゴールを段階化し、資料ダウンロードやメルマガ登録、比較記事の閲覧などのマイクロCVも設定して、回遊と到達の状況を評価に含めましょう。
さらに、章末の内部リンクやCTAの文言、設置位置を変えて、どのパターンが次の一歩に進ませやすいかを検証します。
継続運用では、チャネル別・デバイス別の差を見て、最も効果の高い導線を標準化すると負荷が下がります。
【KPI設計の流れ】
- 最終ゴールを一つに定義→問い合わせや購入などの基準を明確化。
- マイクロCVを設定→資料DL・登録・比較閲覧など段階的な指標を追加。
- 回遊の指標を選定→次ページ遷移、滞在、離脱ページで導線を評価。
- 改善サイクルを固定→タイトル→見出し→CTAの順に検証を繰り返す。
| 目的 | 主要KPI | 補助指標 |
|---|---|---|
| 問い合わせ獲得 | フォーム到達、送信件数、CTAクリック | 比較ページ閲覧、料金ページ到達、スクロール深度 |
| 資料DL・登録 | DL数、登録完了、LP到達 | 記事→LPの遷移率、直帰率、再訪率 |
| EC購入 | カート到達、購入完了、クーポン利用 | 商品詳細到達、関連商品の閲覧、離脱ページの種類 |
- 最終CVだけで判断しない→段階的な到達で成長度を追う。
- 役割の違う記事を同じ物差しで比べない→入口とハブで評価を分ける。
ペルソナと検索意図を接続|用件ベースでテーマ決定
テーマ決定は、想定読者の状況と検索意図を接続するところから始めます。まず、読者がどの段階にいるかを仮置きし、段階ごとの用件を具体化します。
初学者なら基礎の理解や用語の確認、比較検討なら選定基準や違いの整理、導入直前なら事例や料金の不安解消が主な用件です。
次に、サーチコンソールで実際に集まっているクエリを確認し、同じ意味の言い換えを束ねて重複を避けます。見出しは質問文に合わせ、直下に答えの要約を置くと意図に一致しやすくなります。章末には「次に読むべき1本」を固定配置し、読者の疑問が続けて解ける経路を作ります。
無理に広いテーマを一度で解決しようとせず、クラスターとして分割して深掘りしていくと、サイト全体の理解が進みます。
【テーマ選定のヒント】
- 読者の段階を「知りたい→比べたい→決めたい」で仮置き。
- 検索クエリを束ねて代表語を選定→見出しとタイトルに自然に反映。
- 各段階に対応する記事タイプを決定→基礎ガイド、比較、事例、料金など。
- 章末に関連リンク→次の一歩へ誘導して回遊を設計。
- 読者段階を混在させる構成→意図が散らばり離脱が増える。
- 見出しが抽象的→検索クエリの言い回しをそのまま使って具体化。
- 内部リンクが多すぎる→「次に読む1本」を明確にして迷いを減らす。
計測の土台|GA4・サーチコンソール・UTMを整える

「誰が見るか」を正しく捉えるには、計測の土台を先に整えることが近道です。GA4で行動データを、サーチコンソールで検索データを、UTMで外部施策の来路を識別し、三つを突き合わせて判断します。
まず、タグの二重設置やテスト環境の混入を排除し、主要ページ(トップ・記事・LP・フォーム)で正しく計測されているかを確認します。
次に、サーチコンソールとサイトを紐づけ、検索クエリとランディングページの対応を見られる状態にします。
SNS・メール・広告など外部発信はUTMで共通の命名ルールを定め、チャネルごとの評価指標を前もって決めておくと、施策間の比較が容易になります。
権限は「必要最小限」を付与し、担当が代わっても運用が止まらないように、設定・ルール・ダッシュボードをドキュメント化しておくと安心です。
| 項目 | 確認ポイント |
|---|---|
| GA4 | タグ設置の重複防止、主要ページでのヒット、内部トラフィックの除外、コンバージョン設定、テスト環境の除外 |
| サーチコンソール | サイト所有権の確認、プロパティの選択(ドメイン推奨)、インデックス状況、検索クエリ×LPの対応 |
| UTM | 命名ルールの統一(source/medium/campaign)、短縮URLの管理、Google広告の自動タグとの整合 |
【最初に決めること】
- 評価軸(CV/回遊)と優先LP→何を成功とみなすかを明確化。
- チャネル別の役割→入口用・比較用・決定用の記事を割り当て。
- レポート更新日→毎週同じ指標で振り返り、改善点を共有。
基本設定とアクセス権限|計測漏れを防ぐ初期チェック
初期設定の抜け漏れは、後からの分析を難しくします。GA4は計測タグの設置方法(GTMか直接設置か)を統一し、同じページに複数の測定IDが走っていないかを確認します。
主要CV(問い合わせ送信、資料DL、カート到達など)はイベント名を明確にし、重複計測や誤発火がないかテストします。
内部トラフィック(社内IPや検証端末)は除外設定を行い、ステージング環境が本番に混ざらないようにドメインやパスでフィルタします。
サーチコンソールは所有権の確認とサイトマップ送信を行い、検索結果に出てほしいURLがインデックスされているかを点検します。
アクセス権限は、編集できる人と閲覧のみの人を分け、退職・異動時の管理手順も決めておくと運用が止まりません。
フォーム完了ページがない場合は、送信ボタンのクリックやサンクス表示のトリガーでコンバージョンを記録する方法を選びます。
【初期チェック】
- 主要ページでイベントが発火しているかをデバッグ表示で確認。
- CVイベントは一意の条件で記録し、二重計測を防止。
- 内部トラフィックとテスト環境を除外し、数値の純度を担保。
- サーチコンソールの所有権とサイトマップ送信を完了。
- 権限管理のルール(付与・剥奪・記録)をドキュメント化。
- タグの二重設置や古いタグの混在→実装経路を一元化する。
- CVの誤発火→同意バナーや遷移条件で発生しやすいので必ず実機テスト。
- 内部アクセスの混入→社内IP・端末識別で除外し、定期的に見直す。
参照元とキャンペーン識別|媒体別の評価基準を準備
外部施策の効果を見分けるには、UTMで参照元と媒体を統一ルールで付与し、GA4のチャネル分類と整合させることが大切です。
最低限、utm_source(配信元)、utm_medium(媒体種別)、utm_campaign(企画名)を設定し、必要に応じてutm_content(クリエイティブ差)とutm_id(一意ID)で管理します。
Google広告は自動タグ(例:gclid)を優先し、手動UTMで上書きしない運用にすると計測の一貫性が保てます。
メールはmediumを「email」、オーガニックSNSは「social」、有料SNSは「paid_social」、検索広告は「cpc」など、GA4の標準チャネルにマップされる表記を使うと集計が安定します。命名は短く一貫性を持たせ、キャンペーン期間や対象セグメントが分かるようにします。
| チャネル | 推奨utm_medium | 主に見るKPI |
|---|---|---|
| オーガニック検索 | organic(自動判定のためUTM付与は通常不要) | LP別CTR(サチコ)、表示回数、クリック、直帰・回遊 |
| SNS(自然投稿) | social | 初回流入、再訪率、次ページ遷移、指名検索の増加 |
| SNS(有料) | paid_social | LP到達、CVR、クリエイティブ別の差、獲得単価 |
| 検索広告 | cpc(自動タグ優先) | クエリ一致度、LP適合度、キーワード別CV |
| メール・メルマガ | クリック率、LP到達、既存ユーザーの再活性化 | |
| 外部サイト紹介 | referral | 紹介元別の質、回遊、指名検索の増加 |
【命名ルールの例】
- utm_source=配信面(twitter、newsletter、partnerAなど)
- utm_medium=媒体種別(social、email、cpc、paid_socialなど)
- utm_campaign=企画名(spring_sale、guide_releaseなど)
- utm_content=訴求・CTA差(coupon、case_study、videoなど)
- チャネルごとに主要KPIを一つ決め、週次で同じ指標を確認。
- 短縮URLを使う場合もUTMを維持し、テスト配信は別キャンペーン名に。
- SNSの固定ツイートやプロフィールリンクは常に最新LPへ差し替える。
流入と意図の特定|チャネル×検索クエリ

「誰が見るか」を具体化するには、来路(チャネル)と検索意図(クエリ)を突き合わせて読むことが重要です。GA4は「どこから来たか」「どのページに着地したか」「次にどこへ進んだか」を教えてくれます。
一方、サーチコンソールは「どんな言葉で探して来たか」「どのURLが露出・クリックされたか」を示します。
両者を組み合わせ、チャネル別に主要ランディングページ(LP)と上位クエリの対応を作ると、読者の“用件”が見えてきます。
たとえばオーガニック検索では「比較したい」「やり方を知りたい」の意図が強く、SNS自然流入ではブランドや企画名への関心が中心になりやすい、などの傾向が読み解けます。
傾向が分かれば、LPの見出し・要約・CTAを用件に合わせて調整できます。下表はチャネルごとの代表的なクエリ傾向と適切なLPタイプの整理です。
| チャネル | 代表的なクエリ傾向・例 | 適切なLPタイプ |
|---|---|---|
| オーガニック検索 | 選び方・比較・やり方・トラブル例→「◯◯ 比較」「◯◯ 使い方」 | 基礎ガイド/比較表/チェックリスト/料金解説 |
| SNS(自然) | ブランド名・企画名・ハッシュタグ→「◯◯ まとめ」「◯◯ 事例」 | 要点まとめ/舞台裏記事/キャンペーン概要 |
| 外部紹介(referral) | レビュー・引用文脈→「◯◯ 評判」「◯◯ 事例名」 | 事例詳細/検証レポート/引用用に構造化した記事 |
| メール・メルマガ | 更新情報・限定オファー→「今週の新着」「限定クーポン」 | 新着まとめ/特集ハブ/クーポン提示LP |
【読み解き手順】
- GA4でチャネル×ランディングページを抽出→流入の主役ページを把握。
- サーチコンソールで各ページの上位クエリを確認→用件を言語化。
- 用件に合う見出し・要約・CTAへ調整→章末に「次に読む1本」を固定。
- チャネルごとに“想定される用件”を先に仮置き→データで検証する。
- 同じ意味の言い回しは束ねて集計→言葉のブレで判断を誤らない。
- LPは1意図1ページを基本に→カニバリゼーションを避ける。
ランディングページとクエリの対応を確認
LPとクエリの適合性が低いと、露出があってもクリックや回遊が伸びません。まず、サーチコンソールの「検索パフォーマンス」でページ単位の上位クエリを確認し、質問文(〜とは、〜やり方、〜比較 など)の種類を分類します。
次に、LPのタイトル・H1・見出し直下の要約を読み、クエリの質問に即答できているかを点検します。
意図が「比較」なら早い段階で評価軸と結論を表に示し、意図が「やり方」なら手順・前提条件・必要なツールを先に置く、など“用件先出し”が基本です。
章末には「次に読む1本」を固定し、比較→料金→事例、基礎→応用→チェックリストのように最短経路を作ります。内部リンクのアンカーテキストは、代表クエリや読者の質問文を自然に含めるとクリック意図が伝わりやすくなります。
【確認ポイント】
- 上位クエリのトップ3が、H2/H3と冒頭要約に反映されているか。
- “何が分かるか”がファーストビューで伝わるか→要約・目次を最適化。
- 次の一歩(比較・料金・事例・登録)が章末で明確になっているか。
- 古い情報・季節要因・価格改定は追記済みか→更新履歴を明示。
| LPタイプ | 期待するクエリの方向性 | 次の一歩(導線例) |
|---|---|---|
| 基礎ガイド | とは・メリット・始め方 | チェックリスト→比較記事→登録/資料DL |
| 比較記事 | 比較・違い・おすすめ | 料金→事例→問い合わせ/購入 |
| 事例記事 | 成功例・使い方の実像 | 機能詳細→デモ予約→導入相談 |
CTR・掲載順位・エンゲージメントの改善余地
改善の余地は「露出→クリック→体験→CV」の各段で見つかります。掲載順位が2〜5位なのにCTRが低い場合は、タイトルの語順・具体語・ベネフィット提示を見直し、メタ説明は要点+差別化要素を先頭に置きます。
表示回数が多く順位が11〜20位に固まっているページは、クエリの網羅性・内部リンク・ハブ記事との関連強化で底上げします。
エンゲージメント(滞在・次ページ遷移)が弱いときは、見出し直下に答えの要約を置き、章末に明確な「次の一歩」を配置して迷いを減らします。
スクロールが深いのにCV転換しない場合は、CTAの位置・文言・数を最小限に整理し、読者の温度感に合わせた複数パターン(資料DL/無料相談/カートへ)をテストします。
【優先順位の付け方】
- 高表示×低CTRの組み合わせ→タイトル・要約・リッチリザルトを改善。
- 中位表示×高関連のクエリ群→内部リンクと章構成の強化で順位押し上げ。
- 高閲覧×低CVのページ→CTA配置と導線のA/Bでボトルネック解消。
- データは十分なサンプルで評価→短期の変動で結論を急がない。
- ブランド名やDiscoverはCTRが特殊→混在時はセグメントを分ける。
- 構造変更は検索反映まで時間差がある→週次で同じ指標を観察。
受け手像の深掘り|属性・デバイス・行動

「誰が見るか」をより具体化するには、流入チャネルだけでなく〈属性(地域・年齢・興味関心)〉〈デバイス〉〈行動(回遊・離脱・CV到達)〉を組み合わせて読み解きます。
GA4では「ユーザー属性」「テクノロジー」「ページとスクリーン」「探索(経路)」などを横断し、サーチコンソールのクエリと突き合わせると、読者の“用件”が鮮明になります。
たとえば同じオーガニック検索でも、モバイルの20代とデスクトップの40代では読む速度や求める情報の粒度が異なります。
前者には要点の先出しと図解、後者には比較表や価格前提の丁寧な解説が効く、といった具合です。また、新規とリピーターでは導線の最適解が変わります。
新規には基礎→比較→料金の順路、リピーターには事例→料金→問い合わせの順路を明示すると迷いが減ります。
属性データはサンプル数や同意設定の影響を受けるため、十分な母数が取れない場合は、期間を延ばす・主要地域に絞るなどで安定化させましょう。
| 軸 | 見る観点 | 改善アクション例 |
|---|---|---|
| 地域 | 主要都道府県・市区郡、言語設定、時差アクセス | 地域名や商圏用語を見出しに反映、営業時間や配送条件を明記 |
| 年齢 | ボリューム帯、CV率、閲覧記事タイプ | 要点先出し/詳細解説の配分、事例の年代合わせ |
| 興味関心 | 関心カテゴリ別の回遊とCV | 訴求別LPを用意、アンカーテキストを関心語で最適化 |
| デバイス | モバイル/デスクトップの滞在・離脱 | ファーストビューの要約強化、表の簡略版をモバイル優先で設計 |
| 行動 | 次ページ遷移、離脱点、スクロール・クリック | 章末に「次に読む1本」、CTA位置と文言のAB改善 |
- 期間と指標を固定→週次で同じKPIを確認してブレを排除。
- チャネル→属性→デバイス→行動の順で深掘りし、母数不足は期間延長で補完。
- 差が出た要因を見出し・要約・CTAへ反映→翌週のデータで検証。
地域・年齢・興味関心でセグメントを作成
属性でセグメントを切る目的は、読者の状況に合わせて〈見出し〉〈要約〉〈導線〉の最適化ポイントを見つけることです。
まず、主要地域(例:関東・関西・地方中核都市)を抽出し、地域別にランディングページと検索クエリを確認します。
地域名や商圏用語(配送・エリア特有の名称)がクエリに表れている場合は、見出しへ自然に組み込み、章末の内部リンクで地域別の情報へ案内します。
年齢はボリューム帯とCV率のバランスを見て、若年層には「短文+図解+要点リスト」、中高年層には「比較表+前提条件+料金前提」を厚めに配置します。
興味関心(利用可能な範囲)では、関心カテゴリ別に反応の良い訴求を把握し、同じ記事でもCTA文言や事例の切り口を変えると効果が上がります。
属性データはサンプル不足で変動しやすいため、直近だけで結論を出さず、期間を延ばす・主要チャネルに限定する・複数の指標で整合を見る、といった安定化が重要です。
【セグメントの作例】
- 地域×デバイス:都市圏モバイルは「要点先出し+簡易比較」、地方デスクトップは「詳細比較+価格前提」。
- 年齢×行動:20代はSNS経由→基礎ガイド滞在→比較へ、40代は検索→比較→料金→問い合わせ。
- 興味関心×CTA:学習志向にはチェックリストDL、導入志向には事例→相談予約を提示。
【反映のコツ】
- 見出しに地域名や年代の“自分事化語”を自然に含める。
- 同一URLで訴求を切り替えるときは、章末のCTAを属性別に最適化。
- 母数が少ない属性はハブ記事でまとめ、実例を増やして再検証。
回遊経路と離脱点から課題ページを特定
改善の近道は、ユーザーの実際の移動経路を可視化し、離脱が集中する箇所を特定して原因仮説を立てることです。
まず、ランディングページから「次に進んだページ」を確認し、理想経路(基礎→比較→料金→CV、事例→料金→CVなど)に沿って動けているかを見ます。
章末に「次に読む1本」がない、見出し直下に答えがない、CTAが多すぎて迷う、画像が重く読み込みが遅い、といった要因は離脱を招きます。
次に、離脱ページの共通点(デバイス、滞在の短さ、スクロールの浅さ、サイト内検索の発生)を洗い出し、章構成の見直し・要約の追加・テーブル化・画像圧縮・CTAの整理を行います。
モバイルでの可読性は特に重要で、表は簡易版を先に示し、詳細は折りたたみや別記事で補うと直帰が下がります。
| 症状 | よくある観測 | 改善アクション |
|---|---|---|
| 直帰が高い | ファーストビューに答えがない、画像が重い | 見出し直下に要約、画像最適化、要点リストで先出し |
| 回遊が伸びない | 章末に導線がない、アンカーが抽象的 | 「次に読む1本」を固定、アンカーにクエリ語を含める |
| CVに届かない | 比較→料金の間で離脱、CTAが散らばる | 評価軸の表を冒頭に、CTAを1〜2種に絞り位置を統一 |
| モバイルで離脱 | 表が横スクロール、改行が少なく読みにくい | 簡易表を先に、段落を短く、ボタンを親指到達圏に配置 |
【診断の進め方】
- 主要LPの理想経路を定義→実データと照合して差分を特定。
- 離脱点の共通条件(デバイス・滞在・スクロール・検索)を抽出。
- 章構成・要約・CTA・画像の順で軽量な施策から実施→翌週に再計測。
- 高表示×高離脱のLPから着手→影響範囲が大きい順に改善。
- モバイルでの可読性を最優先→行間とボタン間隔を広げる。
- 理想経路に必須のページは章末に固定導線→迷いをなくす。
導線と改善|内部リンク・CTA・リライト

導線づくりは「読者が迷わず次の一歩へ進める状態」をつくることです。入口記事では疑問に即答し、章末で関連ページへ自然に橋渡しします。
ハブ記事はテーマ全体の地図として機能させ、比較・料金・事例などの主要ページへ最短で案内します。
CTA(行動ボタンやリンク)は読者の温度感に合わせて、冒頭=低負荷(チェックリストDL)、本文中=学習継続(比較や事例)、記事末=意思決定(問い合わせ・購入)を配置します。
リライトでは検索意図のズレや情報の古さを直し、見出し直下に要約を置いて離脱を防止します。内部リンクは「次に読む1本」を固定表示し、アンカーテキストは読者の質問文を自然に含めるとクリックされやすくなります。
下表は導線の要素と具体施策の整理です。
| 要素 | 目的 | 具体施策 |
|---|---|---|
| 入口記事 | 検索意図に即答し回遊へつなぐ | 見出し直下に要約、章末に「比較/事例」への固定リンク |
| ハブ記事 | 全体像を提示し最短経路を示す | テーマ別の目次化、重要3ページへの太い導線 |
| CTA | 適切な行動を促す | 冒頭=軽い提案、本文中=関連深掘り、末尾=主CVに一本化 |
| リライト | 鮮度と適合性を回復 | 古い数値と価格を更新、重複項目を整理、事例を追加 |
【優先順】
- 章末の「次に読む1本」を全記事で明確化→回遊の基盤を作る。
- 記事末CTAを主目的に一本化→迷いを減らし到達率を高める。
- 検索意図とズレた見出しを修正→要約と表で先出しする。
- 入口→比較→料金→CVの基準経路を定義し、各記事に役割を割り当てる。
- アンカーテキストは質問文を活用→クリック意図を明確化。
- リライトは「高表示×低CTR」「高閲覧×低CV」から着手する。
記事タイプ別CTA配置|比較・事例・料金の順路
記事タイプごとに読者の用件は異なるため、CTAの位置と文言を最適化します。比較記事では、冒頭で評価軸と結論を示し、本文中に「料金」「事例」への導線を置きます。
事例記事では、背景→課題→施策→結果の流れを簡潔にまとめ、同業種の追加事例や機能ページへ誘導します。
料金記事では、前提条件と費用の内訳を明確にし、「見積もり依頼」「無料相談」のCTAを記事末に一本化します。
ECなら「ランキング→商品詳細→カート」、B2Bなら「比較→料金→事例→問い合わせ」の順路が基本ですが、途中で離脱が多い箇所には章末の追従CTAや簡易Q&Aを置き、躓きを解消します。
モバイルではCTAを親指で押しやすい位置に固定し、表現は「今すぐ資料を受け取る」のように行動を具体化します。
| 記事タイプ | 主な読者の用件 | 推奨CTA配置と導線 |
|---|---|---|
| 比較記事 | 違いを知り最適を選びたい | 冒頭=結論/評価軸、本文中=料金・事例、末尾=相談/購入 |
| 事例記事 | 導入イメージと再現条件を知りたい | 本文中=同業種事例・機能詳細、末尾=デモ予約/問い合わせ |
| 料金記事 | 費用と条件を確かめたい | 冒頭=価格要約、本文中=内訳・比較、末尾=見積もり/相談 |
| 基礎ガイド | 始め方と全体像を知りたい | 本文中=チェックリストDL、末尾=比較・事例への導線 |
【配置ルール】
- 冒頭=不安の緩和、本文中=学習継続、末尾=意思決定→役割を分ける。
- CTAは1ページ1〜2種類に絞る→主目的を明確化して迷いを減らす。
- 章末には必ず「次に読む1本」を固定→比較→料金→事例へ導く。
タイトルと見出しのAB改善で継続最適化
継続最適化の要は、タイトルと見出しのA/B改善です。まずは高表示なのにクリック率(CTR)が低いページを抽出し、検索クエリの言い回しを自然に含めた案を複数作成します。
タイトルは「結論の具体化」「数字の明示」「読者の用件語」の三点を意識し、見出し直下に要約を置いて“何が分かるか”を先出しします。
本文は大きく変えず、タイトル・導入・H2の順で小さく検証すると、検索評価の安定を保ちながら改善できます。
効果判定は1〜2週間の同条件比較で行い、季節要因や媒体差を避けるため、期間と指標を固定します。CTR改善後に回遊とCVが伸びない場合は、章末導線とCTAを見直し、読者の温度感に合う文言へ調整します。
【ABの進め方】
- 対象の選定→「高表示×低CTR」「高閲覧×低CV」を優先。
- 案の作成→用件語・数字・結論を組み合わせたタイトルと要約を準備。
- 検証→期間・指標を固定し、他施策の影響を避けて比較。
- 反映→勝ち案を適用し、関連ページのアンカー文言も統一。
【検証のヒント】
- タイトルは語順を変えるだけでもCTRが改善することがある。
- 見出しは読者の質問文をそのまま採用→検索意図とのズレを縮小。
- 要約で結論を先出し→スクロール初動と滞在が安定しやすい。
まとめ
誰がどこから何を求めて来て、どこで離脱するかを可視化できれば、改善点は明確になります。
目標とKPIの設定→計測の整備→チャネル×クエリ確認→属性・行動の深掘り→導線とリライトの反復が基本です。まずはUTM設定と重要LPの計測漏れを点検し、優先1本から改善を始めましょう。