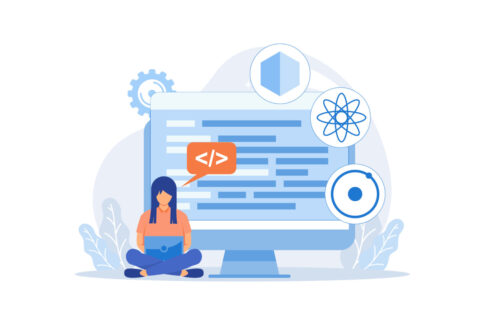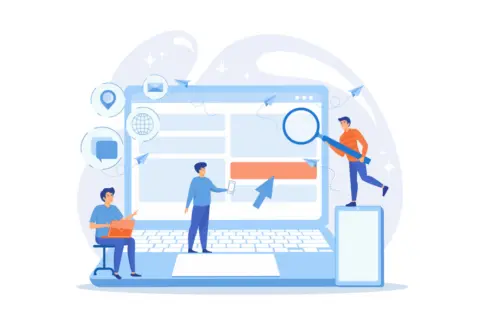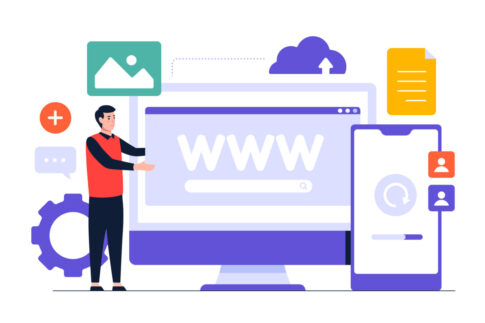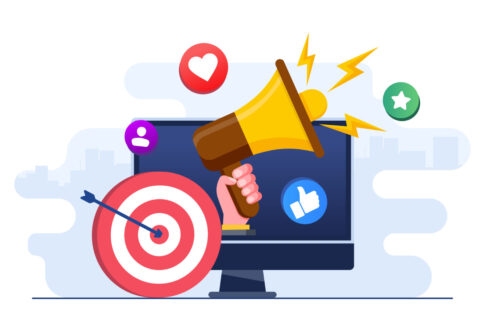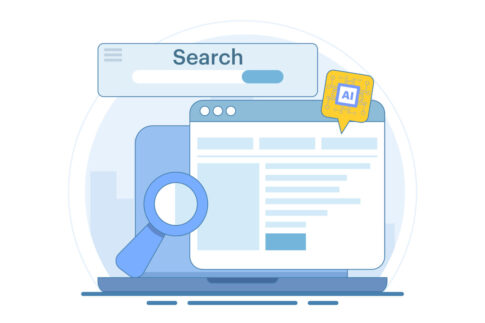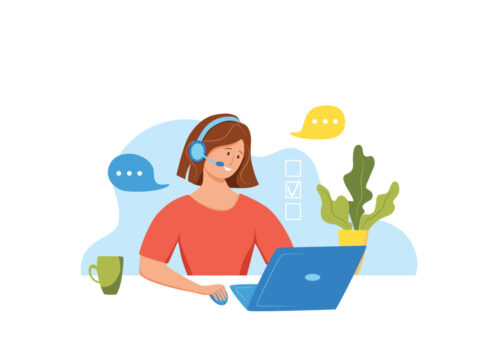ブログ集客とSNS集客、どちらを優先すべきか迷っていませんか。本文では、検索とタイムラインの違い、相性の良い目的・商材、入口→記事→LPの導線設計、再訪を増やす運用、GSC/GA4と各SNSのKPIまでを整理。
少人数でも再現しやすい「5つのコツ」で、両チャネルをムダなく連携させ成果を伸ばす方法を解説します。
目次
ブログ集客とSNS集客の違い

ブログ集客とSNS集客は、同じ「集客」でも仕組みと伸び方がまったく異なります。ブログは検索からの流入が中心で、読者が能動的に課題解決の答えを探す「プル型」。
コンテンツはURLと独自ドメインに紐づいて資産化し、内部リンクや比較表・FAQの整備で長期的に露出と信頼が積み上がります。
一方、SNSはタイムラインやレコメンドに乗る「プッシュ型」。拡散性が高く短期の到達が得意ですが、投稿寿命が短く継続露出には頻度と再利用設計が必要です。
計測面では、ブログはSearch ConsoleとGA4でクエリ→ページ→CVまでを追いやすく、SNSはクリックや再生、エンゲージメントを中心に見ます。
少人数運用では、ブログで意図一致の柱記事を用意し、SNSで要点を切り出して時差告知→再訪を促す構成が効率的です。
| 観点 | ブログ集客 | SNS集客 |
|---|---|---|
| 到達の仕組み | 検索意図に合致した結果に掲載(プル型) | タイムライン/レコメンドで露出(プッシュ型) |
| 効果の出方 | 中長期で安定的に積み上がる | 短期でピーク→減衰が早いことが多い |
| 資産性 | URL単位で評価・内部リンクで強化 | 投稿単位の瞬発力、再掲・再編集が鍵 |
| 計測 | クエリ/CTR/順位→CVを紐づけやすい | クリック/再生/保存→LP到達を重視 |
| 向く用途 | 比較・手順・FAQ・長文解説 | 告知・キャンペーン・事例の要点共有 |
【判断の目安】
- 初期から安定流入を作る→ブログの柱記事を整備
- 短期の露出や再訪を増やす→SNSで要点を切り出し時差配信
- ブログ=検索意図に答える「図書館」
- SNS=関心を広げる「掲示板」
到達経路の違い 検索とタイムライン
検索は、読者が「◯◯の比較」「◯◯のやり方」など明確な目的で調べる経路です。意図が具体的なため、比較表・手順・価格目安のような判断材料を提示するとCVまでつながりやすくなります。
タイムラインは、フォロー/フォロワー関係やレコメンドで偶発的に発見される経路です。興味喚起と再訪のきっかけづくりに強く、要点を短く、ビジュアルで伝えるほど反応が上がります。
ただし露出の寿命は短いため、同じテーマでも切り口を変えた再告知(要点→図表→導入後の変化)が有効です。
検索は「深く刺す」、SNSは「広く届く」。この違いを前提に、入口→記事→LPの最短ルートを全チャネルで共通化するとムダが減ります。
【設計ポイント】
- 検索向け:タイトル・導入・H2の語彙を揃え、章冒頭に結論→末尾に行動
- SNS向け:1投稿1メッセージ。見出し画像+短文+リンクで即行動を促す
- 両者の橋渡し:記事要点のカード化→SNSで配布→詳細はブログへ誘導
- ブログ:『◯◯の選び方|比較表とチェックリスト』
- SNS①:比較表の一部を画像化→「価格とサポートの違い」
- SNS②:導入後の変化を箇条書き→「導入までの流れ」
得意な目的と向いている商材
チャネルごとに“勝ちやすい目的”と“相性の良い商材”があります。ブログは、読者が情報を比較して決めたい場面に強く、BtoBサービス、専門性の高いツール、手順が重要な商材(会計/制作/リフォーム等)で成果が出やすいです。
SNSは、話題性・ビジュアル・時間性があるものと相性が良く、キャンペーンや季節商品、実物の見栄えが伝わるEC商材、イベントやセミナー告知で力を発揮します。
ローカル/ニッチでは、ブログで地域名×用途の柱を作り、SNSで現場写真・ビフォーアフター・お客様の声を短文で回すと信頼と再訪が両立します。
| 目的 | 向くチャネル | 商材/テーマ例 |
|---|---|---|
| 比較・意思決定 | ブログ中心(検索意図に合わせ構成) | BtoBツール、士業/制作の料金・工程、サブスク比較 |
| 認知・拡散 | SNS中心(短文+ビジュアル) | 新発売・セール・イベント、ECの新着/ランキング |
| 再訪・育成 | ブログ×SNS併用(更新通知・シリーズ化) | 連載HowTo、事例追加、テンプレ/資料更新 |
| ローカル集客 | ブログで柱、SNSで現場発信 | 地域名×サービス事例、来店導線の案内 |
【チャネル選択のコツ】
- 高単価・比較重視→ブログで深く、SNSは要点の再告知
- 低単価・衝動性→SNSで露出を増やし、LP直結の導線を強化
- 「ブログ=決める情報」「SNS=見つけるきっかけ」の役割分担
- 全チャネルでCTA文言と行き先を統一(迷いをなくす)
ブログ×SNSの連携の作り方

ブログとSNSは「別々に頑張る」よりも、役割を分けて一連の体験として設計すると成果が伸びます。
基本は、SNSで関心を生み(認知)→ブログ記事で理解と比較を進め(検討)→LPで行動を完了する(成約)という流れを、どの投稿・記事から入っても同じ構造でたどれるようにすることです。
まず、柱記事(入門/比較/手順)をブログ側に用意し、各記事の冒頭に要点、末尾に「次の一歩(関連記事→LP/問い合わせ)」を固定します。
次に、SNSではその要点をカード化(見出し画像+短文+リンク)して、同一テーマでも切り口を変えつつ複数回展開します。
最後に、UTMなどで起点を判別できるようリンクを統一し、GSC/GA4や各SNSのアナリティクスで「どの入口→どの記事→どのLP」が機能しているかを週次で確認。
導線は“最短・一貫・逆走可能(記事↔LP↔関連記事)”を合言葉に、迷いを減らす配置にします。
| フェーズ | ブログ×SNSの役割 | 実装のポイント |
|---|---|---|
| 認知 | SNSで要点を短文と画像で告知 | 1投稿1メッセージ/CTAと行き先を統一 |
| 検討 | ブログ記事で比較・手順・FAQを整理 | 章冒頭に結論→末尾に行動/内部リンクで最短化 |
| 成約 | LP/フォームで完了 | CTA3点配置(上部・中部・末尾)/必須は3項目目安 |
【連携チェック】
- 全チャネルでCTA文言と行き先が一致しているか
- 記事末の「まとめ→CTA→関連3本」が固定されているか
入口から成約までの導線 ランディング→記事→LP
理想の流れは、SNSランディング(投稿クリック先)→ブログ記事(理解と比較)→LP/フォーム(行動)の3段で統一します。
まずランディングは、SNS投稿の約束と記事冒頭の内容を一致させることが最優先です。見出し画像の文言と、記事のH1/導入で同じメッセージを繰り返し、冒頭に要点(誰に/何が/なぜ良い)を短文で提示します。
記事本文は、結論→理由→具体(比較表・手順・事例・FAQ)→行動の順に整え、章末には必ず「次の一歩(比較→個別→LP、または問い合わせ)」を置きます。
LPは、上部・中部・末尾の3点にCTAを固定し、ボタン直下に補助文(所要時間・費用の有無・返信目安)を添えて不安を下げます。モバイルでは、1画面1CTAの密度、フォント/行間、タップ領域、画像の読み込み速度を優先的に点検してください。
| 場所 | 目的 | 配置・文言のコツ |
|---|---|---|
| SNSランディング | 興味喚起→離脱防止 | 見出し画像=記事H1の要約/導入100〜200字で約束を再提示 |
| 記事本文 | 理解・比較→意思決定 | 章冒に結論、章末に行動/比較は評価軸を先出しで表に |
| LP/フォーム | 行動完了 | CTA3点固定/必須3項目目安/自動返信で次の流れを明示 |
【導線最短化の手順】
- 入口記事を特定→タイトル・導入とSNS文面を一致
- 関連記事の並びを「柱→比較/事例→LP」に再編
- LPのCTA文言に利益+所要時間を追記(例:最短10分・無料)
再訪を増やす方法 更新通知とシリーズ化
再訪は“積み上がる成果”の源泉です。最も効果的なのは、更新通知の仕組み(SNS告知・メール/ニュースレター・RSS/通知)と、続きが気になるシリーズ化を組み合わせる方法です。
更新通知は同一記事でも切り口を変えて複数回行います。公開直後は「要点の抜粋」、数日後に「比較表や図の見どころ」、翌週に「導入後に得られる変化」。
各告知で同じCTAと行き先を用い、カード化した要点画像を再利用します。シリーズ化は、柱テーマを分割して「入門→比較→選び方→導入手順→失敗回避→チェックリスト」の順で連載し、各回の冒頭に前回サマリー、末尾に次回予告と登録導線(通知/メール)を固定します。
これにより、アルゴリズムに依存しない定期的な再訪が生まれ、ブログ側の回遊とLP到達率が安定します。
| 施策 | 実装ポイント | 効果が出やすい理由 |
|---|---|---|
| 更新通知 | 切り口違いで時差告知/CTAと行き先を統一 | 寿命の短い投稿でも総露出が増え再訪が増加 |
| シリーズ化 | 各回の冒頭に前回リンク/末尾に次回予告 | 次回の期待値が高まり連続視聴ならぬ連続閲覧を促進 |
| 資産化コンテンツ | テンプレ・チェックリストをDL導線付きで配置 | 「手元に置きたい」価値が再訪と共有を生む |
【今日できる再訪施策】
- 人気記事1本を選び、要点・表・変化の3パターンで時差告知
- 柱テーマを5回連載に分割→前回/次回リンクと登録導線を固定
- 同一テーマは「切り口を変えて」3回伝える
- 連載は「前回サマリー」と「次回予告」をセットで
コンテンツの分担と作り方

ブログとSNSは「同じ内容をそのまま流用」ではなく、役割と表現を分けて作ると成果が伸びます。ブログは検索意図に沿って情報を深く整理し、比較・手順・FAQのように“判断材料”を提示する場所です。
見出しは要約文に統一し、章冒に結論、章末に行動(CTA)を固定して、内部リンクで次の一歩へ最短移動できるようにします。一方のSNSは、関心喚起と再訪の起点です。
要点を短文と画像で切り出し、同一テーマでも切り口を変えて複数回配信します。重要なのは、両者をつなぐ導線の一貫性です。
SNS投稿の見出し画像・本文・リンク先記事のタイトル/導入で同じ約束を繰り返し、記事側はLP/フォームへ誘導する導線を「上部・中部・末尾」の3点に固定します。下表のように、役割・書き方・KPIを分担しておくと、少人数でも制作判断がシンプルになります。
| 観点 | ブログ(深く伝える) | SNS(広く届ける) |
|---|---|---|
| 役割 | 比較・手順・FAQで意思決定を後押し | 要点とベネフィットを短文と画像で告知 |
| 書き方 | H2に結論→H3で理由/具体→章末にCTA | 1投稿1メッセージ/見出し画像+リンク |
| KPI | オーガニック流入・CTR・CV/CVR | クリック・保存・再訪・LP到達 |
【制作時のチェック】
- 同一テーマでも“ブログ=判断材料、SNS=興味喚起”を徹底
- CTA文言と行き先URLは全チャネルで統一→迷いを削減
ブログ記事の型 比較・手順・FAQ
ブログでは、検索意図に合わせて記事タイプをあらかじめ決め、見出しと要素をテンプレ化します。比較は「判断基準→横並び表→ケース別のおすすめ」の順で、最初に評価軸(価格・機能・サポート・導入難易度など)を開示します。手
順は「結論→理由→手順→チェック」の順で、1操作1文に短文化し、図やスクリーンショットは最小限の文字で補足します。
FAQは「申し込み前の不安」に先回りし、価格・期間・対応範囲・解約・サポートを具体的に記載。
いずれも章末に“次の一歩”を固定し、比較→個別レビュー→LP、手順→チェックリストDL→問い合わせ、FAQ→関連事例→相談のように、行動につながる導線を最短にします。
| 記事タイプ | 目的 | 主要見出し/要素の例 |
|---|---|---|
| 比較 | 選び方を明確化し最適案へ誘導 | 判断基準の提示→横並び表→ケース別の向き不向き→おすすめ |
| 手順 | 実装の不安を解消し再現性を担保 | 結論→理由→手順(箇条書き)→よくあるつまずき→チェック |
| FAQ | 申込前の疑問を解消し離脱を防止 | 価格/期間/範囲/解約/サポート→各回答は具体例と時点を明記 |
【運用のコツ】
- H2は要約文、H3は理由や具体を補足→読み飛ばしでも理解可能に
- 比較表は同単位・同語順・脚注で条件を明示→恣意性を排除
- 章末に「まとめ→CTA→関連3本」を固定→回遊と成約を両立
SNS投稿の型 見出し画像・短文・ハッシュタグ
SNSは「一瞬で伝わること」が最優先です。まず見出し画像(カード)でテーマとベネフィットを短く提示し、本文は1投稿1メッセージで要点→行動(リンク/保存/予約など)の順に構成します。
文章は冒頭3行で結論、以降は補足と箇条書きで可読性を高めます。ハッシュタグは“テーマの主語”と“検索される語”を中心に3〜6個に絞り、乱用は避けます。
再訪を増やすため、同じ記事でも切り口を変えた時差告知(要点→図表の見どころ→導入後の変化)を行い、毎回同じCTAと行き先を使って測定を揃えます。
画像や動画は縦長/正方形などプラットフォームに最適化し、字幕・テロップで無音でも伝わる工夫をします。
| 要素 | 作り方のポイント | 例 |
|---|---|---|
| 見出し画像 | 大きな文字で1メッセージ/ロゴや顔は小さめ | 「◯◯の選び方 3つの基準」 |
| 本文(短文) | 結論先出し→箇条書き→CTA/1投稿1リンク | 「結論:◯◯が最適。理由は…→詳しくは記事へ」 |
| ハッシュタグ | 主語+検索される語を3〜6個/乱用しない | #ブログ集客 #SNS集客 #比較 #チェックリスト |
- 要点カード+短文+リンク(保存推奨の一言を添える)
- 図表の抜粋+補足2行+リンク(比較の見どころを提示)
- 同一テーマは週内に切り口違いで3回配信→総露出と再訪を底上げ
- UTMで起点を固定→GSC/GA4とSNSアナリティクスで比較
KPIと計測の見方
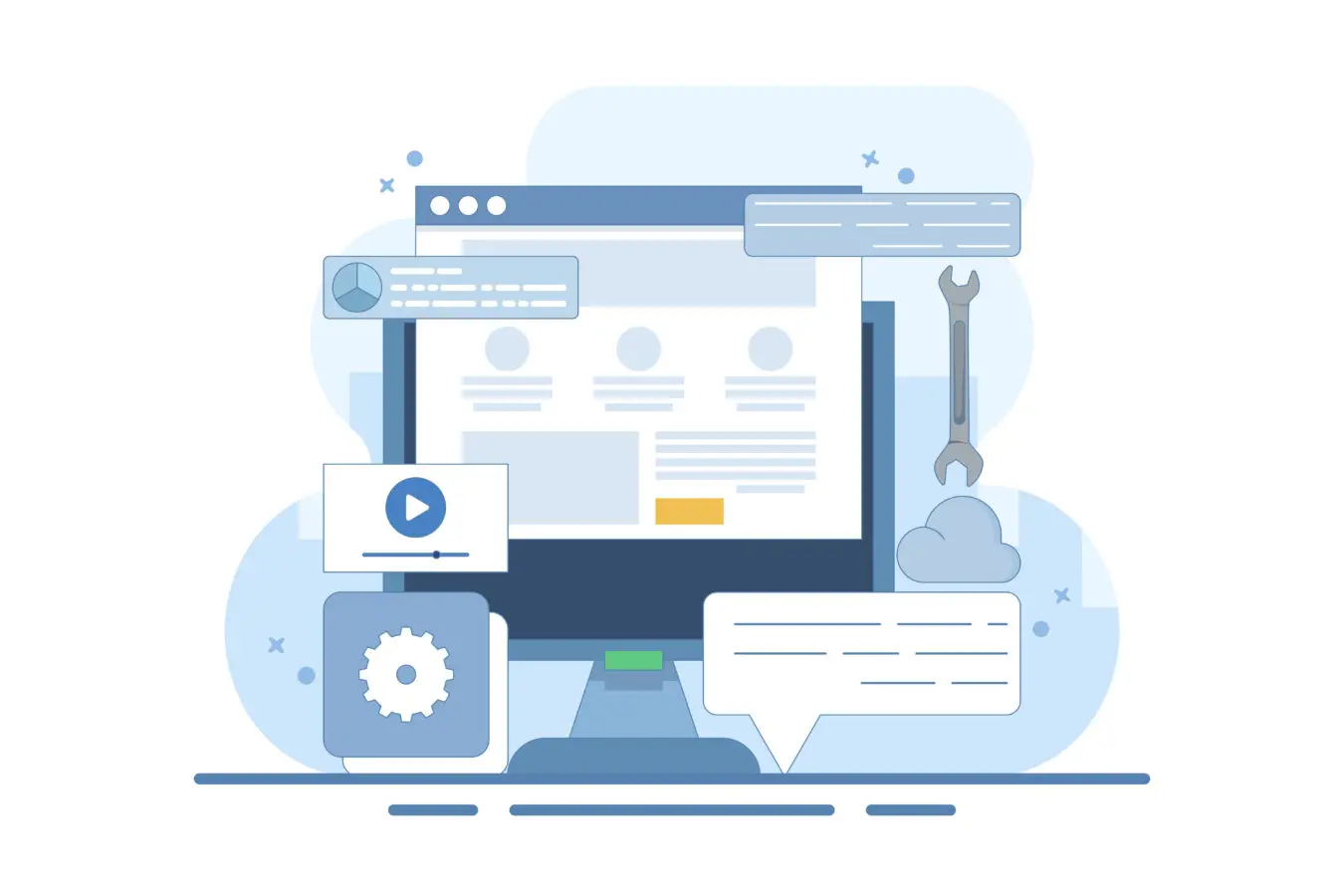 KPIは「チャネルの役割」に合わせて分けて管理すると判断が早くなります。ブログは検索意図に合う読者を集め、記事で比較・手順・FAQを提示し、LP/フォームで成約させる流れです。
KPIは「チャネルの役割」に合わせて分けて管理すると判断が早くなります。ブログは検索意図に合う読者を集め、記事で比較・手順・FAQを提示し、LP/フォームで成約させる流れです。
よって、表示回数・CTR・平均掲載順位・オーガニック流入・CV/CVRが主要KPIになります。SNSは関心喚起と再訪づくりが役割で、リーチ・エンゲージメント率・リンクCTR・保存/シェア・動画再生完了率などが重要です。
計測は「同じ条件で比較できること」が最優先です。期間・デバイス・地域を固定し、週次で入口ページ→クエリ→導線→CVの順に確認します。
施策は一度に一要素だけ変更し、2〜4週間の差分で効果を判定すると因果が切り分けやすくなります。最後に、チャネル別のKPIを混ぜずにダッシュボードを分け、週次(小さく速く)・月次(統合/導線棚卸し)で運用すると継続改善が安定します。
| 領域 | 主なKPI | 見る観点 |
|---|---|---|
| ブログ(SEO) | 表示回数・CTR・平均掲載順位・オーガニック流入・CV/CVR | 需要と可視性→記事の具体化→LP到達率→CVの一貫性 |
| SNS | リーチ・エンゲージメント率・リンクCTR・保存/シェア・再訪 | 切り口の良否→再訪の増減→ブログへの送客品質 |
【運用の型】
- 週次→入口ページと直近投稿を点検→一手だけ修正
- 月次→重複URLの統合・導線の再編→AB結果の整理
GSCとGA4で見る指標
Search Console(GSC)は「検索での見え方」、GA4は「サイト内の動き」を確認する道具です。GSCでは期間を直近28日、デバイスはモバイルで固定し、ページ→クエリの順で表示回数・CTR・平均掲載順位を見ます。
表示が多いのにCTRが低いページは、タイトル/導入の具体性不足や約束の不一致が疑われます。4〜10位に滞留しているページは、比較・価格目安・手順・FAQなど“具体”の不足が原因になりがちです。
GA4ではコンバージョン(CV)とCVR、入口ページのエンゲージメント、CTAクリック、フォーム到達/完了を確認し、ボトルネック(冒頭の弱さ・CTA位置・入力項目過多)を特定します。
施策は「タイトル/導入」「見出し/本文」「内部リンク」「CTA/フォーム」など層ごとに一要素だけ変え、2〜4週間で差分比較すると因果が明瞭になります。
| KPI | 確認ビュー | 打ち手の例 |
|---|---|---|
| CTR | GSC|ページ→クエリ | タイトル具体化・導入で要点前出し・重複語の削除 |
| 平均掲載順位 | GSC|検索パフォーマンス | 比較表/価格/手順/FAQの追加・内部リンク強化 |
| オーガニック流入 | GA4|ユーザー獲得 | 柱→派生の公開順序の最適化・古い記事の改稿 |
| CV/CVR | GA4|コンバージョン/経路探索 | CTA文言/位置のAB・フォーム必須3項目化 |
| 離脱箇所 | GA4|ページのエンゲージメント | 章冒の結論強化・図表追加・内部リンク再配置 |
- 期間・デバイス・地域を毎回固定→比較のブレを排除
- 一度に多要素を変更しない→原因が不明確になる
各SNSアナリティクスで見る指標
SNSは「見つけてもらう→興味を持つ→ブログへ来る→再訪する」までを段階で見ます。
共通して確認すべきは、リーチ(届けた人数)、エンゲージメント率(いいね/コメント/保存/シェア等)、リンクCTR(投稿→ブログ)、保存/シェア数(再訪と波及の見込み)、動画ならフル視聴率や前半離脱率です。
画像・短文主体のプラットフォームでは、要点カード+短文の初動(最初の1時間/1日)を重視し、伸びた切り口は時差・曜日違いで再投下します。
動画主体では、最初の数秒でのフック率、平均視聴時間、最後まで見た割合、字幕の有無を確認します。いずれもUTMで起点を固定し、ブログ側のLP到達率・CVRとつなげて評価します。
| 段階 | 見る指標 | 改善のヒント |
|---|---|---|
| 発見 | リーチ・表示回数・インプレッション | 見出し画像の文字を大きく・主語を明確化 |
| 関心 | エンゲージメント率・保存/シェア | 要点の短文化・図表抜粋・比較の一部公開 |
| 送客 | リンクCTR・クリック数 | 1投稿1リンク・CTAの具体化・リンク位置の統一 |
| 育成 | 再訪率・フォロー増・ニュースレター登録 | シリーズ化・更新通知・固定投稿/ハイライト整備 |
| 動画 | フック率・平均視聴時間・完了率 | 冒頭に結論→字幕追加→長さの最適化 |
【運用のコツ】
- 同一テーマを切り口違いで3回配信→総露出と再訪を底上げ
- 保存とシェアが伸びた投稿の切り口を、ブログ側のH2/H3に反映
- リンクにUTMを必ず付与→起点別にLP到達率とCVRを比較
- SNSのトップ固定/ハイライトに「はじめて読む記事」を設置
運用の進め方と注意点

ブログとSNSの運用は、思いつきではなく「同じ手順を同じ条件で繰り返す」ことで成果が安定します。まず、チャネル別KPI(例:SEOは表示回数・CTR・CV、SNSはリーチ・リンクCTR・再訪)を分けて管理し、週次は小さく一手、月次は構造の見直しという役割を決めます。
作業は「計測→仮説→一手修正→比較→横展開」の順で回し、変更点と狙い指標は必ず記録します。
制作物はテンプレ化(H2に結論、H3に理由/具体、章末に行動)し、CTAは上部・中部・末尾の3点固定で迷いをなくします。
さらに、ポリシー表示や出典・時点の明記、画像・ロゴの権利確認などの“守り”を日常運用に組み込みます。下表の型をベースに、少人数でも回せる週間/ 月間リズムへ落とし込みましょう。
| 頻度 | 主なタスク | 成果物/チェック |
|---|---|---|
| 週次 | GSC/GA4点検→一手修正(タイトル/導入/CTA/内部リンクのいずれか)→SNS時差告知 | 変更メモ・比較スクリーンショット・次週の仮説 |
| 月次 | 重複URLの統合・導線再編・LP検証/AB整理・編集カレンダー更新 | 統合リスト・導線マップ・来月の制作計画 |
| 随時 | 価格/仕様/法令等の差し替え・広告表記/出典の修正 | 更新履歴(更新日/変更箇所/要約) |
- KPI・期間・デバイスを固定して比較(週次は直近28日・モバイル推奨)
- 一度に一要素だけ変更→2〜4週間で差分確認
週次と月次のルーチン
週次は「狭く速く」。入口ページ(上位×流入大)を対象に、GSCでページ→クエリを確認し、表示多×CTR低・4〜10位停滞・直近下落のいずれかに該当するページへ一手だけ施します。
例:タイトルの具体化、導入で要点の前出し、比較表/FAQの追加、章末の“次の一歩”固定、CTA文言の利益+所要時間明記など。GA4では入口ページのエンゲージメント、CTAクリック、フォーム到達/完了を見て、ボトルネック(冒頭の弱さ、CTA位置、入力項目過多)を特定します。
SNSは同一テーマを切り口違いで3回配信(要点→図表→導入後の変化)し、UTMで起点を固定します。
月次は「広く深く」。重複URLの統合(同意図は一意図一記事へ)、内部リンクの再編(柱→比較/事例→LPの最短化)、LPのAB結果整理、来月の編集カレンダー更新(柱1本+派生3本+再告知計画)を行います。作業後は変更履歴を残し、OG画像・メタ説明・表の単位や脚注も同時に整合を取ります。
| タイミング | やること | 指標/合格ラインの目安 |
|---|---|---|
| 週次 | ページ→クエリ点検→一手修正→時差告知 | CTR上昇・LP到達率改善・フォーム完了率の微増 |
| 月次 | 統合/改稿・導線再編・LP検証/AB整理 | 4〜10位→3位以内の比率増・重複URLの削減 |
- 一度に多要素を変更→因果が不明に。要素は一つに絞る
- KPI混在(SEOとSNSを同指標で評価)→チャネル別に分離
表記と権利のルール
成果を伸ばすうえで「信頼の担保」は欠かせません。広告/PR/アフィリエイトを含む場合は、読者が最初に気づける位置(タイトル近接・導入直下・リンク付近)に明示します。
ランキングや比較では、評価軸や収集方法を簡潔に開示し、根拠のない「No.1」「最安」といった表現は避けます。
価格やキャンペーン等の可変情報には時点と条件を添え、変更があれば本文を差し替え、ページ末に更新履歴(更新日/変更箇所/要約)を残します。
画像・ロゴ・スクリーンショットは権利と出典を確認し、引用は主従関係と区分、出典明記を満たす形で行います。個人情報を扱うフォームでは、目的・取得項目・保管・問い合わせ窓口をプライバシーポリシーで示し、同意チェックとリンクを近接配置します。
| 領域 | 必須の表示/ルール | 実装ポイント |
|---|---|---|
| 広告表記 | 「広告/PR/アフィリエイトを含みます」を冒頭やリンク近接で明示 | フォントサイズを十分に・リンク直前にも再掲 |
| 比較/ランキング | 評価軸・データ収集方法・加点基準を開示 | 表の単位/語順統一・脚注で条件を記載 |
| 著作権/引用 | 出典明記・区分・改変不可・主従関係を順守 | 画像/ロゴの権利確認・転載ではなく要約中心に |
| 個人情報 | 目的/項目/保管/第三者提供/窓口の明示 | 同意チェックとポリシーリンクをフォーム近接に配置 |
- 広告表記は冒頭とリンク付近にあるか
- 比較表は条件と時点を脚注で明記しているか
まとめ
結論は「役割分担+導線固定」。新規はブログ、拡散はSNS、成約はLP/フォームに任せ、入口→記事→LPの最短ルートを全ページで統一します。
再訪は更新通知とシリーズ化で育成。KPIはSEOとSNSで分けて管理し、週次で一手ずつ改善。まずは柱記事の改稿、SNSで要点・表・事例の3回告知、CTAの3点配置から着手しましょう。