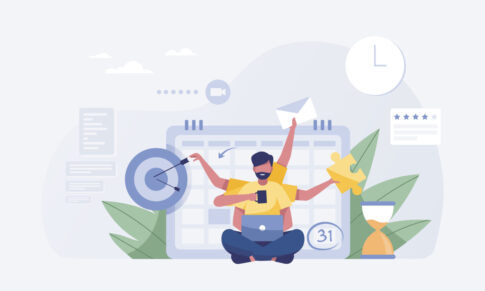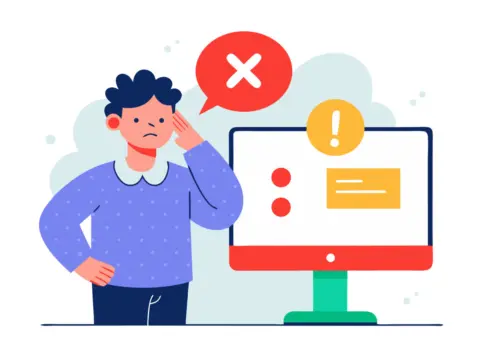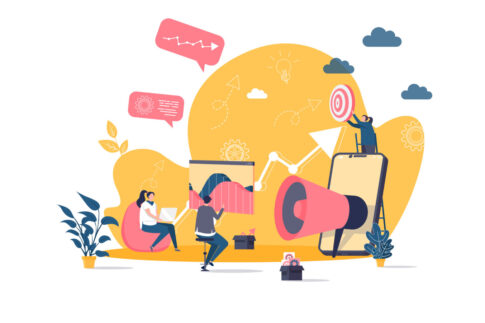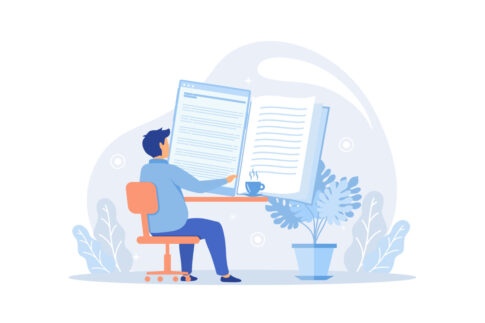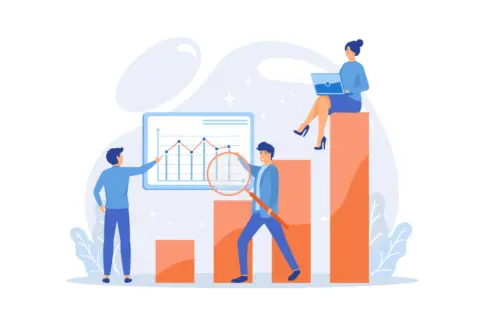Web集客コンサルの費用相場・料金体系・選び方を一気に理解。依頼できる支援範囲、見積の見方、危ない提案の見分け方、契約チェックまで具体例で解説します。
SEO・広告・SNS・計測の進め方とKPI設計も整理し、初めてでも使える手順書とチェックリストを収録。読むだけで費用対効果の判断軸が手に入ります。
Web集客コンサルの基本と役割

Web集客コンサルは、現状診断→戦略設計→実行支援→計測改善までを横断し、限られた予算でも成果につながる意思決定を支える専門家です。
具体的には、アクセスやコンバージョンのデータを整理し、課題(流入不足・導線の弱さ・測定不備など)を見える化します。
そのうえで、SEO・広告・SNS・メール/CRM・サイト改善のどこに投資すべきかを優先順位付きで提案し、KPIとスケジュールを設定します。
実行段階では、社内/外注の体制に合わせてタスク化し、制作物のレビュー、入稿やタグ設定の点検、レポートの読み解きまで並走します。
たとえば「ECの新商品が伸びない」場合は、検索語の意図ずれやLPの不安要素、在庫やレビュー数の条件を点検し、短期施策(広告・LP修正)と中期施策(SEO・UGC)を組み合わせて改善計画を作ります。役割を理解すると、依頼範囲と期待値が明確になり、費用対効果の判断がしやすくなります。
【よくある悩み】
- 何にいくら使えば良いか分からない→優先順位の設計ができていない
- レポートを見ても次の一手が決まらない→KPIと改善仮説が未定義
- 外注が増えたが成果が横ばい→チャネル連動と責任範囲が曖昧
| 主な役割 | 典型アウトプット | 期待できる効果 |
|---|---|---|
| 診断 | 現状分析、ボトルネック特定 | 無駄な施策の停止、優先課題の明確化 |
| 戦略 | KPI設計、予算配分、ロードマップ | 短期/中期の打ち手が決まり投資が集中 |
| 実行支援 | 制作/運用レビュー、タグ・計測整備 | 品質の底上げ、実装ミスの削減 |
| 改善 | レポート解釈、AB計画、再配分 | 学習速度の向上、継続的なCV増加 |
- 判断軸が明確になりムダな出費が減る
- 社内メンバーの学習が進み自走化に近づく
- 成果が出た施策へ素早く再配分できる
依頼できる支援領域の全体像を丁寧に整理
支援領域は広く、戦略立案だけでなく「手を動かす前提作り」から「日々の運用設計」まで含まれます。たとえば戦略では、目的(売上・リード・来店)と主要KPI(CVR・CPA・LTVなど)を決め、チャネルごとの役割分担を設計します。
実行面では、SEOのキーワード/構成案、広告の入札・除外語、SNSの配信カレンダー、LPの改善点、計測タグの設計など具体タスクに落とし込みます。
運用では、週次のレポートを「次の行動」に翻訳し、勝ちパターンの見極めと撤退判断を行います。
内製化を目指す場合は、運用手順書やチェックリスト、教育の場づくり(勉強会/レビュー会)もコンサルの領域です。全体像を把握しておくと、どこまでを依頼し、どこからを自社で担うかが決めやすくなります。
| 領域 | 主な支援内容 | 成果イメージ |
|---|---|---|
| 戦略/設計 | KPI・予算配分・チャネル役割の定義 | 投資の集中と意思決定の迅速化 |
| SEO/コンテンツ | キーワード設計、構成案、内部リンク計画 | 指名外流入の増加、CV導線の整備 |
| 広告運用 | 入札/除外語、広告文AB、入稿レビュー | CPA改善、テストの高速化 |
| SNS/CRM | 配信カレンダー、UGC収集、セグメント配信 | リピート率向上、指名検索の増加 |
| 計測/改善 | タグ設計、ダッシュボード、AB設計 | 学習の蓄積、改善の自動化に近づく |
【依頼前に決めておくこと】
- 主要CV(購入・資料DL・予約)と許容CPAの目安
- 社内で担える作業範囲(入稿・デザイン・開発)の線引き
- レポートの頻度と形式(週次で改善点→次週の実装)
- 依頼範囲は優先課題に絞り、段階的に拡張する
- 「なんでもお願いします」では責任と成果が曖昧になる
代行・制作会社との違いをやさしく解説
コンサルは「設計と意思決定の支援」が中心で、実務を大量にこなす「代行」やサイト・LPを作る「制作会社」と役割が異なります。
代行は手数を増やして運用量を担保でき、制作会社は見た目や構造の品質を確保できます。一方で、どのチャネルに投資するか、どの順で改善するかといった上流の判断やKPI管理は、コンサルが得意とする領域です。
実務では、コンサルが設計→代行/制作が実装→コンサルが結果を解釈して次の手を決める、という分担がスムーズです。
| 項目 | コンサル | 代行/制作会社 |
|---|---|---|
| 中心業務 | 戦略設計、KPI管理、優先順位決定 | 運用作業、入稿/制作、更新 |
| 成果責任 | 意思決定の質と投資配分 | 指定範囲の実装品質と納期 |
| 向いている状況 | 予算配分や施策選定に迷っている | やることは決まっており手が足りない |
| 料金の傾向 | 月額顧問/伴走、スポット診断 | 媒体手数料/時間単価/制作見積 |
【使い分けの例】
- 新規事業の立ち上げ→コンサルで設計→制作/代行に落とす
- 既存運用の量が不足→代行で入稿や配信量を確保
- LPが弱い→制作会社で改善→コンサルがAB計画を設計
- 「◯日で必ず売上◯倍」などは要注意→前提条件の確認が必須
- 作業量=成果ではない→KPIと因果の説明があるか確認
相談から契約までの一般的な進め方の流れ
相談から契約までは、要件整理→候補選定→初回相談→提案/見積→比較検討→トライアル→契約の順で進めるとスムーズです。
まず、目的・KPI・予算幅・現状の課題を一枚に整理します。次に、候補は3社程度に絞り、初回相談で実績と考え方、コミュニケーションの相性を確かめます。
提案/見積では支援範囲・成果物・レポート頻度・担当体制・契約期間を明確にし、比較は「安さ」ではなく「仮説の質」と「再現性」で行います。迷う場合は小規模トライアルで検証し、良ければ本契約へ進みます。
- 要件メモ作成→目的・KPI・予算・課題・体制を整理
- 候補選定→サイト/事例/発信内容から3社に絞る
- 初回相談→課題の捉え方と進め方の相性を確認
- 提案/見積→範囲・成果物・体制・頻度を明文化
- 比較検討→仮説の妥当性と再現手順の明確さを重視
- 小規模トライアル→レポートと改善提案の質を評価
- 契約→守秘・解約・成果物権利を最終確認
| 段階 | 目的 | チェック項目 |
|---|---|---|
| 要件整理 | 期待値の言語化 | 主要CV/許容CPA、担当範囲、期限の明確化 |
| 初回相談 | 仮説力と相性の確認 | 課題の特定力、説明の分かりやすさ、宿題の質 |
| 提案/見積 | 再現手順の確認 | KPI設計、ロードマップ、レポート形式 |
| トライアル | 実務遂行力の検証 | 改善提案の具体性、実装速度、柔軟性 |
- 支援範囲と成果物が具体か→曖昧語(サポート一式)は避ける
- 週次で何を決めるか→「次の一手」まで落ちているか
- 撤退基準と更新条件→成果が出ない場合の合意があるか
費用相場と料金体系の基礎知識
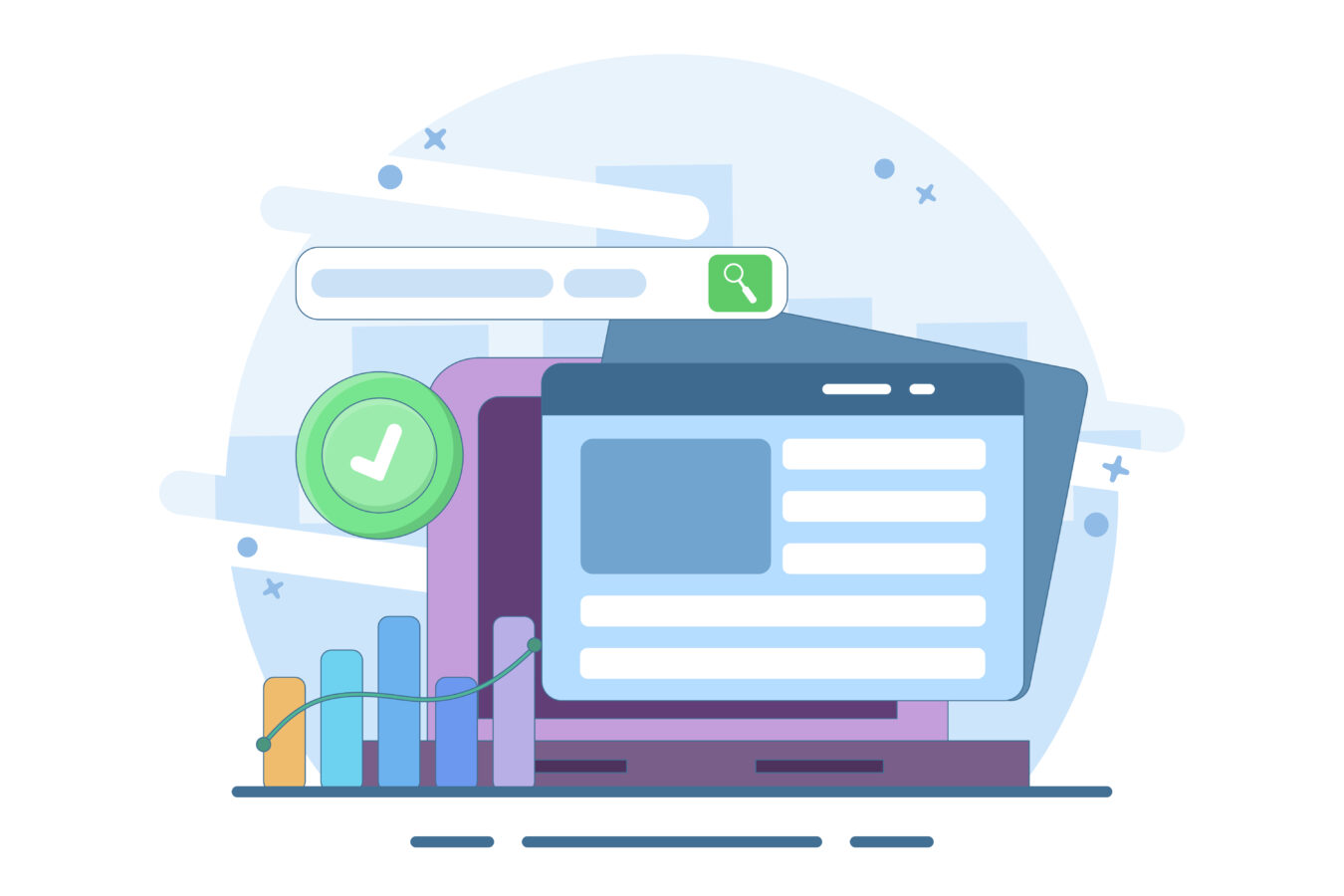
Web集客コンサルの料金は、契約形態(スポット診断・月額顧問・伴走支援)と、支援の範囲・頻度・チャネル数で大きく変わります。
一般的には、課題特定だけの短期支援よりも、実装と改善まで含めた継続支援のほうが工数が増え、月額が高くなる傾向です。
費用の見方は「何に何時間かけるか」「どこまで責任を持つか」を明らかにすることが基本です。たとえば、分析や計測設計、会議の回数、広告やSEOの設計、LPや記事のレビュー、運用ルール作成など、見積に含まれる作業の粒度で値段は変わります。
予算が限られる場合は、短期のスポット診断で優先順位とKPIを固め、次に月額の小さな枠で「必須タスクだけ」回すとムダが出にくくなります。
下表は、よくある契約類型の目安と向いているケースの整理です。
| 契約類型 | 料金帯の目安 | 向いているケース |
|---|---|---|
| スポット診断 | 単発10〜30万円/回 | 課題の棚卸し・KPI設計を急ぎたい |
| 月額顧問 | 15〜50万円/月 | 週次レビューと改善方針の伴走が必要 |
| 伴走支援 | 30〜100万円/月 | 設計+実装レビュー+運用設計まで一体 |
- 範囲を明文化→「やること」より「やらないこと」を先に決める
- 会議は決定の場に一本化→報告はダッシュボードで代替
- 短期の勝ち筋→中長期の資産化(SEO等)へ段階的に拡張
月額相場と費用内訳の目安を具体的に整理
月額費用は「企画・分析」「定例会」「施策設計(SEO/広告/SNS)」「レビュー・改善」「計測・ダッシュボード」の配分で構成されます。
金額だけで比較せず、内訳の比率と成果に直結する作業がどこまで含まれるかを確認しましょう。たとえば、月30万円のプランでも、会議とレポートに偏ると改善の速度は落ちます。
逆に、仮説出し→小さなAB→翌週反映のサイクルが回る配分なら、少額でも学習が前に進みます。以下は代表的な内訳の目安です。
【よくある内訳】
- 企画・分析(KPI/仮説)→全体の20〜30%
- 定例会(週次/隔週)→10〜20%
- 施策設計(SEO/広告/SNS)→30〜40%
- レビュー・改善(LP/記事/入稿)→20〜30%
- 計測・ダッシュボード整備→10〜20%
| 項目 | 30万円プランの配分例 | 50万円プランの配分例 |
|---|---|---|
| 企画・分析 | 6〜9万円(仮説出し/優先順位) | 10〜15万円(深掘り分析/ロードマップ) |
| 施策設計 | 9〜12万円(SEO構成/広告設計) | 15〜20万円(多チャネル連動の設計) |
| レビュー・改善 | 6〜9万円(LP/記事/入稿レビュー) | 10〜12万円(改善ABの設計/評価) |
| 定例・計測 | 3〜6万円(週次会/数値管理) | 5〜8万円(ダッシュボード拡張) |
ここで重要なのは、時間の使い道が「次の一手」に変換される設計になっているかです。会議での報告に時間を使いすぎず、目標CPAやCVR、LTVの更新に直結する作業を優先しましょう。
ダッシュボードは「見る指標を絞る」「毎週の改善案を1つは実装する」運用にすると、少額でも成果が積み上がります。
スポット・顧問・伴走の違いを丁寧に比較
スポット診断は短期で課題を特定し、優先順位とKPIの叩き台を作るのに向いています。月額顧問は週次の意思決定を支え、施策の質とスピードを一定に保つ役割があります。
伴走支援は設計に加えて実装レビューや運用ルール策定まで踏み込み、学習サイクルを強く回すのが特徴です。自社の体制やスピードに合わせて使い分けると、費用対効果が安定します。
| 形態 | 主な中身 | 向いている状況 |
|---|---|---|
| スポット診断 | 分析/KPI設計/改善テーマの提示 | まず現状把握→優先課題を決めたい |
| 月額顧問 | 週次レビュー/改善指示/実装チェック | 内製や外注を動かす司令塔が必要 |
| 伴走支援 | 設計+実装レビュー+運用ルール化 | 短期で勝ち筋を作り中長期に展開 |
- 「◯日で必ず成果」など過度な断定や保証
- 範囲が曖昧(サポート一式)で成果物が不明
- 会議/報告比率が高く、改善実装の時間が少ない
- 成果連動のみで基本料ゼロ(判断が広告偏重になりやすい)
選び方のポイントは、ミッション(何をいつまでに改善するか)と撤退基準(どの指標がどの水準なら見直すか)を最初に合意することです。これがないと、良し悪しの判断が感覚に寄り、コストだけが積み上がります。
見積書と契約時の重要チェック項目一覧
見積と契約では、「範囲・成果物・頻度・体制・権利・期間・費用」の7点を具体化することが肝心です。見積は金額だけでなく、タスクと時間配分、期待するアウトプット例(KPI設計書、改善リスト、AB計画、ダッシュボード定義)まで書かれているかを確認します。
契約では、守秘義務とデータ/成果物の権利、途中解約やスコープ変更時の費用、遅延や対応期限の取り決めが明文化されていると安心です。初回は小さめの期間で開始し、更新時に範囲を広げる方式だとリスクを抑えられます。
| 項目 | 確認内容 | 見落としリスク |
|---|---|---|
| 支援範囲 | やること/やらないことを明記 | 責任の分散→成果が曖昧になる |
| 成果物 | 形式と納品タイミングを明記 | 「報告のみ」で改善が進まない |
| 頻度/体制 | 週次/隔週会議・担当者・連絡手段 | 意思決定が遅れ学習が停滞 |
| 権利/データ | ダッシュボード/帳票の帰属と閲覧権 | 契約終了後に運用不可 |
| 期間/解約 | 初回期間・更新条件・途中解約ルール | 成果が出ないのに固定費が継続 |
| 費用/支払 | 基本料・実費・支払サイト・遅延規定 | 追加費用の発生で想定超過 |
【契約前の最終チェック】
- KPIと撤退基準を合意→判断ができる契約にする
- ダッシュボードの閲覧権と更新頻度を明記
- 初回は小さく開始→延長時に範囲拡張を検討
- 「価格」ではなく「再現手順の明確さ」で選ぶ
- 報告会ではなく「次の一手」を毎週決める設計にする
失敗しない選び方と見極め基準

コンサル選びで失敗しない鍵は、価格より「再現できる手順」と「測れるKPI(重要指標)」が提示されているかどうかです。
良い提案は、現状の課題をデータで示し、達成したい状態を数値で約束し、そこへ到達する道筋(いつ・何を・どの順で)が具体です。
さらに、実行後の振り返り方法(週次で何を見るか、改善は何を変えるか)が明確です。たとえば「問い合わせ数を増やす」では曖昧なので、「3か月でCVR(成約率)を0.8→1.2%」「CPA(1件あたり獲得費)を2万円→1.5万円」など、判断できる単位に落としてもらいましょう。
提案内容が、あなたの商材・単価・検討期間に合ったものかも重要です。BtoBの長い検討に短期の施策だけを当てる、ECに説明重視の長文LPだけを当てる、
といったミスマッチは成果が出にくいです。契約前に「やること・やらないこと」「撤退基準」「データの見える化」を合意し、毎週の会議は報告の場ではなく、次の一手を決める場にすることが、後悔しない選び方の基本です。
【確認の流れ】
- 現状の数値と課題の明文化→ベースラインを共有
- 目標KPIと期間の設定→達成イメージを数値化
- 実行ステップと担当の割り振り→遅延を防止
- 週次で見る指標と改善ルール→学習を高速化
実績とKPI設計の確認ポイントを整理
実績は「誰に・何で・どれくらい・どんな条件で」達成したかまで見てはじめて意味があります。単なる社名ロゴの羅列や「売上◯倍」だけでは判断できません。
あなたの状況(業態、客単価、検討期間、地域)に近い事例があり、目標までの道筋とKPIの置き方が現実的かを確認しましょう。
KPIは最小セット(CVR、CPA、LTV=累計利益)で十分です。良い設計は、チャネルごとに中間指標(例:クリック率、資料DL率、カート到達率)もセットで提案され、改善の打ち手(ABテストの対象、実装期限)まで落ちています。
| 確認項目 | 見る資料・情報 | 合格ラインの目安 |
|---|---|---|
| 再現性 | 事例の前提(業態/単価/期間/体制) | 自社に近い条件での成果が複数ある |
| KPI設計 | 目標値、計測方法、期間 | CVR・CPA・LTVが定義付きで提示 |
| 中間指標 | 回遊/DL/カート到達など | 週次で見て改善に紐づく設計 |
| 打ち手 | AB対象、実装期限、責任 | 誰がいつ何を変えるか明確 |
- 社名ロゴだけでなく数値と前提が開示されている
- 目標は「◯%・◯円・◯週」など判断できる単位
- 中間指標→次の一手までの因果が説明されている
- できないこと・対象外の範囲も明文化されている
【チェックポイント】
- LTVの算出法が曖昧→粗利ベースか売上ベースか要確認
- KPIが多すぎる→3つに絞って比較可能にするのが基本
担当体制と連絡方法の合意事項を明確化
成果は「誰が・いつまでに・何をするか」が決まると出やすくなります。担当体制は、戦略(設計)、実務(入稿・制作・開発)、計測(タグ・GA・広告管理)、意思決定(承認)に分けて役割を固めます。
連絡方法は、週次の定例で意思決定、日常連絡はチャット、課題やタスクはチケット管理、緊急連絡は電話など、シーン別に決めておくと迷いが減ります。
会議は「報告会」ではなく「決める会」にし、議事には誰が何をいつやるか(担当・期限・完了条件)を必ず残してください。
| 項目 | 合意しておく内容 | 見落としリスク |
|---|---|---|
| 役割分担 | 設計/実装/計測/承認の担当者 | 責任が曖昧でタスクが滞る |
| 会議運営 | 週次の目的、アジェンダ提出期限 | 報告だけで意思決定が進まない |
| 連絡手段 | 定例/日常/緊急の窓口とSLA(返信目安) | 重要連絡の見落としや対応遅延 |
| タスク管理 | ツール、期限、完了条件の定義 | やった/やってないの判定ができない |
| 資料/権限 | ダッシュボード・広告権限の付与範囲 | 計測が不完全、ブラックボックス化 |
【合意のひな形】
- 週次定例→毎週◯曜、決めることを3点に絞る
- チャット→当日内返信、緊急は電話→◯時間以内
- ダッシュボード→閲覧権限と更新頻度(週1)を明記
- 承認→LP/広告文は提出から◯営業日以内に可否
危ない提案の見分けポイントを具体解説
魅力的に見える提案ほど、注意深く中身を確認しましょう。たとえば「数日で必ず売上◯倍」「広告費ゼロで◯万PV」「予算いくらでもOK。全部やりましょう」などは、前提条件の説明が抜けがちです。
再現には、対象ユーザー・在庫・レビュー数・競合状況・計測環境などの条件が伴います。条件の話が出ず、作業量や抽象的なスローガンだけが並ぶ提案はリスクが高いです。
見積りも、会議や報告に偏って改善の実装時間が少ない場合、学習が進みにくく成果も出にくいです。契約条項では、成果物の権利やデータの閲覧権限、途中解約の条件が曖昧だと、関係解消後に運用できなくなる恐れがあります。
- 過度な断定や保証(◯日で必ず◯倍)→前提と根拠がない
- 支援範囲「一式」で成果物が不明→責任がぼやける
- 会議/報告が中心で実装時間が少ない→改善が進まない
- データと権限の帰属が未定→契約終了後に運用不能
【見極めのコツ】
- 「何を、誰が、いつまでに」まで言語化されているか確認
- 撤退基準(この数値なら見直す)が提案に含まれているか
- 仮説→AB→実装のサイクル時間が具体か(週単位が目安)
- できないこと・対象外が明記されているか(誠実さの指標)
以上を満たす提案は、費用対効果の判断がしやすく、実行後の学習も早く回ります。
支援内容と成果の出る進め方

成果が出やすい進め方は、設計→実装→計測→改善のサイクルを短く回し、学習したことをすぐ次の配分に反映することです。最初に目的(売上・リード・予約など)と主要KPI(CVR・CPA・LTVなど)を決め、現状の数値と課題を一枚に整理します。
次に、短期で効果が見えやすい施策(広告・LP改善など)と、中長期で効く施策(SEO・CRMなど)を役割分担し、6週間程度のミニ計画を立てます。
週次では「決める会」を開き、仮説→AB→実装の順に具体化します。計測はダッシュボードでチャネル別のCVR・CPA・指名検索・再来率を見える化し、良い要素に予算と工数を寄せます。
たとえばECなら、広告で高意図語に絞りながら、LPの不安(価格/配送/レビュー)を解消し、同時にSEO記事やSNS動画で想起を積み上げる、といった連動が効果的です。
下表は各フェーズの成果物イメージです。
| フェーズ | 主な作業 | 成果物の例 |
|---|---|---|
| 設計 | KPI設定・優先順位・役割分担 | KPIシート、6週間計画、担当表 |
| 実装 | 記事/LP/広告/配信の作成と設定 | 構成案、広告設計、配信カレンダー |
| 計測 | タグ設定、目標設定、可視化 | GA/広告の目標、ダッシュボード |
| 改善 | AB設計、勝ち要素抽出、再配分 | 改善リスト、次週の実装指示 |
- 目標と撤退基準を先に決める→判断が早くなる
- 短期で効果が見える施策から検証→勝ち要素に集中
- 週次で「次の一手」を必ず決定→学習を止めない
SEOとコンテンツ施策の基本的な型
SEOとコンテンツは、検索意図に合う答えを用意し、次の行動に自然につなげることが基本です。まず、キーワードを「情報収集」「比較」「行動準備」に分け、入口記事→比較記事→事例/FAQ→CTA(資料DL・相談・購入)という回遊の道筋を作ります。
記事は「結論先出し→根拠→具体例→行動」の順にまとめ、図や表で理解コストを下げます。内部リンクは同テーマで三角形(入口↔比較↔事例)になるように貼ると、回遊とCVRが安定します。
更新では、Search Consoleの表示回数・CTR・掲載順位を見て、タイトル/見出しの言い換えや追記を行います。FAQや用語集を整えると指名外のロングテールが伸び、CVに近い読者が増えます。
下表はコンテンツの型とKPIの例です。
| 型 | 目的 | 主なKPI |
|---|---|---|
| 入口(ハウツー) | 非指名の流入と信頼形成 | 検索流入、滞在、内部リンククリック |
| 比較(選び方) | 迷いの解消と意思決定の後押し | CVR、離脱率、CTAクリック率 |
| 事例/FAQ | 不安の解消と最終背中押し | 資料DL率、相談予約率 |
- 情報過多で読みにくい→結論と要点を先に提示
- 回遊が弱い→内部リンクを役割ごとに設計
- 更新が止まる→月1で優先記事の改善を固定
広告運用と計測設計の進め方
広告は「今すぐ客」を取り込みつつ、学習データを貯める役割です。出稿前に、目標KPI(許容CPAや最低ROAS)と日予算、到達したいCV数の目安を決めます。
設計は、検索なら高意図語を中心に完全一致とフレーズ一致を組み合わせ、除外語を初期から用意します。
SNS広告は、認知→興味→比較の階段を想定し、動画/静止画/カルーセルをABで試します。LPは広告文と同じ約束を冒頭で示し、証拠(レビュー・実績)と不安解消(配送・返品・料金)を近くに置きます。
計測はGAと広告管理画面で同じCV定義にそろえ、UTMで流入を区別します。ダッシュボードでは週次でCTR・CVR・CPA・在庫/粗利を確認し、勝っている組み合わせに入札と予算を寄せます。
- 目標と日予算・CV定義を決める(購入/予約/資料DLなど)
- 検索は高意図語に集中→除外語で無駄打ちを抑える
- SNSはクリエイティブを複数用意→短サイクルでAB
- LPは約束の一致と証拠提示→離脱点を潰す
- ダッシュボードで週次評価→良い要素に再配分
| チャネル | 主な用途 | 見る指標 |
|---|---|---|
| 検索広告 | 高意図の刈り取り/検証 | CTR・CVR・CPA、検索語とLPの一致度 |
| SNS広告 | 想起作り/比較材料の提示 | 再生率・保存・LP遷移・CVR |
| リマーケ | カゴ落ち/再訪促進 | 復帰率・CVR・獲得単価 |
- 検索語→見出し→CTAの一貫性を毎週点検
- 除外語の追加と成果の相関を見る
- 在庫/粗利と広告配分を連動させる
SNSとCRM活用の実務ポイント整理
SNSは発見と共感、CRM(メール/LINEなど)は関係の維持に強みがあります。まず、SNSは月ごとのテーマを決め、短尺動画・カルーセル・比較図の型を用意します。
投稿の目的は「保存したくなる」か「今すぐ知りたい」に寄せ、プロフィールと投稿に同じリンク導線を設置します。
LP直前でLINE登録やメール購読を挟み、初回特典や再入荷通知を用意すると登録率が上がります。登録後はセグメント(新規/既存/休眠・興味カテゴリ)ごとに配信を分け、キャンペーン・使い方・事例・FAQの順で信頼を積み上げます。
SNSのKPIは保存・プロフィール遷移・リンククリック、CRMは開封・クリック・解除率・再購入率が中心です。月次で「保存が多い投稿」「開封率が高い件名」を伸ばし、低い配信は停止して学習を加速させます。
| 目的 | SNSの役割 | CRMの役割 |
|---|---|---|
| 認知 | 短尺動画/カルーセルで発見を作る | 初回特典の案内、ブランド紹介 |
| 比較 | レビューや使い方の実演 | 導入事例・FAQ・比較表の送付 |
| 購入/再来 | 限定/締切の告知、リンク誘導 | カゴ落ち/再入荷/誕生日クーポン |
【運用チェックリスト】
- 投稿→LP→登録→配信の導線が一貫している
- セグメント別に頻度と内容を変えている
- 「保存」「開封」など次回に活きる指標を重視している
- 月次で停止と強化を決め、学習を前に進めている
依頼手順と契約チェック項目

コンサル依頼は、準備→比較→小さく検証→本契約の順で進めると失敗しにくいです。最初に、目的(売上・リード・予約など)と主要KPI(CVR・CPA・LTVなど)、現状の数字を一枚に整理します。
次に、候補を複数社ピックアップし、初回相談で課題の捉え方と進め方の相性を確認します。提案と見積では、支援範囲・成果物・担当体制・レポート頻度・期間・費用が具体かをチェックし、いきなり長期ではなく短いトライアルで再現性を確かめます。
契約前には、守秘・権利・解約・データの閲覧権限を明文化し、週次で「次の一手」を決める運用ルールまで合意しておくと、学習サイクルが止まりません。下記の流れを参考に、迷わず段取りを進めてください。
【基本の進め方】
- 目的・KPI・予算の整理→現状の数値を共有
- 候補3社の抽出→初回相談で相性確認
- 提案/見積の比較→支援範囲と成果物を具体化
- 小規模トライアル→学習の速さと質を検証
- 契約締結→守秘・権利・解約・権限を明記
- 週次運用開始→ダッシュボードで意思決定
目的設定とKPI・予算整理の基本ステップ
成果を出す土台は、目的・KPI・予算・撤退基準を同じ言葉で共有することです。まず、最終目的(購入件数・相談予約・来店予約など)を一つに絞り、期間と達成水準を置きます。
次に、チャネル別の中間KPI(クリック率・資料DL率・カート到達率など)を決め、週次に見直す前提で設定します。
予算は「許容CPA」や「最低ROAS」から逆算し、短期は検証に、余剰は勝ち施策に再配分します。撤退基準は数値で明文化し、到達しない場合は方針を変える合図として使います。
これらを事前に紙一枚で共有すると、提案の良し悪しが比較しやすく、会議が「決める場」に変わります。
【準備しておく項目】
- 目的の定義→例:問い合わせ◯件、来店予約◯件
- KPIの最小セット→CVR・CPA・LTVの定義
- 予算枠→月額の上限と配分の考え方
- 撤退基準→この数値なら見直す、の線引き
| 項目 | 決め方のヒント | 目安の例 |
|---|---|---|
| 目的 | 最終CVを一つに絞る | 月間相談予約◯件、来店予約◯件 |
| KPI | 中間指標を2〜3に限定 | 資料DL率◯%、カート到達率◯% |
| 予算 | 許容CPAや最低ROASから逆算 | CPA上限◯円、ROAS◯以上 |
| 撤退 | 数値で合意し更新時に判定 | 2週連続でCPA上限超→見直し |
- 目的とKPIの定義(用語ぶれを防止)
- 今月の重点チャネルと理由
- 撤退基準と次の候補手段
提案依頼と比較・トライアルの進め方と手順
提案依頼(RFP)は、狙いと制約を先に渡すと精度が上がります。目的・現状の数値・予算枠・体制・使える素材や制約(制作可否、入稿可否、計測環境)を共有し、成果物の例(KPI設計書、改善リスト、AB計画、ダッシュボード定義)まで指定すると、比較が容易です。比
較は安さではなく「仮説の質」「再現手順の明確さ」「学習の速さ」で行い、迷う場合は小さなトライアルで検証します。
トライアルでは、実装の速さ、ABの設計、レポートの解釈が「次の一手」に落ちているかを見ます。開始後は、週次で良い要素に再配分し、できないことや対象外が早めに共有されるかも評価します。
【RFPの流れ】
- 狙いと制約を1枚に整理→目的・数字・体制・予算
- 提出物の型を指定→KPI設計・改善リストなど
- 比較軸を事前共有→仮説の質/再現手順/学習の速さ
- 小規模トライアル→実装と意思決定の速さを検証
| 評価軸 | 見るポイント | 判断の目安 |
|---|---|---|
| 仮説の質 | 課題の特定と因果の説明 | 数字と前提で一貫性がある |
| 再現手順 | 誰が何をいつ行うか | 実装期限と責任が明記 |
| 学習の速さ | AB設計→反映のサイクル | 週単位で改善が回る |
| 透明性 | できないこと/対象外の明示 | リスク説明が具体 |
守秘・解約条項と成果物の権利確認の要点
契約で最も揉めるのは、情報の扱い・権利・解約です。まず守秘義務は、閲覧可能な人・目的・期間・再委託の範囲を明確にします。
成果物の権利は、資料・ダッシュボード・広告アカウント・タグ設定・テンプレートの帰属を個別に定義し、契約終了後も自社で運用できる状態を確保します。
データの閲覧権限は、閲覧・編集・管理権限の範囲を合意し、契約終了時の権限返却の手順も記載します。
解約は初回期間と更新条件、途中解約の通知期限、違約金や費用精算のルールを明文化します。これらを事前に整えると、関係解消時も混乱せず、学習資産を失いません。
| 項目 | 確認観点 | 例 |
|---|---|---|
| 守秘義務 | 対象情報・目的外利用の禁止・再委託 | 第三者提供の可否、違反時の措置 |
| 成果物の権利 | ドキュメント/ダッシュボード/設定の帰属 | 終了後も閲覧・複製・改変が可能 |
| データ権限 | 広告/分析ツールの権限範囲 | 閲覧・編集・管理のレベル別に合意 |
| 解約条件 | 通知期限・違約金・費用精算 | ◯日前通知、成果物引渡しの期日 |
【契約書で明記しておくと安心な事項】
- 帳票・タグ設定・テンプレートの帰属と再利用可否
- 権限返却の期限と方法(管理者アカウントの移管)
- 再委託先の守秘義務と責任範囲
- 途中解約時の費用精算と未実施分の扱い
- 権限が返ってこない→返却期限と手順を条項化
- 資料の再利用を禁じられる→成果物の権利を自社帰属に
- 解約時に業務が止まる→引継ぎ期間と範囲を明記
- 情報漏えいの懸念→再委託時の承認制と記録保存
まとめ
コンサル選びは目的・KPI・予算を先に決め、相場と支援範囲を照合することが近道です。本稿では費用の見方、実績確認の要点、危ない提案のサイン、契約時の注意点を整理しました。
次の一歩は、要件メモ作成→3社比較→小規模トライアル→契約条項の最終確認。迷わず実行に移せるはずです。