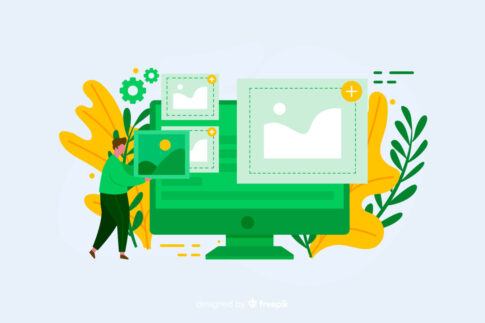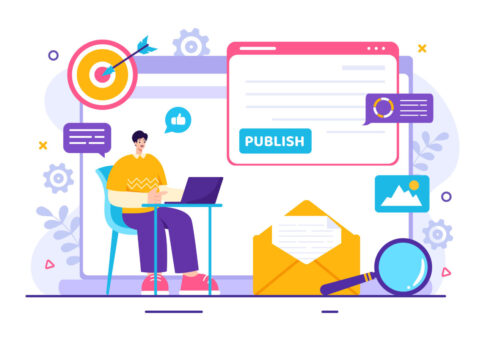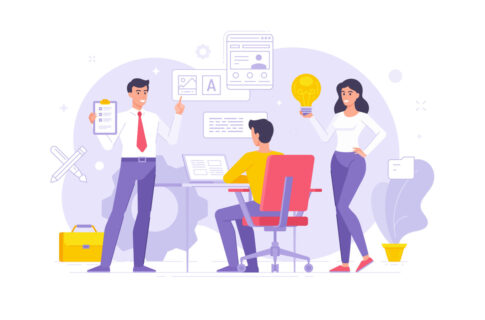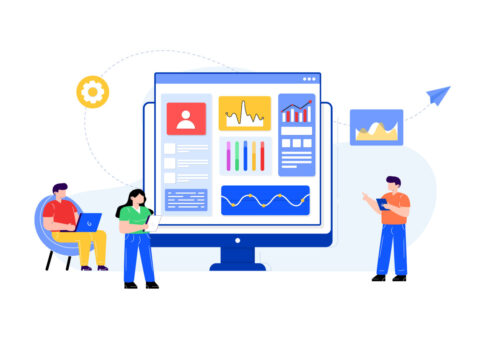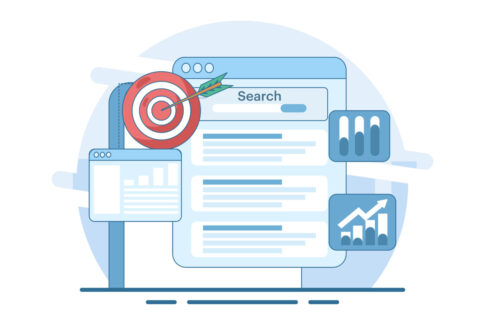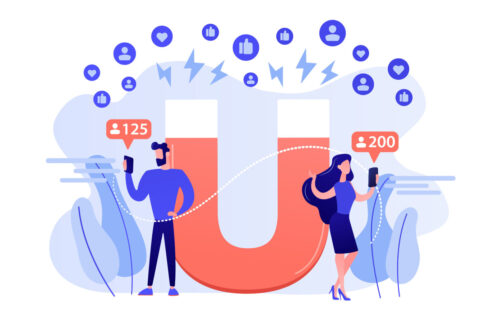色はクリックや滞在に直結します。本記事では、アメブロ集客に色彩心理学をどう生かすかを、配色10ルールと実例でやさしく解説していきます。
主要色のイメージ、ベース/メイン/アクセントの比率、CTAボタンの色と余白、OGPと本文の整合、A/Bテストの進め方までを一気通貫。今日から配色を見直し、クリックを増やしましょう。
色彩心理学の基礎と注意点

色彩心理学は「色が人に一定の印象を与えやすい」という傾向を扱います。ただし魔法ではありません。色だけで反応が決まるのではなく、①読みやすさ(コントラスト)②優先順位(どこを目立たせるか)③一貫性(毎回同じ使い方)の積み重ねで成果が出ます。
アメブロ集客では、背景・本文・CTA(行動ボタン)・リンクの“役割分担”を先に決め、配色の比率をベース6:メイン3:アクセント1の目安にすると迷いません。ベースは背景と本文、メインは見出しや囲み、アクセントはCTAや重要語に限定します。
注意点は、強い色を使いすぎて本文の可読性を落とさないこと、そして“目立たせる場所は1画面1か所”に絞ることです。配色は検証が要なので、まずは2パターンを7日ずつ比べ、クリック率と滞在で判断しましょう。
- 役割分担:本文=落ち着いた色/CTA=コントラスト強
- 比率:ベース6・メイン3・アクセント1に収める
- 検証:色だけを一要素変更→7日比較で判断
主要色と連想イメージの基本整理図解
主要色には一般的な連想があります。配色を決める前に、どの印象で読者に行動してほしいかを言語化し、それに合う色を“アクセント”として選びます。
本文は黒系/濃紺など目に優しい色で統一し、強い色はCTAや強調に限定すると、クリックポイントが明確になります。
| 色 | 印象・向いている使いどころ(アメブロ例) |
|---|---|
| 赤 | 注意・情熱・緊急。キャンペーンや期間限定のCTAに向く。本文多用は疲れやすい。 |
| オレンジ | 親しみ・活力。無料体験・資料請求など“行動を促す”ボタンに使いやすい。 |
| 黄 | 明るさ・注意喚起。注意書きの枠やポイントの下線に少量。本文面積は控えめに。 |
| 緑 | 安心・調和・自然。実績紹介やお客様の声背景に。長文でも読みやすいトーンを選ぶ。 |
| 青 | 信頼・誠実・清潔。問い合わせ・登録ボタンやリンク色の基調に向く。 |
| 紫 | 上品・専門性。価格表や実績セクションの見出しに少量。濃色は重くなりすぎ注意。 |
| 黒/グレー | 落ち着き・プロ感。本文や表・枠線の基調に。コントラスト確保が前提。 |
| 白 | 清潔・余白。背景の基本。余白を広めに取りCTAを目立たせる土台にする。 |
- 例:記事の本文は濃いめの文字色+白背景で読みやすさ優先。CTAは青またはオレンジなど“背景と明確に差が出る色”を選び、同じ色をサイト内で一貫して使います。
トーンと明度・彩度の考え方入門
同じ色でも「トーン(明るさと鮮やかさの組み合わせ)」で印象は変わります。鮮やかすぎる色は注目を集めますが、本文の読みやすさを下げがち。
まずは“本文=落ち着いたトーン、CTA=鮮やか寄り、背景=明るめ低彩度”と覚えてください。
| トーン | 見え方・効果 | 向いている場面(アメブロ例) |
|---|---|---|
| パステル(明・低彩度) | やわらかく親しみやすい。長文でも疲れにくい。 | 囲み枠・図解背景。CTAにはコントラスト不足になりやすいので注意。 |
| ビビッド(明・高彩度) | 強い注意喚起。視線を集めやすい。 | CTAボタン・期間限定バナー。本文面では面積を小さく。 |
| ダーク(暗・中〜高彩度) | 落ち着き・重厚。高級感が出る。 | 価格表や実績セクションの帯。文字は明るく太さを確保。 |
- 本文の可読性:背景は明るめ、文字は十分に濃い色で。薄いグレーの本文色や、背景が暗いのに文字も暗い配色は避けます。
- CTAの視認性:周辺に余白を取り、本文や見出しと明確に“色と明るさ”を変えます。色だけでなくサイズ・余白・位置で優先度を示すと効果的です。
- 見出しの階層:H2>H3で色の強さ(彩度)や太さを段階付けすると、流し読みでも構造が伝わります。
文化差と個人差への配慮ポイント
色の感じ方は文化・経験・視覚特性で変わります。たとえば赤は注意・祝祭の両義性があり、青は信頼・冷たさの両面があります。
万人に同じ反応を期待せず、「色だけに依存しない設計」を心がけましょう。リンクは色+下線、重要ボックスは色+アイコン(!など)、エラーは色+テキストで明示するなど“二重化”が安心です。
背景と文字色ははっきり差を付け、淡色背景に淡い文字、濃色背景に暗い文字といった低コントラストは避けます。
検証は、色以外の要素を固定し“ボタン色だけ”など一要素で比較するのが基本。週次でクリック率と滞在を見て、勝ち配色をテンプレにしましょう。
- 色だけの区別→下線・太字・アイコンを併用
- 低コントラスト→背景を明るく/暗くし、文字は十分濃く
- 強色の多用→1画面1か所に限定、余白で呼吸を作る
- 実務例:問い合わせボタンを青→オレンジに変更し、周囲に余白を広げて7日比較。色差と余白のどちらが効いたか分かるよう「一要素ずつ」検証します。
ブランドと世界観の配色設計

配色は「世界観を伝える言語」です。アメブロでは、本文の読みやすさを最優先しつつ、ブランドの雰囲気(信頼・親しみ・上質・元気など)を色で一貫させると、初見の読者でも“何屋さんか”を数秒で理解できます。
基本は〈ベース=背景と本文、メイン=見出しや区切り、アクセント=CTAや重要語〉の三役を先に決め、比率と役割を固定します。
さらに、ジャンルに合うトーン(明るさ×彩度)を選び、ロゴ・ヘッダー・見出し・ボタンの色を同系統で揃えると、ページ遷移や記事ごとの差が出ても“同じブランド”として認識されやすくなります。
注意点は、強い色を面積で使いすぎないこと、リンクやボタンの色を記事ごとに変えないこと、そしてOGP画像の配色も本文と揃えることです。
まずは「ブランドの性格一言(例:落ち着いた信頼/明るい元気)」を決め、その言葉に合う配色を三役に割り当てるところから始めます。
- ブランドの性格を一言で決める(信頼/親しみ/上質/元気 など)
- ベース・メイン・アクセントの三役を定義→色を仮決め
- 比率(6:3:1)と使う場所(本文/見出し/CTA)を固定
- ロゴ・ヘッダー・ボタンを同系統で統一→記事にも適用
ベース・メイン・アクセント比率設計
読みやすさと“押されやすさ”を両立させるため、配色は比率で考えると迷いません。目安は〈ベース6:メイン3:アクセント1〉です。
ベースは背景と本文の文字色(白背景+濃い文字など)で、長文でも疲れない落ち着いたトーンにします。
メインは見出し・区切り線・表のヘッダーなど情報のまとまりを示す要素に使い、ブランドらしさを出す色ですが、彩度を少し落として本文を邪魔しない強さに。
アクセントはCTAボタン・重要語・バッジに限定し、背景とのコントラストをしっかり確保します。
| 役割 | 主な使いどころ | 色選びの目安・例 |
|---|---|---|
| ベース(約60%) | 背景、本文文字、カード内背景 | 白/ごく薄いグレー+濃いグレー/黒文字。長文でも可読性重視。 |
| メイン(約30%) | H2/H3見出し、区切り線、表ヘッダー | ブランドカラーの中〜低彩度版(例:#2F6CABの低彩度) |
| アクセント(約10%) | CTAボタン、重要ラベル、リンクホバー | 背景と高コントラストの鮮やか色(例:オレンジ/ブルー) |
- 実務のコツ:アクセント色は1色に統一し、サイト内の「行動」をすべて同色にします。ボタン以外の装飾に多用しないことで、クリックポイントが明確になります。
ジャンル別に合うおすすめトーン
同じ色相でも、明度・彩度(トーン)が合っていないと“雰囲気違い”になります。ジャンルに合わせて、まずトーンから決めると失敗が減ります。
| ジャンル | 合いやすいトーン | 具体の使い方(例) |
|---|---|---|
| 不動産・士業 | 低〜中彩度のブルー/ネイビー系+明るいベース | 見出しをネイビー、CTAはコントラストの高いブルー。価格表はグレー帯。 |
| 美容・ライフスタイル | パステル〜ミドルトーン(ピンク/ラベンダー/ミント) | カード背景を淡色、本文は濃いグレー、CTAはサーモン/ローズで視認性確保。 |
| フィットネス・教育 | 明るめで中〜高彩度(オレンジ/グリーン) | H2をグリーン、CTAをオレンジ。図解背景は淡いグリーンで可読性を担保。 |
| 高単価・上質訴求 | ダークトーン+アクセント少量(ゴールド/ディープパープル) | ヘッダーをチャコール、見出しは低彩度、CTAはゴールドで一点集中。 |
- 注意:ダークトーン主体は文字の視認性が落ちやすいので、文字色はしっかり明るく・太く。明度差(コントラスト)を常に確認します。
- ジャンルと読者像を一言に→目指す印象(信頼/親しみ/上質/元気)を決定
- その印象に合う色相を選び、まずは低〜中彩度で検討
- CTAだけ鮮やか寄りにし、本文は落ち着いたトーンに固定
ロゴとヘッダーの色統一設計
ロゴ・ヘッダー・ボタンの色がバラバラだと、記事ごとに世界観が切れて見えます。先に「ブランド基準色」を1〜2色決め、派生の明度・彩度を用途別に定義すると、更新が格段に楽になります。
ロゴ色はヘッダーや見出しのメイン色と同系統にし、CTA(アクセント)はロゴと被らない色相で高コントラストを確保。ヘッダー画像やOGPにも同じパレットを適用し、文字色は白/黒のどちらを使うかを先に固定します。
| 要素 | 統一の考え方 | チェック項目 |
|---|---|---|
| ロゴ | ブランドの“基準色”。派生色をメインに展開 | ロゴ色=見出し色の系統か/暗背景でも見えるか |
| ヘッダー | ロゴと同系統で世界観を固定 | OGPやアイキャッチと配色が一致しているか |
| CTAボタン | ロゴと被らない高コントラスト色 | 本文やヘッダーと十分な明度差があるか |
- ロゴ色=見出し/ヘッダーの系統、CTAは別系統で強調
- リンク色・ボタン色は記事ごとに変えず全ページ統一
- OGPと本文の配色が一致(タイトル色・背景色)
- 実例:ロゴがネイビーの場合→見出しと区切り線を低彩度ネイビー、CTAはオレンジに統一。ヘッダー画像とOGPの文字色は白で固定し、どのページでも同じ印象にそろえます。
クリックを生む色の使い方

「色」は注意を引くだけでなく、読む順番と行動ポイントを示すサインです。アメブロでは、①タイトル・見出しで内容理解を早め、②CTA(行動ボタン)で“ここを押す”を明確にし、③本文リンクで回遊の道筋をそろえる――の3つを色で設計します。
まず大前提は可読性(コントラスト)です。背景が明るいなら文字は十分に濃く、赤や黄など強い色は“面積ではなく点”で使います。
次に一貫性。タイトル色・見出し色・リンク色・ボタン色を記事ごとに変えず、全ページで同じルールを維持すると、読者は意識せずに“読む→押す→戻る”を迷わず繰り返せます。
最後に余白。色だけで目立たせるのではなく、周囲の余白で「浮かせる」ほうが、押しやすさと清潔感が両立します。以下の各h3で、具体ルールと配置のコツを解説します。
- タイトル・見出し=内容の区切り色(メインカラー)
- CTAボタン=行動の色(アクセントカラー)
- 本文リンク=回遊の色(常に同じ色+下線)
タイトル・見出しの強調色ルール
タイトルと見出しは「何の話か」「どこまで読めば良いか」を色で素早く伝える場所です。基本は、H2にブランドのメインカラー(低〜中彩度)、H3にその薄い版またはグレーを使い、階層差を色の強さで表現します。
本文は濃いグレー/黒で統一し、見出しだけ色を付けると情報のまとまりが一目で分かります。強い原色は面積が増えるほど疲れやすいので、見出し色は“少し落ち着いたトーン”を選び、太字やアイコンと併用してメリハリを付けると読みやすさが上がります。
強調したい単語を本文中で着色する場合は1段落1箇所までに抑え、色ではなく「太字→箇条書き」の順に優先。見出し末に小さな色付きラベル(例:「手順」「注意」)を置くと、流し読みでも要点が拾えます。
| 要素 | 色の選び方 | 実装のコツ |
|---|---|---|
| H2 | メインカラーの低〜中彩度(例:ネイビー) | 太さを上げ、前後に余白を広く取る |
| H3 | H2より明るい/薄い同系色 or グレー | H2より細く、小さめにして階層差を明確に |
| 本文強調 | 基本は太字、色付けは最小限 | 1段落1箇所まで、コントラストを確保 |
- 見出しが原色でギラつく→彩度を1段下げる/太字と余白で補う
- 段落内に色だらけ→太字と箇条書きへ置き換え
- ページごとに見出し色が不統一→全記事で同じ色を固定
CTAボタン色と周囲の余白設計
CTAは「押す色×浮かせる余白」で決まります。背景が白系なら、CTAはオレンジ/ブルー/グリーンなど背景と明度差・色相差のある色を選び、必ず同じ色を全ページで使います。
ボタン色だけを派手にしても、周囲が詰まっていると押しにくいため、上下に文字2〜3行分の余白、左右にボタン幅の15〜20%の余白を確保するとクリック率が安定します。
文言は「申し込む」より「◯◯を予約する」「無料チェックを受け取る」のように行動を具体化し、直前に不安を消す一行(所要3分/当日OK/キャンセル無料)を添えましょう。
2箇所配置が基本で、本文末と“まとめ前”に同文言で設置。中段に置く場合は、要点が完結した段落直後のみに限定します。
| 背景色 | 相性の良いCTA色 | 避けたい組み合わせ |
|---|---|---|
| 白/薄グレー | オレンジ/ブルー/グリーン(高コントラスト) | ライトイエロー/ライトグレー(沈む) |
| 淡色(パステル) | 同系の濃色 or 補色系(彩度高め) | 同じ明度の淡色(境界が曖昧) |
| 濃色(ダーク) | 白/ライトイエロー(文字は黒/濃色) | 暗色×暗色(文字が読めない) |
- 背景とのコントラストが十分か(遠目で識別できるか)
- 上下左右にしっかり余白があるか(詰め込みNG)
- サイト内でCTA色が統一されているか(毎回同じ色)
リンクと強調の色使い統一ルール
回遊を増やすには「リンクはいつも同じ見た目」にします。色は青系など“慣れ”のある色を推奨、必ず下線を付け、訪問後は色が変わると便利です。
本文強調(太字や背景マーカー)とリンク色を混同すると“押す場所”が曖昧になるため、強調は太字+淡い背景色、リンクは青+下線のように役割を分けます。
強調色やマーカーの多用は読みづらさに直結するので、1スクロールに2箇所までを目安に。表や図の中のリンクは、色だけだと見落とされやすいので、アイコン(↗)や「詳しく見る→」などテキストを添えます。
全体の印象を崩さないため、ヘッダー・本文・フッターでリンク色を変えないのも重要です。
| 要素 | 見た目ルール | 運用のコツ |
|---|---|---|
| 本文リンク | 青系+下線(訪問後は色変更) | アンカーは「こちら」ではなく内容が分かる語に |
| 強調(非リンク) | 太字+淡い背景(色は固定) | 1スクロール2箇所まで、役割を限定 |
| 表/図中リンク | リンク色+アイコン/矢印 | クリック範囲を十分に確保 |
- リンク色がページごとに違う→全体で統一、CSS相当の設定を固定
- 強調色=リンク色→読者が混乱。強調は太字+背景へ変更
- 色だけの識別→下線・アイコン・テキストで二重化
- 実務メモ:まずは「リンクは青+下線、CTAはオレンジ、見出しはネイビー」といった3ルールを決め、全記事に適用。7日比較でクリックと回遊の変化を確認し、必要なら色相ではなく“余白”から調整します。
画像・OGPの配色と可読性

アメブロで画像とOGP(シェア時のサムネ)を整える目的は、①一覧で「内容が一目」で分かる、②本文で「読みやすい」、③クリック後も「色の一貫性」で迷わせない、の3点です。
まず、背景と文字の明るさの差をはっきり取り、色同士をぶつけないことが基本です。淡い写真の上に淡い文字、暗い写真の上に暗い文字は避け、必要に応じて半透明の色面やグラデーションで“文字を置く土台”を作ります。
次に、サイト全体の配色と役割(見出し=メイン色/リンク=青系/CTA=アクセント色)を画像側にも反映し、OGP・ヘッダー・本文の色が自然に連続するようにします。
最後に、モバイルのトリミング差(上下左右の切れ)を前提に、重要要素は中央寄せ・2行以内に収めると可読性が安定します。
- 文字は必ず“色面の上”に置き、背景と明確なコントラストを確保
- サイトの役割色(見出し/リンク/CTA)をOGPにも踏襲
- 要素は中央寄せ・2行以内・余白広めでモバイルに最適化
アイキャッチ文字の可読性確保
アイキャッチは「何を得られる記事か」を2秒で伝える看板です。文字が読めなければクリックは伸びません。写真の上に直接文字を置くより、半透明の色面(黒またはブランド色の20〜40%)や、上下の帯を敷いてから文字をのせると読みやすくなります。
文字色は背景と反対側の明度を選び、細いフォントや淡い色は避けます。基本は太さしっかり・2行以内・行間広め。
写真の被写体と文字が重ならないよう、被写体を左右にずらすか、文字を中央寄せにします。影(ドロップシャドウ)や縁取りは“薄い一重”のみで、過度な装飾はにじみの原因です。
モバイルでは上下が切れやすいため、重要語は中央付近に。数字や結論を先頭に置くと理解が速まります。
| よくある見づらさ | 原因 | 対処例 |
|---|---|---|
| 文字が背景に溶ける | 背景と文字の明度差が不足 | 20〜40%の暗色オーバーレイ→白文字で2行 |
| にじんで読めない | 細字・低彩度・過剰な影 | 太字へ変更、影は薄く一重、色ははっきり |
| 被写体と競合 | 人物や商品の上に文字 | 文字用の帯を追加/被写体を左右に寄せる |
- 2秒で“誰に・何が”読めるか(数字/結論を先頭に)
- 2行以内・中央寄せ・周囲に十分な余白があるか
- PC/スマホ両方で切れずに読めるか(中央に重要語)
人物・商品写真の色バランス調整
人物や商品の写真は「色かぶり」と「コントラスト不足」が離脱の原因になりがちです。まずホワイトバランスを整え、肌や商品の本来の色に近づけます。
次に、露出を微調整し、暗部がつぶれない範囲でコントラストを上げると立体感が出ます。彩度は上げすぎると安っぽく、下げすぎるとくすみます。
サイト全体のトーン(落ち着き/元気/上質)に合わせて控えめに調整しましょう。背景はできるだけシンプルにし、被写体の主色とCTA色がケンカしないよう配慮します(例:CTAがオレンジなら、被写体に強いオレンジは避ける)。
商品は“色違い比較”が多いため、同一の光・角度・背景で統一撮影すると、比較と理解が速まります。人物は目線の向きや手の位置で“指し示し”を作ると、見出しやCTAへ視線誘導できます。
| 課題 | 調整ポイント | 実務ヒント |
|---|---|---|
| 色がくすむ | WB(白色)と露出を微調整 | 白い紙を基準に色かぶり(黄/青)を補正 |
| 印象が弱い | コントラスト/彩度を控えめに上げる | 肌色が不自然に見えない範囲で+ |
| ごちゃつく | 背景の色数を減らす | 無地背景か浅めの被写界深度に |
- WB→露出→コントラスト→彩度の順に微調整
- 背景の色を減らし、主役の色を際立たせる
- CTA色と被らないよう、衣服/小物の色を選ぶ
OGPと本文の配色整合チェック
OGPは「SNSでの第一印象」、本文は「理解と行動の場」。ここで色が食い違うと、クリック後に違和感が生まれ離脱につながります。
整合の基本は、タイトル色・背景色・アクセント色(CTA)をOGPと本文で合わせること。OGPでオレンジCTAを見せたのに、本文では青ボタン…といった不一致は避けます。
また、OGPの要点語と本文冒頭の結論を同じ言い回しにし、期待落差をゼロにします。共有前にはプレビュー(デバッガー)で最新のOGPが反映されているかを確認し、トリミングで文字が切れていないかをチェック。
配色A/Bは一度に1要素(ボタン色だけ、背景だけ)を変え、7日比較で勝ちをテンプレ化します。
| 項目 | 一致させる要素 | チェック例 |
|---|---|---|
| タイトル | OGPの要点語=本文冒頭の結論 | 「クリック率+15%の色」→冒頭にも同表現 |
| 色の役割 | 見出し=メイン色/CTA=アクセント色 | OGPと本文でボタン色が同じか |
| 背景と余白 | 明度感/余白の取り方 | OGPと本文で“空気感”が近いか |
- OGPのテキスト2行以内・中央配置・切れなし
- タイトル語・ボタン色・背景色が本文と一致
- 1要素だけA/B(例:ボタン色)→7日で比較
- 実務メモ:サイト全体で「見出し=ネイビー/リンク=青+下線/CTA=オレンジ」を決めたら、OGPにも同配色を適用。共有プレビューで文字切れを確認してから公開すると、クリック後も違和感なく読了まで進みます。
検証と運用の実務フロー

配色は「決めたら終わり」ではなく、数値で確認しながら少しずつ整えていく運用が必要です。実務フローはシンプルに〈計画→テスト→判定→テンプレ化〉の4段です。
計画では、まず“色の役割”を文章で決めます(例:見出し=ネイビー、リンク=青+下線、CTA=オレンジ)。
次に、今週はどの1要素だけを試すかを明確にします(ボタン色/余白量/見出し色の彩度 など)。テストは同条件比較が命です。
露出面(タグ面・SNS告知)、時間帯(20時台など)、端末(スマホ中心)をそろえ、7日間の片側テストを基本にします。
判定は〈入口→中腹→出口〉の順に、CTR(クリック率)→滞在/深度→CTAクリック→完了率を確認。勝ち要素はテンプレ化して全記事へ波及させ、来週は次の要素に移ります。
配色は文字や余白ともセットで効くため、色だけで勝負しないのがコツです。ボタンは“色×余白×文言×位置”の総合点で決まり、失敗例の多くは色以外が詰まっています。
以下の各h3で、具体的な手順・基準・回避策をまとめました。
- 今週の検証対象は“一要素だけ”か(色/余白/文言のどれ?)
- 比較条件は固定できているか(面/時間/端末)
- 結果は前週比で判断し、勝ちをテンプレに反映したか
| 段階 | 見る指標 | 主な打ち手 |
|---|---|---|
| 入口 | CTR(面・時間帯・端末別) | タイトル先頭語/OGPの文字2行化/配色の明度差 |
| 中腹 | 滞在・深度・スクロール率 | 見出し色の階層化/本文の可読配色/画像の文字可読性 |
| 出口 | CTAクリック・完了率 | ボタン色統一/余白拡張/近接ベネフィットの一行 |
A/Bテストで色を比べる手順
色の良し悪しは“感覚”ではなく“同条件での数値”で決めます。手順は〈仮説→設定→公開→比較→反映〉の5ステップです。
【準備(仮説づくり)】
- 目的を一行で:例「CTAクリック+10%」
- 変えるのは一要素だけ:ボタン色 or 見出し色 or リンク色のいずれか
- 勝ち判定の指標を決める:CTAクリック率/完了率(入口狙いならCTR)
【設定(同条件を固定)】
- 露出面:いつもと同じタグ面・SNS告知で固定
- 時間帯:例「20:00固定」。日をまたいでも時間は揃える
- 端末:スマホ比率が高い前提でスマホ表示で最終チェック
- 計測:設置場所別リンク(footer/pre-summary など)でクリックを分解
【公開(A→Bの順で)】
- 1週目:Aパターン(現状)を運用し指標を記録
- 2週目:Bパターン(色だけ変更)に差し替え、同条件で運用
【比較(前週比で判定)】
- 入口:CTR、サムネ・OGPの視認性(遠目で判別できるか)
- 中腹:滞在・深度、見出しで迷っていないか
- 出口:CTAクリック・完了率、誤クリックや戻りが増えていないか
【反映(テンプレ化)】
- 勝ちパターンを「サイト全体のルール」に昇格(CTA色・余白・文言)
- 次の週は別要素を検証(例:色→余白→文言→位置の順)
- 複数同時変更→因果が不明に。必ず“一要素だけ”
- 時間帯がバラバラ→固定し、前週比で判定
- 感覚判定→数値(クリック/滞在/完了)で決める
| 検証例 | A(現状) | B(変更) |
|---|---|---|
| CTA色 | ネイビー+白文字 | オレンジ+白文字(周囲に上下2行の余白) |
| 見出し色 | 黒 | 低彩度ネイビー(階層差を色で可視化) |
| リンク色 | グレー | 青+下線(訪問後は色変化) |
コントラスト比と見やすさ基準
色の良し悪し以前に、まず「読めること」が最優先です。見やすさの目安として、文字色と背景色の明るさの差(コントラスト比)を意識します。
一般に小さな文字は4.5:1以上、太字や大きめの文字は3:1以上、より見やすさを高めたい場合は7:1以上を目安にすると、読み疲れを減らせます。
難しい計算は不要で、実務では「遠目にして判読できるか」「白黒にしても読み分けできるか」を簡易チェックにします。
【配色の実務ポイント】
- 本文:白(またはごく薄いグレー)背景+濃い文字(黒/濃紺)
- 見出し:本文より彩度を少し上げるが、原色は避ける
- CTA:背景と色相差・明度差の両方を確保(白背景×オレンジ/ブルーなど)
- リンク:青+下線で“色だけに依存しない”識別にする
| 要素 | やりがちNG | 直すコツ |
|---|---|---|
| 本文 | 薄いグレー文字/背景が色付きで明度差が不足 | 文字は十分濃く。背景は白系に戻し、行間を広めに |
| 見出し | 強彩度の原色でギラつく | 同系色の低〜中彩度へ。太字と余白で強調 |
| CTA | 背景と近い明度で沈む | 色相差+余白で“浮かせる”。ボタン内文字は高コントラスト |
- スマホを腕の長さに離して、見出しとボタンが識別できるか
- 画面を白黒にして、リンクとボタンの場所が分かるか
- 屋外/室内の明るさ違いでも読めるか(反射に注意)
ありがちな配色NGと回避策
配色の失敗は“派手さ不足”ではなく“役割の混線”が原因です。よくあるNGは、①リンク色と強調色が同じで押す場所が分からない、②ページごとにボタン色が違い学習が起きない、③原色を面積で使って本文が読みにくい、の3つ。
回避策は、役割を一度文章で決めて全ページで統一し、強い色は“点で使う”こと。リンクは青+下線、強調は太字+淡い背景、CTAはアクセント色で固定すると迷いが消えます。
さらに、写真やOGPの色が本文とケンカして沈むケースも多いので、被写体色とCTA色が競合しないように色を選ぶ/半透明のオーバーレイで土台を作る、といった下ごしらえが効きます。
| NG | 起こる症状 | 回避策 |
|---|---|---|
| リンク色=強調色 | 押す場所が曖昧、誤クリック | リンクは青+下線、強調は太字+淡色背景に役割分離 |
| ページごとにCTA色が違う | 学習されずクリックが不安定 | CTA色をサイト全体で固定(1色のみ) |
| 原色の面積多用 | 読み疲れ、直帰増加 | 彩度を落とし“面は落ち着き、点で鮮やか”に |
| 写真とボタンが同系色 | ボタンが埋もれる、視線が迷う | オーバーレイ/余白で分離、ボタンは補色寄りに |
- 色×余白×文言×位置の“総合設計”で評価する
- 変更は一要素ずつ→7日比較→勝ちをテンプレ化
- 「読めること」が最優先。可読性を犠牲にしない
- 実務メモ:まずは「見出し=ネイビー/リンク=青+下線/CTA=オレンジ」を全記事で固定。OGPも同配色にそろえたうえで、CTA色だけA/B→勝ちを反映→次は余白量をA/B、と順番に進めると失敗が少ないです。
まとめ
クリックを増やす近道は「色の役割を決めて一貫させる」ことです。ベース6:メイン3:アクセント1を基本に、CTAは背景と高コントラスト・余白広めで配置。
タイトル/見出し/リンクの色を統一し、OGPと本文の配色も揃えます。最後にA/Bテストで先頭語とボタン色を一要素ずつ検証。まずはCTAの色と余白から直し、クリックの変化を7日比較で確認しましょう。