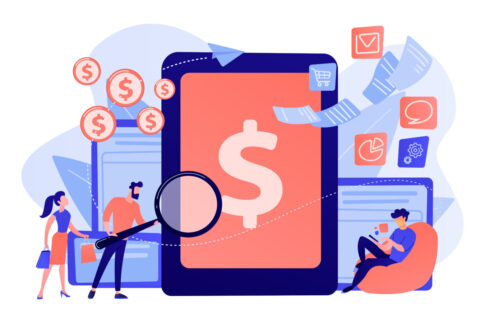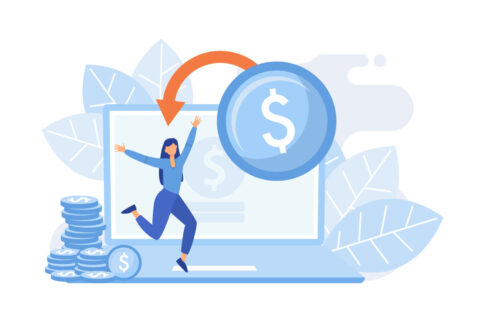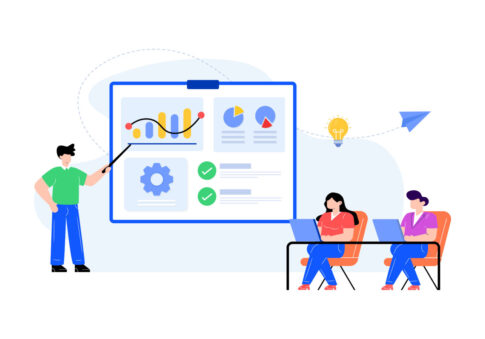アフィリエイト収入が「20万円以下なら確定申告は不要」と聞いても、20万円が“収入”ではなく“所得”の基準だったり、給与の有無などで扱いが変わったりして迷いがちです。さらに、所得税の確定申告が不要になる場合でも、住民税の申告が必要になることがあります。 この記事では、20万円ルールの条件、所得の出し方、申告が必要かの判定手順、手続きの流れまでを整理します。やるべきことが明確になり、ムダなく準備できます。
20万円ルールの基本整理
アフィリエイトの「20万円ルール」は、よく「20万円以下なら確定申告しなくてよい」とまとめられますが、実際は“誰でも一律”ではありません。国税庁の案内では、給与の収入金額が2,000万円以下で、給与を1か所から受けていて給与が源泉徴収の対象となる人など、一定の要件を満たす場合に、給与所得および退職所得以外の所得金額が20万円以下なら、所得税の確定申告をしなくてもよい扱いがあります。
一方で、給与が複数社から出ていて年末調整されていない給与がある場合や、同族会社の役員など特定のケースでは、条件が変わります。また、所得税の確定申告が不要でも、住民税(市民税・県民税)の申告が必要になる自治体が多い点も、このキーワードでつまずきやすいポイントです。
- 20万円は「収入」ではなく「所得(収入−必要経費)」の基準です
- 主に「給与が年末調整済みの会社員」などが対象になりやすいです
- 所得税の申告が不要でも、住民税申告が必要になる場合があります
20万円は所得の基準
この「20万円」は、アフィリエイトの売上(入金額)ではなく、税法上の「所得金額」を指します。所得金額は、基本的に「収入(売上)−必要経費」で計算します。たとえば、アフィリエイト報酬の入金が30万円でも、サーバー代や広告費、取材・検証に必要な支出など必要経費が12万円あるなら、所得は18万円となり、20万円の判定は「18万円」で行います。逆に、入金が18万円でも経費がほとんどなければ、所得も18万円で同じ扱いです。
ここで混乱しやすいのが、「未払いの報酬」や「確定前の報酬」をどう扱うかです。所得税は1月1日〜12月31日の1年間の所得を基に計算し、確定申告で精算します。アフィリエイト報酬がいつの時点で収入計上されるか(入金日か、確定日か等)は取引の状況で扱いが変わる場合があるため、収入計上の基準を自分の帳簿で一貫させることが重要です。
また、20万円は「給与所得および退職所得以外の所得金額の合計額」なので、アフィリエイト以外の副業所得(例:原稿料、フリマ転売など)がある場合は合算で判定します。
- 「報酬の入金が20万円以下ならOK」→ 所得(収入−経費)で判定します
- 「アフィリエイトだけ見ればよい」→ 給与以外の所得は合算で判定します
- 「経費は何でも入る」→ 事業に必要な支出に限り、証拠を残します
対象になりやすい人
20万円ルールの対象になりやすいのは、勤務先で年末調整が行われ、給与が源泉徴収の対象となっている会社員などです。具体的には「会社の給与は年末調整で完了している→アフィリエイト(雑所得や事業所得など)だけが追加で発生している」という形の人が該当しやすいです。
なお、給与が2か所以上から支払われていて年末調整されていない給与がある場合は、別の判定になります。また、同じ20万円でも「公的年金等の確定申告不要制度」など別枠の制度があり、対象要件が異なります。キーワードが「アフィリエイト」であれば、まずは“給与所得者の20万円”に当てはまるかを起点に判断するのが分かりやすいです。
- 会社員で年末調整が済んでいる
- 給与は原則1か所からで、給与は源泉徴収の対象
- 給与以外の所得(アフィリエイト等)の合計が20万円以下
20万円以下でも申告が要る例
「20万円以下なら絶対に申告不要」ではありません。代表例として、給与の年間収入金額が2,000万円を超える人、源泉徴収義務のない者から給与等の支払を受けている人、同族会社の役員などで同族会社から利子や賃貸料等を受け取っている人、などは確定申告が必要になる場合があります。
また、給与が2か所以上で年末調整されなかった給与がある場合などは、年末調整されなかった給与収入と他の所得の合計が20万円を超えるかどうかで申告要否が分岐します。ここは「アフィリエイト所得が20万円以下」だけでは判定できないため、給与の状況も含めて確認が必要です。
加えて、確定申告は「必須」のケースだけでなく、「還付を受けるために行う」ケースもあります。たとえば、年末調整で受けていない控除を適用して所得税の還付を受けたい場合などは、確定申告をする選択肢があります(これは“必要になる”というより“申告することで精算できる”性質です)。
- 給与の収入金額が2,000万円を超える
- 源泉徴収義務のない者から給与等の支払を受けている
- 同族会社の役員などで、会社から利子・賃貸料等も受け取っている
- 給与が複数で、年末調整されていない給与がある
住民税申告が要る場合
所得税の確定申告が不要な場合でも、住民税(市民税・県民税)の申告が必要になることがあります。自治体の案内では、給与所得者で給与以外の所得金額が20万円以下の場合、所得税の確定申告は不要とされる一方で、市民税・府民税(住民税)の申告は必要と説明している例があります。
なぜ住民税申告が問題になるかというと、所得税の確定申告をしない場合、自治体が副業所得を把握できないことがあるためです。また、住民税申告の有無は、課税(非課税)証明書の発行や、国民健康保険料などの算定に影響が出る可能性があると自治体が案内しているケースもあります。
そのため、所得税の確定申告をしないと決めた場合でも、住民税の手続きはお住まいの市区町村の案内に沿って進めるのが安全です。
- 所得税の確定申告をしない場合は、市区町村の「市民税・県民税申告」の要否を確認する
- 給与以外の所得がある場合は、少額でも申告が必要とされる自治体がある
- 不明点は市区町村の税担当窓口に相談する
アフィリエイト所得の計算
「20万円ルール」の判定で必要になるのは、アフィリエイトの“収入(入金額)”ではなく“所得(もうけ)”です。所得は、基本的に「総収入金額 − 必要経費」で計算します。アフィリエイト収入は状況により事業所得になる場合もあれば、雑所得(業務に係るもの)として扱われる場合もありますが、どちらも所得の計算は「収入から必要経費を引く」考え方が基本です。
実務では、①収入を集計する(どの金額をその年の収入にするかを決める)→②必要経費を整理する(事業・業務に必要な支出だけに絞る)→③所得を計算して20万円判定の材料にする→④帳簿と証拠書類を残す、の順に進めると迷いにくくなります。収入と経費を分けておけば、申告が必要になった年も慌てずに対応できます。
- 収入:ASP明細などで年合計を作る
- 経費:業務に必要な支出だけを集める
- 所得:収入−経費で算出して判定に使う
- 証拠:帳簿と領収書等を保存する
収入の集計方法
収入の集計で大事なのは、「その年の収入に入れる金額」をぶれない基準で揃えることです。年末までに実際の入金がなくても「収入すべき権利が確定した金額」がその年の収入になる考え方があるため、入金日だけで年を区切ると、年末年始でズレが出る場合があります。実務では、ASPの支払明細や確定明細など、確定した金額が分かる資料を軸に年合計を作り、銀行の入金履歴で整合を取る形が整理しやすいです。
また、アフィリエイトは成果の確定・取消(否認)が起きる場合があります。そのため、年合計は「最終的に確定した金額」が分かる資料を残し、後から説明できる状態にしておくのが安全です。
【収入集計の最小ステップ】
- ASPごとに「確定した報酬」の月次合計を作る
- 年合計を出し、入金履歴とズレがないかを見る
- ズレがある場合は、手数料控除や繰越の有無をメモする
- 年末確定分が翌年入金になる
- 振込手数料が差し引かれて入金される
- 確定後に取消が入り、月次で相殺される
必要経費の考え方
必要経費は「アフィリエイト収入を得るために直接要した費用」や「業務上の費用」として整理します。アフィリエイトでは、例えばサーバー代・ドメイン代、広告費、記事作成の外注費、取材や検証のための購入(業務に必要な範囲)、書籍代、ソフト代などが“業務に必要”として説明しやすい代表例です。
一方、私生活の支出は必要経費になりません。ただし、自宅の通信費や電気代など家事関連費でも、業務で使う割合を合理的に区分できる場合は、その業務使用分を経費にできる場合があります。按分するなら、割合と計算式をメモしておくと後から説明しやすくなります。
また、高額なパソコン等は、購入した年に全額を経費にせず、減価償却という形で複数年に分けて費用化する扱いになる場合があります。経費は「何の収入に結び付く支出か」を説明できることと、証拠が残っていることが重要です。
- 私用の支出を混ぜる→業務に必要な理由を説明できるものだけ残す
- 家事関連費を全部入れる→按分根拠(割合・計算式)をメモする
- 領収書を捨てる→支払い証拠(領収書・明細)をセットで保存する
所得の計算式と例
所得の計算はシンプルで、基本は「総収入金額 − 必要経費」です。20万円ルールの判定で見る「20万円」は、この所得金額(給与所得・退職所得以外の所得の合計)を指します。
具体例として、年のアフィリエイト収入が28万円で、必要経費が9万5千円なら、所得は18万5千円です。この場合、20万円以下かどうかの判定材料としては「18万5千円」を使います。逆に、収入が同じでも経費が少なければ所得は上がります。重要なのは、年合計で数字を揃えることと、収入と経費の根拠が残っていることです。
| 区分 | 例 |
|---|---|
| 総収入金額 | アフィリエイト報酬(年合計)280,000円 |
| 必要経費 | サーバー代30,000円+広告費50,000円+書籍等15,000円=95,000円 |
| 所得金額 | 280,000円−95,000円=185,000円 |
- 基準は「所得(収入−経費)」でそろえる
- 副業が複数ある場合は、給与以外の所得を合算して考える
- 数字の根拠(明細・領収書)を必ず残す
証拠書類の残し方
所得の計算を正しく行うには、帳簿と証拠書類(明細・領収書など)をセットで残す必要があります。個人で事業や不動産貸付け等を行う場合は、申告の有無にかかわらず、記帳と帳簿書類の保存が求められる点に注意します。
保存期間は、申告形態や書類の種類で扱いが分かれるため、帳簿・領収書・請求書・契約書などは一定期間まとめて保管しておくのが安全です。また、請求書や領収書に相当する電子データをやり取りした場合は、電子データで保存が必要になる場合があります。
実務では、①ASPの月次明細(収入根拠)②銀行入金履歴③経費の領収書・請求書④クレジットカード明細などを月別フォルダでまとめ、帳簿(スプレッドシートや会計ソフト)と紐づく形にしておくと、後から説明しやすくなります。
- 収入:ASPの確定明細・支払明細、入金履歴
- 経費:領収書・請求書・利用明細(カード明細等)
- 帳簿:日付・相手先・金額・内容が分かる記録
- 按分:割合の根拠メモ(家事関連費がある場合)
申告が必要かの判定手順
「アフィリエイト 確定申告 20万円」で迷う理由は、20万円が“収入”ではなく“所得(収入−経費)”の基準であることに加え、給与の状況(年末調整の有無・給与の支払元が1か所か複数か等)で判定が分岐するためです。所得税については、一定の要件を満たす給与所得者で、給与所得および退職所得以外の所得金額が20万円以下であれば確定申告をしなくてもよい扱いがあります。
一方で、年末調整されていない給与がある場合などは別の基準になり、単純に「アフィリエイト所得が20万円以下か」だけでは判断できません。
また、所得税の確定申告が不要でも、住民税(市民税・県民税)の申告が必要になる自治体がある点も重要です。この章では、給与の有無→副収入の合算→控除・還付の有無→迷った時の確認先、の順で“迷わない判定手順”に落とし込みます。
- アフィリエイトの所得:収入−必要経費(年合計)
- 給与の状況:年末調整の有無、給与が1か所か複数か
- 給与以外の所得:アフィリエイト以外の副業があれば年合計
給与ありなしで分岐
最初の分岐は「給与所得があるか(会社員などか)」です。給与がある人の多くは年末調整で所得税が精算されるため、一定の場合には確定申告をしなくてもよいとされています。そのうえで、給与の収入金額が2,000万円以下、給与を1か所から受けていて、その給与の全部が源泉徴収される人で、給与所得および退職所得以外の所得金額が20万円以下である人等は、所得税の確定申告をしなくてもよい扱いがあります。
一方、給与が2か所以上で「年末調整されていない給与」がある場合は判定が変わります。年末調整されなかった給与の収入金額と、給与・退職所得以外の所得金額の合計が20万円を超える場合など、確定申告が必要になる条件があります。
給与がない人(専業でアフィリエイト等を行う人など)は、この“給与所得者の20万円”とは別の枠で判断します。所得が基礎控除などの控除額を超えるかどうか等、全体の所得税計算で申告要否が決まるため、20万円だけで結論を出さないのが安全です(具体的な申告要否は所得や控除の状況で変わります)。
【給与ありの分岐で見るポイント】
- 給与が1か所で年末調整済みか
- 年末調整されていない給与があるか
- 給与以外の所得(アフィリエイト等)の合計が20万円を超えるか
副収入は合算で判定
20万円判定で見ているのは「給与所得および退職所得以外の所得金額の合計」です。つまり、アフィリエイト以外にも副収入がある場合は、原則として合算して20万円を超えるかどうかで見ます。たとえば、アフィリエイト所得が12万円でも、別の副業(原稿料など)で所得が10万円あれば合計22万円となり、給与が年末調整済みの会社員でも所得税の確定申告が必要になる可能性が高まります。
ただし、合計額に含めない所得があるケースもあります。株式・配当等の所得がある場合は、合算に入るかどうかが扱いによって異なる場合があるため、状況に応じた確認が必要です。
実務のコツは、まず“合算する前提”で一覧を作り、例外の可能性がある所得だけ後で確認することです。20万円判定をズレさせやすいのは「収入と所得の取り違え」と「副業の合算漏れ」なので、所得ベースで副収入を並べておくとブレません。
- アフィリエイト:所得=収入−経費
- その他の副業:所得=収入−経費
- 株式・配当等:合算に入るかは扱いにより異なる場合がある
控除や還付の関係
「申告が必要か」と「申告した方が得か」は別問題です。確定申告の義務がない人でも、源泉徴収された所得税などが納め過ぎになっているときは、確定申告をすることで還付(払い過ぎの所得税の返還)を受けられる場合があります。これが還付申告です。たとえば年の途中で退職して年末調整を受けていない、医療費控除や寄附金控除など年末調整で反映されない控除を適用したい、住宅ローン控除の初年度などは、還付申告の対象になり得ます。
注意点として、還付申告をする場合でも、その他の所得があるなら原則としてそれらも申告に含める必要があります。つまり、還付だけ狙って申告すると、結果として他の所得も含めた申告が必要になる可能性があります。
そのため、「20万円以下だから申告しない」と決める前に、還付で得になる可能性があるかを一度確認するのが実務的です。還付が見込めるなら、20万円ルールで“不要”でも、あえて申告する選択肢があります。
- 「不要なら申告しない」で終える → 還付の可能性があるか一度確認する
- 還付だけ申告したい → 他の所得も申告対象になり得る点に注意する
- 控除を入れ忘れる → 年末調整で反映されない控除がないか整理する
迷った時の確認先
判定が難しいときは、確認先を「所得税」と「住民税」で分けると早いです。所得税の申告要否は国税庁の案内(「確定申告をする必要がない方」「給与所得者で確定申告が必要な人」など)で条件が整理されています。特に給与が複数、年末調整されていない給与がある、源泉徴収の対象とされない給与がある等のケースは、国税庁の整理に沿って確認するとブレにくいです。
住民税については、市区町村が申告要否や提出先を案内しています。所得税の確定申告が不要な場合でも、住民税の申告が必要とされる自治体があるため、「所得税は不要だが住民税は?」で迷ったら、お住まいの自治体の“市民税・県民税申告”ページを確認するのが最短です。
実務の最後の一手は「条件を文章で説明できるか」です。給与の状況、給与以外の所得の合計、控除・還付の有無、住民税申告の扱いを自分のメモで説明できれば、申告要否の判断はほぼ固まります。
- 所得税:国税庁の「確定申告が必要か」関連ページで条件確認
- 住民税:市区町村の「市民税・県民税申告」ページで要否確認
- 特殊ケース:源泉徴収されない給与、給与2か所以上などは国税庁の整理を優先
申告する時の手続き
アフィリエイトの所得が20万円を超えて所得税の確定申告が必要になる場合は、①必要書類をそろえる→②申告書(必要なら決算書等も)を作成する→③提出(e-Taxまたは書面)→④納付、の順で進めると迷いにくいです。確定申告書等作成コーナーを使えば、画面案内に沿って入力するだけで申告書や収支内訳書・青色申告決算書等の作成と、e-Tax送信(提出)まで進められます。
期限も先に押さえておくと安心です。所得税の確定申告は毎年期限があり、年度によって日付が変わるため、該当年分の案内で期限を確認してから準備を始めます。あなたの所得区分(事業所得か雑所得か等)や、給与の有無・控除の状況によって必要書類が変わる場合があるため、ここでは“共通して必要になりやすいもの”を中心に整理します。
- 準備:収入(ASP明細等)と経費(領収書等)を年合計で整理
- 作成:申告書+必要に応じて収支内訳書/青色申告決算書を作る
- 提出:e-Tax送信または書面提出
- 納付:期限までに納付(方法は複数)
準備する書類一覧
申告の準備は「収入の根拠」「経費の根拠」「控除の根拠」をそろえる作業です。アフィリエイトの場合、収入はASPの確定明細・支払明細(年合計が分かるもの)や入金履歴が中心になります。経費はサーバー代・広告費・外注費など、業務に必要な支出の領収書やカード明細を集め、内容が分かる形で整理します。給与がある人は、源泉徴収票が申告書入力の前提になることが多いので用意します。控除を追加で使う場合は、控除証明書や明細書が必要になることがあります(控除の種類により異なる場合があります)。
実務でつまずきやすいのは「資料はあるのに、年合計にまとまっていない」状態です。月別フォルダで「収入(ASP)」「経費(領収書)」「支払い明細」を分け、最後に年合計へ集計すると、入力が早くなります。また、家事関連費(通信費等)を按分する場合は、割合と計算式のメモを残しておくと説明しやすいです。電子の請求書・領収書を受け取っている場合、保存方法に注意が必要になる場合があるため、削除せず保管する運用が安全です。
- 収入:ASPの確定明細・支払明細、入金履歴
- 経費:領収書・請求書・利用明細(カード明細等)
- 給与あり:源泉徴収票
- 本人確認:マイナンバーカード等(提出方法により必要)
- 控除:保険料控除証明書など(適用する場合)
- 還付:還付先口座情報(還付が出る場合)
申告書類の選び方
アフィリエイトの申告で使う書類は、基本の「確定申告書」に加えて、所得の内容によって「収支内訳書」または「青色申告決算書」を付ける形になります。白色申告で事業所得(または不動産所得)がある場合は収支内訳書、青色申告の場合は青色申告決算書を作成するのが一般的です(どちらになるかは、青色申告の承認を受けているか等で変わります)。
また、アフィリエイト収入が雑所得(業務に係るもの)として扱われる場合は、収支内訳書・青色申告決算書が必須にならないこともありますが、所得の計算根拠(収入と経費の内訳)は説明できるように整えておく必要があります。作成ツールでは申告内容に応じて入力画面が変わるため、まずは「所得の種類」選択を正しく行い、収入と経費を年合計で入力できる状態にします。
迷うポイントは「どの所得区分か」ですが、ここは継続性・営利性・記帳状況などで変わる場合がある点を前提に、案内に沿って進め、必要なら税務署等で確認するのが現実的です。少なくとも「確定申告書に何を足すか(内訳書か決算書か)」を判断できるように、青色申告の有無と、帳簿の整備状況を整理しておくとスムーズです。
- 収支内訳書/青色申告決算書を作らず止まる → 申告形態(青色か白色か)を先に整理する
- 雑所得か事業所得かで迷う → 断定せず、案内に沿って入力し必要なら確認する
- 年合計が出ていない → 先に収入・経費を年合計にしてから入力する
e-Taxと提出の流れ
提出方法は大きく「e-Taxで送信」「書面で提出」に分かれます。e-Taxは国税電子申告・納税システムで、確定申告書等作成コーナーから申告書を作成し、そのまま送信まで完結できます。送信にはマイナンバーカード等を用いる方式が一般的で、スマホで送信する場合はマイナンバーカード読取対応のスマホやアプリが必要になることがあります。
実務の流れは、①作成ツールで申告内容を入力して申告書を作成→②送信方法を選ぶ(マイナンバーカード方式等)→③送信→④送信結果を確認、という順です。
書面提出の場合は、作成した申告書を印刷して税務署へ持参・郵送する形になりますが、提出方法によって必要書類や提示の要否が変わる場合があるため、案内に沿って準備します。e-Taxは自動計算や送信控えの確認など実務面の利点があるため、可能ならe-Taxを第一候補にすると手続きが安定しやすいです。
【e-Tax提出の最小ステップ】
- 作成ツールで申告書を作成する
- 送信方法を選び、必要な準備を整える
- 送信し、送信結果を確認する
納付と期限の注意
期限は「提出」と「納付」でセットで押さえる必要があります。確定申告は年ごとに期限が定められているため、該当年分の期限を確認し、期限内に提出・納付できる計画を立てます。期限を過ぎると、延滞税などが発生する場合があるため注意します。納付方法は複数あり、キャッシュレス納付なども利用できますが、口座振替など事前手続きが必要な方法もあるため、選ぶ方法によっては早めの準備が必要です。
また、申告結果が還付(戻る)になる場合は、還付先口座情報を正確に入力することが重要です。逆に納付が発生する場合は、納付資金の確保も必要になります。納付が難しい場合に利用できる制度は条件があるため、該当しそうな場合は案内や税務署で確認します。
注意点として、アフィリエイトの申告では「所得=収入−経費」であるにもかかわらず、入金額のまま判断して申告漏れや過大申告になるケースが起きやすいです。期限前に、収入・経費・所得の年合計が合っているか、住民税の手続きが別に必要にならないかも含めて見直すと安全です。
- 所得(収入−経費)の年合計が出ている
- 提出方法(e-Tax/書面)に必要な準備が揃っている
- 納付が必要なら、期限までの納付方法を決めている
- 住民税の申告が別途必要かを自治体案内で確認している
よくある誤解と回避策
「アフィリエイト 確定申告 20万円」でつまずく人の多くは、制度が難しいというより、前提の取り違えや手順の抜けで判断がズレています。特に多いのは、20万円を“収入”だと思う誤解、経費の入れ方が極端になる誤解、所得税だけ見て住民税の手続きを落とす誤解です。さらに、給与の状況や副業の増減など“条件が変わった年”に、前年と同じ判断をしてしまうケースもあります。
回避策は、毎年の判断を「所得の計算→給与状況の確認→合算→住民税→提出方法」の順に固定することです。特に20万円ルールは、一定の給与所得者で「給与所得および退職所得以外の所得金額」が20万円以下の場合に、所得税の確定申告が不要になる扱いがある、という前提なので、まず所得を出せないと正しい判定ができません。ここでは、ありがちな誤解を4つに整理し、それぞれの対処を具体的にまとめます。
- 20万円は所得(収入−経費)で計算できている
- 給与の状況(年末調整の有無・給与が複数か)を確認した
- 給与以外の所得を合算して20万円判定した
- 住民税の手続きが別途必要かを自治体案内で確認した
収入と所得の取り違え
最も多い誤解は「アフィリエイト報酬の入金が20万円以下なら申告不要」という取り違えです。20万円ルールで基準になるのは、原則として「給与所得および退職所得以外の所得金額」であり、所得は「収入−必要経費」で計算します。したがって、入金が20万円以下でも経費がほとんどなければ所得が20万円近くになり得ますし、入金が20万円を超えても経費があれば所得が20万円以下になる場合もあります。
具体例として、アフィリエイト報酬の入金が22万円でも、サーバー代や広告費などの必要経費が5万円あれば、所得は17万円です。逆に入金が19万円でも、経費がほぼ0円なら所得も19万円で、基準に近い数字になります。ここで「収入だけ」で判断すると、必要以上に申告を恐れたり、逆に申告が必要なケースを見落としたりします。
回避策は、年に一度でよいので、ASP明細と経費を年合計にして「所得=収入−経費」を必ず算出することです。所得が出せれば、20万円判定や住民税の判断も一気に進みます。
- 基準は「所得(収入−経費)」で見る
- 入金額だけで判断しない
- 年合計で計算し、月のブレに引っ張られない
経費の入れ過ぎ不足
次に多いのが、経費を入れ過ぎる(私用を混ぜる)か、逆に経費をほとんど入れずに所得が大きく見える、の両極端です。必要経費は「収入を得るために必要な支出」に限られます。私生活の支出を経費に入れると説明が難しくなり、反対に必要な経費を落とすと、本来より所得が大きくなり、不要な申告や税負担につながる場合があります。
具体例として、サーバー代やドメイン代、広告費、取材・検証のための購入(業務に必要な範囲)、記事作成の外注費などは、業務との関係を説明しやすい支出です。一方、食費や日用品などは原則として私用になりやすく、業務との関係を明確にできないまま経費にするとリスクが高まります。通信費や電気代など家事関連費は、業務利用分を合理的に区分できる場合に限り、按分して計上する形が現実的です。
回避策は、経費を「説明できる形」で残すことです。領収書だけでなく、何のための支出かをメモし、家事関連費は按分の根拠(割合・計算式)を残します。これで入れ過ぎも不足も防ぎやすくなります。
- 業務に必要な理由を一文で説明できるか
- 証拠(領収書・明細)と内容メモが残っているか
- 私用と混在するなら按分根拠があるか
住民税の申告漏れ
20万円ルールで特に落とし穴になりやすいのが、所得税の確定申告をしない場合でも、住民税(市民税・県民税)の申告が必要になることがある点です。給与所得者で給与以外の所得が20万円以下の場合、所得税の確定申告は不要とされる一方で、自治体の住民税申告は必要と案内されることがあります。ここを知らないと「申告しなくていいと思っていたのに、住民税の手続きが必要だった」という状態になりやすいです。
具体例として、会社の年末調整だけで所得税が完結している人でも、副業所得があると住民税の計算に反映する必要があり、自治体が把握できない場合は申告が求められます。さらに、住民税の申告状況は、各種証明書の発行や、国民健康保険料などの算定に関係する可能性があるため、放置しない方が安全です。
回避策は、「所得税は不要」と判断した時点で、必ず自治体の“市民税・県民税申告”の案内を確認することです。自治体ごとに手続きの案内が整理されているので、迷ったら税担当窓口に確認します。
- 所得税の確定申告をしないと決めたら、住民税申告の要否を確認する
- 必要なら、給与以外の所得(アフィリエイト等)を住民税申告に反映する
- 不明点は市区町村の税担当窓口に相談する
条件変更時の見直し
前年と同じ感覚で判断して失敗しやすいのが、条件が変わった年です。条件変更とは、給与が増えた・副業が増えた・副業の種類が増えた・年末調整されない給与が出た・経費の構造が変わった、などです。特に給与が複数になり年末調整されない給与がある場合は、確定申告の要否が変わることがあります。また、アフィリエイト以外の副収入が増えれば、給与以外の所得を合算すると20万円を超える可能性が上がります。
具体例として、アフィリエイト所得が18万円で前年は20万円以下だったとしても、今年は原稿料の所得が5万円増えれば合計23万円となり、判定が変わります。経費も同様で、外注費や広告費を増やして所得が下がる場合もあれば、経費を入れ忘れて所得が上がる場合もあります。
回避策は、毎年同じ手順で再計算することです。収入と経費を年合計で整理し、所得を出し、給与状況と副収入を合算し、住民税の手続きまで確認します。条件が変わった年ほど、早めに数字を出しておくと、提出方法や納付資金の準備も余裕を持って進められます。
- 給与:年末調整の有無、給与が複数になっていないか
- 副業:アフィリエイト以外の所得が増えていないか
- 所得:収入−経費の年合計が前年と変わっていないか
- 住民税:所得税申告をしない場合の手続き要否
まとめ
20万円ルールは、一定の給与所得者などで「給与以外の所得」が20万円以下なら、所得税の確定申告が不要になる場合があるという考え方です。ただし、所得税の申告が不要でも住民税の申告が必要になることがあるため注意します。まず収入と経費を整理して所得を算出して確認→必要なら書類を揃えて申告して実行→翌年に帳簿の付け方や経費整理を改善、の順で進めると迷いにくくなります。