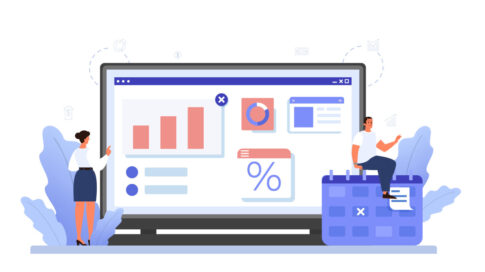アフィリエイト運用で「どこまでOKか」を迷ったら本記事。景品表示法・ステマ規制、特定商取引法、電気通信事業法の外部送信規律、個人情報保護法、薬機法までを横断解説。
PR表記や定期購入の見せ方、Cookie等データの扱い、ASP規約の要点を整理し、今日から実装できるチェックと体制づくりのヒントを示します。
目次
アフィリエイト規制の全体像—関係法令と適用範囲

アフィリエイトは「広告の表現」「販売ページの表示」「データの扱い」「分野別の広告規制」の4面からルールが関わります。まず、景品表示法は誤認させる表示の禁止に加え、広告であることを隠すステルスマーケティングを不当表示として扱います。
特定商取引法は通信販売における最終確認画面や定期購入の表示を求めます。データ面では、電気通信事業法の外部送信規律がCookie等による外部送信の通知・公表を求め、個人情報保護法は「個人関連情報」の第三者提供に本人同意が必要となる場面を定めています。
健康・美容など特定領域では、薬機法・健康増進法が効能効果の表現を制限します。これらは広告主・ASP・運営者のどこに義務が生じるかが異なるため、案件選定と表現設計の前に全体像を把握しておくことが大切です。
| 法令 | 主な対象・ポイント | アフィリエイト運用での要点 |
|---|---|---|
| 景品表示法 | 不当表示の禁止/ステマは「広告であることが分からない表示」を規制 | PR表記の明確化、誇大・優良誤認の回避、表示主体の整理 |
| 特定商取引法 | 通販の最終確認画面・定期購入の表示義務 | カート画面で価格・回数・解約方法等を同一画面で明示 |
| 電気通信事業法 | 外部送信規律(Cookie/SDK等の送信先・目的等の通知・公表) | 第三者送信の一覧・目的・オプト手段をポリシー等で提示 |
| 個人情報保護法 | 個人関連情報の第三者提供で、受領側が個人データ化する場合は同意が必要 | 広告識別子の連携やMA/CRM連携時の同意取得設計 |
| 薬機法・健康増進法 | 医薬品等・健康効果の過大表示の禁止 | 効能の断定・体験談の一般化を避け、根拠資料の範囲で表現 |
- 「表示」「販売画面」「データ」「分野別規制」の4面で点検
- 誰が表示主体か→広告である旨の明示と誤認防止を最優先
景品表示法とステルスマーケティング規制の基礎
景品表示法は、商品・役務の取引に関して、実際より著しく優良・有利であると誤認させる表示(優良誤認・有利誤認)を禁止します。
さらに、広告であるにもかかわらず一般消費者が広告と分からない表示(いわゆるステルスマーケティング)は、不当表示として扱われます。
規制の対象は「表示の主体」である事業者(広告主)で、インフルエンサー等の第三者に依頼した場合でも、広告主に措置命令等が及ぶ設計です。
実務では、レビュー・投稿・記事・動画などで、広告主からの金銭・物品提供・指示関与があるなら、読者が容易に判別できる位置・サイズ・用語で「広告・PR」を明示します。
媒体特性により省略・埋没しやすい箇所(冒頭・サムネ・タイトル付近)が誤認の温床になりやすいため、表示は導線の最初から行い、折りたたみ領域に隠さないことが大切です。
運用側は、案件ごとに推奨ラベル文言と掲出位置をテンプレート化し、差し替え時もブレないように管理します。
| 基準 | NGの典型 | 実装の目安 |
|---|---|---|
| 広告の明確化 | 本文末や小文字でのPR表記のみ | タイトル付近・冒頭・サムネ近傍に「広告/PR」を明瞭表示 |
| 誤認防止 | 体験談を一般的結果と誤認させる | 前提条件・再現性の幅を併記、根拠資料の範囲で表現 |
特定商取引法の通販ルール(定期購入・最終確認画面)
通信販売では、注文確定直前の「最終確認画面」で、価格(初回・2回目以降・総額)、支払時期・方法、引渡時期、申込み期間、返品・解約方法と条件など、契約の要点を容易に確認できる表示が必要です。
特に定期購入は、回数条件や自動継続の有無、解約期限と手続方法、次回の請求時期・発送時期を同一画面で明確に示します。
強調見出しと相反する条件を小さな注記に隠す見せ方は、特商法違反のリスクが高まります。アフィリエイト運用では、記事側で定期条件を誤解なく伝えるとともに、リンク先LPやカートの要件(最終確認画面の必須項目)が満たされているかを点検しましょう。
複数商品を同時購入させる導線では、支払総額が一目で分かる設計が重要です。案件レビュー時は、スクリーンショットで表示箇所を記録し、LP差し替えのたびに再確認する運用が安全です。
- 定期の回数・解約期限・手段→最終確認画面で並置
- 初回・2回目以降・総額→同一画面で金額を明示
電気通信事業法の外部送信規律(クッキー等の取り扱い)
改正電気通信事業法により、Webサイトやアプリで第三者に情報を送る仕組み(Cookie・SDK・タグ等)を用いる場合、送信先ごとの目的、送信先の名称、送信される情報の項目、送信先での利用目的などを、利用者に通知または容易に知り得る状態に置くことが求められます。
これは、いわゆる「外部送信規律」で、登録・届出の有無を問わず幅広いオンラインサービスが対象となり得ます。
多くのアフィリエイト媒体は分析・広告・A/Bテストのために第三者送信が発生するため、Cookieポリシー等で一覧化し、オプトアウトや同意管理の手段(選択肢)を提示すると実務上の不一致を減らせます。
なお、この規律は「透明性確保(通知・公表)」が中心で、同意の要否は別途APPI側の整理と併せて判断します。対応の根拠は、総務省・個人情報保護委員会の共同ガイドラインとその解説にまとめられています。
| 確認観点 | 必要な表示例 | 実務のポイント |
|---|---|---|
| 送信先 | ベンダー名(例:Google LLC 等) | ベンダー追加・削除時に一覧を更新 |
| 目的 | アクセス解析/広告配信/ABテスト等 | 目的ごとにグルーピングし誤解を防止 |
| 情報項目 | 識別子/閲覧履歴/端末・ブラウザ情報等 | 抽象化し過ぎず代表項目を明示 |
個人情報保護法(個人関連情報とプライバシーポリシー)
個人情報保護法は、氏名等で特定できない識別子や閲覧履歴などを含む「個人関連情報」を定義し、提供先が他情報と照合して個人データとして取得することが想定される場合、提供元で本人同意を取得することを求めます。
たとえば、広告IDと会員情報を突合してユーザープロファイル化するようなケースが該当します。実務では、プライバシーポリシーで取得情報・利用目的・第三者提供の有無と範囲を明示し、同意が必要な提供(特に他社データと結合され得る提供)には、事前にわかりやすい同意フローを用意します。
国外の第三者へ個人データを提供する場合は、移転先国の制度や受領者の保護措置の情報提供が必要になる点も重要です。
外部送信規律(電気通信事業法)と混同しやすいため、透明性の確保(通知・公表)と本人同意の要否を分けて設計しましょう
- 提供先で個人データ化(他情報と照合)され得る提供
- 国外の第三者へ個人データを提供する場合の情報提供
薬機法・健康増進法の広告規制(健康・美容ジャンル)
健康・美容系のアフィリエイトは、薬機法と健康増進法の両面に注意が必要です。医薬品・医薬部外品・化粧品・医療機器等の広告は、承認範囲外の効能効果の標榜や、誤認を与える表現が禁止されます。
食品分野では、健康増進法に基づき、健康保持増進効果等に関する虚偽・誇大な広告が禁止され、機能性表示食品や特定保健用食品の範囲を超える表現は問題になります。
体験談・ビフォーアフター画像の一般化は誤解を招きやすく、注記の埋没もリスクです。記事執筆では、効能を直接断定せず、許容される表示の範囲内で、用途・用法・注意事項をわかりやすく示し、根拠資料の在処を明確にします。
レビューやランキング企画でも、医薬品的な効能を想起させる表現を避け、表示の面積や階層で注意点を同列に掲載すると誤認が減ります。
【重要ポイント】
- 効能の断定→承認範囲外は避ける、食品は健康増進法の枠内で表現
- 体験談の一般化や誇張→前提条件と限界を併記し誤認を防止
ステルスマーケティング対応—広告の明確化と管理措置

ステルスマーケティング(広告であることが分からない表示)は、読者の判断を誤らせる代表的なリスクです。
アフィリエイトでは、記事・レビュー・SNS・動画・メルマガなど媒体が多岐にわたるため、「広告である旨の明示(PR表記)」と「社内の表示管理措置」をセットで設計することが重要です。実装の基本は、読者が最初に接触する地点で広告性を明確にし、フォールド上(画面の第一ビュー)で視認できる位置・大きさ・言葉で示すことです。
さらに、テンプレート化と点検フローをつくり、差し替え時にもブレない運用にします。外部パートナーやインフルエンサーを活用する場合は、投稿前ガイドラインの共有→サンプル原稿の事前確認→公開後のモニタリング→修正依頼という一連のプロセスを決めておくと、表現のバラつきや埋没を防げます。
読者にとって「広告かどうかが一目で分かる」状態を常に維持し、PR表記と注意点を同一面で並置する——このシンプルな原則が、長期的な信頼と成果の両立につながります。
| 対象 | 表示タイミング | 管理ポイント |
|---|---|---|
| 記事・LP | タイトル付近/冒頭/導入直下 | PR表記をフォールド上に配置→小文字や薄色で埋没させない |
| SNS・動画 | 本文冒頭/サムネ・タイトル付近/固定コメント | #PR 等の明確語+説明文→概要欄だけに依存しない |
| メルマガ | 件名または冒頭 | PRを件名近傍に明示→本文末のみは避ける |
- 最初の接点で広告性を明示→フォールド上・十分なサイズ
- テンプレ・点検・記録の3点セットで差し替え時も維持
PR表記の基本と明瞭性の要件
PR表記の目的は、読者が「これは広告だ」と即座に認識できる状態を作ることです。したがって、表示位置はタイトル付近や導入直下など、視線の最初の到達点に置きます。文字は本文と同等以上のサイズ・コントラストで、薄色・極小文字・折りたたみ内への格納は避けます。
用語は「広告」「PR」「提供」「タイアップ」など、曖昧さの少ない表現を用い、ハッシュタグのみの依存は避けてテキスト説明を添えると誤解が減ります。
画像主体の投稿やサムネイルでは、画像内にもPRを重ね、代替テキストやキャプションにも明示して埋没を防ぎます。
長文記事では、冒頭だけでなく本文中の広告ブロックの直前にも小見出しで再掲し、ページ遷移やスクロールでPR表記が視界から消える状態を減らします。
複数の案件を並べる比較記事では、ページ最上部の全体PR明示に加え、案件ごとのブロックでも個別に広告性を示す二段構えが実務的です。
公開後は、デバイス(スマホ優先)とダークモードでの視認性をチェックし、画面幅による折返しでPRが下段に落ちないかを確認すると安定します。
| 要件 | 実装例 | NG例 |
|---|---|---|
| 位置 | タイトル直下・導入1段落目に[PR] | 本文末や折りたたみ内のみ |
| 表現 | 「広告/PR/提供」など明快語+短い説明 | 暗黙の絵文字・曖昧な比喩のみ |
| 可視性 | 本文同等以上のサイズ・十分なコントラスト | 極小文字・薄色・背景と同系色 |
【チェックリスト】
- フォールド上にPRがある→スクロール前に認識できる
- テキスト説明付き→ハッシュタグだけに依存しない
- 画像内の隅に極小でPR→ダークモードで消える
- ページ上部に要素を追加した結果、PRが下段へ押し出される
口コミ・レビュー・SNS投稿での留意点
口コミやレビューは信頼感を生む一方で、広告関与があるのに明示が不足すると誤認につながります。金銭・物品・クーポン提供、原稿の事前確認や指示など、広告主の関与がある場合は、投稿の冒頭でPRを明記し、読者がすぐに把握できるようにします。
体験談は個別事例であり、一般的結果ではないことを併記し、期間・前提・作業量などの条件を簡潔に示すと期待値のズレを防げます。
SNSでは、#PR のみでなく、本文に「本投稿は広告を含みます」等の平易な文章を加え、固定コメントやプロフィールにも補足を置くと、再共有時の単体表示でも広告性が伝わります。
動画はサムネ・タイトル・概要欄・固定コメントの複数箇所でPRを重ね、口頭でも短く明示すると、視聴開始位置が分散しても誤認を減らせます。
レビュー集約ページでは、編集部作成分と提供品レビューを明確に区別し、表示ラベルの色・形状を統一して見落としを防ぎます。
第三者の体験を引用する際は、引用元・編集有無・提供の有無を明示し、擬似レビュー(自作他称)と混同されないように運用してください。
| 場面 | リスク | 実装ポイント |
|---|---|---|
| SNS投稿 | 本文のみ表示時にPRが見えない | #PR+本文で明示→固定コメントにも再掲 |
| 動画 | 途中視聴で冒頭のPRが見逃される | サムネ/タイトル/口頭/概要欄の四重明示 |
| レビュー集約 | 提供レビューと自発レビューが混在 | ラベルとセクションを分離→凡例で説明 |
- 冒頭でPR明示→再共有・単体表示でも認識できる配置に
- 体験談は条件と限界を併記→一般化を避ける
広告主の表示管理措置(景表法26条)の実務
広告主は、委託・提携先が行う表示も含め、誤認を招く表示を防ぐための「表示管理措置」を講じる責務があります。
実務では、①ガイドライン整備(PR表記の位置・文言・サイズ、体験談の扱い、注意書きの並置ルール)②契約条項(遵守義務・修正指示への対応・違反時の措置)③公開前チェック(テンプレ・チェックリストによる事前確認)④公開後モニタリング(クローリングと目視点検)⑤記録・改善(修正依頼履歴・完了確認・再発防止)という流れで体制化します。
ASP経由の案件でも、広告主・運営者・制作会社の役割と承認フローを明文化し、差し替え・キャンペーン時にPR表記が埋没しないようチェックポイントを固定化することが有効です。
外部パートナーには初回オンボーディングでサンプルの「良い例・悪い例」を配布し、更新時は差分レビューで変更点のみを素早く点検します。記録はスクリーンショットとURL、日時、担当者、判断根拠まで残し、問い合わせ発生時に迅速に説明できる状態を保ちましょう。
| 工程 | 管理措置 | 記録・証跡 |
|---|---|---|
| 事前 | ガイドライン・契約条項・テンプレ配布 | 最新版の配布ログ・受領確認 |
| 公開前 | チェックリストで位置・文言・可視性を点検 | レビュー記録・差し戻し履歴 |
| 公開後 | モニタリング→修正指示→再確認 | スクショ・URL・日時・担当者・完了記録 |
【チェックリスト】
- 役割分担と承認フローが文書化され、代替要員でも運用可能
- 差し替え・季節企画でPR表記が埋没しない仕組みがある
- スマホ表示・ダークモードでPRが視認できない
- UGCやリポストに広告性が継承されない
価格・条件表示の実務—誤認防止のUI/文言

価格や条件は、読者の意思決定に直結します。特に定期購入や初回割引の訴求では、強い見出しと矛盾しない位置・サイズで「次回以降の金額」「回数・自動継続の有無」「解約期限と手続き」を同じ画面に並置することが重要です。
ページ上部に魅力的な価格を出し、注意点を下層や折りたたみへ分散させる設計は誤認の温床になります。
実装面では、CTA(申込みボタン)近傍に主要条件を再掲し、金額は「初回→2回目以降→合計」の順で読み下せる構造にします。送料・手数料・クーポン適用後の最終額も一目で分かるよう、表組みや合計欄を活用して視線の迷いを減らしましょう。
スマホ優先で文字サイズとコントラストを確保し、ダークモードでも可読性が落ちないかを点検すると、誤解と離脱を同時に防げます。
| 領域 | 誤認が生まれやすい点 | 実装の要点 |
|---|---|---|
| 価格 | 初回だけの価格を全体価格と誤解 | 初回・2回目以降・合計を同一画面で縦並び表示 |
| 定期条件 | 自動継続・最低回数・解約期限の埋没 | CTA近傍に回数・期限・方法を再掲→折りたたみ不可 |
| 費用内訳 | 送料・手数料・割引後の最終額が不明 | 合計欄で内訳と最終額を同列提示→例示も併記 |
- 主要条件は同じ画面・同じ階層で並置→離れた注記にしない
- CTA近傍に「次回金額・回数・解約方法」を再掲→迷いを減らす
定期購入の表示義務と解約条件の見せ方
定期購入の訴求では、初回の安さだけを強調すると「想定外の継続費用」による不満が生じやすくなります。
ページでは、まず読者が目にする導入部で「自動継続の有無」「最低回数」「次回以降の金額」「請求・発送サイクル」を明確化し、CTA近傍で解約手続き(期限・手段・受付時間)を再掲します。
文言は「◯日までの連絡で翌月停止」「マイページ→契約一覧→解約」など、行動を具体的に想像できる粒度にし、メールのみ・電話のみといった窓口の制約も同列で示すと誤解が減ります。
初回と2回目以降の金額はフォントサイズや色のコントラストを揃え、初回だけ極端に大きくしないことがポイントです。
加えて、回数条件のある割引は「何回受け取ると総額いくらになるか」を例示すると納得感が高まります。スマホ表示では1画面内に要点が収まるよう、テキストと表を組み合わせ、折りたたみ領域に重要条件を隠さない設計が安全です。
| 項目 | UI/文言の例 | 確認ポイント |
|---|---|---|
| 金額 | 初回1,000円→2回目以降3,000円→合計例6,000円 | 初回だけ強調しない/合計の例示を併記 |
| サイクル | 30日ごとに自動お届け・請求は発送日の翌日 | 請求と発送のズレ・休止可否を明記 |
| 解約 | 次回発送7日前までにマイページ→契約一覧→解約 | 期限・手段・受付時間を同列で表示 |
【表示の手順】
- 導入部で自動継続・最低回数・次回金額を明示
- CTA近傍に解約方法と期限を再掲→折りたたみ不可
- 合計例で総負担を提示→納得感を担保
- 初回価格のみ極大表示→2回目以降は小文字で埋没
- 解約期限をFAQだけに記載→CTA周辺に不在
最終確認画面で必須の表示項目
注文ボタン直前の「最終確認画面」は、読者が条件を最終チェックする場所です。
ここで必要なのは、商品名・数量・各単価・送料・手数料・割引・消費税込みの合計金額、支払い方法とタイミング、配送・提供時期、連絡先、そして定期購入なら回数・次回以降の金額・解約期限と方法までを、一つの画面で俯瞰できる構成です。
項目が別ページや折りたたみに分散すると、総額や条件が把握しづらくなります。スマホではスクロールが前提になるため、合計欄を固定表示にして金額変動が即時反映されるようにし、クーポン適用後の最終額を明確に示すと安心感が高まります。
ボタン周辺には「注文確定で料金が発生する」などの重要文言を短く再掲し、文量は最小限に保ちつつ、リンクで詳細へもアクセスできる二段構えが扱いやすい設計です。
| 区分 | 必須情報の例 | UIの工夫 |
|---|---|---|
| 金額 | 各単価・送料・手数料・割引・税込合計 | 合計欄を固定/内訳を折りたたまず同列表示 |
| 支払い | 方法・請求タイミング・分割の有無 | 選択変更で合計が即更新→誤認を防止 |
| 提供 | 発送・提供時期、連絡先(窓口・営業時間) | CTA近傍に短文で再掲→詳細は別ページへ |
| 定期条件 | 次回以降の金額・回数・解約期限と方法 | 金額欄と同階層で表示→小文字・淡色は避ける |
- 合計額・次回金額・解約方法が同一画面で完結している
- クーポン適用後の最終額が即時に反映・表示される
注意書きの配置・可読性と情報の並置
注意書きは量より「配置」と「対比」が肝心です。強い訴求(特別価格・初回無料など)の近くに、関連する制約(回数条件・自動継続・解約期限)を同階層で並置し、本文同等の文字サイズと十分なコントラストを確保します。
画像内の淡色テキストや脚注番号だけで下部に誘導する見せ方は、スマホ環境で読み落としが増えます。重要な注意点はテキストで表示し、折りたたみは補足情報に限定しましょう。
文言は「後から分かった」感を生まない具体性を意識し、期限・手段・受付時間など行動に直結する要素を短文で示すと誤解が減ります。
ページ改修時は要素の追加で注意書きが下段に押し出されないか、ダークモードで可読性が保たれるかを点検し、デバイス別にスクリーンショットで記録しておくと再発防止に役立ちます。
| 注意文 | 悪い配置 | 良い配置 |
|---|---|---|
| 回数条件 | ページ最下部の脚注のみ | 価格訴求の直下で同サイズ・同コントラスト表示 |
| 解約期限 | FAQページにのみ記載 | CTA近傍で「◯日前まで/手段」を短文で再掲 |
| 追加費用 | リンク先に分散表示 | 合計欄に内訳と最終額を同列提示→例示を添える |
【チェックポイント】
- 重要な注意文は訴求の近接位置に配置→折りたたみは避ける
- 文字サイズとコントラストを本文並みに統一→色だけに依存しない
追跡技術・データ取扱い—外部送信規律とAPPIの関係

アフィリエイト運用では、計測タグ・広告タグ・SDK・埋め込みウィジェットなどを通じて、利用者の端末から第三者へ情報が送られます。
ここで関係するのが「電気通信事業法の外部送信規律(通知・公表で透明性を確保)」と「個人情報保護法(APPI:同意・第三者提供・国外移転などの要件)」です。
前者は、送信先・目的・情報項目などを利用者に分かるよう示すことが中心で、同意は原則要件ではありません。一方、後者は、個人関連情報の提供が受領側で個人データ化され得る場合に「本人同意」が必要となるなど、状況により選択すべき措置が変わります。
したがって、まず「どのタグ/SDKが、誰へ、何の目的で、どの情報を送るのか」を棚卸しし、外部送信規律での公表・通知の実装を行ったうえで、APPI側で同意が必要となるパターンに該当するかを判定する流れが実務的です。
媒体・LP・アプリを横断して、送信の可視化(台帳化)→公表ページの整備→同意/オプト手段の分岐を揃えると、改修や差し替え時にも一貫性を保てます。
| 枠組み | 主な目的・ポイント | 実務の要点 |
|---|---|---|
| 外部送信規律 | 第三者への送信の透明化(送信先・目的・情報項目等の通知/公表) | タグ/SDK台帳→公表ページに反映。更新時は差分管理 |
| APPI | 本人の権利保護(同意・第三者提供管理・国外移転の説明等) | 個人関連情報の第三者提供に該当するか判定→同意や契約で補強 |
- タグ/SDKの棚卸し(送信先・目的・情報項目・設置場所)
- 外部送信の公表ページを作成→変更ログと責任者を明記
外部送信規律の対象判断と「真に必要な情報」
外部送信規律の対象は、サイトやアプリが利用者の端末から第三者へ情報を送る仕組み(Cookie、広告タグ、解析タグ、SDK、埋め込み等)です。
対象判断の第一歩は「送信の相手が事業者外(第三者)か」「送信の起点が利用者端末か」を見ることです。委託先クラウドであっても、実体として第三者に送るなら原則として開示の対象に含めます。
なお「真に必要な情報」という考え方は、ログイン維持・カート保持・セキュリティなど、役務の提供自体に不可欠な情報を指し、広告・行動解析・A/Bテストのような付加価値系とは区別されます。
不可欠な情報であっても、送信先・目的・項目の明示は基本であり、免除を意味するものではありません。
実装では、機能系(セキュアCookie、セッションID、CSRF対策)と付加価値系(計測ID、広告識別子、閲覧イベント)を区別して台帳化し、ユーザーが誤解しやすい要素(クロスサイト識別・リマーケティング・SNS連携)を平易な言葉で記載します。
グレーなケース(サーバーサイド計測やCDP連携など)は、送信経路と受領主体を図解して判断根拠を残すと改修時の迷いが減ります。
| 類型 | 具体例 | 記載の要点 |
|---|---|---|
| 機能提供に必須 | ログイン維持、カート、決済の不正検知 | 目的を機能名で明示。保存期間や無効化の影響も説明 |
| 付加価値(計測/広告) | アクセス解析、リマーケ、A/Bテスト | 送信先・目的・情報項目を具体化→誤解しやすい点を補足 |
| 埋め込み | SNSタイムライン、動画プレイヤー | 埋め込み先が取得する項目・目的を別立てで説明 |
- 「委託だから第三者ではない」→受領主体が外部なら原則開示対象
- 「匿名IDなら対象外」→外部送信は識別可能性の有無に依らず透明化が基本
公表・通知・同意・オプトアウトの選択肢
実務では、ユースケースごとに「公表/通知」「同意」「オプトアウト」を組み合わせて設計します。外部送信規律は透明性(通知または容易に知り得る状態の公表)が中心で、常に同意が必須ではありません。
ただし、個人関連情報の第三者提供が受領側で個人データ化され得る場合など、APPIの要件で同意が必要になることがあります。
広告のパーソナライズのように選好の反映が望ましい場合は、同意ではなく「設定でオフにできる」オプトアウトの導線を用意すると、ユーザー体験と運用負荷のバランスを取りやすくなります。
海外ベンダーを多用する場合やマルチサイト運用では、同意管理ツール(CMP)を導入し、「同意が必要な処理」と「公表で足りる処理」を分岐させると保守性が上がります。
| ユースケース | 推奨する措置 | 実装のヒント |
|---|---|---|
| アクセス解析 | 公表/通知+オプトアウト導線 | ベンダー名・目的・項目を明示→停止方法を分かりやすく案内 |
| 広告パーソナライズ | 公表/通知+オプトアウト(必要に応じ同意) | パーソナライズON/OFFをUI化→同意要件はAPPIで判定 |
| 会員データ連携 | 公表/通知+本人同意(該当時) | 個人関連情報の第三者提供に該当する場合は明示的同意を取得 |
- 外部送信一覧:Cookie/外部送信ポリシーに集約し、プライバシーにリンク
- 同意/設定:バナー・フッター・マイページの3箇所から到達可能に
個人情報保護法との整合とポリシー整備
APPIの整合では、まず「収集する情報の分類(個人データ/個人情報/個人関連情報)」と「第三者提供の有無・範囲」を切り分けます。
広告IDや閲覧履歴などの個人関連情報を第三者へ提供し、受領側で他データと照合して個人データ化することが想定される場合は、提供元で本人同意の取得が必要になります。
国外の受領者に個人データを提供する場合は、移転先の制度・保護措置の情報提供も求められます。これらを踏まえ、プライバシーポリシーには「取得項目」「利用目的」「第三者提供(目的・範囲・同意要否)」「保管期間」「問い合わせ窓口」を明記し、外部送信規律の公表ページ(送信先・目的・項目・停止方法)と相互リンクさせると、利用者が迷いません。
運用面では、台帳(データマップ)を最新化し、LP差し替えや新規タグ追加時にポリシーとバナー設定を同時更新するワークフローを定着させることが重要です。監査の観点では、変更履歴・審査記録・問い合わせ対応ログを保管し、説明可能性を担保しましょう。
| ドキュメント | 最低限の記載 | 運用ポイント |
|---|---|---|
| プライバシーポリシー | 取得項目・目的・第三者提供・保管期間・連絡先 | APPI要件の同意が要る処理を明確化→変更時に速やかに更新 |
| 外部送信一覧 | 送信先・目的・情報項目・停止/設定方法 | タグ追加/削除の差分反映。多言語・スマホ画面で可読性を確認 |
| 同意/設定UI | ON/OFFの選択肢、再設定動線 | フッター常設・マイページから再設定可能に |
- サーバーサイド計測やCDP連携の外部送信も一覧に反映しているか
- 埋め込みSNS/動画の取得項目と目的を明記しているか
ASP・プラットフォーム規約の遵守ポイント

アフィリエイトでは、ASP(アフィリエイトサービスプロバイダ)の規約と、検索・SNS・動画・メルマガなど配信先プラットフォームのポリシーを同時に満たす必要があります。どちらか一方でも逸脱があると、案件停止や報酬取消、アカウント制限など実害が発生します。
まず押さえたいのは、禁止事項の型を知り、曖昧な表現を自分の言葉に翻訳して解釈を合わせることです。次に、案件差し替えやキャンペーン追加の度に規約の再点検を行い、掲載物(記事・LP・クリエイティブ)の最新版だけでなく履歴も保管しておくことが安全です。
媒体側の編集ガイドを整備し、PR表記・価格表示・体験談の扱い・キーワード利用の境界線をテンプレート化すると、チーム内のブレが減ります。
最後に、検索やSNSのアルゴリズム更新でグレーになる箇所が出やすいため、変更が起きたら「文言」「配置」「導線」を最小修正で合わせられる運用フローを用意しておくと復旧が速くなります。
| 領域 | 主な禁止・制限 | 運用の要点 |
|---|---|---|
| ASP規約 | 誇大表示、商標入札、広告文改変、自己成果の不正計測、クリック誘導 | 案件詳細の禁止事項を抜き出し、記事テンプレに反映 |
| 検索/SNS | ステマ、スパム的誘導、誤認表示、危険な医療・健康訴求 | PR明示と注意点の並置、医療・金融は表現粒度を統一 |
| 広告配信 | 不適切ターゲティング、虚偽主張、ブランド毀損 | 審査NGパターンをナレッジ化、入稿前チェックを定例化 |
- 案件ごとに「禁止事項抜き出し表」を作成し、テンプレへ反映
- 差し替え時の再点検フローとスクリーンショット保管をルール化
ASPの禁止事項と表現ルールの読み方
ASP規約は、案件ページの「禁止事項」「表現ルール」「リスティング条件」「承認基準」「否認事由」に散在しがちです。読み方のコツは、禁止の型をカテゴリ化し、自分の媒体にどう影響するかを具体化することです。
代表例として、商標やブランド名を含むキーワードでの入札や見出し使用の禁止、広告主が指定した文言・価格・画像の無断改変、体験談の断定や医療的効能の強調、クリックを目的化する訴求(アンケート・ポイント付与での誘導)、自己アフィリエイトの不正活用、Cookieを強制付与する手法(いわゆる不正計測)などが挙げられます。
これらは一見一般論ですが、案件ごとに許容ラインが異なる点が実務の難所です。案件詳細に例示が少ない場合は、過去の否認事由や審査NG事例を自分たちで収集し、禁止の「境界線」を可視化しましょう。
表現ルールは、PR表記の位置や注意書きの面積、定期購入の条件の出し方などUI寄りの指定が含まれることも多いため、編集ガイドとデザインパーツを連動させると抜けが減ります。
【チェックポイント】
- 商標・ブランド名の扱い(見出し/比較表/入札の可否)を明文化
- 価格・特典・画像の改変可否と、更新時の差し替え期限を明示
| 区分 | 典型の禁止事項 | 確認ポイント |
|---|---|---|
| 検索連動 | 商標入札、誤認を招く広告文、直リンク不可 | 入札可否、表示URL/遷移先の指定、否認キーワード |
| コンテンツ | 誇大/断定、医療・健康の効能強調、虚偽レビュー | 根拠の提示、体験談の前提/限界の併記、PR表記の位置 |
| 計測 | 不正なCookie付与、自己成果の水増し | 計測タグの設置手順、自己購入・同一IPの扱い |
- 「比較は可」だが商標+レビューの見出しは禁止→タイトル設計で違反
- 指定画像の縦横比変更が不可→自動最適化でリジェクト
逸脱時の影響(案件停止・報酬取消)の理解
規約逸脱の影響は、目先の掲載停止にとどまりません。軽微な場合でも該当記事の修正・非表示、一定期間の案件停止が発生します。重い場合は、該当期間の報酬取消や遡及否認、媒体全体の新規案件受け入れ停止、最悪はASPアカウントの制限や解約に至ることがあります。
広告主側の審査部門に負荷を与えると、同ジャンル案件への参加が難しくなるなど、中長期の機会損失が生じます。さらに、検索・SNSのポリシーにも抵触していると、流入減やアカウント警告が重なり、回復に時間がかかります。
損失を最小化するには、発覚時の初動手順をあらかじめ決めておくことが重要です。具体的には、掲載停止→該当箇所の特定→根本原因の切り分け(文言/配置/導線/入札)→一次対処(非表示・修正)→ASP/広告主への報告→再発防止の反映、という順で動きます。
報告ではスクリーンショット・URL・掲載期間・トラフィック影響・修正内容をまとめ、再発防止のチェック項目をガイドに追記してクローズします。
【手順】
- 違反疑いを検知→該当URL/箇所を特定し一時非表示
- 原因(表現/配置/計測/入札)を分類→一次修正
- ASP/広告主へ経緯・対処・再発防止を報告→ガイドに反映
| リスク | 起こり得る影響 | 予防の要点 |
|---|---|---|
| 案件停止 | 掲載ストップ、入稿差し戻し | 差し替え時チェックリスト、承認フローの明文化 |
| 報酬取消 | 遡及否認、収益の一時的な断絶 | 根拠の明記、価格・条件の並置、PR表記の再掲 |
| アカウント制限 | 新規案件不可、全体の信頼低下 | 違反例のナレッジ化、事前レビューの定例化 |
運用フロー(監修・更新・差し替え)の体制化
規約遵守を継続するには、個人の注意ではなく「回る仕組み」を作ることが近道です。基本は、監修(レビュー)・更新(定期点検)・差し替え(案件変更時)の3工程を分離し、責任者と期限を決めます。
監修では、入稿前にPR表記の位置、価格と定期条件の並置、体験談の前提併記、禁止キーワードの有無をチェックリストで確認します。更新は月次や四半期で実施し、主要ページのスクリーンショットと数値(クリック/EPC/承認率)を添えて陳腐化を検出します。
差し替えは、案件の価格・特典・LP変更や、検索/SNSのポリシー更新時に実施し、変更点だけを素早く点検できる「差分レビュー」を採用します。
最後に、デバイス別(スマホ優先)とダークモードでの可読性を毎回確認し、PRや注意文がレイアウト変更で下段に落ちていないかを見ます。小さな改善を積み重ねることで、審査通過率と承認率の安定につながります。
| 工程 | 目的 | 最小アウトプット |
|---|---|---|
| 監修 | 規約適合の担保 | チェックリスト、指摘箇所の修正ログ |
| 更新 | 陳腐化の発見と修正 | 月次レビュー記録、スクショ、数値メモ |
| 差し替え | 変更点の迅速反映 | 差分レビュー、改修前後の比較表 |
- チェックリストを記事テンプレに埋め込み→誰でも同じ品質に
- 差分レビューで「変えた所だけ」素早く承認→速度と正確さを両立
まとめ
アフィリエイト規制の要は、広告の明確化、価格・条件の可視化、データの適法運用、ASP規約の順守です。
法令と運用ルールを同じ画面でわかるように設計し、更新・監修・差し替えを仕組み化すれば、誤認と停止リスクを最小化できます。まず自社基準とチェック表を整え、小さく実装しましょう。