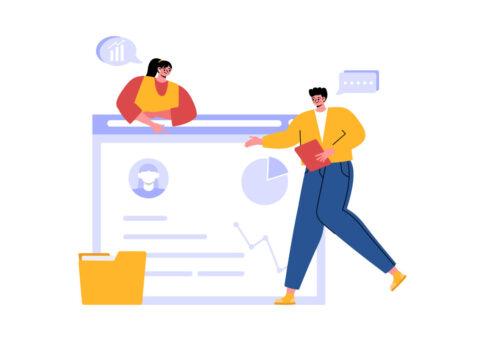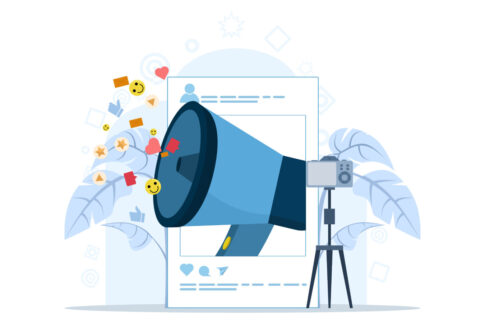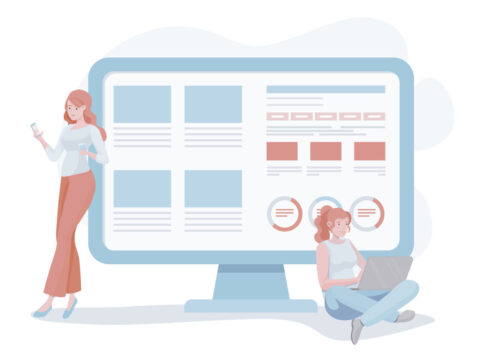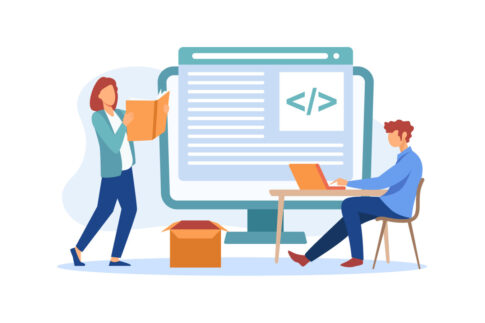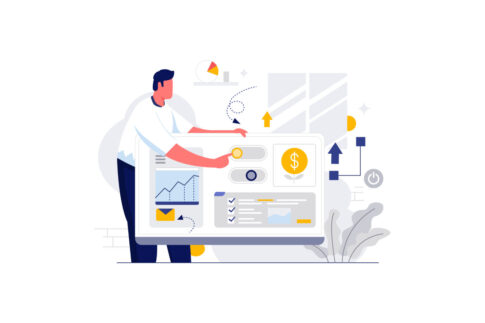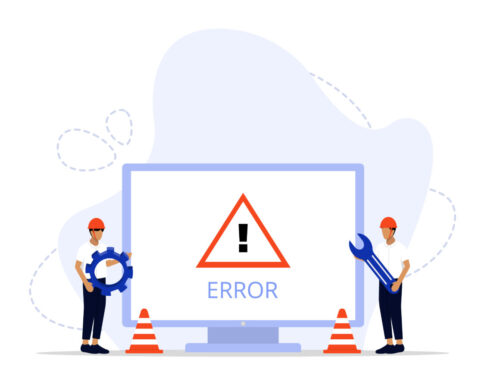「AmebaPickは複数アカウントで使えるの?」という疑問に、運用ルールと切替手順、注意点をまとめて解説していきます。
Ameba本体とAmebaPickの違い、申請・承認の扱い、報酬受取(ドットマネー)の分離、誤掲載を防ぐ設定、ペナルティ回避まで網羅。初めてでも迷わず安全に運用できます。
目次
AmebaPickは複数アカウントの運用可能?

結論からお伝えすると、アメブロ本体は複数のアメーバID(=複数ブログ)を持つことができますが、AmebaPickは「1つのAmebaIDにつき1アカウント」が原則です。
さらに、報酬受取で使うドットマネー口座は“1個人1口座”が原則で、複数口座の作成・併用はできません。
つまり「複数ブログ=複数のAmebaPick口座OK」ではなく、安易な複数登録は規約違反の恐れがあります。
運用の考え方としては、①ブログ側はテーマ別にIDを分けつつ、②AmebaPickは各IDの規定に従い1アカウントで適正に利用、③報酬受取は正しい名義で一元管理、が安全です。外部ASPのリンク掲載はアメブロ内では不可のため、収益化はAmebaPickの範囲に限定します。
誤解しやすいのは「複数IDでAmebaPickを同時登録」や「名義の異なる受取口座を使い分け」するケースですが、どちらも審査・運営上のリスクが高く推奨されません。
【押さえたい要点】
- アメブロ:複数ID(複数ブログ)自体は作成可/同一メールでの複数登録は不可
- AmebaPick:AmebaIDごとに1アカウントが原則/無断の複数登録は不可
- ドットマネー:1個人1口座が原則/複数口座の併用は不可
- 収益化はAmebaPickに限定(外部ASPは不可)
- 報酬受取は正しい名義の1口座で一元管理
Ameba本体とAmebaPickの違い
アメブロ本体(ブログサービス)とAmebaPick(公式アフィリエイト機能)は“できること”と“求められるルール”が異なります。
アメブロ本体は、目的別に複数のアメーバIDを作り、ジャンルごとにブログを使い分けることが可能です(ただし、同一メールアドレスでの複数登録は不可)。
一方のAmebaPickは、広告配信・報酬付与を扱う性質上、本人確認と名寄せが重視され、「AmebaID1つにつきAmebaPick1アカウント」という紐づけが基本となります。
報酬はドットマネーで管理されるため、受取口座は1個人1口座で、複数作成や併用は認められていません。
実務では、たとえば「日記用」「専門ブログ用」とIDを分けるのはOKですが、両方でAmebaPickのアカウントを“無断で”重複作成したり、報酬を複数口座に分散させたりするのはNGです。
運用上の混同を避けるには、①どのIDにどのAmebaPickアカウントが紐づくかを台帳化、②報酬受取は常に同一名義・同一口座、③記事の収益リンクはAmebaPick内の生成リンクだけを利用、というルールで運用すると安全です。
【違いの整理】
| 対象 | 運用のポイント |
|---|---|
| アメブロ本体 | 複数ID(複数ブログ)作成は可/同一メールでの複数登録は不可 |
| AmebaPick | AmebaIDごとに1アカウントが原則/無断の複数登録は不可 |
| ドットマネー | 1個人1口座が原則/複数口座の作成・併用は不可 |
利用規約と禁止事項の該当
複数アカウント運用で最も注意すべきは「どこからが規約違反か」を具体的に理解することです。
代表的なNGは、①AmebaPickの“無断”複数アカウント登録(AmebaID単位の原則に反する)、②ドットマネーの複数口座の作成・併用(1個人1口座に反する)、③外部ASPリンクの掲載(アメブロでは不可)です。
さらに、コンテンツ面では薬機法・景表法に抵触する誇大表現、著作権・肖像権の侵害、公序良俗違反、誹謗中傷なども審査・運用の停止対象になります。
具体例として、同一人物が複数IDでAmebaPickの申請を繰り返し、報酬を別名義・別口座に分散する行為は典型的なリスクです。
また、過去記事に外部ASPのバナーが残っている状態で申請・運用するのも差し戻し・停止の火種になります。
リスクを避けるためには、申請前に「本人情報・リンク運用・表現」の3点を横断チェックし、特にリンクはブログ内検索で“外部ASPの残骸”を一掃するのが近道です。
- 無断のAmebaPick複数登録をしていない(IDごとに1アカウント)
- ドットマネーは1口座のみ(名義の分散・複数作成なし)
- 外部ASPリンクは未掲載(過去記事の残存も削除済み)
【実務のコツ】
- ブログごとに「収益リンクの出所」を統一(AmebaPickのみ)
- 報酬受取は同一名義で一元管理→口座や名義の分散をしない
- 表現・素材は法令とガイドラインに適合(根拠不明のNo.1・断定効能は避ける)
複数アカウント運用の基本と管理

複数のアメーバIDでブログを運用する場合は、まず「アカウントごとの目的・役割・導線」を明確に分けることが重要です。日記・実績・商品紹介などテーマを混在させると、AmebaPickの審査や読者の信頼に影響します。
実務では、ID単位でプロフィール文・ヘッダー画像・アイコン色を変えて識別性を高め、台帳(スプレッドシート)で「ID/担当者/目的/掲載可能テーマ/禁止事項/AmebaPickの可否」を管理します。
ログインは端末やブラウザプロファイルで分け、同一ブラウザの同時ログインを避けると誤投稿のリスクが下がります。
記事制作は「下書き→プレビュー→公開」の順で必ず本人確認を挟み、AmebaPickのリンクは各IDの管理画面から生成したもののみを使う運用に統一しましょう。
収益リンクを貼る前には、外部ASPリンクが混入していないかをブログ内検索で横断チェックし、導線を一本化しておくと安心です。
【基本方針】
- アカウントごとに目的・読者層・掲載範囲を定義し台帳で一元管理
- 端末/ブラウザ/プロファイルを分け、同一環境での多重ログインを回避
- 収益リンクは各IDの管理画面から生成したAmebaPickのみを使用
| 区分 | 運用の要点 |
|---|---|
| 識別 | プロフィール文・アイコン色・ヘッダーでアカウント名を明示 |
| 制作 | 下書き→プレビュー→公開の三段階でアカウント名を目視確認 |
| リンク | AmebaPick生成リンクのみ使用/外部ASPリンクは事前に排除 |
ログイン切替とアカウント分離のコツ
複数アカウント運用でのトラブルの多くは、ログイン切替時の取り違えです。対策の基本は「環境を分ける」「自動サインインを制御する」「確認ポイントを固定化する」の三点です。
PCではChrome等のブラウザでプロファイルをアカウントごとに作成し、プロファイル名とアイコンをアカウント名に合わせます。
片方は通常ウィンドウ、もう片方はシークレットで検証するなど、閲覧と投稿の環境を分離すると誤投稿が減ります。
スマホは「業務用(投稿)」「個人用(閲覧・確認)」でアプリとブラウザを使い分けると安全です。パスワード管理アプリでは、フォルダ名をアカウント名にし、オートフィルは切替作業の間だけ一時停止します。
切替手順は常に同じ順番で行うとミスが減るため、「ログアウト→未ログイン表示確認→目的IDでログイン→プロフィール名を目視」の型を徹底しましょう。
【切替の標準フロー】
- 現在のプロフィール名を確認→ログアウト→未ログイン表示を確認
- 別プロファイル(または別ブラウザ)で目的IDにログイン
- ダッシュボードでアカウント名・アイコンを目視確認→作業開始
- ブラウザプロファイル名=アカウント名(色も固定)
- プレビュー確認は必ず別プロファイル/別端末で実施
【具体例】
- PC:プロファイルA(業務ブログ)=通常ウィンドウ/プロファイルB(趣味ブログ)=別ウィンドウ
- スマホ:アプリは閲覧専用、投稿時はPCから実施→誤アカウント投稿を回避
記事・リンクの誤掲載を防ぐ設定
誤掲載防止は「見た目で気付ける工夫」と「公開前チェックの固定化」で大きく改善します。まず、各アカウントのテーマカラー・ヘッダー・ブログタイトルにアカウント名を含め、エディタ上でも一目で判別できるようにします。
記事テンプレートの冒頭に【この記事の掲載先:◯◯(アカウント名)】と入れておくと、下書き段階で誤りに気づけます。
AmebaPickのリンクは、必ず対象IDの管理画面からその場で生成し、過去記事のコピペで流用しない運用にすると混入を防げます。
公開前には「アカウント名・プロフィール名・ヘッダー」「記事内のAmebaPickリンクの遷移先」「外部ASPリンクがゼロであること」を固定の順でチェックしましょう。
万一の誤掲載に備えて、公開直後5分はプレビュー端末で表示確認を行い、問題があれば即時下書き戻しする体制を決めておくと安心です。
| 起きやすいミス | 予防設定・運用 |
|---|---|
| 別IDで公開 | ブログタイトルにアカウント名を含める/テンプレ冒頭で掲載先を明記 |
| リンク混在 | AmebaPickは各IDで都度生成/過去記事のリンク流用を禁止 |
| 外部ASPの混入 | 公開前にブログ内検索(http, aff, utm 等)で一括確認 |
- アカウント名・プロフィール・ヘッダーの一致を確認
- 本文内のAmebaPickリンク→遷移先とIDを確認
【運用のコツ】
- 記事テンプレに「この記事の掲載先:◯◯」を固定挿入→下書きで視認
- 公開直後5分は別端末で表示確認→問題あれば即下書き戻し
AmebaPick連携の設定と審査ポイント

AmebaPickを複数アカウント(複数のAmeba ID)で安全に使うには、連携の「初期設定」と「審査の見られどころ」を分けて準備するのが近道です。まず、各IDのプロフィール・連絡先・ブログの基本情報を最新化し、本人情報の表記ゆれをなくします。
次に、外部ASPリンク(他社アフィリエイト)や不適切な表現が残っていないかを記事全体で点検し、AmebaPickの生成リンクだけに統一します。
申請前に、受信メール設定(迷惑・プロモーション振り分け)を緩め、認証メールのURLを期限内に開ける状態を作ることも大切です。
審査では、ブログのテーマ整合・更新状況・表現ルール順守・リンク運用の適正などが総合的に見られます。
複数IDを使う場合は、どのIDで申請・運用しているかを台帳化(ID/担当/連絡先/AmebaPick運用可否)し、承認後は各IDの管理画面からリンクを生成して記事へ挿入します。こうした “連携の型” を先に用意しておくと、差し戻しや誤掲載を大幅に減らせます。
| 項目 | 事前に整える内容 |
|---|---|
| アカウント情報 | プロフィール・連絡先・本人情報の最新化(表記ゆれ解消) |
| 記事・リンク | 外部ASPリンクの撤去/AmebaPick生成リンクに統一 |
| メール受信 | 認証・審査メールを確実に受け取れる受信設定に変更 |
| 運用台帳 | ID/担当/運用ルール/掲載範囲を一覧化して共有 |
アカウント別の申請・承認と注意
複数IDで運用する場合、申請は「使うIDごと」に行い、各IDの情報とブログ内容が一致していることを確認します。申請時は、氏名・生年月日・住所・連絡先などの基本情報を正確に入力し、認証メールのURLを期限内に開く流れです。
審査に向けては、①記事表現が法令・ガイドラインに沿っていること(誇大・断定表現の回避、根拠の明示)、②画像・引用の権利関係が明確であること、③外部ASPリンクが残っていないこと、④ブログの更新が止まっていないこと、の4点を重点的に見直します。
承認後は、必ず承認されたIDの管理画面でリンクを生成し、別IDのリンクを流用しないのが原則です。
ログイン切替でのミスを防ぐため、ブラウザのプロファイル名をID名にして色分けし、プレビュー確認は別プロファイルで行うと誤挿入に気づきやすくなります。
差し戻しが発生したときは、該当理由(表現・画像・リンク・情報不備)を切り分け、修正前後のスクリーンショットを保存してから再申請すると、説明がスムーズです。
- 申請は使用IDごとに実施→情報とブログ内容の整合を確認
- 表現・画像・リンクの三点セットを一括是正→外部ASPは撤去
- 承認後のリンクは必ず当該IDの管理画面から都度生成
ドットマネー受取設定の扱い方
報酬受取は運用の根幹です。まず、受取に用いるドットマネーの設定・本人確認を済ませ、名義や連絡先がAmeba側の登録情報と矛盾しないように揃えます。
複数IDで運用する場合でも、受取名義は整合性を最優先にし、名義違い・口座の使い分けなどで計上先が曖昧にならないよう管理ルールを決めましょう。
実務では、①受取名義・連絡先・交換先の管理(変更履歴を台帳化)、②月次で「発生→承認→交換」までの突合(ID別・記事別のメモ欄を用意)、③換金やギフト交換前の“ワンクッション確認”を習慣化すると、計上ミスや受取遅延を防げます。
環境面では、メールの受信設定を見直し、交換手続きの通知を見落とさないようにすること、ネットワーク制限がある端末では処理を行わないことも有効です。
ドットマネーの仕様や手続きは更新されることがあるため、公式の案内に沿って最新のルールを確認し、チームで共有しましょう。
- 受取名義・連絡先をAmeba登録情報と統一しておく
- ID別の発生・承認・交換を月次で突合→記録を残す
- 交換直前に担当以外の目で内容を確認(ワンクッション)
トラブルとペナルティ回避

複数アカウントでAmebaPickを運用するときに起きやすいトラブルは、大きく「リンク運用の不備」「申請情報の不整合」「表現・法令・規約違反」の3系統です。
外部ASPの混入や、別IDで生成したAmebaPickリンクの流用、申請名義と受取名義の不一致、断定的な効果表現や出典不明のNo.1訴求などは、差戻し・広告停止・報酬取消の原因になり得ます。
回避の基本は、申請前と公開前の二重チェックを定型化し、IDごとに「リンクは当該IDで都度生成」「外部ASPゼロ」「名義・受取は統一」という3原則を徹底することです。
さらに、台帳で「ID/担当/連絡先/受取設定/禁止事項」を一元管理し、公開直後5分の目視確認(別端末・別プロファイル)を運用に組み込むと、誤掲載の早期発見につながります。
万一、指摘や差戻しが来た場合は、原因領域(リンク/情報/表現)を切り分け、修正前後のスクリーンショットを保存→再申請という流れを機械的に回すと、再発防止が進みます。
- リンク運用の統一:当該IDで生成したAmebaPickのみ使用
- 名義・受取の整合:申請情報と受取設定を同一名義で統一
- 公開前チェックの定型化:表現・リンク・画像権利を固定順で確認
外部ASP・重複申請のリスクと対処
外部ASPのリンク掲載は、アメブロ内では基本的に認められていません。過去記事のバナーや短縮URLが残存しているだけでも差戻しの火種になります。
また、複数IDでの“無断の”重複申請や、別名義・別口座での受取分散は、名寄せの観点で審査・運用の停止リスクがあります。
まずはブログ全体検索で「http」「aff」「utm」「?tag」等の文字列を横断チェックし、外部ASPと思われるリンクを抽出→削除します。
次に、各IDのAmebaPickリンクは必ずそのIDの管理画面から都度生成し、他IDのリンクを使い回さない運用に切り替えます。
申請情報・受取設定(ドットマネー)は同一名義で統一し、変更時は履歴を台帳化しておくと後追いが容易です。
差戻しや停止が発生した場合は、通知文のキーワード(リンク/名義/表現)で原因を分類し、該当箇所を修正→別端末で再確認→再申請の順で進めます。
| 症状 | 主な原因 | 対処の流れ |
|---|---|---|
| 審査差戻し | 外部ASP残存/名義不一致/表現NG | 全記事検索→該当削除→名義統一→表現置換→再申請 |
| 広告停止 | 他IDリンクの流用/規約違反の継続 | リンクを当該ID生成に統一→再発防止ルールを台帳化 |
| 報酬計上ズレ | 受取口座の使い分け/別名義 | 受取名義を一本化→月次突合→変更履歴を記録 |
【再発防止フロー】
- 全記事を横断チェック→外部ASP・他IDリンクを除去
- 受取名義・連絡先・申請情報を同一に統一
- 公開前チェック(リンク→表現→画像権利)を固定順で運用
- プロフィール欄・フッター・固定ページの旧リンク残存
- 短縮URL内の外部ASP判定の見逃し
- 別端末の自動サインインによる他IDリンク生成ミス
表現ルール・NG行為のチェック
表現面のNGは、差戻しの最頻出領域です。とくに、薬機法・健康増進法・景品表示法の観点で「治る・効く・消える」等の医薬品的断定、根拠のないNo.1/最安、紛らわしい比較、ビフォーアフターの誤認表現は避けます。
体験談は「個人の感想」である旨を明示し、事実と意見を分けて記述します。著作権・肖像権では、出典不明画像やロゴの無断加工、自動生成画像の権利不備に注意し、フリー素材も利用条件(商用可・クレジット表記など)を遵守します。
さらに、クリック誘導の強要、虚偽レビュー、自演コメント、誹謗中傷や差別的表現、ステルスマーケティング的な表現もリスクです。公開前にチェックリストで最終確認し、根拠が提示できない優位表示は削除します。
【NG→OK置換の考え方】
- NG「シミが消える」→ OK「日々のケアでシミを作らせない工夫」
- NG「肌の奥まで浸透」→ OK「角質層まで浸透」
- NG「満足度No.1(根拠なし)」→ OK「◯◯調査(実施日◯月◯日)の結果を紹介」
- 断定効能・最上級表現の削除→根拠は日付・主体・方法まで併記
- 画像・引用の権利確認→出所明示/自作・許諾・適法素材のみ
- リンク整合→AmebaPick生成リンクのみ/外部ASPはゼロ
- 体験談の但し書き→個人の感想で効果保証なしを明記
【運用のコツ】
- 初稿段階でNGワード表に照合→置換を先に完了してから肉付け
- 公開直前に別プロファイルでプレビュー→第三者視点で誤認を確認
よくある質問と運用方法

複数アカウントでAmebaPickを使う際に寄せられる質問は、「家族やチームで安全に共同運用できるか」「誰がどこまでの操作をしてよいか」「別IDへ乗り換える時の手順はどうするか」に集約されます。
基本は、アカウント(Ameba ID)単位で役割と権限を明確化し、ログイン情報の共有を最小化することです。加えて、収益リンクは必ず当該IDの管理画面から生成し、外部ASPリンクは使わない方針で一本化します。
運用ルールは文書化して台帳化し、ID/担当者/可否(作成・編集・公開・リンク生成・受取操作)を見える化すると誤操作を防げます。
乗り換えや統合時は、旧IDの記事の整理→リンクの貼り替え→告知記事→受取設定の確認という順で進めると、収益や導線の損失を最小限にできます。
下表は、よくある運用シーンに対する基本の考え方の整理です。
| シーン | 運用の考え方・注意点 |
|---|---|
| 家族・チームで投稿 | 投稿権限とリンク生成権限を分離。公開前チェックを二重化 |
| 複数IDでの運用 | IDごとにテーマと収益リンクを分離。リンクは都度当該IDで生成 |
| 別IDへ乗り換え | 下書き移管→リンク再生成→旧記事に告知と導線→受取設定の整合 |
家族・チームでの管理ルールと権限
共同運用では、誰が「記事を書く」「公開する」「AmebaPickリンクを生成する」「報酬受取を操作する」のかを分けておくと安全です。
たとえば、ライターは下書き作成のみ、編集責任者が公開、リンク生成は運用管理者のみ、と段階を分けると誤掲載が起きにくくなります。
ログイン切替ミスを防ぐために、PCはブラウザのプロファイルをID名で分け、色やアイコンで識別します。スマホは原則閲覧用にとどめ、公開やリンク生成はPC側の管理プロファイルで行うと良いです。
パスワード管理は個人共有ではなく、チーム向けの管理ツールで「閲覧可/編集不可」など権限を細かく設定し、履歴を残します。
公開前には、プロフィール名・ヘッダー・記事内リンクの遷移先を固定順でチェックし、別プロファイルでのプレビューを標準化します。
【ルール作成のポイント】
- 役割分担→ライター(下書き)/編集責任者(公開)/運用管理者(リンク生成・受取)
- 環境分離→IDごとにブラウザプロファイルを作成し色分け
- 公開前チェック→プロフィール名→ヘッダー→リンク遷移の順で二重確認
| 役割 | 権限・実務 |
|---|---|
| ライター | 下書き作成・画像準備(権利確認済)・NG表現の初期チェック |
| 編集責任者 | プレビュー確認・表現最終チェック・公開ボタン操作 |
| 運用管理者 | AmebaPickリンク生成・受取管理・台帳更新・監査ログ保管 |
- リンク生成権限は運用管理者に集約→誤リンク混入を防止
- 公開直後5分は別端末で表示確認→問題あれば即下書き戻し
乗り換え・統合・解約時の手順と実務
別IDへの乗り換えや統合では、手順を固定化するほどミスが減ります。まず、対象記事を洗い出し、下書きとして新IDに移管します。次に、AmebaPickの収益リンクを新IDの管理画面で必ず再生成し、旧リンクの流用は避けます。
旧ID側では、関連記事の冒頭に「運用移行のお知らせ」を追記し、新IDの記事へ内部リンクで誘導すると、読者の迷子を防げます。
受取(ドットマネー)設定は名義・連絡先の整合を最優先にし、変更があれば台帳に履歴を残します。
解約・停止を行う場合は、リンク撤去→案内記事の残置→アクセス動線の整理→受取残高の交換確認→最終点検、の順でクローズします。
【移行の手順(推奨フロー)】
- 記事洗い出し→新IDへ下書き移管→体裁調整
- 新IDでAmebaPickリンクを都度生成→旧リンクの全削除
- 旧IDの記事に告知と導線→新IDの該当記事へ誘導
- 受取設定の整合→名義・連絡先・交換先を確認→台帳更新
- 旧IDのクローズ作業→リンク撤去→残高確認→最終点検
- 旧リンクのコピペ禁止→必ず新IDでリンク再生成
- 案内記事で読者導線を確保→検索流入も迷わず新記事へ
【移行時に決めておくこと】
- 告知文テンプレ→「運用を◯◯へ統合しました。新記事は→◯◯」
- 台帳項目→対象記事/新旧URL/リンク更新日/担当者/受取確認日
まとめ
本記事では、複数アカウント運用の可否と前提→管理の型→申請・報酬の扱い→トラブル回避を整理しました。
要点は、アカウント単位の分離管理、外部ASP禁止の徹底、ログイン切替と誤掲載防止設定、NG表現の点検です。最後にチェックリストで再確認し、安心して運用を始めてください。