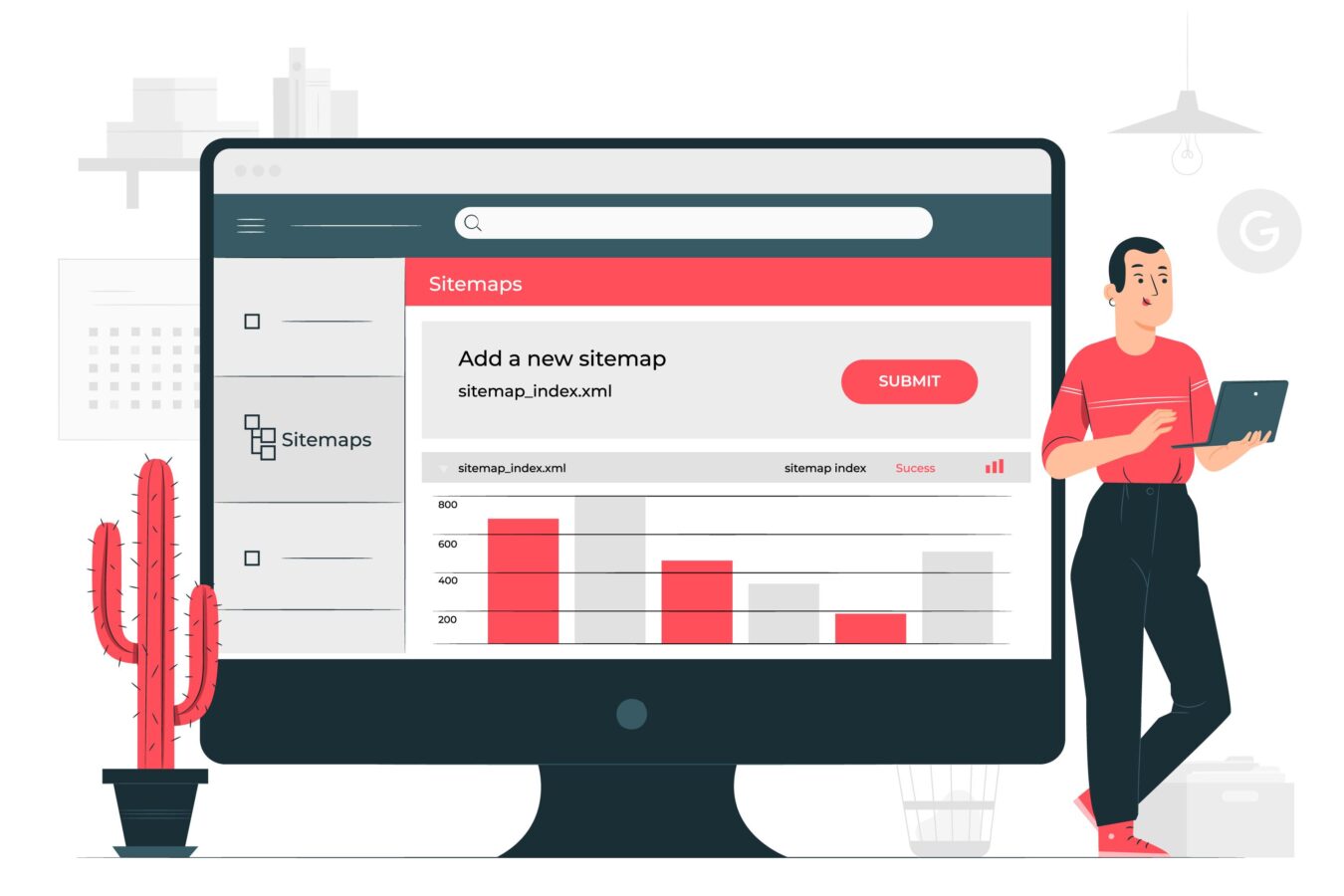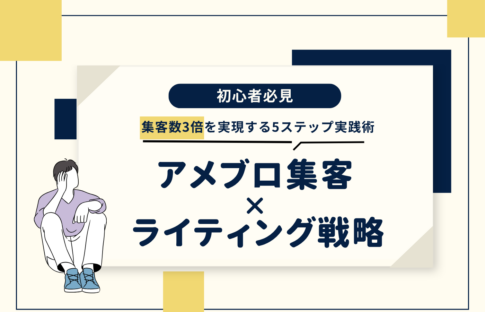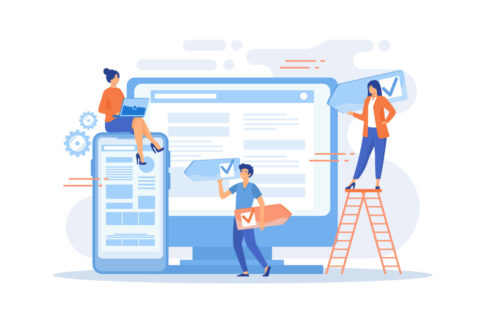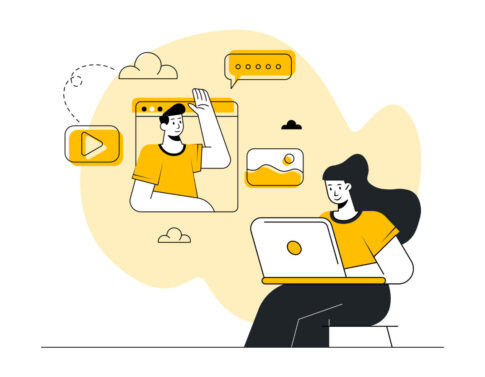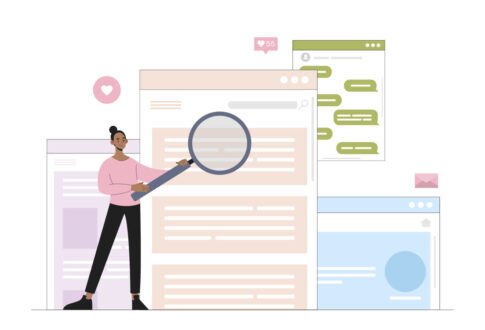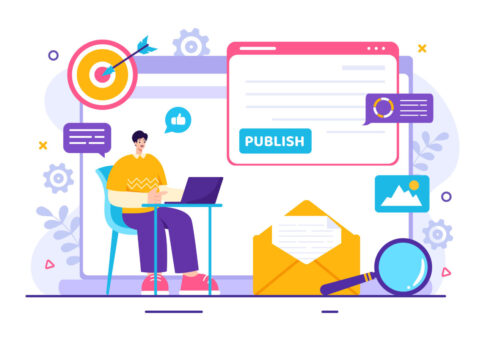アメブロで「最適な文字数はどれくらい?」に答えます。
本記事では、記事全体・導入・見出し・段落の配分、入門/比較/手順など内容別の目安、スマホ前提の読みやすさ、計測に基づく調整手順までをわかりやすく解説していきます。
基本方針と全体文字数の目安

アメブロで集客を狙うとき、文字数は「多ければ良い」「短ければ読まれる」という極端ではなく、目的と読者状況に合わせて配分するのが基本方針です。
スマホ閲覧が中心のため、長文でも“段落を短く・見出し直下に要点・図解で要約”が守れていれば離脱は抑えられます。
まず全体の目安として、検索からの新規獲得と予約導線の両立を考えると2,500〜4,000字が扱いやすいレンジです。
入門や基礎解説は用語の前提説明が必要になりがちなのでやや長め、トラブル対処や手順記事は図解・箇条書きを多用してスリムに仕上げる、といった“テーマ別の濃淡”も前提にします。
配分は「導入→目次→各h2本文→FAQ→CTA」の順で、h2は4〜5章、各章の冒頭で結論を先出しにすることで、スクロール読みにも耐える構造になります。
| ブロック | 配分とポイント |
|---|---|
| 導入 | 120〜160字目安。読者の悩み→結論→本文の地図を一息で提示。 |
| h2本文 | 章ごとに400〜700字。最初の2〜3文で結論→理由→具体例の流れ。 |
| FAQ | 120〜180字×3〜5問。検索クエリの言い回しをそのまま採用。 |
| CTA | 40〜80字。行き先と得られる価値を明記(例:予約方法・所要時間)。 |
- 全体2,500〜4,000字を基本→テーマで増減。
- 段落は80〜120字で小分け→スマホ前提。
- 各h2の直下に要点→その後に詳細と具体例。
記事全体は2,500〜4,000字が基準
全体文字数の基準は、検索から来た読者が「要点を掴みつつ、予約やLINEに進めるか」で決めます。2,500〜4,000字は、入門の定義・比較の基準・手順の注意・FAQ・CTAまでを無理なく収めやすい幅です。
短すぎると検索意図の幅を取りこぼし、冗長だとスマホで読み切る前に離脱しやすくなります。まず2,500字前後の原型を作り、FAQや事例が増えるにつれ3,500字台まで拡張するのが安全です。
増やすときは“章を足す”のではなく“既存章の密度を高める”方が読みやすさを保てます。逆に削るときは、重複表現や類語の並列表現から整理し、例示は1つに絞ります。
【配分の実例(新規向けの基礎記事)】
- 導入・目次:150字前後→本文の地図を提示。
- h2×4章:各500〜600字→結論先出し+具体例+一行サマリ。
- FAQ:120〜150字×3問→疑問への最短回答。
- CTA:60字→予約方法・所要時間・注意点への導線。
- “水増し”の再説明や同義の重ね書き→読了低下。
- 章の冒頭が前置きだらけ→結論を遅らせない。
タイトル32〜45字・導入120〜160字
タイトルは一覧と検索で“何の記事か一目で伝える”ために32〜45字が扱いやすい長さです。主要語は前半に置き、補足(対象・条件)→ベネフィット(得られること)の順で並べるとクリックが安定します。
導入は120〜160字を目安に、悩みの代弁→結論(この記事で分かること)→本文の地図(章立ての要点)までを一気に示します。
長い前置きは避け、数値や具体語を1つ入れて期待値を明確化します。タイトルと導入は記事の“入口”なので、h2の流れと矛盾しないこと、本文末のCTAと同じ言葉を使うことが重要です。
| 要素 | 作り方 | チェックポイント |
|---|---|---|
| タイトル | 主要語→補足→得られること | 前半に主要語、冗長語は削除、数字は必要最小限。 |
| 導入 | 悩み→結論→本文の地図 | 120〜160字で完結、見出しと内容が一致。 |
| 一貫性 | タイトル/導入/CTAの語を統一 | 行き先と表現を合わせ、迷いをゼロに。 |
【具体例(雛形)】
- タイトル例の考え方:主要語(アメブロ集客の文字数)→補足(配分設計)→得られること(判断基準)。
- 導入例の骨子:読者の疑問→この記事で解決できる範囲→章立ての要点。
- タイトルは2案用意→公開後にCTRの高い型をテンプレ化。
- 導入は“本文の地図”を必ず一文で表す→迷いを防止。
見出し別の最適配分

同じ総文字数でも、どこに配分するかで読了率と到達(次の見出しへ進む割合)が変わります。基本は「h2で章の目的と結論を提示→h3で具体化→必要に応じてFAQで補完」という順番です。
スマホ閲覧が中心のアメブロでは、章(h2)ごとに要点が完結していると途中離脱でも価値が伝わります。
そこで、h2は章の結論・理由・例・次の行動をひとまとまりで示し、h3は手順や比較、注意点など“実装の詳細”に集中させます。
FAQは検索やコメントで頻出の疑問に短く答える役割に限定し、本文の重複説明を避けるのがコツです。
下表のように役割×目安文字数×書き方の型を揃えておくと、記事ごとに迷わず量を調整できます。
| ブロック | 役割 | 配分の型 |
|---|---|---|
| h2 | 章の結論・目的提示と全体像 | 結論→理由→具体例→次の行動(一直線) |
| h3 | 手順・比較・注意点などの詳細 | 結論→手順/ポイント→注意→小まとめ |
| FAQ | 狭い疑問への最短回答 | 問いをそのまま見出し→120〜180字で完結 |
- 章(h2)で価値を完結→h3は実装補強に専念。
- FAQは“本文を短くするため”に使い、重複を避ける。
- 段落は短く、見出し直下に要点→詳細→例の順で配置。
h2本文は400〜700字×4〜5章が目安
h2は“章として読み切れる最小単位”にします。400〜700字あれば、スマホでも一息で「結論→理由→具体例→次の行動」まで到達できます。
まず見出し直下の2〜3文で章の結論を言い切り、続けて根拠(数字・比較観点・前提条件)を短文で提示、すぐに具体例を1つだけ入れて読者の状況に結びつけます。最後は「次に読む」や「やってみる」の行動提案で締めると、回遊と実装が進みます。
章の文字数が短すぎると結論が薄く、長すぎると論点が散らかりやすいので、迷ったら“例を1つに絞る・同義の言い換えを削る・図解で圧縮する”の3手で調整しましょう。
【h2の型(テンプレ)】
- 結論:章の主張を一文で。読者の得を明確化。
- 理由:前提・条件・比較軸を端的に。
- 具体例:1つに限定し、状況と効果を短く。
- 行動:次に読む見出し/やることを一文で提示。
- 前置きが長い→結論を最初の2〜3文に。
- 例が多すぎる→1つに絞り、残りはh3やFAQへ。
h3本文は300〜600字・段落80〜120字
h3は“手を動かすための詳細”を短い段落で刻む場所です。300〜600字あれば、手順・比較・注意点を過不足なく収められます。
段落は80〜120字を目安に区切ると、スクロール中でも要点が拾いやすく、音声読み上げでも引っかかりが少なくなります。
構成は〈結論→手順/ポイント→注意→小まとめ〉が基本。手順は行数を増やすより、各段の「到達点」を一言で書くと実装しやすくなります。
比較は表や箇条書きを併用して“差が一行で分かる”ようにし、注意点は“失敗例→回避法”の順で具体化します。最後に一文で小まとめを書き、次のh3やFAQへ自然につなげましょう。
【h3の書き分け例】
- 手順型:準備→実行→確認→例外時の対処。
- 比較型:基準→差分→向き/不向き→選び方。
- 注意型:よくある誤り→影響→回避策→再発防止。
- 1段落1メッセージ。接続詞で無理に文を連結しない。
- 見出し直下に“結論の一文”を必ず置く。
- 表・箇条書きは要点だけに限定して使う。
FAQは1問120〜180字で3〜5問
FAQは“検索やコメントで繰り返し聞かれる短い疑問”に素早く答える場所です。1問120〜180字を目安に、結論→理由/条件→次の行動(リンクや見出し誘導)で完結させます。
本文の内容を繰り返すのではなく、本文では説明しづらい例外や境界条件、迷いやすい用語の定義を補いましょう。
質問文は検索語の言い回しをそのまま使うと、読者の自分ごと化が進みます。数は3〜5問が扱いやすく、増やしたい場合は別記事(用語集やQ&A集)へ分割し、本文から内部リンクで接続すると読みやすさを保てます。
【FAQの作り方(雛形)】
- Q:◯◯はどのくらい必要?/A:結論→条件→例(短く)。
- Q:◯◯できない時は?/A:原因→対処→関連見出しへ誘導。
- Q:◯◯と◯◯の違いは?/A:基準→一行比較→選び方。
- 本文の長文を再掲してしまう(冗長)。
- 結論が後ろにある(途中離脱で伝わらない)。
- 件数が多すぎる(Q&A集は別記事で運用)。
コンテンツ種別の文字数目安

同じ「アメブロ集客」でも、入門・比較・手順では必要な説明量が変わるため、最適な文字数レンジも異なります。
入門・基礎解説は前提や用語を丁寧に整える必要があるためやや長め、比較・選び方は判断材料を網羅するため表を多用して厚め、手順・設定・トラブルは図解と箇条書きでスリムに仕上げるのが基本方針です。
重要なのは、文字数そのものより「読者が何分で何を決められるか」。そこで本章では、入門2,500〜3,500字、比較3,000〜5,000字、手順2,000〜3,500字の目安と、見出し配分・表/図解の使い分けを具体化します。
まずは下表で“目的→必要要素→推奨文字数”の全体像を押さえ、各h2/h3で過不足を調整しましょう。
| 種別 | 目的 | 必要要素と目安文字数 |
|---|---|---|
| 入門・基礎 | 前提整理と誤解の解消 | 用語・範囲・基本手順・注意を簡潔に/2,500〜3,500字 |
| 比較・選び方 | 基準提示と意思決定の支援 | 比較表+「この人はこれ」基準/3,000〜5,000字 |
| 手順・設定・対処 | 短時間で実装・復旧 | 段階図解+チェックリスト中心/2,000〜3,500字 |
- 入門は“用語→範囲→最小手順→注意”の順でムダを削る。
- 比較は“表→選び方→CTA”の一直線導線で迷いを減らす。
- 手順は“到達点の見出し化”+図解で説明を圧縮する。
入門・基礎解説は2,500〜3,500字
入門・基礎解説は、検索から初めて来る読者の「前提のズレ」を解消し、全体像と最小の実践を示す記事です。
2,500〜3,500字あれば、用語定義・できること/できないこと・最初の手順・注意点・よくある誤解までを過不足なく収められます。
構成は〈導入で悩み代弁→h2-1: 用語と範囲→h2-2: 最小手順→h2-3: 注意/NG→FAQ→CTA〉が読みやすいです。文字数の圧縮は「図解1枚+箇条書き3点」を要所に入れるのが効果的で、前提の重複説明を減らせます。
【配分例(入門記事の型)】
- 導入:120〜160字で「何が分かるか」を宣言。
- h2-1(約600字):用語/範囲/前提の整理。境界線を明記。
- h2-2(約700字):最小手順を3〜5段で提示→各段の到達点を一言に。
- h2-3(約600字):NG例と注意。誤解を3点に絞って解消。
- FAQ(120〜160字×3):検索語そのままの質問に短答。
- CTA(60字):固定記事(予約案内)へ一本導線。
| 要素 | 書き方のポイント | やりがちNG |
|---|---|---|
| 用語定義 | 読者の言葉に翻訳し、1文で言い切る | 専門語の羅列や横文字多用 |
| 最小手順 | 段の頭に“到達点”を置く | 前置き長文で手順が埋もれる |
| 注意点 | NG→理由→回避策の順 | NGだけ並べて不安をあおる |
- 結論が遅い(冒頭3文に置く)。
- 同義の言い換えが多い(1表現に統一)。
比較・選び方は3,000〜5,000字(表多め)
比較・選び方は、読者が「どれにするか」を決める段階の記事です。重要なのは“基準→差分→向き/不向き→選び方→CTA”の一直線を崩さないこと。
3,000〜5,000字の幅を使い、比較表(対象/特徴/留意点の3列)を中心に、表直後に「この人はこれ」を箇条書きで短く示すと迷いが減ります。
表は増やすほど冗長になるため、主要1〜2枚に絞り、詳細は個別記事に内部リンクで分岐するのがコツです。ベネフィットだけでなく注意点や条件も併記し、期待値のズレを防ぎます。
【比較記事の配分例】
- 導入(150字):結論先出し「◯◯ならA、△△ならB」。
- 基準提示(600〜800字):評価軸を3〜5個に限定し定義。
- 比較表(400〜600字):1表で対象/特徴/留意点を一望化。
- 「この人はこれ」(200〜300字):箇条書きで適合を短文化。
- 深掘り(800〜1,200字):差が出やすい2〜3点だけ解説。
- FAQ(120〜160字×3):混同しやすい語の違いを短答。
- CTA(60字):固定記事→予約/相談に一本化。
| 要素 | 押さえる点 | 冗長を防ぐコツ |
|---|---|---|
| 評価軸 | 読者が判断に使う軸だけ | 5個以内に限定し定義を1文に |
| 比較表 | 対象/特徴/留意点の3列 | 派生は別記事へ内部リンク |
| 選び方 | 「この人はこれ」を先に | 言い換えを削り具体例は1つ |
- 見出し直下に置き、表の前で“基準”を定義。
- 表の後に“選び方”を必ず置く(結論が先)。
手順・設定・トラブルは2,000〜3,500字(図解多め)
手順・設定・トラブル対応は、「短時間で実装・復旧」させる記事です。2,000〜3,500字のレンジで、段階図解とチェックリストを多めに使い、本文は“到達点の確認”に集中します。
構成は〈結論(何分でどこまで)→準備→手順→確認→例外/トラブル→FAQ→CTA〉が実践的。各ステップの見出しに到達点(例:設定保存まで、エラー表示が消えるまで)を明記し、段落は80〜120字で区切ります。
トラブルは「症状→原因の切り分け→対処→再発防止」の順に統一し、本文が長くなり過ぎたら図解に寄せて圧縮しましょう。
【手順記事の配分例】
- 導入(150字):到達点と所要時間を宣言。
- 準備(300〜400字):必要な設定/情報だけ列挙。
- 手順(800〜1,000字):3〜5段。各段の到達点を一言に。
- 確認(200〜300字):成功判定の方法を明記。
- 例外/トラブル(400〜600字):症状別に短く。
- FAQ(120〜160字×3):境界条件や用語の補足。
- CTA(60字):固定記事→予約/相談に一本化。
| 要素 | ポイント | 短く伝える工夫 |
|---|---|---|
| 図解 | 見出し直下に1枚配置 | 1400×900+一文キャプション |
| 手順 | 到達点を見出しに併記 | 段落80〜120字で刻む |
| トラブル | 症状→切り分け→対処 | 箇条書きは3点まで |
- 前置きが長く、開始までにスクロールが多い。
- 画像なしの長文手順で理解が追いつかない。
要素ごとの推奨文字数

同じ総文字数でも、要素ごとの長さを最適化すると“読みやすさ→到達→行動”の流れが安定します。スマホ中心のアメブロでは、長文を一気に読ませるより「短い要素でテンポよく前進させる」設計が効果的です。
たとえば、箇条書きは1項目を40〜80字に収めて端的に要点化し、数は3〜5点に限定すると“今すぐ使える”印象になります。
H2直下リンクは60字前後で「行き先と得を一文で」言い切るとクリックが伸びやすく、本文末のCTAは40〜80字で“行動→得られる価値→所要”を短く提示するのが基本です。
画像キャプションは30〜60字でポイントを補足、図解補足は200〜300字で条件や例外を整理すると、本文の冗長化を防げます。要素ごとの字数を揃えるだけで、記事のテンポが整い、同じ内容でも読了と回遊が改善します。
- 短く=浅くではない→要点を先出しし、詳細は次段で補足。
- 「行き先+得+所要」を一文で揃えると迷いがゼロに。
- 図解は本文の代替として使い、説明は最小限に圧縮。
箇条書きは1項目40〜80字で3〜5点
箇条書きの目的は「最少の文字で意思決定を助ける」ことです。1項目40〜80字だと、スマホ1行〜2行で収まり、読み飛ばし中でも要点が視認できます。3〜5点に限定することで“選びやすい幅”になり、10点以上の羅列で起きがちな判断疲れを防げます。
書き方は〈結論→条件/注意→得られること〉の順に短文化し、文頭を名詞または動詞で揃えるとテンポが出ます。
並列の粒度は合わせ、同義の言い換えは削除。本文との重複は避け、本文で長く説明しにくい“判断基準・チェック項目・注意点”だけを抽出します。
【良い例(40〜80字×4点)】
- はじめての方→入門記事から。用語と範囲を短く整理。
- 比較で迷う→表の後に「この人はこれ」を先に確認。
- 実装したい→手順の各段で“到達点”を一言でチェック。
- 予約前に不安→固定記事の注意事項と所要時間を確認。
【避けたい例】
- 10点以上の羅列で結局何をすべきか分からない。
- 1項目が100字超で本文と同じ内容を再掲している。
【作成のコツ】
- 各項目は1メッセージに限定→接続詞での多段合体は避ける。
- 末尾に句点を付けず軽快に→文頭の語も統一。
H2直下リンク60字前後・CTA文言40〜80字
H2直下リンクは“次の一歩”を明確にする要所です。60字前後で〈行き先+得られる価値+所要/条件〉を一文化すると、クリックの納得感が高まります。
本文末のCTAは40〜80字で“行動動詞→得られること→所要/注意”を短く統一し、プロフィール・固定記事・他記事と同文言に揃えます。リンクは各セクション1件に限定し、並列リンクの多発は避けると到達が分散しません。
【H2直下リンク例(約60字)】
- ご予約案内はこちら→方法・所要時間・注意事項をまとめて確認できます。
- 選び方の基準まとめ→比較表と「この人はこれ」を先にチェック。
【本文末CTA例(40〜80字)】
- ご予約はこちら→希望日時とメニューを選ぶだけ。所要3分で完了します。
- LINEで相談→空き枠と最適メニューをご案内。迷ったらまずご相談を。
【実装チェック】
- 直下リンクは各h2で1件のみ→固定記事へ一本導線。
- CTAの動詞を「ご予約」「相談」に統一→行き先も同一。
- 矢印は→で統一し、長い装飾は使わない。
画像キャプション30〜60字・図解補足200〜300字
画像キャプションは“何を見れば良いか”を指示する役割です。30〜60字に収め、〈要点→見どころ→次の行動〉を一息で書きます。
図解補足は本文の冗長化を防ぐために200〜300字で〈前提条件→手順の要点→例外/注意〉を整理し、本文では触れにくい境界条件だけを補います。
画像は見出し直下に配置し、本文で説明済みの内容を繰り返さないようにします。キャプションは名詞止めまたは短文で軽快に、図解補足は段落80〜120字で2〜3段に分けると読みやすいです。
【キャプション例(30〜60字)】
- 比較表の見方→対象・特徴・注意を一行で把握し、次に選び方へ。
- 手順の到達点→保存表示が出れば設定完了。次の段へ進む。
【図解補足例(200〜300字)】
- 前提:スマホ表示を前提に、画像は1400×900で作成。文字は大きめに配置。
- 要点:各段の到達点をアイコンで示し、説明文は10〜15字に圧縮。
- 例外:表示が崩れる場合はキャッシュ削除→再読み込み→別端末で確認。
- 写真だけで説明→キャプションがないと理解が遅れる。
- 図解補足が長文→本文と重複し冗長に。条件と例外だけを短く。
計測と調整の判断基準

最適な文字数は“数そのもの”ではなく、数が「クリック→到達(H2直下リンク)→CV(予約/相談)」にどう効いたかで判断します。運用は〈週次=小さなAB/月次=型の更新〉が基本です。
まず週内は同型の記事を時間帯だけ変えて予約投稿し、他条件(見出し構成・リンク位置・画像サイズ)は固定します。
翌日に〈CTR(タイトルの刺さり)〉〈到達(固定記事への遷移)〉〈CV(フォーム送信/LINE開始)〉を確認し、ボトルネックの一箇所だけを修正します。
月末は“勝ち時間×勝ち型(タイトル語順・直下リンク文言・段落長)”をテンプレに反映し、翌月の全記事へ横展開します。文字数の増減は最後の手段です。
まずはタイトル語順とH2直下文言、段落長の3点を基準値に合わせ、過不足が残った章のみ増減させると、読みやすさと到達が安定します。
| 症状 | 主因のあたり | 先に触る箇所 |
|---|---|---|
| CTR低下 | 主要語の後方化/冗長語 | タイトル32〜45字で語順最適化 |
| 到達低下 | 直下リンクの弱さ/リンク過多 | H2直下文言を40〜60字化・各章1件のみ |
| 読了低下 | 段落が長い/前置き過多 | 段落80〜120字化・結論先出し |
- 指標:CTR→到達→CVの順で確認。
- 修正:今週は1点だけ(タイトル or 直下文言 or 段落長)。
- 判断:2週分の合算で“勝ち型”をテンプレ化。
CTR低下時はタイトル語順を40〜45字で最適化
CTRが落ちたら、まずタイトルの“語順と密度”を整えます。長さは32〜45字が扱いやすく、40〜45字に収まる範囲で〈主要語→補足(対象/条件)→得られること〉の順に並べ替えます。
主要語が後ろにある、同義語を重ねている、抽象語が先頭に来ている——この3つはクリック低下の典型です。
冗長語(例:完全に/超/とても など)を1つ削り、数字や具体語は“必要最小限”だけ残します。ABは語順だけ変えた2案で行い、構成や見出しは固定して原因を特定します。
時間帯の影響を排除するため、同じ曜日に朝/昼/夜/21時台を回して比較し、2週分を合算して判断します。
【最適化の進め方】
- 主要語を前半に寄せる(例:アメブロ集客/文字数/配分)。
- 補足は対象や条件を短語で(初心者向け/スマホ前提など)。
- 最後に得られることを具体化(判断基準/配分設計など)。
- 冗長語と重複語を1つずつ削る→密度を上げる。
【チェック項目】
- 一覧で“何の記事か”が一目で分かるか。
- 主要語が先頭〜前半15字以内に入っているか。
- 同義語の重ね書きや装飾語の過多がないか。
到達低下時はH2直下文言を40〜60字に調整
H2直下リンクは“次の一歩を指示する”要の一文です。到達が弱いときは、文言を40〜60字で〈行き先+得られる価値+所要/条件〉に統一し、各章1件のみ配置します。
例:「ご予約案内はこちら→方法・所要時間・注意事項をまとめて確認できます。」のように、クリック前に得が分かると到達が伸びます。
リンクの並列設置や、章の途中に複数リンクを置くのは分散の原因です。必ずh2直下に置き、本文末のCTAと同文言・同リンクで一貫性を持たせます。色や装飾で無理に目立たせるより、文言の明確化と位置の固定が有効です。
【文言づくりのコツ】
- 行き先を明示(固定記事/比較表まとめ/FAQまとめ など)。
- 得られる価値を一語で(予約方法/選び方/注意点)。
- 所要や条件を短く(所要3分/初心者向け など)。
【実装ルール】
- 各h2で1件のみ→固定記事または該当セクション集約へ。
- 本文中の並列リンクは原則禁止→迷いを作らない。
- 見出し・直下リンク・CTAの語彙を統一→一貫性で安心感。
読了低下時は段落80〜120字で再構成
読了が落ちるときは、内容より“読み方”が阻害されています。段落を80〜120字で刻み、各h2直下の2〜3文に結論を先出しします。以降は〈理由→具体例→行動〉の順で短文を積み、同義の言い換えや前置きの重複を削除します。
比較や手順が長い場合は、表・箇条書き・図解に置き換えて情報密度を保ちます。FAQは本文で説明しづらい境界条件だけを120〜180字で補い、本文の再掲は避けます。
画像は見出し直下に1枚、キャプション30〜60字で“何を見れば良いか”を指示するとスクロール中でも理解が途切れません。内部リンクは各セクション1件に限定し、回遊の“一本道”を維持します。
- 各h2の冒頭に結論がある(2〜3文で言い切り)。
- 段落長は80〜120字に収まっている。
- 表・箇条書き・図解で“差”や“到達点”が一目化されている。
- 内部リンクは1件に絞り、直下リンク→固定記事→CTAが一直線。
まとめ
文字数は“目的×読者状況”で最適が変わります。まず本記事の目安で配分を決め、H2直下リンクを固定し、CTR・到達・読了で週次検証。
弱い箇所だけ増減し、段落を短く整えることから始めましょう。次の一歩は、1記事の導入の簡潔化と見出し配分の見直しです。