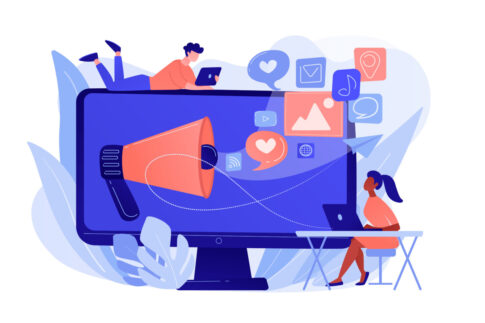ブログはどれがいい?——本記事は主要7サービスを横並びで比較し、目的別に「選ぶ基準」と「最短の始め方」を整理します。
機能・コスト・集客力・収益化・移行性をチェックしつつ、いますぐ集客を始めたい方に向けてアメブロを推しどころとする理由と活用ポイントも解説。迷わず最適解にたどり着けます。
目次
比較の前提とゴールをそろえる

ブログサービスを比べる前に、「誰が・何のために・どこまで」を先に決めておくと、判断がぶれません。
本記事では、主要サービス(アメブロ、WordPress、はてなブログ、note、livedoorブログ、Blogger、Wix など)を対象に、個人発信・収益化・企業広報・EC連動の用途を想定します。
ゴールは、読者ごとの目的に合うサービスを一つ選び、初期設定と記事公開まで進められる状態になることです。
比較軸は、機能(書きやすさ・デザイン調整のしやすさ)、コスト(初期・月額・追加費用)、集客力(サービス内の読者機能・SNS連携)、収益化(広告やアフィリエイトの可否・表記方法の明確さ)、移行性(データの書き出し・独自ドメイン運用)の5つに絞ります。
最短で結論に近づくために、まずは自分の用途を一つに絞り、次に5軸で最低限の要件を満たすかを確認してください。
迷ったときは「開始のしやすさ→集客のしやすさ→将来の移行」の順で優先すると、失敗が減ります。
| 決めること | 内容と例 |
|---|---|
| 用途 | 個人発信/収益化(アフィリエイト)/企業広報/EC連動のいずれかに固定 |
| 到達点 | 初期設定→1記事公開→導線と表記の確認までを今週中に完了 |
| 比較軸 | 機能・コスト・集客力・収益化・移行性の5つだけを見る |
- 用途を一つに固定(例:まずは無料で集客を始めたい)
- 比較軸は5つに限定(機能・コスト・集客力・収益化・移行性)
- 到達点=1記事公開までの期限を決める(例:1週間)
読者像と用途を整理する(個人発信 収益化 企業広報 EC連動)
サービス選びは、読者像と用途を最初に言語化することから始まります。個人発信は「日々の発信を気軽に始めたい」「読者との交流も重視したい」といったニーズが中心で、書き始めやすさやサービス内の読者機能が重要です。
収益化(アフィリエイト)では、広告やリンクの可否・表記ルール・記事内の導線設計の自由度が欠かせません。
企業広報は、ブランドに合ったデザインや運用体制(権限・下書き承認など)、法令・表記の統一がポイントになります。
EC連動では、商品ページやカテゴリへの導線、FAQや事例との接続、外部ストア(BASE等)への送客のしやすさが評価軸になります。
これらを混在させると要件が衝突しやすいので、まずは中心となる用途を一つに絞り、残りは将来の拡張として扱うと判断がスムーズです。
| 用途 | 合う読者像 | 重視ポイント(例) |
|---|---|---|
| 個人発信 | 日記+情報発信を気軽に始めたい | 書きやすさ/読者機能/テンプレの見やすさ |
| 収益化 | アフィリエイト中心に導線を作りたい | 広告・リンク可否/表記方法/内部リンクの自由度 |
| 企業広報 | ブランド統一と体制運用を重視 | デザイン調整/権限・承認/表記ガイドの徹底 |
| EC連動 | 商品理解→購入へ最短で導きたい | 商品/カテゴリへの導線/FAQ・事例の配置/外部ストア連携 |
- 用途は1つに固定→「今やりたいこと」に寄せる
- 残りの用途は将来の拡張(移行性の確認)に回す
- 読者の最初の一歩(購読・問い合わせ・購入)を一文で定義
判定基準を明確にする(機能 コスト 集客力 収益化 移行性)
判定基準は5つに絞ると比較が速くなります。機能では、記事作成のしやすさ(見出し・画像・目次など)とデザイン調整の自由度を確認します。
コストは、初期費用・月額・追加費用(独自ドメイン・テーマ・プラグイン等)を合計で見るのがポイントです。
集客力は、サービス内の読者機能やSNSとの相性、検索に載せやすい構造かを見ます。収益化は、広告やアフィリエイトの可否、リンク表記のルール、収益導線の作りやすさが重要です。
移行性は、データの書き出しや独自ドメイン運用、将来WordPress等へ移る際の手間を想定してチェックします。各基準で「最低限の合格ライン」を先に決め、満たさない候補は早めに外すと、時間を節約できます。
| 基準 | 確認ポイント | 注意・メモ |
|---|---|---|
| 機能 | 見出し/画像/目次の扱いやすさ、テンプレ調整の容易さ | カスタムが必要なら体制と時間を確保 |
| コスト | 初期・月額・追加費用を合算 | 将来の拡張費(テーマ変更等)も見込む |
| 集客力 | 読者機能、SNS連携、検索に載せやすい構造 | 開始直後は「露出の作りやすさ」を優先 |
| 収益化 | 広告/アフィリエイトの可否、表記ルール | 表記の徹底でトラブル防止と信頼確保 |
| 移行性 | データ書き出し、独自ドメイン、リダイレクト可否 | 将来の移行プランを事前に想定 |
- 5基準の合格ラインを先に言語化(例:独自ドメイン必須 など)
- 満たさない候補は早めに除外→検討負荷を下げる
- 同じ条件で候補を比較(表にして一気に判断)
主要プラットフォームの特徴をつかむ

「どれを選ぶか」は、書きやすさ・見つけてもらいやすさ・収益導線・将来の移行という4点で違いが出ます。
国産サービスは書き出しが早く、読者機能やランキングなど“内側の流入”が得やすい一方、デザインやサイト設計の自由度は限定的になりがちです。
自前構築型(WordPressなど)は自由度と資産性が高く、構造や内部リンクを思い通りに作れますが、サーバー管理や更新・バックアップなどの手間が増えます。
海外サービスは無料で安定して使えるものもありますが、日本語圏のコミュニティやサポートの濃さは各社で差があります。
まずは各サービスの強み・弱みを把握し、自分の「最初の一歩」と「半年後の姿」の両方に合うかを確認しましょう。下の各見出しでは、代表的な選択肢を用途目線で整理します。
- 書きやすさと“内側の流入”を優先するか→国産プラットフォーム
- 自由度と資産性を優先するか→自前構築(WordPressなど)
- 半年後に記事数・導線・移行の計画をどうするか→拡張性を確認
アメブロの特徴と強み 弱み
アメブロは、登録直後から投稿・更新が簡単で、フォロー・いいね・ランキング・公式ジャンルなど“内側の読者導線”が豊富です。
スマホアプリでの下書き→公開も軽く、日々の更新や告知と相性が良いのが強みです。ハッシュタグやトピック掲載、読者登録からの再訪など、記事以外の接点が多く、ゼロからでも露出を作りやすい設計になっています。
一方、レイアウトや装飾はテンプレート前提で、自由度は限定的です。サイト全体の構造(カテゴリ深掘り、複雑な回遊設計など)を作り込みたいケースでは物足りなさが出やすく、将来の移行時は記事データ・画像パスなど仕様差への配慮が必要です。
収益面では、アフィリエイトや紹介リンクを設ける際に表記ルールを守り、記事末に「関連→商品・カテゴリ」の導線を1本だけ置くと迷いが減ります。
【向いているケース】
- 今すぐ無料で始め、更新頻度で露出を増やしたい
- コミュニティ的な読者接点を活かし、初期流入を得たい
- スマホ中心の運用で、軽い作業フローにしたい
【注意したい点】
- 細かなデザイン・構造の自由度は限定的→記事導線で工夫する
- 移行時はデータ形式や画像の扱いを事前に確認しておく
WordPressの自由度と運用負荷
WordPressは、テーマ・プラグイン・固定ページ・カスタム分類など、設計の自由度が最大の強みです。
カテゴリ―構造や内部リンク網、商品・事例・FAQの型を柔軟に作れ、将来の拡張や多言語化にも対応しやすい一方、サーバー・ドメインの管理、更新・バックアップ、セキュリティ対応といった“運用の手間”が発生します。
記事の速度・見やすさ・回遊をテンプレ側でコントロールできるため、コンテンツ在庫が増えるほど効果が出やすい反面、最初の立ち上げには最低限の設定時間が必要です。
【向いているケース】
- 長期的に資産化し、構造やデザインを自分で決めたい
- 商品・事例・比較・FAQなど複数の型で記事群を運用したい
- 将来、機能追加や他サービス連携を広げたい
【注意したい点】
- 更新・バックアップ・不具合対応の体制(人か外部委託)を決める
- テーマ選定とプラグインの入れすぎに注意(速度・保守性を優先)
はてなブログとnoteの手軽さと拡張性
はてなブログは、書き心地が軽く、読者コミュニティや「はてなブックマーク」経由の露出が得やすい点が魅力です。
シンプルな管理画面で、見出し・目次・画像の扱いも分かりやすく、文章中心の発信に強みがあります。デザイン自由度は中程度で、深いカスタマイズをしたい場合は限界が出ることもあります。
noteは、執筆→公開→拡散までを最短で回しやすく、有料記事や定期購読など“文章のマネタイズ”機能が分かりやすい設計です。
プラットフォーム内のおすすめ表示やタグからの流入も見込めますが、サイト全体の設計や複雑な回遊は不得意です。
いずれも「まずは書き始める」「反応を確かめる」に向いており、将来の拡張(独自ドメイン運用、外部連携、移行)を視野に用途を限定して使うとミスマッチを避けやすくなります。
【向いているケース】
- 文章中心で、まずはスピード重視で公開したい
- プラットフォーム内の露出やコミュニティを活用したい
【注意したい点】
- 複雑なサイト構造や高度なデザインは不得意→記事導線で補う
- 広告や外部リンクの扱いは各ガイドラインを必ず確認する
livedoorブログ Blogger Wixなどの位置づけ
livedoorブログは、無料運用のしやすさと安定感が特長で、長く書き続ける日記・情報発信と相性が良い一方、サービス側広告やデザイン制約が残る場面があります。
Blogger(Google提供)は、無料でシンプルに運用でき、基本的な独自ドメイン設定にも対応するなど“気楽に続ける”用途に向きますが、テンプレや機能拡張の選択肢は多くありません。
Wixはドラッグ&ドロップでビジュアル設計しやすく、コーポレート+ブログを一体で作れるのが利点です。フォームや予約など周辺機能も揃いますが、細かなSEO設計・超高速化や複雑なデータ構造は工夫が必要です。
【向いているケース】
- livedoor:無料で長期運用したい、更新を最優先したい
- Blogger:最低限の機能で気軽に続けたい
- Wix:見た目重視でサイト全体を素早く用意したい
【注意したい点】
- サービス側広告やテンプレ制約→読者体験とのバランスを確認
- 移行や拡張の可否・手順を事前に把握しておく
目的別のおすすめを整理する

同じ「ブログ」といっても、目的と体制によって最適解は変わります。まずは「今すぐ無料で始めて露出を作りたい」「自社の資産として長く育てたい」「文章中心でシンプルに運用したい」のどれに当てはまるかを決めましょう。
本章では判断を迷わないよう、主要サービスを目的別に割り振り、最初の一手と次の導線まで落とし込みます。すぐに集客の手応えを得たいならアメブロ。
デザインや構造の自由度を取り、将来的な拡張や移行まで見据えるならWordPress。文章中心で反応を素早く確かめたいなら、はてなブログやnoteが有力です。
どの選択肢でも、記事の区切りごとに最適な内部リンクを一つだけ置き、本文末に次の行き先を必ず示すことが離脱防止の基本です。
| 候補 | 向いている人・目的 | 最初の一手と次の導線 |
|---|---|---|
| アメブロ | 無料で早く始めたい/サービス内の読者導線を活かしたい | プロフィールとジャンル設定→タグ運用→本文末にカテゴリへの案内 |
| WordPress | 自社資産化・構造設計・デザイン自由度を重視 | 独自ドメインとテーマ選定→記事テンプレ作成→内部リンク網の設計 |
| はてなブログ・note | 文章中心/反応確認を優先/運用はシンプルに | シリーズ化とタグ整理→おすすめ記事へ誘導→必要に応じて外部へ送客 |
- 今の目的を一つに固定する(露出の速さ/資産化/シンプル運用)
- 最初の一手を決める(設定→1記事公開→導線配置)
- 翌週に数字で前後比較し、当たりの型をテンプレ化する
今すぐ無料で始めて集客したい人向けはアメブロ
アメブロは、登録直後から投稿・更新が簡単で、フォローやいいね、ランキング、公式ジャンル、タグ検索といった「内側の読者導線」が充実しています。
つまり、外部からの検索流入に頼り切らなくても、新しい読者と接点を作りやすい設計です。スマホアプリで下書き→公開までが軽く、日次更新や告知との相性も良好です。
はじめにプロフィールとヘッダーを整え、ジャンルとタグを固定化。記事は導入で結論を先出し、本文は要点→理由→具体→次の行動の流れで統一します。
本文の区切りごとに関連記事やカテゴリへの案内を一つだけ置き、本文末では「まず見るべきカテゴリ」か「おすすめ記事」へのリンクを明確に。
週に一度、検索とアクセスの数字を見てタイトルと導入、導線の位置を小さく修正すると、少ない工数でも露出と回遊が安定します。
【最初の一手】
- プロフィール・ジャンル・タグを固定→読者が見つけやすい状態に
- 記事テンプレを作成(導入で結論→本文→要点ボックス→次の行動)
- 本文末にカテゴリへの案内を一つだけ設置(迷いを減らす)
| 強み | 活かし方 | 注意点 |
|---|---|---|
| 内側の導線が豊富 | タグ・ジャンル・読者機能を継続運用 | 装飾やレイアウトの自由度は控えめ→導線で補う |
| スマホ運用に強い | 短い更新を高頻度で投入 | データ移行時の仕様差は事前に確認 |
- 導入直後に要点ボックスを置き、流し読みでも要点が伝わるようにする
- タグは上位3つを固定し、記事間の回遊を作る
- 毎週同じ曜日に数字を比較し、タイトル語順と導線位置を小さく改善
自社資産化やデザイン自由度を重視するならWordPress
WordPressは、テーマや固定ページ、カスタム分類などを使って構造を自在に設計でき、独自ドメインで長期的な資産化がしやすいのが最大の魅力です。
商品や事例、比較、FAQなど複数の記事型を並走させ、内部リンク網で回遊を設計できるため、コンテンツ在庫が増えるほど効果が乗りやすくなります。
一方で、サーバーとドメインの管理、更新・バックアップ、画像最適化、表示の速さや安定性の管理など、運用面の手間は避けられません。最初は「最小構成」で立ち上げ、月次の運用で必要な機能を足すのが安全です。
【最小構成での始め方】
- 独自ドメインとサーバーを用意→軽量テーマを選定
- 記事テンプレ(導入で結論→本文→要点ボックス→次の行動)を作成
- 内部リンクの固定順路(入門→比較→手順→事例)を決めて設置
| 強み | 具体例 | 運用メモ |
|---|---|---|
| 設計の自由度 | 商品・事例・Q&Aなど型別テンプレを量産 | プラグインは必要最小限にして速度と保守性を確保 |
| 資産化 | 独自ドメインで指名検索や被リンクを蓄積 | 定期バックアップと更新フローを標準化 |
- 機能を盛り込みすぎて表示が重くなる→最小構成から始める
- 更新や不具合対応の役割が曖昧→担当か外部委託を早めに決める
文章中心でシンプル運用ならはてなブログやnote
はてなブログとは、書き心地の軽さとコミュニティ由来の露出が特長で、タグやシリーズ化、ブックマークからの再訪が見込めます。
noteは、執筆から公開、拡散までが一直線で、有料記事や定期購読などの収益機能が分かりやすい設計です。いずれも「複雑なサイト構造は作り込まず、まず反応を見る」場面に適しています。
最初は1記事1キーワードに絞り、導入で結論を先出し、本文は要点→理由→具体→次の行動を徹底。本文末におすすめ記事か外部の送客先を一つだけ置き、行き止まりをなくします。
将来、独自ドメイン運用や外部サイト連携を拡張したい場合は、早い段階から「どのタイミングでどこへ移行するか」をメモしておくと迷いません。
【向いている使い方】
- 文章中心で、更新頻度を高めながら反応を確かめる
- プラットフォーム内のおすすめ表示やタグで露出を作る
| 長所 | 活かし方 | 留意点 |
|---|---|---|
| 始めやすい | テンプレに沿って短い更新を継続 | 複雑な回遊や高度なデザインは不得意→導線で補う |
| 収益導線の用意(特にnote) | シリーズ化→関連へ誘導→有料や登録へ橋渡し | 広告やリンクの扱いは各ガイドに沿って表記 |
- 記事末に「次に読む一つ」を必ず提示(迷いを作らない)
- タグやシリーズ名を固定化し、テーマごとに束ねる
- 週一でタイトルと導線の位置を前後比較して微修正
livedoorブログ Blogger Wixなどの位置づけ
無料運用のしやすいlivedoorブログ、シンプルで安定したBlogger、見た目をドラッグ&ドロップで整えやすいWixは、「まず情報発信を続ける」「企業サイトとブログを一体に見せたい」といった場面で選ばれます。
livedoorブログは長期運用と相性が良く、Bloggerは最小構成で手間をかけずに継続できます。
Wixはフォームや予約などの周辺機能をまとめて用意でき、コーポレートサイトとブログをまとめて立ち上げたい時に便利です。
いずれも移行や拡張の可否を早めに確認し、将来の計画をメモしてから着手すると、後戻りのコストを抑えられます。
【選ぶ前の確認ポイント】
- サービス側広告の扱いとデザイン制約が許容できるか
- 独自ドメイン・書き出し・リダイレクトなど移行要件を満たすか
- 必要な周辺機能(フォーム・予約・多言語等)が揃うか
アメブロをすすめる理由と活用ポイント

アメブロは「今日から書き始めて、すぐに見てもらう」までの距離が短いのが最大の魅力です。登録後すぐに投稿でき、フォロー・いいね・リブログ・ジャンル・ハッシュタグ・ランキングといった“内側の読者導線”が最初から用意されています。
これにより、検索やSNSに頼り切らなくても初期の露出を得やすく、少人数運用でも更新→反応→改善のサイクルを回しやすいです。
スマホアプリの操作も軽く、下書き→公開→画像差し替えまでストレスが少ない点も実務向きです。一方、レイアウトやサイト全体の設計自由度は控えめなので、深いカスタマイズより「読みやすいテンプレ+分かりやすい内部リンク」で成果を出す考え方が相性◎です。
記事は導入で結論を先出しし、本文は要点→理由→具体→次の行動の型で統一。区切りごとに最適な1本だけ関連リンクを置き、末尾はカテゴリやおすすめ記事へ誘導します。
週1回、検索とアクセスの数字を前後比較し、タイトル語順・導線位置・FAQの追加など小さな改修を積み上げるのがコツです。
- プロフィール・ヘッダー・ジャンルを固定→誰に向けたブログかを一目で伝える
- 記事テンプレを作成→導入で結論・本文は要点→理由→具体→行動
- 本文末の導線を1本に絞る→カテゴリ or おすすめ記事へ自然に誘導
読者機能と内部導線で新規流入を得やすい仕組み
アメブロは「プラットフォーム内で見つかる仕組み」が豊富です。フォロー・いいね・リブログで記事が連鎖的に広がり、ジャンルとハッシュタグの組み合わせで新規読者に届きます。
まずはジャンルを1~2個に絞り、タグは上位3~5個を固定して記事間の関連性を強めましょう。タイトルは主要語を前半に置き、導入1段落は結論先出し。
本文は1見出し1テーマで、要点ボックスを要所に配置すると流し読みでも価値が伝わります。内部導線は「比較→商品(またはサービス紹介)」「事例→ノウハウ」「FAQ→カテゴリ一覧」など、読者の次の疑問に直結する1本だけを区切りごとに提示します。
スマホ前提で、見出し直後と本文末に導線が視界に入るよう配置するのが効果的です。週に一度、クリックが少ないリンクのアンカー文を「価値+名詞」に言い換える(例:通学で軽い◯◯を見る→)だけでも到達が伸びます。
| 導線の置き場所 | おすすめのアンカー文例 |
|---|---|
| 見出し直後 | 「まずは人気の◯◯カテゴリを見る→」「今日のレシピで使った◯◯はこちら→」 |
| 比較表の直後 | 「通勤重視なら◯◯を選ぶ→」「雨の日に強い◯◯を見る→」 |
| FAQの回答直後 | 「返品条件を確認したら、サイズ別の一覧へ→」 |
- ジャンル:1~2個に固定/タグ:上位3~5個を使い回す
- 1ブロック=リンク1本に絞る(選択肢を増やしすぎない)
- 毎週同じ曜日に数字を比較→アンカー文と位置を小さく調整
テンプレとカスタマイズで読みやすさを確保
デザインを作り込みすぎなくても、「読みやすいテンプレ」と「軽いカスタマイズ」を徹底するだけで離脱は減らせます。
ファーストビューは文字+小さめ画像1枚に抑え、下の画像はスクロール後に読み込む設計に。見出しはH2=章の結論、H3=具体(手順・比較・Q&A)で1見出し1テーマにします。
段落は短く区切り、長い説明は要点ボックスで要約。画像は同じ幅で統一し、代替テキストに画像の役割(例:生地の質感、サイズ比較)を短文で入れます。
ボタンとテキストリンクは併用し、見出し直後と本文末の2か所に置くとタップ機会が増えます。サイド要素に頼りすぎず、本文の流れの中で次の行き先が自然に目に入る配置が理想です。
最後に、テンプレの更新は週1で1か所だけ(例:導入下の要点ボックスの文面)に限定し、前後比較で効果が出たら全記事に反映しましょう。
| 要素 | 実装ポイント |
|---|---|
| 導入 | 結論→本文で提供する内容→次の一歩を一段で明示 |
| 見出し | H2は結論、H3は動詞や質問で具体化(1見出し1テーマ) |
| 画像 | 幅を統一/雰囲気写真より説明画像優先/代替テキストを付与 |
| リンク | 具体的アンカー文+本文の区切りごとに1本だけ設置 |
- 変更点は1か所に限定→効果を判定しやすくする
- 更新前後のスクリーンショットと日付を保存
- 良い結果が出たら全記事に横展開→運用を軽くする
収益導線の作り方と広告表記の基本
収益導線は「記事→比較/事例→商品・申込」の一本道に絞ると、少ないPVでも成果が見えやすくなります。
基本の流れは、入門やFAQで不安を解消→比較で用途別の結論を提示→結論直後に対象商品のリンクを1本だけ配置→事例では「使用アイテム」ボックスで再掲、が鉄則です。
自社商品・サービスはフォームや問い合わせへ、アフィリエイトは商品ページやカテゴリへ誘導します。広告・アフィリエイトを含む場合は、読者が一目で分かる位置(リンクの近くや冒頭)に「広告/PR」などの表記を置き、誤解を避けます。
比較や「おすすめ」表現を使うときは、評価軸(価格・耐久性・レビュー件数など)と条件(対象期間・型番等)を近接表示しましょう。
計測は、商品リンクとカテゴリリンクでクリック名を分け、週1で到達率を前後比較。クリックが弱いときは、アンカー文を「価値+名詞」(例:雨でも安心な防水◯◯を見る→)へ言い換えるだけでも改善します。
| 場面 | 導線と配置 | 表記と計測のポイント |
|---|---|---|
| 比較の結論直後 | 用途別に商品リンクを1本ずつ | 「広告/PR」を近接表示/リンク名で商品とカテゴリを区別 |
| 事例の結果直後 | 使用アイテムをボックスで再掲+色違いはカテゴリ | ベネフィットを短文で添えてクリックを後押し |
| FAQの回答直後 | 不安解消→対応カテゴリへ1本だけ | 断定表現を避け、条件や注意書きを明記 |
- 1段落に複数の購入リンクを並べる(迷いと離脱の原因)
- 根拠のないNo.1/最安の断定(条件と評価軸を必ず併記)
- 広告表記が遠い・小さい(リンク近くで明確に)
始め方の手順とチェックリスト

ブログを「今日から始めて、1週間以内に1本公開」まで進めるには、手順を固定して迷いを減らすことが重要です。
最初に、用途を一つに絞ります(例:個人発信で集客を増やしたい/アフィリエイトで収益化したい/企業広報として実績を蓄積したい 等)。
つぎに、プラットフォームの規約・独自ドメイン・広告可否・費用の4点を確認し、最小構成で立ち上げます。記事はテンプレを用意し、導入で結論を先出し→本文は要点→理由→具体→次の行動の順で統一。
内部リンクは区切りごとに最適な1本だけを置き、本文末に「次に読むべき1本」を必ず提示します。公開後は、検索レポート(検索語×ページ)とアクセス解析(着地→内部リンク→CTA→フォーム)の二本柱で前後比較し、毎週1か所だけ小さく直すのがコツです。
以下の表とリストを、そのまま初期運用のチェックとして使ってください。
| 段階 | やること(最小構成) |
|---|---|
| 準備 | 用途を一つに固定→プラットフォーム比較(規約・独自ドメイン・広告可否・費用) |
| 設計 | 記事テンプレ作成/内部リンクの固定順路(入門→比較→手順→事例→FAQ) |
| 公開 | タイトル前半に主要語/導入は結論先出し/本文末に「次に読む1本」 |
| 計測 | 検索語×ページのクリック率/着地→CTA→フォーム到達率を記録 |
| 改善 | 変更は1テーマだけ(例:タイトル)→7〜14日で前後比較→テンプレへ反映 |
- Day1:用途と比較基準を決め、プラットフォームを確定
- Day2:テンプレと内部リンクの順路を作る
- Day3〜5:1記事を完成→公開
- Day6:検索とアクセスの数字を記録
- Day7:タイトル or 導線のどちらか1点を小さく修正
プラットフォーム選定の確認項目(規約 独自ドメイン 広告可否 費用)
プラットフォーム選びは、次の4点を押さえれば失敗が減ります。まず規約です。広告やアフィリエイト、外部リンク、画像やロゴの扱いなど「やってよいこと/ダメなこと」が明確かを確認します。
次に独自ドメインの可否と運用方法(設定手順、将来の移行時にリダイレクトができるか)を見ます。
3つ目は広告可否と表記ルールで、リンク付近や冒頭に「広告/PR」表記を置けるか、比較・ランキング時の基準表記を許容しているかを要チェック。
最後は費用で、初期・月額・追加(テーマ・アプリ・画像容量等)を合算し、1年総額で比較します。これら4点はいずれも公開後の運用に直結するため、「合格ライン」を先に言語化し、満たさない候補は早めに除外しましょう。
| 項目 | 確認ポイント | 合格ラインの例 |
|---|---|---|
| 規約 | 広告/アフィリエイトの可否、外部リンク、画像やロゴの扱い | 広告可/外部リンク可/引用の条件が明文化 |
| 独自ドメイン | 設定可否、常時HTTPS、将来のリダイレクト | 独自ドメイン可+基本的なリダイレクト対応 |
| 広告可否 | 表記の位置・書式、比較やランキング時の基準表記 | リンク近くで「広告/PR」明記を許容/基準表記が可能 |
| 費用 | 初期・月額・追加費用(テーマ/アプリ/容量) | 1年総額が予算内/追加費用の見通しが立つ |
【赤信号(選定から外す目安)】
- 広告や外部リンクの扱いが不明確/禁止が多すぎる
- 独自ドメイン不可、またはリダイレクトが用意されていない
- 追加費用が不透明で、長期の総額が読めない
- 合格ライン→○/×判定→残った2候補を「開始のしやすさ」で決定
- 移行性は必ずメモ(書き出し形式、画像の扱い)
記事設計と内部リンクの型を決める
記事設計は「型」を先に作ると速く、品質も安定します。導入は読者の悩みを一文で受け、すぐ結論を提示。本文は要点→理由→具体→次の行動の順で統一し、H2は章の結論、H3は手順・比較・Q&Aなど具体を1見出し1テーマで書きます。
内部リンクは、入門→比較→手順→事例→FAQという順路を固定し、区切りごとに最適な1本だけ置きます。アンカーテキストは「こちら」ではなく、価値+名詞で具体に(例:雨でも安心な防水ジャケットを見る→)。
本文末には必ず「次に読む1本」を提示し、行き止まりを無くします。プラットフォームの自由度が低い場合でも、この“本文内の順路設計”だけで回遊は大きく変わります。
テンプレ更新は週1で1か所に限定し、前後比較で効果があれば全記事に反映して作業を軽くしましょう。
| 記事型 | 骨子(例) | 次の導線(例) |
|---|---|---|
| 入門 | 全体像→用語→最初の一歩→注意点 | カテゴリ一覧へ→、入門の続き |
| 比較 | 評価軸→用途別の結論→比較表→根拠 | 結論直後に該当商品へ→ |
| 手順 | 準備→やること→確認→つまずき対処 | 手順の最後で関連商品/申込みへ→ |
| 事例 | 背景→施策→結果→学び | 使用アイテム、同テーマの比較へ→ |
- タイトル前半に主要語/導入は結論先出し
- H2は結論、H3は動詞や質問で具体化(1見出し1テーマ)
- 本文末に関連記事1本+目的行動への導線1本
公開後の計測と見直しの進め方
改善は“作業量”ではなく“数字”で行います。週1回、同じフォーマットで「検索の数字(検索語×ページの表示回数・クリック率)」と「アクセスの動き(着地→内部リンク→CTA→フォーム到達→完了)」を前後比較します。
変更は1テーマに絞るのが鉄則です(例:今週はタイトル、来週はCTAの位置)。検索の数字でクリック率が低い組み合わせは、タイトル前半の語順を検索語に寄せ、導入の結論先出しで一致度を上げます。
アクセスの動きで詰まっている箇所は、見出し直後の導線追加、アンカー文の具体化、フォーム項目の削減・任意化などで摩擦を下げます。
変更前後はスクリーンショットと日付を保存し、7〜14日の同条件で差を確認。効果が出た配置・文言・手順はテンプレに昇格して横展開します。
| 症状 | 見る数字 | 最初の打ち手 |
|---|---|---|
| 表示多・クリック少 | 検索語×ページのクリック率 | タイトル前半の語順調整/記事タイプの明示/導入の結論先出し |
| 着地後に離脱 | 平均滞在・スクロールの深さ | 要点ボックス前倒し/段落を短く/画像を説明用に |
| 内部リンクが踏まれない | リンククリック率・回遊先到達率 | 区切りごとに1本へ削減/アンカーを価値+名詞に言い換え |
| CTAやフォームで離脱 | 到達率・完了率・項目ごとの離脱 | CTA位置の追加(見出し直後/末尾)/項目削減・任意化・入力例 |
- 対象ページを一つ選ぶ→変更テーマを一つに固定
- 検索とアクセスの数字を記録→小さく改修→前後比較
- 当たりはテンプレ化→同タイプの記事へ適用
将来の移行とリスク対策

ブログは「始めやすさ」で選んでも、成長すると要件が変わります。記事数が増え、カテゴリーが増え、収益導線を増やしたい段階では、別プラットフォーム(例:WordPress)へ移る判断が出てきます。
そのときに困るのが、URLが変わって検索や共有リンクが切れる、画像が消える、広告表記や出典の記録が残っていない、といった“移行リスク”です。
対策の基本は、日頃から移行を前提とした運用にしておくことです。具体的には、本文・画像・メタ情報を定期的に保存、内部リンクは一貫した並びで設計、独自ドメインの運用で住所を自分で持つ、公開前後の変更履歴を残す、という4点を徹底します。
移行そのものは「準備→試験→切替→監視」の短いサイクルで小さく進め、同じ指標で前後比較を行います。下表をリスクの棚卸しと予防策のメモとして使ってください。
| 想定リスク | 起きやすい場面 | 予防策の例 |
|---|---|---|
| リンク切れ | URL構造が変わる、スラッグが自動付与 | 独自ドメイン運用、記事スラッグを統一、転送表を事前作成 |
| 画像欠損 | 外部保存のみ、画像パスが固定 | 原寸画像を別保管、挿入画像の一覧を台帳化 |
| 表記不備 | 広告や出典の記録が散在 | 広告表記と出典を記事ごとに台帳管理 |
| 順位/流入の急変 | 切替日に大きな変更を同時実行 | 段階移行、恒久転送の動作確認、2週間は監視を強化 |
- 本文・画像・メタ情報のバックアップを週1で取得
- 内部リンクを固定順路で設計し、台帳に残す
- 独自ドメインを取得・運用して“住所”を自分で持つ
データの管理とバックアップの考え方
移行がうまくいくかは、平時のデータ管理で決まります。保存すべきは「本文」「画像と代替テキスト」「メタ情報(タイトル、説明、タグ、カテゴリー、公開日、スラッグ)」「内部リンクの対応表」「広告/出典/権利の台帳」の5系統です。
形式は、本文はテキストまたはHTML、画像は原寸と掲載用の両方、メタ情報は表形式が扱いやすいです。
頻度は、初回の全件保存、週1の差分保存、レイアウト変更や大量公開の前後で臨時保存、という三層で考えます。
保存先は二重化が基本で、クラウド保存に加えて外部ドライブにも置きます。命名は「日付_記事ID_用途」の順で統一し、あとから検索できる状態にしておきます。最後に、復元テストを月1で実施し、「別環境で1本復元→画像も表示→内部リンクも通る」まで確認しておくと安心です。
| 対象 | 保存形式・内容 | 頻度・保管場所 |
|---|---|---|
| 本文 | テキストまたはHTML、見出し構造を保持 | 週1で差分保存/クラウド+外部ドライブ |
| 画像 | 原寸と掲載用の二種、代替テキストを別表に | 公開時と改稿時に保存/台帳と同一階層に配置 |
| メタ情報 | タイトル、説明、タグ、カテゴリー、公開日、スラッグ | 週1で一覧更新/表計算に集約 |
| 内部リンク | 出発URL→到達URLの対応表、アンカー文 | 改稿のたび更新/移行時の転送表に流用 |
| 広告・出典 | 広告表記の位置、出典URL、ライセンス条件 | 公開時に登録/表と証跡ファイルを紐づけ |
- 画像をプラットフォーム任せで保管し、原本を残さない
- 記事IDやスラッグを途中で頻繁に変える(対応表が崩れる)
- 復元テストをしないまま、いきなり移行日に本番切替
独自ドメイン運用とWordPressへの移行プラン
独自ドメインは、住所を自分で持つという意味です。ドメインを先に確保してブログに割り当てておけば、将来プラットフォームを変えても、読者は同じ住所に来られます。
移行は「準備→試験→切替→監視」の順で小さく進めます。準備では、現行サイトのURLと新サイトのURLを一対一で結んだ転送表を作り、見出しや画像の差も併せて点検します。
試験では、別環境で新サイトを立ち上げ、数本の代表記事で表示・内部リンク・画像・広告表記が想定どおりか確認します。
切替では、恒久的な転送を設定し、重要ページから順に反映。監視では、検索のクリック率、着地からの遷移率、フォーム完了の変化を同期間で比較します。
下の手順を素直に踏めば、大きなトラブルを避けやすくなります。
- 独自ドメインを取得し、現行ブログに割り当てる(可能な範囲で)
- WordPressを最小構成で用意し、軽いテーマと固定の記事テンプレを準備
- 代表記事で表示・内部リンク・画像・広告表記の動作を確認
- 全URLの転送表を作成し、旧→新の対応をチェック
- 恒久的な転送を設定し、優先ページから段階的に切替
- 切替後2週間は、検索とアクセスの数字を前後比較し微調整
| 段階 | 目的 | チェック項目 |
|---|---|---|
| 準備 | 住所と内容の整合を取る | 独自ドメイン設定/転送表/画像と出典の確認 |
| 試験 | 代表記事で不具合を潰す | 表示、内部リンク、画像、表記、導線の動作 |
| 切替 | 読者を迷わせずに移行 | 恒久転送の動作、検索結果の見え方、共有リンクの到達 |
| 監視 | 数字で微調整 | クリック率、滞在と回遊、完了率の前後差 |
- URL構造を無理に変えない。変える場合は転送表で一対一に対応
- 切替日に複数の大改修を同時にしない。効果が判定できない
- 旧環境は30日以上残し、未転送URLの洗い出しに使う
まとめ
本記事では、比較の前提と判定基準をそろえた上で主要7サービスの特徴を解説し、目的別のおすすめと実践手順を提示しました。
結論は、即効性と始めやすさを重視するならアメブロ、自由度や資産化重視ならWordPress。次の一歩は、チェックリストで要件を確認→アメブロで初期設定→記事と導線を整え、週次で数字を見直しましょう。