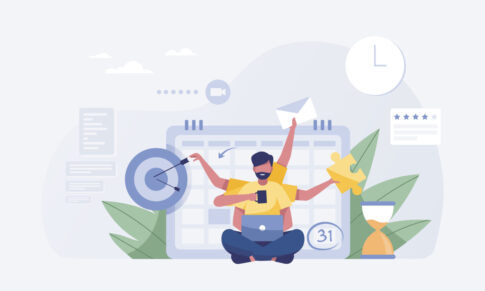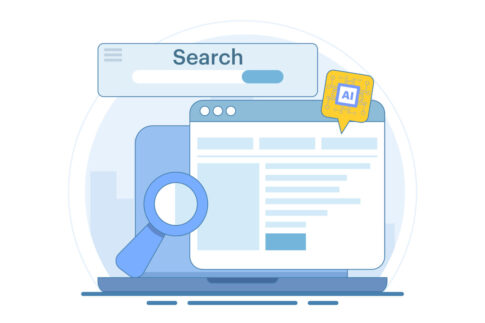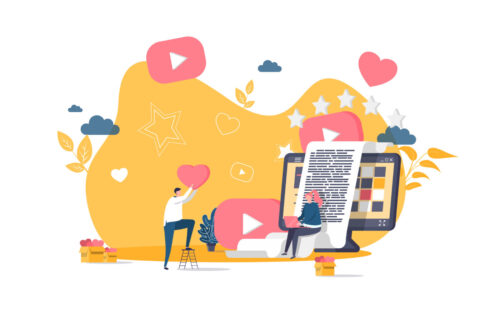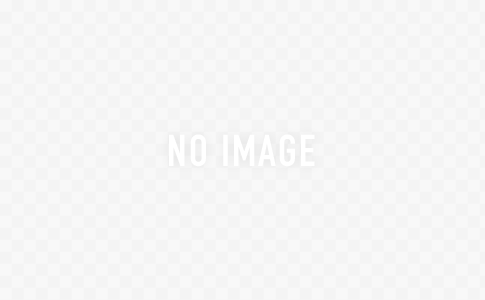Web集客のSEOは何から始める?本記事は、検索意図とキーワード設計、コンテンツ作成、内部対策、技術SEO、計測までを10手順でやさしく解説します。
Search ConsoleとCore Web Vitalsの見方も整理し、少ない予算でも再現しやすい進め方と成果を伸ばすコツをまとめます。
Web集客のSEOの基本と全体像

SEOは「検索ユーザーの疑問を最短で解決し、行動(購入・問い合わせ・予約)につなげるための設計と改善」のことです。
広告のように入札で露出を買う手法ではなく、検索結果に自然表示される「オーガニック流入」を継続的に増やします。
全体像は、目的とKPIの設定→検索意図に基づく情報設計→コンテンツ制作と内部対策→技術面の整備(表示速度・モバイル対応・インデックス)→計測と改善の循環です。
特定のテクニックだけで順位が上がるわけではなく、サイト全体の体験と信頼、そして更新運用の仕組みが揃ってはじめて成果が安定します。
たとえばECなら「比較ページ→レビュー強化→FAQ→カート導線」を一続きに設計し、BtoBなら「課題解決記事→資料DL→導入事例→相談予約」へと段階的に進めます。下表はSEOを支える3つの層と役割の整理です。
| 層 | 主な内容 | 代表KPI |
|---|---|---|
| コンテンツ | 検索意図に合う答え・事例・FAQ | 表示回数、CTR、読了率、CVR |
| 内部/導線 | 見出し・内部リンク・CTA・回遊 | 直帰率、回遊率、CTAクリック率 |
| 技術 | Core Web Vitals、モバイル、インデックス | LCP/FID/CLS、クロール/インデックス率 |
【押さえるポイント】
- 目的(CVの種類)とKPI(CVR・CPAなど)を先に固定する
- 検索意図→情報設計→導線の「一貫性」を最優先にする
- 計測→改善→再配分を週次で回す運用を決める
- テクニックではなく「設計×運用」の継続が成果を作る
- 短期(LP改善・内部リンク)と中期(記事更新)を並走
SEOの目的とWeb集客の関係整理
SEOの目的は「検索から来た人が、迷わず目的の行動に進める状態を作る」ことです。順位やアクセス数は手段であり、真のゴールは問い合わせ・購入・予約などのコンバージョンです。
Web集客の中での位置づけは、広告が短期の集客を担い、SNSが想起と関係づくりを担うのに対し、SEOは「課題解決の入口」を広く作り、中長期で安定した流入と信頼を蓄えます。
たとえばBtoBでは、検索での情報収集→比較→事例確認→資料DL→相談という段階があり、各段階に合うページを用意して内部リンクで結びます。
ECなら、カテゴリ検索→商品比較→レビュー・FAQ→カートの導線を短くし、途中で配送・返品・価格の不安を解消します。目的を明確にすると、記事のテーマ選定、見出しの言い換え、CTAの配置などの判断が揃い、改善が早く進みます。
【目的と指標の置き方】
- 目的を一つに絞る→例:月間の相談予約◯件を目標
- 主要KPI→CVR・CTR・読了率(比較ができる定義に統一)
- 中間KPI→内部リンククリック・資料DL率・カート到達率
| 段階 | ページ例 | 見る指標 |
|---|---|---|
| 入口 | ハウツー・用語・課題解決記事 | 表示回数、CTR、滞在時間
|
| 比較 | 選び方・比較・チェックリスト | 直帰率、内部リンククリック、読了率 |
| 背中押し | 導入事例・FAQ・レビュー | CTAクリック率、CVR |
初心者が整える必須3点の基礎
最初に整えるべきは「①計測環境」「②情報設計」「③技術の土台」の3つです。計測環境は、Search Consoleの所有権確認と、GAの目標(購入・問い合わせ・予約)設定、主要LPのイベント計測をそろえます。
情報設計は、優先キーワードを「情報収集」「比較」「行動準備」に分け、入口→比較→事例/FAQ→CTAの順で回遊を設計します。
技術の土台は、サイトマップの送信、noindex/robotsの誤設定がないか、モバイル表示と速度(画像最適化・不要スクリプト削減)を点検します。これらが整うと、記事やLPの改善が数字に反映され、次の一手が決めやすくなります。
| 基礎 | やること | 確認の目安 |
|---|---|---|
| 計測 | Search Console/GA設定、目標の定義 | 主要CVの計測・クエリ/ページの可視化 |
| 情報設計 | 意図別にキーワード整理、内部リンク計画 | 入口→比較→事例の三角リンクが機能 |
| 技術 | サイトマップ、モバイル、画像最適化 | 主要ページの表示速度・インデックス安定 |
- CVの未設定→改善しても効果が見えない
- 記事単発で完結→内部リンクが弱く回遊しない
- 画像が重い→ファーストビューで離脱が増える
Google公式を軸に学ぶ基本手順
学習と実装は、Googleが公開している公式ドキュメントやガイドを軸に進めると迷いません。
基本手順は、キーワードと検索意図の確認→検索結果の上位ページの見出し調査→自サイトの役割(入口/比較/背中押し)の決定→構成案の作成→公開→Search Consoleで検証→見出し・導線の改善の循環です。
技術面は、Core Web Vitalsの主要指標(表示速度やレイアウトの安定性)を改善し、サイトマップ送信とインデックス状況を定期確認します。
構造化データ(FAQ・製品・パンくず)を使うと検索結果での見え方が改善し、CTR向上が期待できます。
【実装フロー(6週間の例)】
- 週1〜2本の改善/新規記事を計画→役割とKPIを設定
- 公開1週間後にSearch Consoleで表示/CTRを確認
- 見出しの言い換え・内部リンク追加で回遊を強化
- 速度改善(画像圧縮・不要スクリプト削除)を実施
- CVRを見てCTAの位置・文言・FAQを改善
- 良い要素にリソース再配分→次の6週間へ
- 公式情報→上位ページ→自サイトの検証の順で確認
- 「用語の定義」をそろえ、数字は同じ条件で比較
検索意図とキーワード設計の基本

「どの言葉で検索した、どんな悩みを解決したいのか」を読み解くのが検索意図です。Web集客では、検索意図に合うページを用意し、入口→比較→背中押し→CV(購入・相談・予約)へ自然につなげる設計が基本になります。
キーワードは量(検索数)だけで選ぶのではなく、自社の目的に近い“意図の強さ”と、作れるコンテンツとの相性で決めます。
たとえば「やり方・比較・口コミ・最安・近くの〜」では求めている答えが違うため、適切なページ型(ハウツー、選び方、事例、FAQ、店舗情報など)を割り当てます。
さらに、内部リンクで近い意図のページを結ぶと回遊とCVRが安定します。下表は意図とページ型、見る指標の整理です。
| 意図 | 合うページ型 | 主な指標 |
|---|---|---|
| 情報収集 | ハウツー・用語解説・チェックリスト | 表示回数、CTR、読了率 |
| 比較検討 | 選び方・比較表・メリデメ・事例 | 内部リンククリック、直帰率、CVR |
| 今すぐ行動 | LP・価格/申込・Q&A・保証/返品 | CTAクリック率、CVR |
| ローカル | アクセス・営業時間・予約/地図 | 電話/経路/予約アクション |
【この章でやること】
- 意図を4タイプに分けて理解する
- キーワードを役割別に種分けする
- 需要と難易度で優先度を決める
- “量より適合”→意図に合うページ型を先に決める
- 内部リンクで意図をまたぐ導線を作る
検索意図4タイプと調べ方
検索意図は大きく「情報収集(Know)」「比較検討(Commercial)」「今すぐ行動(Do/Transactional)」「ローカル(Local)」の4タイプに分けると整理しやすいです。
例えば「やり方・とは」は情報収集、「おすすめ・比較・口コミ」は比較検討、「申し込み・価格・クーポン」は今すぐ行動、「近くの・地域名+業種」はローカルのサインです。
実際の調べ方は、検索結果の1ページ目を観察し、出ているページ型と検索結果の機能(地図・動画・ショッピング・FAQなど)を確認します。
上位の見出し(H2/H3)に並ぶ語を拾うと、読者が求めている具体的な答えが分かります。社名やブランド名が多い場合は指名寄りで、非指名で集客したい場合は別の切り口を探すのが安全です。
【調べ方の手順】
- 1ページ目のページ型を分類(ハウツー/比較/LP/店舗)
- 出現する機能を確認(地図・動画・ショッピング・FAQ)
- 上位ページの見出しを収集→頻出語をメモ
- 関連キーワード/サジェストで意図の幅を確認
- 自サイトの役割(入口/比較/背中押し)を決める
| 意図タイプ | 見分けるヒント | 設計のコツ |
|---|---|---|
| 情報収集 | 「やり方・とは・手順・チェック」 | 図解とチェックリスト、結論先出し |
| 比較検討 | 「おすすめ・比較・メリット・口コミ」 | 比較表と判断基準、事例リンク |
| 今すぐ行動 | 「価格・申込・予約・クーポン」 | 保証/送料/返品を近くに配置 |
| ローカル | 「近くの・駅名・地域名+業種」 | 地図/営業時間/予約導線を最短化 |
- 上位10件のページ型が揃っているか→揃う=意図が明確
- FAQリッチ結果の有無→質問に直接答える必要あり
- 動画/地図が強いか→別フォーマットの用意を検討
キーワード種分けと選定手順
集めた候補語は、役割と目的に合わせて種分けすると迷いが減ります。基本は「指名(ブランド/商品名)」「非指名のカテゴリ/悩み/用途」「ロングテール(3語以上の具体語)」「季節・キャンペーン」の4区分です。
指名はCVに直結しますが、新規獲得には非指名の入口が必要です。ロングテールは検索数が少なくても競合が弱い場合が多く、早期に成果を作りやすいです。
季節語は変動が大きいので、前倒しの準備が鍵になります。選定の流れは、目的→テーマ群→候補抽出→意図タグ付け→重複整理→優先度スコア(需要×意図の強さ×難易度×事業適合)で決める、の順がシンプルです。
【選定の手順】
- 目的とCV定義を確認→「何を増やしたいか」を固定
- テーマ群を作成→悩み/用途/比較/地域で箱分け
- 候補語を収集→関連語・サジェスト・社内FAQ
- 意図タグ付け→情報収集/比較/行動/ローカル
- 優先度スコア付与→需要・難易度・事業適合で評価
| 種別 | 例 | 合うページ型 |
|---|---|---|
| 指名 | サービス名+料金/評判 | LP・料金/FAQ・事例 |
| カテゴリ | 「SEO ツール」「集客 施策」 | 選び方・比較・ベスト◯選 |
| 悩み/用途 | 「表示速度 遅い 改善」 | ハウツー・チェックリスト |
| ロングテール | 「BtoB リード 獲得 方法」 | 具体手順・事例・テンプレ |
| 季節/地域 | 「年末 セール 集客」「新宿 美容」 | カレンダー記事・ローカル情報 |
- “勝てる小さな山”を先に取る→ロングテールから着手
- CVに近い語へ内部リンクを用意→回遊でCVRを底上げ
需要と難易度の見極めポイント
需要は「どれくらい検索され、いつ伸びやすいか」、難易度は「上位にどんな強さのページがいるか」で判断します。需要は検索回数の目安や関連語の広がり、季節性の有無で見ます。
難易度は、上位のページ型が大手サイトや公的機関で固まっていないか、被リンクやブランド力が極端に強くないか、情報の深さや更新の新しさ、検索結果に動画・地図・ショッピングなど専用枠が多すぎないかを確認します。
勝ち筋のサインは、上位に古い記事や個人ブログが混ざる、見出しが検索意図とズレている、FAQや表の整理が甘い、といった“改善余地”が見えることです。
【評価の観点】
- 需要→検索回数の目安、関連語の数、季節性の波
- 難易度→上位サイトの種類、情報の深さ、更新頻度
- 収益性→CVに近いか、在庫/提供可否、粗利との相性
| 指標 | チェック内容 | 判断のヒント |
|---|---|---|
| 需要 | 検索数/関連語/季節性 | 安定×関連語が多い=中長期の柱 |
| 難易度 | 上位のサイト力/情報量/新しさ | 多様なサイトが混在=入り込む余地あり |
| 収益性 | CV近接性/粗利/提供体制 | CV導線が短い語を優先 |
- 検索数だけで選ぶ→意図不一致で離脱が増える
- 大手独占の語に固執→学習が進まず工数浪費
- 季節語の準備が遅い→波が来ても載れない
【まとめ方のヒント】
- 需要×難易度×収益性でS/M/Lの優先度を付与
- 小さく勝てた語→内部リンクでCV近接語へ送客
コンテンツ制作と内部対策の要点

コンテンツ制作と内部対策は、検索意図に合った「答え」を用意し、ページ内外の導線で迷いをなくし、読み終わりの行動(購入・問い合わせ・予約)へ自然につなげることが基本です。
記事は「結論→理由→具体例→行動」の順にまとめ、タイトル・見出し・本文のメッセージを揃えます。内部対策では、見出し構造(H1→H2→H3)の階層を守り、関連ページとの内部リンクで回遊を設計します。
さらに、パンくずや構造化データで検索エンジンに文脈を伝え、表示速度やモバイル表示の快適さを確保すると、直帰率が下がりCVRが安定します。
ポイントは「小さく作り、早く計測し、毎週直す」運用に落とすことです。公開後1週間でSearch Consoleの表示回数・CTR、GAの読了率やCTAクリックを確認し、見出しの言い換えやFAQの追記、内部リンクの追加など、少ない工数で効果の大きい改善から手を付けると、学習が前に進みます。
| 要素 | 目的 | 主なKPI |
|---|---|---|
| タイトル/見出し | 検索意図との一致・期待の形成 | CTR、読了率、直帰率 |
| 本文/画像 | 疑問の解消・理解の促進 | スクロール率、滞在時間 |
| 内部リンク | 比較・事例・CTAへの誘導 | 回遊率、CTAクリック率、CVR |
- 構成案で意図と導線を先に設計
- 公開後1週間で表示/CTR/読了を確認
- 見出し言い換え・FAQ追記・内部リンク増強
タイトル・見出し・本文の整合性
タイトル・見出し・本文の整合性が高いほど、検索者の期待と実際の内容にズレが生まれにくく、CTRや読了率、CVRが伸びやすくなります。
タイトルでは検索意図の核心語(例:やり方・比較・料金・注意点)を入れ、読者が「自分の疑問に答えてくれる」と判断できる表現にします。H2は章の約束を短く明確にし、H3は手順・要点・事例など具体の切り口に分解します。
本文は各見出しの問いに即答し、根拠→具体例→行動(CTAや関連リンク)の順でまとめます。ファーストビューには結論とベネフィット、続く段落に図表や箇条書きで要点を提示すると、離脱が減ります。
公開後はSearch Consoleでタイトルと見出しの語を調整し、CTRが高いクエリを本文の見出しに反映すると一貫性がさらに高まります。
| 部位 | 役割 | チェック観点 |
|---|---|---|
| タイトル | 意図の提示・期待形成 | 核心語を含む/誇張なし/重複回避 |
| H2/H3 | 質問の分解・道筋提示 | 章の約束が明快/重複や飛びがない |
| 本文 | 即答→根拠→具体例→行動 | 冒頭で結論/図表で要点/CTAが近い |
【整合性を高める小ワザ】
- 見出しごとに「この段落で解く疑問」を一行で先に書く
- 本文の重要語をH2/H3にも反映→検索語との一致度UP
- CTA文言とタイトルの約束を一致→迷いを減らす
内部リンクと回遊導線の設計法
内部リンクは「次に知りたいこと」へ読者を誘導する道標です。入口記事から比較・事例・FAQ・CTAへ、逆に比較から入口や事例へ、三角形の回遊を意識して貼ると、直帰と取りこぼしが減ります。
リンクは文中の自然な位置(疑問が生まれる直後)に置き、アンカーテキストはクリック後に得られる価値を具体にします。
カテゴリページやパンくずで上位概念に戻れる道も用意し、関連記事ウィジェットは「関連性の高い順」に絞るとノイズが減ります。
LPや商品ページでは、レビュー・配送/返品・サイズ/料金など不安解消ページへ最短で移動できるリンクを近くに配置します。
公開後はクリックマップや回遊レポートを見て、クリックが少ないリンクは位置や文言を見直し、役割が重なるページは統合して迷子を防ぎます。
| 導線 | 目的 | 主なKPI |
|---|---|---|
| 入口→比較 | 選択肢の提示・判断基準の提供 | 内部リンクCTR、比較ページ読了率 |
| 比較→事例/FAQ | 不安解消・社会的証明の付与 | CTAクリック率、直帰率の低下 |
| 事例/FAQ→CTA | 行動の背中押し | CVR、フォーム到達率 |
【設計のコツ】
- 各ページの「次の一歩」を一つに絞って誘導
- アンカーテキストは「得られる価値」を明記
- 関連記事は厳選し、関連性の高い3〜5件に限定
- リンク過多で迷う→役割重複ページは統合
- 曖昧な文言→クリック後の価値が分かる表現に修正
- 重要導線が下部のみ→本文前半にも配置し機会損失を防止
構造化データとFAQ活用の基礎
構造化データは、ページの中身(記事・商品・FAQ・パンくず等)を検索エンジンに伝えるための「ラベル付け」です。
適切に実装すると、検索結果での見え方(リッチリザルト)が改善し、CTR向上が期待できます。まずはパンくず(BreadcrumbList)で階層を示し、記事やブログにはArticle、商品や料金ページにはProduct、Q&A形式のセクションにはFAQPageを検討します。
FAQは本文の重複を避け、検索者が実際に気にする質問(料金・返品・納期・使い方)を短く明快にまとめます。
スパム的な大量FAQや不自然なマークアップは逆効果なので、ユーザーの理解と行動を助ける目的に徹するのが安全です。
公開後はSearch Consoleでエラーや警告の有無を確認し、表示機会があるタイプから優先して整備すると、少ない工数で効果を得られます。
| 種類 | 主な用途 | 注意点 |
|---|---|---|
| BreadcrumbList | サイトの階層を明示 | パンくずと実際の階層を一致させる |
| Article | 記事/ブログの内容を明示 | タイトル・著者・日付の整合性を保つ |
| Product | 商品名・価格・在庫・レビュー | 価格/在庫の更新を怠らない |
| FAQPage | よくある質問と回答 | 重複乱用を避け、実用的なQ&Aに限定 |
- 質問は「料金・返品・納期・使い方」を優先
- 回答は短く→必要なら詳細ページへリンク
- 本文の重複は避け、最新情報に合わせて更新
SEOと表示速度の改善要点
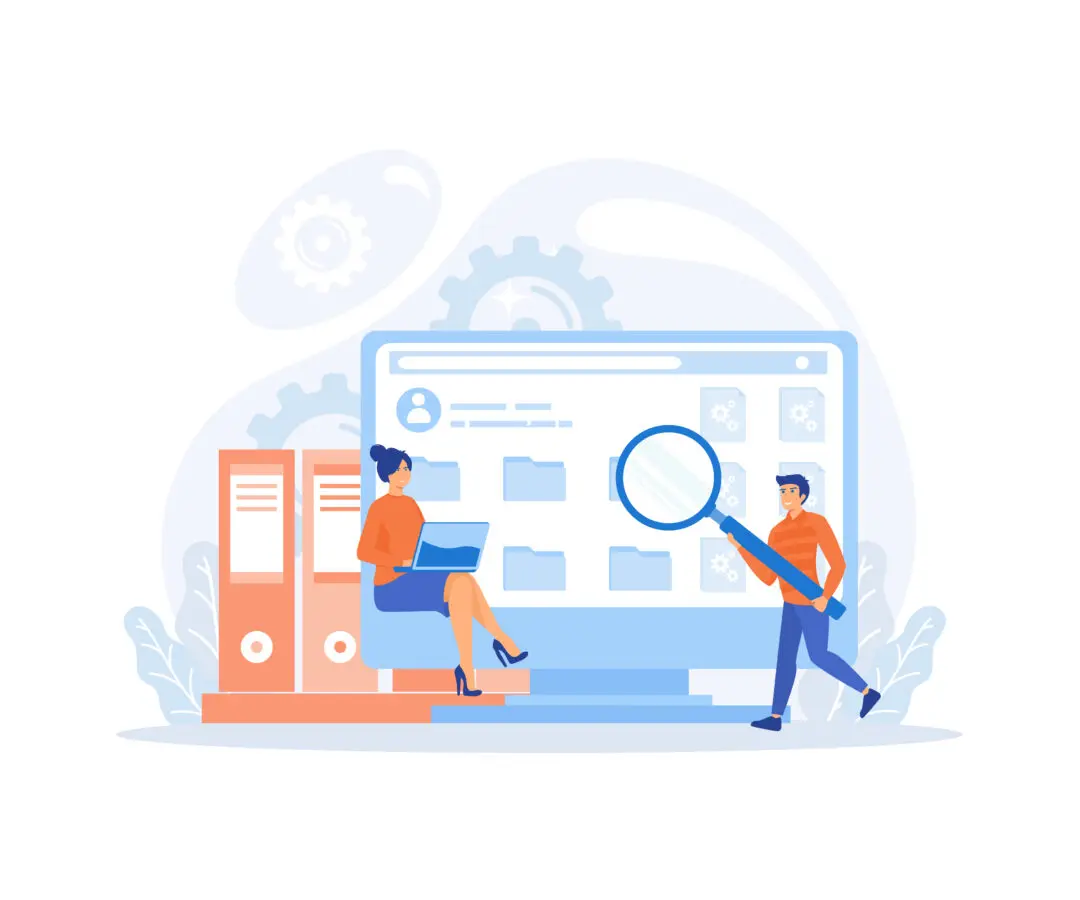
表示速度は検索順位だけでなく、直帰率やCVRにも直結します。とくにファーストビューが表示されるまでの体感速度が遅いと、ユーザーは読む前に離脱しやすくなります。
基本は、不要な通信と描画のブロック要因を減らし、重要な要素(ヒーロー画像・本文テキスト・主要ボタン)を先に出す設計です。
実務では、画像サイズの適正化・モダン形式(WebP/AVIF)・遅延読み込みの過不足調整、CSS/JSの分割と軽量化、フォントの最適化、キャッシュとCDNの併用が柱になります
。計測はラボ(PageSpeed計測等)とフィールド(実ユーザー)をセットで見て、Search Consoleの「ウェブに関する指標」と組み合わせて判断します。
また、改善は一度で終わりません。リリースや計測タグの追加で劣化しやすいため、週次で監視し、小さな修正を継続する体制が重要です。
| 領域 | 主な改善 | 見る指標/確認先 |
|---|---|---|
| 画像 | 適正サイズ化、WebP/AVIF、遅延読込、プレロード(ヒーロー) | LCP、CLS、合計転送量 |
| CSS/JS | 不要削除、分割、圧縮、遅延/遅延実行、重要CSSの優先 | INP、初回描画までの遅延、リクエスト数 |
| 配信 | CDN、キャッシュ制御、プリコネクト/プリロード | TTFB、地域別の応答時間 |
- ヒーロー画像と主要フォント→即軽量化/先読み
- 不要JSの停止→INP改善の即効打
- 画像遅延の過剰を解消→Above the Foldは除外
Core Web Vitalsの基本と改善
Core Web Vitalsは、実ユーザーの体験を測る代表指標です。現在は、最大コンテンツの表示速度を示すLCP、レイアウトのズレ量を示すCLS、操作の応答性を示すINPの3つが中心です。
目安は、LCPは2.5秒以内、CLSは0.1未満、INPは200ms未満が概ね良好のラインです。
LCPが遅い場合は、ヒーロー画像のサイズ過大・遅延読み込みの誤用・サーバ応答の遅さが原因のことが多く、画像の先読みやCDN、重要CSSの優先ロードが効きます。CLSは、画像や広告枠にサイズ指定がない、Webフォント切替でレイアウトが揺れる、
動的挿入の位置が不安定、といった設計起因が主因です。INPは、重いスクリプト・不要イベントの多発・メインスレッドの占有が原因になりやすく、不要JSの停止や分割、インタラクション直後の処理削減で改善します。
| 指標 | 目安(良好の目標) | 主な改善の打ち手 |
|---|---|---|
| LCP | 2.5秒以内 | ヒーロー画像の最適化/先読み、重要CSS優先、CDN・TTFB短縮 |
| CLS | 0.1未満 | 画像/広告の幅高さ指定、フォント最適化、予約領域の確保 |
| INP | 200ms未満 | 不要JS削減、遅延実行、イベント処理の見直し/分割 |
- ファーストビュー画像まで遅延→LCP悪化
- フォント最適化不足→読み込み時のレイアウト揺れ
- 解析タグの増設→INP/TTFBの悪化(必要最小限に)
サイトマップとインデックス最適化
XMLサイトマップは「発見」を助けますが、掲載=必ずインデックスではありません。重要なのは、クロールされやすく、重複や価値の低いURLを減らし、正規URLへ評価を集約することです。
基本は、主要テンプレートの代表URLのみをサイトマップに載せ、noindex指定や重複(パラメータ/重複カテゴリ)を除外します。
正規化(canonical)の整合、robots.txtでのブロック確認、404/リダイレクトの健全性も並行して点検します。公開後はSearch Consoleの「ページのインデックス」レポートやURL検査で、クロール済みだが未登録・代替ページ扱いなどの理由を確認し、内部リンク強化や重複解消で是正します。
多言語や地域別ではhreflangの整合を取り、ニュースや求人など特殊な領域は専用のサイトマップを使うと効率的です。
| 項目 | 目的/役割 | チェックの要点 |
|---|---|---|
| XMLサイトマップ | 重要URLの提示・更新通知 | 重複/パラメータ除外、lastmodの更新 |
| 正規化 | 評価の集約 | canonicalと内部リンクの一致 |
| クロール最適化 | 無駄URLを減らす | noindex/robots/リダイレクトの整合 |
- 重要ページ→サイトマップ+内部リンクで優先クロール
- 重複URLは統合→canonicalとリンク構造を一致
- 「クロール済み未登録」は品質/重複を疑う→内容を強化
モバイル対応と画像最適化の要点
検索流入の多くはモバイルです。モバイル対応は、単なるレスポンシブ表示だけでなく、読みやすさと誤タップ防止、そして画像の最適化まで含みます。
文字は十分なサイズと行間、ボタンは指で押しやすい間隔を確保し、折りたたみ要素は「開く→すぐ内容が見える」距離にします。
画像は、横幅に合わせた適正サイズを用意し、 srcset/sizes相当の仕組みで端末ごとに最適なものを配信します。ヒーロー画像は遅延対象から外し、必要に応じてプレロードしてLCPを守ります。サムネイルなど下部の画像は遅延で通信を節約します。
幅・高さの指定やアスペクト比の保持でCLSを防止し、アイコンは極力SVGに置き換えると軽量です。CDNで画像変換とキャッシュを任せると運用負荷が下がります。
| 領域 | 最適化ポイント | 効果/指標 |
|---|---|---|
| レイアウト | フォント/行間/タップ領域、折りたたみの設計 | 直帰率、読了率、INPの改善 |
| 画像配信 | 適正サイズ、WebP/AVIF、遅延/先読みの使い分け | LCP、転送量、CLSの安定 |
| アセット | SVG利用、スプライト整理、キャッシュとCDN | TTFB、再訪時の描画速度 |
- 全画像を遅延→ヒーローまで遅れてLCP悪化
- サイズ無指定→画像読込後にレイアウトがズレる
- 巨大フォントファイル→初回描画が重くなる
計測設計と改善サイクルの回し方

計測は「見える化→判断→実装」を素早く回すための仕組みです。最初に、最終CV(購入・問い合わせ・予約など)を一つに定義し、チャネル別の中間KPI(CTR・読了率・内部リンククリック・資料DL率など)を紐づけます。
次に、Search Consoleと分析ツールの目標定義をそろえ、広告管理画面のCV定義とも一致させます。ダッシュボードは“見るだけ”にせず、週次会議で「何をやめ、何に寄せるか」を決めるための画面にします。
改善は小さく短くが原則です。見出しの言い換え・内部リンク追加・FAQ追記・画像最適化など、工数が小さく効果が大きいものから順に実装し、翌週の数値で検証します。
BtoBなら資料DL→商談→受注の歩留まり、ECならカート到達→決済完了までの離脱点を特定して、最も影響が大きい箇所から潰します。
| 可視化対象 | 更新頻度 | 決めること |
|---|---|---|
| 検索パフォーマンス | 週次 | 高表示低CTRの見出し改善、上位クエリの深掘り |
| 回遊/導線 | 週次 | 内部リンクの追加/統合、CTAの位置・文言 |
| CVファネル | 週次 | 離脱点の特定→AB対象の選定と期限 |
- 指標は最小セットに絞る→CVR/CTR/読了率/内部リンクCTR
- 週次で改善を必ず一つ実装→翌週に結果を確認
- 勝ち要素へ予算と工数を再配分→選択と集中
Search Consoleの見るべき指標
Search Consoleは、検索ユーザーの「見られ方」と「クリックされ方」を把握する基本ツールです。検索パフォーマンスでは、クエリ・ページ・デバイスごとに「表示回数・クリック数・CTR・平均掲載順位」を確認し、高表示なのにCTRが低いページはタイトル/見出しの言い換えで改善します。
平均掲載順位の下落は競合や検索意図の変化が原因のことがあるため、上位ページの見出しを再調査し、意図に沿った不足項目を追記します。
ページタブでは、同一テーマで複数URLが競合していないか(カニバリ)にも注意し、統合や内部リンクの再設計を検討します。
インデックスレポートも毎週確認し、「クロール済み→インデックス未登録」「代替ページ(適切な canonical あり)」などの理由を特定して品質と重複を是正します。
【指標→アクションの変換例】
- 表示↑・CTR↓ → タイトル/見出しの約束を具体化、FAQを追加
- 表示↓・順位↓ → 上位の見出し調査→不足トピックを追記
- 表示↑・クリック↑ → 同テーマを派生記事化→内部リンクで面を広げる
- 未登録多発 → 重複解消・本文強化・内部リンクで正規URLへ評価集約
| ビュー | 目的 | 主な判断 |
|---|---|---|
| クエリ | 需要の把握と不足語の発見 | 高表示語の見出し反映、派生テーマの抽出 |
| ページ | URLごとの役割最適化 | 重複の統合、導線強化、カニバリ解消 |
| デバイス | モバイル最適化の検証 | CTR差と読了率差→FVやボタン配置を修正 |
CVR・CPA目標設定と改善手順
目標は「達成可否を数値で判断できる形」に落とし込みます。CVR(訪問→CVの割合)とCPA(1件獲得あたり費用)を最小セットにし、許容CPAは粗利やLTVから逆算します(例:粗利1万円ならCPA上限はそれ未満)。
BtoBは資料DL→商談→受注の歩留まりを見て、どの段階の改善が全体に効くかを判断します。改善手順は、①離脱点の特定→②仮説の言語化→③ABの設計→④実装期限→⑤結果の解釈→⑥再配分、という流れです。
たとえば「比較記事の直帰が高い」なら、表の一行目に判断基準を追加し、CTAの文言を「無料相談」から「失敗回避チェック配布」に変更して不安を先に解く、など“約束の再定義”が効きます。
| 課題 | 見る指標 | 改善例 |
|---|---|---|
| CTRが低い | 表示・CTR・クエリ一致度 | タイトルの核心語追加、見出しの並び替え、FAQ追加 |
| 読了率が低い | スクロール/滞在/離脱位置 | 結論先出し、要点表・図解、前半に内部リンク |
| CVRが低い | CTAクリック・フォーム到達 | CTA文言/位置変更、FAQで不安解消、フォーム短縮 |
- CVは一種類に固定→比較可能にする
- CPA上限は粗利/ LTVから逆算→意思決定を早く
- ABは“ひとつだけ変える”→因果が分かる
6週間テストで学習を加速する
6週間を一区切りにすると、仮説→検証→再配分のリズムが作れます。週1回の定例で「次の一手」を必ず決め、翌週の実装を前提に数値を見ます。
1〜2週目は基準線の把握と即効性のある改善(タイトル/見出しの言い換え、内部リンク追加、FVの要点表)、3〜4週目はABテスト(CTA文言・位置、FAQの有無、表現の粒度)、5〜6週目は勝ち要素への集中配分(同型記事の増産、導線の統一、広告やSNSとの連動強化)に充てます。
サンプル不足を避けるため、テスト対象は流入の多いURLから選び、同時に変える要素は一つに絞ります。撤退基準(例:2週連続で改善幅が目標未満なら終了)も先に決めて、感覚ではなくルールで継続/停止を判断します。
【6週間の運用イメージ】
- 現状把握と即効改善→タイトル/見出し/内部リンク
- 計測の整備→CV定義・イベント・ダッシュボード統一
- AB着手→CTA/FAQ/表現の粒度など一要素ずつ
- 結果反映→勝ち要素を横展開、負け要素は撤退
- 面づくり→派生記事と導線を増やし面で勝つ
- 振り返り→学びを次の6週間計画に反映
| 週 | 主な作業 | 判定/次の手 |
|---|---|---|
| 1–2 | 基準線の確認・即効施策の実装 | CTR/読了/内部リンクCTRの改善確認 |
| 3–4 | ABテストの実施 | 勝敗判定→勝ち案を本実装 |
| 5–6 | 集中配分と横展開 | 投資配分の更新→次サイクル計画 |
- 同時に多要素を変更→因果が不明になる
- 会議が報告会化→「次の一手」を決めない
- 判定基準が曖昧→撤退と継続の線引きを事前合意
まとめ
SEOは目的とKPIを定め、検索意図→設計→制作→計測→改善の順で回すことが重要です。本稿では10手順の型と指標を整理しました。
今すぐやることは、目的とCVの定義→優先キーワードの棚卸し→1本の改善実装→Search Consoleで検証→6週間のPDCA継続です。