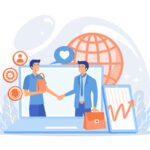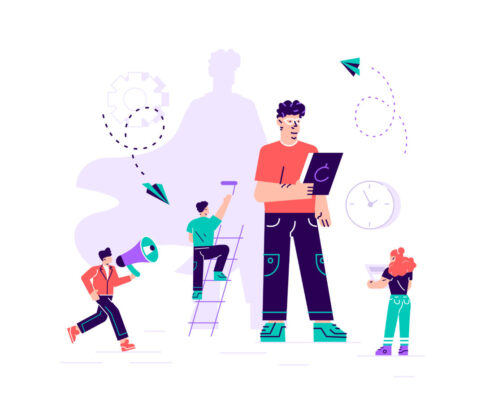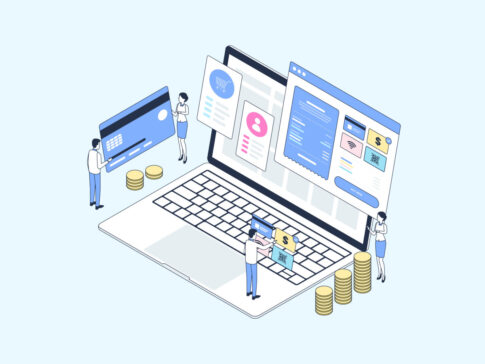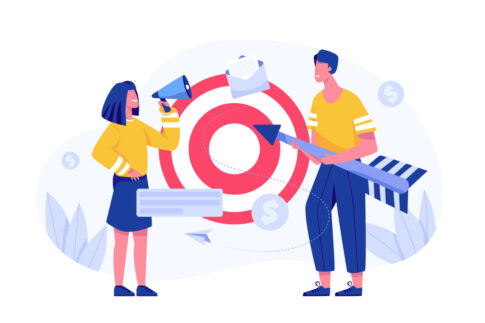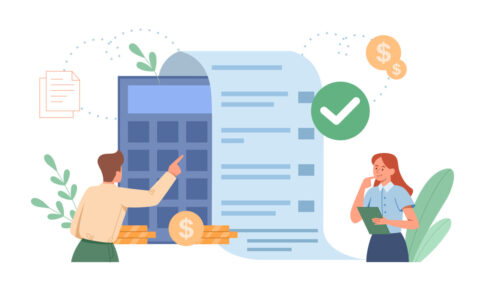アフィリエイトで収益が出てくると、「いくらから確定申告が必要?」「経費はどこまでOK?」「申告書はどう作る?」と不安になりがちです。この記事では、会社員の20万円目安や住民税申告が必要なケース、事業所得と雑所得の考え方、収入の集計方法、経費と家事按分の整理、申告書の作成から提出・納付までを手順でまとめます。やることが整理できるので、申告漏れや経費の迷いを減らし、準備から提出までスムーズに進められます。
申告が必要かの判定
アフィリエイト収益で確定申告が必要かどうかは、「あなたの立場」と「所得の金額」で決まります。ここでいう所得は、収入そのものではなく、収入から必要経費を差し引いた金額です。例えば、報酬の受取が30万円でも、サーバー代や教材代などの必要経費が10万円なら、所得は20万円になります。この判定を誤ると、申告が必要なのにしていない、逆に不要なのに不安で準備に時間を使いすぎる、といったムダが起きやすいです。
判断の入口は大きく2つです。1つは会社員など給与所得がある人か、もう1つは個人事業主やフリーランスなど給与がない人かです。さらに、住民税については所得税の確定申告とは別に扱いが変わる場合があります。ここで重要なのは、断定できるルールは押さえつつ、自治体の扱いなどで違いが出る場合がある点は条件付きで整理することです。
- 所得は収入ではなく 収入から経費を引いた金額
- 会社員は副業所得20万円超が一つの目安
- 所得税の申告が不要でも住民税の申告が必要な場合がある
- 還付につながる控除があるなら申告した方がよい場合がある
会社員は副業所得20万円超が目安
会社員など給与所得がある人は、アフィリエイトなどの副業による所得が一定額を超えると、所得税の確定申告が必要になります。一般に目安として知られているのが「副業所得が20万円を超える場合」です。ここで注意したいのは、判定が収入ではなく所得である点です。例えば、アフィリエイトの確定報酬が25万円でも、必要経費が6万円あれば所得は19万円になり、目安の20万円を下回る形になります。逆に、報酬が18万円でも経費がほとんどなければ所得は18万円で、やはり下回ります。
ただし、同じ年に複数の副業所得がある場合は合算して判定する必要があります。例えば、アフィリエイト所得が12万円、別の副業所得が10万円なら合計22万円となり、申告が必要になる可能性があります。また、年末調整をしている会社員でも、副業所得が一定額を超えると確定申告が必要になる点は変わりません。
【20万円判定の考え方】
- 所得は 収入から必要経費を引いた金額
- 複数の副業がある場合は所得を合算する
- 年末調整済みでも副業所得が一定額を超えると申告が必要になる場合がある
- 振込額で判断する → 報酬の収入と経費を整理して所得で判定する
- アフィリエイトだけ見てしまう → 他の副業所得も合算して確認する
- 経費を差し引かずに20万円超と判断する → 必要経費を集計してから判定する
20万円以下でも住民税申告が必要な場合
副業所得が20万円以下で、所得税の確定申告が不要と判断できる場合でも、住民税については申告が必要になる場合があります。これは、所得税と住民税で申告の扱いが一致しないことがあるためです。実務で迷いやすいのは「確定申告しなくていいと聞いたので何もしない」というケースですが、住民税の申告が必要な自治体もあるため、何もせず放置すると後から指摘されるリスクが出る場合があります。
具体例として、会社員で副業所得が15万円の場合、所得税の確定申告は不要と整理できても、住民税の申告が必要となるケースがあります。住民税は市区町村が課税する税金なので、手続きや書類名、申告方法は自治体により異なる場合があります。そこで、最も安全なのは「所得税の確定申告をしない場合でも、住民税の申告が必要かを自治体の案内で確認する」ことです。副業所得が少額でも、住民税の計算に反映させるための手続きが求められる場合がある点を押さえておきます。
【住民税で迷わないための整理】
- 所得税の申告不要と住民税の申告不要は一致しない場合がある
- 住民税の申告は自治体ごとに扱いが異なる場合がある
- 確定申告しない場合は住民税申告の要否を自治体の案内で確認する
- 住民税の申告が必要なのに未申告 → 自治体の案内に沿って申告する
- 副業分の所得が反映されず後から修正になる → 収入と経費の整理を先に行う
- 会社に副業が伝わるのが不安 → 住民税の手続きは扱いが自治体で異なる場合があるため案内を確認する
申告した方が得になるケース
確定申告は「必要だからやる」だけでなく、「申告した方が得になる」場合があります。代表例は、所得税が戻る還付の可能性があるケースです。例えば、医療費控除や寄附金控除など、年末調整で反映されない控除を適用したい場合は、確定申告を行うことで税額が調整され、還付が発生することがあります。アフィリエイト収益が少額でも、控除の適用で結果が変わる場合があるため、該当する人は検討する価値があります。
また、アフィリエイトの収入や経費を整理しておくと、翌年以降の申告が楽になります。例えば、サーバー代やドメイン代、取材費、書籍代など、業務に関連して支払った費用は必要経費になり得ますが、領収書や請求書などの証拠がないと説明が難しくなります。申告が必要な水準に達していない年でも、記録の型を作っておくと、翌年に所得が増えたときに慌てずに済みます。
【申告した方がよい可能性がある例】
- 年末調整に入らない控除を適用したい
- 副業所得が20万円前後で翌年以降に増える見込みがある
- 経費の整理と記録の型を早めに作っておきたい
- 控除で税額が変わるかを先に整理する
- 申告が必要な年に備えて収入と経費の記録を残す
- 迷う場合は税務署や自治体の案内に沿って手続きを確認する
所得区分と記録の前提
アフィリエイト収益の確定申告では、最初に「所得区分」と「記録の前提」を整えることが重要です。所得区分とは、アフィリエイトで得た所得を税務上どの種類として扱うか、という考え方です。ここが曖昧だと、申告書の作り方や必要書類、帳簿の作り方がブレやすくなります。また、確定申告で一番困りやすいのが「収入や経費の根拠を示せない」状態です。後から思い出して埋めようとしても、振込明細や領収書が揃っていないと整理が難しくなります。
記録は、税額を下げるためのテクニックではなく、正しく申告するための土台です。特にアフィリエイトは、確定報酬と入金のタイミングがズレることがあり、ASPが複数になると管理が複雑になりがちです。そこで、本章では、事業所得と雑所得の考え方、帳簿と証拠の最低限、収入と支出を分ける実務的な管理方法を整理します。所得区分の判断は個別事情で変わる場合があるため、断定できない部分は条件付きで捉え、迷う場合は税務署等の案内に沿って整理することが安全です。
- 所得区分の考え方を理解し申告の前提を固める
- 帳簿と証拠を残す最低限のルールを決める
- 収入と支出を分けて迷わず集計できる状態にする
事業所得と雑所得の考え方
アフィリエイト収益は、状況により事業所得または雑所得として扱われることがあります。ポイントは、単に「収入があるか」ではなく、継続性や事業性などの状況を踏まえて整理する点です。一般に、継続して収益を得る目的で取り組み、帳簿を整え、一定の規模で運営している場合は事業所得として整理される可能性があります。一方で、規模が小さく、空いた時間に行っている副業で、事業としての実態が弱い場合は雑所得として扱われることがあります。
ただし、どちらに当たるかは個別事情で判断が分かれる場合があるため、ここでは「どちらを選ぶと有利」といった断定は避け、実務で困らないための考え方を押さえます。大切なのは、どちらの区分でも収入と必要経費を正確に記録し、説明できる状態にしておくことです。例えば、同じアフィリエイトでも、複数サイトを運営し、取材や外注を使い、毎月継続的に更新している人と、たまに記事を書いて少額の報酬がある人では、状況が違います。迷う場合は、税務署や税理士などに相談して整理するのが安全です。
【整理の観点】
- 継続して収益を得る目的で取り組んでいるか
- 作業の実態があり記録を整えているか
- 規模や継続性がどの程度あるか
- 区分を決めずに申告直前に迷う → 年の途中で前提を決め記録を揃える
- 根拠がなく主張だけで区分を決める → 実態が説明できる記録を残す
- 経費計上だけ先行して帳簿が追いつかない → 収入とセットで記録する
帳簿と証拠を残す最小ルール
帳簿と証拠は、確定申告の正確性を支える基本です。最小ルールは「いつ、何に、いくら使ったか」「なぜ必要経費と言えるか」「支払いを裏付ける証拠があるか」を揃えることです。証拠とは、領収書、レシート、請求書、クレジットカード明細、銀行振込の履歴、メールの請求通知など、支出を説明できるものです。アフィリエイトはオンライン支出が多いので、電子明細やメールも重要な証拠になります。
具体例として、サーバー代やドメイン代は、サイト運営に必要な支出として説明しやすいです。書籍やツール代は、内容が業務に関連していることを説明できるように、購入目的をメモしておくと後で迷いません。取材費や交通費がある場合も、何のための支出かを一言添えておくと整理が楽です。
証拠を残すポイントは、支出が発生したタイミングで整理することです。申告前にまとめてやると漏れが出やすくなります。月1回だけでも、収入と支出を帳簿に転記し、証拠をフォルダにまとめる習慣を作ると、申告時の負担が大きく減ります。
【最小ルール】
- 支出は日付 金額 内容 用途を記録する
- 領収書や明細は月ごとに保管する
- 目的が伝わりにくい支出はメモを残す
- メールの請求通知は専用フォルダへ移す
- レシートは撮影して月別に保存する
- 帳簿は月1回の締め作業で更新する
収入と支出を分ける管理方法
収入と支出を分けて管理すると、所得の計算が一気に簡単になります。特にアフィリエイトは、確定報酬と入金のズレ、複数ASPの併用、振込手数料の差し引きなどがあり、通帳だけ見ても分かりにくいことがあります。そこで、管理は「収入の一覧」と「支出の一覧」を分け、最後に月ごとに合算する形が実務的です。
具体例として、収入はASPごとに「確定報酬」「入金日」「入金額」「手数料の有無」を列にして管理します。支出は「サーバー」「ドメイン」「外注」「ツール」「書籍」などカテゴリを決め、日付と金額、用途を記録します。家賃や通信費などの家事按分がある場合は、支出一覧にいきなり経費額だけ入れるのではなく、按分前の金額と按分率の根拠を別で残すと、翌年以降の見直しがしやすくなります。
【分けて管理する手順】
- 収入はASP別に確定報酬と入金を並べる
- 支出はカテゴリ別に日付と用途を記録する
- 月末に収入と支出を合算して所得を把握する
- 証拠は収入と支出で同じ月にまとめて保管する
- 入金額だけで収入を判断する → 確定報酬と入金を並べて管理する
- 振込手数料の扱いで迷う → 手数料の有無を列で固定する
- 支出が後追いになり漏れる → 月1回の締め作業で必ず更新する
収入の集計方法
アフィリエイトの確定申告でつまずきやすいのが、収入の集計です。理由は、アフィリエイト報酬には「確定報酬」と「入金」があり、月をまたいでズレることが多いからです。さらに、ASPが複数になると、入金日や最低支払額、振込手数料の扱いが混ざり、通帳だけでは正しい金額が追いにくくなります。収入を正しく集計できると、所得の計算が安定し、経費や家事按分の整理も一気に楽になります。
ここでのポイントは、入金額だけで判断しないことです。入金額は振込手数料が差し引かれていたり、確定報酬の一部が翌月以降に繰り越されたりする場合があります。したがって、収入の集計は「ASPの管理画面にある確定報酬」と「通帳の入金」を並べて管理し、ズレの理由が説明できる状態にします。計上のタイミングは所得区分や状況で扱いが変わる場合があるため、まずは記録を揃え、後から申告書作成の段階で整理できる形にしておくのが安全です。
- 入金額だけで収入を決めない
- 確定報酬と入金を並べて管理する
- ASPごとに月次で締めてズレを説明できる状態にする
確定報酬と入金の整理手順
確定報酬と入金を整理する目的は、申告で説明できる「根拠のある収入一覧」を作ることです。実務では、収入をASP別に管理し、月ごとの確定報酬と入金を同じ表に並べる方法が分かりやすいです。最初に、ASPごとに月次の確定報酬を記録します。次に、同じ月の通帳の入金を記録し、差額があれば理由をメモします。
具体例として、ある月の確定報酬が10万円で、通帳の入金が9万5千円だった場合、差額の5千円は振込手数料の差し引きや、支払い条件による繰り越しなどが考えられます。ここで大事なのは、推測で処理を決めるのではなく、差額の理由をあとで確認できるようにしておくことです。ASPの入金明細や支払い履歴を保存しておけば、後から説明がしやすくなります。
【整理手順】
- ASPごとに月次の確定報酬を記録する
- 通帳の入金をASPごとに紐付けて記録する
- 差額があれば理由をメモし明細を保存する
- 月末に合計して年間の収入一覧を作る
| 項目 | 記録する内容 | 根拠の例 |
|---|---|---|
| 確定報酬 | 月ごとの確定額 | ASP管理画面の確定レポート |
| 入金 | 入金日と入金額 | 通帳や明細の入金履歴 |
| 差額メモ | 手数料や繰越など | 入金明細や支払条件の記録 |
- 通帳の入金だけを収入にする → 確定報酬と並べて管理する
- ASPが複数で入金元が分からない → 入金名義をメモし紐付ける
- 明細を保存せず後で説明できない → 月ごとにPDFや画面を保存する
発生月と入金月がズレる場合
アフィリエイトでは、成果が確定した月と、実際に振り込まれる月がズレることがよくあります。たとえば、1月に確定した報酬が、支払いサイクルの関係で2月や3月に入金されることがあります。さらに最低支払額が設定されている場合は、確定報酬が一定額に達するまで入金が繰り越される場合もあります。これがあると、入金ベースで管理していると月ごとの収入がブレ、年間の集計も分かりにくくなります。
実務の対策は、発生と入金を切り分けて並べることです。具体例として、月次で「確定報酬の月」と「入金された月」を別列にし、どの確定分がどの入金に対応しているかを追えるようにします。そうすれば、翌年の1月に前年分の報酬が入金されるようなケースでも、混乱せず整理できます。計上のタイミングは所得区分や状況で扱いが変わる場合があるため、少なくともズレが分かる記録を作っておくと、申告書作成の段階で判断しやすくなります。
【ズレがあるときの整理のしかた】
- 確定報酬の月と入金月を別列にする
- 最低支払額や締め日による繰り越しをメモする
- 前年確定分が翌年入金される可能性を想定して残高管理する
- 月末に確定報酬を必ず記録する
- 入金があったらその月に紐付けメモを残す
- 年末に未入金の確定報酬を一覧化する
振込手数料や返金がある場合
振込手数料や返金があると、収入の数字がさらに分かりにくくなります。振込手数料は、入金額から差し引かれて振り込まれる場合があり、確定報酬と一致しない原因になります。返金は、承認後にキャンセルや条件不備などが判明し、後から調整が入るような形で発生する場合があります。こうした調整を放置すると、確定報酬と入金の差額が積み上がり、申告直前に説明できなくなることがあります。
対策は、手数料と返金を「独立した項目」として扱い、必ずメモと根拠を残すことです。具体例として、入金が9万5千円で、確定報酬が10万円なら、差額5千円を「手数料」として記録し、入金明細を保存します。返金がある場合は、返金の発生日、理由、どの案件の調整かを記録し、ASPの調整履歴の画面を保存します。処理の方法は状況で変わる場合があるため、ここでは「正しい数字を再現できる記録を残す」ことを優先します。
【手数料と返金の記録方法】
- 入金額と確定報酬の差額は手数料として記録する
- 返金や調整があれば日付と理由をメモする
- 明細や履歴の画面を月別に保存する
- 差額の理由が説明できない → 手数料と調整を別項目で記録する
- 返金が混ざって合計が合わない → 調整履歴を保存し案件単位でメモする
- 年末に未整理が残る → 月末の締め作業で必ず更新する
経費と家事按分の整理
アフィリエイトの確定申告で多くの人が迷うのが、必要経費と家事按分です。必要経費とは、収入を得るために直接必要だった支出のことです。収入と支出を正しく分けられると、所得が整理でき、申告がスムーズになります。一方で、根拠が薄い経費計上や、プライベートの支出を混ぜると、説明が難しくなったり、後から修正が必要になる場合があります。
アフィリエイトは自宅作業が多く、家賃や通信費など仕事と私用が混ざる支出が出やすいです。そこで家事按分という考え方を使い、仕事に使った割合だけを経費として整理します。按分は「何となく」で決めるのではなく、作業スペースの面積や使用時間など、説明できる基準で決めるのが基本です。経費にできるかどうかは支出の内容や使い方で変わる場合があるため、迷う支出は「業務との関係が説明できるか」「証拠が残っているか」を基準に整理すると安全です。
- 収入を得るために必要だった支出かを説明できる
- 領収書や明細など証拠が残っている
- 家事按分は基準を決めて継続して同じ方法で整理する
必要経費になりやすい支出例
必要経費になりやすい支出は、アフィリエイトの作業に直接使うもの、またはサイト運営に欠かせないものです。具体例として、サーバー代やドメイン代はサイト公開に必要で、業務との関係も説明しやすいです。記事作成に使うツール代、画像作成の素材費、外注費も、業務目的が明確であれば整理しやすい支出です。取材や撮影のための交通費、業務に関連する書籍代も、内容と目的が説明できるなら経費になり得ます。
ただし、同じ支出でも使い方によって扱いが変わる場合があります。例えば、パソコンやカメラなど高額な機材は、購入した年に全額を経費にするのではなく、資産として扱って分割して計上する必要が出る場合があります。また、サブスクのツールでも私用が混ざる場合は、家事按分の考え方が必要になることがあります。いずれも「業務に必要だったこと」と「金額の根拠」を説明できるよう、領収書や請求書、クレジット明細を残し、購入目的を一言メモしておくと整理が楽です。
【必要経費になりやすい例】
- サーバー代 ドメイン代
- 有料テーマや業務用ツールの利用料
- 外注費 記事作成 画像作成
- 取材や撮影の交通費
- 業務に関連する書籍や教材
- 何のための支出か説明できない → 購入目的をメモして残す
- 私用が混ざる → 按分ルールを決めて割合で整理する
- 証拠がない → 領収書や明細を月別に保存する
家賃や通信費の按分手順
家賃や通信費は、自宅でアフィリエイトをする人がよく按分する支出です。家事按分とは、仕事と私用が混ざる支出を、仕事で使った分だけ経費にする考え方です。按分の基準は、説明できる形で決める必要があります。家賃は作業スペースの面積比で按分する方法が分かりやすく、通信費は業務に使った時間や業務用回線の利用状況などで按分する方法が考えられます。
具体例として、家賃が月10万円で、部屋のうち作業スペースが全体の20パーセントなら、家賃のうち2万円を経費として整理する考え方になります。通信費は、家族全員で使う回線を業務にも使う場合、業務利用の割合を説明できるようにします。例えば、作業時間の記録や、業務用端末の使用状況を基準にする方法があります。重要なのは、一度決めた基準を継続して使うことです。年ごとに基準が変わると説明が難しくなる場合があります。
【按分の手順】
- 按分対象を決める 例 家賃 通信費 電気代
- 基準を決める 例 面積比 使用時間
- 割合を計算して毎月同じ方法で記録する
- 基準の根拠をメモして証拠と一緒に保管する
| 費目 | 按分基準の例 | 残す根拠の例 |
|---|---|---|
| 家賃 | 作業スペースの面積比 | 間取り図 作業場所の写真 メモ |
| 通信費 | 業務利用時間の割合 | 作業時間の記録 利用目的メモ |
| 電気代 | 作業時間と設備の使用状況 | 作業時間の記録 使用機器メモ |
- 面積比か時間比など説明しやすい基準にする
- 割合は一度決めたら同じ方法で継続する
- 根拠になるメモや資料を残しておく
経費にしにくい支出の判断
経費にしにくい支出は、業務との関係が薄い、または私用の要素が強いものです。代表例は、日常生活の支出としての性質が強い食費や衣類、家族で使う娯楽費などです。アフィリエイトで「ネタになるから」としても、業務としての必要性が説明しにくい場合があります。
判断の基準は、業務に必要だったことを第三者に説明できるか、証拠が残っているか、私用と切り分けられるかです。例えば、打ち合わせがある場合の飲食費でも、内容や相手、目的の記録がなく、私的な食事と区別できないと説明が難しくなります。逆に、明確な取材目的があり、日時や目的を記録し、領収書が残っているなら整理しやすくなる場合があります。
迷う支出は、無理に経費に入れず、説明できる支出から整理するのが安全です。どうしても判断が難しい場合は、税務署や税理士に相談して整理するのが現実的です。
【経費にしにくい支出の見分け方】
- 業務目的を説明できない
- 私用の要素が強く切り分けが難しい
- 領収書や明細がなく根拠が残らない
- 説明ができず修正が必要になる場合がある
- 按分の基準が崩れて計算が合わなくなる
- 記録があいまいで翌年以降も迷いが増える
申告書の作成から提出まで
アフィリエイト収益の確定申告は、収入と経費の整理ができていれば、あとは「申告書を作る→提出する→納付する→控えを残す」の順で進みます。難しく感じやすいのは、何から入力すればよいかが見えないことと、提出方法が複数あって迷うことです。そこで、この章では、確定申告書等作成コーナーを使う場合の入力の流れ、e Taxと書面提出の選び方、申告後の納付と控えの保管までを実務目線で整理します。
申告書の作成では、いきなり画面を開く前に、必要な資料を手元にそろえることが重要です。具体例として、会社員なら源泉徴収票、アフィリエイトの収入集計表、経費と家事按分の一覧、控除に関する資料が必要になります。資料が不足していると、入力途中で止まり、申告直前に焦る原因になります。提出方法は、電子送信か書面提出かで手順が変わる場合があります。どちらを選ぶにしても、期限内に提出し、納付が必要なら納付を完了させ、控えを保存して翌年に使える状態にするのがゴールです。
- 会社員は源泉徴収票
- アフィリエイトの収入集計と入金明細
- 経費と家事按分の一覧と証拠
- 控除に関する資料がある場合はその書類
確定申告書等作成コーナーの入力順
確定申告書等作成コーナーを使う場合、入力は「所得の種類→収入と経費→控除→税額→提出」の順に進めると迷いにくいです。最初に所得の種類を選び、アフィリエイト収益をどの所得として入力するかを決めます。次に、収入と経費を入力しますが、ここで収入が入金額だけになっていないか、経費が証拠のないものになっていないかを確認しながら進めます。家事按分がある場合は、按分前の金額と按分割合の根拠を持ったうえで、計算結果を入力します。
具体例として、会社員は給与所得の入力が必要になるため、源泉徴収票の数字を見ながら入力します。そのうえでアフィリエイト分の所得を入力し、合算して税額が計算される流れです。入力中に迷いが出やすいのが、控除の入力と、必要書類の扱いです。控除の内容は人によって異なるため、該当する資料がある場合だけ入力し、資料がないものは無理に入れないことが安全です。
【入力の進め方】
- 所得の種類を選びアフィリエイト分の入力枠を決める
- 収入を確定報酬や入金の整理に基づいて入力する
- 経費と家事按分の結果を入力する
- 給与所得や控除を入力して税額を確定する
- 提出方法を選んで送信または印刷する
- 入金額だけを収入として入力する → 収入集計表と照合して入力する
- 按分の根拠がなく割合を決める → 面積比や時間比など基準をメモしておく
- 控除を勘で入れてしまう → 資料があるものだけ入力する
e Tax送信と書面提出の選び方
提出方法は、大きくe Taxで送信する方法と、書面を作成して提出する方法があります。どちらが向くかは、利用できる環境と、作業のしやすさで決めます。e Taxは、自宅から送信できるため移動が不要で、控えの管理もしやすい一方で、事前準備や認証方法の設定が必要になる場合があります。書面提出は、印刷して提出するためシンプルに見えますが、印刷や郵送の手間がかかり、控えの管理も自分で行う必要があります。
具体例として、平日に税務署へ行く時間が取りにくい人はe Taxが向きやすいです。反対に、電子設定が不安な人は、まず作成コーナーで書面を作り、提出する方法が合う場合があります。どちらを選んでも重要なのは、期限に間に合う形で提出することです。提出が完了したら、提出した内容を後から見返せる状態にしておくと、翌年の入力が速くなります。
【選び方の判断】
- 自宅で完結させたいならe Tax
- 印刷と郵送や持参で進めたいなら書面提出
- どちらでも控えを残して翌年に使える形にする
- 収入と経費の合計が集計表と一致している
- 按分割合と根拠がメモとして残っている
- 提出方法が決まり期限内に完了できる
申告後の納付と控えの保管
申告書を提出したら終わりではなく、納付が必要な場合は納付まで完了して手続きが締まります。納付方法には複数ありますが、どの方法でも「期限内に納付した事実が残る」形にしておくことが重要です。納付が遅れると延滞が発生する可能性があるため、提出後はすぐに納付方法を決めて実行します。
控えの保管は、翌年の作業をラクにするための投資です。保管すべきものは、提出した申告書の控え、収入集計表、経費の一覧、家事按分の根拠メモ、領収書や明細などの証拠です。具体例として、収入集計表と経費一覧を同じフォルダにまとめ、月別の証拠を紐付けて保存すると、翌年に同じ型で集計できます。控えがないと、翌年に数字の整合が取れず、作業が倍になります。
【提出後にやること】
- 納付が必要かを確認する
- 納付方法を決めて期限内に実行する
- 申告書控えと集計表と根拠資料を保存する
- 翌年用に同じフォルダ構成を作っておく
- 提出したのに納付を忘れる → 提出直後に納付まで終わらせる
- 控えを保存せず翌年困る → 申告書と集計表をセットで保管する
- 領収書が散らばる → 月別フォルダで証拠をまとめて保存する
まとめ
アフィリエイト収益の確定申告は、申告が必要かの判定→所得区分と記録の整備→収入集計→経費と家事按分の整理→申告書作成と提出の順に進めると迷いません。まず自分が申告対象かを整理し、収入と支出の記録を分けて残します。次に、確定報酬と入金のズレ、手数料や返金も含めて集計し、必要経費は根拠を残しつつ按分ルールを決めましょう。最後に申告書を作成して提出し、納付と控えの保管まで行えば、次年度の作業も改善しやすくなります