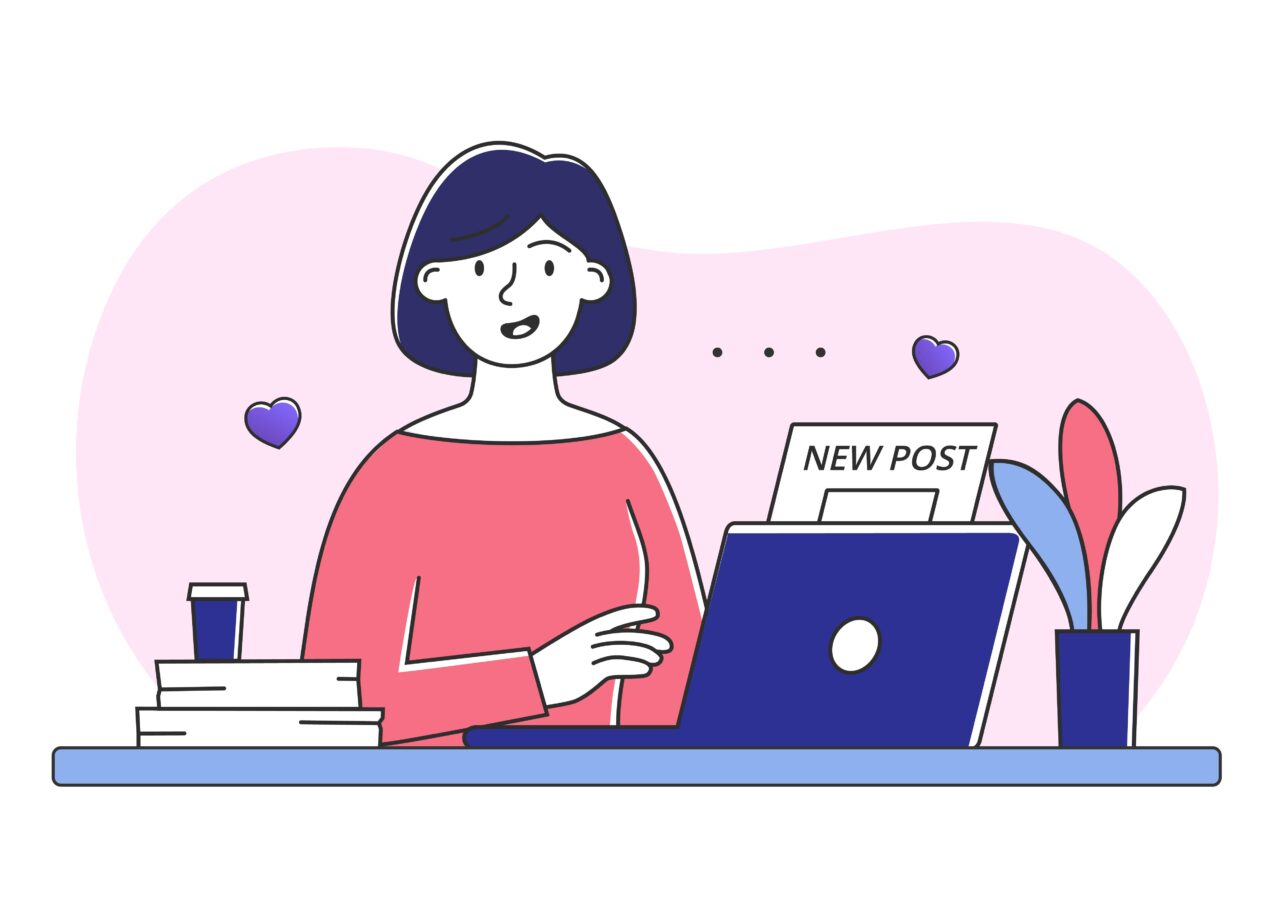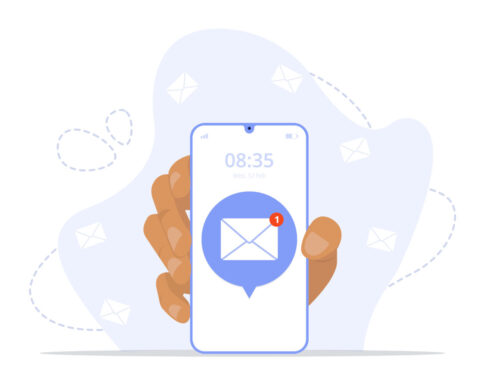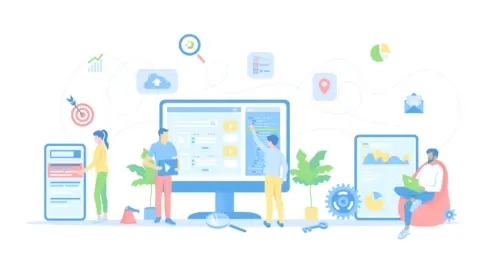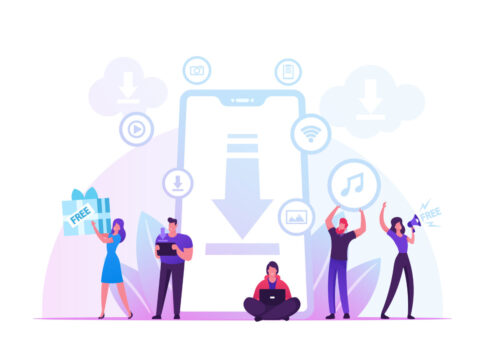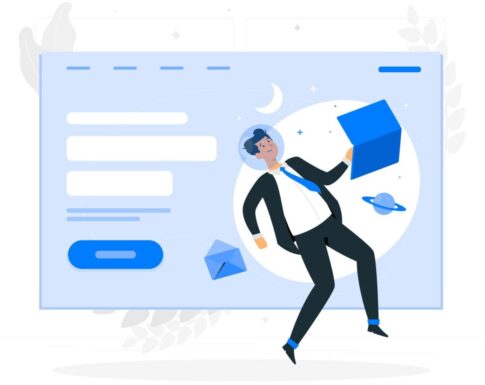アメブロで育てたブログ名やロゴを真似されたら、せっかくの集客と信頼が水の泡──。本記事では商標登録でブランドを守りつつ、違反トラブルを回避し、登録後に収益まで伸ばす3ステップを徹底解説します。
区分選定のコツやオンライン出願手順、登録後の®表記活用まで一次情報を基に網羅。読めば「いつ・何を登録し、どう稼ぐか」が一気に明確になります。
目次
アメブロと商標登録の基礎知識

アメブロで育てたブログ名やロゴは「ネット上の看板」です。しかし看板を掲げただけでは権利が確立されず、第三者に同じ名称を使われても法的に守れない場合があります。
そこで活躍するのが商標登録です。商標とは「商品やサービスを他と区別する識別標識」をいい、日本の制度では特許庁に出願し審査を経て登録されると、全国で独占使用できる排他的権利が10年(更新可)与えられます。
ブロガーにとっては〈ニックネーム〉〈ブログタイトル〉〈ロゴデザイン〉が主な登録対象で、登録すると模倣サイトへの差止請求や損害賠償請求が可能になります。
また、商標をプロフィールや記事下に表示することで「公式感」が高まり、コラボ依頼や広告掲載の営業にも好影響を及ぼします。商標区分は「広告・マーケティング」を含む第35類や「オンライン教育」を含む第41類が一般的に該当し、料金は出願区分数によって変動します。
| 項目 | 概要 |
|---|---|
| 権利期間 | 登録日から10年間(更新で延長可) |
| 対象区分 | 第35類:広告・販売促進、第41類:電子出版・教育 など |
| 費用目安 | 1区分あたり出願1.2万円+登録2.8万円前後(10年一括納付の場合) |
- 商標は“早い者勝ち”。使用開始より先に他者に取られると権利主張が困難
- 登録前でも先使用権が認められるケースはあるが、証明資料の準備が大変
商標の定義と登録で守れる権利
商標は「文字・図形・記号・立体形状・色彩などの組み合わせ」で構成され、自社の商品やサービスを他社と識別させるためのマークです。
登録が完了すると〈指定した区分〉においてそのマークを独占的に使用でき、第三者の類似使用を差し止めたり損害賠償を請求したりする法的根拠となります。
たとえば「〇〇ダイエットブログ」という語句を第41類で登録した場合、同一区分で「○○ダイエットブログ」をタイトルに使うサイトを見つけたら、使用中止を求める警告書を送ることが可能です。
権利行使が認められるのは「同一・類似範囲」であり、まったく異なる区分(例:食品の商標第30類)であれば併存が許容される場合もあります。
【商標で得られる主な権利】
- 使用権:登録商標を独占的に使用できる
- 差止請求権:他人の使用差止めや廃棄を請求できる
- 損害賠償請求権:侵害による損害を金銭で請求できる
- 輸入差止申立権:模倣品の輸入を税関で止められる
- 登録済みロゴを無断でTシャツに印刷・販売→製造元へ販売停止と賠償請求が可能
- ブログ名を商標登録し、同一名称のYouTubeチャンネル開設者へ名称変更を要請
一方、登録していない商標でも、長年の使用実績から周知性を獲得していれば「不正競争防止法」である程度守られるケースがあります。ただし立証負担が重く、紛争コストが高いため、事前の登録は“保険料”として割安と言えます。
ブログ名・ロゴ・ハンドルネームは登録できる?
結論から言うと、ブログ名・ロゴ・ハンドルネームはいずれも商標登録が可能です。ただし、登録には「識別力」と「非類似性」の2条件を満たす必要があります。
識別力とは「一般名詞や業界慣用語ではないか」を示し、たとえば「ダイエットブログ」はそのままでは説明的で識別力が弱く、登録が難しいと判断される傾向があります。一方で「ダイエットブログLUNA」のように造語や独自要素を付加すると識別力が高まり、登録の可能性が上がります。
【登録可否の目安】
- ○:造語・略語・独自ロゴマーク
- △:既存単語+独自語(識別強化が必要)
- ×:一般名詞のみ・既登録商標と酷似
ロゴの場合、文字商標と図形商標をセット出願することで文字のみ・図形のみの使用にも対応でき、権利範囲が広がります。
ハンドルネームは「個人名的な使い方」が想定されるため、第41類(オンライン出版物)や第35類(マーケティングサービス)での登録が一般的です。
- 特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)で類似名称を検索
- SNSアカウント名やドメインの空き状況も同時に確認
- 識別力を高めるため造語化・英字組み合わせを検討
- 登録完了後も3年使用しないと「不使用取消審判」で権利を失う恐れ
- 海外展開予定がある場合はマドプロ国際出願も視野に入れる
知らずに違反!商標侵害リスクとアメブロ規約

アメブロでは「自由に書ける」と油断していると、気付かないうちに商標侵害を起こしているケースがあります。商標法では登録商標を無断で「同一・類似商品・サービス」の宣伝や販売に使うことを禁じており、アメブロ利用規約も〈第三者の知的財産権を侵害してはならない〉と明記しています。
さらに公式ヘルプには、ブランド名やロゴを掲載する場合は「権利者の許諾があるか、引用範囲が適切か」を確認するよう注意書きがあります。
違反が発覚すると、運営による記事削除・アカウント停止のほか、権利者からの警告書や損害賠償請求に発展するリスクも。
特にアフィリエイト記事やレビュー記事は商品名・ロゴ画像を頻繁に扱うため、商標トラブルの温床になりがちです。以下の見出しで具体的なNGケースと回避策を解説し、安心して情報発信できる環境づくりをサポートします。
他社ブランド使用がNGになるケース一覧
他社の登録商標を無断で使うとき、すべてが即違反になるわけではありません。しかし以下の状況では商標権者の「業務上の信用」が害されると判断され、侵害とみなされる可能性が高まります。
【典型的NGケース】
- タイトルに競合ブランド名+「公式」を付け、公式サイトと誤認させる
- ロゴ画像をダウンロードしてバナーに使用し、販売リンクへ誘導
- 商標を含むハッシュタグを量産し、検索流入を横取りする
- 商標登録されているキャラクター名を商品名として無断販売
| 行為 | 侵害になりやすい理由 |
|---|---|
| ブランド名を記事タイトルに使用 | 顧客が公式情報と誤認し、権利者の信用を損なう |
| ロゴをバナーに転用 | 商標の出所表示機能を侵害し、混同を招く |
| 商標タグの大量使用 | 検索妨害とみなされ、公正な競争を阻害 |
- レビュー目的で商品写真を掲載する場合でも、改変・トリミングで原型を損なうと侵害リスク増
- 頭文字を並べ替えただけの「語呂合わせ商標」は類似と判断されることが多い
- 正当な引用範囲でブランド名を記載し、出典を明示
- 権利者から画像使用許可を得たうえでプロモーションを実施
- 比較記事で客観的事実を示し、誤認を与えない
警告・削除・損害賠償のトラブル事例と回避策
商標侵害が疑われると、まず権利者からメールや内容証明で警告書が届くケースが多いです。「7日以内に該当記事を削除し、今後同様の行為を行わない旨を誓約せよ」といった内容が一般的で、無視すると法的措置へ発展します。
実例として、美容機器のレビュー記事に公式ロゴを無断掲載したブロガーが、1クリックあたり300円の損害賠償(推定広告費)を請求されたケースがあります。さらにアメブロ運営が権利者の申立てを認めた場合、該当記事は即時非公開になり、繰り返すとアカウント停止処分を受けます。
【トラブル発生から解決までの流れ】
- 権利者から警告書が届く
- 運営へ削除申請→記事非公開
- 損害額の協議・示談交渉
- 合意不成立なら裁判・仮処分申立て
- 公開前にJ-PlatPatで商標検索し、類似名称の有無を確認
- ロゴ使用はメーカー公式サイトの「プレスキット」から取得し、許諾範囲を守る
- タイトルにブランド名を使う場合は「非公式レビュー」と明示
- ハッシュタグはブランド名+一般キーワードの複合形で混同を避ける
- 指摘を受けたら24時間以内に記事修正・削除し、誠意を示す
- 警告メールを無視して放置→損害賠償額が膨らむ
- 謝罪文の公開前に権利者許可を取らず炎上リスクを拡大
- 記事を非公開にせずURLだけ変更→検索キャッシュで証拠が残る
最後に、商標侵害防止は「知らなかった」では通用しません。アメブロ利用規約と商標法の両方を意識し、公式ガイドラインや先行事例を定期的に確認することで、安心して収益化を続けられます。
個人ブロガー向け商標登録の申請フロー

商標登録は「思い立ったらすぐ出願」で進めると、費用がかさみ途中で挫折しがちです。そこで今回は〈事前調査→区分選択→電子出願→審査対応→登録料納付〉の5ステップに落とし込み、個人でも無理なく進められるフローを解説します。
まず特許庁データベース「J-PlatPat」で類似商標を検索し、同一・類似が無いことを確認します。次にブログ運営の内容に合った区分(第35類:広告・販売促進、第41類:電子出版など)を選定し、費用をシミュレーション。
ここで予算オーバーなら区分数を絞るか、自分で手続きを行うセルフ出願を検討します。電子出願はパソコンから24時間可能で、出願後の進捗もオンラインで確認できるため効率的です。
審査は平均10~12か月かかるため、途中で中断しないようスケジュール表を作りタスク管理を徹底しましょう。
- 先行調査→区分決定→電子出願→形式・実体審査→登録料納付→商標権発生
- 完了まで最短11か月、長いと18か月を見込む
出願区分の選び方と費用シミュレーション
商標は「どの事業分野で使うか」を示す〈区分〉を指定しなければなりません。ブログ運営の場合、多くが第35類(広告・マーケティング)か第41類(オンライン出版・教育)に該当します。区分ごとに費用が加算されるため、闇雲に複数指定するとコストが跳ね上がります。
【主要区分と該当例】
| 区分 | 該当するブログ活動 |
|---|---|
| 第35類 | アフィリエイト広告、商品紹介記事、コンサルティング |
| 第41類 | 電子書籍販売、オンライン講座、セミナー配信 |
| 第42類 | アプリ開発、サイト制作サービス |
【費用シミュレーション(1区分あたり)】
- 電子出願印紙代:12,000円
- 登録料(5年分前納):17,200円
- 合計:29,200円
区分を2つに増やすと出願料が+12,000円、登録料も×2になるため約58,400円となります。予算に余裕がない場合は、現時点で最も収益と直結する区分だけを先行出願し、事業拡大に合わせて追加出願する方法が現実的です。
- 今後3年以内に行う予定のサービスだけを対象にする
- 第35類か第41類のどちらかに統一し、複数区分出願を避けてコスト削減
- 独自グッズ販売を始めるなら第25類(衣類)を追加検討
- 区分は追加変更不可。追加したい場合は新規出願扱いで費用が倍増
- 登録後3年以内に実際に使用しないと「不使用取消審判」で取り消される
特許庁オンライン出願と審査結果までのタイムライン
電子出願は「特許庁特許電子出願ソフト」またはWeb出願システム(β版)を使います。ここでは初心者でも操作が簡単なWeb出願を前提に説明します。
【オンライン出願手順】
- GビズIDプライムアカウントを取得
- Web出願システムにログインし「商標登録出願」を選択
- 出願人情報・商標見本・指定区分を入力
- 電子印紙をクレジット決済で購入し送信
- 受付完了メールを受信し控え番号を保存
【審査結果までの平均タイムライン】
| 時期 | 主なステータス | 対応ポイント |
|---|---|---|
| 0〜2か月 | 方式審査 | 書類不備があれば補正指令、7日以内にオンライン補正 |
| 3〜10か月 | 実体審査 | 拒絶理由通知が来たら60日以内に意見書・補正書提出 |
| 11〜12か月 | 登録査定 | 30日以内に登録料納付(5年 or 10年) |
| 12〜13か月 | 商標登録公告 | 登録証受領。®表記使用開始 |
- 先行調査で類似商標を徹底排除し、拒絶理由通知を回避
- 区分は必要最小限に絞り、審査範囲を狭くして審査期間を短縮
- 電子登録証明書を選択し、郵送待ち時間を削減
- ロゴ画像の解像度不足で見本差替え指令
- 区分指定が広すぎて「識別力なし」と判断される
- 補正書を郵送提出し、オンライン処理が遅れる
登録後に差がつく商標活用&収益化戦略

商標は「登録して終わり」ではありません。権利化した瞬間から、ブランド信頼性を高めるマーケティング資産として活用できます。
最初にすべきは、ブログヘッダー・プロフィール・商品パッケージなど読者や購入者が最初に接触する場所へ®または™を表記し、視覚的に“公式”を印象付けることです。さらに、記事内で「当ブランドは商標登録済みです」と明言すると、模倣品リスクを懸念する読者の不安を払拭でき、CTRやCVRが向上する傾向があります。
商標番号をリンク付きで特許庁データベースに公開すれば透明性が増し、法人取引やタイアップ案件の交渉材料にもなります。加えて、独自ロゴを縦横比を保ったままアイキャッチに統一することで、SNSシェア時のサムネイル認知率が高まり回遊率アップに直結。
最後に、AmebaPickと連携しオリジナル商品や独自教材を販売すれば、広告自由度が低いアメブロ内でも高い収益性を確保できます。これらの施策を組み合わせることで、「権利の盾」と「利益の矛」を同時に手に入れ、他ブログとの差別化を図れます。
商標表示ルールと信頼性アップの導線設計
商標表示にはルールがあります。登録完了後は®マーク、出願中は™マークを使い、誤認を避けるのが鉄則です。
表示位置は〈ロゴ右上〉〈ブログタイトル横〉〈商品名末尾〉が一般的で、フォントサイズは本文より一段階小さくすることで視認性と可読性を両立できます。
【表示パターン別の効果】
| 配置箇所 | 期待できる効果 |
|---|---|
| ヘッダー | 初見読者へ公式感を瞬時に伝え直帰率を低減 |
| 記事アイキャッチ | SNSシェア時のサムネイルに映え指名検索を促進 |
| 購入ボタン付近 | 安心材料となりCVRを押し上げる |
- ブログタイトル横に®を付与しファーストビューで権威付け
- プロフィールに「登録第×××××号」と商標番号を明記し信頼を補強
- 商品LPやAmebaPickリンク先に同一ロゴ+®を配置しブランド統一
【導入チェックリスト】
- 商標番号をクリックすると特許情報プラットフォームが開くか
- ヘッダーロゴとSNSアイコンの縦横比が一致しているか
- 出願中は™、登録後は®に即時差し替えているか
- 登録前から®を付けると虚偽表示となり罰則対象
- アイキャッチに商標を入れ過ぎて画像がゴチャつく
独自ブランド商品×AmebaPickで利益を最大化する方法
商標登録が完了したら、次は“名前が売れる”仕組みを作ります。おすすめは、独自ブランド商品をBASEやSTORESで製作し、その商品ページをAmebaPickの「外部リンク機能」で紹介するハイブリッド収益モデルです。
AmebaPick経由であればクリック報酬を受け取りながら、自社商品の購入で高い粗利も得られるため、一石二鳥。
【実践フロー】
- オリジナル商品に商標ロゴを印刷(例:ハンドメイド雑貨)
- ECサイトに登録し、アメブロ記事で制作秘話をストーリー形式で投稿
- AmebaPick「フリーリンク」で商品URLを生成し、記事中盤と末尾にウィジェット配置
- ストーリーズで「登録商標入り新作発表▶︎詳細はブログへ」の導線を設置
- クリック報酬と成果報酬の両方を狙うため、1,500〜3,000円の低単価商品を用意し成約率を高める
- 商標入り限定パッケージを月限定50個など希少性を演出し単価アップ
- 購入者レビューをブログに埋め込み、®マークとともに社会的証明を強化
【メリットと限界】
| 項目 | メリット | 注意点 |
|---|---|---|
| AmebaPick経由販売 | クリック報酬+商品利益のダブル収益 | 外部ASPより料率が低い場合がある |
| 商標ロゴ商品 | ブランド差別化・リピート購買が期待 | 在庫管理と返品対応の手間が増加 |
- ロゴ改変依頼を受けた際は、商標権を守るためガイドラインを提示
- 在庫リスクが高い場合は受注生産型のプリントサービスを活用
まとめ
商標登録は「自分の名前を守る盾」であり、「信頼を獲得する名刺」です。基礎知識で必要性を把握し、侵害リスクと規約を確認、区分選定とオンライン出願で権利化──ここまで進めばアメブロでも安心してブランド展開が可能。
さらに®表記とAmebaPickを組み合わせれば収益導線も強化できます。今日から先行調査だけでも始め、安心して発信できる土台を整えましょう。