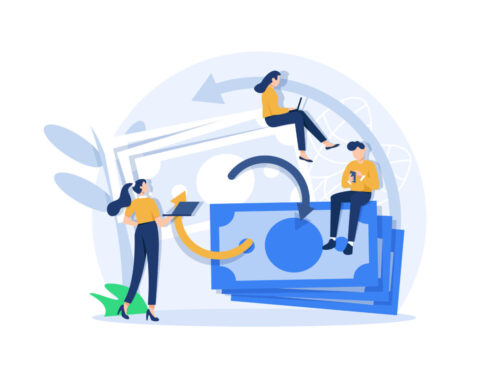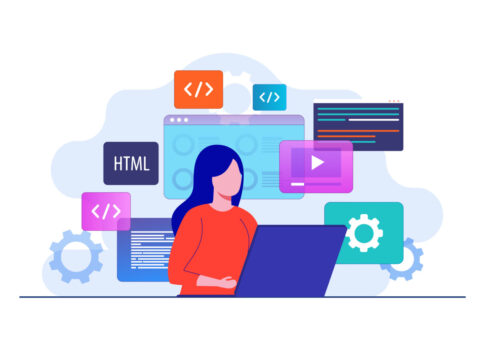アフィリエイト報酬で「インボイス登録は必要?」「ASPや広告主から登録番号を求められたら?」「消費税の扱いはどうなる?」と迷う人は多いです。この記事では、アフィリエイト取引でインボイスが関係する場面を整理し、登録するかの判断フロー、登録後・未登録それぞれの取引先対応、書類と申告の注意点をまとめます。やるべき手続が明確になり、対応漏れや無用なトラブルを避けやすくなります。
アフィリエイトとインボイス制度の関係
インボイス制度は、消費税の仕入税額控除を受けるために「適格請求書(インボイス)」などの保存を求める仕組みです。アフィリエイトでは、広告主→ASP→アフィリエイターのようにお金の流れが分かれることが多く、どの取引が「課税仕入れ」に当たるかで、インボイス対応の要否が変わります。特に、ASPがアフィリエイターへ支払う成果報酬は、取引実態として役務提供の対価に当たる場合があり、ASP側が仕入税額控除を行うにはインボイス(または要件を満たす請求書等)が必要になります。適格請求書は「請求書」という名称に限らず、一定の記載事項を満たす請求書・納品書・明細書などでもよいとされています。
一方で、アフィリエイターが免税事業者で適格請求書発行事業者の登録をしていない場合、原則として取引先はその支払いについて仕入税額控除ができません。ただし制度開始後は、免税事業者等からの仕入れに一定割合を控除できる経過措置が設けられています。
- インボイスは「仕入税額控除」とセットで考える
- アフィリエイトは取引の段が分かれやすく、相手が誰かで対応が変わる
- 請求書以外の「明細書等」でも要件を満たせば使える
広告主・ASP・アフィリエイターの取引整理
アフィリエイトの取引関係は、契約形態により異なる場合がありますが、実務では「広告主がASPへ広告費を支払い、ASPがアフィリエイターへ成果報酬を支払う」構造が典型です。ここで重要なのは、インボイス制度が問題になるのは“お金の流れ”そのものではなく、「誰が誰から役務の提供を受けたことになるか」という取引実態です。アフィリエイターが広告掲載などの役務を提供し、ASP(または広告主)が対価を支払う関係に当たる場合、その支払いは取引先にとって課税仕入れになり得ます。
また、取引先が仕入税額控除を行うために保存する書類は、必ずしもアフィリエイターが作成した請求書に限られません。仕入側が作る「仕入明細書・仕入計算書等」も、一定の記載事項を満たせば適格請求書等として扱える整理があります。そのため、ASPが支払明細(報酬明細)を発行し、そこに登録番号など必要事項を載せて運用する形になる場合もあります。どの運用になるかはASPの方針や契約で異なるため、実際の対応は取引先の案内に合わせて整理するのが安全です。
| 支払側 | 受取側 | 取引の例 |
|---|---|---|
| 広告主 | ASP | 広告配信・成果計測等の対価 |
| ASP | アフィリエイター | 広告掲載等の成果報酬 |
- 取引相手を曖昧にする → 契約先と支払元をまず整理する
- 請求書が必須と思い込む → 明細書等でも要件を満たせる場合がある
インボイスが関係するのはどの取引か
インボイスが関係する中心は「事業者間の課税仕入れで、仕入税額控除をしたい取引」です。アフィリエイトでは、ASPや広告主がアフィリエイターへ支払う報酬について、支払側が仕入税額控除を行うには、原則として適格請求書発行事業者から交付される適格請求書等(または要件を満たす明細書等)の保存が必要になります。
ここで実務に影響が出やすいのが、アフィリエイターが免税事業者で登録していないケースです。制度上、免税事業者等からの課税仕入れは原則として仕入税額控除ができません。ただし、制度開始後の一定期間は経過措置があり、仕入税額相当額の一定割合を控除できる期間があります。
具体例として、ASPが多数のアフィリエイターへ報酬を支払っている場合、未登録のままだと控除が制限されるため、登録番号の提示を求められたり、取引条件が見直される場合があります。どこまで求められるかは相手の運用方針で異なるため、通知やヘルプの案内を踏まえて対応します。
- 支払側が仕入税額控除をしたい→適格請求書等の保存が論点
- 未登録の免税事業者→原則控除不可だが経過措置あり
- 書類は請求書に限らず、要件を満たす明細書等でもよい
消費税の課税・免税の基本と判定軸
インボイス対応を判断する前提として、まず自分が消費税の課税事業者か免税事業者かを整理します。消費税は、原則として基準期間の課税売上高が一定以下の事業者は免税事業者に該当します。ただし、一定の場合には特定期間の課税売上高(または給与等支払額)で判定し、免税にならないことがあります。これにより「売上は増えていないつもりでも、判定上は課税事業者になる」ケースが起こり得るため、過去の売上や特定期間の条件を含めて確認することが重要です。
具体例として、アフィリエイト報酬が増えてきた年は、翌々年の納税義務に影響する場合があります。また、途中から課税事業者になる場合は、請求書等の記載や帳簿保存、申告の準備が必要になります。なお、適格請求書発行事業者として登録するには登録番号が付与され、取引先が求める書類(請求書等)には一定の記載事項が必要です。必要事項の整理は国税庁の案内で具体化されており、請求書等や仕入明細書等それぞれで記載事項が定められています。
- 基準期間だけ見て安心する → 特定期間の判定も確認する
- 免税=一切対応不要と思い込む → 取引先側の仕入税額控除の影響を整理する
- 書類要件を後回しにする → 取引先の運用(明細書方式など)に合わせて準備する
登録するかの判断フロー
アフィリエイトのインボイス対応は、「取引先が仕入税額控除をどう扱うか」と「自分が消費税の課税事業者になる負担」を天秤にかけて決めるのが基本です。インボイス(適格請求書)を発行できるのは、適格請求書発行事業者として登録した事業者です。免税事業者のまま登録しない場合、取引先(例:ASP)がその支払いを仕入税額控除できないのが原則で、取引条件の見直しが起きる場合があります。一方、登録すると課税事業者となり、消費税の申告・納付や帳簿保存などの実務が増えます。
判断は「自分の立場(免税か課税か)→取引先からの要請→税負担の試算→運用のしやすい申告方法」の順で整理すると迷いにくいです。特にアフィリエイトは、複数のASPから報酬が入ることが多いため、登録の有無を決めた後は、支払明細の扱い・登録番号の共有・帳簿の付け方までセットで固めると実務が安定します。
- 自分が免税か課税かを整理する
- 取引先が登録番号を求めるか把握する
- 登録した場合の税負担と事務負担を試算する
- 2割特例・簡易課税など使える方法を比較する
免税事業者のままの影響と経過措置
免税事業者のまま(適格請求書発行事業者として登録しない)場合、取引先はその支払いについて、原則として仕入税額控除ができません。ただし制度開始後の一定期間は、免税事業者等からの課税仕入れでも、仕入税額相当額の一定割合を仕入税額とみなして控除できる「経過措置」が設けられています。期間と割合は、令和5年10月1日から令和8年9月30日までは80%、令和8年10月1日から令和11年9月30日までは50%です。
具体例として、ASPがあなたに報酬を支払うとき、ASP側はその支払いについて仕入税額控除を行いたい場面があります。あなたが未登録だと原則控除できないため、ASPの方針によっては「登録番号の提示依頼」「取引条件の見直し(報酬体系の変更等)」が起きる場合があります。どこまで影響が出るかは取引先の運用や契約次第なので、案内メールやヘルプで「登録番号の提出方法」「未登録の場合の扱い」を先に確認するのが現実的です。
【免税のまま進めるときの整理】
- 取引先が登録番号を求めるか
- 経過措置の範囲で運用する方針か
- 報酬条件の変更があり得るか
- 登録番号の提出依頼が来る → 未登録である旨と取引先の手順に沿って回答する
- 報酬条件の変更が発生する場合がある → 契約・利用規約の更新通知を見落とさない
登録すると課税事業者になる点
適格請求書発行事業者(インボイス発行事業者)として登録するには、原則として課税事業者であることが前提です。免税事業者が登録申請を行う場合、登録を受けることで課税事業者となり、消費税の申告・納付が必要になります。
実務上のポイントは「登録=消費税の事務が増える」という点です。具体的には、課税売上・課税仕入れの区分、帳簿・請求書等の保存、確定申告(消費税申告)の準備が必要になります。アフィリエイトでは、取引先が支払明細を発行しているケースが多く、インボイス要件を満たす明細の運用になる場合もありますが、どの形式で対応するかは取引先の仕組みにより異なります。
また、登録後は取引先から登録番号の提示を求められることが一般的です。登録番号の扱い(どこで共有するか、明細にどう反映されるか)はASPごとに違う場合があるため、登録を決めたら「登録番号の登録フォーム」「反映時期」「未対応時の扱い」を早めに確認すると、支払いトラブルを避けやすくなります。
- 消費税の申告・納付が必要になる
- 帳簿・請求書等の保存要件を意識する
- 取引先へ登録番号を共有し、明細の反映を確認する
2割特例・簡易課税を使える場合の考え方
登録して課税事業者になった場合、消費税の計算方法として「2割特例」や「簡易課税制度」を選べるケースがあります。2割特例は、インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者になった事業者などを対象に、納付税額を「売上に係る消費税額の2割」として計算できる特例です。適用できる期間は、令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間とされています。
一方、簡易課税制度は、基準期間の課税売上高が5,000万円以下などの要件を満たす場合に選択でき、業種ごとの「みなし仕入率」を使って仕入税額控除を計算します。原則は事前の届出が必要ですが、免税事業者が登録によって課税事業者となるケースでは、登録日の属する課税期間から簡易課税を適用できる取扱いが設けられている旨が整理されています。
考え方としては、まず「2割特例を使うと納付がどう変わるか」を試算し、次に「簡易課税の方が有利になり得るか」を確認します。どちらが有利かは、課税売上の内容や仕入(経費)の構造で変わるため一律には言えません。
- 2割特例は対象期間が決まっている
- 簡易課税は要件(5,000万円以下等)と届出が必要
- 有利不利は経費構造で変わるため試算して決める
登録した後にやること
インボイス発行事業者として登録した後は、「登録番号を取引に反映する」「書類(支払明細・請求書等)を要件に合わせる」「取引先へ共有して運用を安定させる」の3点を優先すると迷いません。アフィリエイトはASP経由の支払いが多く、毎月の報酬明細がそのまま経理資料になるケースがあるため、対応を後回しにすると、明細の取り直しや取引先とのやり取りが増える場合があります。
また、登録すると消費税の申告・納付や帳簿保存が必要になります。登録日(課税事業者となる扱いの起点)は申請状況で変わる場合があるため、届く通知や登録情報に基づいて、いつから何を変えるかを整理することが重要です。ここでは、登録申請から登録番号の扱い、支払明細・請求書の整え方、登録番号の共有と照会対応までを、実務で抜けが出にくい順番でまとめます。
- 登録番号と登録日の整理
- 明細・請求書の運用ルール決め
- 取引先(ASP等)への登録番号共有
登録申請の流れと登録番号の扱い
登録申請は、手続きそのものより「登録日と登録番号を運用に反映する」ことが重要です。登録が完了すると、登録番号が付与されます。登録番号は原則として「T+数字」で構成され、取引先が仕入税額控除のために保存する書類(適格請求書等)に記載する情報の一つになります。登録後は、登録番号だけでなく、取引先に伝える名称・所在地などの登録情報も揃えておくと照会対応がスムーズです。
具体例として、ASPが「登録番号を管理画面に入力してください」という運用の場合、入力が遅れると明細への反映が翌月以降になる場合があります。逆に、登録番号を伝えたつもりでも、登録情報の表記ゆれ(氏名・屋号、住所の表記差など)があると、取引先側の確認が止まることがあります。回避策は、登録後に「登録番号」「登録日」「登録情報(名称・所在地など)」を1枚のメモにまとめ、ASPごとに同じ情報を登録することです。
【登録番号の扱いでやること】
- 登録番号と登録日を控える
- 取引先へ出す書類で使う表記(名称・所在地)を統一する
- ASPの登録フォームや提出方法に合わせて番号を登録する
- 登録日を見落として運用開始がズレる → 登録日を基準に切替タイミングを決める
- 表記ゆれで確認が止まる → 登録情報をそのまま転記して統一する
- 登録番号の共有が遅れて反映が先延びになる → ASPごとに期限と反映時期を確認する
支払明細・請求書をインボイス要件に合わせる
登録後に迷いやすいのが「自分が請求書を出すのか」「ASPの支払明細がインボイス相当として運用されるのか」です。アフィリエイトでは、取引先が支払明細を発行し、その明細が一定の記載事項を満たすことで、適格請求書等として扱える形になる場合があります。一方で、取引先によっては「アフィリエイターが請求書を発行する」運用を求める場合もあります。どちらになるかは取引先の方針で異なるため、まずはASPの案内に沿って運用を決めます。
適格請求書等として必要な記載事項は、取引の内容や税率区分に応じて揃える必要があります。アフィリエイト報酬は通常、役務提供の対価として整理されることが多いため、税率は原則1種類で足りる場合が多いですが、取引実態や運用で異なる場合があるため、明細や請求書の記載項目が不足していないかを点検します。
【インボイスで不足しやすい記載項目】
- 登録番号
- 取引年月日
- 取引内容(役務の内容が分かる記載)
- 税率ごとの金額・消費税額(税率が1つでも区分が必要)
- 取引先(交付を受ける事業者)の名称
- 明細を保存せず後から出せない → PDF等で毎月保存し、帳簿とひも付ける
- 登録番号の反映漏れに気づかない → 明細の表示項目を毎月チェックする
- 請求書発行が必要なのに出していない → 取引先の運用(明細方式か請求書方式か)を先に確定する
登録番号の共有と取引先からの確認対応
登録番号の共有は、登録しただけでは完了しません。取引先が「どこで登録番号を受け付けるか」「明細や支払処理にいつ反映されるか」を決めているため、取引先ごとに手順を合わせる必要があります。具体的には、ASPの管理画面で登録番号を入力する、所定フォームに送信する、メールで提出するなど、方法が分かれる場合があります。提出後は「反映されたか」を支払明細で確認し、未反映なら問い合わせるのが確実です。
また、取引先が登録番号の正しさを確認する場面では、登録番号だけでなく「登録名義(氏名や事業者名)」や「所在地」などの照合が行われる場合があります。表記が異なると確認が止まることがあるため、登録情報をそのまま共有するのが安全です。住所や名称の変更がある場合も、取引先側の登録情報とズレると手続きが滞る可能性があるため、変更時は早めに更新します。
【登録番号共有の実行手順】
- 取引先ごとの提出方法を確認する
- 登録番号と登録情報を提出する
- 次回の支払明細で反映を確認する
- 未反映なら取引先へ連絡し、反映時期を把握する
- 登録番号、登録名義(表記どおり)、所在地をセットで返す
- 明細の反映時期を確認し、反映後に再チェックする
- 運用が明細方式か請求書方式かを再確認する
登録しない場合の取引先対応
インボイス発行事業者として登録しない選択は、特に免税事業者に多い判断です。ただし、登録しない場合は「取引先(多くはASP)が仕入税額控除をどう扱うか」という論点が残ります。制度上、免税事業者等からの課税仕入れは原則として仕入税額控除ができないため、取引先側でコスト増になる可能性があります。その結果、登録番号の提出を求められたり、未登録の場合の取引条件が提示されたりする場合があります。どこまで影響が出るかは、取引先の運用や契約内容、経過措置の取り扱い方針によって異なるため、断定ではなく「起きる場合がある」として整理します。
登録しない場合に重要なのは、取引先の案内に沿って回答し、明細や契約条件の変更を見落とさないことです。アフィリエイトは取引先が複数になりやすく、ASPごとに手続やルールが違う場合があります。ここでは、仕入税額控除の影響と求められやすい対応、報酬条件の見直しが起きる場合の整理、消費税相当額の扱いと契約の考え方をまとめます。
- 取引先からの登録番号照会に対応する
- 未登録時の条件変更があるかを把握する
- 報酬明細・契約の記載を見落とさない
取引先の仕入税額控除と求められやすい対応
未登録の免税事業者の場合、取引先は原則としてその支払いについて仕入税額控除をできません。ただし、制度開始後の一定期間は、免税事業者等からの課税仕入れでも仕入税額相当額の一定割合を控除できる経過措置があります。このため取引先は、経過措置の適用期間中は一定の控除をしつつ、長期的には未登録取引の扱いをどうするか検討することになります。
求められやすい対応は「登録番号の有無の申告」と「未登録である旨の回答」です。多くの場合、取引先は登録番号の提出フォームを用意し、未登録の場合の選択肢や回答欄を設けます。具体例として、ASPの管理画面で「登録番号の入力」か「未登録を選択」する形式があり、未登録を選ぶと明細にその旨が反映される場合があります。ここで曖昧な返答をすると再照会が増えるため、取引先が指定する方法で明確に回答するのが現実的です。
【未登録時に求められやすい対応】
- 登録番号の提出依頼に対して「未登録」を選択または回答する
- 取引先の手順どおりに情報を更新する
- 明細で自分の状態が正しく反映されているか確認する
- 照会メールを見落とす → 取引先からの通知を定期的に確認する
- 未登録の回答が曖昧 → 指定フォームで明確に未登録を選ぶ
- 明細の反映を見ない → 反映後の明細を保存し内容を点検する
報酬条件の見直しが起きる場合の整理
未登録のままだと、取引先にとって仕入税額控除が制限されるため、取引条件の見直しが起きる場合があります。ここで注意したいのは「必ず報酬が下がる」とは言えない点です。実際の対応は、取引先の方針、経過措置の扱い、契約条件、取引規模などで異なります。
ただし、見直しの方向性としては、未登録者と登録者で条件を分ける、未登録者向けに別の支払方法や明細の扱いを用意する、一定の条件変更を告知する、といった運用が取られる場合があります。具体例として、ASPが「登録番号の提出を推奨」し、未登録の場合の扱いを利用規約やヘルプで明示するケースがあります。アフィリエイター側の現実的な対応は、条件変更の通知を見落とさず、影響がある場合は「登録するか」「取引先を整理するか」「報酬設計を見直すか」を選ぶことです。
- 変更内容が適用される時期を確認する
- 自分の状態(登録/未登録)で何が変わるか整理する
- 影響が大きい場合は登録の再検討や取引先整理を行う
消費税相当額の扱いと契約の考え方
未登録(免税事業者)の場合でも、報酬明細に「消費税相当額」のような項目が表示されるかどうかは、取引先の計算・表示方法で異なる場合があります。また、報酬の表示が「税込」「税抜」「消費税相当額を含む」など、表記方法が異なることもあります。重要なのは表記よりも、契約上の報酬条件がどう定義されているかです。
具体例として、報酬条件が「報酬単価は税込で支払う」と整理されているのか、「税抜単価で、消費税相当額を上乗せする」と整理されているのかで、未登録時の扱いが変わる場合があります。未登録だとインボイスを発行できないため、取引先が税額を仕入税額控除できない点を踏まえて、契約条件の見直しが議論されることがあります。
回避策は、取引先のヘルプや利用規約、報酬明細の注意書きを読み、報酬が税込なのか税抜なのか、未登録時の扱いがどうなるのかを把握することです。判断が難しい場合は、税務署や税理士などの専門家へ相談し、自分の取引実態に合わせて整理するのが安全です。
- 報酬は税込か税抜か、明細の表記はどうか
- 未登録の場合の扱いが規約やヘルプに明記されているか
- 条件変更の通知方法と適用時期はどうか
失敗を防ぐチェック表
インボイス対応でつまずきやすいのは、制度の用語を覚えることよりも「実務で何を揃えればよいか」が曖昧なまま進めてしまうことです。アフィリエイトは、取引先(ASPなど)が支払明細を発行し、それが経理資料になるケースが多い一方、取引先ごとに運用が違う場合があります。そのため、登録番号を共有したつもりでも明細に反映されていない、必要な記載項目が足りない、保存すべき書類を残していない、といったミスが起こりやすいです。
また、登録して課税事業者になると、消費税の申告・納付や帳簿保存の負担が増えます。アフィリエイト報酬は毎月発生しやすいので、月次で記録と保存を回しておくと、申告時の手戻りを減らせます。この章では、書類で不足しがちな項目、登録後の申告・保存の注意点、迷ったときの整理手順と相談先を、チェック表としてまとめます。
- 明細や請求書の不備を先に潰す
- 申告前に慌てない運用を作る
- 取引先ごとの違いを整理して漏れを減らす
インボイスで不足しがちな記載項目
インボイス対応で不足しがちなのは「登録番号があるか」だけではありません。適格請求書等として扱うには、取引年月日、取引内容、税率ごとの区分や消費税額の表示など、必要事項を満たす必要があります。アフィリエイトでは、取引先が支払明細で対応する場合があり、その明細にどこまで記載されるかは取引先の運用で異なる場合があります。そのため、登録したら終わりではなく、明細に必要事項が載っているかを毎月点検します。
具体例として、登録番号は入力したのに、反映が翌月以降になることがあります。この場合、該当月の明細が要件を満たさない可能性があるため、反映時期と対象期間を取引先の案内で確認します。また、税率区分が1つしかない取引でも、税率ごとの区分や税額の表示が必要になるため、明細の表示項目が不足していると後から確認が必要になります。
【不足しがちな記載項目チェック】
- 登録番号:Tから始まる登録番号が記載されている
- 取引年月日:いつの取引かが分かる
- 取引内容:アフィリエイト報酬など内容が特定できる
- 税率区分:税率ごとの区分がある
- 税抜金額と消費税額:税率ごとの金額と税額が分かる
- 交付側の氏名・名称、所在地:登録情報と一致している
- 相手先の名称:交付を受ける事業者が分かる
- 登録番号が未反映 → 反映時期を確認し、次回明細で再点検する
- 税額表示が不足 → 取引先の明細方式か請求書方式か確認する
- 表記ゆれがある → 登録情報どおりの表記に統一する
登録後の申告・帳簿保存での注意点
登録して課税事業者になると、消費税の申告・納付が必要になり、帳簿と請求書等(または明細書等)の保存も前提になります。アフィリエイトは、複数のASPから定期的に入金されることが多いため、記録が散らばりやすいのが難点です。申告直前にまとめると、明細の取り寄せや入金日の突合に時間がかかるため、月次で揃えるのが現実的です。
具体例として、同じ月の成果でも入金が翌月になることがあります。この場合、会計上の計上タイミングや管理方法は運用で変わる場合があるため、帳簿上で一貫したルールを決めます。また、支払明細は管理画面から一定期間しか閲覧できない場合もあるため、PDF保存やダウンロードを毎月の作業に組み込みます。
【登録後の月次運用チェック】
- 支払明細:月ごとに保存し、帳簿とひも付ける
- 入金記録:口座入金と明細の一致を確認する
- 税区分:課税・非課税・対象外などの区分を誤らない
- 登録番号反映:明細に登録番号が載っているか確認する
- 変更通知:取引先の規約変更や運用変更を見落とさない
- 明細は月次でPDF保存する
- 入金と明細を毎月突合する
- 取引先ごとの運用差をメモしておく
迷ったときの整理手順と相談先の使い分け
インボイスは、制度自体は共通でも、あなたの状況や取引形態で最適解が変わる場合があります。迷いが出たときは、順番を固定して整理すると判断が速くなります。最初に「自分が免税か課税か」「登録しているか」を整理し、次に「取引先が求める運用(明細方式か請求書方式か)」を確認し、最後に「税負担と事務負担」を試算して判断します。
具体例として、ASPから「登録番号を入力してください」と連絡が来た場合、まず未登録なら未登録として回答し、登録する予定があるなら反映時期を確認します。登録済みなら、登録番号・登録名義・所在地の表記をそのまま提出し、次回明細で反映を確認します。税務判断が絡む部分(課税・免税判定、特例の適用可否、申告の扱い)は、一般論ではなく個別事情で変わりやすいので、必要に応じて税務署や税理士に相談するのが安全です。取引先の運用(明細の形式、登録番号の提出先、反映時期)は、取引先のサポートやヘルプが一次情報になります。
【迷ったときの整理手順】
- 自分の区分:免税か課税か、登録の有無
- 取引形態:支払元は誰か、契約先は誰か
- 運用:明細方式か請求書方式か、必要書類は何か
- 影響:税負担と事務負担、条件見直しの可能性
- 決定:登録するか、未登録で運用するか
- 取引先の運用や提出方法 → ASP等のヘルプ・サポート
- 課税・免税判定や申告の扱い → 税務署や税理士
- 契約条件や変更通知の確認 → 利用規約・契約書・明細の注意書き
まとめ
アフィリエイトのインボイス対応は、取引の形を整理し、登録の要否を判断し、登録後は登録番号の共有と書類対応、未登録なら取引先の求めに応じた説明と条件整理が要点です。まず自分の課税・免税の状況と取引先の要請を確認し、登録の有無に応じた手続を実行してください。運用後は支払明細・請求書・帳簿の整合を見直し、申告まで含めて改善しましょう。