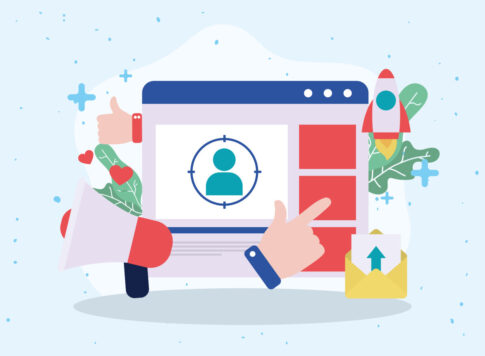ブログ集客は「本流WordPress×支流アメブロ」の二刀流で伸びが変わります。アメブロで接点を作り、代表記事へ最短で送り、WordPressで深掘りと検索資産化。
本記事は、役割分担・固定リンクと内部リンクの導線設計・UTM計測・週次ABの型まで、成果に直結する実装手順をまとめました。
ブログ集客の全体像とアメブロの位置づけ

ブログ集客は「接点を増やすチャネル」と「深掘りして意思決定を後押しする受け皿」を組み合わせる発想が基本です。接点づくりでは拡散性と更新のしやすさが重要で、アメブロは読者ネットワーク・フォロー機能・検索以外の動線が強みです。
一方、受け皿は検索資産化と情報の体系化が要で、WordPressなど独自ドメインの本サイトが向きます。
したがって、アメブロは“支流”として初速の流入をつくり、代表記事へ最短で橋渡し。代表記事では比較表やチェックリストを置き、内部リンクで入門→比較→選択の順路を明示し、CTAで行動を促します。
両者を同時に運用する際の要点は、①同じ主張・同じ言い回し(投稿・H1・CTA・OGPの統一)、②リンクの主経路を固定(プロフィール固定リンクなど)、③UTMで経路別に計測の三つです。下表に役割分担の目安を示します。
| チャネル | 主な役割 | 初手の実装 |
|---|---|---|
| アメブロ | 接点創出・拡散・常連の回遊 | プロフィール固定リンク→代表記事へ/記事末に「本編」を明記 |
| 本サイト | 検索資産化・深掘り・意思決定支援 | 比較表・チェックリスト・FAQを上部配置→CTAは上部+末尾 |
| SNS/メール | 再訪喚起・短文告知・導線補強 | 同語の見出しで告知→本文先頭に同リンク/週次で再案内 |
- 主導線は1つに固定(プロフィール固定リンクなど)
- 投稿・H1・OGP・CTAの文言は同じ語で統一
- UTMで「アメブロ→本サイト」経路を分解し週次で比較
検索資産はブログ 本流はWordPress 支流にアメブロ
検索で長期的に読まれ続ける“資産”は、基本的に独自ドメインのブログ(例:WordPress)に蓄積します。理由は、情報の階層化や内部リンクの自由度、テーマ・プラグインの選択肢、速度・セキュリティ・バックアップの自主管理ができるためです。
一方、アメブロはプラットフォーム内の読者ネットワークやランキング、フォロー・リブログ機能の恩恵を受けやすく、更新直後の到達(初速)を得やすい特長があります。
そこで“本流=WordPress”“支流=アメブロ”という役割分担にすると、短期と長期の両方を取りにいけます。
実務では、アメブロの記事上部に「本編リンク(代表記事)」を置き、末尾にも同じ文言で再掲。代表記事では入門→比較→選択の順路を内部リンクで固定し、CTAは本文上部と末尾の2箇所に配置します。
文言はアメブロ側の見出しと同語にそろえ、クリック後の期待値ズレを防ぎます。計測は、アメブロ本文リンク・プロフィール固定リンク・サイドバーなどリンクごとにUTMを付与し、経路別にCTR→到着後の内部リンク到達→CTA到達を比較。
数値に基づき、最短導線(多くはプロフィール固定)が強い週はそこへ投稿を寄せ、弱い経路は文言・位置を1点だけ変更して検証します。
| 導線箇所 | 実装ポイント | 評価の見方 |
|---|---|---|
| プロフィール固定 | 代表記事1本を常設/文言はH1と同語 | CTR→記事のCTA到達率 |
| 本文上部リンク | 導入直後に本編リンク/利点を一文で補足 | CTR→内部リンク到達率 |
| 本文末尾リンク | 要約+本編リンクで締め/同文言を再掲 | 再訪率→CTA到達率 |
接点創出はアメブロ 深掘りは本サイトの役割分担
アメブロは“出会いの場所”、本サイトは“答えの場所”として設計すると、読者は迷いません。アメブロでは、短い導入で結論と読む利点を提示し、本文中に「本編はこちら→」のリンクを置きます。
記事末では要点を3行で要約し、同じ本編リンクで締めます。本サイトに着地した読者には、冒頭で答えを先出し、上部に比較表やチェックリストを置き、内部リンクで入門→比較→選択へ誘導。CTAは本文上部と末尾の2箇所に設置し、ボタン文言はアメブロの見出しと同語に統一します。
これでクリック後の期待値ズレが起きにくくなり、回遊とCVRが安定します。加えて、アメブロのサイドバーやプロフィールに代表記事への固定リンクを常設し、カテゴリやハッシュタグは“本サイトの情報設計(入門・比較・選択)”に対応させると、往復動線が最短化されます。
運用面では、リンクに識別子を付け、プロフィール/本文上部/本文末尾など経路別に計測。週次レビューで「どの経路→どの見出し→どのセクションで落ちたか」を見える化し、変更は1点のみ(リンク位置→文言→補足図解の順)でAB。
効いた型はアメブロ全記事へ横展開し、本サイト側の見出し・OGP・CTA文言にも逆輸入して整合を高めます。
- アメブロ=接点、本サイト=深掘り。文言と導線は同語・同位置で統一
- 主導線をプロフィール固定に置き、本文上部・末尾は補助導線
- UTMで経路別に分解→最短導線へ配分を寄せる
アメブロが優秀な理由と向いているテーマ
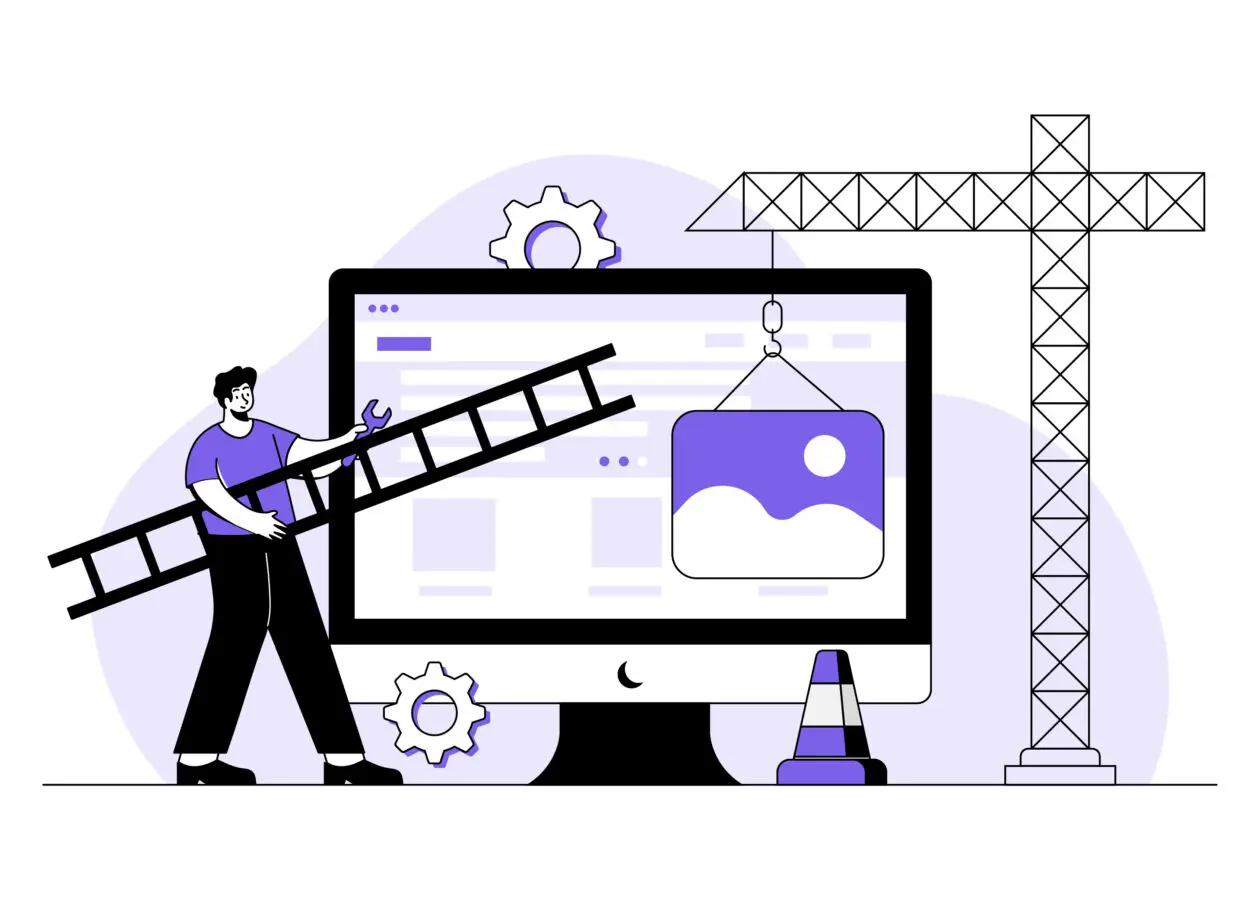
アメブロは、独自ドメインのブログ(例:WordPress)と比べて“初速(公開直後の到達)を作りやすい”のが最大の強みです。
理由は、プラットフォーム内に読者ネットワークがあり、フォロー・いいね・リブログ等の内製動線で新規読者へ露出できること、更新通知や各種一覧・テーマ分類により“検索以外の流入”が見込めること、投稿・画像・簡易装飾までの所要時間が短く更新頻度を維持しやすいことです。
一方で長期の検索資産化やレイアウト自由度は独自ドメインが優位なため、役割は分担します。アメブロで接点を増やし、代表記事(比較・事例・チェックリスト等)を置いた本サイトへ最短遷移させる——この“二刀流”が、短期と長期の両方を伸ばす近道です。
下表は、アメブロの主な強みと活用ポイントの整理です。
| 強み | ねらい | 実装ポイント |
|---|---|---|
| 内製ネットワーク | 更新直後の露出と拡散 | プロフィールに代表記事を固定/本文上部と末尾に同一リンク |
| 更新通知・一覧 | 検索以外の新規接点 | 結論先出しの導入+要点分割→保存・再訪を促す |
| 更新のしやすさ | 継続的な接点づくり | 短い記事で頻度を担保→深掘りは本サイトで |
- 同じ主張と同じ言い回し(アメブロ見出し=本サイトH1=CTA)
- 主導線は1つに固定(プロフィール固定リンク)→他は補助導線
- リンクに識別子を付与し、経路別のCTR→到達→CTA到達で比較
読者ネットワークと拡散機能で初速が作れる
アメブロでは、フォローや“いいね”によるタイムライン露出、リブログでの再掲、テーマ・タグ/カテゴリ一覧など、プラットフォーム内の動線が複数あります。
これらは検索を介さずに新規読者へ届くため、公開直後からの到達(初速)を作りやすいのが特長です。
初速を成果に結び付けるには、
①記事冒頭で結論と読む利点を一息で提示
②本文上部に本サイトの代表記事リンク
③中盤で比較表やチェックリストを配置し“納得”を作る
④末尾で要点3行+同リンクで締める
という“短く・同語・二箇所リンク”の型が有効です。
更新直後は反応が出やすいため、公開時間は読者がアプリを開く時間帯(朝・昼休み・夜)に寄せ、ストックは予約投稿で分散。
リンクには識別子(例:route_bio/route_body_top/route_body_bottom)を付け、プロフィール固定・本文上部・本文末尾の経路別にクリック→到着後の内部リンク到達→CTA到達を比較します。反応が強い経路と文言を“勝ち導線”として横展開すれば、初速の波を確実な送客に変えられます。
| 機能 | 狙い | 運用ポイント |
|---|---|---|
| フォロー・いいね | タイムラインでの接点増 | 冒頭で結論→本文上部に代表記事リンクを固定 |
| リブログ | 他者経由の再露出 | 要点が一目の図解/まとめ3行で“転載価値”を高める |
| テーマ/カテゴリ | 一覧からの流入 | 本サイトの“入門・比較・選択”に対応させ回遊を統一 |
相性の良いジャンルと不向きジャンルの見極め
アメブロは“視覚的・日常接点のある”テーマと相性が良いです。たとえば、美容・ヘア/ネイル、料理・レシピ、子育て・教育、ハンドメイド・教室、健康のセルフケア、占い・パーソナルサービス、士業/コーチのライトな相談記事などは、経験談やビフォーアフター、手順の写真・図解で反応が取りやすいジャンルです。
一方で、専門図表や長大な技術検証、B2Bの制度・法務の詳細解説のように“前提知識が多い”テーマは、アメブロ単体で深追いすると離脱しやすくなります。
この場合は、アメブロでは結論・判断軸・要点だけに絞り、深掘りは本サイトの比較表・事例・チェックリストへ橋渡しする二段構えにすると成果が安定します。下表を目安に、テーマの向き不向きと運用ポイントを整理してください。
| ジャンル | 向き・不向き | 運用ポイント |
|---|---|---|
| 美容・料理・ライフ | 向き:視覚と日常の接点が多い | ビフォーアフター/手順写真→代表記事で詳解 |
| 子育て・学び・教室 | 向き:共感・保存されやすい | チェックリスト配布→本サイトで教材・事例へ |
| 個人サービス(占い・相談) | 向き:短文相談→実績紹介に展開 | 成功談と注意点を近接配置→予約CTAを上部に |
| B2B・技術・法務 | 不向き:前提知識が重い | 結論と判断軸のみ→本サイトの図表・根拠へ誘導 |
- 1枚の図解と3行の要点で「読む利点」が伝わるか
- 本文上部と末尾に同語リンクを置いたとき、違和感なく遷移できるか
アメブロ×本サイトの二刀流導線

二刀流導線とは、アメブロで「接点」を作り、本サイト(独自ドメイン)で「深掘りと意思決定」を完了させるために、入口から出口まで同じ主張・同じ言い回しでつなぐ設計です。
ポイントは、アメブロ側で“最短の橋”を常設すること(プロフィール固定リンク・本文上部リンク)、本サイト側で“答えを先に”示して離脱を抑えること(導入で結論・上部に比較表・チェックリスト・CTA)。
さらに、両サイトの見出し・OGP・CTAの文言を統一し、クリック後の期待値ズレをゼロにします。計測はリンクごとに識別子を付け、プロフィール/本文上部/本文末尾など経路別にクリック→到着後の内部リンク到達→CTA到達を追います。
下表に、導線の主な設置箇所と狙い、初手の実装を整理しました。迷ったら、主導線を“プロフィール固定リンク→代表記事”に定め、その他は補助導線として運用すると安定します。
| 設置箇所 | 狙い | 初手の実装 |
|---|---|---|
| プロフィール固定 | 常時最短の入口 | 代表記事1本を常設/文言はH1と同語/月1で見直し |
| 本文上部 | 離脱前に案内 | 導入直後にリンク+読む利点を一文で補足 |
| 本文末尾 | 読み切り後の誘導 | 要点3行で要約→同リンクで締める |
- 主導線は1つに固定→補助導線は同文言で再掲
- 投稿・H1・OGP・CTAは同じ語で統一→期待値ズレを防止
- 経路別に計測→勝ち導線へ配分を寄せる
プロフィール固定リンクと代表記事で最短遷移を作る
アメブロの強み(内製ネットワーク)を確実な送客に変えるには、プロフィールで“常時最短の橋”を作るのが近道です。
名前欄に主要キーワードを入れ、一行ベネフィットで「誰に・何が・どう良いか」を明記。リンクは代表記事1本を最上段に固定し、同じリンクを記事本文上部・末尾でも再掲します。
代表記事は本サイト側に置き、導入一段目で結論を言い切り、上部に比較表やチェックリスト、CTA(本文上部+末尾)を配置。文言はアメブロ側の見出しと同語にそろえ、クリック後の“違った”を防ぎます。
計測では、プロフィール route_bio/本文上部 route_body_top/本文末尾 route_body_bottom のように識別子を付け、経路別にクリック→内部リンク到達→CTA到達を比較。強い経路と文言を“勝ち導線”として横展開します。
【設定手順】
- プロフィールに代表記事リンクを固定(文言=代表記事のH1)
- 各記事の導入直後と末尾に同リンクを設置(読む利点を一文で補足)
- 代表記事の導入で結論を先出し→上部に比較表・チェックリスト・CTA
- 識別子を付け、経路別のクリック→到達→CTA到達を週次で比較
| 要素 | 実装ポイント | 評価の見方 |
|---|---|---|
| プロフィール | 代表記事1本/同語で統一/月1で更新 | CTR→記事のCTA到達率 |
| 代表記事 | 導入で回答→上部に表・チェックリスト・CTA | 直帰率・内部リンク到達率 |
| 文言統一 | 見出し・OGP・CTAが同語 | 到着後の離脱・CTA到達の改善幅 |
- リンクが毎回違う位置→固定化して迷いをなくす
- 文言が不一致→アメブロ見出し=H1=CTAで統一
入門から比較 選択へ内部リンクで順路を統一
読者が迷わず意思決定へ進むには、記事群を「入門→比較→選択」の順でつなげる内部リンク設計が有効です。入門記事では結論と全体像、基本ルールを提示し、上部に比較へのリンクを配置。
比較記事では評価軸を表で示し、長短と向き不向きを整理して、選択記事(手順・チェックリスト・CTA)へ送ります。選択記事では、手順→注意→チェックリスト→CTAの順で簡潔にまとめ、関連事例やFAQを近接配置して不安を解消。
アメブロ側のカテゴリやハッシュタグも、この三層に対応させて回遊の“道筋”を統一します。リンク文言は必ず本文の小見出しと同語にし、クリック後の期待値ズレを起こさないことが重要です。
計測は、内部リンク到達をイベント化し、どの段で落ちたか(入門→比較/比較→選択/選択→CTA)を把握してから施策を1点だけ打ちます。
| 記事タイプ | 役割 | 内部リンクの置き方 |
|---|---|---|
| 入門 | 結論と全体像で不安を解消 | 導入直後に「比較へ」/末尾で再掲 |
| 比較 | 評価軸と差分で納得を形成 | 表の直下に「選択へ」/冒頭に「入門へ戻る」 |
| 選択 | 手順・注意・チェックで実行を支援 | 冒頭に「比較へ」/末尾に関連事例・資料とCTA |
【実装チェック】
- 三層のリンク文言は見出しと同語→期待値ズレを防止
- 上部リンクを必ず設置→深部まで読まれなくても次へ進める
- イベントで「入門→比較→選択→CTA」の到達を可視化
- 落ち段を特定→位置→文言→補足図解の順で1点AB
- 勝ち型は全記事へ横展開→アメブロと本サイトの両方で統一
アメブロで成果を出す記事と見せ方

アメブロの記事は「短く結論→回遊で深掘り→代表記事へ最短遷移」が基本です。検索で長く読ませるより、アメブロ内の読者ネットワークで“初速”を作り、本文上部のリンクとシリーズ化で迷いなく送客する設計が効果的です。
導入の最初の一段で結論を言い切り、本文は要点を短段落で区切ります。比較や長短は文章ではなく表で可視化し、本文上部と末尾の2箇所に同じリンク(本サイトの代表記事)を配置して行き止まりをなくします。
見出し・本文・リンク文言は本サイトのH1・CTAと同語にそろえ、クリック後の期待値ズレを防ぎます。
ヘッダー画像は主張が一目で分かる短文を重ね、カテゴリは入門→比較→選択の三層で並べ替え、ハッシュタグはテーマ2語+検証1語に絞ると、保存と回遊が安定します。下表に記事の要素と実装ポイント、確認指標をまとめました。
| 要素 | 実装ポイント | 確認指標 |
|---|---|---|
| 導入 | 最初の一段で結論と読む利点を宣言 | 直帰率・冒頭到達後のクリック |
| 本文 | 短段落・表で差分可視化・図解は上部配置 | スクロール深度・内部リンク到達率 |
| リンク | 本文上部+末尾に同リンクを再掲 | 経路別CTR→代表記事のCTA到達率 |
- 同語で統一→アメブロ見出し=本サイトH1=CTA
- 表・図で“差分”と“手順”を見せ、文章は要約中心
見出しテンプレ 結論→理由→具体→比較→行動
見出しは「読む前の意思決定」を左右します。テンプレは、結論→理由→具体→比較→行動の順で固定し、各H2の冒頭に“何が分かるか”を一文で宣言します。
結論では成果や利点を短く提示、理由は2〜3行で根拠を要約、具体は実例や手順を一つ、比較は表で差分、行動は次のリンク(代表記事や資料)を明記します。
アメブロではタイムラインからの流入が多いため、見出しと冒頭の一致が重要です。ここがズレると直帰が増えるので、本サイトのH1・CTAと同語で揃えます。下表に見出しブロックの作り方を示します。
| ブロック | 書き方の要点 | 例(要約) |
|---|---|---|
| 結論 | 利点を即提示・数値や名詞で具体化 | 「本文上部リンクの併設で回遊率が上がります」 |
| 理由 | 2〜3行で根拠を要約 | 「冒頭は離脱前に最も見られるため…」 |
| 具体 | 手順や配置を一つだけ示す | 「導入直後に代表記事リンク→利点を一文で補足」 |
| 比較 | 表で差分・向き不向き | 上部リンク/末尾リンク/サイドの比較表 |
| 行動 | 次の一手を明記・同語で統一 | 「代表記事で手順を詳しく見る→」 |
【チェックリスト】
- 各H2冒頭に“何が分かるか”の一文がある→回遊の迷いを減らす
- 比較は必ず表→文章のみで長文化しない
- 行動リンクは本文上部と末尾に同語で再掲→最短遷移
- 形容詞が多い→数値・固有名で置き換える
- 見出しと本文がズレる→導入で答えを先出し
ヘッダー カテゴリ ハッシュタグで回遊を強化
回遊を強くするには、記事単体の工夫に加えて「入口」と「道標」を整えます。ヘッダーは主張が一目で分かる短文(例:ブログ集客の導線設計を図解)を重ね、画像サイズはモバイルで崩れない比率に統一します。
カテゴリは入門・比較・選択の三層で並べ、記事タイトルや内部リンクの語と一致させると、一覧からの回遊が安定します。
ハッシュタグは多用せず、テーマ2語+検証1語を基本にして、検証1語だけを週次で入れ替えると因果が見えます。
さらに、プロフィールには代表記事3〜5本のリンク集を常設し、本文上部と末尾に同じリンクを再掲して行き止まりをなくします。下表の設計を起点に、回遊→代表記事→CTAまでを一直線にします。
| 要素 | 設計の要点 | 運用・評価 |
|---|---|---|
| ヘッダー | 一言で価値を明示・モバイル比率を統一 | 直帰率の変化・プロフィール遷移 |
| カテゴリ | 入門→比較→選択の三層で整理 | カテゴリ別の回遊率・代表記事到達 |
| ハッシュタグ | テーマ2語+検証1語に絞る | タグ別の保存・プロフィール閲覧 |
【実装ステップ】
- ヘッダー短文と画像比率を統一→主張を一言で
- カテゴリを三層へ再編→記事と同語に整える
- タグは3語に固定→検証1語だけ週替わりで比較
- 主導線はプロフィール固定→本文上部・末尾は補助
- UTMで経路別に分解し、勝ち導線の文言を全記事へ横展開
計測と改善のシンプル運用

アメブロ×本サイトの二刀流は、計測と改善を“シンプルに回す”ほど成果が伸びます。やることは三つだけです。第一に、リンクへ識別子を付けて経路を分割し、どこから来たのかを見える化します。
第二に、到着後の行動を段階で追い、内部リンク到達→CTA到達→完了のどこで落ちたかを特定します。第三に、週に一度だけ一箇所を変えてABテストを行い、勝ち導線の文言と位置を全記事へ横展開します。
ここで大切なのは、ダッシュボードを〈到達前→クリック→到着後→完了〉の順に並べ、弱点だけに施策を当てることです。
アメブロでは「プロフィール固定」「本文上部」「本文末尾」の三経路が主戦場になりやすいため、命名と評価軸を最初に統一しておくと迷いません。下表に、最小構成の可視化セットを整理しました。まずはこの粒度で運用し、数値を毎週横一列で比較できる状態を作るのが近道です。
| 段階 | 見る指標 | 目的 |
|---|---|---|
| 到達前 | 保存・プロフィール閲覧 | 投稿の関心度を把握 |
| クリック | 経路別CTR(プロフィール/固定/本文) | 最短導線を特定 |
| 到着後 | 内部リンク到達率・CTA到達率 | 受け皿の詰まり箇所を特定 |
| 完了 | 送信・購入・登録 | 最終成果を確認 |
- 全リンクへ識別子を付与→経路別に分解
- 到着後イベントを設定→段階順で可視化
- 週次で1点だけAB→勝ち導線を横展開
UTMで経路別に分解 プロフィール 固定 本文を比較
経路別比較の精度は命名の一貫性で決まります。はじめに、アメブロの代表的な三経路を固定します。プロフィール固定リンク、本文上部リンク、本文末尾リンクです。
各リンクにはUTMの命名規則を適用し、媒体名は小文字統一、経路名は“どこを通ったか”が一目で分かる語を使います。
企画名でテーマを束ね、形式で画像やテキストなどの違いを識別します。
到着後は内部リンク到達とCTA到達をイベントで記録し、プロフィール→本文上部→本文末尾の順に到達率が高いかを毎週比較します。強い経路の文言と位置を“勝ち導線”としてテンプレ化し、全記事へ横展開するとブレが減ります。
| UTMキー | 命名例 | 意味・使い方 |
|---|---|---|
| source | ameblo | 媒体名を小文字で統一 |
| medium | route_bio/route_pin/route_body_top/route_body_bottom | プロフィール固定/固定要素/本文上部/本文末尾 |
| campaign | blog_lead_article | 代表記事や特集などテーマ名で束ねる |
| content | text_link_v1/banner_mini/emoji_hookA | リンク形式やフック違いを区別 |
【設定ステップ】
- 命名規則を一枚にまとめ、全員が同じ表記で運用
- プロフィール固定・本文上部・末尾の3経路へ同一リンクを設置
- 内部リンク到達・CTA到達・完了のイベントを設定して週次で比較
- 命名のゆらぎ→比較不能に。表記を固定し、変更時は必ず更新
- 到着後を見ない→CTRだけで判断しない。到達率とCVRまで確認
週次レビューで1点AB 勝ち導線を横展開
改善は“1点変更→判定→横展開”が原則です。週初に仮説を一つだけ立てます。例として、本文上部リンクの文言を「代表記事はこちら」から「導線設計の詳しい手順を見る」に変更する、または上部リンクを導入直後に一段繰り上げる、といった具体的な一点です。
配信条件はできるだけ揃え、露出が同程度になるよう予約投稿で調整します。判定は段階KPIで行い、到達前(保存・プロフィール閲覧)だけでなく、経路別CTR→内部リンク到達→CTA到達→完了までを見ると因果が特定できます。
勝ちが出たら、同週内に全記事へ適用し、次週の仮説を1つだけ設定して回します。下表に、シグナル別の初手を示します。
| シグナル | 読み取り方 | ABの初手 |
|---|---|---|
| 保存↑ CTR↓ | 関心はあるが出口が弱い | 主導線をプロフィール固定に寄せ、本文上部の文言を強化 |
| CTR↑ 到達↓ | 期待値ズレやUIの問題 | H1・CTA・OGPを同語化→導入で回答を先出し |
| 到達↑ CVR↓ | 証拠不足・摩擦が高い | 比較表下に補助CTAと事例を近接配置 |
【レビューの型】
- 弱い段階だけに打ち手を当てる→他条件は固定
- 効果が出たら“文言・位置・形式”の順で全記事へ横展開
- 効果が出なければ元に戻す→次週は別の一点に切替
- 勝ち導線はテンプレにして新規記事へ自動適用
- 代表記事のH1・CTAと同語を保つ→クリック後の期待値ズレを防止
まとめ
結論:アメブロは“接点創出”に優秀、本サイトは“深掘りと検索資産”に最適。
二刀流で①プロフィール固定リンク+代表記事で最短遷移、②入門→比較→選択の順路を内部リンクで統一、③UTMで経路別に可視化→週次で1点AB。まずはアメブロの固定リンクを整え、同語のH1・CTA・OGPで期待値を合わせ、勝ち導線へ配分を寄せましょう。