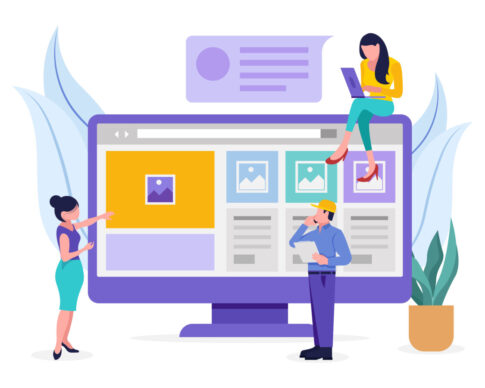ブログ集客をこれから始める初心者向けに、設計・導線・測定の基本を要点だけで解説します。
SEOとSNSの役割分担、キーワード選定と記事構成、CTA/OGP/プロフィールの整え方、UTM×GAでの計測、つまずきやすい失敗の回避までを具体手順で紹介。今日から迷わず実装でき、成果までの道筋がはっきりします。
ブログ集客の全体像
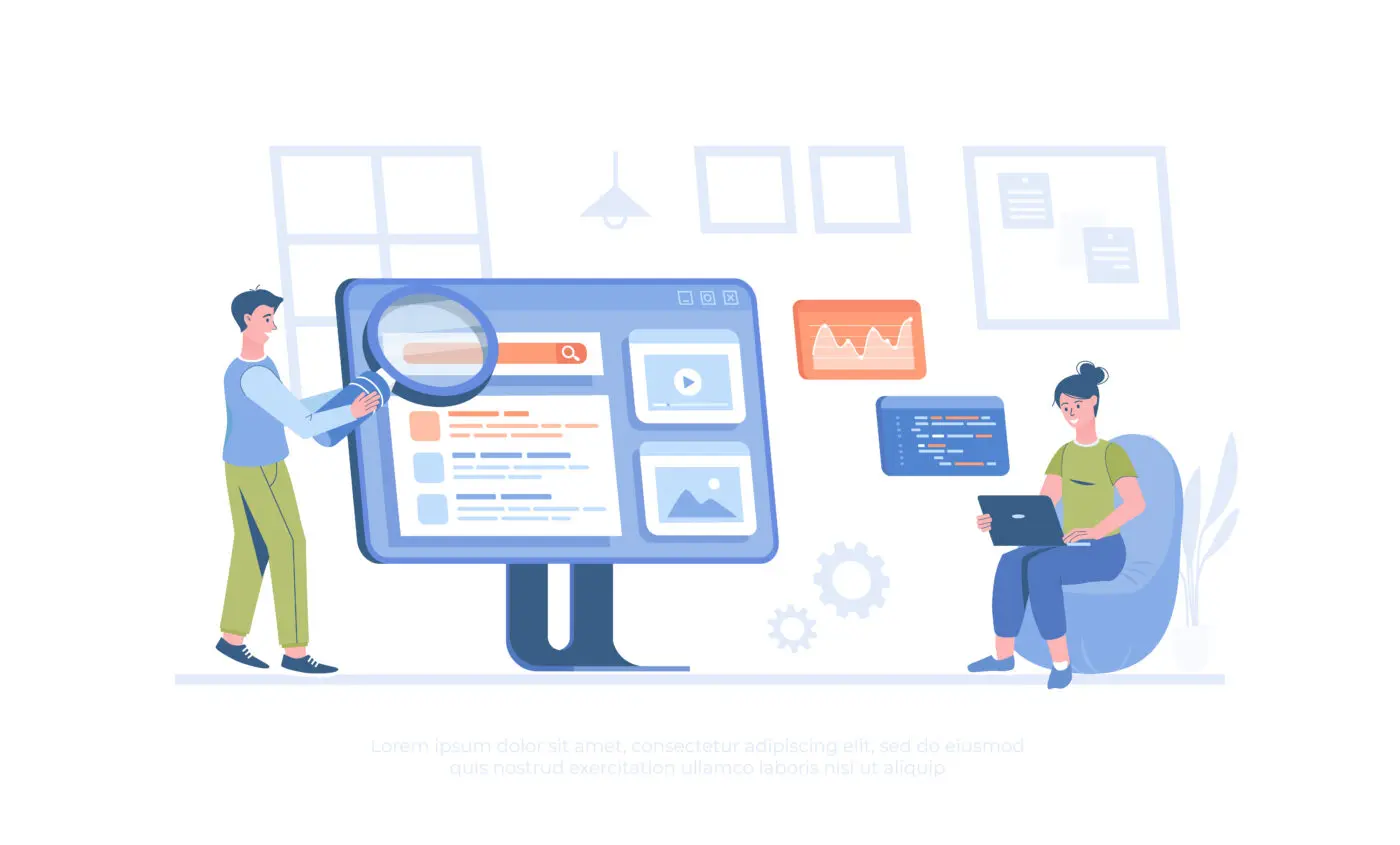
ブログ集客は「接点を作る→興味を高める→意思決定を助ける→行動に移す」という流れを、複数チャネルで分担すると安定します。SNSは新規の接点づくりと拡散、検索(SEO)は常時流入と深掘り、メールは再訪と関係維持に強みがあります。
初心者の方は、まず“役割の分担”を先に決め、各チャネルの文言と導線(リンクの置き場所・言い回し)を同じにそろえるのが近道です。
投稿で使った言葉=記事の見出し・CTA・OGPに反映させると、クリック後の期待値ズレが減り、滞在や回遊が伸びます。
到着後は「内部リンク到達率→CTA到達率→CVR」の順に確認し、詰まり箇所を1つずつ解消します。下の表は、チャネル別の役割と使いどころの整理です。
| チャネル | 主な役割 | 使いどころ(例) |
|---|---|---|
| SNS | 接点創出・拡散・短い要点提示 | 結論を先出し→固定投稿・プロフィールリンクで代表記事へ |
| 検索(SEO) | 常時流入・深掘り・比較と選択 | 入門/比較/選択の記事群で回遊設計→CTAで行動 |
| メール | 再訪喚起・関係維持・限定案内 | 更新通知・補足資料・再読おすすめ→再流入を作る |
- 各チャネルの役割分担と共通の言い回し
- 導線の固定(プロフィール/固定投稿/本文のリンク位置)
- 計測の分解(流入→内部リンク到達→CTA到達→CV)
検索×SNS×メールの役割分担と相乗効果
検索・SNS・メールは“それぞれ得意分野が違う”からこそ、組み合わせると効果が上がります。SNSは関心のきっかけ作りに特化し、短い要点・図解・短尺動画で「読みたい理由」を提示します。
ブログ記事は検索からの常時流入に加え、SNSで生まれた興味を受け止めて詳しく解説し、比較表や事例で意思決定を後押しします。
メールは“忘れられない仕組み”として働き、更新・新記事・特集の案内で再訪を増やします。大切なのは、三者で同じ主張・同じ語を使うことです。投稿タイトル=記事H1=メール件名を近づけ、OGP画像もアイキャッチと統一すると、クリック後の「思っていた内容と違う」が減ります。
KPIはチャネル別に分けて見ますが、判断は“流れで”行います。SNS到達→記事クリック→内部リンク到達→CTA到達→CVRの分解で、どこに壁があるかを特定しましょう。
| チャネル | 強み | 連携のポイント |
|---|---|---|
| SNS | 接点・拡散・瞬発力 | 投稿の結論と言い回し=記事H1・CTAに統一 |
| 検索 | 常時流入・深掘り・比較 | 入門→比較→選択の導線で“読む順番”を用意 |
| メール | 再訪・関係維持 | 要点+関連記事リンク→再読でCV機会を増やす |
読者ニーズとテーマ設定(悩み→検索意図)
集客の土台は「だれの、どんな悩みに、どの順番で答えるか」を決めることです。最初にペルソナの“直近の困りごと”を1つだけ選び、検索窓に入りそうな言葉へ置き換えます(例:「ブログの導線が弱い」→「ブログ 集客 導線 作り方」)。
次に、その意図を「知りたい(入門)」「比べたい(比較)」「選びたい(選択)」の3段階に分解し、記事群を設計します。
各記事には“読み終えた後に起きてほしい行動”を1つだけ定め、見出し・本文・CTAの言い回しを一致させます。
キーワードは月間検索数の大小だけで選ばず、記事の役割(入口/分岐/着地)との相性で判断すると迷いません。下の表は、悩み→検索意図→記事タイプの対応例です。
| 悩み | 検索意図(例) | 記事タイプと役割 |
|---|---|---|
| 導線が弱い | ブログ 集客 導線/CTA 置き方 | 入門:基本の考え方/比較:設置位置別の長短/選択:具体配置と事例 |
| テーマが広すぎ | ブログ テーマ 絞り方/ニッチ 選び方 | 入門:絞り方の軸/比較:候補ニッチ一覧/選択:1テーマの深掘り計画 |
| 伸びが鈍化 | 記事 リライト 手順/OGP 改善 | 入門:基本手順/比較:改善ポイント別の効果/選択:チェックリスト配布 |
【設計ステップ(おすすめ)】
- 悩みを1つ決め、検索語に置き換える(言葉は読者目線)
- 意図を入門/比較/選択に分解→記事群の見出し案を作成
- 各記事の目的行動を1つに絞り、見出し・CTAの文言を統一
準備と設計(キーワード・記事・導線)

集客設計は「どんな検索意図を、どの記事で、どの導線で受け止めるか」を先に決めると失敗が減ります。基本は〈入門〉〈比較〉〈選択〉の3役を分け、同じ主張・同じ言い回しでSNS→ブログ→CTAまで一気通貫にそろえることです。
タイトル・見出し・OGP・ボタン文言を統一すれば、クリック後の「思っていた内容と違う」が減り、内部リンク到達率やCVRが底上げされます。
さらに、プロフィールや固定投稿に“代表記事への常設リンク”を置くと、いつ流入しても最短で本編に到達できます。
最後に、到着後の行動(内部リンク→CTA→送信)を可視化するため、流入経路ごとに識別子を付けて評価軸を揃えましょう。
| 設計要素 | 目的 | 実装ポイント |
|---|---|---|
| キーワード | 意図の明確化と役割分担 | 入門/比較/選択に割り当て→重複を排除 |
| 記事 | 意思決定の支援 | 見出しの順序を固定→表・図解で差分を明示 |
| 導線 | 最短で本編へ誘導 | プロフィール/固定/本文のリンク位置を標準化 |
- 入門・比較・選択の3本に役割を割り振ったか
- タイトル/見出し/OGP/CTAの言い回しを統一したか
- 代表記事のリンクをプロフィールと固定投稿に常設したか
キーワード選定の型(入門/比較/選択)
キーワードは“検索意図の段階”ごとに割り当てると、記事群の役割が明確になります。〈入門〉は用語や全体像を知りたい段階、〈比較〉は条件で絞りたい段階、〈選択〉は申し込みや設定など具体行動の直前です。
同じ語尾でも意図が異なることがあるため、実際の検索結果(上位の見出し)から意図を読み取り、重複を減らします。月間検索数は目安に留め、まずは“役割の適合度”を優先。
入門で集めた読者を比較へ、比較から選択へと内部リンクで送り、各ページのCTAに一貫した文言を使います。これにより、個々のページの勝ち負けではなく“流れ全体の歩留まり”で改善できます。
【選定手順(おすすめ)】
- 読者の悩みを検索語へ置き換える(例:ブログ 集客 導線 作り方)
- 上位10件のH2/H3から意図を確認→入門/比較/選択に振り分け
- 重複語を削り、各段階で不足のテーマを補完する
| 段階 | キーワード例 | 記事のゴール/CTA例 |
|---|---|---|
| 入門 | ブログ 集客 仕組み/導線 基本 | 全体像の理解→「比較記事へ進む」リンクを配置 |
| 比較 | CTA 位置 おすすめ/OGP 作り方 比較 | 条件別の長短→「事例つき解説を読む」ボタン |
| 選択 | プロフィール リンク 設計/固定投稿 例 | 実装手順→「チェックリストをダウンロード」 |
記事構成テンプレと内部リンク設計
構成は「結論→理由→具体→比較→次アクション」の順で固定すると、どのテーマでも読みやすくなります。入門は“用語の整理と判断軸”、比較は“表で差分を可視化”、選択は“手順と注意点”に重点を置きます。
内部リンクは記事冒頭と末尾の両方に設置し、入門→比較→選択へ片道だけでなく、比較→入門の戻り導線も用意すると回遊が安定します。
表や図解は「読者が迷うポイント(位置/文言/画像サイズなど)」を中心に置き、本文では例と注意点を補足。
導線の検証をしやすくするため、CTAや内部リンクの位置はテンプレートで統一し、変更は“1箇所だけ”に限定してABを行いましょう。
| 記事タイプ | 構成テンプレ | 内部リンクの置き方 |
|---|---|---|
| 入門 | 結論→理由→用語整理→全体像→次アクション | 冒頭に比較への導線/末尾に選択への導線 |
| 比較 | 結論→評価軸→表→長短→事例→次アクション | 表の直下に選択への導線/冒頭に入門へ戻るリンク |
| 選択 | 結論→手順→注意点→チェックリスト→FAQ | 冒頭に比較へのリンク/末尾に関連事例・資料 |
- 各見出しの冒頭で“何が分かるか”を一文で宣言
- 比較は必ず表で差分を明示→文章だけにしない
- 内部リンクとCTAの位置はテンプレで固定→ABは1点だけ変更
CTA・OGP・プロフィールで最短導線を作る
「SNS→記事→CTA」までの文言と位置を標準化すると、迷いが激減します。まずCTAは“ページ上部(概要直後)”と“本文末尾”に2回設置し、文言は投稿と同じキーワードを含めます。
OGPはタイトル/説明/画像をアイキャッチと統一し、タイムライン上でも内容が伝わる要約にします。プロフィールはテーマ別リンクを3〜5本に絞り、固定投稿(ピン留め)でも同じ導線を再掲。
YouTubeは概要欄上段と固定コメントに同リンク、Instagramはストーリーズのリンクスタンプ、Xは固定投稿とプロフィールで入口を常設します。
すべてのリンクに識別子を付け、「プロフィール」「固定」「本文/概要欄」「固定コメント」の経路別にクリック→到着後のCTA到達→CVRまで確認しましょう。
【導線整備の手順】
- CTAの文言を投稿タイトル=記事H1と一致させる
- OGPのタイトル/説明/画像をアイキャッチと統一
- プロフィール/固定投稿に代表記事のリンクを常設し、経路別に計測
| 接点 | 整備ポイント | 評価の見方 |
|---|---|---|
| CTA | 上部+末尾の2箇所/文言は投稿と同一 | 到達率→クリック率→完了率の順で確認 |
| OGP | タイトル・説明・画像を統一/要約は一文 | リンクCTR→到着後の直帰率を併読 |
| プロフィール/固定 | リンクは3〜5本に限定/月1で見直し | 経路別CTR→記事CVR→勝ち導線へ寄せる |
集客チャネルの基本施策

集客チャネルは「検索=常時流入」「SNS=接点・拡散」「メール=再訪・関係維持」という役割を前提に、同じ主張と同じ言い回しで統一すると成果が安定します。まずは共通の資産を整えます。
代表記事(入門/比較/選択の核)を用意し、OGP・アイキャッチ・CTAの文言を投稿タイトルと一致させます。
次に、プロフィールと固定投稿(ピン留め)に代表記事へのリンクを常設し、本文や概要欄・固定コメントにも同じリンクを配置して最短導線を作ります。
最後に、チャネル別・導線別に計測できるようリンクへ識別子を付与し、「表示→プロフィール(or固定)クリック→記事到達→内部リンク到達→CTA到達→成約」の流れで詰まりを特定します。下表を使い、初手と継続タスクを分けて運用しましょう。
| チャネル | 初手(整備) | 継続タスク |
|---|---|---|
| 検索(SEO) | 代表記事の構成・タイトル・URL整備 | 内部リンク強化・リライト・比較表の更新 |
| SNS | プロフィール/固定投稿に代表記事リンク常設 | 再投稿・OGP差替・リンク位置のAB |
| メール | 登録フォームと歓迎メールの導線を設置 | 更新通知・特集便・関連記事の再送 |
- 代表記事(入門/比較/選択)と同一文言のCTA
- OGP(タイトル・説明・画像)=記事と統一
- プロフィール・固定投稿・本文のリンク位置を標準化
SEOの初期設定(タイトル・見出し・URL)
SEOの初期設定は「検索意図に即した構成」と「機械・人どちらにも分かる表記」を同時に満たすことが要点です。タイトルは主キーワードを前方に置き、何が分かる記事かを短い語で明示します。
H1はタイトルと同義域で、H2は読者の疑問(なぜ/どうやって/比較は?)に答える順序で並べます。URLは短く分かりやすい英字+ハイフンを推奨し、将来の更新でも意味が変わらないスラッグにします。
導入文は結論→要点→読む利点を一段で提示し、本文では表・図解を使って差分を可視化。内部リンクは入門→比較→選択へ進む道と、比較→入門へ戻る道の両方を配置し、回遊を安定させます。
重複しやすい語は見出しで整理し、ページ内の用語を統一すると、到達後の離脱が減ります。最後に、アイキャッチとOGPの文言・画像を記事と一致させ、一覧やSNS上でも内容が伝わるようにします。
| 項目 | 設定ポイント | チェック観点 |
|---|---|---|
| タイトル/H1 | 主語(テーマ)+読者の利点を前方に | 検索意図と一致・重複表現がない |
| 見出し(H2/H3) | 結論→理由→具体→比較→次アクション | 見出しだけで内容が把握できる |
| URL | 英字+ハイフンで短く固定 | 更新しても意味が変わらない |
| 内部リンク | 入門⇄比較→選択の導線を標準化 | 到達率を計測し詰まりを修正 |
SNS運用の型(固定投稿・再投稿・リンク配置)
SNSは「接点づくり→最短で代表記事へ」の設計が基本です。プロフィールにはテーマ別リンクを3〜5本だけ掲載し、固定投稿(ピン留め)で代表記事と“読む利点”を常時提示します。
通常投稿は、結論→要点→導線の順で簡潔にまとめ、OGP(タイトル・説明・画像)を記事と同じ言い回しに統一。
リンクは本文・固定・プロフィールの3箇所に置きますが、同時期には1つを“主ルート”に決め、他は補助とします。再投稿は角度(見出しの言い換え)と時間帯だけを変えて実施し、ハッシュタグはテーマ2語前後を固定+検証1語で入替。
リンクには識別子を付け、主ルート(プロフィール/固定/本文)別にクリック→記事到着後のCTA到達率→成約率まで比較します。反応が良かった表現はブログの見出しにも逆輸入し、全体の整合を高めましょう。
| 配置箇所 | 実装ポイント | 評価の見方 |
|---|---|---|
| プロフィール | テーマ別リンク3〜5本・説明は一行 | プロフィールCTR→記事CVR |
| 固定投稿 | 代表記事の要点とリンクを常設 | 固定経由CTR→主ルート比較 |
| 本文/概要欄 | 結論→要点→導線の順で配置 | リンクCTR→到着後のCTA到達率 |
- 角度変更:同じ主張を言い換え(例:効果→手順→注意点)
- 時間変更:朝/昼/夜で再投下→主ルート別に比較
- 形式変更:図解1枚↔スレ/カルーセル↔リールで検証
被リンク獲得と共同企画の始め方
自然な被リンクは「引用したくなる価値」を提供すると得やすくなります。まず、自サイトで“参照されやすい資産”を用意します。
例として、チェックリスト・比較表テンプレ・用語集・導線配置のベストプラクティス集など、実務でそのまま使える形式が効果的です。次に、関連サイトやクリエイターとの共同企画で露出を広げます。
相互インタビュー、共同調査・アンケート、事例提供、イベント共催などは、自然な文脈でリンクが生まれやすい施策です。提案時は「相手読者のメリット」を先に示し、掲載場所・想定見出し・引用可能な図表をセットで提示すると採択率が上がります。
獲得後は、該当記事を最新化し直帰を減らすほか、紹介文と同じ言い回しをH1や導入に反映し、期待値のズレを防ぎます。下表を参考に、すぐ始められる施策から着手してください。
| 施策 | 内容 | リンクが生まれる点 |
|---|---|---|
| テンプレ配布 | チェックリスト・比較表・OGP文例の公開 | 出典表記・導入記事への引用 |
| 共同企画 | 相互インタビュー/共同調査・座談会 | 告知・結果公開・事後レポート |
| 事例提供 | 他サイトの検証やリニューアルに協力 | クレジット・制作実績ページ |
- 不自然なリンク取得や過度な相互リンクに依存しない
- 古い情報のまま引用され続ける→更新日と追記を明示
測定と改善(初心者のKPI設計)

集客の改善は「測る→比べる→直す」を小さく速く回すことから始まります。最初に決めるべきは、到達前後の指標を分けることです。
到達前(SNS内)は表示数・エンゲージメント、クリックはプロフィール/固定/本文など“経路別CTR”、到着後(ブログ内)は内部リンク到達率・CTA到達率・最終CVRという具合に段階化します。
段階ごとに“どのデータで確認するか”を決め、週次で同じフォーマットに記録すると、原因の切り分けが容易になります。投稿と記事で同じ言い回し(タイトル・見出し・OGP・CTA)に統一しておくと、期待値のズレが減り、数値の解釈も一貫します。
下表は、初心者がまず押さえるKPIと確認ポイントの対応です。迷ったら、この表の左から順に詰まりを探し、改善は必ず“1点のみ変更”で検証してください。
| 段階 | KPI(例) | 確認ポイント |
|---|---|---|
| 到達前(SNS) | 表示数/保存・いいね/プロフ閲覧 | 1枚目・冒頭3秒で結論を出せているか |
| クリック | プロフィール/固定/本文(概要欄)別CTR | 主ルートを1つ決め、他は補助に回しているか |
| 到着後(ブログ) | 内部リンク到達率/CTA到達率/CVR | 投稿の主張=H1・OGP・CTAの文言に統一済みか |
- 経路別のクリック→到着後の到達→CVRを同一フォーマットで記録
- 最も弱い1指標だけに的を絞って施策を実施
- 効果が出たら“型”として横展開、出なければ元に戻す
UTM×GAで流入とCVRを分解して把握
「どこから来て、どの導線が一番短かったか」を判断するには、リンクに識別子(UTMなど)を付け、到着後の行動を分析ツールで確認します。
最低限、媒体(source)・経路(medium)・企画名(campaign)を統一命名し、必要に応じて投稿パターン(content)やキーワード(term)で細分化します。
例えばXなら、source=x、mediumを route_bio(プロフィール)/route_pin(固定)/route_post(本文)に分けるだけで、主導線が見えてきます。
到着後は、内部リンク到達率・CTA到達率・イベントCVをページ別に確認し、SNS側の表現と記事のH1・CTAの言い回しを揃えることで、ズレ由来の離脱を減らします。数値は“正解”ではなく“方向”を示す目印です。小さな差でも、同じ条件で週次に並べれば十分な判断材料になります。
| UTMキー | 命名例 | 読み方・使い分け |
|---|---|---|
| source | x/instagram/youtube/mail | 媒体名を統一→横比較が容易 |
| medium | route_bio/route_pin/route_post/route_comment | 同一媒体の導線差を判別 |
| campaign | blog_topicA_launch | 企画やテーマ単位で束ね、期間比較に活用 |
| content | img1_diagram/short15s_hookA | 投稿フォーマットやフック違いを区別 |
【設定ステップ】
- 命名ルールを1枚にまとめ、全リンクで統一
- 到着後イベント(内部リンク到達・CTAクリック・送信)を設定
- 媒体×導線ごとにCVRを比較→最短導線へ投稿設計を寄せる
投稿時間・形式・リンク位置のABテスト
同じ主張でも「投稿時間」「形式(画像/動画/テキスト)」「リンク位置」で成果は変わります。ABの原則は“変更は常に1点のみ”。たとえばXなら、同じスレを朝と夜に再投下して時間帯だけを比較。
Instagramでは同テーマでカルーセルとリールを対比。YouTubeではショートの長さ(15秒/30秒)を比較します。
リンク位置も重要で、本文先頭と末尾、概要欄上段と固定コメント、プロフィールと固定投稿など、経路ごとにクリック→到着後のCTA到達→CVRまで追うと、最短ルートが明確になります。
判断基準は“到達前の数字だけに依存しない”こと。保存数・再生数が良くても、記事CVRが伴っていなければ勝ちとは言えません。勝った型は同媒体で横展開し、ブログ側の見出し・CTA文言にも逆輸入して整合を高めます。
| 比較対象 | ABの組み方 | 評価指標 |
|---|---|---|
| 時間帯 | 同一投稿を朝/夜で再投下(その他は固定) | 主導線別CTR→到着後のCTA到達率 |
| 形式 | カルーセル vs リール/図解1枚 vs スレ | 保存率・最終枚到達率・記事CVR |
| リンク位置 | 本文先頭 vs 末尾/概要欄上段 vs 固定コメント | リンクCTR→直帰率・CVR |
【運用ステップ】
- 1要素だけ変えるAB計画を作成(他条件は固定)
- UTMで経路別に計測→1週間同条件で実施
- 勝ち型を同媒体へ横展開→次に別媒体で言い回しを適合
つまずきやすい失敗と回避策

初心者が集客でつまずく多くのケースは、努力不足というより“型の欠如”が原因です。代表例は、SNS内で情報が完結してしまいブログに人を連れて来ない、投稿の訴求と到着先(記事やLP)の内容が一致せず直帰が増える、一時的なバズに依存して再現性のある導線や記事更新が止まる、の3点です。
対策は、①リンクの置き場所・文言・到着先を“常に同じルール”で整える(標準化)、②投稿見出し=記事H1=CTA=OGPの表現を統一して期待値のズレをなくす(整合化)、③週次で再投稿と記事メンテを回し、短期の波を平均化する(平準化)、の3つをセットで実行することです。
下表に症状と初手をまとめました。まずは“最短導線を固定する”から始めると、クリック後の落差が大きく改善します。
| 失敗パターン | 起きやすい症状 | 初手の対策 |
|---|---|---|
| SNS内完結 | 保存・いいねは多いのに記事到達が少ない | プロフィール/固定/本文のリンク位置を標準化し、主ルートを1つ決める |
| 訴求とLP不一致 | クリックはあるが直帰・離脱が多い | 投稿見出し=記事H1=CTA文言=OGPに統一、導入1段目で“約束の回答”を提示 |
| バズ依存 | アクセスが波打ち、CVが安定しない | 再投稿と在庫化を週次で運用、勝ち導線へ配分を寄せる |
- 主ルート(プロフィール/固定/本文)のリンク文言を記事H1と一致
- OGP(タイトル・説明・画像)をアイキャッチと統一
- 週1回の“再投稿+記事メンテ”をカレンダーに固定
SNS内完結/訴求とLP不一致/バズ依存を防ぐ
SNSで反応はあるのにブログの成果が伸びない最大の理由は、「導線の不在」と「約束の不一致」、そして「再現性の欠如」です。
まず、SNS内完結は“どこに何のリンクを置くか”を固定して解決します。プロフィールはテーマ別リンク3〜5本、固定投稿は代表記事の要点とリンク、本文(や概要欄・固定コメント)は結論→要点→導線の順に記載し、文言は記事H1と同じにします。
次に、訴求とLP不一致は、投稿見出し=記事H1=CTA文言=OGPの表現を統一し、導入の最初の一段で“投稿で約束した答え”を提示するだけで直帰が下がります。最後に、バズ依存は“在庫化→再投稿→横展開”の週次運用で平準化します。
角度(見出しの言い換え)か時間帯のどちらか“1点だけ”を変え、リンクには識別子を付けて主導線別にCTR→到着後CTA到達→CVRまで追跡します。数字が小さくても、同条件で並べれば勝ち型が浮かび、次の週の配分判断に使えます。
| 論点 | やること | 評価の見方 |
|---|---|---|
| 導線の標準化 | プロフ/固定/本文の配置と文言を統一 | 経路別CTR→記事のCTA到達率→CVR |
| 表現の整合化 | 投稿見出し・H1・CTA・OGPを同表現 | 直帰率・内部リンク到達率の改善幅 |
| 平準化 | 週次で再投稿、勝ち導線へ寄せる | 平均CV数とばらつき(標準偏差)の低下 |
- 一度に多要素を変更しない→因果が不明になる
- 到達前の指標(保存・再生)だけで勝敗を決めない
週次運用カレンダーとレビューの回し方
成果を安定させるコツは、“やることを週次で固定”し、同じ型で評価することです。
おすすめは、在庫化(記事→スレ/カルーセル/ショートへの変換)、再投稿(時間帯か角度の1点変更)、記事メンテ(見出し・OGP・CTAの整合確認)、レビュー(主導線別のCTR→到着後CTA到達→CVRの確認)を1週間に詰める運用です。
以下のカレンダー例では、無理のない頻度で“接点づくり”“受け皿整備”“評価”を循環させます。重要なのは、勝ち型が出たら当週のうちに横展開し、来週の仮説は1つだけに絞ること。
数字は“方向”を示す道標なので、改善の因果が分かる粒度で記録を残し、効果がなければ必ず元に戻します。
| 曜日 | 主なタスク | 見る指標・アウトプット |
|---|---|---|
| 月 | 在庫化:記事→スレ/カルーセル/ショートへ変換 | OGP整備率・投稿草案・主導線(プロフ/固定/本文)の設定 |
| 火 | 主ルートで投稿①(結論→要点→導線) | ルート別CTR・記事の内部リンク到達率 |
| 水 | 記事メンテ(H1・CTA・OGPの整合/表の更新) | 直帰率・CTA到達率の改善幅 |
| 木 | 再投稿(時間帯 or 角度を1点だけ変更) | 比較対象のCTR差/到着後のCTA到達率 |
| 金 | 共同企画・被リンク施策の提案・下準備 | 返信率・掲載見込み・紹介文草案 |
| 土/日 | 週次レビュー→来週の仮説を1つ決定 | CVR・平均CV数・ばらつき、勝ち型の横展開リスト |
- 経路別にCTR→到着後到達→CVRを同一フォーマットで記録
- 最も弱い1指標だけに打ち手を集中(他条件は固定)
- 効いた型は当週内に横展開→翌週の仮説は1つだけ
まとめ
本記事の要点は、①SEO×SNSで接点と深掘りを分担、②キーワードと内部リンクで記事群を設計、③CTA・OGP・プロフィールで最短導線を常設、④UTM×GAとABで改善、の4つです。
まずは代表記事を1本整え、SNSの固定投稿とプロフィールにリンクを設置→数値を見て言い回しを統一。小さく試し、毎週見直せば着実に伸びます。